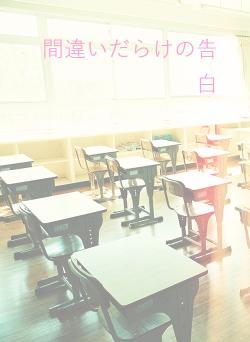「どーなってるんだよ!」
「それは僕も聞きたいですよ」
朝になってもメールは送信できなかった。
試しに仲間うちで送信したメールはきちんと送れている。
つまりは、問題は向こう側。
「給料も振り込まれてないっす」
ハートがスマホで確認しながら肩を落とす。
この一週間はなんだったのか。
ただむさくるしい男たちと一台の車で窮屈でしかない生活をしただけ。
しかもこの依頼が本当に何だったのかもわからぬまま、金も手に入れられずに終了となる。
「おい、行くぞ」
「行くって?」
「決まってんだろ。オレたちが元の依頼を完遂するんだ。雇う側になるんだよ」
「危険すぎるっす」
「でもやならきゃ、いつまでもオレたちは使い捨て側だ。もう、いいだろ。あっち側にいっても」
「……」
境遇は皆同じ。もう進むより他に道はなかった。
グレーから黒へ。後戻りなど出来ない。
このまま手ぶらでなんか帰れるかよ。
ここで生活するために、金は使い切った。
帰ったところで、食べる金もない。
悪いのはオレたちじゃない。みんな他の奴らのせいだ。
「……」
オレが先頭になり、息を殺しながら別荘のドアに手をかけた。
「⁉」
すると不用心にも鍵はかかっておらず、ドアが開く。
玄関に入ると、中は外と比べ物にならないほど春のように暑かった。
オレたちは無意識のうちに、上着を玄関の下駄箱の上に置いた。
そして靴も脱ぎ、音を立てないようにそっと中を進んで行く。
すぐ左手の部屋から、いい匂いがあふれていた。
オレたちは顔を見合わせ、一気にその部屋に突入する。
奇麗なダイニングには、木製の高級なテーブルが置かれていた。
「飯だ!」
テーブルの上には、今作ったばかりと思える食事がたくさん並ぶ。
骨付き肉に、ミネストローネ。
どれも全て、いい匂いがした。
途端に尋常ではないほど、空腹が加速していく。
食べたい。今すぐ食べたい。ああ、食べたい。
「なんで住人はいないんだ?」
テーブルに駆け寄るオレとは違い、二人は警戒して辺りを窺っていた。
確かに食事は出来たてだというのに、人の気配はない。
それならば、誰がこの食事を用意したのか。
元々、この別荘には人の気配などなかった。
そう思えば、おかしなところだらけだ。
しかしそれすら考えられないほど、食べたくて仕方がない。
喉から手が出るほどの空腹と渇き。それがオレを支配していた。
「どーでもいいから、まず食おうぜ!」
金目の物も住人も、食べてから考えればいいだろ。
「急いで食べちゃえばいいっすよね。温かいご飯なんて、久しぶりすぎる」
「それなら……」
三人でテーブルに座り、食事についた。
「それは僕も聞きたいですよ」
朝になってもメールは送信できなかった。
試しに仲間うちで送信したメールはきちんと送れている。
つまりは、問題は向こう側。
「給料も振り込まれてないっす」
ハートがスマホで確認しながら肩を落とす。
この一週間はなんだったのか。
ただむさくるしい男たちと一台の車で窮屈でしかない生活をしただけ。
しかもこの依頼が本当に何だったのかもわからぬまま、金も手に入れられずに終了となる。
「おい、行くぞ」
「行くって?」
「決まってんだろ。オレたちが元の依頼を完遂するんだ。雇う側になるんだよ」
「危険すぎるっす」
「でもやならきゃ、いつまでもオレたちは使い捨て側だ。もう、いいだろ。あっち側にいっても」
「……」
境遇は皆同じ。もう進むより他に道はなかった。
グレーから黒へ。後戻りなど出来ない。
このまま手ぶらでなんか帰れるかよ。
ここで生活するために、金は使い切った。
帰ったところで、食べる金もない。
悪いのはオレたちじゃない。みんな他の奴らのせいだ。
「……」
オレが先頭になり、息を殺しながら別荘のドアに手をかけた。
「⁉」
すると不用心にも鍵はかかっておらず、ドアが開く。
玄関に入ると、中は外と比べ物にならないほど春のように暑かった。
オレたちは無意識のうちに、上着を玄関の下駄箱の上に置いた。
そして靴も脱ぎ、音を立てないようにそっと中を進んで行く。
すぐ左手の部屋から、いい匂いがあふれていた。
オレたちは顔を見合わせ、一気にその部屋に突入する。
奇麗なダイニングには、木製の高級なテーブルが置かれていた。
「飯だ!」
テーブルの上には、今作ったばかりと思える食事がたくさん並ぶ。
骨付き肉に、ミネストローネ。
どれも全て、いい匂いがした。
途端に尋常ではないほど、空腹が加速していく。
食べたい。今すぐ食べたい。ああ、食べたい。
「なんで住人はいないんだ?」
テーブルに駆け寄るオレとは違い、二人は警戒して辺りを窺っていた。
確かに食事は出来たてだというのに、人の気配はない。
それならば、誰がこの食事を用意したのか。
元々、この別荘には人の気配などなかった。
そう思えば、おかしなところだらけだ。
しかしそれすら考えられないほど、食べたくて仕方がない。
喉から手が出るほどの空腹と渇き。それがオレを支配していた。
「どーでもいいから、まず食おうぜ!」
金目の物も住人も、食べてから考えればいいだろ。
「急いで食べちゃえばいいっすよね。温かいご飯なんて、久しぶりすぎる」
「それなら……」
三人でテーブルに座り、食事についた。