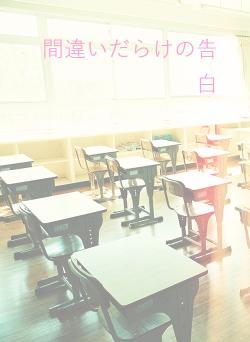「さむっ」
幸せに浸るオレの意識が、どこかから吹き込む冷たい風で引き戻される。
玄関も窓も締まっていたのに、誰か帰ってきたのか?
意識も視線も上げたオレの目に飛び込んできたのは、今まで見てきた景色とは全くの別物だった。
白い埃のかぶる室内は荒れ果て、壊れた窓からは大量の落ち葉などが部屋に吹き込んでしまっている。
もう何十年も使用されていない。
そんな変わり果てた別荘の室内だった。
「なんだこれ! どーなってんだよ! おい、眼鏡! ハート!」
ダイニングの椅子から転げるように、横たわる二人。
近づいたオレは、自分の目を疑った。
「ひっ!」
変わり果てた二人。
しかし恐る恐る触れるとまだ温かい二人は、今さっきまで生きていたらしい。
何で二人が死んでるんだよ。飯食ってる間に、何があったんだ。
夢中で食べてる間の記憶がないなんてことあるのか?
でも食べてる時の二人の声を聞いた覚えはない。
二人はまるで獣にでも齧《かじ》られたように足や顔の肉がなくなり、腸や内臓が辺り一面に巻き散らかされていた。
「なんだよ、どーなってるんだよ!」
この部屋だってそうだ。さっきまでこんなんじゃなかったのに。
確かに別荘に入った時は、小奇麗に掃除されて食事まで用意されていた。
しかしそれが一瞬のうちに、廃屋になって二人が死んでるなんてどう頑張ったってあり得ないだろう。
熊でもいたのか?
いや、それだけじゃこの有様は説明できない。
それにもし熊がいたのなら、オレだって無傷じゃすまないはずだ。
飯を食べていた時間なんて、そうも経過していない。
あいつらから目を離したのだって、夢中になってたほんの一瞬だけ……。
「本当にそうか?」
この別荘に入るまで、人の気配なんてなかった。
むしろ初めから廃屋だったという方が正しい気がする。
「でもじゃあ、あの食事はなんだったんだよ」
出来たてで湯気を立てる美味しい料理たち。
確かにオレはそれをむさぼり食べた。
あり得ないほどの食欲に駆られて。
「あれはなんだったんだ?」
思わず口を手で押さえると、ぬるりという生ぬるく気持ちの悪い感覚が伝わってきた。
食べこぼしか?
しかし手についていたのは、どこまでもどす黒い血液だった。
うわぁと短い叫び声をあげ、手を振れば、反対側の手に黒い人の髪の毛が絡みついているのが分かる。
「嘘だろ、おい……」
もう一度二人の死体を見る。
獣に齧られたような跡、なくなった肉片。
そしてオレの口についた血液……。
嗚咽とともに、何度もその場でオレは吐いた。
そして動けなくなり、警察へ自ら通報した。
オレは悪くない。
オレじゃない。
だっておかしいだろ。
オレはただ飯のために、生きていくためだけに仕事をしただけなのに。
何度もそう繰り返しながら―—
幸せに浸るオレの意識が、どこかから吹き込む冷たい風で引き戻される。
玄関も窓も締まっていたのに、誰か帰ってきたのか?
意識も視線も上げたオレの目に飛び込んできたのは、今まで見てきた景色とは全くの別物だった。
白い埃のかぶる室内は荒れ果て、壊れた窓からは大量の落ち葉などが部屋に吹き込んでしまっている。
もう何十年も使用されていない。
そんな変わり果てた別荘の室内だった。
「なんだこれ! どーなってんだよ! おい、眼鏡! ハート!」
ダイニングの椅子から転げるように、横たわる二人。
近づいたオレは、自分の目を疑った。
「ひっ!」
変わり果てた二人。
しかし恐る恐る触れるとまだ温かい二人は、今さっきまで生きていたらしい。
何で二人が死んでるんだよ。飯食ってる間に、何があったんだ。
夢中で食べてる間の記憶がないなんてことあるのか?
でも食べてる時の二人の声を聞いた覚えはない。
二人はまるで獣にでも齧《かじ》られたように足や顔の肉がなくなり、腸や内臓が辺り一面に巻き散らかされていた。
「なんだよ、どーなってるんだよ!」
この部屋だってそうだ。さっきまでこんなんじゃなかったのに。
確かに別荘に入った時は、小奇麗に掃除されて食事まで用意されていた。
しかしそれが一瞬のうちに、廃屋になって二人が死んでるなんてどう頑張ったってあり得ないだろう。
熊でもいたのか?
いや、それだけじゃこの有様は説明できない。
それにもし熊がいたのなら、オレだって無傷じゃすまないはずだ。
飯を食べていた時間なんて、そうも経過していない。
あいつらから目を離したのだって、夢中になってたほんの一瞬だけ……。
「本当にそうか?」
この別荘に入るまで、人の気配なんてなかった。
むしろ初めから廃屋だったという方が正しい気がする。
「でもじゃあ、あの食事はなんだったんだよ」
出来たてで湯気を立てる美味しい料理たち。
確かにオレはそれをむさぼり食べた。
あり得ないほどの食欲に駆られて。
「あれはなんだったんだ?」
思わず口を手で押さえると、ぬるりという生ぬるく気持ちの悪い感覚が伝わってきた。
食べこぼしか?
しかし手についていたのは、どこまでもどす黒い血液だった。
うわぁと短い叫び声をあげ、手を振れば、反対側の手に黒い人の髪の毛が絡みついているのが分かる。
「嘘だろ、おい……」
もう一度二人の死体を見る。
獣に齧られたような跡、なくなった肉片。
そしてオレの口についた血液……。
嗚咽とともに、何度もその場でオレは吐いた。
そして動けなくなり、警察へ自ら通報した。
オレは悪くない。
オレじゃない。
だっておかしいだろ。
オレはただ飯のために、生きていくためだけに仕事をしただけなのに。
何度もそう繰り返しながら―—