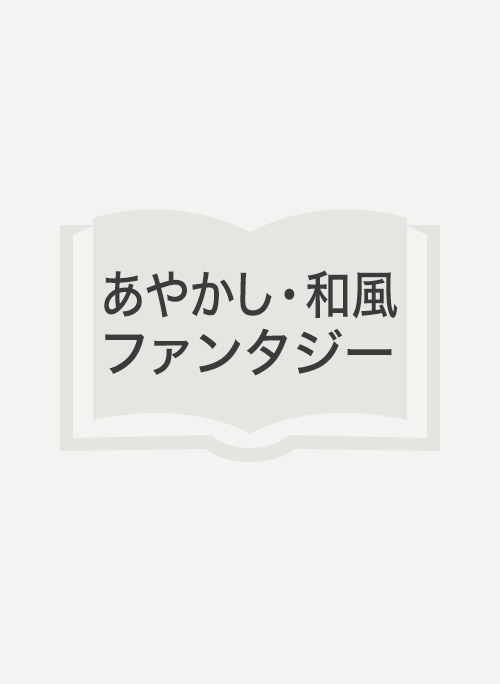「琉生、お前と新太君との婚約は破棄になった」
「え……」
父からの突然の報告に香森琉生は動揺を隠せなかった。
視線を父の横に移すと婚約者だったはずの月守新太が平然とした表情で座っている。
そして彼の隣にぴたりと寄り添っているのは琉生の妹である麗。
二人は視線がぶつかると仲睦まじく微笑み合っている。
まるで恋人同士のような光景にまさかと嫌な予感が頭を過る。
来年の春には結婚をする予定だったのに何の前触れもない婚約破棄。
すぐには受け入れられず、理由を問わずにはいられなかった。
「そんな、どうしてですか」
「麗が新太君と結婚したいと言ったんだ。本人同士も想い合っているようだし、構わないだろう」
「それは本当ですか、新太さま」
「ああ。麗ちゃんの方が愛嬌もあって可愛らしいし、天巫女としての力も十分に備わっている。それに君といても、つまらないから」
「悪く思わないでね、お姉さま。この国も香森家も新太さまと私で支えていくから」
人の婚約者を奪っておきながら反省の色など微塵も見せずに笑いかけてくる。
あまりの衝撃に言葉を失った。
(また奪われてしまった)
いつまでこんな日々が続くのか。
一つ一つ手元から消えていく。
もうこれ以上考えたくはなくて琉生は俯いた。
*
琉生が生きるこの国は大昔から妖魔が現れる。
それを退治できるのは『神在』だけ。
神在とは神を祖にもつ者のことで身体に宿る特別な力を行使して人々を妖魔から守っている。
国からも重宝されており、絶大な権力を放っていた。
そして、そんな神在を支える存在が天巫女である。
天巫女が祈りを捧げることで神在の力の増幅が可能。
稀有な彼女たちも神在の次に人々から尊ばれていた。
昔から婚姻関係もあって、それは天巫女の琉生もその立場だった。
月と夜を司る神、ツクヨミを祖にもつ月守家の次男である新太と婚約していた。
恋愛結婚ではない。
いわゆる家同士が決めた政略結婚である。
たとえ愛がなくても良い妻でありたいと努力してきたのに。
香森家の女当主になるために勉学に励んできたのに。
すべての頑張りが水の泡となってしまった。
正直、婚約破棄という事実を受け入れたくなかった。
しかし、当主である父の決定は絶対で覆すことは無理だ。
「それでは、わたしはこれからどうしたら……」
琉生の女学院卒業と同時に新太が婿として香森家へやって来る予定だった。
あと二ヶ月後に卒業式を迎えるというのに今になって破棄されるとは夢にも思わなかった。
天巫女のみが通える女学院では卒業をすれば、ほとんどの者が結婚をする。
それが白紙となれば、一体どうすれば良いのだろう。
「他の神在の一族から縁談がこない以上、お前に価値はない。この屋敷で使用人として働け」
祈りを捧げることさえできなければ、普通の人間と同じだ。
誰が婚約破棄された女を娶るというのだろう。
一生、そうしていろと告げられたも同じだ。
麗は両手をぱん、と合わせるとわざとらしく声を張って瞳を瞬かせた。
「まあ!良かったじゃない!お姉さまにぴったりの仕事があって。これからお世話、よろしくね」
彼女が当主になれば確実に今よりも扱いが酷くなるだろう。
ただでさえわがままだというのに権力や財力が与えられれば乱用しかねない。
しかし、そのようなことを本人に伝えることなどできない。
「話は以上だ。琉生、お前は部屋から出て行け」
「……はい」
そこからはあまり覚えていない。
言い渡されたその日から記憶が断片的なのは恐らく強い衝撃のせいだろう。
婚約破棄の話題はすぐに女学院に広がり、友人たちは腫れ物に触るように遠ざかっていった。
麗のわがまま、父や使用人たちの態度も日に日に悪化。
寄り添ってくれる大切な人はもうこの世には存在しない。
琉生はひとり、拭いきれない悲しみを抱えたまま卒業を迎えたのだった。
*
「ねぇ、お姉さま。この巾着袋を私にちょうだい」
「えっ……!?」
真っ白な雲がゆっくりと流れ、柔らかな日差しが降りそそぐ昼下がり。
庭の掃き掃除を終えて、玄関から自室に向かって歩いている姉を、華やかな装いの妹が廊下で待ち構えていた。
鏡台の上に置いていたはずの、桃色の巾着袋を持ちながら。
お姉さまと呼ばれた娘──香森琉生は瞠目したあと、妹の麗に駆け寄った。
「麗……!また、わたしの部屋に勝手に入ったの?」
「いいじゃない、私たち姉妹なんだから」
少しも悪びれる様子が見せず、まるで私物かのように巾着袋の赤い紐を手首に通した。
そして、その場でくるりと一回転して見せる。
「それより、お姉さま。この巾着袋は私が貰ってもいいでしょう? ほら見て、私にぴったり」
困惑している琉生にお構いなしに、これでもかと見せつけてくる。
「それは、お母さまが女学校の入学祝いで贈ってくれた物なの。麗にあげるわけにはいかないわ」
首を横に振りながら拒否すると、麗は頬をぷくりと膨らませて、こちらを睨みつけた。
「えー!私、これ欲しい!」
「ごめんなさい、本当に駄目なの。この巾着袋が無くても麗は素敵な物をすでに持っているでしょう?」
「桃色の巾着袋は持っていないもの。それに、こんな可愛らしい物はお姉さまより私に似合うわ」
確かに、桃色の生地に赤と金色の刺繍が施されている巾着袋は甘く、愛らしい雰囲気の麗によく合っている。
だからといって、渡すつもりは毛頭ない。
(困ったわ。こうなった麗はしぶといから)
琉生はどうしたものかと頭を悩ませ、尚もにっこりと微笑んでいる麗を不満げに見つめた。
今、彼女が手にしているのは琉生の亡き母である弥生からの贈り物である。
そんな大切な物だから、妹に見つからないように部屋に置いといたのに。
姉妹だからといって断りもなく、室内に入って物色するなんて神経を疑う。
母の死をきっかけに妹のわがままな性格が、より酷くなった。
化粧品も小物もお菓子も何でも欲しがる。
いや、欲しがるというより『奪う』の表現が正しいかもしれない。
何度、駄目だと言っても言うことを聞かず、最後には父を呼んで彼を味方につける。
嘘の涙を流しながら、というのがいつものお決まりである。
しかし、それを麗にとことん甘い父は気づいていない。
それもそのはず、正真正銘、彼女のあの性格は父親譲りなのだから。
『長女なのだから、それくらいあげなさい』
聞き飽きるほど耳にした言葉。
琉生の母親譲りの真面目な性格を父は好いてはいない。
むしろ嫌っていて、向けられる眼差しは、まるで母の生き写しを見ているかのよう。
それが苦痛で、早く解放されたくて、自分のお小遣いで買った物は仕方なく妹にあげていたのだけれど。
(この巾着袋はこの世にたった一つのお母さまの手作りだもの。体調が悪かったのに、わたしのために一所懸命に作ってくれた……。大切な宝物よ)
孤独で生きてきた琉生の心のよりどころを傲慢で自分勝手な妹に渡すという選択肢はない。
諭して駄目なら、強引に取り返すしか方法はない。
「お願い、返して」
手を伸ばし巾着袋を掴むと、こちらへと引っ張る。
しかし、巾着袋の紐はすでに手首に通されているので簡単には取り返せない。
それに加えて麗も渡すものかと、生地にシワが出来るほど力強く握って離さなかった。
琉生に焦りが募る。
そんな乱暴に扱うと、このままでは壊れてしまう。
ほつれだけだったら直せるかもしれない。
けれど、破けたり繊細な刺繍が解けてしまったら、すべて元通りには出来ない。
そうなったら、母に思いを馳せる物が汚れてしまう気がした。
「嫌よ!お姉さまだけ持っているなんて、ずるいわ!」
お互いに巾着袋を掴む手は緩めず、引っ張り合いになる。
ここで一瞬でも気を抜けば、取られてしまう。
そう感じた琉生は一段と力を込めて、手前へと引き寄せた。
「……っ!」
その瞬間、麗の手から紐がするりと抜けて、巾着袋が手元に戻ってくる。
かなり、くしゃりとなって形が歪んでいるけれど、どこも破れてはいないようだ。
綺麗な状態だった母からの贈り物が不格好になってしまったのは残念だけれど、無事に帰ってくれば、もうそれで十分だった。
(良かっ……)
「きゃあっ!」
安堵して息をつこうとしたとき、甲高く短い悲鳴が辺りに響いた。
気づけば、麗は引っ張り合っていた反動で後ろに倒れ、尻もちをついていた。
痛み、悔しさ、怒り。
彼女から伝わる、黒く渦巻くような感情。
眉をつり上げ、大きな瞳を潤ませながらこちらを睨みつけている。
大丈夫?
そのたった一言が出てこなかった。
気遣う余裕すら今の琉生にはなくて、ただ見ていることしか出来ない。
母からの大切な贈り物をこんな妹に渡すな、何も間違っていないと、まるで悪魔が耳元で囁いているような気分になる。
昔だったら手を差し伸べていたのかもしれない。
ごめんなさいと謝って、物を渡していたかもしれない。
泣いている妹を助けずに、ただ立っているなんて自分が悪い子になったみたいだった。
「何事だ……!」
これだけ大きな声や音を立てれば、第三者の耳に届くのは当然だ。
騒ぎを聞きつけた父、冬吾が板張りの廊下を軋ませながら大股で歩いてくる。
涙目になりながら座り込む麗、呆然と立ち尽くす琉生。
(早く説明しないと)
普段から厳しい父も、麗が欲しがっている物が琉生の宝物だと知れば、味方になってくれるかもしれない。
「お、お父さま──」
「お前、麗に何をした」
「……っ」
状況を説明するために口を開くが、あまりの恐怖にすぐに噤んでしまった。
一度、冬吾と視線が重なるがすぐに逸らされる。
そしてそのまま琉生の横を通り過ぎると片膝をついた。
「どうした、麗」
分かっていた、父が彼女を選ぶことは。
何も驚くような珍しいことではない、これは香森家の常だ。
冬吾の問いかけに待ってましたと言わんばかりに麗は人さし指を琉生に突きつけた。
「お父さま!あのね、お姉さまにその巾着袋が欲しいってお願いしたら意地悪してきたの……!」
まただ、麗お得意の話の誇張。
父の前では必ず、まるで自分が虐められているように仕立てるのだ。
しかし今日こそは、きちんと弁明しなくては。
「意地悪なんてしていないわ。これはあげられないって言っているのに麗が無理矢理──」
「見苦しいぞ、琉生」
冬吾は麗の背中に手を添えながら共に立ち上がると、琉生を睨みつけた。
そして呆れたように息を吐くと、腕を組みながら弁明の余地を与えさせずに続ける。
「お前は姉なのだから巾着袋の一つくらい、麗にあげなさい」
「しかし、これはお母さまからの大切な贈り物なのです」
「あいつなんかが作った物をまだ持っていたのか。さっさと捨ててしまえば良いものを」
父と母も正反対の性格で一緒にいるところをほとんど見たことがない。
傲慢で冷酷な父、心優しく真面目な母。
しかし母は父にどれだけ冷たくされようとも良き妻として勤めを果たそうと頑張っていた。
二人の娘に多くの愛情を注ぎ、時には巫女として妖魔退治の補佐にも赴いていた。
病で倒れる直前まで。
厳しい父から守るように寄り添ってくれた母が琉生は大好きだった。
だからこそ、酷い物言いをする父を許せなかった。
「そんな言い方はあんまりではありませんか、お父さま」
両手を固く握りしめながら訴えかける琉生に、ぴくりと眉を動かすと冬吾は声を荒げた。
「父親に向かってなんだ、その態度は!こんなごみなど見たくもないわ!」
「きゃっ!」
冬吾は琉生が手にしていた巾着袋を奪うと、廊下に叩き付ける。
そして片足を上げると思いっきり踏みつけた。
「お父さま!やめてください!」
冬吾を押しのけようとするが、相手は体格の良い大人の男。
そう簡単に退けられない。
みるみるうちに巾着袋は元の美しさを失っていく。
(麗だってあんなに欲しがっていたのに)
手に入れたかった物がこのようなざまになってしまえば麗も黙ってはいないだろう。
彼女も止めに入れば、父も我に返るかもしれない。
本当は協力などしたくないが、今は悠長にしてはいられない。
ちらりと麗に視線を移すと琉生は愕然とした。
馬鹿さ加減に自分で自分を殴りたくなる。
『一緒に止めてくれる』なんて考えが甘かったのだ。
視線の先の彼女は泣いているわけでも怒っているわけでもなかった。
(ああ、麗。これが貴方の本来の狙いなのね)
父の背後に立っていた彼女は恐ろしいほど美しい笑みを浮かべていた。
気に食わない姉の宝物を壊すこと、最初から麗はこの時を待っていたのだ。
自分がいかに愚かで馬鹿な存在だと身に染みて理解する。
術中に陥って酷い目にあうなんて幾度なく味わってきたのに。
「お前はそんなだから、新太君に愛想をつかれるんだ」
(今、新太さまの名前を出さなくても良いじゃない。でも)
反論できなかった、だってその通りだから。
地味で暗い琉生と愛嬌があり華やかな麗。
どんな男性だって迷わずに後者を選ぶだろう。
新太もそのひとりだっただけのこと。
「やだ、お父さま。新太さんは家のことを考えてお姉さまとの婚約関係を続けていただけ。愛など最初からありませんわ」
その彼を手に入れた本人は口元を手で隠しながら笑いを湛えている。
琉生も新太を心から愛していたわけではない。
それでも結婚するのだから、少しでも歩み寄りたいと思っていた。
いつか本物の夫婦になれると信じて。
しかし、彼はその思いを無下にして裏切った。
「麗、百貨店で新しい巾着袋を買うと良い。必要な金なら付き人に持たせておく」
「まあ、本当に? お父さま、ありがとう……!」
麗はぱっと顔を上げ、瞳を輝かせた。
こうして父の同情を得て、物を買ってもらう流れは毎度のこと。
今になっては、この光景に慣れすぎて羨ましいとも思わなくなった。
そしてその瞬間、冬吾が巾着袋を踏みつけていた足を上げた。
(今なら……!)
もう一度、この手の中に戻ってくるのなら汚れていても壊れていても構わない。
今度は絶対に無くさないように、盗られないように肌身離さず持っていよう──。
手を伸ばし、指先が巾着袋に触れる。
(良かっ……)
安堵したのもつかの間。
琉生が掴むより先に冬吾が無造作に掴んだ。
「お父さま!返してください!」
すぐに奪い返そうとするが、巾着袋は高く持ち上げられてしまい、まったく届かない。
数回、飛び跳ねたところで冬吾は琉生を突き飛ばした。
「きゃっ!」
三人が立っていたのは中庭に面した廊下。
琉生は、その衝撃でぐらりと身体が傾き、地面に倒れ込んだ。
そこまでの高さはないとはいえ、全身に痛みが走り、すぐには起き上がれなかった。
苛立ちを滲ませながら見下す父とわざとらしく憐れむ眼差しを向ける妹。
そして何事もなかったように無視をして近くを歩く使用人たち。
誰も手など差し伸べてはくれない。
「あら。お姉さまったら、そんな惨めな姿になっちゃって。鈍くさいから皆から嫌われるのよ」
「これは、お前にはもう必要ないだろう。結婚できないならば使用人として働くしか道はないのだ。自由な外出など私は許可しないからな」
冬吾は鼻を鳴らして踵を返す。
琉生は痛みに耐えながら必死に立ちあがる。
「お父さま!お願いです、どうかそれだけは……!」
「うるさい、耳障りだ。誰か押さえつけとけ。これ以上騒ぐようならば蔵に閉じ込めろ」
冬吾は傍に控えていた数名の使用人に指示を与えると廊下の奥へ消えていった。
追いかけようとする琉生の身体を両側から二人の使用人が押さえつける。
必死に解こうとするが、貧弱な琉生では大人にはかなわない。
「離してっ!お父さま、お父さま!」
何度呼びかけても冬吾は足を止め振り返ることはなかった。
顔を青ざめさせている琉生に麗は余裕のある笑みを浮かべながら、ぐいっと近づいた。
「可愛い妹が欲しいって言ったら、素直にあげる。そんなの当たり前でしょう? 心の狭いお姉さま。私が香森家の女当主になったら有無を言わさずに全部奪ってあげる」
ふふっと笑うと艶やかな振袖を翻しながら遠ざかっていく。
わかっていた、自由に生きていけないことは。
途端に全身の力が抜けて、へたり込む。
抵抗しなくなった琉生に使用人たちは顔を見合わせると、彼女の腕から手を離した。
目の前が真っ暗になったような気がして、しばらくの間、その場から動けなかった。
「え……」
父からの突然の報告に香森琉生は動揺を隠せなかった。
視線を父の横に移すと婚約者だったはずの月守新太が平然とした表情で座っている。
そして彼の隣にぴたりと寄り添っているのは琉生の妹である麗。
二人は視線がぶつかると仲睦まじく微笑み合っている。
まるで恋人同士のような光景にまさかと嫌な予感が頭を過る。
来年の春には結婚をする予定だったのに何の前触れもない婚約破棄。
すぐには受け入れられず、理由を問わずにはいられなかった。
「そんな、どうしてですか」
「麗が新太君と結婚したいと言ったんだ。本人同士も想い合っているようだし、構わないだろう」
「それは本当ですか、新太さま」
「ああ。麗ちゃんの方が愛嬌もあって可愛らしいし、天巫女としての力も十分に備わっている。それに君といても、つまらないから」
「悪く思わないでね、お姉さま。この国も香森家も新太さまと私で支えていくから」
人の婚約者を奪っておきながら反省の色など微塵も見せずに笑いかけてくる。
あまりの衝撃に言葉を失った。
(また奪われてしまった)
いつまでこんな日々が続くのか。
一つ一つ手元から消えていく。
もうこれ以上考えたくはなくて琉生は俯いた。
*
琉生が生きるこの国は大昔から妖魔が現れる。
それを退治できるのは『神在』だけ。
神在とは神を祖にもつ者のことで身体に宿る特別な力を行使して人々を妖魔から守っている。
国からも重宝されており、絶大な権力を放っていた。
そして、そんな神在を支える存在が天巫女である。
天巫女が祈りを捧げることで神在の力の増幅が可能。
稀有な彼女たちも神在の次に人々から尊ばれていた。
昔から婚姻関係もあって、それは天巫女の琉生もその立場だった。
月と夜を司る神、ツクヨミを祖にもつ月守家の次男である新太と婚約していた。
恋愛結婚ではない。
いわゆる家同士が決めた政略結婚である。
たとえ愛がなくても良い妻でありたいと努力してきたのに。
香森家の女当主になるために勉学に励んできたのに。
すべての頑張りが水の泡となってしまった。
正直、婚約破棄という事実を受け入れたくなかった。
しかし、当主である父の決定は絶対で覆すことは無理だ。
「それでは、わたしはこれからどうしたら……」
琉生の女学院卒業と同時に新太が婿として香森家へやって来る予定だった。
あと二ヶ月後に卒業式を迎えるというのに今になって破棄されるとは夢にも思わなかった。
天巫女のみが通える女学院では卒業をすれば、ほとんどの者が結婚をする。
それが白紙となれば、一体どうすれば良いのだろう。
「他の神在の一族から縁談がこない以上、お前に価値はない。この屋敷で使用人として働け」
祈りを捧げることさえできなければ、普通の人間と同じだ。
誰が婚約破棄された女を娶るというのだろう。
一生、そうしていろと告げられたも同じだ。
麗は両手をぱん、と合わせるとわざとらしく声を張って瞳を瞬かせた。
「まあ!良かったじゃない!お姉さまにぴったりの仕事があって。これからお世話、よろしくね」
彼女が当主になれば確実に今よりも扱いが酷くなるだろう。
ただでさえわがままだというのに権力や財力が与えられれば乱用しかねない。
しかし、そのようなことを本人に伝えることなどできない。
「話は以上だ。琉生、お前は部屋から出て行け」
「……はい」
そこからはあまり覚えていない。
言い渡されたその日から記憶が断片的なのは恐らく強い衝撃のせいだろう。
婚約破棄の話題はすぐに女学院に広がり、友人たちは腫れ物に触るように遠ざかっていった。
麗のわがまま、父や使用人たちの態度も日に日に悪化。
寄り添ってくれる大切な人はもうこの世には存在しない。
琉生はひとり、拭いきれない悲しみを抱えたまま卒業を迎えたのだった。
*
「ねぇ、お姉さま。この巾着袋を私にちょうだい」
「えっ……!?」
真っ白な雲がゆっくりと流れ、柔らかな日差しが降りそそぐ昼下がり。
庭の掃き掃除を終えて、玄関から自室に向かって歩いている姉を、華やかな装いの妹が廊下で待ち構えていた。
鏡台の上に置いていたはずの、桃色の巾着袋を持ちながら。
お姉さまと呼ばれた娘──香森琉生は瞠目したあと、妹の麗に駆け寄った。
「麗……!また、わたしの部屋に勝手に入ったの?」
「いいじゃない、私たち姉妹なんだから」
少しも悪びれる様子が見せず、まるで私物かのように巾着袋の赤い紐を手首に通した。
そして、その場でくるりと一回転して見せる。
「それより、お姉さま。この巾着袋は私が貰ってもいいでしょう? ほら見て、私にぴったり」
困惑している琉生にお構いなしに、これでもかと見せつけてくる。
「それは、お母さまが女学校の入学祝いで贈ってくれた物なの。麗にあげるわけにはいかないわ」
首を横に振りながら拒否すると、麗は頬をぷくりと膨らませて、こちらを睨みつけた。
「えー!私、これ欲しい!」
「ごめんなさい、本当に駄目なの。この巾着袋が無くても麗は素敵な物をすでに持っているでしょう?」
「桃色の巾着袋は持っていないもの。それに、こんな可愛らしい物はお姉さまより私に似合うわ」
確かに、桃色の生地に赤と金色の刺繍が施されている巾着袋は甘く、愛らしい雰囲気の麗によく合っている。
だからといって、渡すつもりは毛頭ない。
(困ったわ。こうなった麗はしぶといから)
琉生はどうしたものかと頭を悩ませ、尚もにっこりと微笑んでいる麗を不満げに見つめた。
今、彼女が手にしているのは琉生の亡き母である弥生からの贈り物である。
そんな大切な物だから、妹に見つからないように部屋に置いといたのに。
姉妹だからといって断りもなく、室内に入って物色するなんて神経を疑う。
母の死をきっかけに妹のわがままな性格が、より酷くなった。
化粧品も小物もお菓子も何でも欲しがる。
いや、欲しがるというより『奪う』の表現が正しいかもしれない。
何度、駄目だと言っても言うことを聞かず、最後には父を呼んで彼を味方につける。
嘘の涙を流しながら、というのがいつものお決まりである。
しかし、それを麗にとことん甘い父は気づいていない。
それもそのはず、正真正銘、彼女のあの性格は父親譲りなのだから。
『長女なのだから、それくらいあげなさい』
聞き飽きるほど耳にした言葉。
琉生の母親譲りの真面目な性格を父は好いてはいない。
むしろ嫌っていて、向けられる眼差しは、まるで母の生き写しを見ているかのよう。
それが苦痛で、早く解放されたくて、自分のお小遣いで買った物は仕方なく妹にあげていたのだけれど。
(この巾着袋はこの世にたった一つのお母さまの手作りだもの。体調が悪かったのに、わたしのために一所懸命に作ってくれた……。大切な宝物よ)
孤独で生きてきた琉生の心のよりどころを傲慢で自分勝手な妹に渡すという選択肢はない。
諭して駄目なら、強引に取り返すしか方法はない。
「お願い、返して」
手を伸ばし巾着袋を掴むと、こちらへと引っ張る。
しかし、巾着袋の紐はすでに手首に通されているので簡単には取り返せない。
それに加えて麗も渡すものかと、生地にシワが出来るほど力強く握って離さなかった。
琉生に焦りが募る。
そんな乱暴に扱うと、このままでは壊れてしまう。
ほつれだけだったら直せるかもしれない。
けれど、破けたり繊細な刺繍が解けてしまったら、すべて元通りには出来ない。
そうなったら、母に思いを馳せる物が汚れてしまう気がした。
「嫌よ!お姉さまだけ持っているなんて、ずるいわ!」
お互いに巾着袋を掴む手は緩めず、引っ張り合いになる。
ここで一瞬でも気を抜けば、取られてしまう。
そう感じた琉生は一段と力を込めて、手前へと引き寄せた。
「……っ!」
その瞬間、麗の手から紐がするりと抜けて、巾着袋が手元に戻ってくる。
かなり、くしゃりとなって形が歪んでいるけれど、どこも破れてはいないようだ。
綺麗な状態だった母からの贈り物が不格好になってしまったのは残念だけれど、無事に帰ってくれば、もうそれで十分だった。
(良かっ……)
「きゃあっ!」
安堵して息をつこうとしたとき、甲高く短い悲鳴が辺りに響いた。
気づけば、麗は引っ張り合っていた反動で後ろに倒れ、尻もちをついていた。
痛み、悔しさ、怒り。
彼女から伝わる、黒く渦巻くような感情。
眉をつり上げ、大きな瞳を潤ませながらこちらを睨みつけている。
大丈夫?
そのたった一言が出てこなかった。
気遣う余裕すら今の琉生にはなくて、ただ見ていることしか出来ない。
母からの大切な贈り物をこんな妹に渡すな、何も間違っていないと、まるで悪魔が耳元で囁いているような気分になる。
昔だったら手を差し伸べていたのかもしれない。
ごめんなさいと謝って、物を渡していたかもしれない。
泣いている妹を助けずに、ただ立っているなんて自分が悪い子になったみたいだった。
「何事だ……!」
これだけ大きな声や音を立てれば、第三者の耳に届くのは当然だ。
騒ぎを聞きつけた父、冬吾が板張りの廊下を軋ませながら大股で歩いてくる。
涙目になりながら座り込む麗、呆然と立ち尽くす琉生。
(早く説明しないと)
普段から厳しい父も、麗が欲しがっている物が琉生の宝物だと知れば、味方になってくれるかもしれない。
「お、お父さま──」
「お前、麗に何をした」
「……っ」
状況を説明するために口を開くが、あまりの恐怖にすぐに噤んでしまった。
一度、冬吾と視線が重なるがすぐに逸らされる。
そしてそのまま琉生の横を通り過ぎると片膝をついた。
「どうした、麗」
分かっていた、父が彼女を選ぶことは。
何も驚くような珍しいことではない、これは香森家の常だ。
冬吾の問いかけに待ってましたと言わんばかりに麗は人さし指を琉生に突きつけた。
「お父さま!あのね、お姉さまにその巾着袋が欲しいってお願いしたら意地悪してきたの……!」
まただ、麗お得意の話の誇張。
父の前では必ず、まるで自分が虐められているように仕立てるのだ。
しかし今日こそは、きちんと弁明しなくては。
「意地悪なんてしていないわ。これはあげられないって言っているのに麗が無理矢理──」
「見苦しいぞ、琉生」
冬吾は麗の背中に手を添えながら共に立ち上がると、琉生を睨みつけた。
そして呆れたように息を吐くと、腕を組みながら弁明の余地を与えさせずに続ける。
「お前は姉なのだから巾着袋の一つくらい、麗にあげなさい」
「しかし、これはお母さまからの大切な贈り物なのです」
「あいつなんかが作った物をまだ持っていたのか。さっさと捨ててしまえば良いものを」
父と母も正反対の性格で一緒にいるところをほとんど見たことがない。
傲慢で冷酷な父、心優しく真面目な母。
しかし母は父にどれだけ冷たくされようとも良き妻として勤めを果たそうと頑張っていた。
二人の娘に多くの愛情を注ぎ、時には巫女として妖魔退治の補佐にも赴いていた。
病で倒れる直前まで。
厳しい父から守るように寄り添ってくれた母が琉生は大好きだった。
だからこそ、酷い物言いをする父を許せなかった。
「そんな言い方はあんまりではありませんか、お父さま」
両手を固く握りしめながら訴えかける琉生に、ぴくりと眉を動かすと冬吾は声を荒げた。
「父親に向かってなんだ、その態度は!こんなごみなど見たくもないわ!」
「きゃっ!」
冬吾は琉生が手にしていた巾着袋を奪うと、廊下に叩き付ける。
そして片足を上げると思いっきり踏みつけた。
「お父さま!やめてください!」
冬吾を押しのけようとするが、相手は体格の良い大人の男。
そう簡単に退けられない。
みるみるうちに巾着袋は元の美しさを失っていく。
(麗だってあんなに欲しがっていたのに)
手に入れたかった物がこのようなざまになってしまえば麗も黙ってはいないだろう。
彼女も止めに入れば、父も我に返るかもしれない。
本当は協力などしたくないが、今は悠長にしてはいられない。
ちらりと麗に視線を移すと琉生は愕然とした。
馬鹿さ加減に自分で自分を殴りたくなる。
『一緒に止めてくれる』なんて考えが甘かったのだ。
視線の先の彼女は泣いているわけでも怒っているわけでもなかった。
(ああ、麗。これが貴方の本来の狙いなのね)
父の背後に立っていた彼女は恐ろしいほど美しい笑みを浮かべていた。
気に食わない姉の宝物を壊すこと、最初から麗はこの時を待っていたのだ。
自分がいかに愚かで馬鹿な存在だと身に染みて理解する。
術中に陥って酷い目にあうなんて幾度なく味わってきたのに。
「お前はそんなだから、新太君に愛想をつかれるんだ」
(今、新太さまの名前を出さなくても良いじゃない。でも)
反論できなかった、だってその通りだから。
地味で暗い琉生と愛嬌があり華やかな麗。
どんな男性だって迷わずに後者を選ぶだろう。
新太もそのひとりだっただけのこと。
「やだ、お父さま。新太さんは家のことを考えてお姉さまとの婚約関係を続けていただけ。愛など最初からありませんわ」
その彼を手に入れた本人は口元を手で隠しながら笑いを湛えている。
琉生も新太を心から愛していたわけではない。
それでも結婚するのだから、少しでも歩み寄りたいと思っていた。
いつか本物の夫婦になれると信じて。
しかし、彼はその思いを無下にして裏切った。
「麗、百貨店で新しい巾着袋を買うと良い。必要な金なら付き人に持たせておく」
「まあ、本当に? お父さま、ありがとう……!」
麗はぱっと顔を上げ、瞳を輝かせた。
こうして父の同情を得て、物を買ってもらう流れは毎度のこと。
今になっては、この光景に慣れすぎて羨ましいとも思わなくなった。
そしてその瞬間、冬吾が巾着袋を踏みつけていた足を上げた。
(今なら……!)
もう一度、この手の中に戻ってくるのなら汚れていても壊れていても構わない。
今度は絶対に無くさないように、盗られないように肌身離さず持っていよう──。
手を伸ばし、指先が巾着袋に触れる。
(良かっ……)
安堵したのもつかの間。
琉生が掴むより先に冬吾が無造作に掴んだ。
「お父さま!返してください!」
すぐに奪い返そうとするが、巾着袋は高く持ち上げられてしまい、まったく届かない。
数回、飛び跳ねたところで冬吾は琉生を突き飛ばした。
「きゃっ!」
三人が立っていたのは中庭に面した廊下。
琉生は、その衝撃でぐらりと身体が傾き、地面に倒れ込んだ。
そこまでの高さはないとはいえ、全身に痛みが走り、すぐには起き上がれなかった。
苛立ちを滲ませながら見下す父とわざとらしく憐れむ眼差しを向ける妹。
そして何事もなかったように無視をして近くを歩く使用人たち。
誰も手など差し伸べてはくれない。
「あら。お姉さまったら、そんな惨めな姿になっちゃって。鈍くさいから皆から嫌われるのよ」
「これは、お前にはもう必要ないだろう。結婚できないならば使用人として働くしか道はないのだ。自由な外出など私は許可しないからな」
冬吾は鼻を鳴らして踵を返す。
琉生は痛みに耐えながら必死に立ちあがる。
「お父さま!お願いです、どうかそれだけは……!」
「うるさい、耳障りだ。誰か押さえつけとけ。これ以上騒ぐようならば蔵に閉じ込めろ」
冬吾は傍に控えていた数名の使用人に指示を与えると廊下の奥へ消えていった。
追いかけようとする琉生の身体を両側から二人の使用人が押さえつける。
必死に解こうとするが、貧弱な琉生では大人にはかなわない。
「離してっ!お父さま、お父さま!」
何度呼びかけても冬吾は足を止め振り返ることはなかった。
顔を青ざめさせている琉生に麗は余裕のある笑みを浮かべながら、ぐいっと近づいた。
「可愛い妹が欲しいって言ったら、素直にあげる。そんなの当たり前でしょう? 心の狭いお姉さま。私が香森家の女当主になったら有無を言わさずに全部奪ってあげる」
ふふっと笑うと艶やかな振袖を翻しながら遠ざかっていく。
わかっていた、自由に生きていけないことは。
途端に全身の力が抜けて、へたり込む。
抵抗しなくなった琉生に使用人たちは顔を見合わせると、彼女の腕から手を離した。
目の前が真っ暗になったような気がして、しばらくの間、その場から動けなかった。