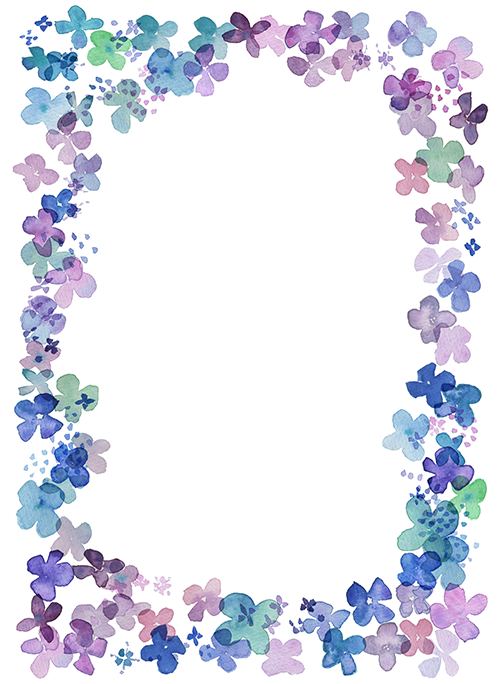俺の予想に反して、高森はなかなか諦めなかった。
ある日の放課後。
俺は高森に見つからぬよう校舎を出た。下校中まで何か言われたらと危惧したからだったけれど、帰り道で会ってしまった。
「偶然ですね先輩」
「偶然じゃないだろ」
「実は待ってました」
へへっと照れたように笑う高森に、俺はため息をこらえ、仕方なく一緒に歩き出す。
すでに外は暗くなりかけていて、ひっそりとした二車線の道路には外灯の明かりがきらめき始めていた。
歩く間、高森はテンション高く喋り続け、顔もどこかにやけていた。
何がそんなに嬉しいんだ。ただ一緒に帰るだけなのに。
俺は浮かれた高森が車と接触しないように、車道側を歩いた。
「あのさ、もし今俺と高森が付き合うとしたら──」
「え? 俺と付き合ってくれるんですか?」
「もしって言ってんだろ。……お互いの気持ちに大きなズレがあると思うんだけどいいのか?」
「気にしません。むしろその差が心地いいです」
「嫌だろ。自分ばっかりが相手のこと好きなの」
「嫌じゃないです。というより好きになってもらってから付き合いますよ俺は」
笑顔になって宣言される。
どこからそんな自信が来るのだろう。
そのあとも高森は相変わらず嬉しそうで。
道端の側溝の蓋が開いてるのに気付かずにずぼっと落ちた。
まあまあ幅があったせいで、高森は体ごと側溝にはまっている。
ちょうど外灯の下、照らし出された高森の姿はお世辞にもかっこいいとは言えず、笑いそうになる。
しかし、落ちた本人が相当ショックを受けて呆然とした様子なので、俺は笑わないよう気をつけて手を差し出した。
「大丈夫か? よかったな。水がない時期で」
「ほんとですね。あーもう。くそださくて先輩呆れてますよね」
「落ちる前から呆れてるよ」
腕を掴んで起こしてやると、勢いがよすぎたのか、高森がこっちにもたれ掛かってくる。
細く見えてもしっかり重いんだな、と思いながら体を離し、制服についた汚れを払ってやる。
「怪我してないか?」
「……大丈夫です」
やけに静かな声で高森が答える。
なぜだろうと顔を見れば真っ赤になっていた。
外灯の明かりのおかげで首筋までうっすら染まっているのまで見える。
本当に俺のことが好きなんだ、と嫌でも実感してしまう。
黙り込んでしまった俺に、ふざけて高森が抱きついてこようとして、柄にもなくびくつきそうになった。
「先輩が久々に俺に優しくて泣きそう」
その声は俺が高森の想いの強さに驚かないように、わざと茶化しているみたいに明るかった。
「離れろよ。溝の匂いがうつるだろ」
手で押し返すと、横から逆に抱きつかれる。意外と溝くさくはない。
「先輩、このまま帰りましょう」
「帰れるか。二人まとめて溝に落ちたらどうすんだよ」
「その時は朝まで一緒にいます」
「だめだろ」
高森を引きはがし、二人で並んで歩いて行く。
途中の交差点で高森とは別れた。
「先輩さようならー」
大きく手を振る高森に俺は「おー」とだけ返す。
しばらく歩いて振り返ったらまだ高森はこっちを見ていた。
高森の健気な姿を見ても、相変わらずきゅんとはしない。
けれど、胸の奥をほんの少し揺さぶられた。
(美紀もこんな気分だったのかも)
一人歩きながら俺は思う。
元彼女の美紀とは一年の頃同じクラスで、俺から告白して付き合うようになった。
彼女が自分のことをそんなに好きじゃないのは付き合う前から知っていた。
それでも、告白を受け入れてくれたのだから、いつかはちゃんと好きになってくれるのではと思っていた。
けれど、そう上手くはいかなかった。
『ごめんね』とあっさり別れを告げられた。
あの時のごめんねにはたぶん「好きになってあげられなくて」が含まれていた。
彼女とは今も普通に話せているので、嫌いだから俺を振ったわけではないのだろう。
よっぽど嫌な相手ではない限り、人は好きだと言ってくれる相手に対して情が湧いてしまうのものなのかもしれない。
今の俺の高森に対する思いもそれと似ている。
彼女にフラれて、自尊心がすり減っているところに好きと言われて、どこかで心地よくなっていたんじゃないだろうか。
いつか諦めるだろうなんて静観したまま、流されるのはよくない気がしてくる。
答えをきっちり出してもらえないまま、側にいるのは俺なら耐えられない。
もっと高森のことをちゃんと拒絶しよう。
そう決めて俺は家に帰った。
ある日の放課後。
俺は高森に見つからぬよう校舎を出た。下校中まで何か言われたらと危惧したからだったけれど、帰り道で会ってしまった。
「偶然ですね先輩」
「偶然じゃないだろ」
「実は待ってました」
へへっと照れたように笑う高森に、俺はため息をこらえ、仕方なく一緒に歩き出す。
すでに外は暗くなりかけていて、ひっそりとした二車線の道路には外灯の明かりがきらめき始めていた。
歩く間、高森はテンション高く喋り続け、顔もどこかにやけていた。
何がそんなに嬉しいんだ。ただ一緒に帰るだけなのに。
俺は浮かれた高森が車と接触しないように、車道側を歩いた。
「あのさ、もし今俺と高森が付き合うとしたら──」
「え? 俺と付き合ってくれるんですか?」
「もしって言ってんだろ。……お互いの気持ちに大きなズレがあると思うんだけどいいのか?」
「気にしません。むしろその差が心地いいです」
「嫌だろ。自分ばっかりが相手のこと好きなの」
「嫌じゃないです。というより好きになってもらってから付き合いますよ俺は」
笑顔になって宣言される。
どこからそんな自信が来るのだろう。
そのあとも高森は相変わらず嬉しそうで。
道端の側溝の蓋が開いてるのに気付かずにずぼっと落ちた。
まあまあ幅があったせいで、高森は体ごと側溝にはまっている。
ちょうど外灯の下、照らし出された高森の姿はお世辞にもかっこいいとは言えず、笑いそうになる。
しかし、落ちた本人が相当ショックを受けて呆然とした様子なので、俺は笑わないよう気をつけて手を差し出した。
「大丈夫か? よかったな。水がない時期で」
「ほんとですね。あーもう。くそださくて先輩呆れてますよね」
「落ちる前から呆れてるよ」
腕を掴んで起こしてやると、勢いがよすぎたのか、高森がこっちにもたれ掛かってくる。
細く見えてもしっかり重いんだな、と思いながら体を離し、制服についた汚れを払ってやる。
「怪我してないか?」
「……大丈夫です」
やけに静かな声で高森が答える。
なぜだろうと顔を見れば真っ赤になっていた。
外灯の明かりのおかげで首筋までうっすら染まっているのまで見える。
本当に俺のことが好きなんだ、と嫌でも実感してしまう。
黙り込んでしまった俺に、ふざけて高森が抱きついてこようとして、柄にもなくびくつきそうになった。
「先輩が久々に俺に優しくて泣きそう」
その声は俺が高森の想いの強さに驚かないように、わざと茶化しているみたいに明るかった。
「離れろよ。溝の匂いがうつるだろ」
手で押し返すと、横から逆に抱きつかれる。意外と溝くさくはない。
「先輩、このまま帰りましょう」
「帰れるか。二人まとめて溝に落ちたらどうすんだよ」
「その時は朝まで一緒にいます」
「だめだろ」
高森を引きはがし、二人で並んで歩いて行く。
途中の交差点で高森とは別れた。
「先輩さようならー」
大きく手を振る高森に俺は「おー」とだけ返す。
しばらく歩いて振り返ったらまだ高森はこっちを見ていた。
高森の健気な姿を見ても、相変わらずきゅんとはしない。
けれど、胸の奥をほんの少し揺さぶられた。
(美紀もこんな気分だったのかも)
一人歩きながら俺は思う。
元彼女の美紀とは一年の頃同じクラスで、俺から告白して付き合うようになった。
彼女が自分のことをそんなに好きじゃないのは付き合う前から知っていた。
それでも、告白を受け入れてくれたのだから、いつかはちゃんと好きになってくれるのではと思っていた。
けれど、そう上手くはいかなかった。
『ごめんね』とあっさり別れを告げられた。
あの時のごめんねにはたぶん「好きになってあげられなくて」が含まれていた。
彼女とは今も普通に話せているので、嫌いだから俺を振ったわけではないのだろう。
よっぽど嫌な相手ではない限り、人は好きだと言ってくれる相手に対して情が湧いてしまうのものなのかもしれない。
今の俺の高森に対する思いもそれと似ている。
彼女にフラれて、自尊心がすり減っているところに好きと言われて、どこかで心地よくなっていたんじゃないだろうか。
いつか諦めるだろうなんて静観したまま、流されるのはよくない気がしてくる。
答えをきっちり出してもらえないまま、側にいるのは俺なら耐えられない。
もっと高森のことをちゃんと拒絶しよう。
そう決めて俺は家に帰った。