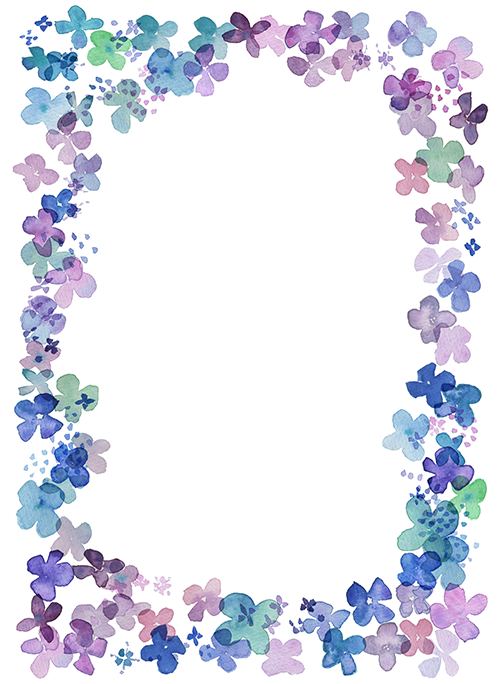戸惑う俺に対し、その日から高森は今までの高森ではなくなった。
「先輩。先輩って男ですよね」
部活中、校舎の外を走っていたら隣にいた高森が話しかけてくる。
週に何回かある体力づくりのためのトレーニングが行われる日のことだった。
俺は何を言い出すんだと思いながらも、一応答える。
「高森には俺が女子に見えてんのか?」
「いえ。ちゃんと男に見えてますけど、なんかこう、俺と同じ男なのにむさ苦しさみたいなのがまったくないなあと思って。好きだからこう思うんですかね」
俺はどう反応すればいいのか迷って逃げることにした。
俺もお前と同じ男だよ、と言うのすら面倒だった。
「俺先行くからな」
「待ってください! 先輩最近俺のこと適当に扱いすぎじゃないですか? 前は『大丈夫か?しんどくないか?ゆっくりでいいからな』とか気遣ってくれたのに!」
「知るか!」
無視して先に音楽室に戻る。
真面目に指導してきた後輩が突然変なことを言いだし始めたこっちの身にもなってほしい。
今までの高森は本当にいい後輩だった。
何を言ってもすぐ理解してくれるし、肺活量もあって何なら俺より楽器の演奏も上手いくらいで。
それが今はものすごく手の掛かる後輩に変わってしまった。
高森は部活で会う度、俺に好きだの何だのと伝えてくる。
俺はそんなこと言われてもどうすることもできないのに。
「先輩は平気なんですか。こんなこと言う俺が毎日側にいるの」
数日過ぎてから、いつもの練習場所で高森がこちらをうかがうように聞いてきた。
「平気じゃないし迷惑だってわかってるならやめてくれよ」
「今更無理です。黙ってて先輩が俺に振り向いてくれるなら黙ってますけど、そんなわけないでしょ?」
大人な顔をして高森が言う。
「だからこれからも続けます。……先輩もそんなに嫌ってわけじゃなさそうだし」
「どこを見てそう思うんだよ」
「好きです先輩」
高森が微笑む。
放課後の誰もいない廊下は静かで逃げ場もない。
どきどきなんかはしないけど、このまま言葉を浴びせ続けられたらいったいどうなってしまうんだろうと不安になる。
思えば、こんな風に誰かから一途に想われたことなんてなかった。
別れた彼女にも告白は俺からしたし、それまでも片想いしかしたことがない。
それに、俺は高森のことが嫌いってわけではない。
普通こんな風に誰かに対して、まっすぐ好きと言えるものなんだろうか。
少なくとも俺にはできない。
だから素直にすごいと思う。
それを俺に言うのは理解できないけど。
「どこがそんなにいいんだよ俺なんか」
「だから言ったじゃないですか。女の子に囲まれてるの連れ出してくれたからだって。ああいうのどうせ嬉しいんだろとか男子からは言われがちなんですけど、先輩は言わないじゃないですか」
「迷惑だと思ってんなら話しかけるなって一言言えよ。……とは思ってるよ」
「それが言えないんです。俺は場の空気を読む方だから。なので先輩が俺にいつも『行くぞ』って言ってくれるの嬉しいんです」
ふわっと柔らかい表情になる高森から俺は目をそらす。
何だか背中のあたりがむずむずする。
気のせいだろうけど。
「先輩、もしかして嬉しいんですか?」
「そんなわけないだろ。少しは静かにしてろよ」
顔を覗きこんでくる高森を追い払う。
いったいいつまでこんなことを続ける気なんだろう。
(……まあそのうち諦めるか)
「先輩。先輩って男ですよね」
部活中、校舎の外を走っていたら隣にいた高森が話しかけてくる。
週に何回かある体力づくりのためのトレーニングが行われる日のことだった。
俺は何を言い出すんだと思いながらも、一応答える。
「高森には俺が女子に見えてんのか?」
「いえ。ちゃんと男に見えてますけど、なんかこう、俺と同じ男なのにむさ苦しさみたいなのがまったくないなあと思って。好きだからこう思うんですかね」
俺はどう反応すればいいのか迷って逃げることにした。
俺もお前と同じ男だよ、と言うのすら面倒だった。
「俺先行くからな」
「待ってください! 先輩最近俺のこと適当に扱いすぎじゃないですか? 前は『大丈夫か?しんどくないか?ゆっくりでいいからな』とか気遣ってくれたのに!」
「知るか!」
無視して先に音楽室に戻る。
真面目に指導してきた後輩が突然変なことを言いだし始めたこっちの身にもなってほしい。
今までの高森は本当にいい後輩だった。
何を言ってもすぐ理解してくれるし、肺活量もあって何なら俺より楽器の演奏も上手いくらいで。
それが今はものすごく手の掛かる後輩に変わってしまった。
高森は部活で会う度、俺に好きだの何だのと伝えてくる。
俺はそんなこと言われてもどうすることもできないのに。
「先輩は平気なんですか。こんなこと言う俺が毎日側にいるの」
数日過ぎてから、いつもの練習場所で高森がこちらをうかがうように聞いてきた。
「平気じゃないし迷惑だってわかってるならやめてくれよ」
「今更無理です。黙ってて先輩が俺に振り向いてくれるなら黙ってますけど、そんなわけないでしょ?」
大人な顔をして高森が言う。
「だからこれからも続けます。……先輩もそんなに嫌ってわけじゃなさそうだし」
「どこを見てそう思うんだよ」
「好きです先輩」
高森が微笑む。
放課後の誰もいない廊下は静かで逃げ場もない。
どきどきなんかはしないけど、このまま言葉を浴びせ続けられたらいったいどうなってしまうんだろうと不安になる。
思えば、こんな風に誰かから一途に想われたことなんてなかった。
別れた彼女にも告白は俺からしたし、それまでも片想いしかしたことがない。
それに、俺は高森のことが嫌いってわけではない。
普通こんな風に誰かに対して、まっすぐ好きと言えるものなんだろうか。
少なくとも俺にはできない。
だから素直にすごいと思う。
それを俺に言うのは理解できないけど。
「どこがそんなにいいんだよ俺なんか」
「だから言ったじゃないですか。女の子に囲まれてるの連れ出してくれたからだって。ああいうのどうせ嬉しいんだろとか男子からは言われがちなんですけど、先輩は言わないじゃないですか」
「迷惑だと思ってんなら話しかけるなって一言言えよ。……とは思ってるよ」
「それが言えないんです。俺は場の空気を読む方だから。なので先輩が俺にいつも『行くぞ』って言ってくれるの嬉しいんです」
ふわっと柔らかい表情になる高森から俺は目をそらす。
何だか背中のあたりがむずむずする。
気のせいだろうけど。
「先輩、もしかして嬉しいんですか?」
「そんなわけないだろ。少しは静かにしてろよ」
顔を覗きこんでくる高森を追い払う。
いったいいつまでこんなことを続ける気なんだろう。
(……まあそのうち諦めるか)