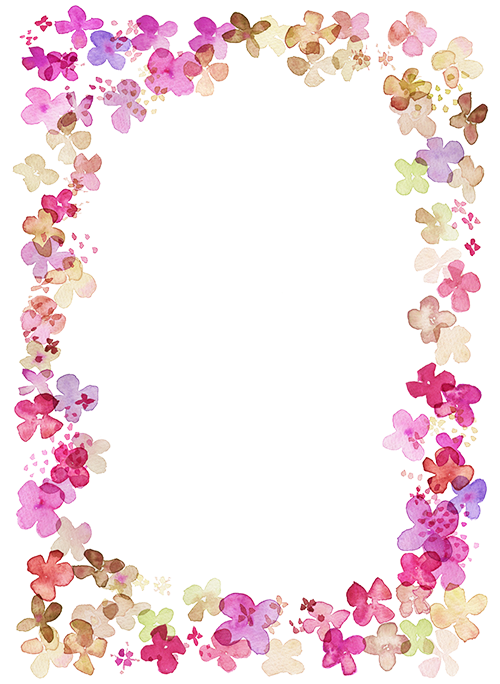白亜のドームに集められた姫君たちの前に、その選定者はちょこんと椅子に座していた。
女官長テラはうやうやしく彼女の側でひざまずいて言う。
「第二の選定者は、皇帝陛下の養女、シーナ様でいらっしゃいます」
十歳になる彼女は、後宮で特殊な地位にあった。ふんわりとした淡い金髪と青い瞳は、砂漠のジャハル帝国においては異質だ。それもそのはずで、彼女は皇帝が遠い盟約国から預かった義理の娘なのだった。
シーナは自分に集中するまなざしに、居心地悪そうに下を向く。
「私が、えらぶ、の……?」
彼女はこの激しい陽射しが照り付けるジャハル帝国では、日中は外に出ることもできない体質だった。それは彼女を内向きな性格にしていて、こういった社交の場に出てくることもまれだった。
皇后アナベルに仕えていたソフィアでも、彼女と実際に会うのは初めてだった。
儚げで、今にも泣きだしてしまいそうなシーナを、姫君たちは扱いづらいものにするように見ていた。
「お会いできて光栄でございます、シーナ様」
「ほんとうに美しい方……」
けれど彼女に気に入られることが皇帝陛下の側に召されることと見て、姫君たちは口々に彼女をほめそやす。
シーナはそんな姫君たちの輪の中で、居心地悪そうに視線をさまよわせていた。大人たちの打算と欲望を感じたというより、ただ戸惑っているように見えた。
そんなシーナを遠目から、ソフィアだけは選ばれる側ではなく選ぶ側として彼女をみつめていた。
まだ幼く、手助けが必要な姫君。長く時を重ね、これから共に未来を探していく。
……それはそれで、素敵な未来ではないか。ソフィアは心に抱いた希望のまま、一歩前に足を踏み出す。
「シーナ様」
ソフィアはそう声をかけて、彼女の前でひざまずく。
「面白いものをお見せします」
「え?」
シーナがその声に、ソフィアの方を振り向いたときだった。
ソフィアは一度勢いをつけると、彼女の前で跳んで一回転して見せたのだった。
女官長テラはうやうやしく彼女の側でひざまずいて言う。
「第二の選定者は、皇帝陛下の養女、シーナ様でいらっしゃいます」
十歳になる彼女は、後宮で特殊な地位にあった。ふんわりとした淡い金髪と青い瞳は、砂漠のジャハル帝国においては異質だ。それもそのはずで、彼女は皇帝が遠い盟約国から預かった義理の娘なのだった。
シーナは自分に集中するまなざしに、居心地悪そうに下を向く。
「私が、えらぶ、の……?」
彼女はこの激しい陽射しが照り付けるジャハル帝国では、日中は外に出ることもできない体質だった。それは彼女を内向きな性格にしていて、こういった社交の場に出てくることもまれだった。
皇后アナベルに仕えていたソフィアでも、彼女と実際に会うのは初めてだった。
儚げで、今にも泣きだしてしまいそうなシーナを、姫君たちは扱いづらいものにするように見ていた。
「お会いできて光栄でございます、シーナ様」
「ほんとうに美しい方……」
けれど彼女に気に入られることが皇帝陛下の側に召されることと見て、姫君たちは口々に彼女をほめそやす。
シーナはそんな姫君たちの輪の中で、居心地悪そうに視線をさまよわせていた。大人たちの打算と欲望を感じたというより、ただ戸惑っているように見えた。
そんなシーナを遠目から、ソフィアだけは選ばれる側ではなく選ぶ側として彼女をみつめていた。
まだ幼く、手助けが必要な姫君。長く時を重ね、これから共に未来を探していく。
……それはそれで、素敵な未来ではないか。ソフィアは心に抱いた希望のまま、一歩前に足を踏み出す。
「シーナ様」
ソフィアはそう声をかけて、彼女の前でひざまずく。
「面白いものをお見せします」
「え?」
シーナがその声に、ソフィアの方を振り向いたときだった。
ソフィアは一度勢いをつけると、彼女の前で跳んで一回転して見せたのだった。