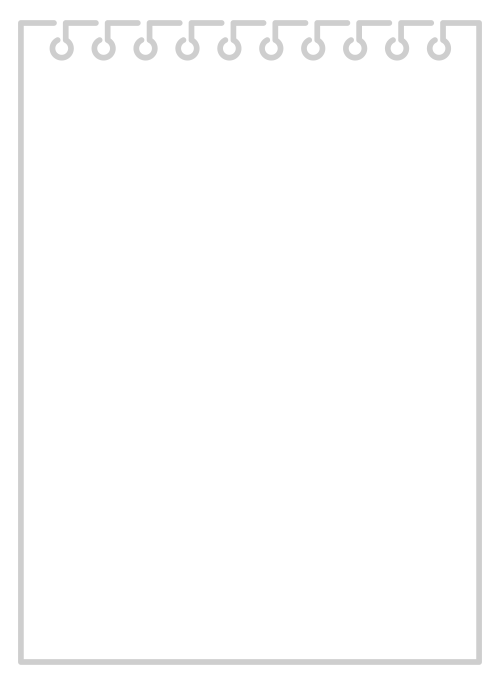折目雅人にはじめて出会ったのは雨が降りしきる梅雨の放課後だ。
俺は親の迎えを待ちながら、誰もいない廊下を歩いていた。四方から雨音が鳴っていて他の音はろくに聞こえず、絶妙な薄暗さは高校の校舎を不気味な空気に変えていた。生徒の姿はまったくなかった。廊下の窓から見下ろした職員室には明かりがついていたけど、雨だし暗いからかカーテンは閉め切られていた。
人がいなくて少し暗いだけで、学校というものは様変わりする。
不穏さは不安だ。雨で軋む古傷が余計に痛いなと思いながら階段そばの美術室近くに差し掛かった。
ここで明るさに目が留まった。つい足を止めて、美術室の扉にあるはめ殺しの窓へと近付いた。すりガラスだから中は見えないけど人影はないようだった。
美術部の消し忘れか。それなら消しておこうかなと、扉に手をかけた。施錠されてるかもと思ったがそんなことはなく、引き戸はがらりと滑らかに開いた。電気は煌々と明るく、美術室の窓の向こうは暗い雨雲に塗りつぶされていた。
電気電気と考えながら中に踏み入った瞬間、死角から蛇みたいなものが伸びてきた。
「どあぇっ!?」
手首に絡まれて変な声が出た。はじめの瞬間はなにかわからず混乱したけど、よく見ると手首に絡んでいたのは誰かの手だった。
その誰かは俺の視線の先で無言のままこっちを見ていた。目が合うと、長めの前髪の隙間から覗く形のいい両目に睨まれた。
「あんた誰?」
普通にこっちの台詞だった。でもイラッとする前に美術室の中を改めて見回したから、招かれざるのは俺だとわかった。
美術室の机は端に寄せられていて、床には新聞紙と和紙が敷かれており、そこには墨汁で書かれた文字が踊っていた。
美術部じゃなく、書道部だった。
「ごめん、部活中だったのか」
すぐに謝り、やんわりと手を離させながら頭を下げる。
「電気ついてたから誰かの消し忘れかと。雨でいろんな部活休みになってるからさ、誰かいると思わなかった」
「……ああ、なるほど」
納得してもらえたので俺もほっとして、
「あれ書いたの君? すごいね、命がけで踊ってるみたいだ」
床の作品を指差しながら聞いた。彼はまばたきもせず俺を見ていて、その顔にはじわじわと驚きが波紋のように広がっていった。
なにかの色が変わったのはこの時だと後々思った。
「なあ、あんた名前は?」
と、さっきよりもちょっとだけ丁寧に聞き返されて、
「三年三組の北辻望」
素直に答えたあの瞬間は、この子が噂の書道部か、としか思っていなかった。
俺の通う南澤高校は特別強い部活のない公立だ。けれど俺が二年の頃の全校集会で、一回だけ部活の功績を称える話を校長がした。
それが書道部。書道の全国コンクールで銀賞か何かをとったらしく、校長はやや興奮気味だったけど賞をとった本人が壇上に上がることはなかった。
でも名前だけは発表された。
一年生の折目雅人。
全校生徒のまばらな拍手を折目がどんな気持ちで聞いていたのか。雨の放課後以降の俺は、なぜか聞けそうな立場になった。
あれから折目は、暇なら美術室に来てくれと俺に言ってくる。
断る理由は別になかった。部活も入っていないし、暇だし、放課後は帰る前に美術室へと立ち寄るルーチンを作って、一人で何かしら書いている折目に声をかけるようになった。
俺が行くと笑って迎え入れてくれる。受験がつらいとか数学の担当教師が計算間違いしたとか今日は雨降ってないなとか、ひとしきり世間話をした後に、折目は和紙の上に文字を書く。
どんな文字も折目が書くと躍動した。
その動きを見ているのが楽しくて、俺が美術室に通う頻度はすぐ増えた。書く文字以外が何もわからない折目雅人についてもっと知りたくなっていた。
夏休み前、蒸し暑い中で美術室を訪問した時に、そういえばなぜ美術室でやっているのか、美術部や他の書道部はいないのかと聞いてみた。
折目は硯を擦る手を止めて、
「美術部は全員名前だけの帰宅部、書道部はおれ一人」
と言ってから、
「顧問が同じだし書道室はないから、おれが美術室使ってる」
そう付け加えて、こっちに横目を向けながら硯を置いた。
「先輩は帰宅部でしたっけ」
「あー、まあ今は」
「前は何か入ってた?」
「うん。バスケ部だったけど、膝やっちゃった」
握り拳で自分の膝頭をとんとん叩く。バスケに未練はあまりないし、負傷ももう落ち着いてはいるけど、雨の日は多少軋んで具合いが悪くなる。歩けないほどではなくても、歩くたびにじりじり痛む。
俺の説明を聞いた折目は、和紙へと目を落とし何かを考えていた。
「だから雨の日、迎えに来てもらってたのか……」
と呟いてから、黒い筆に指を添えて持ち上げた。
俺は折目の隣に座って、邪魔だろうしと口を閉じた。そのあと、和紙に向かう横顔へと視線を向けた。顔は目鼻立ちがくっきりしていて、イケメンというよりは男前、が近い。背は俺より折目の方が高いし、声もちょうどよく低い。ついでに書道での賞持ちと全体的に秀でているから、わりとモテるんじゃないかなと思う。
でもそれを、折目はどうでもいいと考えているみたいだった。
息を吸って、吐いて、また吸ってから筆を持ち直した折目は、一気に集中を深めて鬼気迫る。顔つきも、まとう雰囲気も、変わる。これだけで俺は折目の才能というものを勝手に感じ取って背筋が震える。表彰されたことのある、明らかに突出した才能。
息をつき、折目ではなく筆に目をやる。和紙の上に落とされた底のない黒が、狭いフロアで踊る様子を無心で見る。暑さがその時は遠のく。汗は落ちていて外も中も蒸し暑いけれどそんなことは関係なくなっている。
最後の線だけはそっと穿たれた。名残りを持って和紙から離れた筆が音もなく筆置きの上に戻される。
「今日は何書いたの」
「あんたです」
折目は目を細めて笑い、俺は和紙の上で踊る、一つの文字を改めて注視する。
望。
小学生の習字で書きそうな、俺の名前。
「北辻先輩は名前もきれいだ」
なんてことを、普通の顔に戻りながら言う。俺はちょっと焦ってしまう。
「名前も、ってなんだよ? 他にきれいなとこあんの?」
「あるよ」
「え、マジであるの」
「うん、おれにはわかる」
イマジナリーな話だろうか。俺がわからずに困っていると、折目は声を上げて笑ってから、文鎮を外して和紙を摘んだ。
望の一文字は乾かすために横へと退けられ、
「先輩、晴れてるし一緒に帰ろう」
折目ははじめて、下校の約束を口にした。
それからはほぼ毎日一緒に帰るようにもなった。
すぐに夏休みに入ったし二学期になったらたち消える約束かなとも思ったけど、交換したメッセージツールに夏休みの部活動日について連絡が来た。
受験のための塾がない日は美術室に行った。暑い校内に生徒の姿はぜんぜんなかったけど、美術室のひとつ上にある音楽室からは吹奏楽部の練習する音がほんのりと響いていた。
美術部はやっぱりいない。一人きりの書道部は、半袖シャツの制服姿で筆を持っている。
折目は夏休みだろうが相変わらず書いていて、俺は横でずっと見ている。
「北辻先輩は、書道パフォーマンスってやつ、知ってるか?」
大きめの和紙に何かの歌詞を書いたあと、不意に折目が聞いてきた。
「いや知らないな……なにそれ?」
「めちゃくちゃ簡単に言うと、でかい筆を持ったりして数人で文字を書くパフォーマンス」
「へえ? 面白そうだなー」
「観てる分には、面白いんじゃないですか」
含みのある言い方だ。何も書かずに文鎮を撫でている折目を見つつ、スマホで書道パフォーマンスとやらを探してみる。
すぐにヒットした。一番上に表示されている動画を開くと、和装した十人ほどの高校生が現れた。教室の半分はありそうな巨大な和紙が敷かれていて、厳かながら激しさのある曲が流れ出す。
和装の高校生は曲に合わせて踊り始めた。
「踊ってる」
つい口に出した俺の目の前で、高校生の一人が両手で大きな筆を持ち、和紙になにかの文字を書いていく。その動きもリズムに乗っており流暢だ。和紙の周りでは他の高校生がキレのある踊りを続けている。
いつの間にか見入っていた。隣にいる折目も俺のスマホを覗き込んでいて、頭同士が軽く当たった。
「伊豆の踊子」
折目が呟いて、俺は何のことだと思ったが、高校生たちが仕上がった作品を全員で持ち上げたところで気が付いた。和紙には伊豆の踊子の冒頭や、踊子を模した絵が描かれてある。はじめに大きな筆で書かれた一文字は旅だ。
なんというか、圧巻だった。バスケをやめてからぼんやりと高校生を続けていた俺には、眩しくて仕方ないパフォーマンスだ。
「こんなんあるんだね、すごい」
「北辻先輩は好きだろうなと思ってた」
「あはは、俺パフォーマンスとかダンスとか、そういうの好きそうに見える?」
「うん。はじめて会ったとき、おれの書道を踊ってるみたいって言ったから」
「だってそれは、本当にそう見えたんだよ」
雨の日に見た折目の文字を思い出す。紙の上から立ち上がり、美術室の中を踊り出しそうな勢いに満ちたあの書道。
「折目、俺はさ」
「うん」
「バスケもできないし受験勉強くらいしかやることなくて、でも、あのとき見た折目の作品は、ちゃんと自由なんだけど生きるために踊ってる、って雰囲気でハッとして……ヤバい、うまく言えないんだけどとにかく、俺にはめちゃくちゃ刺さったんだよ。膝の痛さを忘れるくらいには……」
これ以上言葉が思い付かなくて隣を見た。折目の顔が、すぐ近くにあった。フラットな雰囲気のある表情がゆっくりと揺らいでいった。折目って驚いたり喜んだりするときちょっとずつ浸透していく感じだよなとか、呑気に思いながらその変化を見つめていた。
俺は間抜けだ。波みたいに広がっていった、折目が全身に馴染ませたなにかの感情は、スマホを構える俺の手が握られた時に伝播した。
あ、折目って俺のこと好きなのか。
そう気付かされた直後に、視界の中にふっと影が降りた。思わずスマホを机に落とす。唇に触れた柔らかさと震えが何なのかなんて考えるまでもなかった。
キスされていた。脳が弾けたのか、くらっとした。
硬直して身動きできない間に触れ合いは終わった。顔と唇が離れていく時に声をかけようとしたけれど、真上の音楽室から吹奏楽の大きな演奏が響いてきて押し潰された。
課題曲らしき合奏を呆けたまましばらく聴いた。その間に折目は俺の落としたスマホを持ち、無言で手渡して来る。こっちも無言で受け取った。スマホの画面は書道パフォーマンスの動画が開きっぱなしになっていた。
「明日、雨降るみたいですよ」
折目は何事もなかったようにそう言って、筆を洗ってくると立ち上がった。
吹奏楽の演奏が途切れる。俺はスマホの動画を閉じたあと、折目が立てる洗浄音を聞きつつ自分の口元を掌で覆った。
ぜんぜん嫌じゃなかったことに動揺し過ぎて、次の日から美術室に行けなくなった。
二学期は、塾の量を増やせばすぐにやってきた。クラスメイトの話題はそれなりに受験生めいてきて、九月末にはさっそく実力テストが行われた。俺の成績は伸びていた。クラスの友達にすごいじゃんと褒められて、たまたまだよなんて返しながら俺は、受験じゃなくて美術室のことばかり考えていた。
二年生と三年生は階が違うため、会おうとしなければほぼ顔を合わせない。移動教室の時にすれ違う可能性はなくもなかったけど、九月中に折目の姿は見なかった。
名前を聞く機会は十月に入ってから訪れた。
全校集会が開かれて、長い校長の話が終わったあとに、書道コンクールで優秀賞をとった生徒がいると発表された。
その時点で俺は全身がぶわりと粟立った。
『二年一組、折目雅人』
名前を耳にした瞬間は思わず俯いた。折目が壇上に上がるかもと思ったからでもあったけど、それよりも俺は、申し訳なかった。
そう、申し訳ないんだ。俺は膝を壊す前だって大したバスケ選手じゃなかったし、成績が上がったとはいえ手放しで頭脳明晰なわけじゃない。絵や音楽みたいな芸術方面の技術やセンスがあったりももちろんしない。普通だ。普通の高校三年生。
賞をとれるような才能を持つ折目に好かれるわけがないのに好かれてしまったことが申し訳ない。
『折目くん、壇上に──え、休み? そうですか……』
校長が歯切れ悪く言葉を途切れさせ、生徒に拍手だけを促した。ここにはいない受賞者に向けての拍手がぱらぱらと鳴り始める。
その後に校内行事の説明があって、十月末の文化祭の話になれば生徒たちがかすかに浮足立って、いくつかの私語が聞こえた。毎年どのクラスの出し物も凝っているし、すでに準備を始めている生徒もいる。俺も去年は楽しかった。
今年はわからない。全校集会終了の声を聞いて立ち上がりながら、今日は休みらしい折目が自由に書いている姿を思い返していた。
文化祭の日は、あいつのことばかり考えている間に来た。
中庭では模擬店をやるクラスが和気あいあいと盛り上がっていて、体育館では吹奏楽部や演劇部が次々に日頃の成果を発表していた。別の高校から遊びに来た人の姿もいくつか見た。保護者らしき年齢の人もいる。
満喫しなきゃ損だとばかりにあちこちが賑わっているのに、俺はすこしも楽しめる気がしなかった。
でもそんな俺に、文化祭はちゃんと切っ掛けをくれた。
立ち並ぶ模擬店から離れ、友達に校舎内をぶらついてくると声をかけた。一人でいたい気分だったからそのまま誰も伴わず、クラスごとの出し物の方へと足を運んだ。
人の数は思っていたより多かった。肝だめしや喫茶店、リアル脱出ゲームなど、いろんなブースが軒を連ねている。写真や絵の展示をやっているクラスもあるみたいだ。俺のクラスはそっちの方向性で、段ボールで作ったオブジェを並べて撮影スポットに仕上げている。
喧騒を聞きつつ、一人で廊下をゆったり歩いた。その途中で明るい声を上げながら客引きをする女子生徒にチラシを渡された。ぼーっとしていたので反射で受け取ってしまった。クイズ大会(景品あり!)という文字に目を落としてから、二年一組と書かれていることに気が付いた。
折目のクラス、と思った時には足を止めていたが、あいつはこういうの積極的に参加しないよな、と続けて思ってなんとなく笑ってしまった。
「景品って?」
客引きをしていた女子生徒に聞いてみた。彼女は満面の笑みでこう言った。
「色々あるんですけど、おすすめは書道界の超新星、折目雅人くん渾身の一枚です! 目の前で書いてくれますよー!」
俺は考える前に足を教室の方に向けていた。
クイズはわりあい簡単だった。日本の世界遺産を三つ答えよとか、第八十四代総理大臣の名前はとか、黄金比の図を出されてこれはなんの形でしょうなど、高校生の知識でカバーできる範囲だった。
最終問題の、「道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃……の続きと作品名は?」だけは面食らったが、その困惑はわからないから湧いたものじゃなかった。
俺は解答じゃなくて世間話だと言ってから、クイズの司会者をやっていた男子生徒に聞いた。
「その最終問題って、折目が出した?」
「えっ」
司会者はおろおろしたけど、近くにいた客引きの女子生徒が何かしらを耳打ちすると、俺の方に向き直った。
「正解したら、教えます!」
「ほんとに?」
「本当です!」
「わかった」
俺は息をついて、二年一組の中を見渡した。見物客がちらほらいる。隣にはもう一つクイズ台があって、眼鏡をかけた男子生徒が出されたパネルの数学問題を解いている。ざっと見渡すが折目の姿はない。でも俺がいるってわかっていると思う。
だから司会者と視線を合わせながら一気に答えた。
「雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。──伊豆の踊子、ついでに川端康成」
一瞬の間があってから、正解! の声と拍手が響いた。俺は入っていた肩の力を抜いて、客引き生徒のおすすめ賞品を指定した。
司会者は俺に両手で握手しながら、生の書道会場は美術室だと笑顔で言った。
書道パフォーマンス券と書かれた紙を手渡され、二年一組を後にする。クイズを出した人間について聞き忘れたなと思った時には美術室についていた。周りに教室がないからなのか、人の姿はほぼ見当たらない。
本人に聞くかと、美術室の扉に指をかけた。少しだけ躊躇ったけど、逃げるばかりじゃダメだよなと、自分の膝に視線を落として考えた。俺にバスケの才能みたいなものはなかった。怪我をしようがバスケが好きなら続けていただろう。そうしなかった時点で、結局は逃げだ。
なんていうか俺は、こんな俺のままではいたくない。申し訳ないとか言って都合よく逃げるのは、やめたい。
美術室の扉を一気に開け放つ。現れた窓の向こうの青空はすがすがしく秋で、非の打ち所がなく晴れている。
その晴れやかさの前に立っている折目は、腕組みをしながら俺をまっすぐに見つめていた。
「正解おめでとう、北辻先輩」
そうフラットな声で言ってから、
「おれが出した問題ですよ」
とスマホを翳して笑ったので、俺は緊張が少し和らいだ。
「やっぱりそうか……」
「うん。おれはここで賞品として待機してるけど、クイズに回答者が来たら、クラスのやつから連絡が来るんだ。学年と名前つきで」
「三年生の北辻望、って来た?」
「書道パフォーマンスに興味ありそう、ってコメントもあった」
客引きの生徒だろう。俺が書道パフォーマンスに反応したのは明確だった。でもそこまで共有されていると恥ずかしい。
普段よりも早い鼓動を落ち着けつつ、美術室の扉を閉める。床に敷かれている和紙は教室の机くらいの大きさだ。その隣には普段より太い筆がしずかに置かれている。
「何書く? 何でも書くよ」
折目が筆を持ちながら聞いてきた。
「好きな曲の歌詞でもいい、好きな格言やら四字熟語があるならそれでもいい、おまかせってのも、一応受け付けてる。書いた字は賞品だから、そのまま持ち帰ってくれればいい」
「……今まで何人来た?」
「あんたで三人目です。物好きだよな、みんな」
「そんなこと、ないよ。折目の字をもらえるのうれしいだろ」
ゆっくり目を丸くしていく折目に一歩近付いて、
「望。俺の名前、もう一回書いて」
意志が変わらないうちに頼むと、浸透していた驚きが一瞬で不敵な笑顔に変わった。
「いいよ、そこで見てて」
自信を孕んだ低い声にぞくりとする。書道の時の折目は、本当に自由に見える。太い筆先に墨を含ませて俺にはわからない微調整をしたあとに、和紙へと滑らせるまでの動作が踊るように滑らかだ。
亡、月、王。三つの漢字でできた俺の名前。由来なんて知らないけれど、折目も多分、今はそこを考えていない。
俺にはわかる。前に書いてくれた時よりも、文字が俺の方に寄っている。
ダンスフロアというよりは、バスケコートの中を舞っている。細かくドリブルしながらボールを回し、フェイクの動きで相手を撹乱する。
まるで踊っているように。
ぐっと喉の奥が詰まる。折目の腕、身体全体の動きを見つめながら、俺はこいつが好きだと腑に落ちる。
書道の才能だけじゃなくて、折目の持つフラットな空気とか少しずつ感情を染み込ませるところとか表彰されても放置して休んでしまうところとか、書いている時の気迫とか集中力とか自由な筆捌きとか、少しずつ知って積み上がっていった細かな部分も、ぜんぶ好きだ。だからこそキスされて困惑した。釣り合っていない気がした。
逃げたくなった。でも逃げ続ける方が、折目に対して失礼なんだ。
自覚した感情に立ち眩みつつ、一歩だけ足を踏み出した。
その途端に折目が、和紙からは目を離さないまま口を開いた。
「北辻先輩がきれいなのはさ、ちゃんとしてるからだ」
「え……?」
唐突な言葉にうろたえた。その間に折目は、ふっと息をついてからまた話す。
「あんたはおれの字見て、素直にすごいって言えるから。踊ってるみたいだって、自分の心に響いたって、おれ本人にまっすぐ伝えられるから。はじめて会った時だって、電気消し忘れなら消しとこうってさ、ちょっとしたことだけど、やらないやつもたくさんいると思う。だから、そういうところがきれいだ」
墨が最後の線を強く穿つ。シュートを決めたような鮮やかさの余韻が、そっと離れた筆の先に乗っている。
「おれはおれのためにばっか書いてたけど、これはあんたのためにしか書いてない」
顔を上げた折目は俺と目を合わせるなり苦笑する。
「前、急にキスして、すみません。おれ先輩が好きです。ずっと一人で書くつもりだったけど、今は先輩にいてほしい。多分、ほぼ一目ぼれだ。……色々言ったけど、先輩は、元々持ってる雰囲気みたいなもんが、きれいなんだと思う。それが、好きです」
目を合わせたまま、俺は数秒何も言えなかった。改まった告白に左胸が激しく踊り、にわかに緊張して呼吸が浅くなってくる。
はやく何か言わなきゃと口を開いたけど、何かが出て来たのは口じゃなくて両目だった。
ぼろぼろと涙をこぼし始めた俺を見て折目は焦ったらしく、じわじわと慌てながら俺のそばにやってきた。肩を撫でようとした手は墨で汚れていたからか途中で止まる。
「困らせて、すみません」
再び謝る折目に向けて首を振った。
「俺も、折目が好きだ……」
震える涙声だったけどちゃんと言って、俺の告白が浸透し切る前に折目の肩に顔を押し付けた。
折目は困って、驚いて、最後に心底ほっとしたような笑い声を漏らした。
「汚れるけど抱き締めたい、です」
一応のようにつけられた丁寧語に笑いを返し、俺の方から折目の体に腕を回した。折目は一旦躊躇ったあとに抱き返して来て、書道パフォーマンス引き受けてよかった、と嬉しさの沁みた声で呟いた。
秋の空と折目の書いた俺の文字に見られながら、俺たちは文化祭をそっちのけでしばらく抱き合っていた。
俺は親の迎えを待ちながら、誰もいない廊下を歩いていた。四方から雨音が鳴っていて他の音はろくに聞こえず、絶妙な薄暗さは高校の校舎を不気味な空気に変えていた。生徒の姿はまったくなかった。廊下の窓から見下ろした職員室には明かりがついていたけど、雨だし暗いからかカーテンは閉め切られていた。
人がいなくて少し暗いだけで、学校というものは様変わりする。
不穏さは不安だ。雨で軋む古傷が余計に痛いなと思いながら階段そばの美術室近くに差し掛かった。
ここで明るさに目が留まった。つい足を止めて、美術室の扉にあるはめ殺しの窓へと近付いた。すりガラスだから中は見えないけど人影はないようだった。
美術部の消し忘れか。それなら消しておこうかなと、扉に手をかけた。施錠されてるかもと思ったがそんなことはなく、引き戸はがらりと滑らかに開いた。電気は煌々と明るく、美術室の窓の向こうは暗い雨雲に塗りつぶされていた。
電気電気と考えながら中に踏み入った瞬間、死角から蛇みたいなものが伸びてきた。
「どあぇっ!?」
手首に絡まれて変な声が出た。はじめの瞬間はなにかわからず混乱したけど、よく見ると手首に絡んでいたのは誰かの手だった。
その誰かは俺の視線の先で無言のままこっちを見ていた。目が合うと、長めの前髪の隙間から覗く形のいい両目に睨まれた。
「あんた誰?」
普通にこっちの台詞だった。でもイラッとする前に美術室の中を改めて見回したから、招かれざるのは俺だとわかった。
美術室の机は端に寄せられていて、床には新聞紙と和紙が敷かれており、そこには墨汁で書かれた文字が踊っていた。
美術部じゃなく、書道部だった。
「ごめん、部活中だったのか」
すぐに謝り、やんわりと手を離させながら頭を下げる。
「電気ついてたから誰かの消し忘れかと。雨でいろんな部活休みになってるからさ、誰かいると思わなかった」
「……ああ、なるほど」
納得してもらえたので俺もほっとして、
「あれ書いたの君? すごいね、命がけで踊ってるみたいだ」
床の作品を指差しながら聞いた。彼はまばたきもせず俺を見ていて、その顔にはじわじわと驚きが波紋のように広がっていった。
なにかの色が変わったのはこの時だと後々思った。
「なあ、あんた名前は?」
と、さっきよりもちょっとだけ丁寧に聞き返されて、
「三年三組の北辻望」
素直に答えたあの瞬間は、この子が噂の書道部か、としか思っていなかった。
俺の通う南澤高校は特別強い部活のない公立だ。けれど俺が二年の頃の全校集会で、一回だけ部活の功績を称える話を校長がした。
それが書道部。書道の全国コンクールで銀賞か何かをとったらしく、校長はやや興奮気味だったけど賞をとった本人が壇上に上がることはなかった。
でも名前だけは発表された。
一年生の折目雅人。
全校生徒のまばらな拍手を折目がどんな気持ちで聞いていたのか。雨の放課後以降の俺は、なぜか聞けそうな立場になった。
あれから折目は、暇なら美術室に来てくれと俺に言ってくる。
断る理由は別になかった。部活も入っていないし、暇だし、放課後は帰る前に美術室へと立ち寄るルーチンを作って、一人で何かしら書いている折目に声をかけるようになった。
俺が行くと笑って迎え入れてくれる。受験がつらいとか数学の担当教師が計算間違いしたとか今日は雨降ってないなとか、ひとしきり世間話をした後に、折目は和紙の上に文字を書く。
どんな文字も折目が書くと躍動した。
その動きを見ているのが楽しくて、俺が美術室に通う頻度はすぐ増えた。書く文字以外が何もわからない折目雅人についてもっと知りたくなっていた。
夏休み前、蒸し暑い中で美術室を訪問した時に、そういえばなぜ美術室でやっているのか、美術部や他の書道部はいないのかと聞いてみた。
折目は硯を擦る手を止めて、
「美術部は全員名前だけの帰宅部、書道部はおれ一人」
と言ってから、
「顧問が同じだし書道室はないから、おれが美術室使ってる」
そう付け加えて、こっちに横目を向けながら硯を置いた。
「先輩は帰宅部でしたっけ」
「あー、まあ今は」
「前は何か入ってた?」
「うん。バスケ部だったけど、膝やっちゃった」
握り拳で自分の膝頭をとんとん叩く。バスケに未練はあまりないし、負傷ももう落ち着いてはいるけど、雨の日は多少軋んで具合いが悪くなる。歩けないほどではなくても、歩くたびにじりじり痛む。
俺の説明を聞いた折目は、和紙へと目を落とし何かを考えていた。
「だから雨の日、迎えに来てもらってたのか……」
と呟いてから、黒い筆に指を添えて持ち上げた。
俺は折目の隣に座って、邪魔だろうしと口を閉じた。そのあと、和紙に向かう横顔へと視線を向けた。顔は目鼻立ちがくっきりしていて、イケメンというよりは男前、が近い。背は俺より折目の方が高いし、声もちょうどよく低い。ついでに書道での賞持ちと全体的に秀でているから、わりとモテるんじゃないかなと思う。
でもそれを、折目はどうでもいいと考えているみたいだった。
息を吸って、吐いて、また吸ってから筆を持ち直した折目は、一気に集中を深めて鬼気迫る。顔つきも、まとう雰囲気も、変わる。これだけで俺は折目の才能というものを勝手に感じ取って背筋が震える。表彰されたことのある、明らかに突出した才能。
息をつき、折目ではなく筆に目をやる。和紙の上に落とされた底のない黒が、狭いフロアで踊る様子を無心で見る。暑さがその時は遠のく。汗は落ちていて外も中も蒸し暑いけれどそんなことは関係なくなっている。
最後の線だけはそっと穿たれた。名残りを持って和紙から離れた筆が音もなく筆置きの上に戻される。
「今日は何書いたの」
「あんたです」
折目は目を細めて笑い、俺は和紙の上で踊る、一つの文字を改めて注視する。
望。
小学生の習字で書きそうな、俺の名前。
「北辻先輩は名前もきれいだ」
なんてことを、普通の顔に戻りながら言う。俺はちょっと焦ってしまう。
「名前も、ってなんだよ? 他にきれいなとこあんの?」
「あるよ」
「え、マジであるの」
「うん、おれにはわかる」
イマジナリーな話だろうか。俺がわからずに困っていると、折目は声を上げて笑ってから、文鎮を外して和紙を摘んだ。
望の一文字は乾かすために横へと退けられ、
「先輩、晴れてるし一緒に帰ろう」
折目ははじめて、下校の約束を口にした。
それからはほぼ毎日一緒に帰るようにもなった。
すぐに夏休みに入ったし二学期になったらたち消える約束かなとも思ったけど、交換したメッセージツールに夏休みの部活動日について連絡が来た。
受験のための塾がない日は美術室に行った。暑い校内に生徒の姿はぜんぜんなかったけど、美術室のひとつ上にある音楽室からは吹奏楽部の練習する音がほんのりと響いていた。
美術部はやっぱりいない。一人きりの書道部は、半袖シャツの制服姿で筆を持っている。
折目は夏休みだろうが相変わらず書いていて、俺は横でずっと見ている。
「北辻先輩は、書道パフォーマンスってやつ、知ってるか?」
大きめの和紙に何かの歌詞を書いたあと、不意に折目が聞いてきた。
「いや知らないな……なにそれ?」
「めちゃくちゃ簡単に言うと、でかい筆を持ったりして数人で文字を書くパフォーマンス」
「へえ? 面白そうだなー」
「観てる分には、面白いんじゃないですか」
含みのある言い方だ。何も書かずに文鎮を撫でている折目を見つつ、スマホで書道パフォーマンスとやらを探してみる。
すぐにヒットした。一番上に表示されている動画を開くと、和装した十人ほどの高校生が現れた。教室の半分はありそうな巨大な和紙が敷かれていて、厳かながら激しさのある曲が流れ出す。
和装の高校生は曲に合わせて踊り始めた。
「踊ってる」
つい口に出した俺の目の前で、高校生の一人が両手で大きな筆を持ち、和紙になにかの文字を書いていく。その動きもリズムに乗っており流暢だ。和紙の周りでは他の高校生がキレのある踊りを続けている。
いつの間にか見入っていた。隣にいる折目も俺のスマホを覗き込んでいて、頭同士が軽く当たった。
「伊豆の踊子」
折目が呟いて、俺は何のことだと思ったが、高校生たちが仕上がった作品を全員で持ち上げたところで気が付いた。和紙には伊豆の踊子の冒頭や、踊子を模した絵が描かれてある。はじめに大きな筆で書かれた一文字は旅だ。
なんというか、圧巻だった。バスケをやめてからぼんやりと高校生を続けていた俺には、眩しくて仕方ないパフォーマンスだ。
「こんなんあるんだね、すごい」
「北辻先輩は好きだろうなと思ってた」
「あはは、俺パフォーマンスとかダンスとか、そういうの好きそうに見える?」
「うん。はじめて会ったとき、おれの書道を踊ってるみたいって言ったから」
「だってそれは、本当にそう見えたんだよ」
雨の日に見た折目の文字を思い出す。紙の上から立ち上がり、美術室の中を踊り出しそうな勢いに満ちたあの書道。
「折目、俺はさ」
「うん」
「バスケもできないし受験勉強くらいしかやることなくて、でも、あのとき見た折目の作品は、ちゃんと自由なんだけど生きるために踊ってる、って雰囲気でハッとして……ヤバい、うまく言えないんだけどとにかく、俺にはめちゃくちゃ刺さったんだよ。膝の痛さを忘れるくらいには……」
これ以上言葉が思い付かなくて隣を見た。折目の顔が、すぐ近くにあった。フラットな雰囲気のある表情がゆっくりと揺らいでいった。折目って驚いたり喜んだりするときちょっとずつ浸透していく感じだよなとか、呑気に思いながらその変化を見つめていた。
俺は間抜けだ。波みたいに広がっていった、折目が全身に馴染ませたなにかの感情は、スマホを構える俺の手が握られた時に伝播した。
あ、折目って俺のこと好きなのか。
そう気付かされた直後に、視界の中にふっと影が降りた。思わずスマホを机に落とす。唇に触れた柔らかさと震えが何なのかなんて考えるまでもなかった。
キスされていた。脳が弾けたのか、くらっとした。
硬直して身動きできない間に触れ合いは終わった。顔と唇が離れていく時に声をかけようとしたけれど、真上の音楽室から吹奏楽の大きな演奏が響いてきて押し潰された。
課題曲らしき合奏を呆けたまましばらく聴いた。その間に折目は俺の落としたスマホを持ち、無言で手渡して来る。こっちも無言で受け取った。スマホの画面は書道パフォーマンスの動画が開きっぱなしになっていた。
「明日、雨降るみたいですよ」
折目は何事もなかったようにそう言って、筆を洗ってくると立ち上がった。
吹奏楽の演奏が途切れる。俺はスマホの動画を閉じたあと、折目が立てる洗浄音を聞きつつ自分の口元を掌で覆った。
ぜんぜん嫌じゃなかったことに動揺し過ぎて、次の日から美術室に行けなくなった。
二学期は、塾の量を増やせばすぐにやってきた。クラスメイトの話題はそれなりに受験生めいてきて、九月末にはさっそく実力テストが行われた。俺の成績は伸びていた。クラスの友達にすごいじゃんと褒められて、たまたまだよなんて返しながら俺は、受験じゃなくて美術室のことばかり考えていた。
二年生と三年生は階が違うため、会おうとしなければほぼ顔を合わせない。移動教室の時にすれ違う可能性はなくもなかったけど、九月中に折目の姿は見なかった。
名前を聞く機会は十月に入ってから訪れた。
全校集会が開かれて、長い校長の話が終わったあとに、書道コンクールで優秀賞をとった生徒がいると発表された。
その時点で俺は全身がぶわりと粟立った。
『二年一組、折目雅人』
名前を耳にした瞬間は思わず俯いた。折目が壇上に上がるかもと思ったからでもあったけど、それよりも俺は、申し訳なかった。
そう、申し訳ないんだ。俺は膝を壊す前だって大したバスケ選手じゃなかったし、成績が上がったとはいえ手放しで頭脳明晰なわけじゃない。絵や音楽みたいな芸術方面の技術やセンスがあったりももちろんしない。普通だ。普通の高校三年生。
賞をとれるような才能を持つ折目に好かれるわけがないのに好かれてしまったことが申し訳ない。
『折目くん、壇上に──え、休み? そうですか……』
校長が歯切れ悪く言葉を途切れさせ、生徒に拍手だけを促した。ここにはいない受賞者に向けての拍手がぱらぱらと鳴り始める。
その後に校内行事の説明があって、十月末の文化祭の話になれば生徒たちがかすかに浮足立って、いくつかの私語が聞こえた。毎年どのクラスの出し物も凝っているし、すでに準備を始めている生徒もいる。俺も去年は楽しかった。
今年はわからない。全校集会終了の声を聞いて立ち上がりながら、今日は休みらしい折目が自由に書いている姿を思い返していた。
文化祭の日は、あいつのことばかり考えている間に来た。
中庭では模擬店をやるクラスが和気あいあいと盛り上がっていて、体育館では吹奏楽部や演劇部が次々に日頃の成果を発表していた。別の高校から遊びに来た人の姿もいくつか見た。保護者らしき年齢の人もいる。
満喫しなきゃ損だとばかりにあちこちが賑わっているのに、俺はすこしも楽しめる気がしなかった。
でもそんな俺に、文化祭はちゃんと切っ掛けをくれた。
立ち並ぶ模擬店から離れ、友達に校舎内をぶらついてくると声をかけた。一人でいたい気分だったからそのまま誰も伴わず、クラスごとの出し物の方へと足を運んだ。
人の数は思っていたより多かった。肝だめしや喫茶店、リアル脱出ゲームなど、いろんなブースが軒を連ねている。写真や絵の展示をやっているクラスもあるみたいだ。俺のクラスはそっちの方向性で、段ボールで作ったオブジェを並べて撮影スポットに仕上げている。
喧騒を聞きつつ、一人で廊下をゆったり歩いた。その途中で明るい声を上げながら客引きをする女子生徒にチラシを渡された。ぼーっとしていたので反射で受け取ってしまった。クイズ大会(景品あり!)という文字に目を落としてから、二年一組と書かれていることに気が付いた。
折目のクラス、と思った時には足を止めていたが、あいつはこういうの積極的に参加しないよな、と続けて思ってなんとなく笑ってしまった。
「景品って?」
客引きをしていた女子生徒に聞いてみた。彼女は満面の笑みでこう言った。
「色々あるんですけど、おすすめは書道界の超新星、折目雅人くん渾身の一枚です! 目の前で書いてくれますよー!」
俺は考える前に足を教室の方に向けていた。
クイズはわりあい簡単だった。日本の世界遺産を三つ答えよとか、第八十四代総理大臣の名前はとか、黄金比の図を出されてこれはなんの形でしょうなど、高校生の知識でカバーできる範囲だった。
最終問題の、「道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃……の続きと作品名は?」だけは面食らったが、その困惑はわからないから湧いたものじゃなかった。
俺は解答じゃなくて世間話だと言ってから、クイズの司会者をやっていた男子生徒に聞いた。
「その最終問題って、折目が出した?」
「えっ」
司会者はおろおろしたけど、近くにいた客引きの女子生徒が何かしらを耳打ちすると、俺の方に向き直った。
「正解したら、教えます!」
「ほんとに?」
「本当です!」
「わかった」
俺は息をついて、二年一組の中を見渡した。見物客がちらほらいる。隣にはもう一つクイズ台があって、眼鏡をかけた男子生徒が出されたパネルの数学問題を解いている。ざっと見渡すが折目の姿はない。でも俺がいるってわかっていると思う。
だから司会者と視線を合わせながら一気に答えた。
「雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。──伊豆の踊子、ついでに川端康成」
一瞬の間があってから、正解! の声と拍手が響いた。俺は入っていた肩の力を抜いて、客引き生徒のおすすめ賞品を指定した。
司会者は俺に両手で握手しながら、生の書道会場は美術室だと笑顔で言った。
書道パフォーマンス券と書かれた紙を手渡され、二年一組を後にする。クイズを出した人間について聞き忘れたなと思った時には美術室についていた。周りに教室がないからなのか、人の姿はほぼ見当たらない。
本人に聞くかと、美術室の扉に指をかけた。少しだけ躊躇ったけど、逃げるばかりじゃダメだよなと、自分の膝に視線を落として考えた。俺にバスケの才能みたいなものはなかった。怪我をしようがバスケが好きなら続けていただろう。そうしなかった時点で、結局は逃げだ。
なんていうか俺は、こんな俺のままではいたくない。申し訳ないとか言って都合よく逃げるのは、やめたい。
美術室の扉を一気に開け放つ。現れた窓の向こうの青空はすがすがしく秋で、非の打ち所がなく晴れている。
その晴れやかさの前に立っている折目は、腕組みをしながら俺をまっすぐに見つめていた。
「正解おめでとう、北辻先輩」
そうフラットな声で言ってから、
「おれが出した問題ですよ」
とスマホを翳して笑ったので、俺は緊張が少し和らいだ。
「やっぱりそうか……」
「うん。おれはここで賞品として待機してるけど、クイズに回答者が来たら、クラスのやつから連絡が来るんだ。学年と名前つきで」
「三年生の北辻望、って来た?」
「書道パフォーマンスに興味ありそう、ってコメントもあった」
客引きの生徒だろう。俺が書道パフォーマンスに反応したのは明確だった。でもそこまで共有されていると恥ずかしい。
普段よりも早い鼓動を落ち着けつつ、美術室の扉を閉める。床に敷かれている和紙は教室の机くらいの大きさだ。その隣には普段より太い筆がしずかに置かれている。
「何書く? 何でも書くよ」
折目が筆を持ちながら聞いてきた。
「好きな曲の歌詞でもいい、好きな格言やら四字熟語があるならそれでもいい、おまかせってのも、一応受け付けてる。書いた字は賞品だから、そのまま持ち帰ってくれればいい」
「……今まで何人来た?」
「あんたで三人目です。物好きだよな、みんな」
「そんなこと、ないよ。折目の字をもらえるのうれしいだろ」
ゆっくり目を丸くしていく折目に一歩近付いて、
「望。俺の名前、もう一回書いて」
意志が変わらないうちに頼むと、浸透していた驚きが一瞬で不敵な笑顔に変わった。
「いいよ、そこで見てて」
自信を孕んだ低い声にぞくりとする。書道の時の折目は、本当に自由に見える。太い筆先に墨を含ませて俺にはわからない微調整をしたあとに、和紙へと滑らせるまでの動作が踊るように滑らかだ。
亡、月、王。三つの漢字でできた俺の名前。由来なんて知らないけれど、折目も多分、今はそこを考えていない。
俺にはわかる。前に書いてくれた時よりも、文字が俺の方に寄っている。
ダンスフロアというよりは、バスケコートの中を舞っている。細かくドリブルしながらボールを回し、フェイクの動きで相手を撹乱する。
まるで踊っているように。
ぐっと喉の奥が詰まる。折目の腕、身体全体の動きを見つめながら、俺はこいつが好きだと腑に落ちる。
書道の才能だけじゃなくて、折目の持つフラットな空気とか少しずつ感情を染み込ませるところとか表彰されても放置して休んでしまうところとか、書いている時の気迫とか集中力とか自由な筆捌きとか、少しずつ知って積み上がっていった細かな部分も、ぜんぶ好きだ。だからこそキスされて困惑した。釣り合っていない気がした。
逃げたくなった。でも逃げ続ける方が、折目に対して失礼なんだ。
自覚した感情に立ち眩みつつ、一歩だけ足を踏み出した。
その途端に折目が、和紙からは目を離さないまま口を開いた。
「北辻先輩がきれいなのはさ、ちゃんとしてるからだ」
「え……?」
唐突な言葉にうろたえた。その間に折目は、ふっと息をついてからまた話す。
「あんたはおれの字見て、素直にすごいって言えるから。踊ってるみたいだって、自分の心に響いたって、おれ本人にまっすぐ伝えられるから。はじめて会った時だって、電気消し忘れなら消しとこうってさ、ちょっとしたことだけど、やらないやつもたくさんいると思う。だから、そういうところがきれいだ」
墨が最後の線を強く穿つ。シュートを決めたような鮮やかさの余韻が、そっと離れた筆の先に乗っている。
「おれはおれのためにばっか書いてたけど、これはあんたのためにしか書いてない」
顔を上げた折目は俺と目を合わせるなり苦笑する。
「前、急にキスして、すみません。おれ先輩が好きです。ずっと一人で書くつもりだったけど、今は先輩にいてほしい。多分、ほぼ一目ぼれだ。……色々言ったけど、先輩は、元々持ってる雰囲気みたいなもんが、きれいなんだと思う。それが、好きです」
目を合わせたまま、俺は数秒何も言えなかった。改まった告白に左胸が激しく踊り、にわかに緊張して呼吸が浅くなってくる。
はやく何か言わなきゃと口を開いたけど、何かが出て来たのは口じゃなくて両目だった。
ぼろぼろと涙をこぼし始めた俺を見て折目は焦ったらしく、じわじわと慌てながら俺のそばにやってきた。肩を撫でようとした手は墨で汚れていたからか途中で止まる。
「困らせて、すみません」
再び謝る折目に向けて首を振った。
「俺も、折目が好きだ……」
震える涙声だったけどちゃんと言って、俺の告白が浸透し切る前に折目の肩に顔を押し付けた。
折目は困って、驚いて、最後に心底ほっとしたような笑い声を漏らした。
「汚れるけど抱き締めたい、です」
一応のようにつけられた丁寧語に笑いを返し、俺の方から折目の体に腕を回した。折目は一旦躊躇ったあとに抱き返して来て、書道パフォーマンス引き受けてよかった、と嬉しさの沁みた声で呟いた。
秋の空と折目の書いた俺の文字に見られながら、俺たちは文化祭をそっちのけでしばらく抱き合っていた。