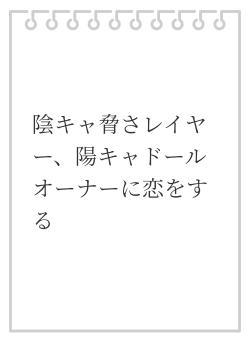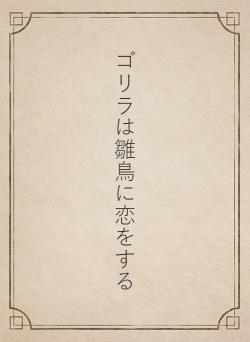「お前がレイヤーだということばらされたくなけりゃ、俺の願い聞いてくれない?」
「え……?」
コスプレ仲間が出来たと思った。
しかも、クラス一軍の男。
だが、それは大きな勘違いだった。
昨日撮られた動画を見せられ、全身から血の気が引いていくのを感じる。
夏だというのに、金井の心は氷点下まで冷え込んだ。
※
室内外共に快適に過ごせる初夏、金井陽(かねいはる)はこの季節が大好きだ。
緑豊かな公園で、シャッター音が響く。感嘆の声が聞こえてくる。現実離れした色とりどりの造形が金井の視覚を刺激した。
皆、思い思いの非日常を楽しんでいた。
何度見ても飽きない、心踊る場所。
コスプレイベント。
「写真、ありがとうございます」
金井がスマホを片手にお辞儀をすると、今流行りのアニメ作品のコスプレをした女性が「こちらこそ」とニコリと笑い、踵を返した。
撮った写真を確認しようとスマホの画面を見ると、黒い和装に刀を構え、カメラ目線の女性がこちらを睨み付けている。
あぁ、カッコいい。メイクはキャラそのものだし、衣装に取り付けられているパーツの造形が美しい。手作りだろうか? オーダーメイドだろうか?
色々考えながら、画面をうっとり眺めていると、金井に声がかかった。
「あの、それ、ミハルちゃんのコスプレだよね? 撮らせてもらってもいいですか?」
振り向くと、バズーカ砲みたいなゴツいレンズがついたカメラを構えた男がいた。
ミハルちゃんとは、日曜日の朝に放送されている魔法少女アニメに出てくるキャラクターの女の子だ。強くてカッコよく、今最も金井が推しているキャラクターだ。
パニエで膨らましたミニ丈スカートに、背中がハート型に大胆に空いたフリルたっぷりのトップス。メインカラーは黒でキリッとしまっており、ミハルちゃんの凛々しさが更に際立つデザインだ。
「いいですよ」
にこやかに返事をすると、男は「うっ」と短く唸った。
「男かよ。あー……ゴメンナサイ」
男はぼそりと呟くと、逃げるように、そばにいたミニスカのメリハリあるボディの女性レイヤーに声をかけた。
コスプレイベントではよくあることだ。
男性だと思ったら女性だった。女性だと思ったら男性だったということが。
金井はがっかりしながらも、自分のコスプレが女性に見えてしまうほど、クオリティが高かったということにしておこうと思った。
ここでなら、普段の弱気な自分とはさよなら出来て、強くなれる。積極的になれる気がする。
そんなワクワク感が大きく、バイトにもやりがいがあるってものだ。
自分は強いミハルちゃんなんだ。
金井は拳を握りしめて、カメコの拒絶の言葉を強い気持ちで拒絶した。
まるで金井の気持ちを肯定するかのように、柔らかな風が、衣装のスカートとふわりと揺らした。
「え……?」
コスプレ仲間が出来たと思った。
しかも、クラス一軍の男。
だが、それは大きな勘違いだった。
昨日撮られた動画を見せられ、全身から血の気が引いていくのを感じる。
夏だというのに、金井の心は氷点下まで冷え込んだ。
※
室内外共に快適に過ごせる初夏、金井陽(かねいはる)はこの季節が大好きだ。
緑豊かな公園で、シャッター音が響く。感嘆の声が聞こえてくる。現実離れした色とりどりの造形が金井の視覚を刺激した。
皆、思い思いの非日常を楽しんでいた。
何度見ても飽きない、心踊る場所。
コスプレイベント。
「写真、ありがとうございます」
金井がスマホを片手にお辞儀をすると、今流行りのアニメ作品のコスプレをした女性が「こちらこそ」とニコリと笑い、踵を返した。
撮った写真を確認しようとスマホの画面を見ると、黒い和装に刀を構え、カメラ目線の女性がこちらを睨み付けている。
あぁ、カッコいい。メイクはキャラそのものだし、衣装に取り付けられているパーツの造形が美しい。手作りだろうか? オーダーメイドだろうか?
色々考えながら、画面をうっとり眺めていると、金井に声がかかった。
「あの、それ、ミハルちゃんのコスプレだよね? 撮らせてもらってもいいですか?」
振り向くと、バズーカ砲みたいなゴツいレンズがついたカメラを構えた男がいた。
ミハルちゃんとは、日曜日の朝に放送されている魔法少女アニメに出てくるキャラクターの女の子だ。強くてカッコよく、今最も金井が推しているキャラクターだ。
パニエで膨らましたミニ丈スカートに、背中がハート型に大胆に空いたフリルたっぷりのトップス。メインカラーは黒でキリッとしまっており、ミハルちゃんの凛々しさが更に際立つデザインだ。
「いいですよ」
にこやかに返事をすると、男は「うっ」と短く唸った。
「男かよ。あー……ゴメンナサイ」
男はぼそりと呟くと、逃げるように、そばにいたミニスカのメリハリあるボディの女性レイヤーに声をかけた。
コスプレイベントではよくあることだ。
男性だと思ったら女性だった。女性だと思ったら男性だったということが。
金井はがっかりしながらも、自分のコスプレが女性に見えてしまうほど、クオリティが高かったということにしておこうと思った。
ここでなら、普段の弱気な自分とはさよなら出来て、強くなれる。積極的になれる気がする。
そんなワクワク感が大きく、バイトにもやりがいがあるってものだ。
自分は強いミハルちゃんなんだ。
金井は拳を握りしめて、カメコの拒絶の言葉を強い気持ちで拒絶した。
まるで金井の気持ちを肯定するかのように、柔らかな風が、衣装のスカートとふわりと揺らした。