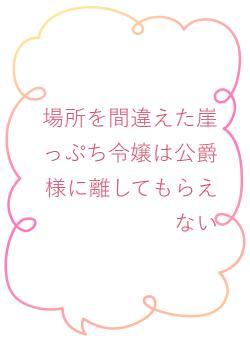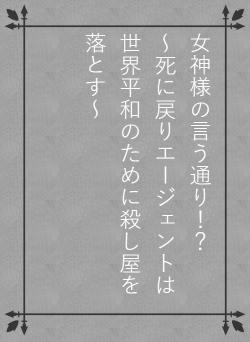第6話
ボォォォ、という笛の音。
それを合図に、広間に集まった面々が森の中へと消えていく。
ドラゴン討伐は早い者勝ちである。先陣を切って先に進む者もあれば、シュリたちのようにあとから追う形で向かう者もいる。あとから向かえば、先に行った者が道を作ってくれるだろうという、一見安易な考えにも見えるが、パーティーの特性を生かす、というのは戦闘においてとても重要だ。
「本当に行かないんですね」
先発者たちを尻目に、トビーが呟いた。
広場にはまだ数組のグループが残っている。皆、一様に動かない。
「言っただろ? これはちゃんとした作戦だ。俺たちは後から行く。状況把握が出来るまでは無暗に突っ走らない!」
「状況把握……?」
リリーナが首を傾げる。
「それとオッサン、今テイムしてる魔獣は何体だ?」
数日間のダンジョン潜入で、一体も増やしてないということはないはずだ。
「……俺の手持ちは八体だ」
「えええっ?」
「いつのまに、そんなっ」
トビーとリリーナが声を荒げた。
たったの数日だ。その間に六体もテイムしてきていると知り、ただただ驚く。
「使えそうなのは?」
「森の中なら三、ドラゴン相手ってことなら……微妙だな」
難しい顔で、答える。
「わかった。とにかく俺たちは最前線まで辿り着くことが目標だ。命の危険を感じたらすぐに退去する」
「でもっ、」
「それじゃ賞金が!」
食い下がる双子に、シュリが真面目な顔で言う。
「前にも言ったが、ドラゴン退治ってのはそう簡単じゃねぇ。今でこそこうしてパーティーごとに動いてるが、最終的には皆が協力し合って、束になってかからねぇと倒せないんじゃないかと思ってる」
「え?」
「そう……なの?」
「ああ。だから俺たちは、あとから行く。なるべく決戦の時まで体力を温存しておかないとな」
先に出ればそれだけ体力を消耗する。若い双子にそこまでのスタミナはない。それに……と、シュリはアシルを見遣る。
(アシルのリベンジも、俺のリベンジも果たさなきゃだしな)
心の中でだけ、そう口にする。
「お前……何が目的なんだ?」
アシルが真剣な顔でシュリを見た。
「目的? もちろん、ドラゴンの討伐さ」
シュリはパチリと片目を瞑ってみせた。
*****
森の中は鬱蒼としていた。
曇っていた空からは雨粒が落ち始め、足元も悪い。コンディションは最悪だ。
あちこちに、獣の死骸が散乱し、異臭が漂っている。
「だいぶ派手にやってんな」
森には討伐隊の姿はない。ずっと先へ進んでいるのだろう。あとから森へ入った他のパーティーの人間が焦りの声を上げているのが聞こえる。
「おい、このままじゃ先に行った奴らに取られちまうぜ?」
「やべぇな。楽して先に進むつもりが、獲物が残ってないなんてことになったら、」
「賞金、どうすんだよっ」
そんなことを言いながら足早に進んでいった。
「……どうなっているんだ?」
アシルが辺りを見ながらシュリに訊ねる。
「……これが単純なドラゴン討伐じゃないってのはオッサンにもわかってんだろ?」
質問を、質問で返す。
「……普通じゃないってことはな」
「気を引き締めていかねぇとだ」
「俺が知りたいのは、お前が何者で、何をどこまで知っているかだ」
アシルがシュリをじっと見つめた。
「照れるからそれ以上見つめるな」
シュリが真顔で返す。
遅れて出たとはいえ、第一陣から半刻ほどだ。しかし森の中からは木々が揺れる音しか聞こえない。先頭が一体どれほど先に進んでいるのか、見当もつかなかった。
「少し急ごう」
シュリが森の奥を見ながら、言った。
アシルは先を行くシュリの姿を見ながら考えていた。
確かに吟遊詩人というスキルを持つ者がいるのは知っている。だがそれはとても曖昧で、戦力になるようなスキルではなかったように記憶している。実際自分が今まで出会った中に吟遊詩人というスキルの者はいなかった。
パーティーを追い出されたと言っていた。あのブライ率いる一団は、界隈でも有名な強者集団だ。メイス片手に大柄な魔獣をも仕留めるブライ。剣を操るアルジムという剣士は、確か近衛師団からスカウトされるほどの腕前だと聞いた。魔法使いのユーフィ。名のある魔法使いの一番弟子ではなかったか?
そんなメンバーと肩を並べていたにもかかわらず、シュリの名を耳にしたことはない。普通は一団が手柄を上げれば個人の名声も聞こえてきそうなものだが、彼にまつわる話はひとつだけ。
『口で食ってる口男』
吟遊詩人の特性でもある『言葉』を使っているからなのだろう。だが、名声というよりは馬鹿にしたような言い方ではないか? 何故彼だけがそんな言われ方をするのだろう。
(単に嫌われているということか?)
多少イラつくこともあるが、面倒見もいいし、そこまで嫌われる要素があるとも思えないのだが……。
「女……か?」
思わず口にしてしまう。
大概、揉めるのはイロコイだ。あの魔法使いに手を出して追い出されたのだろうか。
(まぁ、どうでもいいか)
今は目の前のことに集中すべきだ。
アシルはあの時のことを思い出し、唇を噛み締める。
――つい、数カ月前だ。
アシルが所属していたのは、拠点こそアルゴンにあるが、頼まれればどこにでも出向く、いわば国境を越えた退治屋のような組織。各国で活動する、戦闘に特化したギルドである。近衛師団でも歯が立たなかったというドラゴンを討伐せよという命を国から秘密裏に受け、しかし自信満々に向かったのだ。
目の前に現れた、赤いドラゴン。
アシルは伝説とも言われたテイマーである。自身にも、仲間たちにも当然、勝算があった。余裕で何とかなると思っていたのだ。
しかし……
結果は惨敗。アシルたち一行は大怪我を負いながらも、かろうじてその場から逃げることが出来た。が、アシルのテイムしていた魔獣たちは、皆、その命を絶たれた。ドラゴンの力が段違いだったのだ。
アシルは大切な魔獣たちをすべて失った。仲間たちも大怪我を負い、仕事を続けられなくなっていた。
ギルドは解散……いや、霧散に近いだろう。組織ごと、その存在を潰された形である。
皆、絶望に駆られ、散り散りになったのだ。
そんな折、一般向けにドラゴン討伐の張り紙がなされたことを知り驚いた。無茶苦茶だと思った。転移魔法が使えるほど上級の魔導士がごろつきの中にいるとは思えない。ということは、自力で向かい、自力で戻らなければならないのだ。大怪我を負えば、ポーションでは間に合わないかもしれない相手を前に、ただ数で勝負するなど無謀にもほどがある。
そう思っていたのに、何故かドラゴン討伐の申し込みに足を向けていた。
組む相手もいないのにどうする気だったのか、自分でもわからない。ただ、偶然とはいえ仲間が出来た。しかもまだ年端もゆかぬ子供もいる。
守らねばならないと思った。
そして謎多き吟遊詩人……。
なぜ極秘任務であったあの討伐のことを知っているのか? 一体、何者なのか……。
その時、森の奥で、ドン! という大きな音が響いた。
ボォォォ、という笛の音。
それを合図に、広間に集まった面々が森の中へと消えていく。
ドラゴン討伐は早い者勝ちである。先陣を切って先に進む者もあれば、シュリたちのようにあとから追う形で向かう者もいる。あとから向かえば、先に行った者が道を作ってくれるだろうという、一見安易な考えにも見えるが、パーティーの特性を生かす、というのは戦闘においてとても重要だ。
「本当に行かないんですね」
先発者たちを尻目に、トビーが呟いた。
広場にはまだ数組のグループが残っている。皆、一様に動かない。
「言っただろ? これはちゃんとした作戦だ。俺たちは後から行く。状況把握が出来るまでは無暗に突っ走らない!」
「状況把握……?」
リリーナが首を傾げる。
「それとオッサン、今テイムしてる魔獣は何体だ?」
数日間のダンジョン潜入で、一体も増やしてないということはないはずだ。
「……俺の手持ちは八体だ」
「えええっ?」
「いつのまに、そんなっ」
トビーとリリーナが声を荒げた。
たったの数日だ。その間に六体もテイムしてきていると知り、ただただ驚く。
「使えそうなのは?」
「森の中なら三、ドラゴン相手ってことなら……微妙だな」
難しい顔で、答える。
「わかった。とにかく俺たちは最前線まで辿り着くことが目標だ。命の危険を感じたらすぐに退去する」
「でもっ、」
「それじゃ賞金が!」
食い下がる双子に、シュリが真面目な顔で言う。
「前にも言ったが、ドラゴン退治ってのはそう簡単じゃねぇ。今でこそこうしてパーティーごとに動いてるが、最終的には皆が協力し合って、束になってかからねぇと倒せないんじゃないかと思ってる」
「え?」
「そう……なの?」
「ああ。だから俺たちは、あとから行く。なるべく決戦の時まで体力を温存しておかないとな」
先に出ればそれだけ体力を消耗する。若い双子にそこまでのスタミナはない。それに……と、シュリはアシルを見遣る。
(アシルのリベンジも、俺のリベンジも果たさなきゃだしな)
心の中でだけ、そう口にする。
「お前……何が目的なんだ?」
アシルが真剣な顔でシュリを見た。
「目的? もちろん、ドラゴンの討伐さ」
シュリはパチリと片目を瞑ってみせた。
*****
森の中は鬱蒼としていた。
曇っていた空からは雨粒が落ち始め、足元も悪い。コンディションは最悪だ。
あちこちに、獣の死骸が散乱し、異臭が漂っている。
「だいぶ派手にやってんな」
森には討伐隊の姿はない。ずっと先へ進んでいるのだろう。あとから森へ入った他のパーティーの人間が焦りの声を上げているのが聞こえる。
「おい、このままじゃ先に行った奴らに取られちまうぜ?」
「やべぇな。楽して先に進むつもりが、獲物が残ってないなんてことになったら、」
「賞金、どうすんだよっ」
そんなことを言いながら足早に進んでいった。
「……どうなっているんだ?」
アシルが辺りを見ながらシュリに訊ねる。
「……これが単純なドラゴン討伐じゃないってのはオッサンにもわかってんだろ?」
質問を、質問で返す。
「……普通じゃないってことはな」
「気を引き締めていかねぇとだ」
「俺が知りたいのは、お前が何者で、何をどこまで知っているかだ」
アシルがシュリをじっと見つめた。
「照れるからそれ以上見つめるな」
シュリが真顔で返す。
遅れて出たとはいえ、第一陣から半刻ほどだ。しかし森の中からは木々が揺れる音しか聞こえない。先頭が一体どれほど先に進んでいるのか、見当もつかなかった。
「少し急ごう」
シュリが森の奥を見ながら、言った。
アシルは先を行くシュリの姿を見ながら考えていた。
確かに吟遊詩人というスキルを持つ者がいるのは知っている。だがそれはとても曖昧で、戦力になるようなスキルではなかったように記憶している。実際自分が今まで出会った中に吟遊詩人というスキルの者はいなかった。
パーティーを追い出されたと言っていた。あのブライ率いる一団は、界隈でも有名な強者集団だ。メイス片手に大柄な魔獣をも仕留めるブライ。剣を操るアルジムという剣士は、確か近衛師団からスカウトされるほどの腕前だと聞いた。魔法使いのユーフィ。名のある魔法使いの一番弟子ではなかったか?
そんなメンバーと肩を並べていたにもかかわらず、シュリの名を耳にしたことはない。普通は一団が手柄を上げれば個人の名声も聞こえてきそうなものだが、彼にまつわる話はひとつだけ。
『口で食ってる口男』
吟遊詩人の特性でもある『言葉』を使っているからなのだろう。だが、名声というよりは馬鹿にしたような言い方ではないか? 何故彼だけがそんな言われ方をするのだろう。
(単に嫌われているということか?)
多少イラつくこともあるが、面倒見もいいし、そこまで嫌われる要素があるとも思えないのだが……。
「女……か?」
思わず口にしてしまう。
大概、揉めるのはイロコイだ。あの魔法使いに手を出して追い出されたのだろうか。
(まぁ、どうでもいいか)
今は目の前のことに集中すべきだ。
アシルはあの時のことを思い出し、唇を噛み締める。
――つい、数カ月前だ。
アシルが所属していたのは、拠点こそアルゴンにあるが、頼まれればどこにでも出向く、いわば国境を越えた退治屋のような組織。各国で活動する、戦闘に特化したギルドである。近衛師団でも歯が立たなかったというドラゴンを討伐せよという命を国から秘密裏に受け、しかし自信満々に向かったのだ。
目の前に現れた、赤いドラゴン。
アシルは伝説とも言われたテイマーである。自身にも、仲間たちにも当然、勝算があった。余裕で何とかなると思っていたのだ。
しかし……
結果は惨敗。アシルたち一行は大怪我を負いながらも、かろうじてその場から逃げることが出来た。が、アシルのテイムしていた魔獣たちは、皆、その命を絶たれた。ドラゴンの力が段違いだったのだ。
アシルは大切な魔獣たちをすべて失った。仲間たちも大怪我を負い、仕事を続けられなくなっていた。
ギルドは解散……いや、霧散に近いだろう。組織ごと、その存在を潰された形である。
皆、絶望に駆られ、散り散りになったのだ。
そんな折、一般向けにドラゴン討伐の張り紙がなされたことを知り驚いた。無茶苦茶だと思った。転移魔法が使えるほど上級の魔導士がごろつきの中にいるとは思えない。ということは、自力で向かい、自力で戻らなければならないのだ。大怪我を負えば、ポーションでは間に合わないかもしれない相手を前に、ただ数で勝負するなど無謀にもほどがある。
そう思っていたのに、何故かドラゴン討伐の申し込みに足を向けていた。
組む相手もいないのにどうする気だったのか、自分でもわからない。ただ、偶然とはいえ仲間が出来た。しかもまだ年端もゆかぬ子供もいる。
守らねばならないと思った。
そして謎多き吟遊詩人……。
なぜ極秘任務であったあの討伐のことを知っているのか? 一体、何者なのか……。
その時、森の奥で、ドン! という大きな音が響いた。