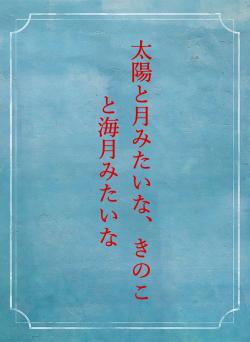5.
──人の記憶って不思議なものだよね。
プレイルームのソファに横並びで座りながら俊明さんはそんなふうに話し始めた。途中で看護師がもうお見舞いの方はお帰りになる時間ですがと告げにきたが、俊明さんはこの人は大丈夫です、と返した。
──そう、記憶だ。
奏くん、君は自分の最も古い記憶を思い出そうとするとそれは何になる? そのときの感情は思い出せるかな? それとも逆にいままでいちばん嬉しかったこと、悲しかったこと、そこから思い出すことはできるかな。
俊明さんは開けたまま、まだ一口もつけていなかった缶コーヒーをようやく口に含んだ。
──これを見てごらん。
俊明さんは僕に一枚の茶封筒を渡した。なかにはびっしりと書かれたカルテや、白黒のMRI写真や波形グラフが書かれた書類が入っていた。
──結論からいうと今回の検査では美月の脳のどの部位の所見にも異常は見られなかった。脳梗塞もなければ、脳出血も見られない綺麗な脳だよ。まして脳腫瘍もなかったし、若年性アルツハイマーで見られるような脳全体の萎縮もなかった。その他専門家として考えられる脳の異常を一つずつチェックしていったが、なにも異常はなかった。そう、何もなかったんだ。
僕は俊明さんの話に口を挟むこともできず、黙って缶コーヒーを口元に運んだ。
味はまるで感じなかった。いや、もしかすると、緊張で脳のどこかの働きが鈍っているのかもしれない。こんなふうに味覚が消えていく感覚も、脳のせいなのだろうか。
僕は俊明さんの話を聞きながら、どこか他人事のように感じる自分を見つけていた。
──ただし異常が見つからなかったというのはMRIなどの画像診断をはじめとする器質的な面においてという意味だ。
そこにはMRI画像だけでなく、美月の脳波図も含まれているね。MRIは脳の器質的な状態、つまり脳そのものをを観察するためのものだが、脳波図は神経活動の生理的な状態、つまり脳の活動を反映するものだ。
美月の脳波は、特にシータ波とガンマ波の活動が一般的な人とは明らかに異なっている。
通常、シータ波はリラックスや浅い睡眠時に多く観測されるが、美月の場合、覚醒時にもシータ波が強く出現し、一方で集中時や高度な認知活動の際に生じやすいといわれているガンマ波がどういうわけか睡眠中にその活動が異常なレベルで高まっている傾向が見られるんだ。
俊明さんは噛んで含めるように説明を要約してくれた。
──つまり通常であれば観測されるはずのない脳の活動が観測されているということさ。それも一番活動が落ち着くはずの睡眠中にこそ美月の脳は最も活発な活動を示している。
俊明さんが指し示した美月の脳波図はまるで五線譜のうえを流れていくメロディのようだった。
──美月の脳ではなにか異常なことが現象として起こっているのは間違いない。
間違いないが、しかしそれを示すMRI所見が脳内にまるで見つからないんだ。並行して脳以外の全身も念の為くまなく調べてもらったが、やはり器質的な異常は一切見られない。
僕はこのとき美月の検査入院が長期に亘っていることに思い至った。美月は血液検査なんかもされている言っていたことを僕は思い出した。
俊明さんは続ける。
──脳波の異常は従来の波形そのものだけではない。脳波は通常の人間では、おおよそ五種類に分類されるが、美月の脳波図からは通常観測されない世界的にも数例しか報告されていない非常に特殊な波形を観測した。いわば第六の波形だ。
まるで五線譜に紛れ込んだ調和を乱すような一つの不協和音。
──それはどんな波形なんですか?
俊明さんはこちらを見つめた。
それからさっきまでのトーンと声の響きを少し変化させて言った。
──専門的なことは省くよ。いいかい? これから話すことはいささかショッキングなことだ。美月を大切な存在として思ってくれている君にとっても、父親であるわたしにとっても、そしてなによりも本人にとっても。
さきほども言ったとおり、このいわば第六の波形は非常に稀な現象でまだ世界でも数例しか報告がない。
それゆえデータも有効といえるほどのものでもないし、それがゆえに内科的な治療法もなければ、MRIで確認できるような脳の異常所見もないゆえに外科的な治療法もない。はっきりいえばなにもわかってないということなんだ。
だから今から話すことに過度に悲観的にならないでほしい、いいね。
俊明さんの長い話はどうやらようやく一つの結論に辿り着いたらしい。
──この脳波形の存在については医療の世界でははっきりしたことはなにもわかっていない。
ただね、この第六の脳波形が観測された報告例では、そのすべての患者が一年ほどで亡くなっているんだ。
──人の記憶って不思議なものだよね。
プレイルームのソファに横並びで座りながら俊明さんはそんなふうに話し始めた。途中で看護師がもうお見舞いの方はお帰りになる時間ですがと告げにきたが、俊明さんはこの人は大丈夫です、と返した。
──そう、記憶だ。
奏くん、君は自分の最も古い記憶を思い出そうとするとそれは何になる? そのときの感情は思い出せるかな? それとも逆にいままでいちばん嬉しかったこと、悲しかったこと、そこから思い出すことはできるかな。
俊明さんは開けたまま、まだ一口もつけていなかった缶コーヒーをようやく口に含んだ。
──これを見てごらん。
俊明さんは僕に一枚の茶封筒を渡した。なかにはびっしりと書かれたカルテや、白黒のMRI写真や波形グラフが書かれた書類が入っていた。
──結論からいうと今回の検査では美月の脳のどの部位の所見にも異常は見られなかった。脳梗塞もなければ、脳出血も見られない綺麗な脳だよ。まして脳腫瘍もなかったし、若年性アルツハイマーで見られるような脳全体の萎縮もなかった。その他専門家として考えられる脳の異常を一つずつチェックしていったが、なにも異常はなかった。そう、何もなかったんだ。
僕は俊明さんの話に口を挟むこともできず、黙って缶コーヒーを口元に運んだ。
味はまるで感じなかった。いや、もしかすると、緊張で脳のどこかの働きが鈍っているのかもしれない。こんなふうに味覚が消えていく感覚も、脳のせいなのだろうか。
僕は俊明さんの話を聞きながら、どこか他人事のように感じる自分を見つけていた。
──ただし異常が見つからなかったというのはMRIなどの画像診断をはじめとする器質的な面においてという意味だ。
そこにはMRI画像だけでなく、美月の脳波図も含まれているね。MRIは脳の器質的な状態、つまり脳そのものをを観察するためのものだが、脳波図は神経活動の生理的な状態、つまり脳の活動を反映するものだ。
美月の脳波は、特にシータ波とガンマ波の活動が一般的な人とは明らかに異なっている。
通常、シータ波はリラックスや浅い睡眠時に多く観測されるが、美月の場合、覚醒時にもシータ波が強く出現し、一方で集中時や高度な認知活動の際に生じやすいといわれているガンマ波がどういうわけか睡眠中にその活動が異常なレベルで高まっている傾向が見られるんだ。
俊明さんは噛んで含めるように説明を要約してくれた。
──つまり通常であれば観測されるはずのない脳の活動が観測されているということさ。それも一番活動が落ち着くはずの睡眠中にこそ美月の脳は最も活発な活動を示している。
俊明さんが指し示した美月の脳波図はまるで五線譜のうえを流れていくメロディのようだった。
──美月の脳ではなにか異常なことが現象として起こっているのは間違いない。
間違いないが、しかしそれを示すMRI所見が脳内にまるで見つからないんだ。並行して脳以外の全身も念の為くまなく調べてもらったが、やはり器質的な異常は一切見られない。
僕はこのとき美月の検査入院が長期に亘っていることに思い至った。美月は血液検査なんかもされている言っていたことを僕は思い出した。
俊明さんは続ける。
──脳波の異常は従来の波形そのものだけではない。脳波は通常の人間では、おおよそ五種類に分類されるが、美月の脳波図からは通常観測されない世界的にも数例しか報告されていない非常に特殊な波形を観測した。いわば第六の波形だ。
まるで五線譜に紛れ込んだ調和を乱すような一つの不協和音。
──それはどんな波形なんですか?
俊明さんはこちらを見つめた。
それからさっきまでのトーンと声の響きを少し変化させて言った。
──専門的なことは省くよ。いいかい? これから話すことはいささかショッキングなことだ。美月を大切な存在として思ってくれている君にとっても、父親であるわたしにとっても、そしてなによりも本人にとっても。
さきほども言ったとおり、このいわば第六の波形は非常に稀な現象でまだ世界でも数例しか報告がない。
それゆえデータも有効といえるほどのものでもないし、それがゆえに内科的な治療法もなければ、MRIで確認できるような脳の異常所見もないゆえに外科的な治療法もない。はっきりいえばなにもわかってないということなんだ。
だから今から話すことに過度に悲観的にならないでほしい、いいね。
俊明さんの長い話はどうやらようやく一つの結論に辿り着いたらしい。
──この脳波形の存在については医療の世界でははっきりしたことはなにもわかっていない。
ただね、この第六の脳波形が観測された報告例では、そのすべての患者が一年ほどで亡くなっているんだ。