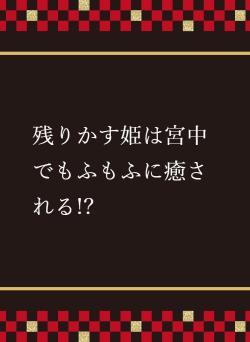振り返ると、そこには見知らぬ男がいた。
長い銀髪を一つに束ね、白い着物みたいなものを纏ったそいつの顔は、男の俺ですら息を呑むほど整っている。
細身だけど、背が高かった。百九十センチを超えてるんじゃないか? そんじょそこらの芸能人が、泣いてひれ伏しそうな見た目だ。
ただ、そのイケメンの頭には、普通の人間にはないものが二つ付いていた。
ふさふさの白い毛に覆われた……狐の、耳?
「これは許されざる所業だよ。覚悟があって、しでかしたことだよね」
イケメンは膝を折り、俺の顎を指でくいっと押し上げた。
俺は目と口を閉じたり開いたりすることしかできなかった。何かこう、動きを封じられているような……。
あ、もしかして、何かの術をかけられてるのか?!
そう気が付いたタイミングで、倉橋伊月の苦しそうな声が割って入ってきた。
「九尾……やめろ。彼には手を出すな」
なんとか目だけを横に向けると、俺のクラスメイトは必死にもがいていた。どす黒い縄のようなものが、小柄な身体にまとわりついている。
突然現れたイケメンの正体は、さっきのデカい狐……九尾とかいう奴らしい。きっと、人間っぽい姿に変身してるんだ。でもって、倉橋伊月も俺と同じく、九尾の術のせいで動けない。
――って、これ、かなりヤバくねぇ?!
「ようやく、自分が置かれている状況を把握したみたいだね」
ゴクリと息を呑んだ俺に、九尾が微笑んだ。優しさからくる笑みじゃない。怒りが透けて見えるような、要するにめちゃくちゃ怖ぇ顔だ。
そんな表情を浮かべたまま、狐の耳を生やしたイケメンは俺の顎から手を離し、傍らに落ちていたグローブに目を留める。
「我らに歯向かった代償は、その身体で受けてもらうよ――朝見幸太郎」
九尾に名前を呼ばれた瞬間、身体じゅうに痛みが走った。まるで、固い鎖でギリギリと締め上げられてるみたいだ。
おまけに、頭まで痛くなってきた。とうとう耐えられなくなって、俺はその場に倒れ込む。
「朝見幸太郎くん!」
倉橋伊月の、悲痛な声が耳に届いた。
そうこうしているうちに、俺は自分の身体の『異変』に気が付いた。
「あ……れ、何か生えてる」
頭の上に、妙な感触がある。伸ばした指先に柔らかいものが触れた。ふわふわの毛に覆われた、三角形の何かが二つ……。
「朝見幸太郎――真名を記しておいてくれたお陰で、簡単に呪いをかけられた。このままでいけば、君はいずれ『狐』になる」
九尾はグローブから目を離し、俺の頭に生えたそれ――狐の耳にそっと触れた。
「俺が、狐に……?」
気付けば苦しさや痛みはすっかり消えていた。だが、突然生えてきた『異質なもの』の存在が、俺に重くのしかかる。
「そうさ。君は人としての理性を失って、ただの獣になるんだ。――楽しみだね」
呆然とする俺の前で、九尾の身体は再び大きな狐の姿に戻った。そのまま屋上のタイルをひと蹴りし、夜空へと舞い上がっていく。
「待て! 彼にかけた呪いを解け、九尾!」
ようやく動けるようになったらしい倉橋伊月が、上空に向かって叫んだ。
しかし、優美な狐の姿はあっという間に遠ざかってしまった。残されているのは、俺の名前がデカデカと書かれたグローブだけ……。
「嘘だろ。何だよこの耳。痛ててっ!」
俺は自分の頭から生えているふわふわの三角形を何度も引っ張った。そのたびに痛みが走り、涙目になる。
痛みがあるってことは、これ、もう俺の身体の一部ってことじゃん。
「何だよこれ、何だよ!」
ぶるぶると頭を振り、再び、躍起になって狐の耳を引っ張る。
「朝見幸太郎くん、やめた方がいい。痛いだけだ」
駆けつけてきた倉橋伊月が、深刻な顔で俺を止めた。俺はもうわけが分からなくなって、小柄な身体に縋り付く。
「なぁ、何だよこの耳。呪いって、どういうことだよ。俺は、一体どうなっちゃうんだよ……うっ!」
泣き事の途中で、猛烈な不快感を覚えた。
尻のあたりが、どうしようもなくむず痒い。
「うわっ、気色悪ィ!」
履いていたいたチノパンが少し盛り上がり、太腿に長くて柔らかいものが触れていた。目で見なくても、感覚で分かる。何てったって、これは俺の身体なんだ。
尾骶骨のあたりから――狐の尻尾がにょきっと生えている。
『君は人としての理性を失って、ただの獣になるんだ』
さっき言われたことが耳の中に蘇った。
狐になるって……理性を失うって、どういうことだ。俺が俺でなくなるってことか?
そんなのは嫌だ。
――怖い。
長い銀髪を一つに束ね、白い着物みたいなものを纏ったそいつの顔は、男の俺ですら息を呑むほど整っている。
細身だけど、背が高かった。百九十センチを超えてるんじゃないか? そんじょそこらの芸能人が、泣いてひれ伏しそうな見た目だ。
ただ、そのイケメンの頭には、普通の人間にはないものが二つ付いていた。
ふさふさの白い毛に覆われた……狐の、耳?
「これは許されざる所業だよ。覚悟があって、しでかしたことだよね」
イケメンは膝を折り、俺の顎を指でくいっと押し上げた。
俺は目と口を閉じたり開いたりすることしかできなかった。何かこう、動きを封じられているような……。
あ、もしかして、何かの術をかけられてるのか?!
そう気が付いたタイミングで、倉橋伊月の苦しそうな声が割って入ってきた。
「九尾……やめろ。彼には手を出すな」
なんとか目だけを横に向けると、俺のクラスメイトは必死にもがいていた。どす黒い縄のようなものが、小柄な身体にまとわりついている。
突然現れたイケメンの正体は、さっきのデカい狐……九尾とかいう奴らしい。きっと、人間っぽい姿に変身してるんだ。でもって、倉橋伊月も俺と同じく、九尾の術のせいで動けない。
――って、これ、かなりヤバくねぇ?!
「ようやく、自分が置かれている状況を把握したみたいだね」
ゴクリと息を呑んだ俺に、九尾が微笑んだ。優しさからくる笑みじゃない。怒りが透けて見えるような、要するにめちゃくちゃ怖ぇ顔だ。
そんな表情を浮かべたまま、狐の耳を生やしたイケメンは俺の顎から手を離し、傍らに落ちていたグローブに目を留める。
「我らに歯向かった代償は、その身体で受けてもらうよ――朝見幸太郎」
九尾に名前を呼ばれた瞬間、身体じゅうに痛みが走った。まるで、固い鎖でギリギリと締め上げられてるみたいだ。
おまけに、頭まで痛くなってきた。とうとう耐えられなくなって、俺はその場に倒れ込む。
「朝見幸太郎くん!」
倉橋伊月の、悲痛な声が耳に届いた。
そうこうしているうちに、俺は自分の身体の『異変』に気が付いた。
「あ……れ、何か生えてる」
頭の上に、妙な感触がある。伸ばした指先に柔らかいものが触れた。ふわふわの毛に覆われた、三角形の何かが二つ……。
「朝見幸太郎――真名を記しておいてくれたお陰で、簡単に呪いをかけられた。このままでいけば、君はいずれ『狐』になる」
九尾はグローブから目を離し、俺の頭に生えたそれ――狐の耳にそっと触れた。
「俺が、狐に……?」
気付けば苦しさや痛みはすっかり消えていた。だが、突然生えてきた『異質なもの』の存在が、俺に重くのしかかる。
「そうさ。君は人としての理性を失って、ただの獣になるんだ。――楽しみだね」
呆然とする俺の前で、九尾の身体は再び大きな狐の姿に戻った。そのまま屋上のタイルをひと蹴りし、夜空へと舞い上がっていく。
「待て! 彼にかけた呪いを解け、九尾!」
ようやく動けるようになったらしい倉橋伊月が、上空に向かって叫んだ。
しかし、優美な狐の姿はあっという間に遠ざかってしまった。残されているのは、俺の名前がデカデカと書かれたグローブだけ……。
「嘘だろ。何だよこの耳。痛ててっ!」
俺は自分の頭から生えているふわふわの三角形を何度も引っ張った。そのたびに痛みが走り、涙目になる。
痛みがあるってことは、これ、もう俺の身体の一部ってことじゃん。
「何だよこれ、何だよ!」
ぶるぶると頭を振り、再び、躍起になって狐の耳を引っ張る。
「朝見幸太郎くん、やめた方がいい。痛いだけだ」
駆けつけてきた倉橋伊月が、深刻な顔で俺を止めた。俺はもうわけが分からなくなって、小柄な身体に縋り付く。
「なぁ、何だよこの耳。呪いって、どういうことだよ。俺は、一体どうなっちゃうんだよ……うっ!」
泣き事の途中で、猛烈な不快感を覚えた。
尻のあたりが、どうしようもなくむず痒い。
「うわっ、気色悪ィ!」
履いていたいたチノパンが少し盛り上がり、太腿に長くて柔らかいものが触れていた。目で見なくても、感覚で分かる。何てったって、これは俺の身体なんだ。
尾骶骨のあたりから――狐の尻尾がにょきっと生えている。
『君は人としての理性を失って、ただの獣になるんだ』
さっき言われたことが耳の中に蘇った。
狐になるって……理性を失うって、どういうことだ。俺が俺でなくなるってことか?
そんなのは嫌だ。
――怖い。