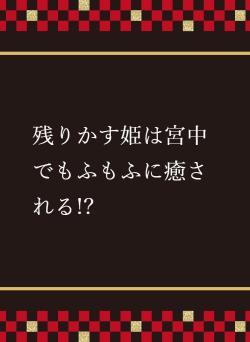漫画とかゲームでしか聞いたことのない単語が飛び出し、俺は目をしばたたかせた。
倉橋伊月は袴の裾をはためかせながら、真顔で告げる。
「人知を超えた力を持つ存在――それがあやかしさ。僕はあやかしたちからこの狸穴一帯を守る、陰陽師だ」
「はあぁぁぁ――っ?
あやかしに陰陽師。
現実離れしすぎて、ただでさえ考えるのが苦手な俺の脳はオーバーヒート気味だった。
こうなったときは、いつも成り行きのまま突っ走ることにしている。『考えるより産むがやすし』とか言うだろ? あれ、ちょっと違うか。
とにかく、やるべきことは一つ――あのグローブを、絶対に取り戻す!
上空にいた狐たちは校庭を突っ切り、メイン校舎へと向かった。四階建ての建物には窓ガラスがずらりと並んでいるが、奴らは二階の一枚をぶち破って中に飛び込む。
倉橋伊月は閉まっている昇降口まで走った。そこで着物の袂から銀色の鍵を取り出し、躊躇いもなく鍵穴に突っ込む。
「どうしてお前が、ここの鍵なんて持ってるんだよ」
追いついた俺はギョッとして、倉橋伊月の手元を指さした。
「僕は『役目』を全うするために、ここのマスターキーを預けられている」
「役目? 何言ってんだか分かんねー。それに、鍵を開けたところで、校内にはセキュリティーが作動してるはずだろ」
このご時世、学び舎も警備システムを利用していると聞く。中に踏み込めば、アラームか何かが鳴り響くはずだ。
だが、倉橋伊月はこともなげに言ってのけた。
「それなら、すでに解除した。僕は然るべき機関から、深夜の校舎への立ち入りを許可されているんだ。だから余計な心配はしなくていいよ、朝見幸太郎くん」
然るべき機関ってどこだよ……そう尋ねる暇もなく、倉橋伊月は校舎の中に駆け込んだ。俺もすぐさま走り出す。
ああ、もう。こうなったら、細かいことはあとだ、あと!
「いた! 上に向かってる」
二人で階段を駆け上がっていると、倉橋伊月が叫んだ。
前方に大小二つの毛玉が見える。小さい方は、まだ俺のグローブを咥えたままだ。
「あいつ、逃がさねぇ!」
俺はスピードを上げて倉橋伊月を追い越した。「危ない」とか「待て」とかいう声が聞こえてくるが、こんなところで止まってたまるか!
校舎は四階建て。二匹の狐どもはよふよと飛びながら最上階に到達した。
階段を上がりきったところにあるのは一枚の扉だ。開ければ屋上へ通じている。
「よっしゃ、追い詰めたぜ」
扉の前で浮いている二匹を前に、俺は拳を握り締めた。
屋上への立ち入りは基本的に禁止だ。だからこの扉は、昼夜問わず頑丈に施錠されている。しかも、分厚い鉄板製。窓みたいに簡単に壊せるはずが……。
「――危ない!」
俺が狐たちに向かって足を踏み出す寸前、倉橋伊月が脇腹に飛びついてきた。その直後、ばたん、とものすごい音が響き渡る。
「う、嘘だろ!」
さっきまで俺が立っていた場所には分厚い鉄扉が横たわり、もうもうと埃を巻き上げていた。壊れて倒れたんだ。倉橋伊月が俺を抱えて横に飛んでなきゃ、今ごろ下敷きに……。
「九尾の術なら、このくらいのことは簡単にできる。だから待てと言ったのに」
俺に怪我がないことを確認したのか、倉橋伊月は腰に回した腕を緩め、渋い顔をして立ち上がった。そのまま、倒れた鉄扉を乗り越えて屋上へ出る。
俺もよろよろとあとを追いかけた。扉があった場所を通り抜けた途端、夜風が身体にまとわりつく。
ここ――都立狸穴高校は、東京都港区にある。
校内は緑が多いものの、やはり都会のど真ん中だ。屋上に立てば、赤く光る東京タワーや六本木ヒルズの存在を、間近に感じることができる。
だが、今は周りの景色なんて目に入らなかった。四角い石のタイルが敷き詰められた屋上の真ん中あたりに、二匹の狐……あやかしが浮かんでいる。
「くっそおぉぉ、俺のグローブ、返せ!」
俺は半ば自棄になって小さい方の狐に突進した。
「あっ、無茶は駄目だよ!」
倉橋伊月の制止の声が、背中に覆い被さる。
無茶なんて承知だっつーの。あやかしとかよく分かんねーし、ぶっちゃけ怖い。だけどな――ここで諦めるわけにはいかねーんだよ!
「返せ。返せよ!」
俺は小さい方の狐に身体ごとぶつかった。捨て身の攻撃を喰らった白い毛玉は遠くに吹っ飛び、屋上の柵を越えて視界から消える。
奴は咥えていたものをその場に落としていった。当て身を喰らわせれば、相手だけじゃなく自分自身にもダメージがくる。痛みを堪えつつ、俺はそれに手を伸ばす。
「……っつ、俺のグローブ」
だが、指先が黄色い革に触れる寸前、背中にすさまじい悪寒が走った。追い打ちをかけるように、後ろから低くて張りのある声が聞こえてくる。
「――ただの人間風情が、あやかしに楯突くとは面白い」
倉橋伊月は袴の裾をはためかせながら、真顔で告げる。
「人知を超えた力を持つ存在――それがあやかしさ。僕はあやかしたちからこの狸穴一帯を守る、陰陽師だ」
「はあぁぁぁ――っ?
あやかしに陰陽師。
現実離れしすぎて、ただでさえ考えるのが苦手な俺の脳はオーバーヒート気味だった。
こうなったときは、いつも成り行きのまま突っ走ることにしている。『考えるより産むがやすし』とか言うだろ? あれ、ちょっと違うか。
とにかく、やるべきことは一つ――あのグローブを、絶対に取り戻す!
上空にいた狐たちは校庭を突っ切り、メイン校舎へと向かった。四階建ての建物には窓ガラスがずらりと並んでいるが、奴らは二階の一枚をぶち破って中に飛び込む。
倉橋伊月は閉まっている昇降口まで走った。そこで着物の袂から銀色の鍵を取り出し、躊躇いもなく鍵穴に突っ込む。
「どうしてお前が、ここの鍵なんて持ってるんだよ」
追いついた俺はギョッとして、倉橋伊月の手元を指さした。
「僕は『役目』を全うするために、ここのマスターキーを預けられている」
「役目? 何言ってんだか分かんねー。それに、鍵を開けたところで、校内にはセキュリティーが作動してるはずだろ」
このご時世、学び舎も警備システムを利用していると聞く。中に踏み込めば、アラームか何かが鳴り響くはずだ。
だが、倉橋伊月はこともなげに言ってのけた。
「それなら、すでに解除した。僕は然るべき機関から、深夜の校舎への立ち入りを許可されているんだ。だから余計な心配はしなくていいよ、朝見幸太郎くん」
然るべき機関ってどこだよ……そう尋ねる暇もなく、倉橋伊月は校舎の中に駆け込んだ。俺もすぐさま走り出す。
ああ、もう。こうなったら、細かいことはあとだ、あと!
「いた! 上に向かってる」
二人で階段を駆け上がっていると、倉橋伊月が叫んだ。
前方に大小二つの毛玉が見える。小さい方は、まだ俺のグローブを咥えたままだ。
「あいつ、逃がさねぇ!」
俺はスピードを上げて倉橋伊月を追い越した。「危ない」とか「待て」とかいう声が聞こえてくるが、こんなところで止まってたまるか!
校舎は四階建て。二匹の狐どもはよふよと飛びながら最上階に到達した。
階段を上がりきったところにあるのは一枚の扉だ。開ければ屋上へ通じている。
「よっしゃ、追い詰めたぜ」
扉の前で浮いている二匹を前に、俺は拳を握り締めた。
屋上への立ち入りは基本的に禁止だ。だからこの扉は、昼夜問わず頑丈に施錠されている。しかも、分厚い鉄板製。窓みたいに簡単に壊せるはずが……。
「――危ない!」
俺が狐たちに向かって足を踏み出す寸前、倉橋伊月が脇腹に飛びついてきた。その直後、ばたん、とものすごい音が響き渡る。
「う、嘘だろ!」
さっきまで俺が立っていた場所には分厚い鉄扉が横たわり、もうもうと埃を巻き上げていた。壊れて倒れたんだ。倉橋伊月が俺を抱えて横に飛んでなきゃ、今ごろ下敷きに……。
「九尾の術なら、このくらいのことは簡単にできる。だから待てと言ったのに」
俺に怪我がないことを確認したのか、倉橋伊月は腰に回した腕を緩め、渋い顔をして立ち上がった。そのまま、倒れた鉄扉を乗り越えて屋上へ出る。
俺もよろよろとあとを追いかけた。扉があった場所を通り抜けた途端、夜風が身体にまとわりつく。
ここ――都立狸穴高校は、東京都港区にある。
校内は緑が多いものの、やはり都会のど真ん中だ。屋上に立てば、赤く光る東京タワーや六本木ヒルズの存在を、間近に感じることができる。
だが、今は周りの景色なんて目に入らなかった。四角い石のタイルが敷き詰められた屋上の真ん中あたりに、二匹の狐……あやかしが浮かんでいる。
「くっそおぉぉ、俺のグローブ、返せ!」
俺は半ば自棄になって小さい方の狐に突進した。
「あっ、無茶は駄目だよ!」
倉橋伊月の制止の声が、背中に覆い被さる。
無茶なんて承知だっつーの。あやかしとかよく分かんねーし、ぶっちゃけ怖い。だけどな――ここで諦めるわけにはいかねーんだよ!
「返せ。返せよ!」
俺は小さい方の狐に身体ごとぶつかった。捨て身の攻撃を喰らった白い毛玉は遠くに吹っ飛び、屋上の柵を越えて視界から消える。
奴は咥えていたものをその場に落としていった。当て身を喰らわせれば、相手だけじゃなく自分自身にもダメージがくる。痛みを堪えつつ、俺はそれに手を伸ばす。
「……っつ、俺のグローブ」
だが、指先が黄色い革に触れる寸前、背中にすさまじい悪寒が走った。追い打ちをかけるように、後ろから低くて張りのある声が聞こえてくる。
「――ただの人間風情が、あやかしに楯突くとは面白い」