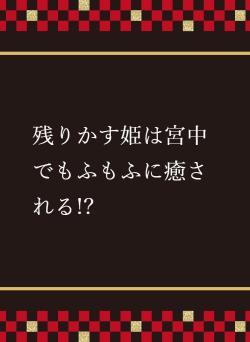声の主は、一陣の風のように傍を通り抜けた。
その横顔に見覚えがあり、俺は咄嗟に呼びかける。
「お前、倉橋! 倉橋伊月か!」
倉橋伊月は、狸穴高校二年B組の生徒――つまり、俺のクラスメイトだ。
口をきいたことはないが、真面目な奴という印象だった。クソつまらん日本史の授業中、居眠りをしてない男子はこいつぐらいだろう。
小柄な身体にいつもきっちりと学ランを纏っているが、今日の格好は奇妙だった。白い着物に水色の袴を合わせ、首には大粒の数珠をかけている。
古風っていうか……何かのコスプレ?
「おい、何だよその服。それに、どうしてお前がここに……」
「黙って! 少し下がっていてくれ、朝見幸太郎くん」
厳しい目つきと鋭い声が飛んできた。俺のフルネームが淀みなく出てきたことに、少し驚く。
休み時間、倉橋伊月はたいてい読書か勉強に没頭している。挨拶しても、会釈が返ってくればいい方だ。部活動には入ってないらしくて、放課後になるとすぐ校内から姿を消す。孤高を貫くタイプだと思ってたが、ちゃんとクラスメイトの顔と名前、覚えてたんだな。
俺が奇妙な装束に身を包んだ姿をまじまじと見ながらそんなことを考えていると、当の倉橋伊月本人が二匹の狐をキッと睨み、両手を顔の前で組んだ。
「もう逃げられないぞ。この狸穴で、お前たちに悪さはさせない!」
ああこれ、漫画で見たことある。確か『印』を結ぶポーズだ。
倉橋伊月はその姿勢を保ったまま眉間に皺を寄せ、袴に包まれた右足をばっと前に踏み出す。
途端に、ごごごごご……と、微かな地響きがした。
「うわっ、何だ、地震か?!」
狐に体当たりされてヘタり込んでいた俺は、慌てて立ち上がった。ごく狭い範囲にある雑草だけがわさわさと揺れていて、薄気味悪い。
狐たちの毛は、ぴりぴりと逆立っていた。なんか二匹とも微妙に苦しそうっていうか、動きがぎこちない気がする。
倉橋伊月が、術か何かを使っているのか? いや、まさかな……。
目の前で起こっていることを受け入れようとする気持ちと、そんなバカなという思いが、俺の中で激しく交錯していた。
そうこうしているうちに、大きい方の狐が尻尾をふわりと振る。
「くっ……!」
ばちりと音がして、見えない何かに弾かれたかのごとく、倉橋伊月がよろめいた。印を結んでいた手がほどけ、地響きがピタリと止まる。
動きが鈍くなっていた狐たちは、自由を取り戻した様子でぴょこぴょこと跳ねた。
あ、もしかして、倉橋伊月の術が……解けたのか?
「尻尾が九つ。大きい方はやはり――九尾か」
倉橋伊月はぐっと顔を歪めた。
数えてみると、確かにデカい方の狐には尾が九本ある。
「おい。何だよあれ。突然変異か?」
俺は奇妙な格好のクラスメイトに詰め寄った。
だが、答えが返ってくるより早く、二匹の狐がこっちに向かって突進してくる。
「うわっ、嘘だろ……狐が、空飛んだ!」
俺にぶつかる寸前、狐たちはぶわっと舞い上がった。あっという間に十メートルの高さに到達した二匹は、宙に浮いたまま俺と倉橋伊月を見下ろしている。
「あ、俺のグローブ!」
よく見ると、小さい方の狐が黄色いグローブを咥えていた。
ヤバい! このまま、どこかに持ち去る気なんだ。
「やめろよ。それ返せ!」
俺が叫ぶと、小さい方の狐はくるりと回って俺たちに尻尾を振ってみせた。「返すもんか、へへん」とでも言っているような仕草だ。
「あ、あいつ……」
歯噛みする俺をよそに、デカい狐が小さい狐を促した。二匹は上空を何度か旋回したあと、すぐ傍にある体育館の屋根を越えて、向こうに逃げていく。
「しまった! 校舎の中に侵入される!」
倉橋伊月が血相を変えて駆け出した。俺も奴の横にぴったりくっついて、狐どものあとを追いかける。
「朝見幸太郎くん。邪魔だから、僕についてこないでくれるかな」
走りながら、倉橋伊月は顔を顰めた。
「お前についていくわけじゃねーよ。小さい方の狐が咥えてたグローブ、俺のなんだ」
「ああ、あの少し使い込まれていたやつか。見た感じ、さほど高級そうじゃなかったよね。悪いけど、諦めて新しいのを買……」
「断る!」
俺は倉橋伊月の声を遮った。
あのグローブには、以前の……まだうちが平和だったころの思い出が詰まってるんだ。だから――。
「そんなことより、あの空飛ぶ狐は何なんだよ。倉橋伊月。お前、事情を知ってるんだろ」
重たくなりそうだった自分の心をなんとか押し留めて、尋ねる。
「あれは、あやかしだよ」
「……は?」
その横顔に見覚えがあり、俺は咄嗟に呼びかける。
「お前、倉橋! 倉橋伊月か!」
倉橋伊月は、狸穴高校二年B組の生徒――つまり、俺のクラスメイトだ。
口をきいたことはないが、真面目な奴という印象だった。クソつまらん日本史の授業中、居眠りをしてない男子はこいつぐらいだろう。
小柄な身体にいつもきっちりと学ランを纏っているが、今日の格好は奇妙だった。白い着物に水色の袴を合わせ、首には大粒の数珠をかけている。
古風っていうか……何かのコスプレ?
「おい、何だよその服。それに、どうしてお前がここに……」
「黙って! 少し下がっていてくれ、朝見幸太郎くん」
厳しい目つきと鋭い声が飛んできた。俺のフルネームが淀みなく出てきたことに、少し驚く。
休み時間、倉橋伊月はたいてい読書か勉強に没頭している。挨拶しても、会釈が返ってくればいい方だ。部活動には入ってないらしくて、放課後になるとすぐ校内から姿を消す。孤高を貫くタイプだと思ってたが、ちゃんとクラスメイトの顔と名前、覚えてたんだな。
俺が奇妙な装束に身を包んだ姿をまじまじと見ながらそんなことを考えていると、当の倉橋伊月本人が二匹の狐をキッと睨み、両手を顔の前で組んだ。
「もう逃げられないぞ。この狸穴で、お前たちに悪さはさせない!」
ああこれ、漫画で見たことある。確か『印』を結ぶポーズだ。
倉橋伊月はその姿勢を保ったまま眉間に皺を寄せ、袴に包まれた右足をばっと前に踏み出す。
途端に、ごごごごご……と、微かな地響きがした。
「うわっ、何だ、地震か?!」
狐に体当たりされてヘタり込んでいた俺は、慌てて立ち上がった。ごく狭い範囲にある雑草だけがわさわさと揺れていて、薄気味悪い。
狐たちの毛は、ぴりぴりと逆立っていた。なんか二匹とも微妙に苦しそうっていうか、動きがぎこちない気がする。
倉橋伊月が、術か何かを使っているのか? いや、まさかな……。
目の前で起こっていることを受け入れようとする気持ちと、そんなバカなという思いが、俺の中で激しく交錯していた。
そうこうしているうちに、大きい方の狐が尻尾をふわりと振る。
「くっ……!」
ばちりと音がして、見えない何かに弾かれたかのごとく、倉橋伊月がよろめいた。印を結んでいた手がほどけ、地響きがピタリと止まる。
動きが鈍くなっていた狐たちは、自由を取り戻した様子でぴょこぴょこと跳ねた。
あ、もしかして、倉橋伊月の術が……解けたのか?
「尻尾が九つ。大きい方はやはり――九尾か」
倉橋伊月はぐっと顔を歪めた。
数えてみると、確かにデカい方の狐には尾が九本ある。
「おい。何だよあれ。突然変異か?」
俺は奇妙な格好のクラスメイトに詰め寄った。
だが、答えが返ってくるより早く、二匹の狐がこっちに向かって突進してくる。
「うわっ、嘘だろ……狐が、空飛んだ!」
俺にぶつかる寸前、狐たちはぶわっと舞い上がった。あっという間に十メートルの高さに到達した二匹は、宙に浮いたまま俺と倉橋伊月を見下ろしている。
「あ、俺のグローブ!」
よく見ると、小さい方の狐が黄色いグローブを咥えていた。
ヤバい! このまま、どこかに持ち去る気なんだ。
「やめろよ。それ返せ!」
俺が叫ぶと、小さい方の狐はくるりと回って俺たちに尻尾を振ってみせた。「返すもんか、へへん」とでも言っているような仕草だ。
「あ、あいつ……」
歯噛みする俺をよそに、デカい狐が小さい狐を促した。二匹は上空を何度か旋回したあと、すぐ傍にある体育館の屋根を越えて、向こうに逃げていく。
「しまった! 校舎の中に侵入される!」
倉橋伊月が血相を変えて駆け出した。俺も奴の横にぴったりくっついて、狐どものあとを追いかける。
「朝見幸太郎くん。邪魔だから、僕についてこないでくれるかな」
走りながら、倉橋伊月は顔を顰めた。
「お前についていくわけじゃねーよ。小さい方の狐が咥えてたグローブ、俺のなんだ」
「ああ、あの少し使い込まれていたやつか。見た感じ、さほど高級そうじゃなかったよね。悪いけど、諦めて新しいのを買……」
「断る!」
俺は倉橋伊月の声を遮った。
あのグローブには、以前の……まだうちが平和だったころの思い出が詰まってるんだ。だから――。
「そんなことより、あの空飛ぶ狐は何なんだよ。倉橋伊月。お前、事情を知ってるんだろ」
重たくなりそうだった自分の心をなんとか押し留めて、尋ねる。
「あれは、あやかしだよ」
「……は?」