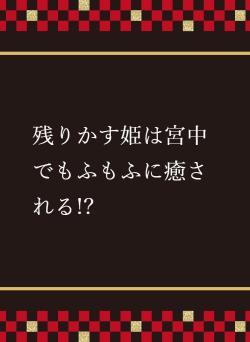「えっ」
「笑っているときも、悲しい顔をしているときも、幸太郎くんは幸太郎くんだよ。自分の気持ちを押さえつける必要はないと思う」
「伊月……」
心の中に押し込められていたものがはじけて、目頭がぐわっと熱くなった。一番聞きたかった言葉を、もらえた気がする。
だが、俺は溢れそうになったものを引っ込めて首を横に振った。
「でもやっぱり、なるべく明るい顔でいたい。特に家ではな。親は兄貴のことで精いっぱいだ。ここで俺まで暗くなったら……」
「だったら――ここに来なよ」
伊月は俺の方に身を乗り出した。
「ここって、伊月の家に?」
思ってもみないことを言われて、俺はやや面食らう。
「うん。夜中に外に出たくなったら、ここにおいでよ。あてもなくうろつくよりマシだろう。たいしたもてなしはできないけど、飲み物くらいなら出せる。それに、僕の応急処置の効果が切れて、夜中に狐の耳が生えてくることもあるかもしれない。そのときも、遠慮なく来ていいから」
はっきり言って、めちゃくちゃありがたい申し出だった。
だが……。
「それって、伊月に迷惑がかかるじゃねーの?」
おずおずと尋ねると、伊月はふわふわの髪に手を当てて、パッとそっぽを向いた。
「迷惑なんかじゃないよ。だって僕と幸太郎くんは――友達、だろう」
伊月は、明らかに少し照れている。
その『友人』がさっき言ったことをふまえて、俺は込み上げてくる気持ちを素直に顔に出すことにした。
「ありがとな、伊月。これからもよろしく!」
満面の笑みを浮かべて片手を差し出すと、伊月もすぐ同じポーズを取る。
「こちらこそ」
二人でガッチリ握手を交わして、笑い合った。静かで質素な和室の中が、温かさで満ちていく。
だが、心地よい余韻は長く続かなかった……。
「あ……なんか変だ」
俺は握手をやめて悶えた。
頭がムズムズする。内側から、何かがせり上がってくるような……。
「幸太郎くん、狐の耳が……」
伊月に言われて頭の上をまさぐると、毛に包まれた三角の物体が生えていた。うっ、これはヤバい。ヤバすぎる!
「い、伊月。なんとかしてくれ~!」
「応急処置の効力が消えちゃったんだ。大丈夫だよ。もう一度僕の気を注入する」
すぐさま、伊月の両腕が俺の背中に回った。胸板と胸板がぴったりくっついて、癖のある髪が俺の頬に当たる。
肩は折れそうなほど華奢だった。それを眺めているうちに、熱さというか、くすぐったさというか……今までに味わったことのない感情が込み上げてくる。
「幸太郎くん。急に身体に力が入ったけど、どうかした?」
伊月は一旦腕を緩め、不思議そうな表情で俺を見上げた。
「あぁ……えーと」
俺は言葉を濁すしかなかった。
うわー、何だこの気持ち。放っとくと、頬が緩みそうだ。なんかふわっとしてて、自分でも上手く説明できん!
「まだ気の注入が中途半端なんだ。もう少し続けていい?」
しどろもどろな俺をよそに、伊月は小首を傾げる。ついでに「おいでよ」と言わんばかりに両腕を広げ……。
「――わ、悪ィ。ちょっと待ってくれ、伊月!」
俺はババッと後ずさって、胸に手を当てた。
そこにある心臓は、なぜか、十七年の人生の中で最も激しいビートを刻んでいた。
了
「笑っているときも、悲しい顔をしているときも、幸太郎くんは幸太郎くんだよ。自分の気持ちを押さえつける必要はないと思う」
「伊月……」
心の中に押し込められていたものがはじけて、目頭がぐわっと熱くなった。一番聞きたかった言葉を、もらえた気がする。
だが、俺は溢れそうになったものを引っ込めて首を横に振った。
「でもやっぱり、なるべく明るい顔でいたい。特に家ではな。親は兄貴のことで精いっぱいだ。ここで俺まで暗くなったら……」
「だったら――ここに来なよ」
伊月は俺の方に身を乗り出した。
「ここって、伊月の家に?」
思ってもみないことを言われて、俺はやや面食らう。
「うん。夜中に外に出たくなったら、ここにおいでよ。あてもなくうろつくよりマシだろう。たいしたもてなしはできないけど、飲み物くらいなら出せる。それに、僕の応急処置の効果が切れて、夜中に狐の耳が生えてくることもあるかもしれない。そのときも、遠慮なく来ていいから」
はっきり言って、めちゃくちゃありがたい申し出だった。
だが……。
「それって、伊月に迷惑がかかるじゃねーの?」
おずおずと尋ねると、伊月はふわふわの髪に手を当てて、パッとそっぽを向いた。
「迷惑なんかじゃないよ。だって僕と幸太郎くんは――友達、だろう」
伊月は、明らかに少し照れている。
その『友人』がさっき言ったことをふまえて、俺は込み上げてくる気持ちを素直に顔に出すことにした。
「ありがとな、伊月。これからもよろしく!」
満面の笑みを浮かべて片手を差し出すと、伊月もすぐ同じポーズを取る。
「こちらこそ」
二人でガッチリ握手を交わして、笑い合った。静かで質素な和室の中が、温かさで満ちていく。
だが、心地よい余韻は長く続かなかった……。
「あ……なんか変だ」
俺は握手をやめて悶えた。
頭がムズムズする。内側から、何かがせり上がってくるような……。
「幸太郎くん、狐の耳が……」
伊月に言われて頭の上をまさぐると、毛に包まれた三角の物体が生えていた。うっ、これはヤバい。ヤバすぎる!
「い、伊月。なんとかしてくれ~!」
「応急処置の効力が消えちゃったんだ。大丈夫だよ。もう一度僕の気を注入する」
すぐさま、伊月の両腕が俺の背中に回った。胸板と胸板がぴったりくっついて、癖のある髪が俺の頬に当たる。
肩は折れそうなほど華奢だった。それを眺めているうちに、熱さというか、くすぐったさというか……今までに味わったことのない感情が込み上げてくる。
「幸太郎くん。急に身体に力が入ったけど、どうかした?」
伊月は一旦腕を緩め、不思議そうな表情で俺を見上げた。
「あぁ……えーと」
俺は言葉を濁すしかなかった。
うわー、何だこの気持ち。放っとくと、頬が緩みそうだ。なんかふわっとしてて、自分でも上手く説明できん!
「まだ気の注入が中途半端なんだ。もう少し続けていい?」
しどろもどろな俺をよそに、伊月は小首を傾げる。ついでに「おいでよ」と言わんばかりに両腕を広げ……。
「――わ、悪ィ。ちょっと待ってくれ、伊月!」
俺はババッと後ずさって、胸に手を当てた。
そこにある心臓は、なぜか、十七年の人生の中で最も激しいビートを刻んでいた。
了