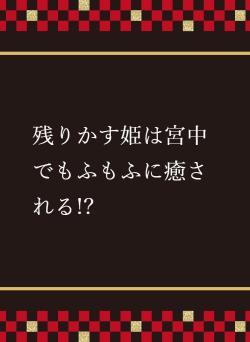小さな両手がパチンと合わさった。
その途端、床の上に何やら丸くて透明な玉が出現した。子供の姿でも、野狐はあやかしだ。術を使って、隠していたものを取り出したんだろう。
玉は直径五センチくらいで、ぴかぴかだった。材質はガラスか、あるいは水晶……?
「この玉は、九尾さまの分身みたいなものなんだよ。九尾さまは自分の力の半分をこれに変えて、おいらに貸してくれたんだ。持っていればすごい妖術が使えるって……。でもおいら、上手く使いこなせなくて、ずっとしまったままだった」
「うむ……確かにこの玉には禍々しさが漂っておる。こうして見ているだけで、息が詰まりそうじゃ」
玄以じいちゃん……先代の陰陽師がゴクリと喉を鳴らした。伊月も同じ顔をしている。
俺にはただのデカいビー玉にしか見えないが、相当厄介な代物のようだ
「九尾の分身――それがここにあるということは、今の九尾は全力を出せないということかな」
伊月の問いかけに、野狐は勢いよく「うん!」と返した。
「九尾さまは、力をいっぱい使って人間を震え上がらせたいって言っていた。だからいつか、この玉を取り返しにくると思うんだ」
「そうか。この『分身玉』を持っていれば、儂らが捜さなくても、九尾の方から会いにくるというわけじゃな!」
玄以じいちゃんが興奮気味に腰を浮かせる。
俺も「おお」と膝を打った。おたずね者の方からやってきてくれるだなんて、都合がいいじゃん! 九尾が現れたら……俺の呪いが解けるかもしれない。
「野狐。その分身玉をこちらに預けてくれんか。儂らは九尾に用がある。玉を使って、奴をおびき寄せたい」
「いいよー。はい!」
野狐は笑顔で玉を差し出した。
「うんうん。素直でいい子じゃの。――そうじゃ、野狐。お前さん、この神社で暮らさないか。儂と伊月はあやかしの存在を重々承知しておる。ここなら隠れる必要はないし、のびのびできるぞ」
「えっ、おいら、一緒にいていいの?!」
玄以じいちゃんはにっこり笑って、小さな頭をひと撫でした。
「もちろんだとも。お前さんはよく腹を空かせているようじゃないか。食べ物も分けてやるぞ。その代わり、掃除やこまごましたことを手伝ってもらうがのぅ。……伊月も、それで構わないか」
「異存はないよ、お祖父ちゃん。九尾が現れるまで、幸太郎くんの呪いは僕の応急処置で凌ぐ」
「よし、決まりじゃ! 野狐はひとまず、人間の姿でいるといい。意思疎通がしやすいからのぅ。子供用の服を用意してやらんといかんな。今から一緒に買い物に行くぞ!」
開襟シャツの袖をぐっとまくると、玄以じいちゃんは野狐の手を引いてすたすたと部屋を出ていってしまった。やることなすことスピーディーで、元気なじいちゃんだ。
二人……いや、人間一人とあやかし一体がいなくなり、あたりは途端に静まり返った。しばらくして、隣に座っていた伊月が俺の方に向き直る。
「幸太郎くんは、何度かうちの神社に来たことがあるよね。しかも、毎回夜中と言っていい時間に、一人で」
俺は思わず、目を見開いた。
「……知ってたのかよ、そのこと」
「うん。僕の部屋から境内が見えるんだ。幸太郎くんは学校ではいつも明るいけど、本殿の前で佇んでいるときは、すごく――寂しそうだった」
「そこまでバッチリ見られてたのか」
「覗き見みたいな真似をして、ごめん。でも幸太郎くんは、どうしてあんなに夜遅くに、一人で外にいるの?」
俺は、ふっと肩の力を抜いた。
ここまで来たら、もう隠しておくわけにはいかねぇよな。
「なんか、居づらいんだよ。自分の家に。……兄貴が今、部屋から出てこなくてさ。親までちょっとナーバスになってて、それで……」
兄貴は夜になると、ドンと壁を叩く。食べ物とか飲み物を持ってこいという合図だ。おふくろはそのたびに身を竦め、親父は溜息を吐く。
暴力を振るわれることはない。喚き散らされるわけでもない。ただ、ドンというその音は、見えないナイフとなって俺たちの心を毎日少しずつ削ぎ取っていく。
俺も親も、なんとかして兄貴の力になりたかった。だが、本人は頑なに顔を見せない。無理に声をかけると、扉の向こうからすすり泣く声が聞こえてくる。
次第に、家の中の空気が重くなった。それに押し潰されそうになったとき、俺は逃げるように外に出る。
とはいえ、夜遅くに高校生が出歩ける範囲は限られる。ゆうべはコンビニをはしごする代わりに、学校に忘れ物を取りにきたんだ。
この狸穴神社は、しばしの間心を落ち着けるのにうってつけの場所だった。たびたび利用させてもらったが、まさか伊月に見られていたとはな……。
「こんなこと学校の連中には話せなかった。親の前でも暗い顔はできねーし。ほら、落ち込んでるのって俺らしくねぇだろ。だから、モヤモヤしたら外に出てたんだ」
たどたどしくそこまで話すと、ずっと黙って聞いていた伊月がふいに顔を上げた。
「幸太郎くんらしさって、何?」
その途端、床の上に何やら丸くて透明な玉が出現した。子供の姿でも、野狐はあやかしだ。術を使って、隠していたものを取り出したんだろう。
玉は直径五センチくらいで、ぴかぴかだった。材質はガラスか、あるいは水晶……?
「この玉は、九尾さまの分身みたいなものなんだよ。九尾さまは自分の力の半分をこれに変えて、おいらに貸してくれたんだ。持っていればすごい妖術が使えるって……。でもおいら、上手く使いこなせなくて、ずっとしまったままだった」
「うむ……確かにこの玉には禍々しさが漂っておる。こうして見ているだけで、息が詰まりそうじゃ」
玄以じいちゃん……先代の陰陽師がゴクリと喉を鳴らした。伊月も同じ顔をしている。
俺にはただのデカいビー玉にしか見えないが、相当厄介な代物のようだ
「九尾の分身――それがここにあるということは、今の九尾は全力を出せないということかな」
伊月の問いかけに、野狐は勢いよく「うん!」と返した。
「九尾さまは、力をいっぱい使って人間を震え上がらせたいって言っていた。だからいつか、この玉を取り返しにくると思うんだ」
「そうか。この『分身玉』を持っていれば、儂らが捜さなくても、九尾の方から会いにくるというわけじゃな!」
玄以じいちゃんが興奮気味に腰を浮かせる。
俺も「おお」と膝を打った。おたずね者の方からやってきてくれるだなんて、都合がいいじゃん! 九尾が現れたら……俺の呪いが解けるかもしれない。
「野狐。その分身玉をこちらに預けてくれんか。儂らは九尾に用がある。玉を使って、奴をおびき寄せたい」
「いいよー。はい!」
野狐は笑顔で玉を差し出した。
「うんうん。素直でいい子じゃの。――そうじゃ、野狐。お前さん、この神社で暮らさないか。儂と伊月はあやかしの存在を重々承知しておる。ここなら隠れる必要はないし、のびのびできるぞ」
「えっ、おいら、一緒にいていいの?!」
玄以じいちゃんはにっこり笑って、小さな頭をひと撫でした。
「もちろんだとも。お前さんはよく腹を空かせているようじゃないか。食べ物も分けてやるぞ。その代わり、掃除やこまごましたことを手伝ってもらうがのぅ。……伊月も、それで構わないか」
「異存はないよ、お祖父ちゃん。九尾が現れるまで、幸太郎くんの呪いは僕の応急処置で凌ぐ」
「よし、決まりじゃ! 野狐はひとまず、人間の姿でいるといい。意思疎通がしやすいからのぅ。子供用の服を用意してやらんといかんな。今から一緒に買い物に行くぞ!」
開襟シャツの袖をぐっとまくると、玄以じいちゃんは野狐の手を引いてすたすたと部屋を出ていってしまった。やることなすことスピーディーで、元気なじいちゃんだ。
二人……いや、人間一人とあやかし一体がいなくなり、あたりは途端に静まり返った。しばらくして、隣に座っていた伊月が俺の方に向き直る。
「幸太郎くんは、何度かうちの神社に来たことがあるよね。しかも、毎回夜中と言っていい時間に、一人で」
俺は思わず、目を見開いた。
「……知ってたのかよ、そのこと」
「うん。僕の部屋から境内が見えるんだ。幸太郎くんは学校ではいつも明るいけど、本殿の前で佇んでいるときは、すごく――寂しそうだった」
「そこまでバッチリ見られてたのか」
「覗き見みたいな真似をして、ごめん。でも幸太郎くんは、どうしてあんなに夜遅くに、一人で外にいるの?」
俺は、ふっと肩の力を抜いた。
ここまで来たら、もう隠しておくわけにはいかねぇよな。
「なんか、居づらいんだよ。自分の家に。……兄貴が今、部屋から出てこなくてさ。親までちょっとナーバスになってて、それで……」
兄貴は夜になると、ドンと壁を叩く。食べ物とか飲み物を持ってこいという合図だ。おふくろはそのたびに身を竦め、親父は溜息を吐く。
暴力を振るわれることはない。喚き散らされるわけでもない。ただ、ドンというその音は、見えないナイフとなって俺たちの心を毎日少しずつ削ぎ取っていく。
俺も親も、なんとかして兄貴の力になりたかった。だが、本人は頑なに顔を見せない。無理に声をかけると、扉の向こうからすすり泣く声が聞こえてくる。
次第に、家の中の空気が重くなった。それに押し潰されそうになったとき、俺は逃げるように外に出る。
とはいえ、夜遅くに高校生が出歩ける範囲は限られる。ゆうべはコンビニをはしごする代わりに、学校に忘れ物を取りにきたんだ。
この狸穴神社は、しばしの間心を落ち着けるのにうってつけの場所だった。たびたび利用させてもらったが、まさか伊月に見られていたとはな……。
「こんなこと学校の連中には話せなかった。親の前でも暗い顔はできねーし。ほら、落ち込んでるのって俺らしくねぇだろ。だから、モヤモヤしたら外に出てたんだ」
たどたどしくそこまで話すと、ずっと黙って聞いていた伊月がふいに顔を上げた。
「幸太郎くんらしさって、何?」