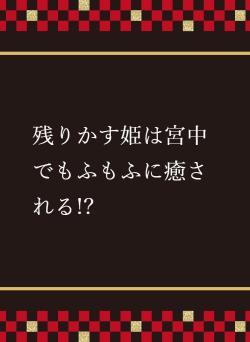「浦辻先生が花村先生に、『中身、見ましたか』と催促するメッセージを何度も送ってきたのは、CD-ROMのケースに仕込んでおいたメモの返事を早く聞きたかったからだろうね」
「なるほどな。そういうことかー」
廊下を歩きながら、俺は伊月の説明に頷いていた。
浦辻からのメモを手にして棒立ちになったちなみちゃんを一人音楽準備室に残し、二人で教室まで戻っているところだ。
二人の教師がどうなるのか気になるが、俺たちの役目は事典を見つけること。これ以上は野暮だろう。
そもそも、彼女なんていたことない俺には、恋愛なんて分かんねーし。
「っていうか、伊月。お前って、めちゃくちゃ頭が切れるんだな。さすがは陰陽師!」
俺は隣を歩く伊月の背中を軽くはたいた。
だが当の本人は、喜ぶどころか少し肩を落とす。
「僕はたいしたことはしてないよ。それに、陰陽師としてはまだ半人前なんだ。ゆうべは九尾に対抗すらできなかったし、野狐も取り逃がした」
「いやいや、伊月はすげえって。……でも、野狐の奴はどこにいるんだろうな。学校の敷地からは出られねーんだろ」
「うん。結界が張ってあるからね。校舎の中にいないなら、体育館か校庭か……」
そんな話をしているうちに、渡り廊下を通ってメイン校舎に戻ってきていた。時を同じくして、俺は猛烈な空腹感に襲われる。
そういや、百科事典を捜してて、昼飯を食いそびれてたぜ。
「伊月。お前、昼っていつもどうしてんの? 弁当とか持ってきてる?」
「いや。僕は昼は毎日、コンビニかどこかで買って食べてるけど」
神社で暮らす陰陽師も、コンビニとか行くんだな……と妙なところに親近感を覚えつつ、俺は前方を指さした。
「俺も買い食い派なんだ。ちょうどいいから一緒に購買行かねー? すぐそこだし」
狸穴高校の一階には購買があって、パンとかおにぎりが置いてある。
昼休みはあと十五分。校外のコンビニに行くには残り時間が心許ないが、目と鼻の購買で飯を調達すれば余裕だ。
伊月がこくりと頷いたので、二人で購買に駆け寄った。
廊下の片隅に台を置いただけの簡単なスペースは、少し寂しかった。すでに大半の商品は売れちまったみたいだな。
そんな中、売り子のおばちゃんが、残っていたパンを二つほど袋に入れていた。やってきた俺たちを見て、「あら」と手を止める。
「これ、本日最後のロールパンなんだけど、買う?」
おばちゃんによって袋詰めされていたパンの種類が判明した。
「俺はいいや」
「僕も結構です」
俺と伊月が揃って首を横に振ると、おばちゃんは「そうかい」と言って、ロールパンの入った袋をゆさゆさと振った。
「あんたたちがいらないなら、このロールパンはあたしが買うよ。自分で食べるんじゃないけどね」
「自分で食べるんじゃないなら、誰が食べるんだ?」
俺が聞くと、おばちゃんの顔に笑みが浮かぶ。
「犬だよ。今朝あたしがここに出勤してきたとき、木の陰からよろよろ出てきたんだ。首輪がないから捨て犬だろうけど、人懐っこいから前はどこかで飼われてたのかもねぇ」
購買のおばちゃんは、その犬に自分の昼飯のおにぎりを分けてやったそうだ。犬はそれそれをがつがつと食べ、なおもおばちゃんにすり寄った。
「あたしはペットを飼う気はないけど、少しの間家に置いて、飼い主を捜そうと思ってるんだ。……でもね、その犬、ちょっと変なんだよ。ワンワン吠えないで鼻を鳴らすだけだし、身体は真っ白で、尻尾が妙に太くて、顔がこう、ちょっとシュッとしてて……」
おばちゃんの話を聞きながら、俺は『あるもの』を思い浮かべた。すかさず、伊月の方を振り返る。
「おい、伊月」
「幸太郎くん……その犬って、もしかして」
伊月も全く同じものをイメージしたらしい。神妙な顔つきで俺を見つめ返してきた。
「おばちゃん。そのキツ……いや、犬って、今どこにいるんだ?!」
俺が勢い込んで問いかけると、おばちゃんはすぐさま答えた。
「体育館の裏に繋いである。『仕事が終わったら迎えにくるから大人しくしときな』って、よーく言い聞かせておいたよ。もう少ししたらこのロールパンを持って、様子を見にいこうかと……」
「サンキュー!」
話の途中で、俺と伊月は身を翻した。
昇降口で上靴からスニーカー履き替え、体育館の裏に向かって猛ダッシュする。
ゆうべも訪れたそこに、真っ白な毛玉が鎮座していた。その身体はアンモナイトみたいにくるっと丸まっていて、何やらすーすーという規則正しい音が……。
マジかよ。こいつ、呑気に寝てやがる。しかも、寝息まで立てて。
「おい、こら――野狐!」
一発怒鳴ると、犬……と勘違いされた野狐はパッと目を覚ました。俺たちの姿を見て飛んで逃げようとしたが、すぐにべしゃっと地面に落ちる。
首にロープが巻かれていたせいだ。反対側の先は木に結ばれていた。購買のおばちゃんが、そうやって繋いでおいたんだろう。
ちょっと情けない野狐の姿を、伊月が呆れたような顔つきで見下ろしている。
「野狐。君はあやかしなのに、どうして大人しく繋がれているんだ。ここで待っていれば食べ物がもらえると思ったのか。プライドはないの?」
プライドに加えて、危機感もなさそうだな。
俺がやれやれと肩を竦めたとき、無機質な電子音が鳴り響いた。伊月が胸ポケットからスマホを取り出して、画面に目をやる。
「祖父からメッセージだ。温泉旅行から帰ってきたって。幸太郎くんにかけられた呪いを詳しく確認したいから、本人を連れてこいって言ってるけど、どうする。うちに来る?」
「行く!」
間髪容れずに俺は首肯した。
「分かった。……ならひとまず、こいつをなんとかしないとね」
俺と同い年の陰陽師はそう言って、白い毛玉にゆっくりと視線を移した。