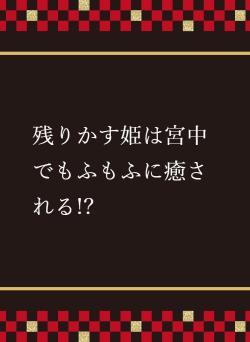半分パニック状態のちなみちゃんを伊月がなんとか宥め、ひとまず事情を聞くことになった。散らかった室内にはもちろん座る場所なんてなく、立ったままだ。
「わたしがなくしたのは……百科事典なの」
「百科事典?」
聞いたことをそのまま俺が鸚鵡返しにすると、ちなみちゃんはこくりと頷いて、傍にあった本の山から、紙ケースに入った分厚い一冊を「よいしょっ」と引っ張り出した。
「老舗の出版社が出してる子供向けの百科事典よ。対象は小・中学生だけど内容がしっかりしてるし、カラー写真も豊富で、大人も楽しめるの。音楽関連の項目もたくさん載ってるから、授業の補助プリントを作るときによく参考にしてるのよ。三巻でワンセットになってて、これは第二巻。一巻と三巻は、ほら、そこにあるわ」
ちなみちゃんは言いながら、足元の本の山に視線を落とす。その中には確かに、同じタイトルの百科事典が二冊埋もれていた。
「わたし、この百科事典を学生時代から愛用してたの。だけど最近、新版が出てね。買い替えようかどうか悩んでたのよ」
百科事典の新版は先月刊行になった。
旧版と同じく全三巻で、新しく加えられた項目が多数あるらしいが、一冊が分厚いだけあって値段もそれなりに張る。
ちなみちゃんとしては、買い替える前に一度中身を確かめたかったそうだ。うんうん。金は大事だもんな。気持ちは分かる。
「でね、他の先生と職員室で雑談したとき、この百科事典の話題を出したのよ。そしたらその先生が『新版を持ってるから貸しますよ』って言ったの。昨日早速、ここまで持ってきてくれたわ。でも、その新版の百科事典が……」
「なくなってしまったんですね」
途中でかき消えた言葉を、伊月が補足する。
ちなみちゃんは、しゅんと項垂れた。
「わたし、昨日は忙しくて。百科事典を持ってきてもらったとき、机に向かって仕事をしていたの。『ここに置いておきますから』っていう声に『ありがとうございます』って返しただけで、実際に事典を置くところを見たわけじゃないのよ。気が付いたときには、借りたものがどこにいったか分からなくなっちゃってた」
確かに、この部屋でボールペンを転がしたらソッコーでどっかに紛れそうではある。
でも、問題の紛失物は百科事典だろ。ちなみちゃんが持ってる本は一抱えほどの大きさだ。しかも、全部で三冊。
いくらここがカオス空間だとしても、そんなデカいものが消えたりするか?
「置くところを見ていなかったとはいえ、事典がなくなるなんて妙だね」
伊月も俺と全く同じことを考えたようだ。顎の下に指を当てて考え込む。
「事典がないのに気付いたのは今朝よ。それからこの部屋をあちこち掻き回してるんだけど、全然見つからなくて……。そうこうしてるうちに棚からものが落ちてきたりして、余計に散らかっちゃった」
ちなみちゃんは旧版の事典を置き、とっ散らかった室内を眺め回して溜息を吐いた。
さっき聞こえてきたのは、棚の中のものが床に落ちた音だったのか……。
「あぁ、どうしよう! 事典を貸してくれた先生から『中身、見ましたか』ってメッセージが何度も届いてるのよ。なくしちゃったなんて言えない!」
再び取り乱したちなみちゃんに、伊月が歩み寄った。
「落ち着いてください、花村先生。百科事典は本当にこの部屋に持ち込まれたんですか。先生は置かれたところを見ていないんですよね」
そうか。そもそもここに、新版の百科事典が初めから存在してない可能性がある。
貸主は『ここに置いておきますから』とか言ってたらしいが、実際は何も置かなかったんじゃないか?
伊月の奴、結構鋭いじゃん……俺はそう思ったが、ちなみちゃんは首を横に振った。
「貸してくれた人が嘘を吐いてたってこと? それはないと思うわ。わたしがあのとき机に向かっていたのはたまたまよ。いつ顔を上げるか分からなかったんだから、そんな状態で嘘を言うはずがないでしょう」
「確かにそうですね。……では、盗まれたということはありませんか。花村先生が百科事典を借りたのは昨日です。夜のうちに誰かが侵入したのかもしれません」
伊月は今度はそんなことを言い出した。俺はまたもや『鋭い!』と感心したが、ちなみちゃんはこれも否定した。
「侵入は無理ね。部屋を出るときは、毎回必ず施錠をするの。鍵はわたしが持ってる一本だけ。ここのロックは旧式だから、マスターキーは合わないわ。無理にこじ開けられた様子はなかった」
うーん……どうやら盗まれたわけでもなさそうだ。ということは、やっぱり百科事典はここに持ち込まれたけど、消えちまったってことになる。
「とにかく、二人とも捜すの手伝って。昼休みの間だけでいいから!」