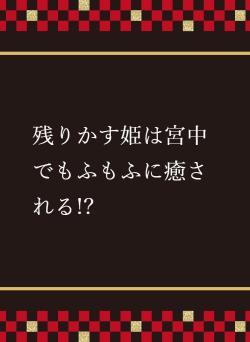俺はゴクリと息を呑んだ。
呪いをかけた本人が、簡単に説得に応じるか? だが、九尾にはそうそう勝てない。
それって、つまり……。
「僕は諦めないよ。できることを、精いっぱいする」
伊月の言葉が、重たい結論を追い出してくれた。
そうだ、諦めるのはまだ早い。暗くなるなんて、俺らしくねぇ!
「分かった。呪いのことは、伊月に任せる」
俺は片手を軽く上げた。何をしようとしているのか察したらしく、伊月も同じポーズを取る。
「頼んだぞ、伊月」
「頼まれたよ、幸太郎くん」
触れ合った手がパンと音を立て、じんわりと温かくなった。
その余韻をしばらく肌で感じていると、伊月は改まった様子で口を開いた。
「退治するにせよ、説得するにせよ、まずは九尾の居所を割り出す必要がある。ゆうべは取り逃がしたからね」
「何か心当たりがあるのか」
「僕にはないけど、野狐……九尾と一緒にいた小さな狐のあやかしなら知っているはずさ。あいつはゆうべ幸太郎くんに突き飛ばされてどこかに行ってしまったけど、実は僕、この学校の周りにぐるっと結界を張っておいたんだよ」
野狐にはたいして力がないらしい。だから、伊月が張った結界を突破できない。つまり、まだこの学校のどこかに身を隠しているってことだ。
「じゃあ、その野狐を見つければいいんだな。俺も手伝っていいか?」
「手が多い方が助かるけど……いいの? 僕たち、今までたいして話したこともなかったのに」
伊月は僅かに目を伏せた。俺はその華奢な肩を、パンとはたく。
「なーに言ってんだ。いいに決まってんじゃん! あ、これからは教室でもバンバン話しかけてくれよ。クラスの連中には『最近仲よくなった』とか適当に言っとくし」
「でも……」
「遠慮すんなって。だって俺たち――もう友達だろ!」
「……!」
伊月は顔をふわりと綻ばせた。
笑ってる。同じクラスになって半年。初めて目の当たりにする表情だった。なんだか嬉しくなって、俺も頬を緩ませる。
「まだ昼休みは残ってるね。幸太郎くん。早速、野狐捜しを手伝ってくれるかな」
微かに口角を上げたまま、伊月は言った。
俺はもちろん、大きく頷く。
「よっしゃ。まずはどこを捜す?」
「校舎内を見て回ろう。野狐は悪戯好きだから、きっとどこかで機会を窺っ……」
がしゃん!
伊月の言葉は、その派手な物音で途切れた。俺は思わず身を竦め、あたりをきょろきょろ見回す。
「何だよ、今の音」
「隣の部屋から聞こえた。幸太郎くん、行ってみよう」
今いる視聴覚倉庫の隣は、音楽準備室だ。伊月、俺の順でそこに飛び込むと、中で誰かが立ち尽くしていた。
「あれっ、ちなみちゃ……じゃなくて、花村先生じゃん」
俺はその人物――音楽の花村ちなみ先生こと、『ちなみちゃん』を指さした。
まだ二十八歳と若く、性格もフレンドリーなこの教師のことを、生徒たちは親しみを込めてちなみちゃんと呼んでいる。もちろん本人を前にしたときは、ちゃんと『花村先生』って言うけどな。
ちなみちゃんは、何を隠そう、俺と伊月の担任だ。この高校に音楽教師は一人しかいないから、音楽準備室はある意味、ちなみちゃんの城ともいえる。
しっかし……。
「すげぇ散らかってんな……」
俺の口から本音が漏れ出る。
風雲ちなみちゃん城は、もので溢れ返っていた。まず、楽譜や本があちこちにうず高く積まれている。その間にはクラシックのCDがこれまた高い山になっていて、一部が雪崩を起こしていた。
窓際にあるのはデスク『らしきもの』だ。書類やらクッションやらひざ掛けやら、細かいもので埋め尽くされてて、それがデスクであると断定できないんだよなぁ。
惨憺たる状態に「うへぇ」っとなる俺。伊月も顔を半分顰めていたが、やがて立ち尽くしたままのちなみちゃんに向き直る。
「花村先生。この部屋から大きな物音がしたようですが、何かありましたか?」
「ああっ、倉橋くんに朝見くん。ちょうどいいところに来てくれたわ!」
ちなみちゃんは、俺たちにがばっと縋り付いてきた。
そして、髪を振り乱して叫ぶ。
「わたし、この部屋で大事なものをなくしちゃったの。二人とも、お願い――助けて!」
呪いをかけた本人が、簡単に説得に応じるか? だが、九尾にはそうそう勝てない。
それって、つまり……。
「僕は諦めないよ。できることを、精いっぱいする」
伊月の言葉が、重たい結論を追い出してくれた。
そうだ、諦めるのはまだ早い。暗くなるなんて、俺らしくねぇ!
「分かった。呪いのことは、伊月に任せる」
俺は片手を軽く上げた。何をしようとしているのか察したらしく、伊月も同じポーズを取る。
「頼んだぞ、伊月」
「頼まれたよ、幸太郎くん」
触れ合った手がパンと音を立て、じんわりと温かくなった。
その余韻をしばらく肌で感じていると、伊月は改まった様子で口を開いた。
「退治するにせよ、説得するにせよ、まずは九尾の居所を割り出す必要がある。ゆうべは取り逃がしたからね」
「何か心当たりがあるのか」
「僕にはないけど、野狐……九尾と一緒にいた小さな狐のあやかしなら知っているはずさ。あいつはゆうべ幸太郎くんに突き飛ばされてどこかに行ってしまったけど、実は僕、この学校の周りにぐるっと結界を張っておいたんだよ」
野狐にはたいして力がないらしい。だから、伊月が張った結界を突破できない。つまり、まだこの学校のどこかに身を隠しているってことだ。
「じゃあ、その野狐を見つければいいんだな。俺も手伝っていいか?」
「手が多い方が助かるけど……いいの? 僕たち、今までたいして話したこともなかったのに」
伊月は僅かに目を伏せた。俺はその華奢な肩を、パンとはたく。
「なーに言ってんだ。いいに決まってんじゃん! あ、これからは教室でもバンバン話しかけてくれよ。クラスの連中には『最近仲よくなった』とか適当に言っとくし」
「でも……」
「遠慮すんなって。だって俺たち――もう友達だろ!」
「……!」
伊月は顔をふわりと綻ばせた。
笑ってる。同じクラスになって半年。初めて目の当たりにする表情だった。なんだか嬉しくなって、俺も頬を緩ませる。
「まだ昼休みは残ってるね。幸太郎くん。早速、野狐捜しを手伝ってくれるかな」
微かに口角を上げたまま、伊月は言った。
俺はもちろん、大きく頷く。
「よっしゃ。まずはどこを捜す?」
「校舎内を見て回ろう。野狐は悪戯好きだから、きっとどこかで機会を窺っ……」
がしゃん!
伊月の言葉は、その派手な物音で途切れた。俺は思わず身を竦め、あたりをきょろきょろ見回す。
「何だよ、今の音」
「隣の部屋から聞こえた。幸太郎くん、行ってみよう」
今いる視聴覚倉庫の隣は、音楽準備室だ。伊月、俺の順でそこに飛び込むと、中で誰かが立ち尽くしていた。
「あれっ、ちなみちゃ……じゃなくて、花村先生じゃん」
俺はその人物――音楽の花村ちなみ先生こと、『ちなみちゃん』を指さした。
まだ二十八歳と若く、性格もフレンドリーなこの教師のことを、生徒たちは親しみを込めてちなみちゃんと呼んでいる。もちろん本人を前にしたときは、ちゃんと『花村先生』って言うけどな。
ちなみちゃんは、何を隠そう、俺と伊月の担任だ。この高校に音楽教師は一人しかいないから、音楽準備室はある意味、ちなみちゃんの城ともいえる。
しっかし……。
「すげぇ散らかってんな……」
俺の口から本音が漏れ出る。
風雲ちなみちゃん城は、もので溢れ返っていた。まず、楽譜や本があちこちにうず高く積まれている。その間にはクラシックのCDがこれまた高い山になっていて、一部が雪崩を起こしていた。
窓際にあるのはデスク『らしきもの』だ。書類やらクッションやらひざ掛けやら、細かいもので埋め尽くされてて、それがデスクであると断定できないんだよなぁ。
惨憺たる状態に「うへぇ」っとなる俺。伊月も顔を半分顰めていたが、やがて立ち尽くしたままのちなみちゃんに向き直る。
「花村先生。この部屋から大きな物音がしたようですが、何かありましたか?」
「ああっ、倉橋くんに朝見くん。ちょうどいいところに来てくれたわ!」
ちなみちゃんは、俺たちにがばっと縋り付いてきた。
そして、髪を振り乱して叫ぶ。
「わたし、この部屋で大事なものをなくしちゃったの。二人とも、お願い――助けて!」