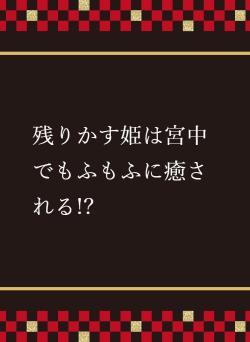「おお、あったあった」
俺は地面に転がっていた黄色いグローブを拾い上げ、ひとりごちた。
やや草臥れているそれには『朝見幸太郎』と書いてある。間違いなく、俺の名前だ。
ここは、俺が通う都立狸穴高校の体育館裏。夜の十一時を越えた今、周囲は闇に包まれている。僅かに届く街灯りと、スマホのバックライトだけが頼りだ。
入学してから一年半ほど経つが、こんなに遅い時間に訪れたのは初めてだった。たった今拾い上げたグローブは、今日の放課後、クラスメイトの矢田吹とキャッチボールをしていて置き忘れたものだ。たいして高価ってわけでもなく、しかも俺の名前まで書いてある使い古された代物。こんなもん、一晩放置したとしても持ち去られることなんてないと思う。
それでも、俺はこの黄色いグローブを取りにきた。夜の十一時に、自転車をせっせと漕いで。
わざわざそんなことをした理由はただ一つ――なるべく、家にいたくなかったから。
無事に捜し物を見つけ出せて安堵する一方で、微かに溜息を吐く。足元に、ようやく涼しくなった十月の風が吹き付けた。
手の中にあるグローブは、三年前に親父や兄貴とお揃いで買ったものだ。自分の持ち物に記名するのが、うちの決まり事だった。それぞれのグローブを嵌めて三人でキャッチボールする様を、おふくろがニコニコと眺めてたっけ。
あのころは、気の合う連中と遊ぶのと同じくらい、家にいるのが好きだった。こんな時間にいたたまれなくなって外に飛び出すなんて、考えられなかった……。
「あー、やめやめ!」
そこで、ぶるぶると頭を振った。
自分で言うのもなんだが、俺は明るいお調子者で通ってる。溜息吐いて落ち込むなんて、らしくねぇ上に何の解決にもならん!
コンビニに寄って夜食でも物色してから帰るか……とりあえずそう思いながら、駐輪場の方へ足を向ける。
「おわっ!」
その瞬間、身体に衝撃を感じた。
何か白いものが思いっきり体当たりしてきたんだ。不意をつかれ、俺はあっけなく地面に転がる。
「痛ってぇな。何だよ、いきなり……って、は?」
ぶつかってきた野郎に文句を言おうとして、そのまま何度か瞬きをした。
十メートルほど先に、大小二つの物体がある。二つとも真っ白な毛に覆われ、顔の上には三角の耳が……。
「き、狐?!」
それは二匹の狐だった。小さい方は普通のサイズだが、大きい方はその四倍ほどある。
おい、いくらなんでもデカすぎだろ。それに、微かに光を放っているように見えるのは、錯覚……だよな。
俺がゴクリと息を呑んだとき、後ろから大声が聞こえた。
「待て! 追いかけっこはここまでだ!」