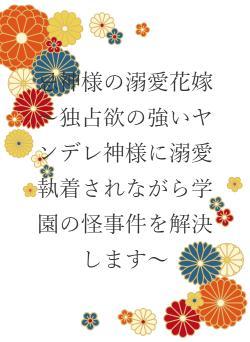「おはよ」
「……お、おはよ」
本日も蝉の大合唱がうるさい中、二人は挨拶を交わす。
鷺宮葵はいつも通りに。
紺堂圭太はやや慌てながら。
「圭太、もしかして意識してる?」
そうであることがバレバレでありながらも、葵は意地悪く圭太にそう訊ねた。
当然圭太は、ビクリと肩を動かした。
「べ、別にそんなことないし……!」
「ふぅん」
葵はニコニコと笑いながら圭太を見つめた。
正直、葵だって表に出さないだけで意識している。
ずっと想い人だった圭太と付き合い始めたのだ。意識しないわけがない。
葵にとって、圭太は夏の太陽のように眩しく、キラキラとした存在だった。圭太本人は自分を陰に潜むオタクなどと卑下しているが、葵から見ればずっと眩しく輝く憧れの想い人だったのだ。
そんな圭太と今、ようやく結ばれることができた。
だから圭太とは違い、葵はとても浮かれていた。
そんな浮かれ具合から出てくる笑顔がいつも以上に魅力的だからか、傍で葵を盗み見ていた女子がキャーキャーと騒ぎ立てている。
当人は全くその子たちを眼中に入れていないのだが。
「ねえ圭太。今日はお昼、視聴覚室で食べようよ」
あえて圭太の耳元で、葵は囁く。
圭太は勢いよく振り返り、真っ赤になった耳を抑えながら言葉を返した。
「なんでだよ? ってか視聴覚室って授業以外で使っていいんだっけ?」
「そこは俺が鍵借りとくからさ。冷房も付いてるし、何より……二人っきりになれるでしょ?」
「ばっ……」
馬鹿野郎、と言いたかったであろう圭太は、しかし声の大きさで人目を集めかけていることに気付き、なんとか言葉を飲み込む。
代わりにジト目で葵を睨み返し、席に着く。
そんな圭太を可愛いと思いながら、葵も席に着くのだった。
そうして迎えた昼休み。
冷房の効いた視聴覚室は、静けさで満たされている。
ドア一枚隔てた廊下側から聞こえる生徒たちの立てる音が、ハッキリと聞こえるぐらいに静かだ。
「ん……」
そんな静けさの中で、二つの吐息が密かに混じっていた。
普通に談笑しながらお昼を食べ終えた途端、葵が圭太にキスをねだったのだ。
最初は拒否していた圭太だったが、葵の懇願に負け、こうしてキスを受け入れることとなる。
「葵……もう……んっ」
「もうちょっと……もうちょっとだけ……」
唇が触れるだけのキスではあるが、それはとても官能的で熱を帯びていた。
重ね合った指先が、互いの体温を交換しているように熱い。
小さく響くリップ音。絡みつく吐息。窓の外の蝉の合唱。廊下から聞こえてくる生徒たちの声。
そのどれもが、二人を煽り、ドキドキと鼓動を早くさせた。
「ん、ん……」
「圭太……」
そうしてしばし沈黙が続き……ようやく、葵の方から圭太と距離を取る。
「……もうやめろって言ったのに」
眼鏡の位置を直しながら、圭太は不満を口にする。
口を尖らせるその姿に、葵は愛おしさを感じた。
「だってキスした時にしか見れない顔するから、もっと見たくて……」
「……っ」
恥ずかしいことを臆面もなく言ってくる葵に、逆に顔を赤くする圭太。
葵からの視線はいつも煽情的だ。
告白されてから、ようやくその視線が、いつも強く自分に絡みついていたことを圭太は知った。
「そろそろ……昼休み、終わる」
「そうだね」
葵からの熱視線に耐えられず、圭太は目を反らし、空になった弁当箱を片付ける。
すると、少し間を開けて葵が言葉を発した。
「……ねえ圭太」
「んー?」
「俺だけが圭太のことを好きなら……その時は別れていいからね」
「んなっ」
いきなりの言葉に、思わず圭太は葵の方を向く。
葵は、アンニュイな微笑を浮かべながら、それでもなお愛おしそうに圭太を見つめていた。
なんだかその表情があまりにも切なくて、圭太は一人慌てた。
「なんだよいきなり。好きだの別れていいだの……わけわかんないよ」
「ははっ、ごめんごめん。俺、圭太のこと本当に好きだから……だからこそ圭太を困らせたくないんだよね」
「べつに、困ってなんか……」
「そ? それなら良かった」
そうは言いつつも、葵の表情はどこか切なげだ。
「葵……」
圭太がその名を口にするのと同時に、お昼休みを終えるチャイムが鳴り響いた。
「よし、バレる前に教室戻ろっか」
「お、おう……」
まだ話したいことがあったような、しかしいざ葵を前にしたら何て言ったらいいのかわからなくなった圭太は、流されるように立ち上がった。
モヤモヤとした気持ちを抱えたまま、圭太は葵の後を続き、視聴覚室を出るのだった。
***
『風邪ひいた、今日は休む』
次の日。
教室に着いたのを見計らったかのようなタイミングで、葵からそんな連絡が来ていた。
三年になってから葵が欠席するのを見たことは一度も無く、珍しいなとさえ思えた。
「………」
その一方で、昨日の昼休みでの出来事が圭太の脳裏に浮かぶ。
まさかあれを気にしてだろうか。
そんな気持ちが脳裏に渦巻く。
あの後、圭太だって様々なことを考えた。
葵の強烈な好きという感情に流されているだけなのではないか。果たして本気で葵のことが好きなのか。
男同士で付き合うということを、ちゃんとわかっていないんじゃないか。
本当に本当に、色々と考えた。
むしろ知恵熱が出そうで休みたいのはこっちの方だ、と圭太は心の中で葵に愚痴る。
「今日、葵くんお休みー?」
席の近い女子が、気さくな感じでそう訊ねてきた。
葵の隣の席なのもあって、よく葵と喋っている女子だ。
「ああ、そうみたい。風邪ひいたって」
「風邪とかうける。めずらしー」
ケラケラと彼女は笑いながら、ふと、真剣な眼差しを圭太へと向ける。
「ねえ、今日の放課後ちょっと時間空けてほしいんだけど」
「え、いいけど……なんで?」
「それは……そん時言うよ!」
何故か彼女は頬を赤らめ、自分の席に着いてしまう。
圭太はハテナマークを浮かべながら、自身も席に着くのだった。
それから、いつも通り授業が始まった。
先生もクラスメイトも、とくに何の変わりも無い。
だけど圭太だけは、どこかいつもと違っていた。
それは葵がいないからだ。
休み時間、葵がすぐに話しかけるから一人になることは無かった。
授業中、他愛もないお喋りのお陰で退屈することは無かった。
お昼休み、一人で寂しく弁当を食べることは無かった。
気付けば葵の気配がどこにでもあった。
けれど今、その当人の姿はどこにもない。
「……なんか寂しい、なんて」
窓際にもたれかかりながら、つい呟いてしまう。
今、葵はどうしているだろうか。
熱にうなされて寝ているのか、それともお粥でも食べているのか。
「なんだよ……俺ばっか考えてんじゃん……」
ただ風邪で休んだだけだというのに、何故か圭太の頭の中は葵でいっぱいだった。
そしてなんだかとてつもなく切なかった。
もしかしたら葵も、いつもこんな気持ちだったのかもしれない。
そう思うと、昨日のあの表情の意味もより鮮明に伝わって来る。
「……バカ」
誰に言うでもなく、誰に宛てるでもなく、圭太はそう呟いた。
そんな気持ちを抱えながら放課後を迎えた圭太は、校舎裏であの女子と向き合っていた。
ひと気の無い校舎裏に来て、圭太はようやく、これはまさか、という気持ちになった。
そしてその予想は的中する。
「あのさ、付き合ってる人いる?」
「え……」
「いないなら、付き合ってほしいんだけど」
顔を赤くさせ、直視できないのかやや俯き気味にそう告げる彼女のことを、少なくとも圭太は可愛いと思った。
実際、彼女とは席が近いこともあり、葵と一緒に何かと関わることがあった。
だから圭太は、彼女は葵に好意を寄せているのではないかと思っていたのだ。
それがまさか、自分の方へ好意が向いていたとは……。
「えっ、と俺……」
相手は割とタイプの女子。顔も可愛いし、性格だって合う。
今、圭太の頭の中を埋め尽くしているのは一つのことだった。
「俺……」
そして、圭太は―――。
***
くしゃみを二回繰り返し、葵はヘトヘトとした顔で鼻をすすった。
風邪なんて久しぶりすぎて、どう対処すればいいのか体がわからなくなっている。
「あーあ」
なんとなしにそう呟いて横になる葵の頭の中は、圭太のことでいっぱいだ。
今日圭太は何をしていたのか。自分がいなくてどうだったのか。
自分がいないことで他の友達と喋っているのではないだろうか。
そう考えるだけで嫉妬心がメラメラと燃えてしまい、更に熱が上がるような気になる。
「………」
果たして、圭太は今何を思っているのだろうか。
こんなにも自分は圭太を思っているが、圭太はそうじゃないかもしれないと、そう考えるだけで葵は胸の奥がギュッと切なくなる。
告白して付き合うまでいったのは嬉しかった。
けれど、圭太の気持ちがもしかしたら追い付いてないのではと思うことが度々ある。
圭太には無理してほしくないという気持ちが生まれてしまう。
そうなると、別れた方がいいのだろうかという弱気な感情も生まれてしまう。
別れたくなどない。
圭太を他の誰かに渡すなんて考えたくもない。
だけど圭太を真の意味で嫌な気持ちにはさせたくない。
「圭太……」
今すぐ圭太に会いたいと思った。
圭太はどうだろうか。
圭太は……
「お邪魔します」
不意に聞こえた圭太の声と扉の開く音。
葵はらしくなく、口をぽかんと開けてそちらを見た。
「えっ……圭太?」
「おう」
おずおずとした態度で入室する圭太に、葵は思わず様々な感情が爆発しそうになるのを必死に抑えた。
圭太は何度か葵から視線を反らしつつ、しばらくしてようやく真っ直ぐと葵の方を見た。
「体調……どうなんだ?」
「あ、ああ。だいぶ熱下がったから明日には登校できると思うよ」
「そっか……」
「うん……」
何故だかとても気まずい空気が流れる。
本当はこんな空気にしたくないと、葵は必死に会話の糸口を見つけようと頑張った。
しかしその前に、圭太の方が先に口を開く。
「あのな」
どこか、覚悟を決めたかのような口振りだった。
「実は今日……告白されて」
「……は?」
圭太の言葉に、葵は一気に血の気が引くのを感じた。
告白? 誰に? なんで?
今にも目の前が真っ白になりそうな状態のまま、葵は圭太に何か言おうとする。
「圭太、それって……」
「でもな」
言葉を遮られ、葵は口を紡ぐ。
「でも……なんつーのかな。せっかく告白されたってのに……」
「………」
「考えてるのはおまえのことばっかだった」
「……え」
「なんでかわかんないけど、告白されたらおまえに無性に会いたくなったんだ。だから来た」
照れ臭そうに笑う圭太を前に、葵は言葉を失っていた。
昨日の続きのように、告白を機に別れ話でもされるのかと思っていたのに。
それなのに。
圭太は、確かに葵を選んだのだった。
「この家来るの、一年の頃以来だな」
「……うん」
「葵はなんかさ、すっげーイケメンなくせに、髪の毛の色がコンプレックスだとか言ってたんだよな」
「覚えてるの?」
「なんか思い出してきた。そんで俺、確か葵の髪、褒めたんだっけ」
「うん……それがきっかけで、俺は圭太に恋したんだよ」
「んなっ」
さらりと返され、圭太は一気に顔を赤くさせる。
そんな圭太を、葵は、いつも以上に愛しく見つめていた。
「ねえ圭太」
「な、なんだよ」
「俺たちで。キスしてみようよ」
「………」
あの日、あの時の言葉を、葵は再び口にした。
葵の微笑混じりの真剣な眼差し。
圭太は顔を赤くさせたまま……それでもゆっくりと葵に近付いた。
「圭太……」
「葵……」
そうして触れる唇は、思った以上に熱かった。
手が重なり、指先が絡み合う。
「好き……好きだよ、圭太……」
「……俺も」
消え入りそうなぐらい小さな声で、圭太はそう返した。
それが死ぬほど嬉しくて……葵は圭太を強く抱き締める。
「だぁああああ、暑苦しいってバカ!」
「あははっ、絶対離さないよー」
そこには、夏の熱さに浮かされた幸せそうなカップルがいた。
葵も圭太も、しばらく抱き合い、そうしてキスを繰り返すのだった。
ちなみに。
次の日、圭太が風邪をひいてしまうのはまた別のお話。
【完】
「……お、おはよ」
本日も蝉の大合唱がうるさい中、二人は挨拶を交わす。
鷺宮葵はいつも通りに。
紺堂圭太はやや慌てながら。
「圭太、もしかして意識してる?」
そうであることがバレバレでありながらも、葵は意地悪く圭太にそう訊ねた。
当然圭太は、ビクリと肩を動かした。
「べ、別にそんなことないし……!」
「ふぅん」
葵はニコニコと笑いながら圭太を見つめた。
正直、葵だって表に出さないだけで意識している。
ずっと想い人だった圭太と付き合い始めたのだ。意識しないわけがない。
葵にとって、圭太は夏の太陽のように眩しく、キラキラとした存在だった。圭太本人は自分を陰に潜むオタクなどと卑下しているが、葵から見ればずっと眩しく輝く憧れの想い人だったのだ。
そんな圭太と今、ようやく結ばれることができた。
だから圭太とは違い、葵はとても浮かれていた。
そんな浮かれ具合から出てくる笑顔がいつも以上に魅力的だからか、傍で葵を盗み見ていた女子がキャーキャーと騒ぎ立てている。
当人は全くその子たちを眼中に入れていないのだが。
「ねえ圭太。今日はお昼、視聴覚室で食べようよ」
あえて圭太の耳元で、葵は囁く。
圭太は勢いよく振り返り、真っ赤になった耳を抑えながら言葉を返した。
「なんでだよ? ってか視聴覚室って授業以外で使っていいんだっけ?」
「そこは俺が鍵借りとくからさ。冷房も付いてるし、何より……二人っきりになれるでしょ?」
「ばっ……」
馬鹿野郎、と言いたかったであろう圭太は、しかし声の大きさで人目を集めかけていることに気付き、なんとか言葉を飲み込む。
代わりにジト目で葵を睨み返し、席に着く。
そんな圭太を可愛いと思いながら、葵も席に着くのだった。
そうして迎えた昼休み。
冷房の効いた視聴覚室は、静けさで満たされている。
ドア一枚隔てた廊下側から聞こえる生徒たちの立てる音が、ハッキリと聞こえるぐらいに静かだ。
「ん……」
そんな静けさの中で、二つの吐息が密かに混じっていた。
普通に談笑しながらお昼を食べ終えた途端、葵が圭太にキスをねだったのだ。
最初は拒否していた圭太だったが、葵の懇願に負け、こうしてキスを受け入れることとなる。
「葵……もう……んっ」
「もうちょっと……もうちょっとだけ……」
唇が触れるだけのキスではあるが、それはとても官能的で熱を帯びていた。
重ね合った指先が、互いの体温を交換しているように熱い。
小さく響くリップ音。絡みつく吐息。窓の外の蝉の合唱。廊下から聞こえてくる生徒たちの声。
そのどれもが、二人を煽り、ドキドキと鼓動を早くさせた。
「ん、ん……」
「圭太……」
そうしてしばし沈黙が続き……ようやく、葵の方から圭太と距離を取る。
「……もうやめろって言ったのに」
眼鏡の位置を直しながら、圭太は不満を口にする。
口を尖らせるその姿に、葵は愛おしさを感じた。
「だってキスした時にしか見れない顔するから、もっと見たくて……」
「……っ」
恥ずかしいことを臆面もなく言ってくる葵に、逆に顔を赤くする圭太。
葵からの視線はいつも煽情的だ。
告白されてから、ようやくその視線が、いつも強く自分に絡みついていたことを圭太は知った。
「そろそろ……昼休み、終わる」
「そうだね」
葵からの熱視線に耐えられず、圭太は目を反らし、空になった弁当箱を片付ける。
すると、少し間を開けて葵が言葉を発した。
「……ねえ圭太」
「んー?」
「俺だけが圭太のことを好きなら……その時は別れていいからね」
「んなっ」
いきなりの言葉に、思わず圭太は葵の方を向く。
葵は、アンニュイな微笑を浮かべながら、それでもなお愛おしそうに圭太を見つめていた。
なんだかその表情があまりにも切なくて、圭太は一人慌てた。
「なんだよいきなり。好きだの別れていいだの……わけわかんないよ」
「ははっ、ごめんごめん。俺、圭太のこと本当に好きだから……だからこそ圭太を困らせたくないんだよね」
「べつに、困ってなんか……」
「そ? それなら良かった」
そうは言いつつも、葵の表情はどこか切なげだ。
「葵……」
圭太がその名を口にするのと同時に、お昼休みを終えるチャイムが鳴り響いた。
「よし、バレる前に教室戻ろっか」
「お、おう……」
まだ話したいことがあったような、しかしいざ葵を前にしたら何て言ったらいいのかわからなくなった圭太は、流されるように立ち上がった。
モヤモヤとした気持ちを抱えたまま、圭太は葵の後を続き、視聴覚室を出るのだった。
***
『風邪ひいた、今日は休む』
次の日。
教室に着いたのを見計らったかのようなタイミングで、葵からそんな連絡が来ていた。
三年になってから葵が欠席するのを見たことは一度も無く、珍しいなとさえ思えた。
「………」
その一方で、昨日の昼休みでの出来事が圭太の脳裏に浮かぶ。
まさかあれを気にしてだろうか。
そんな気持ちが脳裏に渦巻く。
あの後、圭太だって様々なことを考えた。
葵の強烈な好きという感情に流されているだけなのではないか。果たして本気で葵のことが好きなのか。
男同士で付き合うということを、ちゃんとわかっていないんじゃないか。
本当に本当に、色々と考えた。
むしろ知恵熱が出そうで休みたいのはこっちの方だ、と圭太は心の中で葵に愚痴る。
「今日、葵くんお休みー?」
席の近い女子が、気さくな感じでそう訊ねてきた。
葵の隣の席なのもあって、よく葵と喋っている女子だ。
「ああ、そうみたい。風邪ひいたって」
「風邪とかうける。めずらしー」
ケラケラと彼女は笑いながら、ふと、真剣な眼差しを圭太へと向ける。
「ねえ、今日の放課後ちょっと時間空けてほしいんだけど」
「え、いいけど……なんで?」
「それは……そん時言うよ!」
何故か彼女は頬を赤らめ、自分の席に着いてしまう。
圭太はハテナマークを浮かべながら、自身も席に着くのだった。
それから、いつも通り授業が始まった。
先生もクラスメイトも、とくに何の変わりも無い。
だけど圭太だけは、どこかいつもと違っていた。
それは葵がいないからだ。
休み時間、葵がすぐに話しかけるから一人になることは無かった。
授業中、他愛もないお喋りのお陰で退屈することは無かった。
お昼休み、一人で寂しく弁当を食べることは無かった。
気付けば葵の気配がどこにでもあった。
けれど今、その当人の姿はどこにもない。
「……なんか寂しい、なんて」
窓際にもたれかかりながら、つい呟いてしまう。
今、葵はどうしているだろうか。
熱にうなされて寝ているのか、それともお粥でも食べているのか。
「なんだよ……俺ばっか考えてんじゃん……」
ただ風邪で休んだだけだというのに、何故か圭太の頭の中は葵でいっぱいだった。
そしてなんだかとてつもなく切なかった。
もしかしたら葵も、いつもこんな気持ちだったのかもしれない。
そう思うと、昨日のあの表情の意味もより鮮明に伝わって来る。
「……バカ」
誰に言うでもなく、誰に宛てるでもなく、圭太はそう呟いた。
そんな気持ちを抱えながら放課後を迎えた圭太は、校舎裏であの女子と向き合っていた。
ひと気の無い校舎裏に来て、圭太はようやく、これはまさか、という気持ちになった。
そしてその予想は的中する。
「あのさ、付き合ってる人いる?」
「え……」
「いないなら、付き合ってほしいんだけど」
顔を赤くさせ、直視できないのかやや俯き気味にそう告げる彼女のことを、少なくとも圭太は可愛いと思った。
実際、彼女とは席が近いこともあり、葵と一緒に何かと関わることがあった。
だから圭太は、彼女は葵に好意を寄せているのではないかと思っていたのだ。
それがまさか、自分の方へ好意が向いていたとは……。
「えっ、と俺……」
相手は割とタイプの女子。顔も可愛いし、性格だって合う。
今、圭太の頭の中を埋め尽くしているのは一つのことだった。
「俺……」
そして、圭太は―――。
***
くしゃみを二回繰り返し、葵はヘトヘトとした顔で鼻をすすった。
風邪なんて久しぶりすぎて、どう対処すればいいのか体がわからなくなっている。
「あーあ」
なんとなしにそう呟いて横になる葵の頭の中は、圭太のことでいっぱいだ。
今日圭太は何をしていたのか。自分がいなくてどうだったのか。
自分がいないことで他の友達と喋っているのではないだろうか。
そう考えるだけで嫉妬心がメラメラと燃えてしまい、更に熱が上がるような気になる。
「………」
果たして、圭太は今何を思っているのだろうか。
こんなにも自分は圭太を思っているが、圭太はそうじゃないかもしれないと、そう考えるだけで葵は胸の奥がギュッと切なくなる。
告白して付き合うまでいったのは嬉しかった。
けれど、圭太の気持ちがもしかしたら追い付いてないのではと思うことが度々ある。
圭太には無理してほしくないという気持ちが生まれてしまう。
そうなると、別れた方がいいのだろうかという弱気な感情も生まれてしまう。
別れたくなどない。
圭太を他の誰かに渡すなんて考えたくもない。
だけど圭太を真の意味で嫌な気持ちにはさせたくない。
「圭太……」
今すぐ圭太に会いたいと思った。
圭太はどうだろうか。
圭太は……
「お邪魔します」
不意に聞こえた圭太の声と扉の開く音。
葵はらしくなく、口をぽかんと開けてそちらを見た。
「えっ……圭太?」
「おう」
おずおずとした態度で入室する圭太に、葵は思わず様々な感情が爆発しそうになるのを必死に抑えた。
圭太は何度か葵から視線を反らしつつ、しばらくしてようやく真っ直ぐと葵の方を見た。
「体調……どうなんだ?」
「あ、ああ。だいぶ熱下がったから明日には登校できると思うよ」
「そっか……」
「うん……」
何故だかとても気まずい空気が流れる。
本当はこんな空気にしたくないと、葵は必死に会話の糸口を見つけようと頑張った。
しかしその前に、圭太の方が先に口を開く。
「あのな」
どこか、覚悟を決めたかのような口振りだった。
「実は今日……告白されて」
「……は?」
圭太の言葉に、葵は一気に血の気が引くのを感じた。
告白? 誰に? なんで?
今にも目の前が真っ白になりそうな状態のまま、葵は圭太に何か言おうとする。
「圭太、それって……」
「でもな」
言葉を遮られ、葵は口を紡ぐ。
「でも……なんつーのかな。せっかく告白されたってのに……」
「………」
「考えてるのはおまえのことばっかだった」
「……え」
「なんでかわかんないけど、告白されたらおまえに無性に会いたくなったんだ。だから来た」
照れ臭そうに笑う圭太を前に、葵は言葉を失っていた。
昨日の続きのように、告白を機に別れ話でもされるのかと思っていたのに。
それなのに。
圭太は、確かに葵を選んだのだった。
「この家来るの、一年の頃以来だな」
「……うん」
「葵はなんかさ、すっげーイケメンなくせに、髪の毛の色がコンプレックスだとか言ってたんだよな」
「覚えてるの?」
「なんか思い出してきた。そんで俺、確か葵の髪、褒めたんだっけ」
「うん……それがきっかけで、俺は圭太に恋したんだよ」
「んなっ」
さらりと返され、圭太は一気に顔を赤くさせる。
そんな圭太を、葵は、いつも以上に愛しく見つめていた。
「ねえ圭太」
「な、なんだよ」
「俺たちで。キスしてみようよ」
「………」
あの日、あの時の言葉を、葵は再び口にした。
葵の微笑混じりの真剣な眼差し。
圭太は顔を赤くさせたまま……それでもゆっくりと葵に近付いた。
「圭太……」
「葵……」
そうして触れる唇は、思った以上に熱かった。
手が重なり、指先が絡み合う。
「好き……好きだよ、圭太……」
「……俺も」
消え入りそうなぐらい小さな声で、圭太はそう返した。
それが死ぬほど嬉しくて……葵は圭太を強く抱き締める。
「だぁああああ、暑苦しいってバカ!」
「あははっ、絶対離さないよー」
そこには、夏の熱さに浮かされた幸せそうなカップルがいた。
葵も圭太も、しばらく抱き合い、そうしてキスを繰り返すのだった。
ちなみに。
次の日、圭太が風邪をひいてしまうのはまた別のお話。
【完】