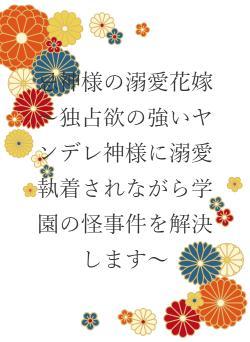「俺は好きだけどね、その髪の色」
たぶん彼からのその一言が、その後の俺を決定付けたと言っても過言ではない。
高校一年の頃、持病の所為で何かと休みがちだった所為で、クラスの連中から何かと好き勝手言われることが多かった。
とくに生まれつき髪の色素が薄いため、そのことを中心にチャラいだの、女遊び激しそうだの、本当に勝手な噂が流された時もあった。
それもあって俺はますます学校に行きたくなくなる始末だった。
だけどある時から、同じクラスの子が俺の家までプリントを届けに来てくれるようになった。
いつもいつも届けてくれるので、一度、母さんがその子を家に上げるよう言った。
そこで俺は対面する。
紺堂圭太に。
彼は凄く緊張した面持ちでウチのリビングのソファに座り、母さんに何か話しかけられる度にビクビクとした反応を示していた。
なんだかそれが、小動物みたいで可愛かったのを覚えている。
それで、母さんが少し席を外している時に、俺からも直接お礼を言ったのだ。
いつもありがとう、とか。髪の色や噂されていることに対する自虐めいたことまで。
そうしたら彼は言ったのだ。
「俺は好きだけどね、その髪の色」
「え……」
「い、いや、なんでもない」
彼はすぐに撤回してみせたが、俺の耳にはしっかりとその言葉は届いていた。
たぶん、そう……これが始まりだった。
圭太に対する恋心は、ここから始まった。
二年生になって、俺は圭太とクラスが離れてしまったことを内心とても嘆いていた。
その代わり、一年生の時の自分とは変わろうと思い奮起した。
それが功を成したのかはわからないが、あれだけいじられていた色素の薄い髪はモテるアイテムへと変わっていた。
周りの俺への扱いも変わり、何かと頼られたり、グループに入るよう言われたりと忙しかった。
女子生徒から告白されることも多々あった。
付き合っちゃおっか、という軽めなものから、真剣な告白まで。
でも俺は、その全てを断った。
何故ならそういった告白を受ける度に、頭に浮かぶのは圭太の姿だったからだ。
だから教室の移動中や、窓際から見える体育の時間……圭太の姿が視界に入る度に、俺はいつだって一人でドキドキしていた。
圭太はいつも、同じメンツで集まって楽しそうにしている。それが俺はとても羨ましくてたまらなかった。
俺も圭太と同じクラスになりたい。同じクラスになったら、片時も圭太から離れない。
そんな俺の願いが届いたのか、三年生に上がり、ようやく俺は圭太と同じクラスになった。
喜びでついつい顔が緩んでいた俺の視界には、肩を落とす圭太の姿が。
圭太はいつものメンツとは違うクラスになったのだ。圭太からすれば最悪だろうが、俺からすれば最高のクラス分けだった。
だから俺から声をかけたのだ。
「紺堂くん。一緒のクラスだね」
危うく圭太と呼びそうになり、少しだけ咳払い。
圭太は俺から声をかけられたことに非常に驚いた様子だった。
「あ、あー……そう、みたいだね」
「また一緒のクラスになりたいと思ってたんだ。良かったよ」
「そ、そう」
「良ければ一緒にクラス行こうよ」
「え、まあ、うん」
なんともぎこちないその態度がとても可愛い。
そのくせ、俺の髪色を好きだと言ってくれた時はとても格好良かった。
なんだろう圭太って……ギャップ萌え?
「あの、なんで俺なの?」
「え?」
圭太の事ばかり考えていたから、不意のその質問の意図に最初は頭が回らなかった。
「いやだってさ、他にも友達いるだろ?」
なんだ、そんなことか……と思った。
他の友達より、圭太が大事だからだよ……なんていきなり言ったら引かれるだろうから、気を付けよう。
「さっきも言ったじゃん。また一緒のクラスになりたかったんだって」
「でも俺たち、そんな接点無かったし……」
「一年の時、プリント届けてくれたでしょ。あれ、嬉しかったんだ、凄く」
「………」
圭太は唖然とした後、恥ずかしさからかそっぽを向いてしまった。
行動の一つ一つが面白くて、見ているだけで楽しい。
二年生の時はできなかったことができているんだと思うと、それだけでワクワクした。
「よ、よ、よく覚えてるな……二年も前のこと」
「覚えてるよ。俺にとってはありがたいことだったし……何より、紺堂くんのあの一言にすっごく救われたからなぁ」
「あの一言? あの一言って?」
食いついてくる圭太に教えてあげたい気持ちと、意地悪したい気持ちの両方が浮かんだ。
それに、圭太からのあの一言は、俺にとって本当に大切な宝物だ。
だから俺は答えた。
「んー……秘密」
「なんでだよ。俺が言ったのに」
「まあまあ、いつか思い出すよ」
少し不貞腐れる圭太がやっぱり可愛くて、俺はケラケラと笑い声を上げた。
作り笑いじゃなく、心からこうして笑うのはいつ振りだろう。
少なくとも二年生の時は、学校でこんなふうに笑ってはいなかったと思う。
ああ。やっぱり好きだな、圭太が。
圭太といると安心する。
圭太には悪いけど、これまで圭太が一緒だったメンツとクラスが別れて良かったと心から思う。圭太を独り占めにできるから。
これからの一年間で、俺は圭太との距離をずっとずっと縮めていきたいと思う。
「じゃあ、俺、席に着くから。じゃあな」
そんな俺に対し、圭太は実にクールなことを言ってきた。
きっと圭太的には、俺がただの気まぐれで声をかけてきたと思っているんだろうなぁ。
俺の一年以上も燻ぶられた恋心をなめないでほしい。
「って言っても、俺たち席の順番前後だけどね」
そもそも圭太はそのことに気付いていないようだった。
名前順だと俺たちは、席順が前後なのだ。
「へ?」
「短い別れだったね」
「……っ」
本当に、圭太といると楽しい。
なんていうか、圭太はいつも真っ直ぐだ。
一つのことに対して、何でも真面目に取り合ってくれる。
だから俺はそんな圭太が好きだ。大好きだ。
「ねえ。圭太って呼んでいい?」
「はい?」
名前で呼ばれたからか、圭太が耳を赤くしているのを俺は見逃さなかった。
でもかく言う俺も、実際にその名を口にしたのは初めてで……ドキドキと高鳴る心音がバレていないか不安になった。
「いや……その……」
「俺のことも葵って呼んでいいからさ」
そうして圭太が恥ずかしさで顔を背けながらも一つ頷いたのを見て、俺は心が熱くなるのを感じた。
それから、俺はできるだけ圭太の傍に居ることにした。
授業中は前後の席だし、休み時間も、お昼の時間も、できるだけ、ずっと。
圭太が席を外していると、たまに他の男子グループや女子たちに呼ばれてそちらに行くこともあった。
だけど圭太が帰ってきたら、俺はすぐに圭太の元へ行く。
ある時に圭太から、さっきまで俺がいたグループの方へ戻らなくていいのかと言われた。
だからハッキリと、圭太といたいと告げた。
その時の圭太の照れ顔は凄く眩しくて、もっともっと見ていたいと感じるぐらいだった。
圭太への独占欲が日に日に増していくことに俺は気付いている。
たまに圭太が、違うクラスの友人のところや、美術部の後輩に会いに行っていることを俺は知っていた。それだけで強い嫉妬心が俺の心を焼いた。
圭太に近付く男も女もいなければいいのに、なんて。
子供のような駄々を心の中でこねてしまう。
そんなことを考えている内に、いつの間にか夏は来てしまった。
受験生の夏だ。やることも考えることもたくさんあるのに。
なのに俺の頭の中は、圭太のことでいっぱいだった。
いい加減、圭太にこの想いを伝えたいという気持ちがある。
でも、どうやって。
どうやって圭太と恋を始めればいいのだろう。
とりあえずそれも、圭太を前にしなければ始まらないことだ。
だから俺は今日も、圭太の居る美術室のドアを開ける。
「あー、居た居た」
圭太が居る場所といえば、大抵教室かこの美術室だ。
当たりだったようで、白いキャンバスを広げ、その前に座る圭太の姿があった。
「なんだよ」
「今日部活無い日でしょ? だから一緒に帰ろうと思ってたのに居ないからさ、探した」
前は美術室に乗り込む俺に、少し警戒心を見せることがあった。
圭太っぽく言うなら、オタク以外が俺のテリトリーに入って来るな、みたいな。
でもこうして何度も圭太のテリトリーに上がり込んだ甲斐あって、今では何の警戒も見せてこない。
俺にだけ見せる、圭太の無防備でリラックスした姿。
それがたまらなく好きだった。
「何描くの?」
「まだ決めてない」
「時期的に卒業制作とか?」
「まあ、そうなる」
「ってことは、締め切りやばいんじゃ……」
「うっさい。そうだよ。だから一人で居残ってんの」
「あははは」
やっぱり真っ直ぐ反応を示す圭太を前にすると、凄く楽しい気持ちになる。
いつまでもこの時間を過ごしていたくなるんだ。
「ずーっと無心でキャンバスとにらめっこしてたの?」
鞄を近くの机の上に置きながら、窓の外をチラリと見る。
校庭では今日もサッカー部が熱い中頑張っていた。
「無心じゃないけど……」
「ふーん。何考えてた? 受験のこと?」
俺の言葉が図星だからか、一瞬圭太は口を紡ぐ。
しかし、その後に続いた言葉は俺の予想通りではなかった。
「それもあるけど……あとは彼女とか」
「……彼女?」
思わず、いつもより低いトーンで訊き返してしまった。
俺は、一気にざわついた心に焦りを感じ始める。
彼女……彼女って、圭太が?
俺が知る限り、圭太にはそういう相手はいないと思っていた。
いや、いるわけない。
圭太に彼女ができてしまわないよう、俺は四六時中、圭太の傍にいたのだから。
それともまさか、学校以外の人だというのだろうか。
落ち着かない俺を余所に、圭太は言葉を続ける。
「いや、つーか、恋愛とかそういうの無かったな、って」
そこで俺は、圭太が何を言いたかったのか理解した。
理解はした……が、それでも俺は口元に手を当てて考え込む。
圭太が恋愛を意識するようになっている。
それはいいことだけど……でもその相手が俺じゃないのは嫌だ。
いつまでも、俺だけの圭太でいてほしい。
圭太には、いつだって俺の隣にいてほしい。
いつも以上に心臓が高鳴って落ち着かない。
これまで溜めてきた感情が、洪水のようになって吐き出されていくのがわかった。
「な、なんだよ……」
あまりにも真剣な表情で見詰め過ぎたからか、圭太が少し引いている。
もう、この際どうとでもなれという気持ちになった俺は、ある一つの提案を持ちかけてみた。
「……してみる?」
「え?」
「キスしてみる?」
空白。
蝉の鳴き声が鼓膜を揺さぶり、校庭から聞こえてくるサッカー部の声が響き渡った。
圭太はしばしフリーズした後、ハッと我に返る。
「……はい? 何が? 誰が?」
「俺たちで。キスしてみようよ」
ゆっくりと、俺は圭太に近付く。
圭太は目を見開いて固まっている。
逆に俺の方は、凄く冷静に、熱い思いが爆発するのを感じた。
この三年間燻ぶらせた感情が、一気に解き放たれるような、そんな感覚。
あ、柔らかい。
気付いた時にはもう、俺の唇は圭太の唇に触れていて、そこで初めて心臓がドクリと揺れた。
「ん……」
吐息混じりの圭太の声に、俺は下腹部が疼くのを感じる。
あんまり変な声を出されると、キスだけじゃ止まらなくなりそうだ。
そんなことを考えていたら、先に圭太の方が動き出した。
「ばっ……だぁああああ!」
まるで芸人のオーバーリアクションのような反応を示し、圭太はそのまま椅子から転げ落ちた。
「なんっ、な、なん、で……」
「大丈夫? 頭打ってない?」
焦る圭太の反応を見て、そこでようやく血の気が引いてきた。
俺は何をしてしまったんだろう。
勢い任せとはいえ、こんなの引かれたに決まってる。
何なら、もう友達としても駄目になったかもしれない。
次に圭太が何を言うのか……それを考えただけで、俺は冷や汗が止まらなかった。
しかし。
「ってかいきなりキスってなんだよ! 普通、あ、あれだろ……手を繋ぐとかさぁ!」
「手……」
「告白とか、そもそも付き合ってからだろキスってやつは!」
沈黙。
目を丸くするとはこのことか。
拒絶されると思ったのに、そうじゃないんだ。
圭太が、俺を拒絶しなかった。
それどころか凄く可愛いことを言ってくる。
泣きたくなるほど嬉しくて、俺は思わず破顔した。
「ぷっ、あはははは!」
「わ、笑うなよ……!」
「ごめんごめん。可愛いなって思って」
「うううるせぇ!」
「ごめん、って。それに……」
俺は非常に繊細な手付きで、圭太の指に自身の指を絡めた。
確かに、キスよりも先に手を繋ぐ必要もあったかもしれない。
だって恋人繋ぎをするだけで、こんなにもドキドキするのだから。
「順番、おかしくなってごめんね」
「は、はい……?」
「圭太。俺と付き合ってください」
俺の髪色を好きだと言ってくれた時から始まった恋心が、ようやく成就した夏だった。
たぶん彼からのその一言が、その後の俺を決定付けたと言っても過言ではない。
高校一年の頃、持病の所為で何かと休みがちだった所為で、クラスの連中から何かと好き勝手言われることが多かった。
とくに生まれつき髪の色素が薄いため、そのことを中心にチャラいだの、女遊び激しそうだの、本当に勝手な噂が流された時もあった。
それもあって俺はますます学校に行きたくなくなる始末だった。
だけどある時から、同じクラスの子が俺の家までプリントを届けに来てくれるようになった。
いつもいつも届けてくれるので、一度、母さんがその子を家に上げるよう言った。
そこで俺は対面する。
紺堂圭太に。
彼は凄く緊張した面持ちでウチのリビングのソファに座り、母さんに何か話しかけられる度にビクビクとした反応を示していた。
なんだかそれが、小動物みたいで可愛かったのを覚えている。
それで、母さんが少し席を外している時に、俺からも直接お礼を言ったのだ。
いつもありがとう、とか。髪の色や噂されていることに対する自虐めいたことまで。
そうしたら彼は言ったのだ。
「俺は好きだけどね、その髪の色」
「え……」
「い、いや、なんでもない」
彼はすぐに撤回してみせたが、俺の耳にはしっかりとその言葉は届いていた。
たぶん、そう……これが始まりだった。
圭太に対する恋心は、ここから始まった。
二年生になって、俺は圭太とクラスが離れてしまったことを内心とても嘆いていた。
その代わり、一年生の時の自分とは変わろうと思い奮起した。
それが功を成したのかはわからないが、あれだけいじられていた色素の薄い髪はモテるアイテムへと変わっていた。
周りの俺への扱いも変わり、何かと頼られたり、グループに入るよう言われたりと忙しかった。
女子生徒から告白されることも多々あった。
付き合っちゃおっか、という軽めなものから、真剣な告白まで。
でも俺は、その全てを断った。
何故ならそういった告白を受ける度に、頭に浮かぶのは圭太の姿だったからだ。
だから教室の移動中や、窓際から見える体育の時間……圭太の姿が視界に入る度に、俺はいつだって一人でドキドキしていた。
圭太はいつも、同じメンツで集まって楽しそうにしている。それが俺はとても羨ましくてたまらなかった。
俺も圭太と同じクラスになりたい。同じクラスになったら、片時も圭太から離れない。
そんな俺の願いが届いたのか、三年生に上がり、ようやく俺は圭太と同じクラスになった。
喜びでついつい顔が緩んでいた俺の視界には、肩を落とす圭太の姿が。
圭太はいつものメンツとは違うクラスになったのだ。圭太からすれば最悪だろうが、俺からすれば最高のクラス分けだった。
だから俺から声をかけたのだ。
「紺堂くん。一緒のクラスだね」
危うく圭太と呼びそうになり、少しだけ咳払い。
圭太は俺から声をかけられたことに非常に驚いた様子だった。
「あ、あー……そう、みたいだね」
「また一緒のクラスになりたいと思ってたんだ。良かったよ」
「そ、そう」
「良ければ一緒にクラス行こうよ」
「え、まあ、うん」
なんともぎこちないその態度がとても可愛い。
そのくせ、俺の髪色を好きだと言ってくれた時はとても格好良かった。
なんだろう圭太って……ギャップ萌え?
「あの、なんで俺なの?」
「え?」
圭太の事ばかり考えていたから、不意のその質問の意図に最初は頭が回らなかった。
「いやだってさ、他にも友達いるだろ?」
なんだ、そんなことか……と思った。
他の友達より、圭太が大事だからだよ……なんていきなり言ったら引かれるだろうから、気を付けよう。
「さっきも言ったじゃん。また一緒のクラスになりたかったんだって」
「でも俺たち、そんな接点無かったし……」
「一年の時、プリント届けてくれたでしょ。あれ、嬉しかったんだ、凄く」
「………」
圭太は唖然とした後、恥ずかしさからかそっぽを向いてしまった。
行動の一つ一つが面白くて、見ているだけで楽しい。
二年生の時はできなかったことができているんだと思うと、それだけでワクワクした。
「よ、よ、よく覚えてるな……二年も前のこと」
「覚えてるよ。俺にとってはありがたいことだったし……何より、紺堂くんのあの一言にすっごく救われたからなぁ」
「あの一言? あの一言って?」
食いついてくる圭太に教えてあげたい気持ちと、意地悪したい気持ちの両方が浮かんだ。
それに、圭太からのあの一言は、俺にとって本当に大切な宝物だ。
だから俺は答えた。
「んー……秘密」
「なんでだよ。俺が言ったのに」
「まあまあ、いつか思い出すよ」
少し不貞腐れる圭太がやっぱり可愛くて、俺はケラケラと笑い声を上げた。
作り笑いじゃなく、心からこうして笑うのはいつ振りだろう。
少なくとも二年生の時は、学校でこんなふうに笑ってはいなかったと思う。
ああ。やっぱり好きだな、圭太が。
圭太といると安心する。
圭太には悪いけど、これまで圭太が一緒だったメンツとクラスが別れて良かったと心から思う。圭太を独り占めにできるから。
これからの一年間で、俺は圭太との距離をずっとずっと縮めていきたいと思う。
「じゃあ、俺、席に着くから。じゃあな」
そんな俺に対し、圭太は実にクールなことを言ってきた。
きっと圭太的には、俺がただの気まぐれで声をかけてきたと思っているんだろうなぁ。
俺の一年以上も燻ぶられた恋心をなめないでほしい。
「って言っても、俺たち席の順番前後だけどね」
そもそも圭太はそのことに気付いていないようだった。
名前順だと俺たちは、席順が前後なのだ。
「へ?」
「短い別れだったね」
「……っ」
本当に、圭太といると楽しい。
なんていうか、圭太はいつも真っ直ぐだ。
一つのことに対して、何でも真面目に取り合ってくれる。
だから俺はそんな圭太が好きだ。大好きだ。
「ねえ。圭太って呼んでいい?」
「はい?」
名前で呼ばれたからか、圭太が耳を赤くしているのを俺は見逃さなかった。
でもかく言う俺も、実際にその名を口にしたのは初めてで……ドキドキと高鳴る心音がバレていないか不安になった。
「いや……その……」
「俺のことも葵って呼んでいいからさ」
そうして圭太が恥ずかしさで顔を背けながらも一つ頷いたのを見て、俺は心が熱くなるのを感じた。
それから、俺はできるだけ圭太の傍に居ることにした。
授業中は前後の席だし、休み時間も、お昼の時間も、できるだけ、ずっと。
圭太が席を外していると、たまに他の男子グループや女子たちに呼ばれてそちらに行くこともあった。
だけど圭太が帰ってきたら、俺はすぐに圭太の元へ行く。
ある時に圭太から、さっきまで俺がいたグループの方へ戻らなくていいのかと言われた。
だからハッキリと、圭太といたいと告げた。
その時の圭太の照れ顔は凄く眩しくて、もっともっと見ていたいと感じるぐらいだった。
圭太への独占欲が日に日に増していくことに俺は気付いている。
たまに圭太が、違うクラスの友人のところや、美術部の後輩に会いに行っていることを俺は知っていた。それだけで強い嫉妬心が俺の心を焼いた。
圭太に近付く男も女もいなければいいのに、なんて。
子供のような駄々を心の中でこねてしまう。
そんなことを考えている内に、いつの間にか夏は来てしまった。
受験生の夏だ。やることも考えることもたくさんあるのに。
なのに俺の頭の中は、圭太のことでいっぱいだった。
いい加減、圭太にこの想いを伝えたいという気持ちがある。
でも、どうやって。
どうやって圭太と恋を始めればいいのだろう。
とりあえずそれも、圭太を前にしなければ始まらないことだ。
だから俺は今日も、圭太の居る美術室のドアを開ける。
「あー、居た居た」
圭太が居る場所といえば、大抵教室かこの美術室だ。
当たりだったようで、白いキャンバスを広げ、その前に座る圭太の姿があった。
「なんだよ」
「今日部活無い日でしょ? だから一緒に帰ろうと思ってたのに居ないからさ、探した」
前は美術室に乗り込む俺に、少し警戒心を見せることがあった。
圭太っぽく言うなら、オタク以外が俺のテリトリーに入って来るな、みたいな。
でもこうして何度も圭太のテリトリーに上がり込んだ甲斐あって、今では何の警戒も見せてこない。
俺にだけ見せる、圭太の無防備でリラックスした姿。
それがたまらなく好きだった。
「何描くの?」
「まだ決めてない」
「時期的に卒業制作とか?」
「まあ、そうなる」
「ってことは、締め切りやばいんじゃ……」
「うっさい。そうだよ。だから一人で居残ってんの」
「あははは」
やっぱり真っ直ぐ反応を示す圭太を前にすると、凄く楽しい気持ちになる。
いつまでもこの時間を過ごしていたくなるんだ。
「ずーっと無心でキャンバスとにらめっこしてたの?」
鞄を近くの机の上に置きながら、窓の外をチラリと見る。
校庭では今日もサッカー部が熱い中頑張っていた。
「無心じゃないけど……」
「ふーん。何考えてた? 受験のこと?」
俺の言葉が図星だからか、一瞬圭太は口を紡ぐ。
しかし、その後に続いた言葉は俺の予想通りではなかった。
「それもあるけど……あとは彼女とか」
「……彼女?」
思わず、いつもより低いトーンで訊き返してしまった。
俺は、一気にざわついた心に焦りを感じ始める。
彼女……彼女って、圭太が?
俺が知る限り、圭太にはそういう相手はいないと思っていた。
いや、いるわけない。
圭太に彼女ができてしまわないよう、俺は四六時中、圭太の傍にいたのだから。
それともまさか、学校以外の人だというのだろうか。
落ち着かない俺を余所に、圭太は言葉を続ける。
「いや、つーか、恋愛とかそういうの無かったな、って」
そこで俺は、圭太が何を言いたかったのか理解した。
理解はした……が、それでも俺は口元に手を当てて考え込む。
圭太が恋愛を意識するようになっている。
それはいいことだけど……でもその相手が俺じゃないのは嫌だ。
いつまでも、俺だけの圭太でいてほしい。
圭太には、いつだって俺の隣にいてほしい。
いつも以上に心臓が高鳴って落ち着かない。
これまで溜めてきた感情が、洪水のようになって吐き出されていくのがわかった。
「な、なんだよ……」
あまりにも真剣な表情で見詰め過ぎたからか、圭太が少し引いている。
もう、この際どうとでもなれという気持ちになった俺は、ある一つの提案を持ちかけてみた。
「……してみる?」
「え?」
「キスしてみる?」
空白。
蝉の鳴き声が鼓膜を揺さぶり、校庭から聞こえてくるサッカー部の声が響き渡った。
圭太はしばしフリーズした後、ハッと我に返る。
「……はい? 何が? 誰が?」
「俺たちで。キスしてみようよ」
ゆっくりと、俺は圭太に近付く。
圭太は目を見開いて固まっている。
逆に俺の方は、凄く冷静に、熱い思いが爆発するのを感じた。
この三年間燻ぶらせた感情が、一気に解き放たれるような、そんな感覚。
あ、柔らかい。
気付いた時にはもう、俺の唇は圭太の唇に触れていて、そこで初めて心臓がドクリと揺れた。
「ん……」
吐息混じりの圭太の声に、俺は下腹部が疼くのを感じる。
あんまり変な声を出されると、キスだけじゃ止まらなくなりそうだ。
そんなことを考えていたら、先に圭太の方が動き出した。
「ばっ……だぁああああ!」
まるで芸人のオーバーリアクションのような反応を示し、圭太はそのまま椅子から転げ落ちた。
「なんっ、な、なん、で……」
「大丈夫? 頭打ってない?」
焦る圭太の反応を見て、そこでようやく血の気が引いてきた。
俺は何をしてしまったんだろう。
勢い任せとはいえ、こんなの引かれたに決まってる。
何なら、もう友達としても駄目になったかもしれない。
次に圭太が何を言うのか……それを考えただけで、俺は冷や汗が止まらなかった。
しかし。
「ってかいきなりキスってなんだよ! 普通、あ、あれだろ……手を繋ぐとかさぁ!」
「手……」
「告白とか、そもそも付き合ってからだろキスってやつは!」
沈黙。
目を丸くするとはこのことか。
拒絶されると思ったのに、そうじゃないんだ。
圭太が、俺を拒絶しなかった。
それどころか凄く可愛いことを言ってくる。
泣きたくなるほど嬉しくて、俺は思わず破顔した。
「ぷっ、あはははは!」
「わ、笑うなよ……!」
「ごめんごめん。可愛いなって思って」
「うううるせぇ!」
「ごめん、って。それに……」
俺は非常に繊細な手付きで、圭太の指に自身の指を絡めた。
確かに、キスよりも先に手を繋ぐ必要もあったかもしれない。
だって恋人繋ぎをするだけで、こんなにもドキドキするのだから。
「順番、おかしくなってごめんね」
「は、はい……?」
「圭太。俺と付き合ってください」
俺の髪色を好きだと言ってくれた時から始まった恋心が、ようやく成就した夏だった。