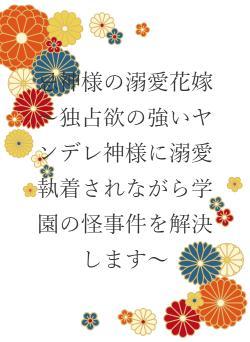「キスしてみる?」
遠くで鳴いている蝉の声が聞こえなくなり、しばらく俺は放心した。
「……はい? 何が? 誰が?」
オタク特有の早口に、上擦った声。
自分でも気持ち悪いと思う喋り方だというのに、相手はこの夏と同じぐらい爽やかに笑う。
「俺たちで。キスしてみようよ」
空耳では一切無かった彼からの言葉に、今度こそ俺は持っていた筆を床に落とした。
鷺宮葵は、いわゆる学年カーストの最上位にいるような男だった。
天然の綺麗な茶髪に、切れ長の瞳。体育の時間に日焼け止めすら塗っていないのに、アイドルみたいに透き通る白い肌。
見た目だけでもう勝ち組だ。
しかも中身も明るくて楽しい奴だから、クラスの中心的存在だし、男女共に人気がある。
更には成績も上位の方なのだから、なんかもう雲の上の存在といった感じだ。
一方の俺は、とくに特筆することも無い。
癖っ気の黒髪に、目付きの悪いタレ目を黒フレーム眼鏡で誤魔化した、ガリひょろのオタクってやつだ。
クラスでも端っこの方でコソコソしているような感じで、高校生活を二年間それで過ごしてきた。
だが、三年目でそれが大きく崩れた。
三年生になった時、それまで仲が良かったオタク仲間たちと別れることとなる。
あれだけ息の合った友人らとクラスを別々にされるだなんてあんまりだ。
クラス分け表の前でその結果に大いに嘆く俺は、近くにその男が寄ってきていることに少しも気付いていなかった。
「紺堂くん。一緒のクラスだね」
俺の肩を叩きながらそう言ってきたそいつこそ、鷺宮葵その人だった。
カースト上位のやつが突然なんだ?
実を言うと鷺宮とは一年生の時に同じクラスだった。だが会話なんて数えるぐらいしかなく、病気かなんかで欠席がちだった鷺宮にプリントを届けた時ぐらいしか喋ったことはない。
だから接点なんてほんのわずかしかなかったというのに、何故か鷺宮はこれだけ大勢の生徒がいる中で何故か俺に声をかけてきた。
「あ、あー……そう、みたいだね」
さすがに無視するわけにもいかないので返答したが、あまりにも急だったため声が引っ繰り返りそうになった。
こういう些細なところでもダサい自分が嫌になる。
だけど鷺宮はとくに気にした様子もなく、人懐っこい笑顔を俺に向けてきた。
「また一緒のクラスになりたいと思ってたんだ。良かったよ」
「そ、そう」
「良ければ一緒にクラス行こうよ」
「え、まあ、うん」
なんとも煮え切らない返事だ。
というのも、オタク仲間と別れて寂しい中、声をかけてもらえて嬉しいという気持ちと、なんで俺なんだという疑心暗鬼が今の俺を揺さぶっている。
鷺宮に声を掛けられたがっているクラスメイトはいくらでもいるだろうし、何なら自分から声をかけようと待機している奴らだっいるぐらいなのに。
なのになんでこんな俺に声をかけてきたんだと、考えても考えても答えは出ない。
だから共に下駄箱で上履きに履き替えながら、直球でそれを訊ねてみた。
「あの、なんで俺なの?」
「え?」
「いやだってさ、他にも友達いるだろ?」
言ってから、なんだか嫌味っぽくなってしまったと思い焦った。
けれど鷺宮は特に気にした様子も見せず、むしろ俺からのその質問に嬉しそうに回答する。
「さっきも言ったじゃん。また一緒のクラスになりたかったんだって」
「でも俺たち、そんな接点無かったし……」
「一年の時、プリント届けてくれたでしょ。あれ、嬉しかったんだ、凄く」
「………」
まさか本当に、その接点だけでそんなにも俺のことを気にかけてくれていたとは思わず、照れ臭さから俺はついそっぽを向いた。
「よ、よ、よく覚えてるな……二年も前のこと」
「覚えてるよ。俺にとってはありがたいことだったし……何より、紺堂くんのあの一言にすっごく救われたからなぁ」
「あの一言? あの一言って?」
「んー……秘密」
「なんでだよ。俺が言ったのに」
「まあまあ、いつか思い出すよ」
ケラケラと笑う鷺宮は、悔しいほど絵になっていて格好いい。
廊下をすれ違う女子も、話を中断して鷺宮の方へ視線を向けているのがわかる。
そこで俺は自分のこと……自分の身のほどみたいなものを思い出す。
鷺宮はカースト上位。そして俺は最下層。
行き交う男子が、なんでそいつと、って目で俺を見ていたことに気付いてないわけじゃない。
鷺宮だって、たまたまちょっとした気まぐれで声をかけてくれただけだ。
調子に乗るな、俺。
「じゃあ、俺、席に着くから。じゃあな」
短い付き合いだったな、鷺宮……と、俺的にはスマートに別れられた、はずだった。
「って言っても、俺たち席の順番前後だけどね」
「へ?」
言われて席に着き、その後ろに鷺宮が座り、俺は非常に間の抜けた声を上げてしまった。
確かに名前順で構成されたこの席順だと、俺たちは離れるに離れられない名前なわけで。
「短い別れだったね」
「……っ」
ニコニコと笑う鷺宮に、俺は何とも言えない表情を浮かべるしかなかった。
まさか席順が前後だとは、不覚!
「ねえ。圭太って呼んでいい?」
「はい?」
あまりにも急な提案。
そして初めて名前で呼ばれるそのくすぐったさに、耳がカッと赤くなるのを感じた。
「駄目かな?」
「いや……その……」
「俺のことも葵って呼んでいいからさ」
そういう問題じゃないと思いつつも、じゃあどんな問題なのかと問われたら俺は上手く回答できないだろう。
気恥ずかしさでまともに鷺宮の……葵の顔を見れないまま、俺は一つ頷いたのだった。
そんな流れから、俺と葵は何かと一緒にいることが多くなった。
休み時間から昼飯、放課後や帰り道……気付けば一緒にいる。クラスメイトからも、いつものコンビみたいな扱いを受けるぐらいには、何かとセットにされることも多かった。
それでもいまだに、なんで一緒にいるのとか訊かれることも少なくない。
正直そんなの俺が知りたいぐらいだ。
葵と俺は、ジャンルというかカテゴリーが全然違う。
言うまでも無く、俺は葵がいなきゃクラスで独りぼっちだが、葵は俺がいなくても選り取り見取りに友達はいる。
以前なんか、電車の関係で遅刻した俺が教室に入ると、葵を中心としたグループが出来上がっていて笑ってしまったぐらいだ。
笑うといっても、ああやっぱりな、という自分に向けた苦笑のようなやつ。
俺がいなくても葵は大丈夫なんだ、と。
そう思った矢先。
「おはよう圭太」
それまで周りの人と喋っていたというのに、葵は俺の姿を見るや否や一直線に俺の元までやって来た。
「圭太が遅刻なんて珍しいね」
「あ……えと、電車がなんか遅れて……」
「うわ、災難だったね。一限目のノート取ってあるから後で貸すよ」
「あ、ありがとう」
窓際の方で、さっきまで葵を取り囲んでいたクラスメイトが、ぽかんとした顔で俺と葵のやり取りを見ているのがわかる。
しかも葵は元の位置に戻るのかと思いきや、そのまま俺の傍で喋り始めるものだから、俺は何故か一人で焦ってしまった。
「おい、いいのかよ」
「なにが?」
「あっち戻らなくて」
「ああ、うん。圭太といたいから」
「……!」
「照れた?」
「ばっ……んなわけないだろ」
「あはは、そっか」
たまにこうやって、葵は俺をからかう時がある。
その度に俺は、すぐ赤くなる自分の顔を呪いつつ、なんとか誤魔化して過ごしてきた。全然誤魔化されてないだろうけど。
ただ、こういうアホみたいなやり取りも含め、葵と一緒にいるのは、なんというか……
居心地がいい。
そう、居心地がいい、だ。
ジャンルもカテゴリーも違う、趣味もとくに合うわけでもないのに、どうしてこうも一緒にいるのか。
居心地がいいからだ。
「………」
たぶんそれはきっと、葵が俺に、その居心地の良さを提供してくれているからなのだと思う。
俺のオタク話やオタク趣味に何かと興味を示してくれたり、話題に詰まると何かと俺の好きそうな話を提案してくれたり。
なんというか、俺はいつも葵に守られている感じがある。あくまで例えの話だが。
こんな流行りのアイドルみたいな優男なくせして、いつも安心感を俺にくれる。
まるで――彼氏みたいに。
「どうしたの?」
「えっ!」
「俺のことそんな熱心に見つめて」
「ち、ちがっ……勘違いすんなよ!」
「あはは」
勘違いは俺の方である。
何が彼氏だ。何が。
それもこれもよくわからん包容力のある葵が悪い。
絶対に。
そうして俺たちは、三年生の夏を迎えた。
この頃になってくると俺たちは受験のことで頭がいっぱいだ。
各言う俺も進路のことが気掛かりでしょうがない。
今の勉強で合っているのか。この進路で間違いないのか。などなど。
そんなことを考える一方、思うのは恋愛面で何も無かったこの三年間についてだ。
元々、教室の隅っこにいるオタクだ。
葵と一緒につるむようになったからといって、俺がモテるようになるわけでもない。
というかむしろ、葵のお邪魔虫のような存在に思われてるだろう。
ちょっといいなと思う女子がいなかったわけでもない。
美術部の後輩とも、それなりに仲良くはなれたと思う。
だけど恋愛としては本当に一切、なんっにも無かった。
それこそ葵と四六時中一緒にいたこともあり、そんなことを考える余裕が無かったとも言えるが。
「あー、居た居た」
なんて考えていたら、ドアを開け、葵が遠慮無く入って来た。
美術室。その端っこでキャンバスを広げていた俺は、呆れた様子で葵を見た。
「なんだよ」
「今日部活無い日でしょ? だから一緒に帰ろうと思ってたのに居ないからさ、探した」
バッグを近くの机の上に置き、葵はすぐに俺の傍にやってくる。
そのまま、真っ白なキャンバスと俺を交互に見る。
「何描くの?」
「まだ決めてない」
「時期的に卒業制作とか?」
「まあ、そうなる」
「ってことは、締め切りやばいんじゃ……」
「うっさい。そうだよ。だから一人で居残ってんの」
「あははは」
俺がキレたり大きく反応を示したりすると、決まって葵は楽しそうに、嬉しそうに笑う。
それがどうにも小動物の反応を面白がる飼い主のようで、俺はますます口角を下げた。
「ずーっと無心でキャンバスとにらめっこしてたの?」
「無心じゃないけど……」
「ふーん。何考えてた? 受験のこと?」
「それもあるけど……あとは彼女とか」
言ってから語弊のある言い方だなと思った。
案の定、あの葵が、目を見開いてその顔から笑みを消していた。
「……彼女?」
「いや、つーか、恋愛とかそういうの無かったな、って」
いざ口に出すと何とも情けない話題だと俺は自嘲気味に笑った。
一方で、葵の方は違う。
こんなくだらない話題だというのに、口元に手を当て、何故か真剣な眼差しで俺の方を見つめていた。
「な、なんだよ……」
さすがにイケメンに真正面から見られていると、何とも言えない気持ちになる。
それが葵からならなおさらだ。なんでかはわかんないけど。
そうしてしばしの沈黙。
蝉の鳴き声や、校庭から聞こえてくるサッカー部の声が、やけに大きく聞こえる。
「……してみる?」
「え?」
「キスしてみる?」
遠くで鳴いている蝉の声が聞こえなくなり、しばらく俺は放心した。
「……はい? 何が? 誰が?」
オタク特有の早口に、上擦った声。
自分でも気持ち悪いと思う喋り方だというのに、相手はこの夏と同じぐらい爽やかに笑う。
「俺たちで。キスしてみようよ」
正気か?
とか。
冗談もほどほどにしろよ。
とか。
色んな言葉が頭の中に浮かんでいるのに。
気付けば間近に迫った葵の端正な顔に俺は見惚れていた。
そして感じた、唇への柔らかな感触。
「ん……」
ジリジリと鳴く蝉の声。顧問にどやされるサッカー部の声。
耳にまで届く吐息の距離。俺の肩に触れる葵の手の熱さ。
「ばっ……だぁああああ!」
反射的に下がった俺は、そのまま椅子から落ちて背中から床に叩きつけられた。
だが、感じた痛みよりもバクバクといっている心音の方がずっと強い。
「なんっ、な、なん、で……」
「大丈夫? 頭打ってない?」
騒いでる俺が馬鹿みたいなほど、葵は実に冷静だった。
俺は慌てて立ち上がり、思わず自分の唇に触れる。
俺は今、こいつとキスをした。
そのまごうこと無き事実に、頭が爆発しそうなほど沸騰する。
葵は、笑っている。
女なんて選びたい放題なほど綺麗な顔で、穏やかに笑っている。
「ってかいきなりキスってなんだよ! 普通、あ、あれだろ……手を繋ぐとかさぁ!」
「手……」
「告白とか、そもそも付き合ってからだろキスってやつは!」
一瞬の間。
目を丸くしていた葵が破顔する。
「ぷっ、あはははは!」
「わ、笑うなよ……!」
「ごめんごめん。可愛いなって思って」
「うううるせぇ!」
「ごめん、って。それに……」
するり、と。
気付けば葵の整った長い指が、俺の無骨な指を絡め取った。
いわゆる恋人繋ぎをしながら、葵は真っ直ぐ俺を見る。
「順番、おかしくなってごめんね」
「は、はい……?」
「圭太。俺と付き合ってください」
こうして俺の夏は、葵から始まった。
遠くで鳴いている蝉の声が聞こえなくなり、しばらく俺は放心した。
「……はい? 何が? 誰が?」
オタク特有の早口に、上擦った声。
自分でも気持ち悪いと思う喋り方だというのに、相手はこの夏と同じぐらい爽やかに笑う。
「俺たちで。キスしてみようよ」
空耳では一切無かった彼からの言葉に、今度こそ俺は持っていた筆を床に落とした。
鷺宮葵は、いわゆる学年カーストの最上位にいるような男だった。
天然の綺麗な茶髪に、切れ長の瞳。体育の時間に日焼け止めすら塗っていないのに、アイドルみたいに透き通る白い肌。
見た目だけでもう勝ち組だ。
しかも中身も明るくて楽しい奴だから、クラスの中心的存在だし、男女共に人気がある。
更には成績も上位の方なのだから、なんかもう雲の上の存在といった感じだ。
一方の俺は、とくに特筆することも無い。
癖っ気の黒髪に、目付きの悪いタレ目を黒フレーム眼鏡で誤魔化した、ガリひょろのオタクってやつだ。
クラスでも端っこの方でコソコソしているような感じで、高校生活を二年間それで過ごしてきた。
だが、三年目でそれが大きく崩れた。
三年生になった時、それまで仲が良かったオタク仲間たちと別れることとなる。
あれだけ息の合った友人らとクラスを別々にされるだなんてあんまりだ。
クラス分け表の前でその結果に大いに嘆く俺は、近くにその男が寄ってきていることに少しも気付いていなかった。
「紺堂くん。一緒のクラスだね」
俺の肩を叩きながらそう言ってきたそいつこそ、鷺宮葵その人だった。
カースト上位のやつが突然なんだ?
実を言うと鷺宮とは一年生の時に同じクラスだった。だが会話なんて数えるぐらいしかなく、病気かなんかで欠席がちだった鷺宮にプリントを届けた時ぐらいしか喋ったことはない。
だから接点なんてほんのわずかしかなかったというのに、何故か鷺宮はこれだけ大勢の生徒がいる中で何故か俺に声をかけてきた。
「あ、あー……そう、みたいだね」
さすがに無視するわけにもいかないので返答したが、あまりにも急だったため声が引っ繰り返りそうになった。
こういう些細なところでもダサい自分が嫌になる。
だけど鷺宮はとくに気にした様子もなく、人懐っこい笑顔を俺に向けてきた。
「また一緒のクラスになりたいと思ってたんだ。良かったよ」
「そ、そう」
「良ければ一緒にクラス行こうよ」
「え、まあ、うん」
なんとも煮え切らない返事だ。
というのも、オタク仲間と別れて寂しい中、声をかけてもらえて嬉しいという気持ちと、なんで俺なんだという疑心暗鬼が今の俺を揺さぶっている。
鷺宮に声を掛けられたがっているクラスメイトはいくらでもいるだろうし、何なら自分から声をかけようと待機している奴らだっいるぐらいなのに。
なのになんでこんな俺に声をかけてきたんだと、考えても考えても答えは出ない。
だから共に下駄箱で上履きに履き替えながら、直球でそれを訊ねてみた。
「あの、なんで俺なの?」
「え?」
「いやだってさ、他にも友達いるだろ?」
言ってから、なんだか嫌味っぽくなってしまったと思い焦った。
けれど鷺宮は特に気にした様子も見せず、むしろ俺からのその質問に嬉しそうに回答する。
「さっきも言ったじゃん。また一緒のクラスになりたかったんだって」
「でも俺たち、そんな接点無かったし……」
「一年の時、プリント届けてくれたでしょ。あれ、嬉しかったんだ、凄く」
「………」
まさか本当に、その接点だけでそんなにも俺のことを気にかけてくれていたとは思わず、照れ臭さから俺はついそっぽを向いた。
「よ、よ、よく覚えてるな……二年も前のこと」
「覚えてるよ。俺にとってはありがたいことだったし……何より、紺堂くんのあの一言にすっごく救われたからなぁ」
「あの一言? あの一言って?」
「んー……秘密」
「なんでだよ。俺が言ったのに」
「まあまあ、いつか思い出すよ」
ケラケラと笑う鷺宮は、悔しいほど絵になっていて格好いい。
廊下をすれ違う女子も、話を中断して鷺宮の方へ視線を向けているのがわかる。
そこで俺は自分のこと……自分の身のほどみたいなものを思い出す。
鷺宮はカースト上位。そして俺は最下層。
行き交う男子が、なんでそいつと、って目で俺を見ていたことに気付いてないわけじゃない。
鷺宮だって、たまたまちょっとした気まぐれで声をかけてくれただけだ。
調子に乗るな、俺。
「じゃあ、俺、席に着くから。じゃあな」
短い付き合いだったな、鷺宮……と、俺的にはスマートに別れられた、はずだった。
「って言っても、俺たち席の順番前後だけどね」
「へ?」
言われて席に着き、その後ろに鷺宮が座り、俺は非常に間の抜けた声を上げてしまった。
確かに名前順で構成されたこの席順だと、俺たちは離れるに離れられない名前なわけで。
「短い別れだったね」
「……っ」
ニコニコと笑う鷺宮に、俺は何とも言えない表情を浮かべるしかなかった。
まさか席順が前後だとは、不覚!
「ねえ。圭太って呼んでいい?」
「はい?」
あまりにも急な提案。
そして初めて名前で呼ばれるそのくすぐったさに、耳がカッと赤くなるのを感じた。
「駄目かな?」
「いや……その……」
「俺のことも葵って呼んでいいからさ」
そういう問題じゃないと思いつつも、じゃあどんな問題なのかと問われたら俺は上手く回答できないだろう。
気恥ずかしさでまともに鷺宮の……葵の顔を見れないまま、俺は一つ頷いたのだった。
そんな流れから、俺と葵は何かと一緒にいることが多くなった。
休み時間から昼飯、放課後や帰り道……気付けば一緒にいる。クラスメイトからも、いつものコンビみたいな扱いを受けるぐらいには、何かとセットにされることも多かった。
それでもいまだに、なんで一緒にいるのとか訊かれることも少なくない。
正直そんなの俺が知りたいぐらいだ。
葵と俺は、ジャンルというかカテゴリーが全然違う。
言うまでも無く、俺は葵がいなきゃクラスで独りぼっちだが、葵は俺がいなくても選り取り見取りに友達はいる。
以前なんか、電車の関係で遅刻した俺が教室に入ると、葵を中心としたグループが出来上がっていて笑ってしまったぐらいだ。
笑うといっても、ああやっぱりな、という自分に向けた苦笑のようなやつ。
俺がいなくても葵は大丈夫なんだ、と。
そう思った矢先。
「おはよう圭太」
それまで周りの人と喋っていたというのに、葵は俺の姿を見るや否や一直線に俺の元までやって来た。
「圭太が遅刻なんて珍しいね」
「あ……えと、電車がなんか遅れて……」
「うわ、災難だったね。一限目のノート取ってあるから後で貸すよ」
「あ、ありがとう」
窓際の方で、さっきまで葵を取り囲んでいたクラスメイトが、ぽかんとした顔で俺と葵のやり取りを見ているのがわかる。
しかも葵は元の位置に戻るのかと思いきや、そのまま俺の傍で喋り始めるものだから、俺は何故か一人で焦ってしまった。
「おい、いいのかよ」
「なにが?」
「あっち戻らなくて」
「ああ、うん。圭太といたいから」
「……!」
「照れた?」
「ばっ……んなわけないだろ」
「あはは、そっか」
たまにこうやって、葵は俺をからかう時がある。
その度に俺は、すぐ赤くなる自分の顔を呪いつつ、なんとか誤魔化して過ごしてきた。全然誤魔化されてないだろうけど。
ただ、こういうアホみたいなやり取りも含め、葵と一緒にいるのは、なんというか……
居心地がいい。
そう、居心地がいい、だ。
ジャンルもカテゴリーも違う、趣味もとくに合うわけでもないのに、どうしてこうも一緒にいるのか。
居心地がいいからだ。
「………」
たぶんそれはきっと、葵が俺に、その居心地の良さを提供してくれているからなのだと思う。
俺のオタク話やオタク趣味に何かと興味を示してくれたり、話題に詰まると何かと俺の好きそうな話を提案してくれたり。
なんというか、俺はいつも葵に守られている感じがある。あくまで例えの話だが。
こんな流行りのアイドルみたいな優男なくせして、いつも安心感を俺にくれる。
まるで――彼氏みたいに。
「どうしたの?」
「えっ!」
「俺のことそんな熱心に見つめて」
「ち、ちがっ……勘違いすんなよ!」
「あはは」
勘違いは俺の方である。
何が彼氏だ。何が。
それもこれもよくわからん包容力のある葵が悪い。
絶対に。
そうして俺たちは、三年生の夏を迎えた。
この頃になってくると俺たちは受験のことで頭がいっぱいだ。
各言う俺も進路のことが気掛かりでしょうがない。
今の勉強で合っているのか。この進路で間違いないのか。などなど。
そんなことを考える一方、思うのは恋愛面で何も無かったこの三年間についてだ。
元々、教室の隅っこにいるオタクだ。
葵と一緒につるむようになったからといって、俺がモテるようになるわけでもない。
というかむしろ、葵のお邪魔虫のような存在に思われてるだろう。
ちょっといいなと思う女子がいなかったわけでもない。
美術部の後輩とも、それなりに仲良くはなれたと思う。
だけど恋愛としては本当に一切、なんっにも無かった。
それこそ葵と四六時中一緒にいたこともあり、そんなことを考える余裕が無かったとも言えるが。
「あー、居た居た」
なんて考えていたら、ドアを開け、葵が遠慮無く入って来た。
美術室。その端っこでキャンバスを広げていた俺は、呆れた様子で葵を見た。
「なんだよ」
「今日部活無い日でしょ? だから一緒に帰ろうと思ってたのに居ないからさ、探した」
バッグを近くの机の上に置き、葵はすぐに俺の傍にやってくる。
そのまま、真っ白なキャンバスと俺を交互に見る。
「何描くの?」
「まだ決めてない」
「時期的に卒業制作とか?」
「まあ、そうなる」
「ってことは、締め切りやばいんじゃ……」
「うっさい。そうだよ。だから一人で居残ってんの」
「あははは」
俺がキレたり大きく反応を示したりすると、決まって葵は楽しそうに、嬉しそうに笑う。
それがどうにも小動物の反応を面白がる飼い主のようで、俺はますます口角を下げた。
「ずーっと無心でキャンバスとにらめっこしてたの?」
「無心じゃないけど……」
「ふーん。何考えてた? 受験のこと?」
「それもあるけど……あとは彼女とか」
言ってから語弊のある言い方だなと思った。
案の定、あの葵が、目を見開いてその顔から笑みを消していた。
「……彼女?」
「いや、つーか、恋愛とかそういうの無かったな、って」
いざ口に出すと何とも情けない話題だと俺は自嘲気味に笑った。
一方で、葵の方は違う。
こんなくだらない話題だというのに、口元に手を当て、何故か真剣な眼差しで俺の方を見つめていた。
「な、なんだよ……」
さすがにイケメンに真正面から見られていると、何とも言えない気持ちになる。
それが葵からならなおさらだ。なんでかはわかんないけど。
そうしてしばしの沈黙。
蝉の鳴き声や、校庭から聞こえてくるサッカー部の声が、やけに大きく聞こえる。
「……してみる?」
「え?」
「キスしてみる?」
遠くで鳴いている蝉の声が聞こえなくなり、しばらく俺は放心した。
「……はい? 何が? 誰が?」
オタク特有の早口に、上擦った声。
自分でも気持ち悪いと思う喋り方だというのに、相手はこの夏と同じぐらい爽やかに笑う。
「俺たちで。キスしてみようよ」
正気か?
とか。
冗談もほどほどにしろよ。
とか。
色んな言葉が頭の中に浮かんでいるのに。
気付けば間近に迫った葵の端正な顔に俺は見惚れていた。
そして感じた、唇への柔らかな感触。
「ん……」
ジリジリと鳴く蝉の声。顧問にどやされるサッカー部の声。
耳にまで届く吐息の距離。俺の肩に触れる葵の手の熱さ。
「ばっ……だぁああああ!」
反射的に下がった俺は、そのまま椅子から落ちて背中から床に叩きつけられた。
だが、感じた痛みよりもバクバクといっている心音の方がずっと強い。
「なんっ、な、なん、で……」
「大丈夫? 頭打ってない?」
騒いでる俺が馬鹿みたいなほど、葵は実に冷静だった。
俺は慌てて立ち上がり、思わず自分の唇に触れる。
俺は今、こいつとキスをした。
そのまごうこと無き事実に、頭が爆発しそうなほど沸騰する。
葵は、笑っている。
女なんて選びたい放題なほど綺麗な顔で、穏やかに笑っている。
「ってかいきなりキスってなんだよ! 普通、あ、あれだろ……手を繋ぐとかさぁ!」
「手……」
「告白とか、そもそも付き合ってからだろキスってやつは!」
一瞬の間。
目を丸くしていた葵が破顔する。
「ぷっ、あはははは!」
「わ、笑うなよ……!」
「ごめんごめん。可愛いなって思って」
「うううるせぇ!」
「ごめん、って。それに……」
するり、と。
気付けば葵の整った長い指が、俺の無骨な指を絡め取った。
いわゆる恋人繋ぎをしながら、葵は真っ直ぐ俺を見る。
「順番、おかしくなってごめんね」
「は、はい……?」
「圭太。俺と付き合ってください」
こうして俺の夏は、葵から始まった。