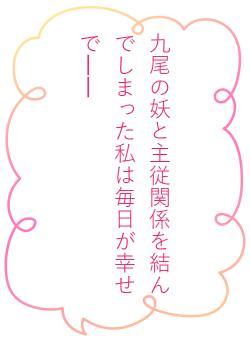手を握って。この言葉を言ったら、握ってくれるのかな。強く、温かく、忘れないようにどこまでも。ベルモットの香りが流れゆく時間と交わりながら、ゆったりと、ただゆったりと私の心を抱え込む。ソファに座りながら、私は彼女と一緒に退屈なテレビを見ている。彼女にとっては面白いのかも知れないけれど、流れるテレビなんて私にはどうでもいいことだった。つまらないドキュメンタリー番組より、私を見て欲しかった。膝に置いた手を、私の手の上に置いて欲しかった。寄りかかりたいけど、心の距離はきっと同じまま。
小さく息を吐く――それは、もしかしたら私が思っているより大きかったのかもしれない。彼女がその吐息に気づいた。
「澪、どうしたの眠い?」と真唯は言った。
「まあ、ちょっとだけ」私は少しばかり嘘をついた――いや、嘘というよりただ肯定しただけ。
「今日帰ってきた時から、ちょっと疲れてるような感じだったし、寝るならわたしも寝るよ?」
真唯は優しい、周りを上手く見ている。夢中にテレビを見ていたのに、私の為に視聴をやめようとしている。けど、心の内側も見て欲しいのは贅沢な願いなのかな。今寄りかかれば、抱いてくれるだろうけど、それは真唯の優しさ。労わるような、あるいはただの慰め。きっと、それを味わったらやめられなくなる。彼女の作る甘いカクテルと同じ。
暖房によって維持している温度みたいに、関係を冷まさない為に私は真唯に言った。
「大丈夫、仕事でムカつくことがあっただけ。気にしないで」私はホットミルクを一口飲むと「それに、まだテレビ途中でしょ。ここまで見たなら最後まで見よう」
真唯はそうだね、と言いテレビを見るのを再開した。持っていた生温いホットミルクをテーブルに置くと、私はソファにもたれかかった。ソファの弾力に体は負け、否定されてる感じだった。臆病な私が気に入らないらしい。これぐらい、はっきりと言ってくれたらどんなに楽なんだろう。顔を隣の真唯に向けると、こちらを見返してきた。私は何かを聞かれる前に、顔を正面に戻し、退屈なテレビを見た(それは、女性で初めて大西洋単独横断無着陸飛行を成功させた人のドキュメンタリー)。ぐっと体をソファに押し付けるが、やっぱり気に入らないみたい。
真唯はバーテンダーをしている(女性はバーメイドと称すらしいが、私はバーテンダーと言っている)。今日は休みだからソファで一緒に座っているが、普段は入れ替わりで過ごせる時間はほとんどない。コインの表と裏が交互に繰り返されると同じ。たまに、コインが立って両面が見える時がある、まさに今日みたいな日。僅かながらの幸運な日をひと時でも多く楽しみたかった。耳をすますと雨の音が聞こえる。小雪と呼ばれても降るのは雨。しとしと、と降る。孤独を感じさせる音は、私を真唯へと近づけさせる為の悪魔のいたずらなのかもしれない。
「凄いね、彼女は」と真唯はテレビに映る、偉大な女性パイロットを指して言う。
「本当にね。空を飛ぶなんてちょっと憧れるかも」私は真唯に視線を移すと「もしも、真唯がパイロットになったら、私を連れてってくれる?」
「もちろん。どこがいい? パリ、ロンドン、ベルリン、カサブランカ――」
「遠いとこばっかり、ソウルにバンコクやダナン、近いところだって――」
真唯は体を動かして、私の腕に軽く触れるぐらいに近づいて言った「すぐに着いたら、二人だけの空の旅は終わっちゃうでしょ? だから、遠い方がいいの。どんなに騒いだって、誰も文句は言わない」首を私の方にかしげると「二人だけの世界」と真唯は言った。
雨の音はかき消された。雨が止んだわけでも、テレビの流れるボリュームが大きくなったわけでもない。外の世界は何も変わってない。きっと、変わったのは私だけ。
真唯はずるい。平気でそういうことを言う。締めつけられる心を抑え、腕で軽く彼女を押した。
「そういう言葉、他の子にも言ってるの?」
「澪以外には言わないよ。言ったら恥ずかしいでしょ」真唯は微笑んだ。
「私なら恥ずかしくないってこと?」
「うーん、改めて考えると恥ずかしかも。ちょっとね」
「もう。言われる側も恥ずかしって」私は手で自分の顔を扇ぐふりをした。火照った体を冷ますように。でも、本当は冷めて欲しいとは思わなかった。温めて欲しかった。扇いだ時にでた、ささやかな風は私の言葉をも連れ去ってしまった。
ドキュメンタリー番組が終わると、二つのカップと、小さなお皿が置いてあったテーブルを片付けた。ルームシェアをしていて(私は大きな声で同棲だと言いたい)個別の部屋で寝ている。一ヶ月に一回ぐらいは、彼女の部屋で一緒に寝ることもある。電気代節約とか、寂しくなってとか、言い訳をしながら二人狭いベッドで寝る(寝相が悪いのか、私の長い髪が彼女を窒息させることがあるらしい。真唯の髪も長い方だとは思うが、私にはその経験がないから寝相が悪いのは間違いないのだろうけど――)。
寒いからと言い訳して、真唯の部屋で寝ることにした。彼女の部屋は黒基調だ、小さなガラステーブルに(モード系のファッション誌が置いてある)、限りなくブラックに近いブラウンカラーのデスクがある(ノートパソコンにデジタルオーディオプレーヤー、ヘッドホンとCDケース、それとマンガが散らかっている)。私はベルモットの匂いを感じつつ、ベッドに入った。真唯はベッドの奥、壁側に位置している。仰向けになり、二人で天井を見ていた。
天井を見ていると真唯が口を開く「明日の朝前には、雨止むらしいよ」
「そうなの?」
「神様にお願いしたらね、そう言ってた」
「なんてお願いしたの?」
「澪を濡らさないでやってください、毎日頑張って髪を巻いているんでって」真唯は両手を広げて祈るような姿で言った。
「それで、なんて答えたの?」
「雷や雹も止んで、地に降り注ぐ雨も止ますぐらいには本気らしい」
「雷も雹も降ってないのに、過剰な神様」
「可愛いから本気をだしたって言ってたよ」両手をしまうと、私の方を見た。
「どっちが?」と私は言った。
「それは、聞きそびれたちゃった」真唯はまた、天井を眺めだした。
雨の音が目立って聞こえるぐらいの沈黙のなか私は聞いた。
「どっちだと思う、実際」
「うーん、やっぱり澪じゃない。いつも頑張ってるでしょ」
「それは、真唯だってそうじゃん」私は真唯に顔を向けた。
指をクルクルと回しながら「わたしなんて、アルコールをステアしたりシェイクしたりしてるだけだし」
「真唯が作る味が一番好きだよ」私のこの言葉は嘘偽りのない言葉。真意に気づいて欲しいと欠片ぐらいの想いを乗せた。
「なら、次の休みに家で飲もう」
そう言うと、彼女も私に顔を向けた。私はその言葉に静かに頷いた。これでも十分なぐらい心は温まった。そして、真唯は続けてこう言った「で、結局どっちが可愛いってことになったんだっけ?」
「両方でしょ」と私は言った。
「うん。両方可愛いか」
向かい合い、目をつぶった。時々目をちょっと開けるが、彼女のまぶたは閉じている。私が目をつぶっている時も、真唯はまぶたを開けないのか気になった。身勝手な願いなのかもしれない、真唯がその目で私を見ていて欲しいと思うのは。布団の温もりと、真唯の温もりの違いもわからないまま、私は眠りに落ちた。
視界が広がると、白くぼやけていた。アラームによる無理やりの起床ではなかった。日の光がカーテンを通り抜け、部屋を僅かながらに明るく間接照明程度には、部屋に光を与えていた。外からは雨の音は聞こえず、程よい雑音が響く。波が引くように、ぼやけた視界から鮮明な視界に移り替わってゆく。一番にいて欲しい姿がそこにはあった。まだ、感覚が浅い手を彼女に伸ばして垂れた前髪に触り、真唯の顔を見た。一定のリズムで、呼吸しているのがわかる。振り子のように反復するみたいに、呼吸をしていた。私は彼女の顔よりも手前にある、腕に手を誘導させた。時々、触る時がある。もしかしたら、私の心が伝わるんじゃないかって思いながら触れていた。今も腕に触ろうとした時、私は手を止めた。
昨日見たドキュメンタリー番組を思い出し、ピタリと静止した。偉大な女性パイロットの最後の飛行が頭によぎる。赤道世界一周飛行をしようとしたが飛行中に消息を絶った。誰よりも先頭に立ち率いた、偉大彼女であったが消える時は霧のように消える。私は怖くなった。真唯が消えてしまう気がした。空に飲まれて、あるいは海に飲み込まれるんじゃないかって思った。空を飛ぶ力も海を泳ぐ力もない私は、飲まれてしまった彼女を見つけられない。だったら、最初から飛ばないで、私は地上にいたい。その手に届かなったとしても、真唯が消えるぐらいなら届かなくていいのかもしれない。私は伸ばしていた手を引いた。翼を折りたたむように、ゆっくりと。
キッチンで朝食を作っていた。いつもより時間に余裕があるので、真唯の為にサラダを用意しておこうと野菜を切った。クルミとアーモンドを入れてナッツサラダを作り、私の朝食と仕事から帰ってきた夕食分、真唯の遅い朝食分(昼食が正しいのかもしれない)を作った。サラダを切ったついでに、パンも切る。トマト、レタス、ベーコンとマヨネーズ、バターを塗ったパンでサンドイッチを作り、真唯の分は冷蔵庫入れた。不規則な生活(それが、彼女の仕事だからしょうがないが)の為に私は出来ることをした。別に、義務感があるわけではないし、真唯が喜んでくれるならそれでよかった。コップにミルクを入れ、テーブルへと朝食を持って行った。ソファには座らず、カーペットに座って(リビングにはテーブルがソファの前にしかなくて、軽食以外はカーペットに直接座っている)テレビをつけ、朝のニュースを流しながら食べた。普段と何が違うのかわからないニュースだった。
雨が降っていたのもあり寒さが際立つ日でもあった。明るいブルーのウールとアクリル混紡のニットにミモレ丈のグレーのスカートを着て、アウターには、真唯から貰ったサンドベージュ色したコットンギャバジンのトレンチコートを身に纏う。鏡を見ると、完璧とは言えないスタイリングだった。ぼんやりとしてる気がする。トレンチコートを着たい気持ちと、明るいブルーのニットを着たい気持ちがぶつかった結果ではあった。変ではなかったので、私はこのままで行こうと考えた。真唯の部屋を覗くと、静かに寝ていた。帰ってきた時には居なくなってると思うと、少し苦しくなる。一緒に寝た日は一段とそう感じてしまう。ドアを閉めると、玄関まで行き家をでた。
揺られる電車に乗り、会社へと向かっていた。電車のなかでは、まるで私はどこか別の世界に飛ばされてるようだった。魂を持ち忘れてきたような感覚。私という抜け殻がただ電車に揺られていた。
私のやることと言えば、カウンターで接客をすること。旅行商品の提案や予約をしている、いわゆる旅行代理店。真唯がお酒を提供するのであれば、私は旅行へのチケット提供している。真唯が夢の世界に旅立てせるのであれば、私は現実の地へ旅立てせている。嫌いな仕事ではないが、好きでもない。苦痛だと思わないだけマシなのかもしれないけど。そうして私は、どこか気絶しているような時間を過ごした。
仕事が終わり、電車を降り、駅から出るとスーパーに寄った。冷蔵庫を補充するように、野菜類、タマゴを一パック(今日見たら二つしかなかった)、牛乳(成分無調整の牛乳、私しか飲まないので好きなのを買っている)、パン、食品用ラップフィルム、私の夕食用のお惣菜を買った。濃色のブルーのマイバッグに詰め込み、スーパーを出ると酒販店が隣にある。おしゃれな酒販店で、いつの頃だったか真唯と一緒に入ったのを思い出す。店の中に入り、お酒を探した。ワイン、日本酒、ウイスキー、選び放題ではあった。私はお酒に詳しいわけじゃない、適任なのは真唯だろう。せっかくなら私が選びそうにないもので、驚かせようと思った。サファイアのような透き通るブルーのボトルが目についた。手に取ると、ジンだった。もっと、珍しい物の方がいいのかもしれないけれど、今日の気分はブルーカラーだったからこれを買った。
酒販店から出ると、冷たい風が吹いた。昨日の雨によって濁った空気は冷たい風とシェイクされ、コートで身を守らなければ荒んでしまいそうだった。一番上までトレンチコートのボタンを閉めて、首元のストラップ(スロートラッチと言うらしいが、いつも忘れてしまう)も閉めた。住宅街を通りながらマンションまで歩いた。たまにすれ違う人は寒そうに歩いていた。街灯が道を照らして、佇む建物からは光が漏れ出しているから不安はなかった。けど、寂しさは感じる。吹く風によって、歩く私が一人であるという事実に苛んだ。孤独ではないのに、この時は孤独と感じた。
鍵を開け、今は一人しかいない家に帰った。暗い一室の電気をつけ、買った荷物や着ている服を整理し、暖房を入れて冷たい部屋を暖めた。真唯の残り香が漂う、つかめない真唯の姿がそこにはあり、僅かにだが孤独さを打ち消した。
私は、すぐに夕食の準備をした(朝作ったナッツサラダと、肉じゃが、豆腐、白米、準備というほどではないが)。テレビドラマ見終わり、食べ終えれば、私はリビングから自室に行った。あのリビングは広いわけじゃないのに、一人だと余白が多すぎた。キャンバスの半分ぐらいが描かれてないみたいで。部屋で数ページだけ見たファッション誌を読んだ。載っているスタイリングは、無難であり、だけど嫌われることもない服装。真唯の読むようなものは私には似合わないから、普通のかわいい服装が載っている雑誌をこうやって見ている。時々、ある文字が目に入る。少しだけ嫌いな文字だった。私が否定されていると感じるから、嫌だった。ページをめくり、何も考えずに読んだ。読み終えると、お風呂に入り、明日の準備をして目を閉じた。
アラームの音で目を覚ましリビングに行くと、テーブルに紙が置いてあった。そこには「サラダのお返し。冷蔵庫を見て」と真唯の字で書かれてあった。冷蔵庫を覗くと、保存容器にミネストローネが入っていて、小さなケーキも置いてあった。ケーキの下には小さな紙で「朝までに食べてね」と書かれていた。ミネストローネは鍋で温め直し、パンと一緒に食べた。野菜の甘さとトマトの風味が内側から体を温めた。ふうと息を吐く、落ち着きのある息だった。このまま、ぼうっとしていたいぐらい。時計の針が、大きく聞こえるぐらいぼうっとしてた。ケーキも最後に食べた。甘くて美味しかったけど、甘さを流すためのスープを残しておけばよかったと思いながら食べた。
白のシャツにショート丈のデニムジャケットを着て、デニムパンツを履いた(シャツの裾は出してレイヤード)。そして、トレンチコートを上から羽織る。私には少し攻めたスタイリングだった。ミネストローネのスープを飲んでから、なんだかやる気に溢れていた。真唯の部屋をそっと開け、覗いた。相変わらずぐっすりと寝ていた。部屋のドアを閉じ家をでた。今日は寂しく感じることはなかった。直接会話してないのに、心の距離が近づいた気がした。
この日の仕事は、なんだか上手くいった気がする。上手くと言っても、何か変わったことが起きたわけじゃないけど。引っ掛かりがないような、そんな感じだった。
昨日と変わらない、道順で帰った(酒販店は除く、用事はないから)。住宅街の道を歩いてると、私の頭に何かが当たった。痛くはない、軽い何かだ。落ちた音も聞こえ、下に目を向けた。白い紙飛行機だった。見渡すが人も、開いている窓もなかった。どこかの誰かが飛ばしたのだろう。拾い上げると文字のような物が書かれていた。紙飛行機を解くと「最も難しいのは、行動するという決断だ」と書かれていた。
記憶にある言葉だった。思い出すまでに時間は掛からなかった。それは、真唯と一緒に見ていた、ドキュメンタリー番組で紹介されていた偉大な女性パイロットの言葉。同じ番組を見た人が飛ばしたのだろう。私は道端に捨てるのにも悪いと思い、コートのポケットに入れて帰って行った。自室にコートを掛けて、紙飛行機だった手紙を取り出した。私へのメッセージなのかと思いながら眺めた。行動する難しさはわかっている。手を握って、と真唯にすら言えない私はよく理解していた。手紙をデスクに置くと、ベッドに倒れ込んだ。口で伝えるのは難しい、その場の空気と相手のことを考えて言葉を止めてしまう。真唯は肯定してくれるだろうけど、上手く口に出せなかった。ベッドに倒れ込んでいた私はゆっくりと立ち上がった。コピー用紙とペンを手に取ってリビングに向かった。ここだったら、真唯への気持ちが書ける気がしたから。まっさらな紙に文を書く。少し正直に。
真唯に。
突然の手紙だけど、許してください。ミネストローネのスープとても美味しかったです。あと、ケーキも美味しかったです。特にスープは、体が温まって気持ちよくて今日は仕事も捗りました。真唯が初めて私に作ってくれた料理のひとつにミネストローネがあったのを思い出し、懐かしさを感じました。けど、それを伝える為にこれを書いたわけではありません。深刻なことでもないです。一応書いておかないと緊張しちゃうだろうから記しておきます。
手紙を書いた理由は、真唯と見たドキュメンタリー番組からです。紹介されていた偉大な女性パイロットの言葉を思い出したので、いま書いています。
前に、次の休日の時は家で飲みましょうと話したのを覚えていますか。寝る前とは言え、さすがに覚えていることを望みます。いつも寄るスーパーの隣にある酒販店でジンを買いました。ボトルの色が青いのです。真唯ならわかるよね?
そして、書いておいて難ですが、本当は驚かせようと思ってジンのことは秘密にしてました。書く内容を考えていたら、勝手に手が進んで書いてしまったのです。鉛筆ではないので消せません。焦りながらも、心の想いを吐くことが大切だと思い、書き直すことはしません。
家に帰ってきて、あなたが居ないことが本当に苦しく感じます。朝起きて、あなたが部屋に居ると安心はしますが、やはり苦しいです。でも、仕事を辞めて欲しいとは思いません。真唯がやりたいことやってください。本当にそう思っています。本当に。二回も本当、と書きましたがそれぐらの気持ちということです。よく、見直したら五回も書かれてました、探し当ててください。
書くことが、なくなってきたので終わりたいと思います。正しくは、言いたいことが言えた。本当はもっとありますが、満足したのでやめます。
勝手に満足して終わらせるのは申し訳ないので、謝罪をしておきたいです。いつかの、CD失踪事件はご存知でしょうか。突如起きた怪事件。ケースの中に入っていたディスクが消えた、あの事件です。家中探し回りましたね。真唯が電子レンジの中を覗いたのが、一番面白かったです。さて、ここまで言えばわかりますよね? 犯人は私です。真唯の部屋にあったマンガを借りるために、デスクにあるマンガを取ろうとしたところ、積み上がったケースが崩れ落ちました。元に戻しつつ、中身を確認していたらディスクが真っ二つに割れているのが見つかり本当に驚き、隠しました。たくさんあるので、正直バレないと思ってましたが、すぐにバレましたね。隠し場所ですが、リビングのカレンダーの裏にテープで貼り付けてあります。つまりは、磔の刑に処されています。どうかその手で救ってください。罪悪感が湧いてきたので、ここで終わります。
追伸・改めて見ると、本当、という言葉をたくさん使っていました。もはや、書き癖なのでしょう。文はここで終わりです。本当の終わりです。
私は手紙を書き終えると、半分に折り、開き、紙飛行機を作った。立ち上がると、真唯の部屋にある小さなガラステーブルに置いた。それから、ルーティンのように寝るまでの作業をすますとベッドに入った。思っていたより、不安はなかった。むしろ、なんだか心地よかった。
朝の目覚めは、アラームの音ではなかった。ふんわりとした感じだった。重力が半分ぐらいになったような、体の軽さ。私はベッドから出ると、ぐっと体を伸ばした。いつもは、仕事に行く前に真唯の部屋を覗くけど、今日はすぐに覗いた。紙飛行機の手紙が気になってしょうがなかったから。音を立てないように部屋を見ると、彼女は寝ていて小さなガラステーブルに紙飛行機は解かれ置かれていた。部屋のドアをゆっくりと閉めた。私は自分でもわかるぐらいに笑顔になっていた。嬉しかった。それから、家を出るまでのことを私は覚えてなかった。いつの間にか会社にいた。ただ、唯一覚えるのは、その日の朝食に食べたパンと目玉焼きは美味しかったこと。
家に帰ってきた時、私はもしかしたらと自室に急いだ。電気をつけると、デスクの上には紙飛行機があった。すぐにも読みたかったけど、私は息を吐き、心を落ち着かせた。とりあえずは、スーパーで買ってきた物を冷蔵庫にしまい、それから読むことにした。自室でベッドに座り、紙飛行機を持ちながら天井を見た。明るいライトが私を照らしていた。心臓の音が、うるさいぐらいだった。顔を下に向け、手に持った紙飛行機を解いた。私は手紙を読み始めた。
おはよう、澪。
わたしの時間では、まだ朝。いつもは、もっと遅いのに今日は早く起きた。まあ、それはこの手紙を書くための時間が欲しかったから。あんまり、手紙なんて書かないからたっぷりの時間が欲しくてさ。というか、普通はそんなに書かないような……わたしだけ? こんなの小学生の頃以降だから、全然わからないや。上手く伝えられるといいんだけどね。あと、こんなふうにラフに書いてるのは、恥ずかしからなのです。
澪が修正なしで書いたから、わたしもそうすることにする。とりあえずは、CD失踪事件についてだけど。無事に救出完了しましたことを、ここに申し上げます。あと、二枚に割れていると思ったら、三枚で驚いた。真っ二つって二枚に割れることじゃないの? ゴルゴタの丘ならぬ、カレンダーの丘に磔刑にされていた三枚割れのディスクをどうするか考えてる。リビングで書いてるんだけど、今まさに目の前にあるの。哀れな姿。ショックだけど、買い直せる物だから悔い改めた澪を許します。待って、買い直せない物だったら許さないってことじゃないよ。勘違いしないで。
三枚の内一枚をゴミという地獄に捨てようと思いましたが、やめた。わたしの部屋に飾ることにした。
ちょうど、飾ってきた。何故? って思うだろうけど、変な意味はないからね。二人で探し回った想いでとして取っておくことにしたの。まさに現代アート。
さて、ここからは真面目に書かざるしかないのでしょうか? なんて答えればいいか、とても難しく感じますでしょう。一緒に居たいのは、わたしもなのです。今すぐにでも、職場を爆発させて、その推進力で澪と宇宙に行きたいぐらいであります。待って、今の仕事が嫌いってことじゃないよ! あと、日本語がおかしくなってきたから、普通に書く。
最初の頃は、家に澪が居るだけで幸せだと思ってた。時々、一緒に過ごす時間もあるからそれでよかったんだけど。最近かな、誰もいないリビングがちょっと怖くなってきたの。お化けが出そうみたいなことじゃないよ。わたしの部屋に居るときも、なんだか怖くてヘッドホンを外せない時もあったぐらい。たまに澪と一緒に寝る日があるでしょ? そういう日は怖くない。目が覚めれば、家にはいなくなっちゃってるけど、澪の感覚だけは何故だか残ってる。わたしも同じ気持ちなの、一緒に居たいのは。
明日は、わたし休みだから早く帰ってきて、食事もお酒も用意しておくから。わたしの……
追伸・ああ、なんだか恥ずかしくなってきた。今すぐにでも窓を開けて、手紙を空に飛ばしたい。待って、そんなことしたら、わたしの手紙を誰かに読まれちゃう。もしも、子供が拾ったらそれこそ笑い者じゃない? この地域で永遠と語り継がれて、新たな都市伝説の幕開け。というか、澪の名前が入ってるから個人情報の流失になる。諦めます。
追追伸・一回澪の部屋に置いたけど回収した。書かなきゃいけないことを忘れてた。家で飲むって話は覚えてる、鮮明に。ジンがあるなら、あれを飲みましょうあれを。書こうと思ったけど、やっぱり秘密にする。あと、ナッツサラダとても美味しかったよ。危なく書き忘れるところだった……最後に手紙を読み終えたら、わたしの目の届かないところに置いといてください。恥ずかしさで、悶え苦しむので。
この日、私は曲が耳に残るみたいに、手紙の内容を頭の中でリピートしていた。食べる時も、お風呂に入る時も、寝る時も。幻みたいに存在していた。幻は消えてなくなるけど、この手紙は無くならない。忘れないように、失わないようにデスクの引き出しに丁寧に入れた。部屋の明かりを消しても寂しくはなかった。
今日の気温は暖かった。昨日よりも、ちょっと暖かった。数字以上に伝わった。朝食はパンだけ食べた(ミルクも飲んだ)。真唯の部屋を開けることはせずに家を出た。最後に開けなかった日はいつかも覚えてないぐらい前で、日課のような動作を今日はやらなかった。電車のなかでの空虚な感覚は滑り落ち、向かう駅に繋がる線路がはっきりと見え。電車の窓からの太陽の光は眩しかった。
仕事が楽しいかと聞かれれば口を噤むが、そういう時も感じるのは実感できた(正確に言えば、思い出したが正しい)。楽しみを取って置いてるような、ケーキに乗ったイチゴを最後に食べる愉しみを感じながら、仕事を終えて、電車に乗り、道を歩いた。
風は、私の体を軽快に通り抜ける。涼しいとさえ感じた。強い風が吹き上がり、髪が乱れたけど気にならなかった。マンションに着くと、私は玄関の前で立ち止まった。色々、頭の中の考えを真っ白にしたかったから。白いペンキを頭の中でぶちまけた。どこもかしこも、ぶちまけた。気持ちを整えるとか、そういうのじゃなくてただ白くしたかった。塗りたくりすぎて、ぽたぽたとペンキが落ちるぐらいに。私は次の色をはっきりと見たかったから。
玄関に入ると「ただいま」と私は言った。
リビングから真唯が顔を出して「おかえり」と言った。
コート置いてくるね、と私は言い、自室にコートを掛けると何も考えずに、リビングに足を進めた。いい匂いがした。
真唯はテーブルにスープらしきものを置いているなか、私は聞いた「それは?」
「とっても美味しいボルシチ、温まると思って。それとサーモンパテ」立ち上がり、キッチンに向かい戻ってくると「そして、宅配ピザでございますお嬢様」
「これはこれは、庶民的ですわね」
「トスカーナ州の赤ワインもございます」
「あら、悪くないわね」
真唯はくすっと笑い「どこだかわかるの?」
「まったくわからない」と言い私も笑った。
私と真唯はカーペットに座り、食べ始めた。ボルシチのスープをひと口すくい上げ飲んだ。
「酸味もちょうどよくて良い、真唯の作るスープはいつも本当に美味しい」
真唯はその言葉を聞くと口角を上げながら、ボルシチを口に入れた。照れを隠すみたいに。
「ありがとう。作ったかいがある」と真唯は言った。私がボルシチに入っている牛肉に食べると「牛肉は固さはどう?」と聞いてきた。
「うん、固くないよ。昔作った、ローストビーフは火が通りすぎて固かったけどね」
「その話はもうやめてよ。怖くて温めすぎちゃっただけなんだから」そう言うと真唯は赤ワインを飲んだ。
「そういえば、ジンは?」私はワイングラスに注がれた赤ワインを手に取った。
「食べ終えてからの、お楽しみで――」
「ふーん」赤ワインを飲んだ。
ボルシチと赤ワインを交互に口に入れ、手をつけるの忘れていたピザを見て、私は真唯に聞いた。
「なんだっけ、このピザの名前……」
「嘘でしょ? 忘れたの? 有名じゃん。マから始まるやつ」
「マ、マ……」ど忘れしてしまい、私はこう言った「……マルガレーテ」
「えー、マルゲリータでしょ。酔うの早すぎない?」
「マルまでは合ってるからセーフ……」
「本命まで酔い潰れないでよ」
ピザを三枚残し、それ以外は食べた。気分になったら、少しずつピザを食べることにして私はソファに座った。体の芯からぽかぽかとしていた。ソファがなんだか、マシュマロに見えて真唯いなければかじりついてた。その思考になんだか笑いがこみ上げてきて、微笑んだ。真唯はキッチンから氷の入ったミキシンググラスとバースプーンに冷やされたカクテルグラス、オリーブとレモンピール、冷えたジンともう一つお酒を持ってきた。
「それは?」持ってきたお酒を指した。
「ベルモット。澪がジン持ってきたからね」
ミキシンググラスにジンとベルモットを入れた。ジンに対してベルモットは添えるような量だった。バースプーンでからからと音を立てながらステアしていた。じいっと見つめるが、からから音がなんだかあやされているように感じた。時間の感覚が虚ろになってゆく。柔らかく伸びているような、だらんと落ちそうな気分だった。全ての物事が滑らかに、這っていた。ステアが終わり、カクテルグラスに注がれるとオリーブが静かに添えられた。レモンピールが振りかけられると、私の前にそっと置いた。
「澪できたよ」と真唯は言った。
「これは?」
「マティーニ。名前ぐらいは知ってるでしょ?」
「うん。真唯も自分の作って――」酔いを醒ます為の時間がちょっとだけ欲しかった。
真唯は自分のマティーニも作り始めた。意識をはっきりさせるために私は聞いた。
「マティーニって、ジンの方が多いんだ――」
「そうだよ、ベルモットは少しだけ……」
私はベルモットが少しなことが不満だった。
「手紙――良かった」真唯の顔を見た。
「この場で言われると恥ずかしいなあ。わたしの文ひどかったでしょ?」
「そんなことないよ、とても心が伝わった」
「澪のもね――」真唯は私の方を見ると「手紙……まだ、あるの?」
「それが窓開けたら、鳩が口に咥えて持ってちゃった」
「ふふ、本当だったら面白い。もし、咥えたとしたら戻ってくると思う?」
「――戻ってくるよ、ハウランド島に届いたあとにね」
「読まれるのは嫌だなあ」
「平和なのが伝わる――」私は窓を見た。
真唯は自分のマティーニを作り終えると、ソファに座った。それに合わせて、ゆっくりと体を起こした。話したら気分が良くなった。
「ほら、澪も持って」真唯に言われ、私はカクテルグラスを持った。
「――ねえ、ジンとベルモットを半分ずつ入れてオリーブを抜いたらどうなるのかな?」カクテルグラスを目の高さに上げて、マティーニを見つめた。
「マティーニではなくなっちゃうと思うけど」
「そうなんだ――長い時間を掛けて少しずつ比率を変えたとしても?」
「うーん、どうなんだろうね。もしかして澪、酔ってる?」
「うん、間違いなく酔ってる。ただ、気になっただけ」私はカクテルグラスを真唯の方に向けた。呼応するように、真唯もグラスを向けた。空いた手を、ソファを這うように真唯に近づけると「手を握って」と私は言った。
真唯は一瞬驚きつつも、柔らかい表情になり私の手を握った。その手は温かかった。
小さく息を吐く――それは、もしかしたら私が思っているより大きかったのかもしれない。彼女がその吐息に気づいた。
「澪、どうしたの眠い?」と真唯は言った。
「まあ、ちょっとだけ」私は少しばかり嘘をついた――いや、嘘というよりただ肯定しただけ。
「今日帰ってきた時から、ちょっと疲れてるような感じだったし、寝るならわたしも寝るよ?」
真唯は優しい、周りを上手く見ている。夢中にテレビを見ていたのに、私の為に視聴をやめようとしている。けど、心の内側も見て欲しいのは贅沢な願いなのかな。今寄りかかれば、抱いてくれるだろうけど、それは真唯の優しさ。労わるような、あるいはただの慰め。きっと、それを味わったらやめられなくなる。彼女の作る甘いカクテルと同じ。
暖房によって維持している温度みたいに、関係を冷まさない為に私は真唯に言った。
「大丈夫、仕事でムカつくことがあっただけ。気にしないで」私はホットミルクを一口飲むと「それに、まだテレビ途中でしょ。ここまで見たなら最後まで見よう」
真唯はそうだね、と言いテレビを見るのを再開した。持っていた生温いホットミルクをテーブルに置くと、私はソファにもたれかかった。ソファの弾力に体は負け、否定されてる感じだった。臆病な私が気に入らないらしい。これぐらい、はっきりと言ってくれたらどんなに楽なんだろう。顔を隣の真唯に向けると、こちらを見返してきた。私は何かを聞かれる前に、顔を正面に戻し、退屈なテレビを見た(それは、女性で初めて大西洋単独横断無着陸飛行を成功させた人のドキュメンタリー)。ぐっと体をソファに押し付けるが、やっぱり気に入らないみたい。
真唯はバーテンダーをしている(女性はバーメイドと称すらしいが、私はバーテンダーと言っている)。今日は休みだからソファで一緒に座っているが、普段は入れ替わりで過ごせる時間はほとんどない。コインの表と裏が交互に繰り返されると同じ。たまに、コインが立って両面が見える時がある、まさに今日みたいな日。僅かながらの幸運な日をひと時でも多く楽しみたかった。耳をすますと雨の音が聞こえる。小雪と呼ばれても降るのは雨。しとしと、と降る。孤独を感じさせる音は、私を真唯へと近づけさせる為の悪魔のいたずらなのかもしれない。
「凄いね、彼女は」と真唯はテレビに映る、偉大な女性パイロットを指して言う。
「本当にね。空を飛ぶなんてちょっと憧れるかも」私は真唯に視線を移すと「もしも、真唯がパイロットになったら、私を連れてってくれる?」
「もちろん。どこがいい? パリ、ロンドン、ベルリン、カサブランカ――」
「遠いとこばっかり、ソウルにバンコクやダナン、近いところだって――」
真唯は体を動かして、私の腕に軽く触れるぐらいに近づいて言った「すぐに着いたら、二人だけの空の旅は終わっちゃうでしょ? だから、遠い方がいいの。どんなに騒いだって、誰も文句は言わない」首を私の方にかしげると「二人だけの世界」と真唯は言った。
雨の音はかき消された。雨が止んだわけでも、テレビの流れるボリュームが大きくなったわけでもない。外の世界は何も変わってない。きっと、変わったのは私だけ。
真唯はずるい。平気でそういうことを言う。締めつけられる心を抑え、腕で軽く彼女を押した。
「そういう言葉、他の子にも言ってるの?」
「澪以外には言わないよ。言ったら恥ずかしいでしょ」真唯は微笑んだ。
「私なら恥ずかしくないってこと?」
「うーん、改めて考えると恥ずかしかも。ちょっとね」
「もう。言われる側も恥ずかしって」私は手で自分の顔を扇ぐふりをした。火照った体を冷ますように。でも、本当は冷めて欲しいとは思わなかった。温めて欲しかった。扇いだ時にでた、ささやかな風は私の言葉をも連れ去ってしまった。
ドキュメンタリー番組が終わると、二つのカップと、小さなお皿が置いてあったテーブルを片付けた。ルームシェアをしていて(私は大きな声で同棲だと言いたい)個別の部屋で寝ている。一ヶ月に一回ぐらいは、彼女の部屋で一緒に寝ることもある。電気代節約とか、寂しくなってとか、言い訳をしながら二人狭いベッドで寝る(寝相が悪いのか、私の長い髪が彼女を窒息させることがあるらしい。真唯の髪も長い方だとは思うが、私にはその経験がないから寝相が悪いのは間違いないのだろうけど――)。
寒いからと言い訳して、真唯の部屋で寝ることにした。彼女の部屋は黒基調だ、小さなガラステーブルに(モード系のファッション誌が置いてある)、限りなくブラックに近いブラウンカラーのデスクがある(ノートパソコンにデジタルオーディオプレーヤー、ヘッドホンとCDケース、それとマンガが散らかっている)。私はベルモットの匂いを感じつつ、ベッドに入った。真唯はベッドの奥、壁側に位置している。仰向けになり、二人で天井を見ていた。
天井を見ていると真唯が口を開く「明日の朝前には、雨止むらしいよ」
「そうなの?」
「神様にお願いしたらね、そう言ってた」
「なんてお願いしたの?」
「澪を濡らさないでやってください、毎日頑張って髪を巻いているんでって」真唯は両手を広げて祈るような姿で言った。
「それで、なんて答えたの?」
「雷や雹も止んで、地に降り注ぐ雨も止ますぐらいには本気らしい」
「雷も雹も降ってないのに、過剰な神様」
「可愛いから本気をだしたって言ってたよ」両手をしまうと、私の方を見た。
「どっちが?」と私は言った。
「それは、聞きそびれたちゃった」真唯はまた、天井を眺めだした。
雨の音が目立って聞こえるぐらいの沈黙のなか私は聞いた。
「どっちだと思う、実際」
「うーん、やっぱり澪じゃない。いつも頑張ってるでしょ」
「それは、真唯だってそうじゃん」私は真唯に顔を向けた。
指をクルクルと回しながら「わたしなんて、アルコールをステアしたりシェイクしたりしてるだけだし」
「真唯が作る味が一番好きだよ」私のこの言葉は嘘偽りのない言葉。真意に気づいて欲しいと欠片ぐらいの想いを乗せた。
「なら、次の休みに家で飲もう」
そう言うと、彼女も私に顔を向けた。私はその言葉に静かに頷いた。これでも十分なぐらい心は温まった。そして、真唯は続けてこう言った「で、結局どっちが可愛いってことになったんだっけ?」
「両方でしょ」と私は言った。
「うん。両方可愛いか」
向かい合い、目をつぶった。時々目をちょっと開けるが、彼女のまぶたは閉じている。私が目をつぶっている時も、真唯はまぶたを開けないのか気になった。身勝手な願いなのかもしれない、真唯がその目で私を見ていて欲しいと思うのは。布団の温もりと、真唯の温もりの違いもわからないまま、私は眠りに落ちた。
視界が広がると、白くぼやけていた。アラームによる無理やりの起床ではなかった。日の光がカーテンを通り抜け、部屋を僅かながらに明るく間接照明程度には、部屋に光を与えていた。外からは雨の音は聞こえず、程よい雑音が響く。波が引くように、ぼやけた視界から鮮明な視界に移り替わってゆく。一番にいて欲しい姿がそこにはあった。まだ、感覚が浅い手を彼女に伸ばして垂れた前髪に触り、真唯の顔を見た。一定のリズムで、呼吸しているのがわかる。振り子のように反復するみたいに、呼吸をしていた。私は彼女の顔よりも手前にある、腕に手を誘導させた。時々、触る時がある。もしかしたら、私の心が伝わるんじゃないかって思いながら触れていた。今も腕に触ろうとした時、私は手を止めた。
昨日見たドキュメンタリー番組を思い出し、ピタリと静止した。偉大な女性パイロットの最後の飛行が頭によぎる。赤道世界一周飛行をしようとしたが飛行中に消息を絶った。誰よりも先頭に立ち率いた、偉大彼女であったが消える時は霧のように消える。私は怖くなった。真唯が消えてしまう気がした。空に飲まれて、あるいは海に飲み込まれるんじゃないかって思った。空を飛ぶ力も海を泳ぐ力もない私は、飲まれてしまった彼女を見つけられない。だったら、最初から飛ばないで、私は地上にいたい。その手に届かなったとしても、真唯が消えるぐらいなら届かなくていいのかもしれない。私は伸ばしていた手を引いた。翼を折りたたむように、ゆっくりと。
キッチンで朝食を作っていた。いつもより時間に余裕があるので、真唯の為にサラダを用意しておこうと野菜を切った。クルミとアーモンドを入れてナッツサラダを作り、私の朝食と仕事から帰ってきた夕食分、真唯の遅い朝食分(昼食が正しいのかもしれない)を作った。サラダを切ったついでに、パンも切る。トマト、レタス、ベーコンとマヨネーズ、バターを塗ったパンでサンドイッチを作り、真唯の分は冷蔵庫入れた。不規則な生活(それが、彼女の仕事だからしょうがないが)の為に私は出来ることをした。別に、義務感があるわけではないし、真唯が喜んでくれるならそれでよかった。コップにミルクを入れ、テーブルへと朝食を持って行った。ソファには座らず、カーペットに座って(リビングにはテーブルがソファの前にしかなくて、軽食以外はカーペットに直接座っている)テレビをつけ、朝のニュースを流しながら食べた。普段と何が違うのかわからないニュースだった。
雨が降っていたのもあり寒さが際立つ日でもあった。明るいブルーのウールとアクリル混紡のニットにミモレ丈のグレーのスカートを着て、アウターには、真唯から貰ったサンドベージュ色したコットンギャバジンのトレンチコートを身に纏う。鏡を見ると、完璧とは言えないスタイリングだった。ぼんやりとしてる気がする。トレンチコートを着たい気持ちと、明るいブルーのニットを着たい気持ちがぶつかった結果ではあった。変ではなかったので、私はこのままで行こうと考えた。真唯の部屋を覗くと、静かに寝ていた。帰ってきた時には居なくなってると思うと、少し苦しくなる。一緒に寝た日は一段とそう感じてしまう。ドアを閉めると、玄関まで行き家をでた。
揺られる電車に乗り、会社へと向かっていた。電車のなかでは、まるで私はどこか別の世界に飛ばされてるようだった。魂を持ち忘れてきたような感覚。私という抜け殻がただ電車に揺られていた。
私のやることと言えば、カウンターで接客をすること。旅行商品の提案や予約をしている、いわゆる旅行代理店。真唯がお酒を提供するのであれば、私は旅行へのチケット提供している。真唯が夢の世界に旅立てせるのであれば、私は現実の地へ旅立てせている。嫌いな仕事ではないが、好きでもない。苦痛だと思わないだけマシなのかもしれないけど。そうして私は、どこか気絶しているような時間を過ごした。
仕事が終わり、電車を降り、駅から出るとスーパーに寄った。冷蔵庫を補充するように、野菜類、タマゴを一パック(今日見たら二つしかなかった)、牛乳(成分無調整の牛乳、私しか飲まないので好きなのを買っている)、パン、食品用ラップフィルム、私の夕食用のお惣菜を買った。濃色のブルーのマイバッグに詰め込み、スーパーを出ると酒販店が隣にある。おしゃれな酒販店で、いつの頃だったか真唯と一緒に入ったのを思い出す。店の中に入り、お酒を探した。ワイン、日本酒、ウイスキー、選び放題ではあった。私はお酒に詳しいわけじゃない、適任なのは真唯だろう。せっかくなら私が選びそうにないもので、驚かせようと思った。サファイアのような透き通るブルーのボトルが目についた。手に取ると、ジンだった。もっと、珍しい物の方がいいのかもしれないけれど、今日の気分はブルーカラーだったからこれを買った。
酒販店から出ると、冷たい風が吹いた。昨日の雨によって濁った空気は冷たい風とシェイクされ、コートで身を守らなければ荒んでしまいそうだった。一番上までトレンチコートのボタンを閉めて、首元のストラップ(スロートラッチと言うらしいが、いつも忘れてしまう)も閉めた。住宅街を通りながらマンションまで歩いた。たまにすれ違う人は寒そうに歩いていた。街灯が道を照らして、佇む建物からは光が漏れ出しているから不安はなかった。けど、寂しさは感じる。吹く風によって、歩く私が一人であるという事実に苛んだ。孤独ではないのに、この時は孤独と感じた。
鍵を開け、今は一人しかいない家に帰った。暗い一室の電気をつけ、買った荷物や着ている服を整理し、暖房を入れて冷たい部屋を暖めた。真唯の残り香が漂う、つかめない真唯の姿がそこにはあり、僅かにだが孤独さを打ち消した。
私は、すぐに夕食の準備をした(朝作ったナッツサラダと、肉じゃが、豆腐、白米、準備というほどではないが)。テレビドラマ見終わり、食べ終えれば、私はリビングから自室に行った。あのリビングは広いわけじゃないのに、一人だと余白が多すぎた。キャンバスの半分ぐらいが描かれてないみたいで。部屋で数ページだけ見たファッション誌を読んだ。載っているスタイリングは、無難であり、だけど嫌われることもない服装。真唯の読むようなものは私には似合わないから、普通のかわいい服装が載っている雑誌をこうやって見ている。時々、ある文字が目に入る。少しだけ嫌いな文字だった。私が否定されていると感じるから、嫌だった。ページをめくり、何も考えずに読んだ。読み終えると、お風呂に入り、明日の準備をして目を閉じた。
アラームの音で目を覚ましリビングに行くと、テーブルに紙が置いてあった。そこには「サラダのお返し。冷蔵庫を見て」と真唯の字で書かれてあった。冷蔵庫を覗くと、保存容器にミネストローネが入っていて、小さなケーキも置いてあった。ケーキの下には小さな紙で「朝までに食べてね」と書かれていた。ミネストローネは鍋で温め直し、パンと一緒に食べた。野菜の甘さとトマトの風味が内側から体を温めた。ふうと息を吐く、落ち着きのある息だった。このまま、ぼうっとしていたいぐらい。時計の針が、大きく聞こえるぐらいぼうっとしてた。ケーキも最後に食べた。甘くて美味しかったけど、甘さを流すためのスープを残しておけばよかったと思いながら食べた。
白のシャツにショート丈のデニムジャケットを着て、デニムパンツを履いた(シャツの裾は出してレイヤード)。そして、トレンチコートを上から羽織る。私には少し攻めたスタイリングだった。ミネストローネのスープを飲んでから、なんだかやる気に溢れていた。真唯の部屋をそっと開け、覗いた。相変わらずぐっすりと寝ていた。部屋のドアを閉じ家をでた。今日は寂しく感じることはなかった。直接会話してないのに、心の距離が近づいた気がした。
この日の仕事は、なんだか上手くいった気がする。上手くと言っても、何か変わったことが起きたわけじゃないけど。引っ掛かりがないような、そんな感じだった。
昨日と変わらない、道順で帰った(酒販店は除く、用事はないから)。住宅街の道を歩いてると、私の頭に何かが当たった。痛くはない、軽い何かだ。落ちた音も聞こえ、下に目を向けた。白い紙飛行機だった。見渡すが人も、開いている窓もなかった。どこかの誰かが飛ばしたのだろう。拾い上げると文字のような物が書かれていた。紙飛行機を解くと「最も難しいのは、行動するという決断だ」と書かれていた。
記憶にある言葉だった。思い出すまでに時間は掛からなかった。それは、真唯と一緒に見ていた、ドキュメンタリー番組で紹介されていた偉大な女性パイロットの言葉。同じ番組を見た人が飛ばしたのだろう。私は道端に捨てるのにも悪いと思い、コートのポケットに入れて帰って行った。自室にコートを掛けて、紙飛行機だった手紙を取り出した。私へのメッセージなのかと思いながら眺めた。行動する難しさはわかっている。手を握って、と真唯にすら言えない私はよく理解していた。手紙をデスクに置くと、ベッドに倒れ込んだ。口で伝えるのは難しい、その場の空気と相手のことを考えて言葉を止めてしまう。真唯は肯定してくれるだろうけど、上手く口に出せなかった。ベッドに倒れ込んでいた私はゆっくりと立ち上がった。コピー用紙とペンを手に取ってリビングに向かった。ここだったら、真唯への気持ちが書ける気がしたから。まっさらな紙に文を書く。少し正直に。
真唯に。
突然の手紙だけど、許してください。ミネストローネのスープとても美味しかったです。あと、ケーキも美味しかったです。特にスープは、体が温まって気持ちよくて今日は仕事も捗りました。真唯が初めて私に作ってくれた料理のひとつにミネストローネがあったのを思い出し、懐かしさを感じました。けど、それを伝える為にこれを書いたわけではありません。深刻なことでもないです。一応書いておかないと緊張しちゃうだろうから記しておきます。
手紙を書いた理由は、真唯と見たドキュメンタリー番組からです。紹介されていた偉大な女性パイロットの言葉を思い出したので、いま書いています。
前に、次の休日の時は家で飲みましょうと話したのを覚えていますか。寝る前とは言え、さすがに覚えていることを望みます。いつも寄るスーパーの隣にある酒販店でジンを買いました。ボトルの色が青いのです。真唯ならわかるよね?
そして、書いておいて難ですが、本当は驚かせようと思ってジンのことは秘密にしてました。書く内容を考えていたら、勝手に手が進んで書いてしまったのです。鉛筆ではないので消せません。焦りながらも、心の想いを吐くことが大切だと思い、書き直すことはしません。
家に帰ってきて、あなたが居ないことが本当に苦しく感じます。朝起きて、あなたが部屋に居ると安心はしますが、やはり苦しいです。でも、仕事を辞めて欲しいとは思いません。真唯がやりたいことやってください。本当にそう思っています。本当に。二回も本当、と書きましたがそれぐらの気持ちということです。よく、見直したら五回も書かれてました、探し当ててください。
書くことが、なくなってきたので終わりたいと思います。正しくは、言いたいことが言えた。本当はもっとありますが、満足したのでやめます。
勝手に満足して終わらせるのは申し訳ないので、謝罪をしておきたいです。いつかの、CD失踪事件はご存知でしょうか。突如起きた怪事件。ケースの中に入っていたディスクが消えた、あの事件です。家中探し回りましたね。真唯が電子レンジの中を覗いたのが、一番面白かったです。さて、ここまで言えばわかりますよね? 犯人は私です。真唯の部屋にあったマンガを借りるために、デスクにあるマンガを取ろうとしたところ、積み上がったケースが崩れ落ちました。元に戻しつつ、中身を確認していたらディスクが真っ二つに割れているのが見つかり本当に驚き、隠しました。たくさんあるので、正直バレないと思ってましたが、すぐにバレましたね。隠し場所ですが、リビングのカレンダーの裏にテープで貼り付けてあります。つまりは、磔の刑に処されています。どうかその手で救ってください。罪悪感が湧いてきたので、ここで終わります。
追伸・改めて見ると、本当、という言葉をたくさん使っていました。もはや、書き癖なのでしょう。文はここで終わりです。本当の終わりです。
私は手紙を書き終えると、半分に折り、開き、紙飛行機を作った。立ち上がると、真唯の部屋にある小さなガラステーブルに置いた。それから、ルーティンのように寝るまでの作業をすますとベッドに入った。思っていたより、不安はなかった。むしろ、なんだか心地よかった。
朝の目覚めは、アラームの音ではなかった。ふんわりとした感じだった。重力が半分ぐらいになったような、体の軽さ。私はベッドから出ると、ぐっと体を伸ばした。いつもは、仕事に行く前に真唯の部屋を覗くけど、今日はすぐに覗いた。紙飛行機の手紙が気になってしょうがなかったから。音を立てないように部屋を見ると、彼女は寝ていて小さなガラステーブルに紙飛行機は解かれ置かれていた。部屋のドアをゆっくりと閉めた。私は自分でもわかるぐらいに笑顔になっていた。嬉しかった。それから、家を出るまでのことを私は覚えてなかった。いつの間にか会社にいた。ただ、唯一覚えるのは、その日の朝食に食べたパンと目玉焼きは美味しかったこと。
家に帰ってきた時、私はもしかしたらと自室に急いだ。電気をつけると、デスクの上には紙飛行機があった。すぐにも読みたかったけど、私は息を吐き、心を落ち着かせた。とりあえずは、スーパーで買ってきた物を冷蔵庫にしまい、それから読むことにした。自室でベッドに座り、紙飛行機を持ちながら天井を見た。明るいライトが私を照らしていた。心臓の音が、うるさいぐらいだった。顔を下に向け、手に持った紙飛行機を解いた。私は手紙を読み始めた。
おはよう、澪。
わたしの時間では、まだ朝。いつもは、もっと遅いのに今日は早く起きた。まあ、それはこの手紙を書くための時間が欲しかったから。あんまり、手紙なんて書かないからたっぷりの時間が欲しくてさ。というか、普通はそんなに書かないような……わたしだけ? こんなの小学生の頃以降だから、全然わからないや。上手く伝えられるといいんだけどね。あと、こんなふうにラフに書いてるのは、恥ずかしからなのです。
澪が修正なしで書いたから、わたしもそうすることにする。とりあえずは、CD失踪事件についてだけど。無事に救出完了しましたことを、ここに申し上げます。あと、二枚に割れていると思ったら、三枚で驚いた。真っ二つって二枚に割れることじゃないの? ゴルゴタの丘ならぬ、カレンダーの丘に磔刑にされていた三枚割れのディスクをどうするか考えてる。リビングで書いてるんだけど、今まさに目の前にあるの。哀れな姿。ショックだけど、買い直せる物だから悔い改めた澪を許します。待って、買い直せない物だったら許さないってことじゃないよ。勘違いしないで。
三枚の内一枚をゴミという地獄に捨てようと思いましたが、やめた。わたしの部屋に飾ることにした。
ちょうど、飾ってきた。何故? って思うだろうけど、変な意味はないからね。二人で探し回った想いでとして取っておくことにしたの。まさに現代アート。
さて、ここからは真面目に書かざるしかないのでしょうか? なんて答えればいいか、とても難しく感じますでしょう。一緒に居たいのは、わたしもなのです。今すぐにでも、職場を爆発させて、その推進力で澪と宇宙に行きたいぐらいであります。待って、今の仕事が嫌いってことじゃないよ! あと、日本語がおかしくなってきたから、普通に書く。
最初の頃は、家に澪が居るだけで幸せだと思ってた。時々、一緒に過ごす時間もあるからそれでよかったんだけど。最近かな、誰もいないリビングがちょっと怖くなってきたの。お化けが出そうみたいなことじゃないよ。わたしの部屋に居るときも、なんだか怖くてヘッドホンを外せない時もあったぐらい。たまに澪と一緒に寝る日があるでしょ? そういう日は怖くない。目が覚めれば、家にはいなくなっちゃってるけど、澪の感覚だけは何故だか残ってる。わたしも同じ気持ちなの、一緒に居たいのは。
明日は、わたし休みだから早く帰ってきて、食事もお酒も用意しておくから。わたしの……
追伸・ああ、なんだか恥ずかしくなってきた。今すぐにでも窓を開けて、手紙を空に飛ばしたい。待って、そんなことしたら、わたしの手紙を誰かに読まれちゃう。もしも、子供が拾ったらそれこそ笑い者じゃない? この地域で永遠と語り継がれて、新たな都市伝説の幕開け。というか、澪の名前が入ってるから個人情報の流失になる。諦めます。
追追伸・一回澪の部屋に置いたけど回収した。書かなきゃいけないことを忘れてた。家で飲むって話は覚えてる、鮮明に。ジンがあるなら、あれを飲みましょうあれを。書こうと思ったけど、やっぱり秘密にする。あと、ナッツサラダとても美味しかったよ。危なく書き忘れるところだった……最後に手紙を読み終えたら、わたしの目の届かないところに置いといてください。恥ずかしさで、悶え苦しむので。
この日、私は曲が耳に残るみたいに、手紙の内容を頭の中でリピートしていた。食べる時も、お風呂に入る時も、寝る時も。幻みたいに存在していた。幻は消えてなくなるけど、この手紙は無くならない。忘れないように、失わないようにデスクの引き出しに丁寧に入れた。部屋の明かりを消しても寂しくはなかった。
今日の気温は暖かった。昨日よりも、ちょっと暖かった。数字以上に伝わった。朝食はパンだけ食べた(ミルクも飲んだ)。真唯の部屋を開けることはせずに家を出た。最後に開けなかった日はいつかも覚えてないぐらい前で、日課のような動作を今日はやらなかった。電車のなかでの空虚な感覚は滑り落ち、向かう駅に繋がる線路がはっきりと見え。電車の窓からの太陽の光は眩しかった。
仕事が楽しいかと聞かれれば口を噤むが、そういう時も感じるのは実感できた(正確に言えば、思い出したが正しい)。楽しみを取って置いてるような、ケーキに乗ったイチゴを最後に食べる愉しみを感じながら、仕事を終えて、電車に乗り、道を歩いた。
風は、私の体を軽快に通り抜ける。涼しいとさえ感じた。強い風が吹き上がり、髪が乱れたけど気にならなかった。マンションに着くと、私は玄関の前で立ち止まった。色々、頭の中の考えを真っ白にしたかったから。白いペンキを頭の中でぶちまけた。どこもかしこも、ぶちまけた。気持ちを整えるとか、そういうのじゃなくてただ白くしたかった。塗りたくりすぎて、ぽたぽたとペンキが落ちるぐらいに。私は次の色をはっきりと見たかったから。
玄関に入ると「ただいま」と私は言った。
リビングから真唯が顔を出して「おかえり」と言った。
コート置いてくるね、と私は言い、自室にコートを掛けると何も考えずに、リビングに足を進めた。いい匂いがした。
真唯はテーブルにスープらしきものを置いているなか、私は聞いた「それは?」
「とっても美味しいボルシチ、温まると思って。それとサーモンパテ」立ち上がり、キッチンに向かい戻ってくると「そして、宅配ピザでございますお嬢様」
「これはこれは、庶民的ですわね」
「トスカーナ州の赤ワインもございます」
「あら、悪くないわね」
真唯はくすっと笑い「どこだかわかるの?」
「まったくわからない」と言い私も笑った。
私と真唯はカーペットに座り、食べ始めた。ボルシチのスープをひと口すくい上げ飲んだ。
「酸味もちょうどよくて良い、真唯の作るスープはいつも本当に美味しい」
真唯はその言葉を聞くと口角を上げながら、ボルシチを口に入れた。照れを隠すみたいに。
「ありがとう。作ったかいがある」と真唯は言った。私がボルシチに入っている牛肉に食べると「牛肉は固さはどう?」と聞いてきた。
「うん、固くないよ。昔作った、ローストビーフは火が通りすぎて固かったけどね」
「その話はもうやめてよ。怖くて温めすぎちゃっただけなんだから」そう言うと真唯は赤ワインを飲んだ。
「そういえば、ジンは?」私はワイングラスに注がれた赤ワインを手に取った。
「食べ終えてからの、お楽しみで――」
「ふーん」赤ワインを飲んだ。
ボルシチと赤ワインを交互に口に入れ、手をつけるの忘れていたピザを見て、私は真唯に聞いた。
「なんだっけ、このピザの名前……」
「嘘でしょ? 忘れたの? 有名じゃん。マから始まるやつ」
「マ、マ……」ど忘れしてしまい、私はこう言った「……マルガレーテ」
「えー、マルゲリータでしょ。酔うの早すぎない?」
「マルまでは合ってるからセーフ……」
「本命まで酔い潰れないでよ」
ピザを三枚残し、それ以外は食べた。気分になったら、少しずつピザを食べることにして私はソファに座った。体の芯からぽかぽかとしていた。ソファがなんだか、マシュマロに見えて真唯いなければかじりついてた。その思考になんだか笑いがこみ上げてきて、微笑んだ。真唯はキッチンから氷の入ったミキシンググラスとバースプーンに冷やされたカクテルグラス、オリーブとレモンピール、冷えたジンともう一つお酒を持ってきた。
「それは?」持ってきたお酒を指した。
「ベルモット。澪がジン持ってきたからね」
ミキシンググラスにジンとベルモットを入れた。ジンに対してベルモットは添えるような量だった。バースプーンでからからと音を立てながらステアしていた。じいっと見つめるが、からから音がなんだかあやされているように感じた。時間の感覚が虚ろになってゆく。柔らかく伸びているような、だらんと落ちそうな気分だった。全ての物事が滑らかに、這っていた。ステアが終わり、カクテルグラスに注がれるとオリーブが静かに添えられた。レモンピールが振りかけられると、私の前にそっと置いた。
「澪できたよ」と真唯は言った。
「これは?」
「マティーニ。名前ぐらいは知ってるでしょ?」
「うん。真唯も自分の作って――」酔いを醒ます為の時間がちょっとだけ欲しかった。
真唯は自分のマティーニも作り始めた。意識をはっきりさせるために私は聞いた。
「マティーニって、ジンの方が多いんだ――」
「そうだよ、ベルモットは少しだけ……」
私はベルモットが少しなことが不満だった。
「手紙――良かった」真唯の顔を見た。
「この場で言われると恥ずかしいなあ。わたしの文ひどかったでしょ?」
「そんなことないよ、とても心が伝わった」
「澪のもね――」真唯は私の方を見ると「手紙……まだ、あるの?」
「それが窓開けたら、鳩が口に咥えて持ってちゃった」
「ふふ、本当だったら面白い。もし、咥えたとしたら戻ってくると思う?」
「――戻ってくるよ、ハウランド島に届いたあとにね」
「読まれるのは嫌だなあ」
「平和なのが伝わる――」私は窓を見た。
真唯は自分のマティーニを作り終えると、ソファに座った。それに合わせて、ゆっくりと体を起こした。話したら気分が良くなった。
「ほら、澪も持って」真唯に言われ、私はカクテルグラスを持った。
「――ねえ、ジンとベルモットを半分ずつ入れてオリーブを抜いたらどうなるのかな?」カクテルグラスを目の高さに上げて、マティーニを見つめた。
「マティーニではなくなっちゃうと思うけど」
「そうなんだ――長い時間を掛けて少しずつ比率を変えたとしても?」
「うーん、どうなんだろうね。もしかして澪、酔ってる?」
「うん、間違いなく酔ってる。ただ、気になっただけ」私はカクテルグラスを真唯の方に向けた。呼応するように、真唯もグラスを向けた。空いた手を、ソファを這うように真唯に近づけると「手を握って」と私は言った。
真唯は一瞬驚きつつも、柔らかい表情になり私の手を握った。その手は温かかった。