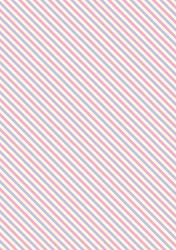味噌ちょい足しバニラアイスのせ激辛ラーメンは俺の中でも定番となり、甲斐は毎日やってくる。漫画は巻を重ねるごとにえっちな成分が薄れ、その代わりにシリアスなエピソードでぐいぐい読ませる内容になっていた。
「あれ?」
いつも帰る頃には宅配BOXに入っている通販の荷物が、今日に限って空だ。
あいつ、昨日も続きポチってたよな――?
今日着の予定だったはずだ。いぶかしく思う俺の耳に、スマホのバイブ音が届く。
『すみません、××運輸の者なんですが』
受信をタップして聞こえてきたのは、配達員さんの声。なんだかめちゃくちゃ恐縮している。
『すみません、実はちょっと積み込みミスがあって、そちらにお伺いするのがいつもより遅くなりそうなんです。一時間ほどみていただきたいんですがよろしいでしょうか?』
どうやら走り回りながら電話しているらしく、お兄さんの息は苦しげに弾んでいた。悪いのは毎日ちまちま買い物をする俺のほうだし、元々時間指定なんかしてなかった代物だ。大丈夫ですと答えて電話を切った。
「さて」
ここのところ帰宅してすぐ買ったものの「開封の儀」を執り行うのが常だったから、急に時間がぽっかり空いてしまった。約束しているわけでないので、甲斐が何時に来るかはわからない。
「――塾の課題、やっとくか」
俺は本棚から参考書を取り出した。
なにも俺は毎日甲斐に振り回されているだけではない。(のだ!)土日には塾に通っている。
生れながらの不運と病弱がたたって今の学校に進学せざるを得なかった。でもまだ転入試験を受けて上の高校に行くという希望は残されている。そのための勉強だ。
これも甲斐が勝手にポチった、星型の折りたたみテーブル(使いにくい)を出し、参考書を広げる。
俺の存在に関心が薄い両親だが、幸い頭の良さは授けてくれた。自分たちが研究に生きているんだから、まさか学校を受け直したいと言って反対されることはないだろう。
勉強は好きだ。
将来なんになりたいかなんて真剣に考えたことはまだないけど、少なくとも今よりいい学校に行きたいという欲はある。
編入するなら早いにこしたことはないだろうから、夏休み明けには試験を受けたい。夏なら、インフルの心配も少ないだろうし。
夏。あと、数ヶ月。あほ高に通うのも、それまでの辛抱だ――
ふと、胸のあたりをよぎったものがあった気がした。
ん?
なんだろう。
どこから吹き込んできたかわからない、だけど確かに一瞬ひやっとする風みたいなものが。
なんだ、今の。
体調不良の予兆だろうか。早めに風邪薬飲んでおいたほうがいいか――数式を書き付ける手が止まったところで、インターホンが鳴った。
荷物より先にやって来た甲斐が、片付け切れていなかった参考書たちに目を留める。その、初めて鏡に映った自分の姿を目にした子犬みたいな顔。
ヘイ、シリ。多分こいつ家で勉強する同級生を見たことがない。
「漫画まだ来てない。今日遅れるんだって」
俺は再びテーブルの前に戻る。甲斐はなんだか俺を遠巻きにしながらラグのはしっこのほうに腰を下ろして、積んであった漫画を手に取った。
「それ、もしかして勉強してんの?」
「もしかしなくてもしてる。おまえもする?」
「いやいやいや」
甲斐は怯えるように首を振った。面白い。どうやら今日は主導権がこっちにある。
「俺とかがやっても意味ないだろ」
「意味なくない。おまえ、地頭悪くないじゃん」
薄々感じていたままを俺は口にする。
一瞬でうちの住所を記憶した。
なにをやらせても手際がいい。
段々えっちなだけじゃなくヒューマンドラマの要素が強くなってきた漫画だってちゃんと楽しんでる。
「本気でやったら、勉強けっこうできるんじゃないの」
いつも教室の真ん中、人の机の上に腰かけてばか笑いしている甲斐の友人たちからは、なんとなく「勉強なんかする奴のほうがおかしい」みたいな空気を感じる。
そうやって落ちこぼれの自分から目をそらしてる。
そんな環境の中で、今までの甲斐はたまたま勉強する機会がなかっただけなんじゃないか。
「……おまえらみんな俺より体がでかくて、丈夫で、本気になったらきっと俺よりなんでもできるはずなのに。それをしないっていうのが、腹立たしい」
使わないんなら俺にくれよ、そのいかつい体。
「意味ないとか、無駄とかいうのは、やらない自分から目をそらしたい奴が言うことじゃん」
気づいたらシャーペンを強く握り込んでしまっていて、はっと我にかえった。
毎日顔を合せているから慣れが生じてしまった。今のは明らかにスクールカースト上位様に対して、分を過ぎた発言だった。
高校生にもなれば、人間には生れながらの格や住む世界の違いが存在していて、それを踏み越えればろくな目に遭わないなんてことはわかってる。
初日と同じ過ちに青ざめる。学習しない俺は、人のことなんかどうこう言えないあほだ。
恐る恐る顔を上げると、漫画を読んでいたはずの甲斐は、あぐらをかいた足の間に漫画を伏せて、じっとこちらを見ていた。眼差しは鋭い。
――ヒッ
震え上がったちょうどそのときインターホンが鳴って、俺は飛び上がるようにして玄関に向かった。