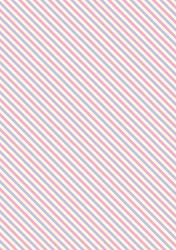翌日、俺は学校を休んだ。
休んで家にいたので、荷物は直接受け取った。こんなもの、このまま捨ててやったっていいのに、そうできない。
「休んでるのに、悪かったな。これ」
やってきた甲斐が差し出した金は、ちゃんと封筒に入っていた。チャラい陽キャのくせに、こういうところはちょっと大人みたいなことをする。そういう奴なのだ。
「じゃ、ちゃんと寝てろよ」
甲斐は玄関先でそう告げ、あっさり背を向ける。
あっさり? 当たり前だ。俺はカツアゲ犯にたかられてるだけだ。ものがなければわざわざ上がっていくわけなんかない。
友だちじゃないんだから。
だいたい、勝手に買い物されて迷惑してたんだから。
ドアを閉めたらひとりになれる。またスマホでサイトを巡って、ひとりでなんでも好きなものを買える。
ひとりで――
「友だちじゃないくせに、友だちみたいな指図すんな」
気づいたら、そう吐き出していた。
甲斐がドアの前で振り返る。
言葉をぶつけたのは自分のほうだったのに、俺はうつむいた。
だって絶対「なにこいつ、キモ」って顔されてるに決まってる。
なにやってんだ俺。
こんなの陰キャの分を超えてる。
このまま帰せばたぶんもう甲斐はやって来なくて、カツアゲから解放される。のに。
ぐるぐるわけのわからない感情が一気に押し寄せる。吐きそうになりながら、それでも俺の言葉は止まらなかった。
「……昨日、聞いたんだからな、コンビニで」
こんなこと言ってやったって、どうせ一ミリも響かないのはわかってる。
カースト上位様は俺みたいな奴のこと、最初からたかっていい奴程度にしか思ってない。便利に使って、それで終わりだ。
けれど俯いた俺の視界から、甲斐のつま先は動かない。
面を上げると、甲斐は俺のキモい態度なんか気にも留めない様子で、目をぱちくりさせていた。
「だって俺みたいなやつと友だちだって思われたら、おまえが嫌じゃん?」
照れるでもなく。おもねるでもなく。考えたことが脳味噌から直接出ちゃいましたみたいな様子で。
思えば甲斐は、いつでもそうだった。
なんだそれ。
なんなんだよ、それ。
体中から力が抜けていく。
おまえはスクールカースト上位の陽キャで。
俺のことなんか都合のいい財布としか思ってないはずだろ。
……そうあってくれないと、困るだろ。
通販で買えないものの扱いなんて、俺にはわからない。
俺は、ふう、とため息をついた。
「……あがってけば」
「具合、悪ィんじゃねーの?」
「ただのサボりだよ」
「おまえサボりとかできんだな――あ、なんかジンジャエールいっぱいある」
「――懸賞で当たった」
「へー、すげえな」
俺の嘘をあっさり信じて、甲斐は俺の部屋にそれを運び込む。今ではすっかり居心地の良くなった部屋に。
相変わらず、こいつと俺の関係がなんなのかはよくわからない。
でも、もうひとりで通販サイトを何時間も眺めて過ごすことはなくなるんじゃないか。
そんな気がしていた。
〈了〉