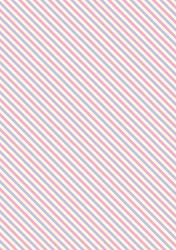くそ、くそ、くそ、と思いながら、俺、相川究は今日も大手通販サイトをスマホで眺める。
休み時間の教室に満ちる、ばかみたいで意味不明な笑い声が耳に入らないように。
高校受験の当日、俺は不運にもインフルエンザで寝込んだ。
ここはそんなことでもなければ絶対に来なかった、この辺りで一番低ランクのあほ高校だ。
あほ高唯一の美点。それはゆるゆるな校則。〈スマホは朝一番に先生に預け、帰りに返却される〉なんていうまどろっこしい決まりもないから、こうして好きなときにいじることができる。
通販サイトの俺のアカウントは、親から小遣いが振り込まれるバンドルカードと紐付けられていた。つまりその範囲内でなら、好きなものがタップひとつでいつでも買える。
「自分でお金の使い方や善悪を判断するのも勉強だから」と、小学生のときからずっと続いているスタイルだ。
うちの両親は、どっちも企業のやり手研究者だった。
父親は研究者にやさしくない日本に見切りをつけ、海外に行ったきり何年も帰ってこない。直接顔を合せたのはもう何年前なのか、ちょっと記憶が怪しい。母親もそんな状況をまったく気にしていないようだった。もっとも、そんなことを深く話し合うほど顔を合わせはしない。
なんでそんなふたりが結婚して子供まで作ったのか、と思うだろう。
その通り。ふたりとも結婚なんかするつもりはさらさらなかった。だけど「人は結婚してこそ一人前」という時代錯誤な考えの上司に当たってしまったのが運の尽き。
しないと出世が望めないという、お互いの利害が一致しての結婚。
結婚したら次は「やっぱり人間は子育てを経験しないと成長しない」云々とやられたのと、「こうなったら研究者として自分の腹の中で子供が育つという興味深い事象を一度は経験しておくかと思った」という母親の考えのもと生まれたのが、俺。
臨月も臨月、生まれるその日まで働いていた母親から未熟児で俺は生まれた。高校生になった今も体は未熟なままで、身長は百六十そこそこだし、しょっちゅう体調を崩す。
受験期にインフルエンザにかかっていたのは、どうしようもない生れながらのフィジカルの弱さ、そして「持ってなさ」だった。
腹の中で生命体を生成して満足したらしい母は、その後の子育てにはまったく興味を持てなかった。
「人にはそれぞれ向き不向きがある。細やかな愛情は注げない代わり、金銭的には絶対に不自由させない」があの人の誓いで、それゆえのバンドルカードだった。つまり「自分でお金の使い方や善悪を判断するのも勉強だから」は、ていのいい口実にすぎない。
脳味噌より体に栄養が回る奴らばかりなのか、教室の真ん中あたりではしゃいでいる奴らはみんな背が高い。俺とだと、大人と子供くらいの差がある。
もちろん友だちなんて、未だにできない。スマホと通販サイトだけが俺の休み時間の共だ。
そういえば、そろそろストックがないな。
履歴から手早く袋麺を検索して、ポチる。食事は親の雇った家事代行サービスの人が作っておいてくれるが、これは夜食用だ。気が向いたときに、ひとりで食べる。
「たまにはジャンクなモノも食べたいよねー」という気持ちを共有する相手も、俺にはいないのだった。
ポチっとしたところで、教室の真ん中がまたどっとわく。ちらっと横目でうかがうと、奴らの態度はどんどんエスカレートして、何人かは机の上にどかっと座っていた。あの辺の席でなくて良かったと俺が心底震える間にも、座った机の上から誰かの椅子をがしがし蹴って爆笑している。
毎日毎日顔つき合せて、なにをそんなに話すことがあるんだろう。そんなに楽しいことが?
……別にぜんぜん気にならないけど。ぜんっぜんまったく一ミリも羨ましくなんかないけど。
俺は笑い声に対抗するように、欲しいものをどんどんカートに入れていく。漫画、ゲーム、スナック菓子に飲み物。母親は履歴を確かめることもしないから――そんなことに時間を使いたくないんだろう――なんでも、好き勝手に買える。
親の詮索なしに、好きなものを好きなときに買える。俺と同じ年代の奴からしたら、きっと夢みたいな話。
だけどオンラインショッピングって、楽しいのは初めのうちだけだ。
なんでもあって、なんでもあるから、段々どれでもいいような、いっそどれも欲しくないような気がしてくる。
俺の欲しいものって、なんだったっけ?
そのとき、ふっと画面に影がさした。
「それ、買い物してんの?」
いつもなら教室の真ん中で喋ってる陽キャ代表、甲斐大河が俺を見下ろしていたからだ。鞄を片手で肩に担いで。
同じ一年だっていうのに、百八十近くある奴にそうされると、巨人のごとき圧迫感がある。ツーブロックにした髪型の、上の方は金色。制服はブレザーだが、ジャケットもシャツの胸
元も、注意された数分間しかとまっているのを見たことがない。もちろんネクタイははずしてポケットに突っ込まれている。
そんなだらしない着こなしでも、俺と同じものを着ているとは思えないほどこなれて見えるんだから人生は不公平だ。心臓がちりっとひっかかれたみたいな不快感。持って生れたフィジカルのアドバンテージにはどうやったって勝てないんだと痛感する。
あいかわとかい。出席番号順で席は前後だけれど、直接話すのはこれが初めてだった。
「通販て、コンビニだるくない?」
「こんびに?」
「支払い」
間抜けに聞き返して、やっとわかった。
未成年はカード支払いが使えないから、せっかくオンラインで買い物しても、コンビニ支払いか代引きになる。
だから普通はそのめんどくささを受け入れるか、親のアカウントで買い物してもらうことになるけど――この学校の連中のような輩は、色々親バレしないものを買いたいのだろう。
俺より図体がでかくてクラスの中心のクソ陽キャでも、しょせん子供は子供。好きなものも自由に買えないのだ。
そう思うと俺は俄然得意になって、頼まれてもないのに説明してやった。
「バンドルカードってのがあって、親がそこに小遣い入れといてくれるから、その範囲ならなんでも好きなもの買えるんだ」
甲斐の顔が驚きに満ちていく。
「へえ、いいなおまえんち」
「いいってほどのことじゃ……」
否定しつつ、内心ほくそ笑む。「いいな」なんて言葉をスクールカースト上位の奴から引き出して、俺は完全にいい気になっていたのだと思う。
その油断を見透かしたように、さっと甲斐がスマホを取り上げた。
俺が取り返す間もなく素早く操作して、支払い完了ボタンを軽やかにタップする。
「な、なにす……!」
「おー、大河、遅刻〜?」
うろたえる俺をよそに、教室の真ん中からはからかう声が飛んでくる。
「重役出勤だっつーの」
甲斐はそう応じると、俺のほうを見もせずにスマホを放って返す。見もしないのに「キャンセルすんなよ」と付け足すのは忘れずに。
休み時間の教室に満ちる、ばかみたいで意味不明な笑い声が耳に入らないように。
高校受験の当日、俺は不運にもインフルエンザで寝込んだ。
ここはそんなことでもなければ絶対に来なかった、この辺りで一番低ランクのあほ高校だ。
あほ高唯一の美点。それはゆるゆるな校則。〈スマホは朝一番に先生に預け、帰りに返却される〉なんていうまどろっこしい決まりもないから、こうして好きなときにいじることができる。
通販サイトの俺のアカウントは、親から小遣いが振り込まれるバンドルカードと紐付けられていた。つまりその範囲内でなら、好きなものがタップひとつでいつでも買える。
「自分でお金の使い方や善悪を判断するのも勉強だから」と、小学生のときからずっと続いているスタイルだ。
うちの両親は、どっちも企業のやり手研究者だった。
父親は研究者にやさしくない日本に見切りをつけ、海外に行ったきり何年も帰ってこない。直接顔を合せたのはもう何年前なのか、ちょっと記憶が怪しい。母親もそんな状況をまったく気にしていないようだった。もっとも、そんなことを深く話し合うほど顔を合わせはしない。
なんでそんなふたりが結婚して子供まで作ったのか、と思うだろう。
その通り。ふたりとも結婚なんかするつもりはさらさらなかった。だけど「人は結婚してこそ一人前」という時代錯誤な考えの上司に当たってしまったのが運の尽き。
しないと出世が望めないという、お互いの利害が一致しての結婚。
結婚したら次は「やっぱり人間は子育てを経験しないと成長しない」云々とやられたのと、「こうなったら研究者として自分の腹の中で子供が育つという興味深い事象を一度は経験しておくかと思った」という母親の考えのもと生まれたのが、俺。
臨月も臨月、生まれるその日まで働いていた母親から未熟児で俺は生まれた。高校生になった今も体は未熟なままで、身長は百六十そこそこだし、しょっちゅう体調を崩す。
受験期にインフルエンザにかかっていたのは、どうしようもない生れながらのフィジカルの弱さ、そして「持ってなさ」だった。
腹の中で生命体を生成して満足したらしい母は、その後の子育てにはまったく興味を持てなかった。
「人にはそれぞれ向き不向きがある。細やかな愛情は注げない代わり、金銭的には絶対に不自由させない」があの人の誓いで、それゆえのバンドルカードだった。つまり「自分でお金の使い方や善悪を判断するのも勉強だから」は、ていのいい口実にすぎない。
脳味噌より体に栄養が回る奴らばかりなのか、教室の真ん中あたりではしゃいでいる奴らはみんな背が高い。俺とだと、大人と子供くらいの差がある。
もちろん友だちなんて、未だにできない。スマホと通販サイトだけが俺の休み時間の共だ。
そういえば、そろそろストックがないな。
履歴から手早く袋麺を検索して、ポチる。食事は親の雇った家事代行サービスの人が作っておいてくれるが、これは夜食用だ。気が向いたときに、ひとりで食べる。
「たまにはジャンクなモノも食べたいよねー」という気持ちを共有する相手も、俺にはいないのだった。
ポチっとしたところで、教室の真ん中がまたどっとわく。ちらっと横目でうかがうと、奴らの態度はどんどんエスカレートして、何人かは机の上にどかっと座っていた。あの辺の席でなくて良かったと俺が心底震える間にも、座った机の上から誰かの椅子をがしがし蹴って爆笑している。
毎日毎日顔つき合せて、なにをそんなに話すことがあるんだろう。そんなに楽しいことが?
……別にぜんぜん気にならないけど。ぜんっぜんまったく一ミリも羨ましくなんかないけど。
俺は笑い声に対抗するように、欲しいものをどんどんカートに入れていく。漫画、ゲーム、スナック菓子に飲み物。母親は履歴を確かめることもしないから――そんなことに時間を使いたくないんだろう――なんでも、好き勝手に買える。
親の詮索なしに、好きなものを好きなときに買える。俺と同じ年代の奴からしたら、きっと夢みたいな話。
だけどオンラインショッピングって、楽しいのは初めのうちだけだ。
なんでもあって、なんでもあるから、段々どれでもいいような、いっそどれも欲しくないような気がしてくる。
俺の欲しいものって、なんだったっけ?
そのとき、ふっと画面に影がさした。
「それ、買い物してんの?」
いつもなら教室の真ん中で喋ってる陽キャ代表、甲斐大河が俺を見下ろしていたからだ。鞄を片手で肩に担いで。
同じ一年だっていうのに、百八十近くある奴にそうされると、巨人のごとき圧迫感がある。ツーブロックにした髪型の、上の方は金色。制服はブレザーだが、ジャケットもシャツの胸
元も、注意された数分間しかとまっているのを見たことがない。もちろんネクタイははずしてポケットに突っ込まれている。
そんなだらしない着こなしでも、俺と同じものを着ているとは思えないほどこなれて見えるんだから人生は不公平だ。心臓がちりっとひっかかれたみたいな不快感。持って生れたフィジカルのアドバンテージにはどうやったって勝てないんだと痛感する。
あいかわとかい。出席番号順で席は前後だけれど、直接話すのはこれが初めてだった。
「通販て、コンビニだるくない?」
「こんびに?」
「支払い」
間抜けに聞き返して、やっとわかった。
未成年はカード支払いが使えないから、せっかくオンラインで買い物しても、コンビニ支払いか代引きになる。
だから普通はそのめんどくささを受け入れるか、親のアカウントで買い物してもらうことになるけど――この学校の連中のような輩は、色々親バレしないものを買いたいのだろう。
俺より図体がでかくてクラスの中心のクソ陽キャでも、しょせん子供は子供。好きなものも自由に買えないのだ。
そう思うと俺は俄然得意になって、頼まれてもないのに説明してやった。
「バンドルカードってのがあって、親がそこに小遣い入れといてくれるから、その範囲ならなんでも好きなもの買えるんだ」
甲斐の顔が驚きに満ちていく。
「へえ、いいなおまえんち」
「いいってほどのことじゃ……」
否定しつつ、内心ほくそ笑む。「いいな」なんて言葉をスクールカースト上位の奴から引き出して、俺は完全にいい気になっていたのだと思う。
その油断を見透かしたように、さっと甲斐がスマホを取り上げた。
俺が取り返す間もなく素早く操作して、支払い完了ボタンを軽やかにタップする。
「な、なにす……!」
「おー、大河、遅刻〜?」
うろたえる俺をよそに、教室の真ん中からはからかう声が飛んでくる。
「重役出勤だっつーの」
甲斐はそう応じると、俺のほうを見もせずにスマホを放って返す。見もしないのに「キャンセルすんなよ」と付け足すのは忘れずに。