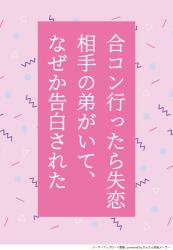土曜日のよく晴れた朝、僕はフミヤ先輩の家の前に立っていた。
少し、いやだいぶ胸がバクバクしている。手のひらに汗が滲み、インターホンを押そうとした指が、わずかに震えていた。
もじゃもじゃか、イケメンか。
そんな思いが、頭の中を駆け巡る。できればイケメン姿のフミヤ先輩に出迎えてもらいたい。傲慢な願望を持ちながら、僕はここに来るまでの経緯を思い返していた。
すべては先日の雨の日、先輩から借りたハートの傘から始まった。
その日の夜のこと。お風呂上がりの僕は、いつものルーティンでスキンケアに励んでいた。その時、突然スマホが鳴り始める。この時間にかけてくるのは、モモだけだ。
「もしもーし」
ろくに画面も見ずに通話ボタンをフリックし、パックを顔に貼り付ける。モモに話したいことがたくさんある。学校でもじゃもじゃのフミヤ先輩に会ったこと、先輩に膝枕をしたこと、そして電車で一緒に帰ってさらに心を掴まれてしまったこと、カフェで見た先輩の姿はやっぱりかっこよかったこと。怒涛のように起こった今日の出来事をモモに伝えようと、「ねえ、モモ聞いて」と口にしようとした瞬間。
『さっちゃん、こんばんは』
聞き慣れた低い声に、心臓が跳ね上がった。明らかにモモじゃない。
「フ、フミヤ先輩!」
驚きのあまり、声が裏返る。しかもビデオ通話だったようで、画面に先輩の姿が映っている。ハーフアップでもなく、もじゃもじゃでもなく、お風呂上がりなのか、濡れた髪がまっすぐに下りていた。
『あ、さっちゃん、パックしてる』
先輩の言葉に、急に恥ずかしさが込み上げてくる。普段見せない素の自分を、なんの防御もなく先輩に見られてしまった。
「せ、先輩、待ってください! 今、ビジュ悪すぎる……! メイクするので、あと二時間だけください!」
『なげーよ』
先輩の屈託のない笑い声が、耳に心地よく響く。フミヤ先輩はスマホを持ち、ベッドに寝転がったようだった。画面越しに見える、無防備な先輩の表情。妙な親密さを感じて、胸がドキドキする。まるで同じベッドの上に乗っているみたいな錯覚を覚え、僕は慌てて言葉を発した。
「えっと、フミヤ先輩、ハートの傘、ありがとうございました。おかげさまで、僕の大事な髪と顔面を濡らさずに帰れました」
本当は鞄の中に折りたたみ傘があったけれど。
『あーそれそれ』
「え? どれですか?」
『その傘なんだけど……』
何か言いたげな様子の先輩に、やけに緊張が高まる。
『さっちゃんさ、傘返しに俺んちこない?』
「……え?」
もちろん、傘は返しにいくつもりだったが……、フミヤ先輩の家? まるで心臓が一拍分、止まったような気がした。
『妹たちに傘貸したって言ったら、会いたい会いたいってうるさくてさ。それに、さっちゃんとした約束のこともあるし、ぜひこの機会に俺のことを、知ってもらおうじゃないかと』
穏やかで優しい先輩の声を聞きながら、指切りをして交わしたあの言葉が頭の中でよみがえる。
――ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく。
僕があんなにも突然にアプローチをして、フミヤ先輩もさぞ困惑したと思う。それでも先輩は、本当に誠実に僕と向き合おうとしてくれているのだ。泣きたくなるほど嬉しいのに、僕は心の奥底で小さな不安にも似た何かが芽吹いていくのを感じていた。
そして今、僕は先輩の家の前に立っている。インターホンを押そうとした瞬間、突然の自意識に襲われる。慌ててミラーを取り出し、こっそりと顔をチェックした。
髪は乱れていないか、肌の状態は大丈夫か、ヘアピンは曲がっていないか、服はしわくちゃになっていないか、イヤリングは取れていないか。先輩の前では完璧でありたい。そんな気持ちが胸いっぱいに広がる。
リップを少しだけ塗り直した。
大丈夫、今日も僕はかわいい。
よし、と覚悟を決めて顔を上げた瞬間、空から声が降ってきた。
「とってもかわいいよ、さっちゃん」
「なっ!?」
驚きの声を上げると同時に、二階の窓から覗く先輩の姿が目に入る。ずっと見られていたらしく、イケメンバージョンのフミヤ先輩がこっちを見下ろし、楽しそうに笑っていた。
「いらっしゃい。場所、すぐわかった――」
「さっきの最低ですからね!」
玄関を開けてくれた先輩を見るなり、僕はグーパンチを繰り出した。けれど、僕の手は呆気なく、彼の大きな手にすっぽりとおさまってしまう。攻撃はもう意味をなさない。それどころか、フミヤ先輩の手の温もりに、僕のほうがノックアウトされそうだった。
「ごめんね。さっちゃんが家わかるかなって見てたんだけど、かわいくてつい」
先輩はワッフル素材の白いロンTに、シンプルなブラックのデニムパンツを合わせていた。ハーフアップにセットされた髪と、シルバーの小ぶりなピアス。先輩は自分に似合うものをちゃんと理解しているみたいだ。初めて見る私服姿はあまりに僕のドストライクで、胸が苦しくなってくる。
「……今日はオンモードなんですね」
「そう、午前中シフト入ってたから」
その言葉を聞いた瞬間、胸がちくりと痛んだ。バイト終わりだったから、イケメン姿のフミヤ先輩だったらしい。僕のためにおしゃれしてくれたわけではなさそうで、少しだけ残念に思う。それに比べて僕はといえば、いつもは自分のためだけにするオシャレだけれど、今日は特別に先輩のためもプラスして、上から下までオシャレをしてきた。意識しているのは僕だけですか、ふーんそうですか。ていうかちょっと拗ねましたけど、何か。
「傘、ありがとうございました。それと、お土産です」
頬を膨らませて、ぐいっと傘とお土産を差し出す。
「手ぶらでいいのに。なんなら別に傘もよかったし。……てか、今日の髪も似合ってんね。ちょっとウェーブ入ってる」
冗談めかして、先輩が僕の髪にそっと触れる。先輩の言うとおり、せっせとヘアーアイロンで、髪をウェーブ巻きにしてきた。気づいてくれたのは嬉しいけれど、こんなにも張り切っている僕に対し、フミヤ先輩は悲しいくらい自然体だった。しかも、僕のスタイリングが崩れないよう、優しく髪に触れてくる仕草に、胸が勝手にときめいてしまって内心はとても複雑だ。
「お土産、何買ってくれたの?」
「トゥンカロンです。妹さんがいらっしゃるって言ってたから、映える系がいいかなと思って」
「ああ、トゥンカロン! 韓国のやつだよね? あいつらめっちゃ好きだから、喜ぶよ」
さすがカフェ店員のフミヤ先輩だ。トゥンカロンは先輩の言うように韓国発祥の進化系マカロンで、マカロンよりもボリュームがあり、動物型だったり花型だったり、見た目のレパートリーも多くてとてもかわいい。
「……あ、立ち話もなんですし、上がって上がって」
「お邪魔しまーす」
靴を揃え、用意してもらったスリッパに履き替えた。先輩のあとを追ってリビングに足を踏み入れると、自分の家の匂いとは違う、どこか懐かしい匂いがした。リビングは僕の家よりこぢんまりとしているけれど、暖かな雰囲気に包まれている。大きな窓から差し込む陽光が、部屋全体を明るく照らしていた。フミヤ先輩みたいに優しい家だ。
失礼にならないよう気をつけながら、でも好奇心を抑えきれず、僕は部屋を見回した。テレビとソファ。タンスの上にはかわいいヘアゴムが入った透明な容器。
「そういえば、妹さんたちは?」
「今、部活。演劇やってんだけど、あと三十分くらいで帰ってくると思う。ガチでうるせぇから、覚悟してね、さっちゃん」
フミヤ先輩によく似た『うるさい女の子バージョン』を思い浮かべ、僕はこらえきれず、ふふっとのんきに笑っていた。次の瞬間、先輩が僕の心を揺さぶるような発言をするまでは――。
「さっちゃん、あいつら帰ってくるまで、フミヤ先輩のルームツアーでもする?」
好奇心には抗えず、僕は『フミヤ先輩のルームツアー』を開催してもらうことにした。
二階の角部屋。フミヤ先輩の部屋に初めて入った時の率直な感想は、『フミヤ先輩の匂いがする』だった。先輩がいつもしているブランド物の香水の香りを、肺いっぱいに吸い込む。
「なんも楽しいのないけど」
壁は落ち着いたグレーで塗られ、モダンな雰囲気を醸し出していた。初めて遊びに来た先輩の部屋だけれど、それほど初めてな気がしないのは、以前、ビデオ通話で見たことがあったからだ。
本棚には、ラテアートの本、それからファッション誌と小説が並んでいる。その中に僕も読んだことがある小説を見つけて、とても嬉しくなった。部屋の隅には、スタイリッシュなハンガーラックが置かれ、先輩のオシャレな私服がかけられている。
「すごくいいと思います、先輩の部屋。清潔感があって、いい匂い。あ! ベッドも大きいですね!」
先輩の体が悠々入るくらい、大きくて居心地が良さそうだ。シンプルなグレーのベッドカバーが、部屋全体の雰囲気と見事に調和している。僕はベッドに座り、ご機嫌に先輩を見上げた。
「おー、うれしい。さっちゃんに褒められるとマジでうれしいわ」
先輩は本当に嬉しそうに目を細め、僕の隣に座る。その距離の近さに、少しだけ心臓が高鳴った。
「あれ? さっちゃん、ピアスの穴開いてたっけ? 似合うね」
先輩の視線が耳に注がれる。突然、僕はどう振る舞っていいかわからなくなってしまった。
「……ピアスじゃなくて、イヤリングです。穴は怖いから、開けたことなくて」
今は言葉を絞り出すので精一杯だ。
「そっか、痛いもんね。いいよ、さっちゃんは開けなくて」
何を考えているのか、先輩は静かに僕の耳に手を伸ばした。鮮やかなネオンカラーのイヤリングに触れつつ、僕のことを切れ長の目で射抜く。
ふたりの視線が絡まる。心臓が熱い。今、先輩と僕は、先輩の部屋にいて、ベッドの上で、ふたりきり……。
先輩は僕が醸し出す雰囲気を何かしら察したのか、ぱっと手を離し、ベッドから降りて距離をとった。その動きに、少しの寂しさと安堵が入り混じる。
「ごめん。あんま深く考えてなかったけど、誰もいない部屋でふたりきりは嫌だったよな……」
「そ、そんなことないです」
心の内を見透かされたような気がして、恥ずかしさでひどくバツが悪い。
「ほんとになんもする気ないから、安心して。怖がらせてごめんね、さっちゃん」
先輩の気づかいに、胸が締め付けられる。先輩が謝る必要なんて、これっぽっちもない。
「僕は嫌だったら嫌って言います。それに、空気に流される人間でもないので、気にしないでください」
「だよね、うん」
「……だけど、なんもする気ないって言われるのは、それはそれで嫌です」
まるで子どもの駄々っ子だ。先輩は目を丸くすると、そのあと「ははっ」と噴き出しておかしそうに肩を揺らす。
「なんもする気ないけど、する時はするよ。でも、今はしない」
先輩は笑っていたけれど、その目にはとても真剣な光が宿っていたように思えた。期待にも緊張にも似た何かが湧き起こる。先輩の真意をもっと探りたい気持ちと、まだこのままの関係を大切にしたい気持ちが交錯していた。
「僕は――」
その時、
「さっちゃん、来てますかー!」
妹さんたちの声ではっと我に返った。先輩は声のほうを振り返りながら、やけに力の抜けた声を発する。
「……あ、うるせぇのが帰ってきた」
「おにいから聞いてはいたけど、さっちゃんってめっちゃかわいいですね!」
「髪がいい色~! ほんとに似合ってる!」
「イヤリングもかわいいし、服もかわいい。え、どこで服買ってます?」
「てか、爪もかわいい~! 肌も……うっわ、これが無加工?」
「ドラコス使ってますか、やっぱりデパコス?」
「てか、おにいうざくないですか? うざかったら、うちらぶん殴るんで言ってくださいね」
「さっちゃん、泊まっていきません? うちの服サイズ合うかな?」
「てか、うちらの見分けついてます?」
「うちがユキナで、右目の下にほくろがあって髪が長いほう」
「で、ホクロがなくて、髪が短いほうがカンナでーす!」
怒濤の勢いで話しかけられ、目を回した。ふたりとも顔も体型も話し方もよく似ている。ユキナちゃんは栗色のミディアムヘアで、カンナちゃんはユキナちゃんより明るい髪色のボブヘアだ。彼女たちはあまりフミヤ先輩には似ておらず、ぱっちりとした大きな目をしていた。
フミヤ先輩は〝さっき警告したぞ〟という顔でニヤついていて、僕は想像以上に元気なふたりを柄にもなく苦笑いで見つめている。モモがこの場面を見たら、手を叩きながら笑い転げるに違いない。「借りてきた猫みたい~!」そんな言葉とともに。
「お前ら、さっちゃんを困らすな」
いつの間に作ってくれたのか、フミヤ先輩は僕の前にマグカップに入った紅茶と、僕が買ってきたトゥンカロンをお皿に載せて差し出してくれた。大きなマグカップには、人生で一度も見たことのないマイナーな猫のキャラクターが描かれている。普段は感じられないフミヤ先輩の生活感に触れられた気がして、自然と口角が上がってしまった。
「ありがとうございます、先輩」
「紅茶熱いから、フーフーして、さっちゃん」
まるで子どもに言うみたいな先輩の言い方。僕が目だけでからかうような視線を送ると、先輩はなんのことかわからないというように肩をすくめてみせる。
「……キモ、フーフーしてって。おにい、それはない」
「おにいは、自分のキモさよりも、さっちゃんが火傷しないことを選んだんだよ? 君たちにわかるかな?」
「ねー待って! もっとキモいんだけどぉ! 駆逐してぇ~~!」
目の前で繰り広げられる妹たちと兄の会話に、僕はもう我慢できなくて、声を出して笑ってしまった。
息もできないくらい笑っている間、妹さんたちは僕の顔をじいっと見つめて、
「さっちゃん笑うと、さらにレベチじゃん……」
と、双子らしく同時につぶやく。先輩はどこか誇らしげな顔で「だろ」と相好を崩していた。
「うん……うん……。大丈夫、ごちそうになってくる。うん……うん……お礼はちゃんと言う……。帰る時ラインするから……じゃあね、はーい」
こそこそとママとの通話を切り、振り向いてみんなにOKのサインをする。フミヤ先輩は優しく微笑み、ユキナちゃんとカンナちゃんは、まるで花が咲いたみたいにぱっと嬉しそうに笑った。
――まだ帰さないよ、さっちゃん。たこ焼きパーティーするからさ。夕飯食べていきなよ。
帰り支度をしていたら、フミヤ先輩に言われた言葉。急なお誘いだったけれど、全然重さは感じず、まるでポップコーンみたいに僕の心にふんわりと柔らかに降り積もった。やっぱり先輩はとっても不思議な人だ。ほかの人に言われたら受け入れられない言葉も、先輩からなら許せてしまう。
フミヤ先輩はエプロンをすると、とても手際よくたこ焼きパーティーの準備に取りかかった。省エネ系男子高校生はどこへやら、まるで仕事をしている時みたいだ。
イケメンバージョンの先輩は、本当に絵になって困る。テキパキと働く彼をうっとりと見つめつつ、僕は気になっていたことを尋ねた。
「そういえば親御さんは?」
夜の七時を過ぎたけど、彼らのお父さんもお母さんも帰ってくる気配がない。
「あー、親ね。えーと、俺の父親は天国。で、そっちの妹たちの父親は日本のどこか。母さんは入院してる」
「……へー、って、え!?」
言葉の意味が理解できなくて、大きなリアクションで聞き返してしまった。フミヤ先輩はカウンターキッチンで、何事もないかのように手際よくキャベツを切っている。
「おにい、いっぺんに情報提供しすぎ」
と、ユキナちゃん。
「詐欺師でも、もっと段階踏むから」
と、カンナちゃん。
「なんで。ややこしいから先に言っといたほうがいいだろ」
フミヤ先輩が言うには、先輩のお父さんは、彼が五歳の時に亡くなってしまったらしい。それから、四年後にお母さんが再婚して、妹さんたちが生まれた。そして数年後、離婚して新しいお父さんが家を出ていくことになり、今に至るらしい。
僕は何も言えなかった。フミヤ先輩の淡々とした語り口に、心がぎゅうぎゅうと締め付けられる。
「母さんが入院してんのは、自損事故で複雑骨折したんだよね。もう少しで退院だし、韓国ドラマめっちゃ見てるし、ぴんぴんしてるから心配いらないよ、さっちゃん」
フミヤ先輩は入院しているお母さんの代わりに、カンナちゃんたちのご飯や洗濯なども担当しているみたいだ。ちょっとずつ先輩のことを知った気でいたのに、実際はこの瞬間まで彼の苦労とか、生い立ちとか、なんにもわかってなかったのだ。フミヤ先輩の人生は、僕の想像をはるかに超える出来事の連続だ。
「……先輩、あの、僕も何か手伝います」
カウンターにいる先輩に少しずつ近づき、彼のつけているエプロンの裾を握る。先輩は振り向いて僕を見据え、意地悪く笑った。
「だめ。さっちゃんは、ソファで妹たちとゲームでもやってて」
「……でも」
「なんで? 俺の隣にいたい?」
思わせぶりに口角を上げる先輩。僕はそれが優しさからくる冗談だということに気づいていた。けれど、僕の悪い癖で、どうしても悔しい気持ちを抑えられなくなっていた。やられっぱなしは嫌だ。先輩とはいつも対等な関係でいたい。僕は先輩の左肩に両手をつき、精一杯背伸びをして吐息混じりにささやく。
「だってせんぱい……、料理してるところ、かっこいいから」
突然耳に息を吹きかけられて、ぞくりとしたのかもしれない。先輩は珍しく、少しだけ赤い顔で僕を見やった。
「……あざと」
呆れたような、困ったような彼のひとことに、ようやく留飲を下げる。
「あーあ、さっちゃんは困った子だ。フミヤ先輩のもっとかっこいいとこ見せちゃおうかな」
先輩はそう言うと、軽やかな手つきでエスプレッソマシンを操作し始めた。抽出されたエスプレッソの香ばしい匂いが、僕の鼻先まで届く。興味津々になって、先輩の動作を見守った。先輩は冷蔵庫から出した冷たい牛乳を銀のカップに入れ、蒸気が出ている機械をミルクにさして泡立てる。
「こうやってミルクをスチーミングしたら、エスプレッソの下にこのミルクを落とす。片方はミルクを注ぐ動き、もう片方はカップを戻す動き。この連動がすげぇ大事」
集中している先輩の声が静かに響く。僕は息を呑んで、先輩の手元に釘付けになった。カップを少しずつ傾けながら、ミルクピッチャーの先端をカップの縁に近づける。そして、細い線を描くように、ゆっくりとミルクを注ぎ始めた。
エスプレッソの表面に、小さな白い円が現れる。先輩の手が少し高くなり、注ぐ速度を上げた。繊細な手の動きを見ているうち、あっという間にきれいなハートのラテアートが浮かび上がる。
「かわいい……!」
僕は思わず感嘆の声を上げた。以前、聞いた話では、『Cafe Miracle』のバイトが決まった時に、店長から練習用としてこのエスプレッソマシンをもらったらしい。先輩はそれ以上言及しなかったけれど、きっとこんな風に上手なラテアートができるようになるまで、たくさんの練習を重ねてきたに違いない。
「どう? かっこよかった?」
僕が勝手に始めた先輩との勝負は、二対一で僕の負けだった。キュンキュンとときめく心臓を持て余し「……すごく、かっこよかったです」と唇を尖らせる。
「さっちゃん、なんでそんな悔しがってんの」
先輩がおかしそうに笑っていると、
「さっちゃーん、一緒にマリカやりましょー!」
ソファの前でゲームの準備をしていたカンナちゃんたちが、元気よく手をこまねいた。
「ほら、さっちゃんはカフェラテをゆっくり飲みながら、あっちでうるせぇ妹たちの相手して」
フミヤ先輩の言うとおり、ソファで妹さんたちとゲームをすること三十分。結論、僕とユキナちゃんとカンナちゃんは、とても交流を深めた。なんなら話をしてすぐにラインのIDを交換し、グループラインまで作ってしまった。
「おにいって無気力じゃないですか? だから今日とか、あんなに生き生きしてるのマジでビビる」
と、カンナちゃん。
「そうなの……?」
と、僕。
「そうですよ。バイトも学校もない時のおにいって『無』って感じだもん」
と、ユキナちゃん。
ゲーム機のコントローラーをかちかちと動かしながら、僕たちは内緒話をしていた。
フミヤ先輩を省エネ系高校生だと感じたことはあるけれど、無気力だとは感じたことがなかった。さっきだって、エスプレッソの苦みと、ミルクのまろやかな甘みが見事に融合した、おいしいカフェラテを僕に作ってくれた。僕が率直な感想を述べると、彼女たちは意味ありげに顔を見合わせ、
「それって、ねー?」
「ねー?」
まるでテレパシーを送るみたいに笑い合う。
「え、怖い。何? どういうこと? ……ああっ!」
動揺のあまりコースから落ちた僕に、「さっちゃんがんばれー!」と奇跡みたいに同じタイミングで彼女たちが叫ぶ。
「君たち、タコパ始めるよ」
ユキナちゃんたちの言葉の意味は気になっていたが、現金な僕は、フミヤ先輩に呼ばれたらすぐに忘れてしまった。
リビングに溢れる香ばしい匂いと賑やかな笑い声。僕たちの初めてのたこ焼きパーティーは、想像以上に楽しい雰囲気に包まれていた。
「君らさぁ、俺が見てない間に、めっちゃ仲良くなってんじゃん」
「ごめんだけど、おにいより全然仲いい。ラインも交換したし」
「おい……会って数時間でそれは傷つくわ」
僕は彼らの冗談に笑って、炭酸ジュースを飲んだ。フミヤ先輩は華麗な手さばきで、たこ焼き機に油を塗ったり、生地を入れたりしている。
具材を入れた生地がだんだん固まってきたみたいだ。先輩はくっついた生地同士を格子状に切り取り、器用にひっくり返してゆく。
「すごいですね。とってもおいしそう……!」
「俺のほうの親父が関西出身でさ、よく作ってくれたんだよね。まぁもう死んでるし、顔もあんま覚えてねぇんだけど、これだけは体が覚えてんの。ウケるでしょ?」
「そうだったんですか……」
僕は小さくつぶやき、手持ち無沙汰にジュースを飲んだ。さっきまで平気だった炭酸ジュースが、なんだか小さな痛みを放ちながら喉を通りすぎていく。
ジュージューという音と香ばしい匂いが立ち込めている。先輩は集中しているのか、黙々《もくもく》と半分くらいたこ焼きを裏返したあとに言った。
「さっちゃんもやってみる?」
「……え、いいんですか? やってみたいです!」
好奇心いっぱいで、たこ焼き器の前に立つ先輩の隣に並ぶ。彼の腕が僕の腕にかすかに触れた。その温もりに、僕はますます先輩のことを意識してしまう。先輩と出会ってから、こんなことの繰り返しだ。
「ほら、こうやって」
先輩が僕の手を取って、生地を裏返す。
「あー、おにい、さっちゃんにセクハラしてるー」
ユキナちゃんとカンナちゃんは、同じタイミングで声を上げた。
「言うなよ。さっちゃんが気づいちゃうだろ」
くるんと丸まったたこ焼き。熱い。湯気と、たこ焼きと、それに僕の顔も。
先輩の家を出ると、外はもう暗かった。星が瞬く静かな夜道を、先輩とふたりきりで歩く。
「たこ焼き、すごく、ほんとにすごーくおいしかったです」
言葉にしてみたものの、こんな陳腐な褒め言葉だけでは僕の気持ちを伝えるのには足りない気がした。先輩の優しさ、家族への愛情、そのすべてが詰まったたこ焼きだったのに。
「さっちゃんに楽しんでもらえて、俺はハッピーだよ」
「先輩って料理上手ですね。包丁さばきも、たこ焼き作ってるのも、とっても様になってましたし、……すごいです、ほんとに。僕はお菓子なら作れるけど、ご飯系は無理です」
「あー、マジで? 逆に俺はそういうちゃんと計るお菓子系は無理だわ。調味料は感覚でぶち込んで作ってるから」
「調味料感覚ニキ……」
「いや、なんそれ。てか今度、さっちゃんにお弁当作ってもいい?」
僕は先輩の横顔をちらりと見た。街灯に照らされた横顔が、いつも以上に大人びて見える。
「言いましたね? 絶対ですよ?」
思わずちょっとだけ大きな声になってしまった。興奮を隠せない自分が少し恥ずかしい。先輩は軽く笑って、「やくそくね」と僕の後頭部に触れた。さりげない自然な仕草で、先輩はいとも簡単に僕の心臓をドキドキさせてしまう。
もうすぐ駅に着く。
別れの時間が迫っている。そう思うと、今まで言えなかった言葉がようやく口をついて出た。
「……ごめんなさい、先輩」
先輩は不思議そうな顔で僕を見た。僕は深呼吸をして、心の中で思っていたことを、なんとか先輩に伝えようとする。
「この前の言葉、訂正させてください」
「……ん、訂正?」
「僕ががんばってるって言ったことです。……先輩のほうがよっぽどがんばってます。僕は自分のことしか考えてないし、先輩みたいに優しくもないんです。先輩のがんばりの足元にも及びません」
――僕、ほんとに毎日がんばってます……。
学校の非常階段で、彼に放った無神経な言葉。あの時の自分を力いっぱい殴ってやりたい。
おそらく自分には、人間として大切な何かが欠けているのだ。昔投げられた鋭利な言葉で、見た目だけ整えられて、いびつになってしまった僕の心のカタチ。
先輩は立ち止まり、真剣なまなざしで僕を見つめた。
「さっちゃん、ちゃんとがんばってるでしょ。俺は本気でえらいなって思ってるよ」
「でも……」
「謝んないでよ、さっちゃん。その分、かっこいいって言って。さっちゃんが言ってくれたら、もっとがんばれるよ、俺」
言葉に詰まる僕を見て、先輩は優しく微笑んだ。僕は嬉しくて、悔しくて、唇を噛む。先輩の優しさと強さが、またひとつ僕の心に刻まれた。先輩は僕の言葉を求めてくれている。僕の存在を必要としてくれている。
「先輩は、かっこいいです。本当にかっこいい……私服姿も、ラテアートしてる時も、たこ焼きを作ってる時だって……ぜんぶ。……今日だって、先輩がかっこいいせいで、ずっとドキドキさせられてました、僕……」
少しだけ頬を赤らめながら、僕は続けた。
「……でも、学校にいる時はもじゃもじゃです」
照れ隠しの僕の言葉に、先輩はけらけらと笑ってつぶやく。
「ありがとね、さっちゃん」
少し、いやだいぶ胸がバクバクしている。手のひらに汗が滲み、インターホンを押そうとした指が、わずかに震えていた。
もじゃもじゃか、イケメンか。
そんな思いが、頭の中を駆け巡る。できればイケメン姿のフミヤ先輩に出迎えてもらいたい。傲慢な願望を持ちながら、僕はここに来るまでの経緯を思い返していた。
すべては先日の雨の日、先輩から借りたハートの傘から始まった。
その日の夜のこと。お風呂上がりの僕は、いつものルーティンでスキンケアに励んでいた。その時、突然スマホが鳴り始める。この時間にかけてくるのは、モモだけだ。
「もしもーし」
ろくに画面も見ずに通話ボタンをフリックし、パックを顔に貼り付ける。モモに話したいことがたくさんある。学校でもじゃもじゃのフミヤ先輩に会ったこと、先輩に膝枕をしたこと、そして電車で一緒に帰ってさらに心を掴まれてしまったこと、カフェで見た先輩の姿はやっぱりかっこよかったこと。怒涛のように起こった今日の出来事をモモに伝えようと、「ねえ、モモ聞いて」と口にしようとした瞬間。
『さっちゃん、こんばんは』
聞き慣れた低い声に、心臓が跳ね上がった。明らかにモモじゃない。
「フ、フミヤ先輩!」
驚きのあまり、声が裏返る。しかもビデオ通話だったようで、画面に先輩の姿が映っている。ハーフアップでもなく、もじゃもじゃでもなく、お風呂上がりなのか、濡れた髪がまっすぐに下りていた。
『あ、さっちゃん、パックしてる』
先輩の言葉に、急に恥ずかしさが込み上げてくる。普段見せない素の自分を、なんの防御もなく先輩に見られてしまった。
「せ、先輩、待ってください! 今、ビジュ悪すぎる……! メイクするので、あと二時間だけください!」
『なげーよ』
先輩の屈託のない笑い声が、耳に心地よく響く。フミヤ先輩はスマホを持ち、ベッドに寝転がったようだった。画面越しに見える、無防備な先輩の表情。妙な親密さを感じて、胸がドキドキする。まるで同じベッドの上に乗っているみたいな錯覚を覚え、僕は慌てて言葉を発した。
「えっと、フミヤ先輩、ハートの傘、ありがとうございました。おかげさまで、僕の大事な髪と顔面を濡らさずに帰れました」
本当は鞄の中に折りたたみ傘があったけれど。
『あーそれそれ』
「え? どれですか?」
『その傘なんだけど……』
何か言いたげな様子の先輩に、やけに緊張が高まる。
『さっちゃんさ、傘返しに俺んちこない?』
「……え?」
もちろん、傘は返しにいくつもりだったが……、フミヤ先輩の家? まるで心臓が一拍分、止まったような気がした。
『妹たちに傘貸したって言ったら、会いたい会いたいってうるさくてさ。それに、さっちゃんとした約束のこともあるし、ぜひこの機会に俺のことを、知ってもらおうじゃないかと』
穏やかで優しい先輩の声を聞きながら、指切りをして交わしたあの言葉が頭の中でよみがえる。
――ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく。
僕があんなにも突然にアプローチをして、フミヤ先輩もさぞ困惑したと思う。それでも先輩は、本当に誠実に僕と向き合おうとしてくれているのだ。泣きたくなるほど嬉しいのに、僕は心の奥底で小さな不安にも似た何かが芽吹いていくのを感じていた。
そして今、僕は先輩の家の前に立っている。インターホンを押そうとした瞬間、突然の自意識に襲われる。慌ててミラーを取り出し、こっそりと顔をチェックした。
髪は乱れていないか、肌の状態は大丈夫か、ヘアピンは曲がっていないか、服はしわくちゃになっていないか、イヤリングは取れていないか。先輩の前では完璧でありたい。そんな気持ちが胸いっぱいに広がる。
リップを少しだけ塗り直した。
大丈夫、今日も僕はかわいい。
よし、と覚悟を決めて顔を上げた瞬間、空から声が降ってきた。
「とってもかわいいよ、さっちゃん」
「なっ!?」
驚きの声を上げると同時に、二階の窓から覗く先輩の姿が目に入る。ずっと見られていたらしく、イケメンバージョンのフミヤ先輩がこっちを見下ろし、楽しそうに笑っていた。
「いらっしゃい。場所、すぐわかった――」
「さっきの最低ですからね!」
玄関を開けてくれた先輩を見るなり、僕はグーパンチを繰り出した。けれど、僕の手は呆気なく、彼の大きな手にすっぽりとおさまってしまう。攻撃はもう意味をなさない。それどころか、フミヤ先輩の手の温もりに、僕のほうがノックアウトされそうだった。
「ごめんね。さっちゃんが家わかるかなって見てたんだけど、かわいくてつい」
先輩はワッフル素材の白いロンTに、シンプルなブラックのデニムパンツを合わせていた。ハーフアップにセットされた髪と、シルバーの小ぶりなピアス。先輩は自分に似合うものをちゃんと理解しているみたいだ。初めて見る私服姿はあまりに僕のドストライクで、胸が苦しくなってくる。
「……今日はオンモードなんですね」
「そう、午前中シフト入ってたから」
その言葉を聞いた瞬間、胸がちくりと痛んだ。バイト終わりだったから、イケメン姿のフミヤ先輩だったらしい。僕のためにおしゃれしてくれたわけではなさそうで、少しだけ残念に思う。それに比べて僕はといえば、いつもは自分のためだけにするオシャレだけれど、今日は特別に先輩のためもプラスして、上から下までオシャレをしてきた。意識しているのは僕だけですか、ふーんそうですか。ていうかちょっと拗ねましたけど、何か。
「傘、ありがとうございました。それと、お土産です」
頬を膨らませて、ぐいっと傘とお土産を差し出す。
「手ぶらでいいのに。なんなら別に傘もよかったし。……てか、今日の髪も似合ってんね。ちょっとウェーブ入ってる」
冗談めかして、先輩が僕の髪にそっと触れる。先輩の言うとおり、せっせとヘアーアイロンで、髪をウェーブ巻きにしてきた。気づいてくれたのは嬉しいけれど、こんなにも張り切っている僕に対し、フミヤ先輩は悲しいくらい自然体だった。しかも、僕のスタイリングが崩れないよう、優しく髪に触れてくる仕草に、胸が勝手にときめいてしまって内心はとても複雑だ。
「お土産、何買ってくれたの?」
「トゥンカロンです。妹さんがいらっしゃるって言ってたから、映える系がいいかなと思って」
「ああ、トゥンカロン! 韓国のやつだよね? あいつらめっちゃ好きだから、喜ぶよ」
さすがカフェ店員のフミヤ先輩だ。トゥンカロンは先輩の言うように韓国発祥の進化系マカロンで、マカロンよりもボリュームがあり、動物型だったり花型だったり、見た目のレパートリーも多くてとてもかわいい。
「……あ、立ち話もなんですし、上がって上がって」
「お邪魔しまーす」
靴を揃え、用意してもらったスリッパに履き替えた。先輩のあとを追ってリビングに足を踏み入れると、自分の家の匂いとは違う、どこか懐かしい匂いがした。リビングは僕の家よりこぢんまりとしているけれど、暖かな雰囲気に包まれている。大きな窓から差し込む陽光が、部屋全体を明るく照らしていた。フミヤ先輩みたいに優しい家だ。
失礼にならないよう気をつけながら、でも好奇心を抑えきれず、僕は部屋を見回した。テレビとソファ。タンスの上にはかわいいヘアゴムが入った透明な容器。
「そういえば、妹さんたちは?」
「今、部活。演劇やってんだけど、あと三十分くらいで帰ってくると思う。ガチでうるせぇから、覚悟してね、さっちゃん」
フミヤ先輩によく似た『うるさい女の子バージョン』を思い浮かべ、僕はこらえきれず、ふふっとのんきに笑っていた。次の瞬間、先輩が僕の心を揺さぶるような発言をするまでは――。
「さっちゃん、あいつら帰ってくるまで、フミヤ先輩のルームツアーでもする?」
好奇心には抗えず、僕は『フミヤ先輩のルームツアー』を開催してもらうことにした。
二階の角部屋。フミヤ先輩の部屋に初めて入った時の率直な感想は、『フミヤ先輩の匂いがする』だった。先輩がいつもしているブランド物の香水の香りを、肺いっぱいに吸い込む。
「なんも楽しいのないけど」
壁は落ち着いたグレーで塗られ、モダンな雰囲気を醸し出していた。初めて遊びに来た先輩の部屋だけれど、それほど初めてな気がしないのは、以前、ビデオ通話で見たことがあったからだ。
本棚には、ラテアートの本、それからファッション誌と小説が並んでいる。その中に僕も読んだことがある小説を見つけて、とても嬉しくなった。部屋の隅には、スタイリッシュなハンガーラックが置かれ、先輩のオシャレな私服がかけられている。
「すごくいいと思います、先輩の部屋。清潔感があって、いい匂い。あ! ベッドも大きいですね!」
先輩の体が悠々入るくらい、大きくて居心地が良さそうだ。シンプルなグレーのベッドカバーが、部屋全体の雰囲気と見事に調和している。僕はベッドに座り、ご機嫌に先輩を見上げた。
「おー、うれしい。さっちゃんに褒められるとマジでうれしいわ」
先輩は本当に嬉しそうに目を細め、僕の隣に座る。その距離の近さに、少しだけ心臓が高鳴った。
「あれ? さっちゃん、ピアスの穴開いてたっけ? 似合うね」
先輩の視線が耳に注がれる。突然、僕はどう振る舞っていいかわからなくなってしまった。
「……ピアスじゃなくて、イヤリングです。穴は怖いから、開けたことなくて」
今は言葉を絞り出すので精一杯だ。
「そっか、痛いもんね。いいよ、さっちゃんは開けなくて」
何を考えているのか、先輩は静かに僕の耳に手を伸ばした。鮮やかなネオンカラーのイヤリングに触れつつ、僕のことを切れ長の目で射抜く。
ふたりの視線が絡まる。心臓が熱い。今、先輩と僕は、先輩の部屋にいて、ベッドの上で、ふたりきり……。
先輩は僕が醸し出す雰囲気を何かしら察したのか、ぱっと手を離し、ベッドから降りて距離をとった。その動きに、少しの寂しさと安堵が入り混じる。
「ごめん。あんま深く考えてなかったけど、誰もいない部屋でふたりきりは嫌だったよな……」
「そ、そんなことないです」
心の内を見透かされたような気がして、恥ずかしさでひどくバツが悪い。
「ほんとになんもする気ないから、安心して。怖がらせてごめんね、さっちゃん」
先輩の気づかいに、胸が締め付けられる。先輩が謝る必要なんて、これっぽっちもない。
「僕は嫌だったら嫌って言います。それに、空気に流される人間でもないので、気にしないでください」
「だよね、うん」
「……だけど、なんもする気ないって言われるのは、それはそれで嫌です」
まるで子どもの駄々っ子だ。先輩は目を丸くすると、そのあと「ははっ」と噴き出しておかしそうに肩を揺らす。
「なんもする気ないけど、する時はするよ。でも、今はしない」
先輩は笑っていたけれど、その目にはとても真剣な光が宿っていたように思えた。期待にも緊張にも似た何かが湧き起こる。先輩の真意をもっと探りたい気持ちと、まだこのままの関係を大切にしたい気持ちが交錯していた。
「僕は――」
その時、
「さっちゃん、来てますかー!」
妹さんたちの声ではっと我に返った。先輩は声のほうを振り返りながら、やけに力の抜けた声を発する。
「……あ、うるせぇのが帰ってきた」
「おにいから聞いてはいたけど、さっちゃんってめっちゃかわいいですね!」
「髪がいい色~! ほんとに似合ってる!」
「イヤリングもかわいいし、服もかわいい。え、どこで服買ってます?」
「てか、爪もかわいい~! 肌も……うっわ、これが無加工?」
「ドラコス使ってますか、やっぱりデパコス?」
「てか、おにいうざくないですか? うざかったら、うちらぶん殴るんで言ってくださいね」
「さっちゃん、泊まっていきません? うちの服サイズ合うかな?」
「てか、うちらの見分けついてます?」
「うちがユキナで、右目の下にほくろがあって髪が長いほう」
「で、ホクロがなくて、髪が短いほうがカンナでーす!」
怒濤の勢いで話しかけられ、目を回した。ふたりとも顔も体型も話し方もよく似ている。ユキナちゃんは栗色のミディアムヘアで、カンナちゃんはユキナちゃんより明るい髪色のボブヘアだ。彼女たちはあまりフミヤ先輩には似ておらず、ぱっちりとした大きな目をしていた。
フミヤ先輩は〝さっき警告したぞ〟という顔でニヤついていて、僕は想像以上に元気なふたりを柄にもなく苦笑いで見つめている。モモがこの場面を見たら、手を叩きながら笑い転げるに違いない。「借りてきた猫みたい~!」そんな言葉とともに。
「お前ら、さっちゃんを困らすな」
いつの間に作ってくれたのか、フミヤ先輩は僕の前にマグカップに入った紅茶と、僕が買ってきたトゥンカロンをお皿に載せて差し出してくれた。大きなマグカップには、人生で一度も見たことのないマイナーな猫のキャラクターが描かれている。普段は感じられないフミヤ先輩の生活感に触れられた気がして、自然と口角が上がってしまった。
「ありがとうございます、先輩」
「紅茶熱いから、フーフーして、さっちゃん」
まるで子どもに言うみたいな先輩の言い方。僕が目だけでからかうような視線を送ると、先輩はなんのことかわからないというように肩をすくめてみせる。
「……キモ、フーフーしてって。おにい、それはない」
「おにいは、自分のキモさよりも、さっちゃんが火傷しないことを選んだんだよ? 君たちにわかるかな?」
「ねー待って! もっとキモいんだけどぉ! 駆逐してぇ~~!」
目の前で繰り広げられる妹たちと兄の会話に、僕はもう我慢できなくて、声を出して笑ってしまった。
息もできないくらい笑っている間、妹さんたちは僕の顔をじいっと見つめて、
「さっちゃん笑うと、さらにレベチじゃん……」
と、双子らしく同時につぶやく。先輩はどこか誇らしげな顔で「だろ」と相好を崩していた。
「うん……うん……。大丈夫、ごちそうになってくる。うん……うん……お礼はちゃんと言う……。帰る時ラインするから……じゃあね、はーい」
こそこそとママとの通話を切り、振り向いてみんなにOKのサインをする。フミヤ先輩は優しく微笑み、ユキナちゃんとカンナちゃんは、まるで花が咲いたみたいにぱっと嬉しそうに笑った。
――まだ帰さないよ、さっちゃん。たこ焼きパーティーするからさ。夕飯食べていきなよ。
帰り支度をしていたら、フミヤ先輩に言われた言葉。急なお誘いだったけれど、全然重さは感じず、まるでポップコーンみたいに僕の心にふんわりと柔らかに降り積もった。やっぱり先輩はとっても不思議な人だ。ほかの人に言われたら受け入れられない言葉も、先輩からなら許せてしまう。
フミヤ先輩はエプロンをすると、とても手際よくたこ焼きパーティーの準備に取りかかった。省エネ系男子高校生はどこへやら、まるで仕事をしている時みたいだ。
イケメンバージョンの先輩は、本当に絵になって困る。テキパキと働く彼をうっとりと見つめつつ、僕は気になっていたことを尋ねた。
「そういえば親御さんは?」
夜の七時を過ぎたけど、彼らのお父さんもお母さんも帰ってくる気配がない。
「あー、親ね。えーと、俺の父親は天国。で、そっちの妹たちの父親は日本のどこか。母さんは入院してる」
「……へー、って、え!?」
言葉の意味が理解できなくて、大きなリアクションで聞き返してしまった。フミヤ先輩はカウンターキッチンで、何事もないかのように手際よくキャベツを切っている。
「おにい、いっぺんに情報提供しすぎ」
と、ユキナちゃん。
「詐欺師でも、もっと段階踏むから」
と、カンナちゃん。
「なんで。ややこしいから先に言っといたほうがいいだろ」
フミヤ先輩が言うには、先輩のお父さんは、彼が五歳の時に亡くなってしまったらしい。それから、四年後にお母さんが再婚して、妹さんたちが生まれた。そして数年後、離婚して新しいお父さんが家を出ていくことになり、今に至るらしい。
僕は何も言えなかった。フミヤ先輩の淡々とした語り口に、心がぎゅうぎゅうと締め付けられる。
「母さんが入院してんのは、自損事故で複雑骨折したんだよね。もう少しで退院だし、韓国ドラマめっちゃ見てるし、ぴんぴんしてるから心配いらないよ、さっちゃん」
フミヤ先輩は入院しているお母さんの代わりに、カンナちゃんたちのご飯や洗濯なども担当しているみたいだ。ちょっとずつ先輩のことを知った気でいたのに、実際はこの瞬間まで彼の苦労とか、生い立ちとか、なんにもわかってなかったのだ。フミヤ先輩の人生は、僕の想像をはるかに超える出来事の連続だ。
「……先輩、あの、僕も何か手伝います」
カウンターにいる先輩に少しずつ近づき、彼のつけているエプロンの裾を握る。先輩は振り向いて僕を見据え、意地悪く笑った。
「だめ。さっちゃんは、ソファで妹たちとゲームでもやってて」
「……でも」
「なんで? 俺の隣にいたい?」
思わせぶりに口角を上げる先輩。僕はそれが優しさからくる冗談だということに気づいていた。けれど、僕の悪い癖で、どうしても悔しい気持ちを抑えられなくなっていた。やられっぱなしは嫌だ。先輩とはいつも対等な関係でいたい。僕は先輩の左肩に両手をつき、精一杯背伸びをして吐息混じりにささやく。
「だってせんぱい……、料理してるところ、かっこいいから」
突然耳に息を吹きかけられて、ぞくりとしたのかもしれない。先輩は珍しく、少しだけ赤い顔で僕を見やった。
「……あざと」
呆れたような、困ったような彼のひとことに、ようやく留飲を下げる。
「あーあ、さっちゃんは困った子だ。フミヤ先輩のもっとかっこいいとこ見せちゃおうかな」
先輩はそう言うと、軽やかな手つきでエスプレッソマシンを操作し始めた。抽出されたエスプレッソの香ばしい匂いが、僕の鼻先まで届く。興味津々になって、先輩の動作を見守った。先輩は冷蔵庫から出した冷たい牛乳を銀のカップに入れ、蒸気が出ている機械をミルクにさして泡立てる。
「こうやってミルクをスチーミングしたら、エスプレッソの下にこのミルクを落とす。片方はミルクを注ぐ動き、もう片方はカップを戻す動き。この連動がすげぇ大事」
集中している先輩の声が静かに響く。僕は息を呑んで、先輩の手元に釘付けになった。カップを少しずつ傾けながら、ミルクピッチャーの先端をカップの縁に近づける。そして、細い線を描くように、ゆっくりとミルクを注ぎ始めた。
エスプレッソの表面に、小さな白い円が現れる。先輩の手が少し高くなり、注ぐ速度を上げた。繊細な手の動きを見ているうち、あっという間にきれいなハートのラテアートが浮かび上がる。
「かわいい……!」
僕は思わず感嘆の声を上げた。以前、聞いた話では、『Cafe Miracle』のバイトが決まった時に、店長から練習用としてこのエスプレッソマシンをもらったらしい。先輩はそれ以上言及しなかったけれど、きっとこんな風に上手なラテアートができるようになるまで、たくさんの練習を重ねてきたに違いない。
「どう? かっこよかった?」
僕が勝手に始めた先輩との勝負は、二対一で僕の負けだった。キュンキュンとときめく心臓を持て余し「……すごく、かっこよかったです」と唇を尖らせる。
「さっちゃん、なんでそんな悔しがってんの」
先輩がおかしそうに笑っていると、
「さっちゃーん、一緒にマリカやりましょー!」
ソファの前でゲームの準備をしていたカンナちゃんたちが、元気よく手をこまねいた。
「ほら、さっちゃんはカフェラテをゆっくり飲みながら、あっちでうるせぇ妹たちの相手して」
フミヤ先輩の言うとおり、ソファで妹さんたちとゲームをすること三十分。結論、僕とユキナちゃんとカンナちゃんは、とても交流を深めた。なんなら話をしてすぐにラインのIDを交換し、グループラインまで作ってしまった。
「おにいって無気力じゃないですか? だから今日とか、あんなに生き生きしてるのマジでビビる」
と、カンナちゃん。
「そうなの……?」
と、僕。
「そうですよ。バイトも学校もない時のおにいって『無』って感じだもん」
と、ユキナちゃん。
ゲーム機のコントローラーをかちかちと動かしながら、僕たちは内緒話をしていた。
フミヤ先輩を省エネ系高校生だと感じたことはあるけれど、無気力だとは感じたことがなかった。さっきだって、エスプレッソの苦みと、ミルクのまろやかな甘みが見事に融合した、おいしいカフェラテを僕に作ってくれた。僕が率直な感想を述べると、彼女たちは意味ありげに顔を見合わせ、
「それって、ねー?」
「ねー?」
まるでテレパシーを送るみたいに笑い合う。
「え、怖い。何? どういうこと? ……ああっ!」
動揺のあまりコースから落ちた僕に、「さっちゃんがんばれー!」と奇跡みたいに同じタイミングで彼女たちが叫ぶ。
「君たち、タコパ始めるよ」
ユキナちゃんたちの言葉の意味は気になっていたが、現金な僕は、フミヤ先輩に呼ばれたらすぐに忘れてしまった。
リビングに溢れる香ばしい匂いと賑やかな笑い声。僕たちの初めてのたこ焼きパーティーは、想像以上に楽しい雰囲気に包まれていた。
「君らさぁ、俺が見てない間に、めっちゃ仲良くなってんじゃん」
「ごめんだけど、おにいより全然仲いい。ラインも交換したし」
「おい……会って数時間でそれは傷つくわ」
僕は彼らの冗談に笑って、炭酸ジュースを飲んだ。フミヤ先輩は華麗な手さばきで、たこ焼き機に油を塗ったり、生地を入れたりしている。
具材を入れた生地がだんだん固まってきたみたいだ。先輩はくっついた生地同士を格子状に切り取り、器用にひっくり返してゆく。
「すごいですね。とってもおいしそう……!」
「俺のほうの親父が関西出身でさ、よく作ってくれたんだよね。まぁもう死んでるし、顔もあんま覚えてねぇんだけど、これだけは体が覚えてんの。ウケるでしょ?」
「そうだったんですか……」
僕は小さくつぶやき、手持ち無沙汰にジュースを飲んだ。さっきまで平気だった炭酸ジュースが、なんだか小さな痛みを放ちながら喉を通りすぎていく。
ジュージューという音と香ばしい匂いが立ち込めている。先輩は集中しているのか、黙々《もくもく》と半分くらいたこ焼きを裏返したあとに言った。
「さっちゃんもやってみる?」
「……え、いいんですか? やってみたいです!」
好奇心いっぱいで、たこ焼き器の前に立つ先輩の隣に並ぶ。彼の腕が僕の腕にかすかに触れた。その温もりに、僕はますます先輩のことを意識してしまう。先輩と出会ってから、こんなことの繰り返しだ。
「ほら、こうやって」
先輩が僕の手を取って、生地を裏返す。
「あー、おにい、さっちゃんにセクハラしてるー」
ユキナちゃんとカンナちゃんは、同じタイミングで声を上げた。
「言うなよ。さっちゃんが気づいちゃうだろ」
くるんと丸まったたこ焼き。熱い。湯気と、たこ焼きと、それに僕の顔も。
先輩の家を出ると、外はもう暗かった。星が瞬く静かな夜道を、先輩とふたりきりで歩く。
「たこ焼き、すごく、ほんとにすごーくおいしかったです」
言葉にしてみたものの、こんな陳腐な褒め言葉だけでは僕の気持ちを伝えるのには足りない気がした。先輩の優しさ、家族への愛情、そのすべてが詰まったたこ焼きだったのに。
「さっちゃんに楽しんでもらえて、俺はハッピーだよ」
「先輩って料理上手ですね。包丁さばきも、たこ焼き作ってるのも、とっても様になってましたし、……すごいです、ほんとに。僕はお菓子なら作れるけど、ご飯系は無理です」
「あー、マジで? 逆に俺はそういうちゃんと計るお菓子系は無理だわ。調味料は感覚でぶち込んで作ってるから」
「調味料感覚ニキ……」
「いや、なんそれ。てか今度、さっちゃんにお弁当作ってもいい?」
僕は先輩の横顔をちらりと見た。街灯に照らされた横顔が、いつも以上に大人びて見える。
「言いましたね? 絶対ですよ?」
思わずちょっとだけ大きな声になってしまった。興奮を隠せない自分が少し恥ずかしい。先輩は軽く笑って、「やくそくね」と僕の後頭部に触れた。さりげない自然な仕草で、先輩はいとも簡単に僕の心臓をドキドキさせてしまう。
もうすぐ駅に着く。
別れの時間が迫っている。そう思うと、今まで言えなかった言葉がようやく口をついて出た。
「……ごめんなさい、先輩」
先輩は不思議そうな顔で僕を見た。僕は深呼吸をして、心の中で思っていたことを、なんとか先輩に伝えようとする。
「この前の言葉、訂正させてください」
「……ん、訂正?」
「僕ががんばってるって言ったことです。……先輩のほうがよっぽどがんばってます。僕は自分のことしか考えてないし、先輩みたいに優しくもないんです。先輩のがんばりの足元にも及びません」
――僕、ほんとに毎日がんばってます……。
学校の非常階段で、彼に放った無神経な言葉。あの時の自分を力いっぱい殴ってやりたい。
おそらく自分には、人間として大切な何かが欠けているのだ。昔投げられた鋭利な言葉で、見た目だけ整えられて、いびつになってしまった僕の心のカタチ。
先輩は立ち止まり、真剣なまなざしで僕を見つめた。
「さっちゃん、ちゃんとがんばってるでしょ。俺は本気でえらいなって思ってるよ」
「でも……」
「謝んないでよ、さっちゃん。その分、かっこいいって言って。さっちゃんが言ってくれたら、もっとがんばれるよ、俺」
言葉に詰まる僕を見て、先輩は優しく微笑んだ。僕は嬉しくて、悔しくて、唇を噛む。先輩の優しさと強さが、またひとつ僕の心に刻まれた。先輩は僕の言葉を求めてくれている。僕の存在を必要としてくれている。
「先輩は、かっこいいです。本当にかっこいい……私服姿も、ラテアートしてる時も、たこ焼きを作ってる時だって……ぜんぶ。……今日だって、先輩がかっこいいせいで、ずっとドキドキさせられてました、僕……」
少しだけ頬を赤らめながら、僕は続けた。
「……でも、学校にいる時はもじゃもじゃです」
照れ隠しの僕の言葉に、先輩はけらけらと笑ってつぶやく。
「ありがとね、さっちゃん」