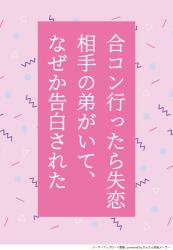イケメン店員の名前は、貞文哉先輩、高校三年生。カフェでのネームプレートの印象が強くて、僕はフミヤ先輩と呼ぶことにした。
あの指切りげんまんから一週間、僕はカフェに通い続けた。当日は、もらったIDに僕からメッセージを送った。次の日はラインのIDを教え合い、次の日には先輩に双子の妹がいることを教えてもらった。その次の日には先輩がバイセクシャルで、僕がゲイだと教え合った。その次の日には初めて電話をして、その次の次の日には夜遅くまでメッセージを交わし合った。
『なんと来週から新しく「シトラスティーパフェ」が出ます』
『食べたい! 絶対食べに行きます!』
『待ってるよ、幸朗』
『本名で呼ぶなぁ……。あ、フミヤ先輩がパフェの名前を忘れても僕が教えますから、安心してくださいね』
『その節は大変お世話になりました』
放課後の教室で、僕は昨日のラインのやりとりを見つめ、「ふふっ」と勝手に口から笑みがこぼれてしまった。最近はちょっとした冗談も言い合えるようになり、心の距離も少しだけ近づいたような気がする。
僕のにやついた顔を見たモモが、「幸せそうだねぇ、さっちゃん」とからかってくる。
「まぁまぁかな。今はゆっくりお互いを知っていくところだから」
だらしない顔を急いで戻し、僕はキリッとしてつぶやいた。
フミヤ先輩がある日突然、君と連絡するのはこれきりにしたいと言うかもしれないし、逆に僕がそう言うかもしれない。でもなんだかんだ言っても、先輩とやりとりできるのは、やっぱり言葉にならないくらい嬉しい。
「さっちゃんに春が来たって、あさ子さんに報告しよっと」
「気が早いって」
「なんでいいじゃん、うちは嬉しいんだから」
モモは椅子から立ち上がると、スマホの時計を見やった。
「そろそろ行かなきゃ」
まるで外国のお土産のお菓子みたいに、甘々な顔でモモが笑う。
「あさ子さんと楽しんできてね、デート」
「りょうかい。てか、はやくフミヤ先輩も一緒に、四人でWデートしたいね」
「だから、気が早すぎだって……。いいから、もう行きな!」
僕はまんざらでもない顔をして、犬でも追い払うようにシッシッと右手でジェスチャーした。軽やかな笑い声と、タータンチェックの短いスカートが、ひらひらと揺れながら遠ざかっていく。
フミヤ先輩は夕方からバイトだって言ってたっけ。あとでまたカフェに遊びに行こうかな。そんなことを考えてご機嫌に廊下を歩いていると、突然、声をかけられて身震いした。
「……さっちゃん?」
振り向いた先には、見た目にまったく気をつかってなさそうな男子高校生がいた。
「あ、ほんとにさっちゃんだ」
上履きの色から察するに、学年は二つ上だ。長身でスタイルはいいけど、伸びたくせっ毛はぼさぼさで、長すぎる前髪のせいで瞳は見えず、制服もシャツのボタンを上から二つも外していてだらしない。ネクタイだって、かろうじて結ばれているようなルーズさだ。
思わず顔をしかめそうになるのを抑え、こんな知り合いがいただろうかとしばらく逡巡した。いや、どう考えても知り合いなわけがない。僕は見た目に気をつかわない人間が一番苦手なのだ。
「やっぱ同じ高校だったんだ。制服似てると思った」
そう言って近づいてくる彼に、警戒心が強い猫のような鋭い視線を返す。
「昨日聞こうと思って忘れてたわ。でも、よかったね、さっちゃん。カフェ以外でも会えるから」
彼は制服のズボンのポケットに両手を突っ込んで、やけに親しげに話しかけてくる。僕は死んだ魚のような目をして、曖昧に流そうとした。――でも、なぜか彼の声が、どこか聞き覚えがあることに気づいた。
それに……ほんのかすかに漂う爽やかで甘いムスクみたいな香水の香りも。
――でも、よかったね、さっちゃん。カフェ以外でも会えるから。
僕はまるで雷に打たれたように、点と点が繋がるのを感じた。
「カフェって……も、もしかして……」
急いで彼のそばに行き、恐る恐る乱れたもじゃもじゃの前髪をかき分けてみる。すると、そこには――。
「フ、フミヤ先輩!?」
「あれ、もしかして気づいてなかった?」
けらけらと笑った彼の顔は、あのフミヤ先輩に間違いなかった。けれど、カフェでビシッと髪を結わき、黒いエプロンをつけてキビキビと働く店員の姿と、今のだらしない男子高校生の姿とでは、まるで月とすっぽんで同じ人物とは思えない。
僕にとってフミヤ先輩と一緒の高校なのはとてもラッキーだけれど、もじゃもじゃのこの人と一緒なのは全然ラッキーじゃなかった。
ほかの生徒たちが、なんだなんだと僕たちの様子を窺っていた。廊下のど真ん中で話すことじゃないと悟った僕は、困惑しながらもフミヤ先輩の腕を引っ張って、人目につかない非常階段のほうへと向かった。
「先輩、なんでですか!? ど、どうしてこんな無惨な姿に……!?」
「無惨て」
フミヤ先輩はもじゃもじゃの前髪の奥で、困ったように目を細めながら言う。
「どっちかっつうと、こっちのほうが素なんだけど……。バイト先のはオンモードっていうか、戦闘モードっていうか」
「学校でもオンになってくださいよ!」
「えー、でも……金、出ねぇしな」
「僕が出しますから!」
「ははっ。ほんとおもしれぇね、さっちゃん。愉快愉快」
フミヤ先輩は、ことの重大さがわかっていない。あんなにもすごいポテンシャルを持っているのに、学校ではお金が出ないという非常に不憫な理由で、イケメンで居続ける努力を怠っているのだ。
「愉快愉快じゃないですよ! ほんとになんなんですかこの頭! せっかくのきれいな先輩の目が、全然見えないじゃないですかぁ!」
「さっちゃん、俺の目褒めてくれんの? うれしー」
「……そ、そうじゃなくて! 髪型の話ですよ、髪型の!」
「だって、朝、髪整えんのめんどくさいし……。バイトの時だけでいっかなって」
ね? と、悪びれもせず同意を求められて、体中の力がどっと抜けていく。
「燃費悪いから、できれば省エネで生きたいんだよね」
燃費……? 省エネ……?
僕はわなわなと震え、フミヤ先輩に詰め寄った。
「僕は毎朝スタイリングしてます! 髪もアイロンかけてますし、朝パックもします! 化粧水も乳液も美容液もクリームも塗りますし、日焼け対策も、ファンデも、マスカラもリップも、えーとそれから……!」
日々、かわいいを作り出すための努力を息切れしながら力説する。おそらく並の男の子だったら気分を害したはずだけれど、さすがのフミヤ先輩は悠々としていた。
「すげぇえらいじゃん、さっちゃん」
そうやって感心されても内心は複雑だ。
「……僕のがんばりに対して、その言葉だけじゃちょっと足りないと思います」
フミヤ先輩はおもしろがるように、にっと口角を上げる。
「足りないかぁ。俺、何すればいい?」
「この前みたいに頭を撫でてもらうとか……」
「こう?」
別に意地悪を言いたかっただけで、本当に撫でてもらいたかったわけじゃない。なのに、フミヤ先輩の長い指に触れられたら、気持ちがよくてすべてがどうでもよくなってしまった。
「よしよし、さっちゃん。がんばっててえらいね」
先輩の手からマイナスイオンでも出ているのか、それとも僕の前世が気まぐれな猫だったのか。先輩の指が僕の髪に触れるたび、抵抗する力が奪われていく。
「僕、ほんとに毎日がんばってます……」
飼い主にすり寄る猫のように、僕はにゃあにゃあと鳴いた。
「うん。さっちゃんは、一生懸命でとってもかわいいよ」
今の言葉がイケメンカフェ店員のフミヤ先輩からだったら、鼻血が出るくらい興奮してしまったかもしれない。あのカフェで働く先輩の姿を思い浮かべただけで、胸がキュンとなり、頬が熱くなる。完璧な笑顔、洗練された立ち振る舞い、そのすべてが僕の心を掴んで離さない。
でも、目の前にいる彼は、
「先輩は、もじゃもじゃ……ですね」
カフェにいる彼とは違う。もじゃもじゃの髪、だらりとリラックスした表情。カフェのギャルソン風ではなく、ラフでだらしない省エネ系男子高校生の制服姿。
「おーありがと」
「全然褒めてないです」
「こら一年生、そういうこと言わない」
気だるげに目を細めたフミヤ先輩は、生意気な僕の発言にもまったく気にしている素振りを見せなかった。僕の髪の毛に指先を絡めて、感心したようにつぶやく。
「髪、さらさらじゃん。あとすげぇキラキラ。前から思ってたけど、この銀髪いいよね。ブリーチした?」
「……しました」
撫でられて、褒められて、笑顔を向けられて、気がつけば、うっとりと目を閉じていた。喉から漏れる甘い声。自分でも信じられないほど先輩に身を委ねている。
どれだけそうされていたのか、
「はい、おしまい」
先輩の声で現実に引き戻された。ゆっくりと瞳を開く。声はいつものフミヤ先輩の声だけど、いつもと違うもじゃもじゃの髪の先輩。カフェでの完璧な姿とのギャップに、まだ戸惑いを感じる。それでも――。
「僕も……先輩のもじゃもじゃ、触ってもいいですか?」
「んー、ほかの人なら嫌だけど、さっちゃんならいいかぁ」
そういうことを淡々と述べるのはとてもずるい。そう心の中で思ったつもりだったけれど、どうやら実際に口に出していたようで、フミヤ先輩は「え、だめ?」と飄々と笑っている。
「こっち来て触ってよ、さっちゃん」
躊躇いながらも、先輩のあとに続いて階段を上る。大袈裟だけれど、僕には一歩一歩が、未知の領域に踏み込むような緊張感に満ちていた。
先輩に連れられ、階段の三段目に腰を下ろす。隣に座る先輩の長い脚が、僕の視界の端で存在感を放っていた。ふたりの距離の近さに、悔しいくらい呼吸が乱れてしまう。
突然、先輩の大きな手が僕の右手を包み込んだ。伝わる温もりに、一瞬時が止まったかのような錯覚を覚えた。そして、その手に導かれるまま、フミヤ先輩の髪に触れた瞬間、思わず息を呑む。
「や、柔らか……」
予想をはるかに超える柔らかさだった。ふわふわの髪の中を探るように、ゆっくりと指先を動かす。
「なんか犬になった気分」
指を動かすたび、まるで先輩に心を許してもらっているような気がして、胸の奥がキュンと軋む。
ワックスでキメた時のクールな印象も素敵だけど、シフォンケーキのようなふわふわ感も悪くない……気がする。もちろん、比べようもないくらい僕の一番は、イケメンのフミヤ先輩だ。
「さっちゃんの手きもちー。……眠くなってきたわ」
先輩は度重なるバイトと学業の両立で、ひどく疲れているのかもしれない。省エネを目指すフミヤ先輩のまぶたが、だんだんと重くなっていく。
「いいですよ。……僕の膝で寝ても」
自分の声が少し震えているのを感じた。心臓が早鐘を打っている。僕は先輩の髪に触れていないほうの手で、ためらいがちに膝をポンポンと叩いた。この小さな仕草が、彼にとってどれほどの意味を持つのか、自分でもよくわかっていない。
「ほんとに?」
先輩の声には、いつもの冗談めかした雰囲気が混ざっている。でも、とろんとした瞳の奥に、僕は何か別のものを見た気がした。期待? 不安? それともまったく違う何か。
「ほかの人は嫌だけど、先輩ならいいです」
僕はさっきのお返しとばかりに、わざとらしく瞳を潤ませて先輩をじっと見つめる。冗談っぽい仕草で誤魔化したのは、ふたりの繋がった視線に言葉以上のメッセージが込められているかもしれないと考え、少しだけ怖くなったからだ。
「あざといな」
先輩の軽やかな笑い声が、緊張した空気を柔らかく溶かす。
「じゃあお言葉に甘えまして」
彼はゆっくりと僕の膝に頭を乗せた。その動作の慎重さに、フミヤ先輩の優しさと気づかいを感じる。
どうしてこんなことになったんだっけ。僕は先輩の髪を撫でながら、不思議な気持ちに包まれていた。ほんの少し前までは、こんな展開になるとは夢にも思わなかった。でも今は、ちょっとだけこの瞬間を楽しんでいる自分がいる。
先輩の規則正しい寝息を聞きながら、ふわふわと風船みたいに漂っている自分の気持ちを掴もうとしていた。
やっぱりよくわからない。
たしかなのは、この瞬間が特別だということ。そして、これからのふたりの関係が、少しずつ、でも確実に変わっていくだろうということ。甘くて切ない予感に、僕は期待と不安を抱きながら、もう一度彼のもじゃもじゃな髪に手を差し入れた。
十分間くらい、先輩は僕の膝で静かに眠っていた。その間、僕は先輩の寝顔を見つめたり、彼の髪を撫でたりしていた。カフェ店員をやっている時には、絶対に見せない脱力した無防備な表情。今、僕だけが見ているその姿に、ちょっとした優越感を持ってしまったのは、誰にも言えない秘密だ。
ふたりで学校を出る頃には、外の景色が変わっていた。小雨が降り始め、まるで世界がぼんやりとした霞の中に包まれているみたいだった。
「あ、降ってんね」
「……ほんとですね」
「もしかしてさっちゃん、傘持ってない?」
「持っ、……てないです」
先輩の言葉に、一瞬ためらった。本当は鞄の中に折りたたみ傘があることを正直に言うべきだとわかっていたけれど、先輩との時間をもっと共有したいという気持ちが、正直さを上回ってしまう。フミヤ先輩に知られたら、またきっと「あざとい」と言われてしまうだろう。
「よかったらこれ使って。膝貸してもらったお礼」
三年生専用の傘立てから二本の傘を持って戻ってきた先輩が、ありきたりな透明の傘ではない、ピンク色の愛らしいほうの傘を僕に差し出す。
「昔、妹が買ったやつだから、すげぇハート描いてあるけど。嫌だったら、俺が使うから」
以前たまたま使って、それ以来傘立ての隅に忘れ去られていたらしい。このハートの傘で登校したフミヤ先輩を想像すると、自然と頬が緩んでしまった。
「ははっ、フミヤ先輩がハートの傘」
「笑ってんなよ、一年」
「先輩には似合いませんけど、きっと僕なら似合いますよ」
「どうだろうね。俺を超えられるかな、さっちゃん」
下駄箱で上履きを履き替え、貸してもらった傘を差して、水溜まりをひょいと跳び越えた。湿気で髪の毛が爆発するから雨の日は大っ嫌いだったけれど、なんだか今日はすべてが許せるような気がする。
「あっさり超えられたな。やっぱ似合うわ、さっちゃんのほうが」
「でしょう?」
自分で言うのもなんだけど、僕の圧勝だ。ハートの傘の柄を持ち、くるくると回す。
「竹内幸朗家ってどっち方面? のぼり? くだり?」
「くだりの八駅先です。ていうか、そこの三年、本名で呼ばないでください」
ぶつぶつと文句を言っていると、先輩はもじゃもじゃの髪の奥で目を丸くした。
「なんだ、方向一緒じゃん」
フミヤ先輩のバイト先は学校から三駅先。フミヤ先輩の家は同じ路線で、僕が降りる駅より三つほど前の駅周辺に住んでいるらしかった。
乗る電車は一緒なのにどうして今まで会わなかったかというと、フミヤ先輩が省エネ系男子高校生だからだ。毎朝、ギリギリ学校に間に合う一番遅い電車に乗っていると聞き、僕は呆れてしまった。そういう僕は、もちろん余裕を持って地下鉄に乗っている。
「俺、これからバイトだけど、さっちゃん、一緒にカフェ来る?」
雨の湿気で髪の毛が爆発しているフミヤ先輩を、ちらりと見つめる。僕はこみ上げる笑顔を押し殺し、少しだけ迷うフリをしてから、彼の誘いにこくりとうなずいた。
地下鉄の車内は、高校生やサラリーマン、買い物帰りの親子連れでそこそこ賑わっていた。車両の端っこの空いている席にふたり並んで座る。いつもカフェでしか会わない先輩と一緒に電車に乗るのは、とても新鮮だった。
フミヤ先輩は、また省エネモードに入っているのか、それとも眠くなってしまったのか、とても静かだ。けれど、その沈黙が気詰まりに感じられないのは、先輩の持つ独特な雰囲気のせいかもしれない。先輩は本当に不思議な人だ。
「さっちゃんはメイクが好きなの?」
突然の問いかけに、少しだけ驚いた。とろんとした眠そうな目で穏やかに見つめてくる先輩の視線が、僕からゆっくりと鞄に向けられている。さっき買うのを付き合ってもらったメイク雑誌のことを言っているのだと気づき、僕はこくりとうなずいた。
「好きです。いつか仕事にしたいなって思ってます」
僕は手持ち無沙汰につま先を揃えながら、先輩のほうを見上げた。
「小さい頃から、ヴァイオリンもピアノも水泳もそろばんも体操も、習い事はぜんぶ続かなかったんです。だけど、メイクへの興味だけはずっとあって……」
正確に言えば、一度だけその興味も手放してしまった時期があった。でも、あえて僕はそのことには触れず、言葉を続けた。
「ママに借りて、口紅塗ったりしてました。塗り方がへたくそだったんで、血だらけのおばけみたいになりましたけど」
思い出話をする僕の顔を見つめ、先輩は破顔する。
「そっか。それはかわいいな」
「……先輩って、かわいいの範囲が広すぎません?」
「そう?」
先ほど頭を撫でられながら言われた言葉が、脳裏に浮かぶ。
――さっちゃんは、一生懸命でとってもかわいいよ。
もしかしたら誰にでもかわいいと言っているのかもしれない。
「じゃあ、あの女の子は?」
僕は、斜め前に母親と座っている三歳くらいの女の子に目線を合わせた。小さなくまのぬいぐるみを大事そうに抱えている彼女を眺め、先輩は微笑ましそうに瞳を細める。
「かわいいね」
「じゃあ、あの子が持ってるくまのぬいぐるみは?」
くすくすと肩を揺らして先輩が笑う。
「かわいいよ」
「あっちに座ってるサラリーマンのおじさん……」
「えー、なんかかわいいような気がしてきた」
「もう先輩!」
冗談か本気かわからない先輩の肩を押す。その瞬間、先輩が僕の手を優しく握った。
「でも、さっちゃんが一番かわいいよ」
先輩の言葉に、僕の頬が熱くなる。周りの人目を気にしながらも、僕は先輩の手を振りほどくことができなかった。
それから数秒後、先輩は自然な仕草で僕から手を離した。少しだけ残念に思ってしまったのを顔に出さないようにする。
「もっと教えてよ、さっちゃんの小さい頃の話。小学生の頃とか」
「……え」
不安を警告するように、一瞬痛いくらいの動悸が心臓を打った。
小学生の時の僕。
好きなものを呆気なく手放してしまったあの頃の僕。
殻の中に閉じ込もっていた暗い日々を思い出しそうになり、僕は無理やり口角を上げた。
「べ、別に……どこにでもいる普通の子どもですよ」
本当のことを言えずにいる自分を情けなく思う。先輩は僕の雰囲気を察したのか、それ以上聞いてくることはなかった。
次の駅のアナウンスが流れ、地下鉄がホームに滑り込むように止まる。まだ僕らが降りる駅ではなかったので、何気なく出口を見た。その時、
「くましゃん!」
まるで悲鳴のような女の子の声が聞こえた。先ほどの親子連れがホームに降りる瞬間、女の子がくまのぬいぐるみを落としてしまったようだ。くまのぬいぐるみを取ろうとして、女の子が慌てて車内に戻ろうとする。
「だ、だめよ! あぶないっ!」
女の子の母親が、咄嗟に彼女を抱きかかえた。駅のアナウンスが、
――ドアが閉まります。
と、冷たく警告する。幼い女の子は車内に残されたくまのぬいぐるみがよっぽど大事だったらしく、目には大粒の涙を浮かべていた。
僕を含めて、おそらく電車に乗っている誰もが諦めていた。たったひとりフミヤ先輩を除いて。
ドアが閉まりかけた一瞬、フミヤ先輩は素早く立ち上がると、くまのぬいぐるみを持ち上げ、女の子に向けて優しく放り投げた。
ぬいぐるみが美しい弧を描く。女の子は「あ!」と声を上げ、両手を広げてしっかりとくまのぬいぐるみをキャッチした。プシューと音が鳴り響き、扉が閉まるとともに電車がゆっくりと動き出す。
「おにいちゃん、ありがとうっ!」
声は聞こえなかったけれど、幼い彼女の満面の笑顔を見れば、そう言っているのが手に取るようにわかった。
フミヤ先輩は扉の向こう側に、手を振り続けていた。ホームにいる女の子の姿が見えなくなるまで優しく見守る姿に、僕は胸が熱くなるのを感じる。電車が徐々に加速し、駅のホームが遠ざかっていく。
僕の隣に戻ってきた先輩は、少し息を弾ませながらつぶやいた。
「……今のはガチで焦った」
僕は隣の席に腰を下ろす先輩の姿を見つめていた。ついさっきまで省エネモードだった先輩が、誰かのためならためらわずに行動できる。深い感銘を受けると同時に、自分にはできない行動だと痛感した。
車内の雰囲気が一変したのが伝わってくる。先ほどまで無関心だった乗客たちが、フミヤ先輩の咄嗟の行動を見て、どこか興奮気味にささやき合っている。
「あの女の子よかったね」
「てか、ぎりぎりだったね、あの高校生すごくない? かっこよかった」
まるでヒーローを見るみたいに、みんながフミヤ先輩に羨望のまなざしを送っていた。その中心にいる先輩はといえば、まったく何も気にせず、いつも通り淡々と過ごしている。
「す、すごかったですね、フミヤ先輩……」
僕は先輩にそう告げると、だんだんと笑いが堪えられなくなっていった。すごいものを見たという興奮が、笑いという形で溢れ出す。
「笑いすぎだって、さっちゃん」
少し動いて熱くなったのか、先輩は長い前髪を片手でかき上げた。整った瞳が一瞬露わになり、そしてすぐにまた前髪に隠れてしまう。何気ないその仕草に、僕の心臓が小さく跳ねる。
「……だって、めちゃくちゃ素早かった。そんなに速く動けるの、忍者か、フミヤ先輩くらいですって」
「ほんと? カフェじゃなくて、忍者の面接受ければよかったかな」
フミヤ先輩が真面目な顔で言うから、僕はますます笑いを抑えられなくなる。
「女の子、言ってましたよ。『もじゃもじゃニキ、ありがとう』って」
「もじゃもじゃニキは言ってねえだろ」
先輩のツッコミに、僕はもう声を殺して笑うしかなかった。こんなにも電車がいつまでも駅に着かないでほしいと思うのは初めてだ。
「さっちゃんがいると、やる気が倍増するわ」
先輩はカフェの軒下に着くと、濡れた傘を閉じながらそう言って笑った。誘われるがままカフェに着いてきたものの、僕はまだこのもじゃもじゃなフミヤ先輩が、本当にあのイケメン店員と同一人物なのか、半信半疑でいた。
僕に手を振り、裏口の扉からカフェに入っていった先輩。僕は少しだけ迷ったあと、意を決して店内へと足を踏み入れた。いつも座っている奥のテーブルに陣取り、じっと先輩が現れるのを待つ。
窓ガラスを伝う雨粒が、外の景色をぼんやりと歪めていた。しばらくしてカウンターの向こうに現れたフミヤ先輩は、普段どおり白いシャツの袖をきっちりと折り返し、黒いエプロンを身にまとっていた。けれど、髪はまだもじゃもじゃのままだ。僕がだんだん不安になってきた矢先、先輩はおもむろに手首に付けていたゴムで髪を縛り始めた。手ぐしでハーフアップに整えられた髪、まさに戦闘モードのような凜々しいまなざし。心臓がドクドクと早鐘を打つ。やっぱり同一人物なんだ……。
「さっちゃん、これ俺のおごり。アプリ見たら、あと二十分くらいで、雨弱まるってさ」
僕が驚いている間に、先輩はアイスティーをいれてくれたようだ。慌てて礼を言うと、先輩はかすかに口角を上げ、スマートな仕草で業務へと戻っていく。
アイスティーをストローでかき混ぜると、カランとかわいい音が漏れた。カフェはいつ来ても穏やかで、とても居心地がいい。僕はおいしいアイスティーを飲みながら、ずっと先輩の姿を目で追っていた。
「いらっしゃいませ、何名様ですか?」
落ち着いた態度と洗練された動き。先輩が働く姿は、やっぱり文句なしにかっこよかった。
今日は、先輩の新しい一面をたくさん見られた気がする。
もっともっとフミヤ先輩のことを知りたい。そんな衝動が僕の中で大きくなっているのを、自分でもどうしようもないくらいに感じていた。
あの指切りげんまんから一週間、僕はカフェに通い続けた。当日は、もらったIDに僕からメッセージを送った。次の日はラインのIDを教え合い、次の日には先輩に双子の妹がいることを教えてもらった。その次の日には先輩がバイセクシャルで、僕がゲイだと教え合った。その次の日には初めて電話をして、その次の次の日には夜遅くまでメッセージを交わし合った。
『なんと来週から新しく「シトラスティーパフェ」が出ます』
『食べたい! 絶対食べに行きます!』
『待ってるよ、幸朗』
『本名で呼ぶなぁ……。あ、フミヤ先輩がパフェの名前を忘れても僕が教えますから、安心してくださいね』
『その節は大変お世話になりました』
放課後の教室で、僕は昨日のラインのやりとりを見つめ、「ふふっ」と勝手に口から笑みがこぼれてしまった。最近はちょっとした冗談も言い合えるようになり、心の距離も少しだけ近づいたような気がする。
僕のにやついた顔を見たモモが、「幸せそうだねぇ、さっちゃん」とからかってくる。
「まぁまぁかな。今はゆっくりお互いを知っていくところだから」
だらしない顔を急いで戻し、僕はキリッとしてつぶやいた。
フミヤ先輩がある日突然、君と連絡するのはこれきりにしたいと言うかもしれないし、逆に僕がそう言うかもしれない。でもなんだかんだ言っても、先輩とやりとりできるのは、やっぱり言葉にならないくらい嬉しい。
「さっちゃんに春が来たって、あさ子さんに報告しよっと」
「気が早いって」
「なんでいいじゃん、うちは嬉しいんだから」
モモは椅子から立ち上がると、スマホの時計を見やった。
「そろそろ行かなきゃ」
まるで外国のお土産のお菓子みたいに、甘々な顔でモモが笑う。
「あさ子さんと楽しんできてね、デート」
「りょうかい。てか、はやくフミヤ先輩も一緒に、四人でWデートしたいね」
「だから、気が早すぎだって……。いいから、もう行きな!」
僕はまんざらでもない顔をして、犬でも追い払うようにシッシッと右手でジェスチャーした。軽やかな笑い声と、タータンチェックの短いスカートが、ひらひらと揺れながら遠ざかっていく。
フミヤ先輩は夕方からバイトだって言ってたっけ。あとでまたカフェに遊びに行こうかな。そんなことを考えてご機嫌に廊下を歩いていると、突然、声をかけられて身震いした。
「……さっちゃん?」
振り向いた先には、見た目にまったく気をつかってなさそうな男子高校生がいた。
「あ、ほんとにさっちゃんだ」
上履きの色から察するに、学年は二つ上だ。長身でスタイルはいいけど、伸びたくせっ毛はぼさぼさで、長すぎる前髪のせいで瞳は見えず、制服もシャツのボタンを上から二つも外していてだらしない。ネクタイだって、かろうじて結ばれているようなルーズさだ。
思わず顔をしかめそうになるのを抑え、こんな知り合いがいただろうかとしばらく逡巡した。いや、どう考えても知り合いなわけがない。僕は見た目に気をつかわない人間が一番苦手なのだ。
「やっぱ同じ高校だったんだ。制服似てると思った」
そう言って近づいてくる彼に、警戒心が強い猫のような鋭い視線を返す。
「昨日聞こうと思って忘れてたわ。でも、よかったね、さっちゃん。カフェ以外でも会えるから」
彼は制服のズボンのポケットに両手を突っ込んで、やけに親しげに話しかけてくる。僕は死んだ魚のような目をして、曖昧に流そうとした。――でも、なぜか彼の声が、どこか聞き覚えがあることに気づいた。
それに……ほんのかすかに漂う爽やかで甘いムスクみたいな香水の香りも。
――でも、よかったね、さっちゃん。カフェ以外でも会えるから。
僕はまるで雷に打たれたように、点と点が繋がるのを感じた。
「カフェって……も、もしかして……」
急いで彼のそばに行き、恐る恐る乱れたもじゃもじゃの前髪をかき分けてみる。すると、そこには――。
「フ、フミヤ先輩!?」
「あれ、もしかして気づいてなかった?」
けらけらと笑った彼の顔は、あのフミヤ先輩に間違いなかった。けれど、カフェでビシッと髪を結わき、黒いエプロンをつけてキビキビと働く店員の姿と、今のだらしない男子高校生の姿とでは、まるで月とすっぽんで同じ人物とは思えない。
僕にとってフミヤ先輩と一緒の高校なのはとてもラッキーだけれど、もじゃもじゃのこの人と一緒なのは全然ラッキーじゃなかった。
ほかの生徒たちが、なんだなんだと僕たちの様子を窺っていた。廊下のど真ん中で話すことじゃないと悟った僕は、困惑しながらもフミヤ先輩の腕を引っ張って、人目につかない非常階段のほうへと向かった。
「先輩、なんでですか!? ど、どうしてこんな無惨な姿に……!?」
「無惨て」
フミヤ先輩はもじゃもじゃの前髪の奥で、困ったように目を細めながら言う。
「どっちかっつうと、こっちのほうが素なんだけど……。バイト先のはオンモードっていうか、戦闘モードっていうか」
「学校でもオンになってくださいよ!」
「えー、でも……金、出ねぇしな」
「僕が出しますから!」
「ははっ。ほんとおもしれぇね、さっちゃん。愉快愉快」
フミヤ先輩は、ことの重大さがわかっていない。あんなにもすごいポテンシャルを持っているのに、学校ではお金が出ないという非常に不憫な理由で、イケメンで居続ける努力を怠っているのだ。
「愉快愉快じゃないですよ! ほんとになんなんですかこの頭! せっかくのきれいな先輩の目が、全然見えないじゃないですかぁ!」
「さっちゃん、俺の目褒めてくれんの? うれしー」
「……そ、そうじゃなくて! 髪型の話ですよ、髪型の!」
「だって、朝、髪整えんのめんどくさいし……。バイトの時だけでいっかなって」
ね? と、悪びれもせず同意を求められて、体中の力がどっと抜けていく。
「燃費悪いから、できれば省エネで生きたいんだよね」
燃費……? 省エネ……?
僕はわなわなと震え、フミヤ先輩に詰め寄った。
「僕は毎朝スタイリングしてます! 髪もアイロンかけてますし、朝パックもします! 化粧水も乳液も美容液もクリームも塗りますし、日焼け対策も、ファンデも、マスカラもリップも、えーとそれから……!」
日々、かわいいを作り出すための努力を息切れしながら力説する。おそらく並の男の子だったら気分を害したはずだけれど、さすがのフミヤ先輩は悠々としていた。
「すげぇえらいじゃん、さっちゃん」
そうやって感心されても内心は複雑だ。
「……僕のがんばりに対して、その言葉だけじゃちょっと足りないと思います」
フミヤ先輩はおもしろがるように、にっと口角を上げる。
「足りないかぁ。俺、何すればいい?」
「この前みたいに頭を撫でてもらうとか……」
「こう?」
別に意地悪を言いたかっただけで、本当に撫でてもらいたかったわけじゃない。なのに、フミヤ先輩の長い指に触れられたら、気持ちがよくてすべてがどうでもよくなってしまった。
「よしよし、さっちゃん。がんばっててえらいね」
先輩の手からマイナスイオンでも出ているのか、それとも僕の前世が気まぐれな猫だったのか。先輩の指が僕の髪に触れるたび、抵抗する力が奪われていく。
「僕、ほんとに毎日がんばってます……」
飼い主にすり寄る猫のように、僕はにゃあにゃあと鳴いた。
「うん。さっちゃんは、一生懸命でとってもかわいいよ」
今の言葉がイケメンカフェ店員のフミヤ先輩からだったら、鼻血が出るくらい興奮してしまったかもしれない。あのカフェで働く先輩の姿を思い浮かべただけで、胸がキュンとなり、頬が熱くなる。完璧な笑顔、洗練された立ち振る舞い、そのすべてが僕の心を掴んで離さない。
でも、目の前にいる彼は、
「先輩は、もじゃもじゃ……ですね」
カフェにいる彼とは違う。もじゃもじゃの髪、だらりとリラックスした表情。カフェのギャルソン風ではなく、ラフでだらしない省エネ系男子高校生の制服姿。
「おーありがと」
「全然褒めてないです」
「こら一年生、そういうこと言わない」
気だるげに目を細めたフミヤ先輩は、生意気な僕の発言にもまったく気にしている素振りを見せなかった。僕の髪の毛に指先を絡めて、感心したようにつぶやく。
「髪、さらさらじゃん。あとすげぇキラキラ。前から思ってたけど、この銀髪いいよね。ブリーチした?」
「……しました」
撫でられて、褒められて、笑顔を向けられて、気がつけば、うっとりと目を閉じていた。喉から漏れる甘い声。自分でも信じられないほど先輩に身を委ねている。
どれだけそうされていたのか、
「はい、おしまい」
先輩の声で現実に引き戻された。ゆっくりと瞳を開く。声はいつものフミヤ先輩の声だけど、いつもと違うもじゃもじゃの髪の先輩。カフェでの完璧な姿とのギャップに、まだ戸惑いを感じる。それでも――。
「僕も……先輩のもじゃもじゃ、触ってもいいですか?」
「んー、ほかの人なら嫌だけど、さっちゃんならいいかぁ」
そういうことを淡々と述べるのはとてもずるい。そう心の中で思ったつもりだったけれど、どうやら実際に口に出していたようで、フミヤ先輩は「え、だめ?」と飄々と笑っている。
「こっち来て触ってよ、さっちゃん」
躊躇いながらも、先輩のあとに続いて階段を上る。大袈裟だけれど、僕には一歩一歩が、未知の領域に踏み込むような緊張感に満ちていた。
先輩に連れられ、階段の三段目に腰を下ろす。隣に座る先輩の長い脚が、僕の視界の端で存在感を放っていた。ふたりの距離の近さに、悔しいくらい呼吸が乱れてしまう。
突然、先輩の大きな手が僕の右手を包み込んだ。伝わる温もりに、一瞬時が止まったかのような錯覚を覚えた。そして、その手に導かれるまま、フミヤ先輩の髪に触れた瞬間、思わず息を呑む。
「や、柔らか……」
予想をはるかに超える柔らかさだった。ふわふわの髪の中を探るように、ゆっくりと指先を動かす。
「なんか犬になった気分」
指を動かすたび、まるで先輩に心を許してもらっているような気がして、胸の奥がキュンと軋む。
ワックスでキメた時のクールな印象も素敵だけど、シフォンケーキのようなふわふわ感も悪くない……気がする。もちろん、比べようもないくらい僕の一番は、イケメンのフミヤ先輩だ。
「さっちゃんの手きもちー。……眠くなってきたわ」
先輩は度重なるバイトと学業の両立で、ひどく疲れているのかもしれない。省エネを目指すフミヤ先輩のまぶたが、だんだんと重くなっていく。
「いいですよ。……僕の膝で寝ても」
自分の声が少し震えているのを感じた。心臓が早鐘を打っている。僕は先輩の髪に触れていないほうの手で、ためらいがちに膝をポンポンと叩いた。この小さな仕草が、彼にとってどれほどの意味を持つのか、自分でもよくわかっていない。
「ほんとに?」
先輩の声には、いつもの冗談めかした雰囲気が混ざっている。でも、とろんとした瞳の奥に、僕は何か別のものを見た気がした。期待? 不安? それともまったく違う何か。
「ほかの人は嫌だけど、先輩ならいいです」
僕はさっきのお返しとばかりに、わざとらしく瞳を潤ませて先輩をじっと見つめる。冗談っぽい仕草で誤魔化したのは、ふたりの繋がった視線に言葉以上のメッセージが込められているかもしれないと考え、少しだけ怖くなったからだ。
「あざといな」
先輩の軽やかな笑い声が、緊張した空気を柔らかく溶かす。
「じゃあお言葉に甘えまして」
彼はゆっくりと僕の膝に頭を乗せた。その動作の慎重さに、フミヤ先輩の優しさと気づかいを感じる。
どうしてこんなことになったんだっけ。僕は先輩の髪を撫でながら、不思議な気持ちに包まれていた。ほんの少し前までは、こんな展開になるとは夢にも思わなかった。でも今は、ちょっとだけこの瞬間を楽しんでいる自分がいる。
先輩の規則正しい寝息を聞きながら、ふわふわと風船みたいに漂っている自分の気持ちを掴もうとしていた。
やっぱりよくわからない。
たしかなのは、この瞬間が特別だということ。そして、これからのふたりの関係が、少しずつ、でも確実に変わっていくだろうということ。甘くて切ない予感に、僕は期待と不安を抱きながら、もう一度彼のもじゃもじゃな髪に手を差し入れた。
十分間くらい、先輩は僕の膝で静かに眠っていた。その間、僕は先輩の寝顔を見つめたり、彼の髪を撫でたりしていた。カフェ店員をやっている時には、絶対に見せない脱力した無防備な表情。今、僕だけが見ているその姿に、ちょっとした優越感を持ってしまったのは、誰にも言えない秘密だ。
ふたりで学校を出る頃には、外の景色が変わっていた。小雨が降り始め、まるで世界がぼんやりとした霞の中に包まれているみたいだった。
「あ、降ってんね」
「……ほんとですね」
「もしかしてさっちゃん、傘持ってない?」
「持っ、……てないです」
先輩の言葉に、一瞬ためらった。本当は鞄の中に折りたたみ傘があることを正直に言うべきだとわかっていたけれど、先輩との時間をもっと共有したいという気持ちが、正直さを上回ってしまう。フミヤ先輩に知られたら、またきっと「あざとい」と言われてしまうだろう。
「よかったらこれ使って。膝貸してもらったお礼」
三年生専用の傘立てから二本の傘を持って戻ってきた先輩が、ありきたりな透明の傘ではない、ピンク色の愛らしいほうの傘を僕に差し出す。
「昔、妹が買ったやつだから、すげぇハート描いてあるけど。嫌だったら、俺が使うから」
以前たまたま使って、それ以来傘立ての隅に忘れ去られていたらしい。このハートの傘で登校したフミヤ先輩を想像すると、自然と頬が緩んでしまった。
「ははっ、フミヤ先輩がハートの傘」
「笑ってんなよ、一年」
「先輩には似合いませんけど、きっと僕なら似合いますよ」
「どうだろうね。俺を超えられるかな、さっちゃん」
下駄箱で上履きを履き替え、貸してもらった傘を差して、水溜まりをひょいと跳び越えた。湿気で髪の毛が爆発するから雨の日は大っ嫌いだったけれど、なんだか今日はすべてが許せるような気がする。
「あっさり超えられたな。やっぱ似合うわ、さっちゃんのほうが」
「でしょう?」
自分で言うのもなんだけど、僕の圧勝だ。ハートの傘の柄を持ち、くるくると回す。
「竹内幸朗家ってどっち方面? のぼり? くだり?」
「くだりの八駅先です。ていうか、そこの三年、本名で呼ばないでください」
ぶつぶつと文句を言っていると、先輩はもじゃもじゃの髪の奥で目を丸くした。
「なんだ、方向一緒じゃん」
フミヤ先輩のバイト先は学校から三駅先。フミヤ先輩の家は同じ路線で、僕が降りる駅より三つほど前の駅周辺に住んでいるらしかった。
乗る電車は一緒なのにどうして今まで会わなかったかというと、フミヤ先輩が省エネ系男子高校生だからだ。毎朝、ギリギリ学校に間に合う一番遅い電車に乗っていると聞き、僕は呆れてしまった。そういう僕は、もちろん余裕を持って地下鉄に乗っている。
「俺、これからバイトだけど、さっちゃん、一緒にカフェ来る?」
雨の湿気で髪の毛が爆発しているフミヤ先輩を、ちらりと見つめる。僕はこみ上げる笑顔を押し殺し、少しだけ迷うフリをしてから、彼の誘いにこくりとうなずいた。
地下鉄の車内は、高校生やサラリーマン、買い物帰りの親子連れでそこそこ賑わっていた。車両の端っこの空いている席にふたり並んで座る。いつもカフェでしか会わない先輩と一緒に電車に乗るのは、とても新鮮だった。
フミヤ先輩は、また省エネモードに入っているのか、それとも眠くなってしまったのか、とても静かだ。けれど、その沈黙が気詰まりに感じられないのは、先輩の持つ独特な雰囲気のせいかもしれない。先輩は本当に不思議な人だ。
「さっちゃんはメイクが好きなの?」
突然の問いかけに、少しだけ驚いた。とろんとした眠そうな目で穏やかに見つめてくる先輩の視線が、僕からゆっくりと鞄に向けられている。さっき買うのを付き合ってもらったメイク雑誌のことを言っているのだと気づき、僕はこくりとうなずいた。
「好きです。いつか仕事にしたいなって思ってます」
僕は手持ち無沙汰につま先を揃えながら、先輩のほうを見上げた。
「小さい頃から、ヴァイオリンもピアノも水泳もそろばんも体操も、習い事はぜんぶ続かなかったんです。だけど、メイクへの興味だけはずっとあって……」
正確に言えば、一度だけその興味も手放してしまった時期があった。でも、あえて僕はそのことには触れず、言葉を続けた。
「ママに借りて、口紅塗ったりしてました。塗り方がへたくそだったんで、血だらけのおばけみたいになりましたけど」
思い出話をする僕の顔を見つめ、先輩は破顔する。
「そっか。それはかわいいな」
「……先輩って、かわいいの範囲が広すぎません?」
「そう?」
先ほど頭を撫でられながら言われた言葉が、脳裏に浮かぶ。
――さっちゃんは、一生懸命でとってもかわいいよ。
もしかしたら誰にでもかわいいと言っているのかもしれない。
「じゃあ、あの女の子は?」
僕は、斜め前に母親と座っている三歳くらいの女の子に目線を合わせた。小さなくまのぬいぐるみを大事そうに抱えている彼女を眺め、先輩は微笑ましそうに瞳を細める。
「かわいいね」
「じゃあ、あの子が持ってるくまのぬいぐるみは?」
くすくすと肩を揺らして先輩が笑う。
「かわいいよ」
「あっちに座ってるサラリーマンのおじさん……」
「えー、なんかかわいいような気がしてきた」
「もう先輩!」
冗談か本気かわからない先輩の肩を押す。その瞬間、先輩が僕の手を優しく握った。
「でも、さっちゃんが一番かわいいよ」
先輩の言葉に、僕の頬が熱くなる。周りの人目を気にしながらも、僕は先輩の手を振りほどくことができなかった。
それから数秒後、先輩は自然な仕草で僕から手を離した。少しだけ残念に思ってしまったのを顔に出さないようにする。
「もっと教えてよ、さっちゃんの小さい頃の話。小学生の頃とか」
「……え」
不安を警告するように、一瞬痛いくらいの動悸が心臓を打った。
小学生の時の僕。
好きなものを呆気なく手放してしまったあの頃の僕。
殻の中に閉じ込もっていた暗い日々を思い出しそうになり、僕は無理やり口角を上げた。
「べ、別に……どこにでもいる普通の子どもですよ」
本当のことを言えずにいる自分を情けなく思う。先輩は僕の雰囲気を察したのか、それ以上聞いてくることはなかった。
次の駅のアナウンスが流れ、地下鉄がホームに滑り込むように止まる。まだ僕らが降りる駅ではなかったので、何気なく出口を見た。その時、
「くましゃん!」
まるで悲鳴のような女の子の声が聞こえた。先ほどの親子連れがホームに降りる瞬間、女の子がくまのぬいぐるみを落としてしまったようだ。くまのぬいぐるみを取ろうとして、女の子が慌てて車内に戻ろうとする。
「だ、だめよ! あぶないっ!」
女の子の母親が、咄嗟に彼女を抱きかかえた。駅のアナウンスが、
――ドアが閉まります。
と、冷たく警告する。幼い女の子は車内に残されたくまのぬいぐるみがよっぽど大事だったらしく、目には大粒の涙を浮かべていた。
僕を含めて、おそらく電車に乗っている誰もが諦めていた。たったひとりフミヤ先輩を除いて。
ドアが閉まりかけた一瞬、フミヤ先輩は素早く立ち上がると、くまのぬいぐるみを持ち上げ、女の子に向けて優しく放り投げた。
ぬいぐるみが美しい弧を描く。女の子は「あ!」と声を上げ、両手を広げてしっかりとくまのぬいぐるみをキャッチした。プシューと音が鳴り響き、扉が閉まるとともに電車がゆっくりと動き出す。
「おにいちゃん、ありがとうっ!」
声は聞こえなかったけれど、幼い彼女の満面の笑顔を見れば、そう言っているのが手に取るようにわかった。
フミヤ先輩は扉の向こう側に、手を振り続けていた。ホームにいる女の子の姿が見えなくなるまで優しく見守る姿に、僕は胸が熱くなるのを感じる。電車が徐々に加速し、駅のホームが遠ざかっていく。
僕の隣に戻ってきた先輩は、少し息を弾ませながらつぶやいた。
「……今のはガチで焦った」
僕は隣の席に腰を下ろす先輩の姿を見つめていた。ついさっきまで省エネモードだった先輩が、誰かのためならためらわずに行動できる。深い感銘を受けると同時に、自分にはできない行動だと痛感した。
車内の雰囲気が一変したのが伝わってくる。先ほどまで無関心だった乗客たちが、フミヤ先輩の咄嗟の行動を見て、どこか興奮気味にささやき合っている。
「あの女の子よかったね」
「てか、ぎりぎりだったね、あの高校生すごくない? かっこよかった」
まるでヒーローを見るみたいに、みんながフミヤ先輩に羨望のまなざしを送っていた。その中心にいる先輩はといえば、まったく何も気にせず、いつも通り淡々と過ごしている。
「す、すごかったですね、フミヤ先輩……」
僕は先輩にそう告げると、だんだんと笑いが堪えられなくなっていった。すごいものを見たという興奮が、笑いという形で溢れ出す。
「笑いすぎだって、さっちゃん」
少し動いて熱くなったのか、先輩は長い前髪を片手でかき上げた。整った瞳が一瞬露わになり、そしてすぐにまた前髪に隠れてしまう。何気ないその仕草に、僕の心臓が小さく跳ねる。
「……だって、めちゃくちゃ素早かった。そんなに速く動けるの、忍者か、フミヤ先輩くらいですって」
「ほんと? カフェじゃなくて、忍者の面接受ければよかったかな」
フミヤ先輩が真面目な顔で言うから、僕はますます笑いを抑えられなくなる。
「女の子、言ってましたよ。『もじゃもじゃニキ、ありがとう』って」
「もじゃもじゃニキは言ってねえだろ」
先輩のツッコミに、僕はもう声を殺して笑うしかなかった。こんなにも電車がいつまでも駅に着かないでほしいと思うのは初めてだ。
「さっちゃんがいると、やる気が倍増するわ」
先輩はカフェの軒下に着くと、濡れた傘を閉じながらそう言って笑った。誘われるがままカフェに着いてきたものの、僕はまだこのもじゃもじゃなフミヤ先輩が、本当にあのイケメン店員と同一人物なのか、半信半疑でいた。
僕に手を振り、裏口の扉からカフェに入っていった先輩。僕は少しだけ迷ったあと、意を決して店内へと足を踏み入れた。いつも座っている奥のテーブルに陣取り、じっと先輩が現れるのを待つ。
窓ガラスを伝う雨粒が、外の景色をぼんやりと歪めていた。しばらくしてカウンターの向こうに現れたフミヤ先輩は、普段どおり白いシャツの袖をきっちりと折り返し、黒いエプロンを身にまとっていた。けれど、髪はまだもじゃもじゃのままだ。僕がだんだん不安になってきた矢先、先輩はおもむろに手首に付けていたゴムで髪を縛り始めた。手ぐしでハーフアップに整えられた髪、まさに戦闘モードのような凜々しいまなざし。心臓がドクドクと早鐘を打つ。やっぱり同一人物なんだ……。
「さっちゃん、これ俺のおごり。アプリ見たら、あと二十分くらいで、雨弱まるってさ」
僕が驚いている間に、先輩はアイスティーをいれてくれたようだ。慌てて礼を言うと、先輩はかすかに口角を上げ、スマートな仕草で業務へと戻っていく。
アイスティーをストローでかき混ぜると、カランとかわいい音が漏れた。カフェはいつ来ても穏やかで、とても居心地がいい。僕はおいしいアイスティーを飲みながら、ずっと先輩の姿を目で追っていた。
「いらっしゃいませ、何名様ですか?」
落ち着いた態度と洗練された動き。先輩が働く姿は、やっぱり文句なしにかっこよかった。
今日は、先輩の新しい一面をたくさん見られた気がする。
もっともっとフミヤ先輩のことを知りたい。そんな衝動が僕の中で大きくなっているのを、自分でもどうしようもないくらいに感じていた。