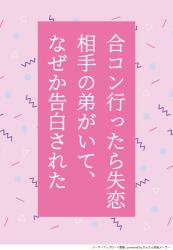買ったばかりの色つきリップを唇に載せ、指の腹で丁寧になじませた。唇にぱっときれいな血色感が出て、前よりも健康的な顔つきになる。艶やかなアッシュホワイトの髪、大きな瞳、整った輪郭、ぷるんとした唇、長いまつげ。
鏡の前の自分ににっこりと微笑む。うん、今日も僕はばっちりかわいい。
「さっちゃん、まだー? お腹でも壊したのー? えー、下痢ー? 大丈夫ー? うちがお腹さすってあげようかー? さっちゃん? 幸朗? 竹内幸朗く――ん?」
前髪をセットしているというのに、デリカシーのない親友の声が、延々と扉の向こうから聞こえてくる。
「モモ、フルネームで呼ぶな!」
メイク道具を大事にポーチの中に入れ、校内の男子トイレから廊下に出た。その途端、パックの野菜ジュースを飲んでいた藤代モモが「えっ、新しいの買ったの? リップかわいい!」と笑顔で話しかけてくる。
「でしょ? どこも売り切れてたやつ。この前田舎のスーパーで、奇跡的に一個見つけた」
モモは、僕と同じクラスの女子生徒だ。スタイル抜群の容姿と、モモの性格を丸ごと表しているような陽気な笑顔。彼女の明るい紅茶色の髪は胸元まで伸び、その毛先には愛らしいピンクの裾カラーが施されている。
飲み終えた紙パックをぎゅうぎゅうとごみ箱に押し込んだあと、モモは唇を尖らせて僕の腕にすり寄ってきた。
「いいなー。うちもつけたいー。ねぇねぇさっちゃんーうちもつけてみたいー」
「しょうがないなぁ」
ポーチからリップを取り出した瞬間、モモは秒速で僕からリップを奪う。モモがリップを塗るのに夢中になっている間、僕はまた「しょうがないなぁ」と、年季が入っている折りたたみ式のミラーを彼女の前に差し出した。
モモのぶ厚い唇に、桜みたいな淡いピンクが色づいていく。
まるで魔法のようなこの瞬間が、僕は大好きだ。
「いいじゃん、モモ」
「ごめん、さっちゃん。うちのほうが似合っちゃった」
「はいはい」
「唇が輝きすぎて、マジ流れ星超えて天の川!」
「はいはい、言ってろ」
気心の知れた間柄の僕たちには、遠慮というものがない。けらけらと笑ったモモと並んで、下駄箱から厚底のスニーカーを取り出す。
モモとの出会いは、僕たちが中学一年生の時まで遡る。とある理由で中学受験をした僕は、知り合いがゼロの状態からのスタートだった。初めてクラスが一緒になったモモとは、話してすぐに意気投合した。僕とモモには、おしゃれもメイクも大好きだという共通点があった。
お昼休み、放課後。休日も朝から晩まで、僕たちはたくさんの話をした。どこのファンデが自然で持ちが良くて崩れないだとか、どこのマスカラを使えば教室の天井まで届くようなまつげが作り出せるのかとか、唇はひとつだけどリップはいくらあってもいいとか。そんな高尚な話ばかりしていたっていうのに、世間一般の大多数の人間から言われる言葉は、悲しいかなひとつだけだ。
――お前ら付き合っちゃえよ。
賑やかな教室で、一斉にクラスメイトたちの好奇心旺盛な視線にさらされた僕ら。
その場では曖昧にお茶を濁した僕だったけれど、一晩中考えて答えを決めた。そして、それはモモも同じだった。
次の日の放課後、僕とモモは駅ビルの化粧品売り場で、自分に一番似合うリップの色を探しながら、今までずっと意識的に避けていた話題を持ち出した。
「あのさ、モモ……ごめん。僕、男の子が好きなんだ。だから、モモのこと恋人にしてあげられない」
モモは試供品を試しすぎて、真っ赤になった左手の甲を口元に持っていくと、今にも泣きそうな顔で言った。
「え――、うちもそう言おうと思ってたぁ! だってうち女の子が好きなんだもん~~! さっちゃんは大好きだけど、男の子は無理~~!」
僕たちは互いの顔をじっと見やった。しばらくして試供品をそっと丁寧に元の場所に戻し、声を押し殺して泣きながら抱き合ったのだ。あの日以来、僕たちは固い友情で結ばれている。
モモは女の子が好き。僕は男の子が好き。なんて最高な組み合わせなんだろう。
「ねぇねぇ、さっちゃん」
昔のことをぼんやりと考えていた僕に、モモがにこっと眩しい笑顔を見せた。
「あさ子さんにもこのリップ見てもらいたい。自撮り送ろうかな? さっちゃんも一緒に写ってよ」
「いいけど……。あさ子さんは、モモだけ写ってたほうが嬉しいんじゃない?」
モモは苦いお茶でも飲まされたような顔で「だってハズいじゃん」とかなんとかブツブツ言っている。
あさ子さんは他校の高校二年生で、一年以上付き合っているモモの恋人だ。男の僕から見ても、とてもボーイッシュでかっこいい。何度も三人で遊んだことがあるけれど、彼女たちの互いに思いやるイチャイチャぶりを見ていると、僕も早く大切な人が欲しいと切実に感じる。
高校一年生になったばかりの僕が掲げる今の目標は、メイクの勉強をたくさんすること、それからたったひとりの好きな人を見つけることだ。二つ目の目標は僕の過去を思えば、ある意味とてもハードルが高いのだけれど。
好きな人に好きになってもらう。そんな奇跡が僕の身に起こったら、今まで以上にとびっきりのおしゃれをして、その彼と花火大会に行ってみたい。
「さっちゃん、キメ顔して」
モモはスマホの加工アプリを慣れた手つきで立ち上げると、僕の顔に頬をつけてキメ顔を要求する。カメラを向けられたら勝手にかわいい顔をしてしまう性質の僕は、口角を少しだけ上げてきれいなウインクを披露した。
「おっけ、ラインで送った!」
モモがメッセージを送ってすぐに既読が付いたらしく、「あさ子さんが『お揃いのリップ似合ってる』って」と嬉しそうに口角を上げる。
「よかったねー、モモ。……あっ、てか、今日チートデーじゃん!」
ダイエットでストレスを溜めないため、一週間に一度、僕たちは摂取カロリーを気にしなくていいチートデーを設けている。ただ痩せるだけではナンセンスだ。健康的で、自分自身がかわいいと思える、自分に合った体形を楽しく維持する。それが僕の譲れない信念で、モモはその考えに賛同してくれている。大事なのは他人ではなく、自分自身が自分をかわいいと思えること。そんな風に考えている僕だけど、最初から強い理想を掲げていたわけじゃない。過去に、あるきっかけがあって、変わりたいと思ったのだ。
「お待ちかねのチートデーということで……。ねぇ、さっちゃん、今日はいつもと違うカフェに行かない? うち、この前穴場見つけちゃったんだよねぇ。さっちゃんに、かなりおすすめなとこ」
得意顔でそう言うモモに、僕は「穴場……?」と首を捻った。
いつもは品揃えがレベチな駅ビルの化粧品売り場に行き、新作のコスメをチェックした流れで、上の階のファミレスに入り浸るのが僕たちのルーティンだった。
「この前、モモが見つけてきた『穴場のカラオケ店』、かなりひどかったじゃん」
壊れそうなくらい建物が古かったことに加え、大学生くらいの店員とおじさん店員が、僕が受付している間、やけにモモの胸と太ももをジロジロ見るのが不快だった。モモはさっぱり気づいていなかったけれど、僕はあまりにひどい店員の態度に、彼女の手を引っ張って一目散に店から逃げ出した。あんな店は二度とごめんだ。
「今日はほんとに大丈夫だって! ガチです、幸朗くん」
「その名前で呼ぶなってばー」
むっとして眉間に皺を寄せてから、いけないいけないと顔面をフラットにする。皺にならないよう、アンガーマネジメントを駆使して自分の怒りを収めた。
モモの言う『穴場のカフェ』がまたひどい場所だったら、すぐに彼女の手を引いて問答無用で帰るつもりだ。
穴場のカフェは、学校から地下鉄で三駅先のところにあった。路地裏に入ると、ふっと目に飛び込んでくる小さな看板。『Cafe Miracle』と、オシャレな筆記体で書かれている。
僕はカフェを見上げ、すでに高得点をあげそうになってしまった。
一階は白で、二階はパステルピンクの建物。白い縁取りの大きなアーチ型の窓があり、まるで童話の挿絵みたいな雰囲気を醸し出している。アンティーク風な木製のドアには、ハート型のガラス窓がはめ込まれていた。中央には『OPEN』の文字が書かれたプレート。
「外観めっちゃかわいいじゃん……。このへん、遊びに来たこともあったのに全然気づかなかった」
「ね、でしょ? うちとさっちゃんってコスメとかの話になると、真剣だから周り見てないんだよね」
ウケる、とモモが白い歯を見せて笑い、僕は「それな」と深くうなずいた。
「どう? このカフェ気に入ったでしょ? さっちゃんはわかりやすいんだから」
「まだだよ! まだなんも食べてないし、店員さんも見てないし、わかんない!」
正直なところ、すでに想像の域は超えていたけれど、僕はふんと猫のように顔を背けた。
「まあまあ、そう言わず」
きっと気に入るよ、と耳元でささやかれ、妙な違和感を覚える。
「なんでそんな自信満々に……」
「それでは、さっちゃん、どうぞお開けください」
モモに促されてドアを開けると、甘い香りとコーヒーの香ばしい匂いが漂ってくる。
店内は、かわいい外観と遜色がない素敵な空間だった。天井から吊るされた小さなシャンデリアが柔らかな光を放ち、ところどころに飾られたアンティークな額縁には、かわいらしい猫や花の絵が収められている。カウンターの横には、ガラスケースに入ったカラフルなマカロンやふわふわのシフォンケーキが並び、目移りしてしまいそうだ。
「いらっしゃいませ。何名様ですか」
心地のよい低音が聞こえ、はっとして声の持ち主を見やった。心臓の鼓動がわかりやすく速くなる。
僕の目の前に立っていたのは、白いシャツと黒いエプロンを身にまとい、目を優しく細めたカフェ店員だった。
僕は言葉を失いながら、じっと彼を見つめた。
長身でスラリとした体型。ウェーブした黒い長髪は後ろでハーフアップに縛られ、整った顔立ちがひときわ目立っている。彼の涼しげな目元から漂うどこかミステリアスな雰囲気。全身から匂い立つ彼の色気に、胸がきゅうっと音を立ててときめく。
カフェ店員は視線を寄越したまま固まっている僕を見て、「ん?」と不思議そうに首を傾げた。
制服に付けられたネームプレートには、カタカナで『フミヤ』と書かれている。普段は社交的な僕なのに、口ごもってしまい何も言葉にできそうにない。
モモはそんな僕を見かねたのか、
「ふたりでーす」
とピースサインをしながら、にこにこと店員に答えた。
「では、こちらへどうぞ」
柔らかな物腰で、その店員は僕たちを広いテーブル席に案内してくれた。それからモモが「何がおすすめですかぁ」とか「じゃあこれにしますぅ」とか勝手に話を進めている最中も、そわそわと落ち着かなかった。
一六六センチの僕が見上げるくらいの身長差を考えると、彼はだいたい一八〇センチくらいだろうか。ピアスの穴は左にふたつ、右にひとつ。けれど、今は何もつけられていない。
彼がカウンターの向こうで器用にコーヒー豆を挽く姿や、ラテアートを描くために繊細な手つきでミルクを注ぐ様子が、気になって気になってしょうがなかった。時折カウンターのほうをチラチラ見つめては、彼と目が合うたびに慌てて視線を逸らしている。
ばかみたいだ、今の僕。
「ねぇ、モモどうしよう……」
僕がぽつりと言うと、まだ何に困っているのか言ってもいないのに、モモはしたり顔でにやりと笑った。いつもなら腹が立つけど、今はそれどころじゃない。
「ガチでかっこいい……ねぇ、モモあの人すごいかっこいい……」
「だと思った~!」
「僕の顔大丈夫? ファンデ崩れてない? リップ取れてない? 昼食べたお好み焼きの青のり歯にくっついてない?」
「大丈夫。大丈夫。宇宙一イケてる」
宇宙一の称号を手に入れても、心臓の鼓動は全然大丈夫じゃなかった。注文した品をトレーに載せて、彼がこちらに向かってくるのが見える。さらに激しく心臓が鼓動を打ち始め、僕はひどく動揺していた。
店員は僕の横に立つと、パフェを手にしてぽつりとつぶやいた。
「こちらは、えーと、なんでしたっけ……」
「……え?」
彼の言葉の意味がわからず、僕とモモはきょとんと目を丸くする。
「やべ、ど忘れした……。苺を英語で言うと」
僕は絞り出すように「……ス、ストロベリー?」と答えた。もちろん正解なんだけれども、その時の僕は思考能力が落ちていたので、祈るような気持ちで彼の次の言葉を待った。
「それだ」
いたずらが成功した少年みたいな顔をして、イケメン店員は小さく口角を上げた。
「スペシャルストロベリーパフェをお持ちしました」
静かに目の前に差し出されるスペシャルストロベリーパフェ。僕はなんだかおかしくて、「ふはっ」と声を出して笑ってしまった。
「ダサいっすね、俺。でも、君に笑ってもらえたから、いいか」
イケメン店員は「ごゆっくりどうぞ」と微笑むと、何事もなかったかのようにカウンターに戻ってしまった。
目の前にあるグラスの中に広がる小さな苺色の世界。透明なグラスの底には、ほんのりピンクがかったスポンジケーキとコーンフレークが敷き詰められていた。僕は黙って、宝石のように輝く苺のスライスとふんわりとしたホイップクリームをひとくち頬張る。甘さと酸味が絶妙なバランスを保ち、口の中いっぱいに苺の香りが広がった。
異様においしいスペシャルストロベリーパフェを食べながら、僕の顔はまるで苺みたいに真っ赤になっている。
「ねぇ、モモ……僕さ……」
「うん」
モモがにっこりと笑って答える。
「あの人がすごく気になるんだけど、がんばってもいいかな」
「あったりまえじゃん! 行ってきなよ!」
「もし、だめだったら――」
「うちが失恋ソング何曲でも一緒に歌ってあげる。もちろんあのクソカラオケ店以外で」
気合いを入れてパフェを食べ終え、僕はずんずんとイケメン店員の元に向かった。お客さんは僕ら以外いなかったし、なるべく迷惑にならないように今しかチャンスはないと思ったのだ。
「あのっ! 恋人はいますか?」
いきなりの僕の質問に、当たり前だけどカフェ店員はとても驚いたようだった。ドン引きされていたらどうしようという気持ちと、そんなの気にしないという強気な気持ちが、心の中でないまぜになって揺れている。
「恋人は、いないです」
こんなイケメンが誰のものでもないなんて奇跡だ。ガッツポーズをしたいところだけど、まだ早い。僕はできるだけかわいく見えるような上目づかいで、彼のことを見つめた。
「ぼ、僕って……あなたの恋愛対象に入りますか?」
店員はしばらく考えていて、まるで生きた心地がしなかった。実際にはたった五秒くらいの時間だったけれど、冗談ではなく、僕には永遠かと思えるくらいの長さに感じられていたのだ。
彼はこめかみをぽりぽりとかき、
「入り、ますね。恋愛対象」
と真面目な顔で言う。
「嘘だ……」
八割、いや九割玉砕する覚悟だった僕は、彼の言葉が信じられなくて、若干涙目でカフェ店員を見上げた。
「ほんと、嘘じゃないって」
イケメンカフェ店員は今日一番の屈託ない笑みを見せ、僕の頭に、本当に本当に……まるでガラス細工を扱うみたいに優しくぽんぽんと触れてくる。その手首から、ふわりと爽やかで甘いムスクの匂いが漂ってきた。
「ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく」
カフェ店員の口元から覗く白い歯と、差し出された細く骨張った小指に、僕はまたキュンと胸をときめかせてしまった。こんなの出来すぎだと思いつつも、ゆっくりと彼の小指に自分の小指を絡める。
小さく指切りげんまんをした僕たちは、互いにじっと見つめ合った。
奥で僕たちを見守っていたモモが、「ひゃあ~~!」と初孫が立つのを見たおばあちゃんのような勢いで、盛大にわめき散らしているのが聞こえる。
「あの、……な、名前と年齢を教えてください!」
口元を押さえてドタバタしているモモから目を逸らし、僕は緊張で震える手を隠すように服の端を掴んだ。心臓が早鐘を打つのを感じながら、目の前の彼に向かって声を絞り出す。
彼は僕をじっと見つめ、それから柔らかな微笑みを浮かべた。
「俺は、フミヤって言います。さだふみや、貞子の貞に、それから……」
言葉を途中で切り、彼が少し考え込むような表情を見せた。
「待って、見てもらったほうが早いわ」
ポケットからスマホを取り出し、スムーズな動きでメモアプリを開く。彼は画面に漢字を入力しながら、僕に説明してくれた。
「年齢は今年十八で、高校三年生です」
落ち着いた話し方に聞き入ってしまった。僕よりふたつ年上のフミヤ先輩。たった二年の違いなのに、彼の存在がまるで雲の上の人に感じられる。
「君の名前も聞いていい?」
僕ははっとして目を見開いた。なんてことだ。緊張しすぎて名乗ることすら失念していたらしい。改めてがっついてしまった自分に気づき、頬が熱くなるのを感じる。
「……じ、自己紹介もせずにすみません。僕は竹内幸朗です。……高校一年生です」
言葉を詰まらせながらも、なんとか続けた。
「ほ、本名はあまり好きじゃないので、『さっちゃん』って呼んでください」
先輩は涼しげな目を細め、不思議そうに言う。
「『さちろう』って名前も素敵だと思うけど、嫌いなの?」
熱心に見つめられて、視線が泳いでしまった。どうやらフミヤ先輩は、人の目をしっかりと見て、話をするタイプらしい。
「嫌いってわけじゃなくて、自己プロデュース的に合わないっていうか、さっちゃんの自分でいるのが好きなんです……」
「そっか、かわいいね」
「……え?」
「これからよろしくお願いします、さっちゃん」
どうか、こんなにもうるさい僕の心音に気づかないでいて。そう祈りながら僕は彼の顔を見上げ、小さくうなずいた。その瞬間、フミヤ先輩の瞳に映る自分の姿を意識して、また頬が熱くなるのを感じる。
それから新しいお客さんの入店を告げるドアベルの音が響き、彼は柔和な笑顔を残して仕事に戻っていった。僕は大人しくテーブルに戻り、彼の背中を目で追いながら、モモに小さく話しかける。
「モモ、どうしよう。ゆっくりお互いを知っていくことになったんだけど……これ、夢? 現実だよね?」
僕の声は自分でもわかるほど震えていて、まったく自分の感情を抑えきれていなかった。
モモは頬を上気させながら、「しっかりして、さっちゃん! 現実だから!」と鼻息荒く言う。彼女の表情には、親友としての喜びと興奮が混ざっているみたいだ。
「実はね……」
モモが追加で頼んだポテトをつまみながら、にやりと口角を上げた。
「……な、何?」
「あさ子さんとここに来た時、あの人が接客してたんだよね。うちとしては、『さっちゃんに似合う男探したろ委員会会長』だから、なんかピンときたの。さっちゃんに合うんじゃないかって。あさ子さんもそう思ったみたいだったから、さらに確信したんだよね~」
さすが大親友のモモと、その恋人のあさ子さんだ。僕は思わず苦笑いを浮かべた。初対面で勢い余って彼をナンパしてしまったくらいだから、彼女たちの勘が当たっていたのは間違いない。
「ねぇ、さっちゃん。きっと叶うよ。好きな人と花火大会に行くって夢」
僕は素直にうなずいた。フミヤ先輩がその「好きな人」になるかはまだわからない。でも、彼と先ほど指切りしたように、『ゆっくりと』知り合う時間はある。
ポテトも食べ終え、僕たちは席を立った。レジに向かう途中、僕はフミヤ先輩に小さく会釈をして、ささやくように言った。
「……あの、また来ます」
「待って、さっちゃん」
彼の声とともに、僕の手首がふわりと掴まれた。心臓が激しく鳴り、頬が熱くなるのを感じる。フミヤ先輩は僕の手に小さな紙切れを握らせ、大人びた笑顔を浮かべた。
「これ、俺のIDです」
「……あ、ありがとうございます!」
上擦った声で礼を言う僕を優しく見つめ、彼は最後にこう言った。
「さっちゃん、またね」
急いで書いてくれたのか、紙切れに浮かぶ少し雑な手書きの文字。カフェを出たあとも、僕の手には彼の温もりが残っているようだった。
――ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく。
フミヤ先輩の言葉を頭の中で反芻する。僕はどうかその言葉が、この世の中に溢れ返る社交辞令ではないことを心から祈るのだ。
鏡の前の自分ににっこりと微笑む。うん、今日も僕はばっちりかわいい。
「さっちゃん、まだー? お腹でも壊したのー? えー、下痢ー? 大丈夫ー? うちがお腹さすってあげようかー? さっちゃん? 幸朗? 竹内幸朗く――ん?」
前髪をセットしているというのに、デリカシーのない親友の声が、延々と扉の向こうから聞こえてくる。
「モモ、フルネームで呼ぶな!」
メイク道具を大事にポーチの中に入れ、校内の男子トイレから廊下に出た。その途端、パックの野菜ジュースを飲んでいた藤代モモが「えっ、新しいの買ったの? リップかわいい!」と笑顔で話しかけてくる。
「でしょ? どこも売り切れてたやつ。この前田舎のスーパーで、奇跡的に一個見つけた」
モモは、僕と同じクラスの女子生徒だ。スタイル抜群の容姿と、モモの性格を丸ごと表しているような陽気な笑顔。彼女の明るい紅茶色の髪は胸元まで伸び、その毛先には愛らしいピンクの裾カラーが施されている。
飲み終えた紙パックをぎゅうぎゅうとごみ箱に押し込んだあと、モモは唇を尖らせて僕の腕にすり寄ってきた。
「いいなー。うちもつけたいー。ねぇねぇさっちゃんーうちもつけてみたいー」
「しょうがないなぁ」
ポーチからリップを取り出した瞬間、モモは秒速で僕からリップを奪う。モモがリップを塗るのに夢中になっている間、僕はまた「しょうがないなぁ」と、年季が入っている折りたたみ式のミラーを彼女の前に差し出した。
モモのぶ厚い唇に、桜みたいな淡いピンクが色づいていく。
まるで魔法のようなこの瞬間が、僕は大好きだ。
「いいじゃん、モモ」
「ごめん、さっちゃん。うちのほうが似合っちゃった」
「はいはい」
「唇が輝きすぎて、マジ流れ星超えて天の川!」
「はいはい、言ってろ」
気心の知れた間柄の僕たちには、遠慮というものがない。けらけらと笑ったモモと並んで、下駄箱から厚底のスニーカーを取り出す。
モモとの出会いは、僕たちが中学一年生の時まで遡る。とある理由で中学受験をした僕は、知り合いがゼロの状態からのスタートだった。初めてクラスが一緒になったモモとは、話してすぐに意気投合した。僕とモモには、おしゃれもメイクも大好きだという共通点があった。
お昼休み、放課後。休日も朝から晩まで、僕たちはたくさんの話をした。どこのファンデが自然で持ちが良くて崩れないだとか、どこのマスカラを使えば教室の天井まで届くようなまつげが作り出せるのかとか、唇はひとつだけどリップはいくらあってもいいとか。そんな高尚な話ばかりしていたっていうのに、世間一般の大多数の人間から言われる言葉は、悲しいかなひとつだけだ。
――お前ら付き合っちゃえよ。
賑やかな教室で、一斉にクラスメイトたちの好奇心旺盛な視線にさらされた僕ら。
その場では曖昧にお茶を濁した僕だったけれど、一晩中考えて答えを決めた。そして、それはモモも同じだった。
次の日の放課後、僕とモモは駅ビルの化粧品売り場で、自分に一番似合うリップの色を探しながら、今までずっと意識的に避けていた話題を持ち出した。
「あのさ、モモ……ごめん。僕、男の子が好きなんだ。だから、モモのこと恋人にしてあげられない」
モモは試供品を試しすぎて、真っ赤になった左手の甲を口元に持っていくと、今にも泣きそうな顔で言った。
「え――、うちもそう言おうと思ってたぁ! だってうち女の子が好きなんだもん~~! さっちゃんは大好きだけど、男の子は無理~~!」
僕たちは互いの顔をじっと見やった。しばらくして試供品をそっと丁寧に元の場所に戻し、声を押し殺して泣きながら抱き合ったのだ。あの日以来、僕たちは固い友情で結ばれている。
モモは女の子が好き。僕は男の子が好き。なんて最高な組み合わせなんだろう。
「ねぇねぇ、さっちゃん」
昔のことをぼんやりと考えていた僕に、モモがにこっと眩しい笑顔を見せた。
「あさ子さんにもこのリップ見てもらいたい。自撮り送ろうかな? さっちゃんも一緒に写ってよ」
「いいけど……。あさ子さんは、モモだけ写ってたほうが嬉しいんじゃない?」
モモは苦いお茶でも飲まされたような顔で「だってハズいじゃん」とかなんとかブツブツ言っている。
あさ子さんは他校の高校二年生で、一年以上付き合っているモモの恋人だ。男の僕から見ても、とてもボーイッシュでかっこいい。何度も三人で遊んだことがあるけれど、彼女たちの互いに思いやるイチャイチャぶりを見ていると、僕も早く大切な人が欲しいと切実に感じる。
高校一年生になったばかりの僕が掲げる今の目標は、メイクの勉強をたくさんすること、それからたったひとりの好きな人を見つけることだ。二つ目の目標は僕の過去を思えば、ある意味とてもハードルが高いのだけれど。
好きな人に好きになってもらう。そんな奇跡が僕の身に起こったら、今まで以上にとびっきりのおしゃれをして、その彼と花火大会に行ってみたい。
「さっちゃん、キメ顔して」
モモはスマホの加工アプリを慣れた手つきで立ち上げると、僕の顔に頬をつけてキメ顔を要求する。カメラを向けられたら勝手にかわいい顔をしてしまう性質の僕は、口角を少しだけ上げてきれいなウインクを披露した。
「おっけ、ラインで送った!」
モモがメッセージを送ってすぐに既読が付いたらしく、「あさ子さんが『お揃いのリップ似合ってる』って」と嬉しそうに口角を上げる。
「よかったねー、モモ。……あっ、てか、今日チートデーじゃん!」
ダイエットでストレスを溜めないため、一週間に一度、僕たちは摂取カロリーを気にしなくていいチートデーを設けている。ただ痩せるだけではナンセンスだ。健康的で、自分自身がかわいいと思える、自分に合った体形を楽しく維持する。それが僕の譲れない信念で、モモはその考えに賛同してくれている。大事なのは他人ではなく、自分自身が自分をかわいいと思えること。そんな風に考えている僕だけど、最初から強い理想を掲げていたわけじゃない。過去に、あるきっかけがあって、変わりたいと思ったのだ。
「お待ちかねのチートデーということで……。ねぇ、さっちゃん、今日はいつもと違うカフェに行かない? うち、この前穴場見つけちゃったんだよねぇ。さっちゃんに、かなりおすすめなとこ」
得意顔でそう言うモモに、僕は「穴場……?」と首を捻った。
いつもは品揃えがレベチな駅ビルの化粧品売り場に行き、新作のコスメをチェックした流れで、上の階のファミレスに入り浸るのが僕たちのルーティンだった。
「この前、モモが見つけてきた『穴場のカラオケ店』、かなりひどかったじゃん」
壊れそうなくらい建物が古かったことに加え、大学生くらいの店員とおじさん店員が、僕が受付している間、やけにモモの胸と太ももをジロジロ見るのが不快だった。モモはさっぱり気づいていなかったけれど、僕はあまりにひどい店員の態度に、彼女の手を引っ張って一目散に店から逃げ出した。あんな店は二度とごめんだ。
「今日はほんとに大丈夫だって! ガチです、幸朗くん」
「その名前で呼ぶなってばー」
むっとして眉間に皺を寄せてから、いけないいけないと顔面をフラットにする。皺にならないよう、アンガーマネジメントを駆使して自分の怒りを収めた。
モモの言う『穴場のカフェ』がまたひどい場所だったら、すぐに彼女の手を引いて問答無用で帰るつもりだ。
穴場のカフェは、学校から地下鉄で三駅先のところにあった。路地裏に入ると、ふっと目に飛び込んでくる小さな看板。『Cafe Miracle』と、オシャレな筆記体で書かれている。
僕はカフェを見上げ、すでに高得点をあげそうになってしまった。
一階は白で、二階はパステルピンクの建物。白い縁取りの大きなアーチ型の窓があり、まるで童話の挿絵みたいな雰囲気を醸し出している。アンティーク風な木製のドアには、ハート型のガラス窓がはめ込まれていた。中央には『OPEN』の文字が書かれたプレート。
「外観めっちゃかわいいじゃん……。このへん、遊びに来たこともあったのに全然気づかなかった」
「ね、でしょ? うちとさっちゃんってコスメとかの話になると、真剣だから周り見てないんだよね」
ウケる、とモモが白い歯を見せて笑い、僕は「それな」と深くうなずいた。
「どう? このカフェ気に入ったでしょ? さっちゃんはわかりやすいんだから」
「まだだよ! まだなんも食べてないし、店員さんも見てないし、わかんない!」
正直なところ、すでに想像の域は超えていたけれど、僕はふんと猫のように顔を背けた。
「まあまあ、そう言わず」
きっと気に入るよ、と耳元でささやかれ、妙な違和感を覚える。
「なんでそんな自信満々に……」
「それでは、さっちゃん、どうぞお開けください」
モモに促されてドアを開けると、甘い香りとコーヒーの香ばしい匂いが漂ってくる。
店内は、かわいい外観と遜色がない素敵な空間だった。天井から吊るされた小さなシャンデリアが柔らかな光を放ち、ところどころに飾られたアンティークな額縁には、かわいらしい猫や花の絵が収められている。カウンターの横には、ガラスケースに入ったカラフルなマカロンやふわふわのシフォンケーキが並び、目移りしてしまいそうだ。
「いらっしゃいませ。何名様ですか」
心地のよい低音が聞こえ、はっとして声の持ち主を見やった。心臓の鼓動がわかりやすく速くなる。
僕の目の前に立っていたのは、白いシャツと黒いエプロンを身にまとい、目を優しく細めたカフェ店員だった。
僕は言葉を失いながら、じっと彼を見つめた。
長身でスラリとした体型。ウェーブした黒い長髪は後ろでハーフアップに縛られ、整った顔立ちがひときわ目立っている。彼の涼しげな目元から漂うどこかミステリアスな雰囲気。全身から匂い立つ彼の色気に、胸がきゅうっと音を立ててときめく。
カフェ店員は視線を寄越したまま固まっている僕を見て、「ん?」と不思議そうに首を傾げた。
制服に付けられたネームプレートには、カタカナで『フミヤ』と書かれている。普段は社交的な僕なのに、口ごもってしまい何も言葉にできそうにない。
モモはそんな僕を見かねたのか、
「ふたりでーす」
とピースサインをしながら、にこにこと店員に答えた。
「では、こちらへどうぞ」
柔らかな物腰で、その店員は僕たちを広いテーブル席に案内してくれた。それからモモが「何がおすすめですかぁ」とか「じゃあこれにしますぅ」とか勝手に話を進めている最中も、そわそわと落ち着かなかった。
一六六センチの僕が見上げるくらいの身長差を考えると、彼はだいたい一八〇センチくらいだろうか。ピアスの穴は左にふたつ、右にひとつ。けれど、今は何もつけられていない。
彼がカウンターの向こうで器用にコーヒー豆を挽く姿や、ラテアートを描くために繊細な手つきでミルクを注ぐ様子が、気になって気になってしょうがなかった。時折カウンターのほうをチラチラ見つめては、彼と目が合うたびに慌てて視線を逸らしている。
ばかみたいだ、今の僕。
「ねぇ、モモどうしよう……」
僕がぽつりと言うと、まだ何に困っているのか言ってもいないのに、モモはしたり顔でにやりと笑った。いつもなら腹が立つけど、今はそれどころじゃない。
「ガチでかっこいい……ねぇ、モモあの人すごいかっこいい……」
「だと思った~!」
「僕の顔大丈夫? ファンデ崩れてない? リップ取れてない? 昼食べたお好み焼きの青のり歯にくっついてない?」
「大丈夫。大丈夫。宇宙一イケてる」
宇宙一の称号を手に入れても、心臓の鼓動は全然大丈夫じゃなかった。注文した品をトレーに載せて、彼がこちらに向かってくるのが見える。さらに激しく心臓が鼓動を打ち始め、僕はひどく動揺していた。
店員は僕の横に立つと、パフェを手にしてぽつりとつぶやいた。
「こちらは、えーと、なんでしたっけ……」
「……え?」
彼の言葉の意味がわからず、僕とモモはきょとんと目を丸くする。
「やべ、ど忘れした……。苺を英語で言うと」
僕は絞り出すように「……ス、ストロベリー?」と答えた。もちろん正解なんだけれども、その時の僕は思考能力が落ちていたので、祈るような気持ちで彼の次の言葉を待った。
「それだ」
いたずらが成功した少年みたいな顔をして、イケメン店員は小さく口角を上げた。
「スペシャルストロベリーパフェをお持ちしました」
静かに目の前に差し出されるスペシャルストロベリーパフェ。僕はなんだかおかしくて、「ふはっ」と声を出して笑ってしまった。
「ダサいっすね、俺。でも、君に笑ってもらえたから、いいか」
イケメン店員は「ごゆっくりどうぞ」と微笑むと、何事もなかったかのようにカウンターに戻ってしまった。
目の前にあるグラスの中に広がる小さな苺色の世界。透明なグラスの底には、ほんのりピンクがかったスポンジケーキとコーンフレークが敷き詰められていた。僕は黙って、宝石のように輝く苺のスライスとふんわりとしたホイップクリームをひとくち頬張る。甘さと酸味が絶妙なバランスを保ち、口の中いっぱいに苺の香りが広がった。
異様においしいスペシャルストロベリーパフェを食べながら、僕の顔はまるで苺みたいに真っ赤になっている。
「ねぇ、モモ……僕さ……」
「うん」
モモがにっこりと笑って答える。
「あの人がすごく気になるんだけど、がんばってもいいかな」
「あったりまえじゃん! 行ってきなよ!」
「もし、だめだったら――」
「うちが失恋ソング何曲でも一緒に歌ってあげる。もちろんあのクソカラオケ店以外で」
気合いを入れてパフェを食べ終え、僕はずんずんとイケメン店員の元に向かった。お客さんは僕ら以外いなかったし、なるべく迷惑にならないように今しかチャンスはないと思ったのだ。
「あのっ! 恋人はいますか?」
いきなりの僕の質問に、当たり前だけどカフェ店員はとても驚いたようだった。ドン引きされていたらどうしようという気持ちと、そんなの気にしないという強気な気持ちが、心の中でないまぜになって揺れている。
「恋人は、いないです」
こんなイケメンが誰のものでもないなんて奇跡だ。ガッツポーズをしたいところだけど、まだ早い。僕はできるだけかわいく見えるような上目づかいで、彼のことを見つめた。
「ぼ、僕って……あなたの恋愛対象に入りますか?」
店員はしばらく考えていて、まるで生きた心地がしなかった。実際にはたった五秒くらいの時間だったけれど、冗談ではなく、僕には永遠かと思えるくらいの長さに感じられていたのだ。
彼はこめかみをぽりぽりとかき、
「入り、ますね。恋愛対象」
と真面目な顔で言う。
「嘘だ……」
八割、いや九割玉砕する覚悟だった僕は、彼の言葉が信じられなくて、若干涙目でカフェ店員を見上げた。
「ほんと、嘘じゃないって」
イケメンカフェ店員は今日一番の屈託ない笑みを見せ、僕の頭に、本当に本当に……まるでガラス細工を扱うみたいに優しくぽんぽんと触れてくる。その手首から、ふわりと爽やかで甘いムスクの匂いが漂ってきた。
「ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく」
カフェ店員の口元から覗く白い歯と、差し出された細く骨張った小指に、僕はまたキュンと胸をときめかせてしまった。こんなの出来すぎだと思いつつも、ゆっくりと彼の小指に自分の小指を絡める。
小さく指切りげんまんをした僕たちは、互いにじっと見つめ合った。
奥で僕たちを見守っていたモモが、「ひゃあ~~!」と初孫が立つのを見たおばあちゃんのような勢いで、盛大にわめき散らしているのが聞こえる。
「あの、……な、名前と年齢を教えてください!」
口元を押さえてドタバタしているモモから目を逸らし、僕は緊張で震える手を隠すように服の端を掴んだ。心臓が早鐘を打つのを感じながら、目の前の彼に向かって声を絞り出す。
彼は僕をじっと見つめ、それから柔らかな微笑みを浮かべた。
「俺は、フミヤって言います。さだふみや、貞子の貞に、それから……」
言葉を途中で切り、彼が少し考え込むような表情を見せた。
「待って、見てもらったほうが早いわ」
ポケットからスマホを取り出し、スムーズな動きでメモアプリを開く。彼は画面に漢字を入力しながら、僕に説明してくれた。
「年齢は今年十八で、高校三年生です」
落ち着いた話し方に聞き入ってしまった。僕よりふたつ年上のフミヤ先輩。たった二年の違いなのに、彼の存在がまるで雲の上の人に感じられる。
「君の名前も聞いていい?」
僕ははっとして目を見開いた。なんてことだ。緊張しすぎて名乗ることすら失念していたらしい。改めてがっついてしまった自分に気づき、頬が熱くなるのを感じる。
「……じ、自己紹介もせずにすみません。僕は竹内幸朗です。……高校一年生です」
言葉を詰まらせながらも、なんとか続けた。
「ほ、本名はあまり好きじゃないので、『さっちゃん』って呼んでください」
先輩は涼しげな目を細め、不思議そうに言う。
「『さちろう』って名前も素敵だと思うけど、嫌いなの?」
熱心に見つめられて、視線が泳いでしまった。どうやらフミヤ先輩は、人の目をしっかりと見て、話をするタイプらしい。
「嫌いってわけじゃなくて、自己プロデュース的に合わないっていうか、さっちゃんの自分でいるのが好きなんです……」
「そっか、かわいいね」
「……え?」
「これからよろしくお願いします、さっちゃん」
どうか、こんなにもうるさい僕の心音に気づかないでいて。そう祈りながら僕は彼の顔を見上げ、小さくうなずいた。その瞬間、フミヤ先輩の瞳に映る自分の姿を意識して、また頬が熱くなるのを感じる。
それから新しいお客さんの入店を告げるドアベルの音が響き、彼は柔和な笑顔を残して仕事に戻っていった。僕は大人しくテーブルに戻り、彼の背中を目で追いながら、モモに小さく話しかける。
「モモ、どうしよう。ゆっくりお互いを知っていくことになったんだけど……これ、夢? 現実だよね?」
僕の声は自分でもわかるほど震えていて、まったく自分の感情を抑えきれていなかった。
モモは頬を上気させながら、「しっかりして、さっちゃん! 現実だから!」と鼻息荒く言う。彼女の表情には、親友としての喜びと興奮が混ざっているみたいだ。
「実はね……」
モモが追加で頼んだポテトをつまみながら、にやりと口角を上げた。
「……な、何?」
「あさ子さんとここに来た時、あの人が接客してたんだよね。うちとしては、『さっちゃんに似合う男探したろ委員会会長』だから、なんかピンときたの。さっちゃんに合うんじゃないかって。あさ子さんもそう思ったみたいだったから、さらに確信したんだよね~」
さすが大親友のモモと、その恋人のあさ子さんだ。僕は思わず苦笑いを浮かべた。初対面で勢い余って彼をナンパしてしまったくらいだから、彼女たちの勘が当たっていたのは間違いない。
「ねぇ、さっちゃん。きっと叶うよ。好きな人と花火大会に行くって夢」
僕は素直にうなずいた。フミヤ先輩がその「好きな人」になるかはまだわからない。でも、彼と先ほど指切りしたように、『ゆっくりと』知り合う時間はある。
ポテトも食べ終え、僕たちは席を立った。レジに向かう途中、僕はフミヤ先輩に小さく会釈をして、ささやくように言った。
「……あの、また来ます」
「待って、さっちゃん」
彼の声とともに、僕の手首がふわりと掴まれた。心臓が激しく鳴り、頬が熱くなるのを感じる。フミヤ先輩は僕の手に小さな紙切れを握らせ、大人びた笑顔を浮かべた。
「これ、俺のIDです」
「……あ、ありがとうございます!」
上擦った声で礼を言う僕を優しく見つめ、彼は最後にこう言った。
「さっちゃん、またね」
急いで書いてくれたのか、紙切れに浮かぶ少し雑な手書きの文字。カフェを出たあとも、僕の手には彼の温もりが残っているようだった。
――ゆっくりお互いを知っていきましょう。……ね、やくそく。
フミヤ先輩の言葉を頭の中で反芻する。僕はどうかその言葉が、この世の中に溢れ返る社交辞令ではないことを心から祈るのだ。