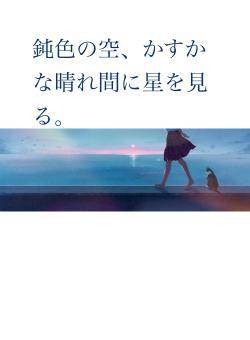テーマパークに着き、解散の合図が出ると、私たちはさっそくアーチ状の入口をくぐった。
カラフルな遊具に楽しげな音楽。まさに夢の国だけど、私の心はいまいち乗り切れない。
「じゃあとりあえず決めたとおりに回ってこ。まずブルースカイエリアだから、こっちか」
安堂くんを先頭に、夢があちこちに散らばった王国を歩く。
平日であるにもかかわらず、一般客の姿が多い。さすが、国内一のテーマパークを誇るだけのことはある。加えて、人混みのなかに私と同じ制服を着た生徒の姿。学校外でじぶんと同じ制服を見かけると、なんだか不思議な気分になる。
あちこちで知り合いを見かけそうだ。
そういえば、桃果からの返信はきただろうか。スマホを取り出して確認するが、新着のメッセージは来ていなかった。
桃果はスマホ中毒だ。これまではすぐに返信がきたのに、いったいどうしたのだろう……?
「亜子ー?」
足を止めてスマホを見ていると、みやびが私を呼んだ。
「あ……ごめん、今行く!」
スマホをスカートのポケットにしまい、私は小走りでみやびたちのところへ急ぐ。
「……あれ? 安堂くんたちは?」
「先、アトラクションのところに行ってくれた。列が空いてるようなら少しでも早く並びたいからって、走っていったよ」
「そうなんだ」
それなら、このままはぐれちゃえばいいのに、と少し思う。
グループ決めのときは六人ひとグループと決められていたが、実際パーク内に入ってしまえば先生の監視はなく、個人の判断に一任される。
バスのなかでは、ほかのグループと合体して回る約束をしていた子たちもいた。とはいえ私は、そんなことをしたら印象が悪くなるから、そんな提案はしないけれど。
と、考えていると、スマホが鳴った。安堂くんからだった。
送られてきたメッセージを見て、眉を寄せる。
私たちが乗ろうとしているアトラクションは、現在約二百分待ちだという。
『チケットを取ればすぐ乗れるけど、どうする? チケットはひとり二千円だけど』
「だって。どうする?」
安堂くんからのメッセージを読み上げて、私はふたりに確認する。
「チケットはムリ。あたし、お金ない」
月宮さんがばっさり言う。出た。どうせこうなるだろうとは思ったけれど。
「じゃあ並ぼっか」
月宮さんの言葉を受けて、みやびが言った。まぁいいけど。
「分かった。じゃあ私、安堂くんにメッセージ送っとくね」
「ありがとー」
私は安堂くんにメッセージを送って、スマホをしまう。
二百分かぁ……。長い。ぜったい飽きる。しかも今日、結構晴れてるから暑いし。待ち時間を聞いた途端に倦怠感を感じる身体。
なにかないかな、と思って視線をめぐらせていると、ふとポップコーンの看板が見えた。あれだ!
私はすぐさまみやびを見た。
「ねぇねぇ、待ち時間かなり長いみたいだしさ、私たちはポップコーン買ってから安堂くんたちに合流しない?」
暑いなか並ぶよりは、ポップコーン店で少しでもいいから涼みたい。ポップコーンの店は、アトラクションほどではないにしろ、それなりに行列ができている。時間つぶしにもなるし、どうせ並ぶならこっちのほうがいい。
「いいね! 私キャラメル食べたい〜」
みやびが乗ってくれた。
「えーみやびはキャラメル派? 私ぜったいハチミツなんだけど」
「あー分かる。ハチミツ味ってここでしか食べられないしね!」
「月宮さんは?」
私は笑顔で訊ねる。べつにキョーミなんてないけど、私は、どんなにきらいでもあからさまな態度は取らない。私のために。
しかし、彼女は、
「は? なんであんたに言わなきゃいけないわけ?」
はい、感じ悪い。笑顔がひきつる。
「……はぁ」
さすがに今のは、交わせなかった。ため息が漏れる。
「……あっ、亜子、ほら、順番来たよ」
みやびが少し焦った口調で私に声をかける。
「あ、うん。じゃあ私、先買っていい?」
「もちろん!」
みやびは大袈裟なくらいにうんうんと頷いた。
先にポップコーンを買い終えて店の端っこで待っていると、レジ横でポップコーンを買い終えたふたりが歩いてくる。スマホをポケットにしまい、その様子を何気なく眺める。
「私ね、ずっと気になってたんだけど、茉莉奈ちゃんって、いつも使ってるカバンにキャラクターのキーホルダー付けてるよね? もしかして、アニメ好きなの?」
なんだ、アニメの話か。くだらない。私は彼女たちから目を逸らした。そういう系は、私はぜんぜんキョーミない。
「これは友だちからもらったんだ。あたしはそこまで詳しくないんだけど……もしかして、みやびちゃんアニメとか好きなの?」
月宮さんは、カバンにつけたキーホルダーを手に持って顔の前にかざしていた。どうやら、ふたりの会話は弾んでいるらしい。
安堂くんたちと合流して、順番待ちの列に並んでいるあいだ、みやびは嬉しそうに月宮さんに話しかけている。
まるで、私のことなんて見えていないみたい。
楽しそうなふたりの横で、私のいらいらは最高潮に達していた。
やっぱり、月宮さんと同じグループになんてなるんじゃなかった。
私だけ置いてけぼりで、つまらない。
なんとなく裏切られた気分になって、居心地が悪くなる。
私は空になったポップコーンの箱の線を指でなぞっていた。ポップコーンは、六人で食べたらあっという間になくなってしまった。
並び始めて小一時間が過ぎた頃だった。
「なんかお腹減った~」
月宮さんが言い出した。
私は無視した。
そもそも、あんたのせいでこんな行列に並ぶ羽目になってるんだっつーの。心のなかで毒づく。
私だってお腹減ってるし、というかそもそもチケット買いたくないって言ったのは月宮さんなんだから、そういうことは思ってても口に出さないでほしい。余計お腹が減るじゃない。
「だねー……私もチュロス食べたくなってきた」
みやびまで言い出す。安堂くんが身動ぎをした。たぶん、「じゃあ俺が買ってくるよ」と言う気だ。その前に、私が言う。
「じゃあ、私が買ってくるよ。みんなは並んでて」
並ぶのにうんざりしていたからちょうどいい。そう思って私は列から抜ける。
「あ、それならあたしも行く。あたしが言い出したんだし」
は? と思って振り返ると、月宮さんが私を見ている。今のセリフを彼女が言ったのだと脳が理解するまで、かなり時間がかかった。
「いいよ。ひとりで行く」
思わず強い口調で返すが、月宮さんは私を無視して列から外れる。
「みやびちゃん、チョコでいい? シナモン?」
「あ、えっとじゃあチョコ……」
続けて、困惑気味に私も行こうか? と言うみやびに、私は頷こうとした。しかし、それよりわずかに早く、月宮さんが「大丈夫。ふたりいればじゅうぶんだから」と返した。勝手に。
舌打ちをしそうになり、慌てて呑み込む。
いちいち気に入らない。
私は睨むように月宮さんを見た。月宮さんも、負けじと私を見つめ返してくる。
あぁ、もう、なに。この、ひとを小バカにしたような瞳。
どうせ、心のなかで思ってるんだろうな。
私のこと、ダサいとか、ブスだとか。
彼女から視線を外し、俯く。すると、スカートの下から伸びたじぶんの足が見える。みやびのように長くなく、月宮さんのように細く小さくもない足。
痩せたつもりだったけど、ふたりと並ぶとじぶんの容姿の劣り具合が顕著になる。
指先も、爪の形すら、ふたりに勝てるところなんてない。
私がふたりと同じ髪型なんて、ただの罰ゲームじゃん。
私は、お揃いにしていたお団子をほどきながら、歩き出した。
***
私は今、なぜか月宮さんとふたりでカラフルなパークを歩いていた。
あーもう。なにこれ、信じらんない状況なんだけど。
このひと、なんでついてきたわけ? マジで意味分かんない。あのまま楽しくみやびと列に並んでいればよかったのに。
大股で歩いていると、ふと背後の気配が消えた。振り返ると、月宮さんはかなりうしろのほうにいた。てか、歩くの遅っ。
月宮さんは小走りで私の元へやってくると、キッと私を睨んだ。
「ごめん。歩くの早かった? ごめんね?」
少し息を切らした月宮さんに、内心笑いながら声をかける。ちょっと声に出たかもしれない。
月宮さんは、膝に手をついて呼吸を整えている。
「ずっと思ってたんだけど」
しばらくして切れていた息が整うと、月宮さんは私を上目遣いで見た。
「……淡島さんってさぁ、あたしのこときらいだよね」
どきりとした。
「えー……なに? いきなり」
私は笑顔を引っ込める。
「いきなり?」
私の反応に、月宮さんがふっと笑う。
「なに言ってんの。あからさまじゃん? 態度が。あたしにだけ」
「……そんなことないよ」
ウソ。そうだよ。あんたみたいな女、だいっきらいだから。
そう言いたくなる喉をきゅっと引き締めて、私は努めて笑顔で聞き返す。こんなことで動揺なんてしない。私は完璧ないい子を演じてみせる。
「……ごめん、私、月宮さんの気に障ること、なにかしたかな?」
「その下手くそな作り笑い、いい加減やめたら?」
「……は?」
笑顔のまま、固まる。
「気持ち悪いよ、能面みたいで」
月宮さんの「気持ち悪い」というひとことは、私の胸を深くえぐった。
みんなに悪口を囁かれてきたあの頃の記憶が蘇る。
言葉につまる私を、月宮さんは白々とした眼差しで見つめる。
その目に嘲笑されているような気がして、なにも返せない。
なにこいつ。
そんなこと、わざわざ言われなくたって分かってる。私はブスだ。化粧で誤魔化してる。
だからなに? そんなのみんないっしょでしょ。世のなか、化粧とったらだいたいの女がブスじゃん。
つーか、あんただってべつにたいした顔してないくせに。どの面下げて言ってんの?
「私は……っ!」
声を荒らげそうになったそのとき、
「ふたりともっ!」
みやびの声がした。振り向くと、みやびが走ってこちらへ向かってくる。
「みやび?」
私も月宮さんも、一旦言い合いを止めて、やってきたみやびを凝視する。
みやびは息を乱している。急いで私たちを追いかけてきたみたいだ。
「やっぱり、私もいっしょに行っていいかな?」
「…………」
私も月宮さんも、うんもなにも言わない。
みやびが来ても、私たちのあいだには微妙な空気が流れたまま。
「え……ど、どうしたの、ふたりとも?」
異変を察知したみやびが、私と月宮さんを交互に見る。
「べつになんでもないよ」
私は気を遣って、笑ってそう言ってやったのに。月宮さんは無遠慮に言った。
「今だから言うけど、あたし、ずーっと思ってた」
私は月宮さんを睨みつける。月宮さんからは、挑戦的な視線が返ってきた。まだ続けるつもりだ。
「あんた、みやびちゃんに対しての態度も違和感だらけだったし?」
月宮さんは言いながら、ちらりとみやびを見た。みやびは月宮さんと目が合うと、びくりと肩を震わせる。
私はため息をつく。可哀想。みやびは今の状況について、なにがなんだか分からないだろうに。
呆れてなにも言わないでいると、月宮さんは今度、みやびを見た。
「てゆーかさぁ、みやびちゃんだって気付いてるよね? このひと、みやびちゃんのステータスが気に入ってるだけで、心のなかでは友だちだなんてぜんぜん思ってないよ?」
月宮さんの言葉に、みやびは困ったように俯く。こいつ、余計なことを言いやがった。
「みやび、気にしなくていいよ」
そう言うけれど、みやびもみやびでなにも言わない。頷きすら、しない。月宮さんは続ける。
「その証拠に、裏ではさんざん悪口言ってるしね」
「はぁ? なんのこと……」
「あたしは人間地雷らしいし?」
人間地雷。
私は奥歯を噛み締める。
「なにそれ……」
知らんぷりをしようとして、その途中でハッとする。そのセリフ、どこかで聞いた。いや、見た。裏アカで私が呟いた言葉だ。
月宮さんは、笑っている。私は眉を寄せた。
「……あんた、なんで」
「あんたって爪が甘いよねぇ。学校で裏アカ開いたら、ぜったいだれかに見られるに決まってんのに」
『学校で』その言葉を聞いて、すべてを察する。
みやびが月宮さんを遠足のグループに誘ったとき、私はいらいらしてトイレで発散した。それを見ていたのだ。あのとき個室にいたのはこいつだったのだ。
「性格悪……」
「あ、それからごめんね? あんたの彼氏も取っちゃって」
こいつ。やっぱり隼くんと連絡取ってた。
「べつに? あんな男、もうどーだっていいし」
強がりなんかじゃない。本心だ。本当にどーでもいい。あんなクズ。
「だよね。あたしも、さすがにあの男とは付き合えないよ。だって隼くん、いいところぜんぜんないんだもん。毎日毎日メッセもしつこいし……あんた、よく半年もあんなのと付き合ってたね?」
半笑いで言われ、頭のなかの血管が二、三本切れた気がした。
「あんた、黙って聞いてれば、いい加減にしなさいよ! ひとの彼氏に色目使っておいて信じらんない!」
私は我慢できず、月宮さんに掴みかかった。思い切り髪の毛を引っ張ってやる。
「きゃっ! いったぁ……なにすんのよ!」
月宮さんの目の色も変わる。仕返しのように月宮さんも私の髪を引っ張ってくる。痛い。最悪。
「ちょっ……ふたりともやめて!」
みやびが割って入ってくる。私たちはみやびを挟み、野良猫のように睨み合った。
もう我慢できない。言ってやる。
私は爆弾を投下した。
「私、知ってるよ。あんたってさぁ――虐待児なんだよね?」
「っ……!」
これにはさすがに、月宮さんも驚いて動きを止めた。
「なんで……」
いつも淡々とした月宮さんが、動揺していた。月宮さんは信じられないものでも見るように、呆然と立っている。
「いっつもそのパーカー着てるから気になってたんだよね。体育のときも、ぜったい長袖だし。胸元の痣、見られたくないんでしょ?」
その瞬間、月宮さんの目の色が変わる。
「……なんであんたがそれを知ってんのよ!」
つばが飛んできた。最悪。でも、笑顔は崩さない。その動揺した顔、目に焼き付けてやる。
私は昨日、月宮茉莉奈の秘密を知ったのだ。
月宮茉莉奈は、虐待児だった。
子どもの頃、実の母親から虐待を受けていたらしい。そして、中学のときに捨てられた。母親が、男を作って出ていったらしい。
かわいそう? 同情? なにそれ、ないない。あり得ない。
「よかったじゃん、殴られなくなってさ」
私は笑う。
これらの情報は、ぜんぶ、もずくさんの投稿にあった。
もずくさんはガールズバーで健気に働くマリちゃんの熱心な信者らしかった。マリちゃんのほうも、こういう妄信的な男は金ヅルになるからか、よく身の上話をしていたようだ。
「残念だけどね、私、もっと知ってるよ。あんたがガールズバーで働いてることも、キモいオッサンと仲良くしてることも」
挑発するように言うと、月宮さんの唇がわなわなと震え出した。
「ちょっと待って、ガールズバーってどういうこと? 茉莉奈ちゃん?」
みやびが困惑して、月宮さんを見る。月宮さんは黙ったまま、なにも答えない。
月宮茉莉奈は、珍しく動揺していた。
先に挑発してきたのは、月宮さんのほうだ。私は悪くない。私はそうじぶんに言い聞かせる。
ざまぁ。
月宮さんは私を睨んでくる。私は負けじと笑みを返す。
「毎日毎日オッサンの相手だなんて、大変だねぇ?」
わざと挑発するように言うと、月宮さんはふんっと鼻で荒く息を吐き、私を蔑むように見つめた。
「……黙れよ。あんただって、昨年まで仲良かった友だちにブロックされてるクセにさ」
「は?」
ブロック?
「どういう意味?」
どこかバカにしたようなその態度に、私は眉を寄せる。すると、私の表情を見た月宮さんが嘲るように笑った。
「はっ! まさかあんた、知らないの? 昨年仲良かった子、ええと桃果ちゃん……だっけ? あの子にあんたの裏アカ教えたら、ガチギレしてたよ。ムカつくから、彼氏にバラしてやるとか息巻いてたっけ」
身体が、凍りついた。
……こいつ今、なんて言った?
桃果、と言った。裏アカのことをバラした、とも、間違いなく言った。
急いでスマホを確認する。チップスを開いて、桃果のアカウントに飛んだ。
『あなたはこちらのアカウントにブロックされています』
画面いっぱいに、見慣れない文字が並んでいた。
……信じらんない。月宮さんを睨むと、月宮さんは蔑むような眼差しを私に向けていた。
「残念だったね。彼があたしを好きにならなくても、あんたの腹黒がバレてどうせふられたんだよ?」
許せない。殺す。殺してやる。
怒りのあまり唇がわなわな震えて、言葉なんて出てきやしない。
とにかくその場で震えて立ち尽くす。しかし、月宮さんはそんな私にかまわず、涼しい顔をして続ける。
「あんたはさ、じぶんだけが我慢してると思ってたみたいだけど、ほんとは、そんなことぜんぜんない。まわりもずーっと我慢してたんだよ」
まるで心をぐりっと鋭利ななにかで抉られたようだった。
「……知らないし、そんなの」
「だろうね。あんた、じぶんのことしか考えてないもんね」
「…………」
うざ。そんなの、あんたもいっしょでしょ。心のなかでそう思う。でも、口には出せなかった。言ってやればいいのに、声が出ない。ムカつく。
「ねぇ、みやびちゃんも、彼女に言いたいことあるんじゃないの。この際、もう言っちゃったら?」
月宮さんは、今度はみやびを挑発する。
なに、いきなり。じぶんの都合が悪くなったからって。いい加減にしてほしい。
「……はぁーっ……」
息を吐いていらいらを誤魔化そうとしたけれど、ダメだった。
「あぁ、もうっ! なんなの、あんた? なにがしたいわけ? 私とみやびをそんなに仲違いさせたいわけ?」
月宮さんが私を見る。
「いい加減にしてって言ってんのよ!」
思わず怒鳴る。すると、月宮さんがにやっと口角を釣り上げた。その顔を見て、しまった、と思う。
「出た! それが本性? こーわっ」
月宮さんが茶化すように言う。私はそれを、ぴしゃりと跳ね除けた。
「うるさいっ! というか、みやびもさぁ……なんなの? そんなことないよ、とか、言ってくれないんだ? それってずいぶん薄情じゃない」
矛先をみやびに向けてどうにかやり過ごそうかと考えるが、みやびは黙ったまま、俯いてしまった。
その仕草を見て、あぁ、なんだ、そっか、と思う。
みやびも私の本心、分かってたんじゃん。
これまで必死に積み上げてきたものが、がらがらと音を立てて崩れていったようだった。
……あーぁ。なんかもう、どうでもよくなっちゃった。
「だったら言わせてもらうけどさぁ、月宮さんこそなに? なにさまなわけ?」
私は睨むように月宮さんを見返した。
「は? なにが?」
月宮さんも、負けじと私を睨み返してくる。
「……月宮さんの言うとおりだよ。私は一軍でいたいからみやびと一緒にいるの。だったらなに? 悪い? べつにいいじゃん。それで平和にやってるんだから、あんたにとやかく言われる筋合いないと思うんだけど?」
月宮さんは、小バカにしたように笑っている。たぶん、私が本音をさらしたことに満足なのだろう。
一方で、みやびはじっとじぶんの足元を見るばかりで、なにも言わない。月宮さんも黙り込んだまま。重い沈黙が、余計にいらいらする。
私は開き直ったように饒舌になった。ギャラリーが集まってきているけど、もうそんなことはどーだっていい。
一度開いてしまった口は、そう簡単には閉じそうになかった。
「だってさ、仕方ないじゃん。私はみやびみたいに可愛くないんだから。じぶんを偽らなきゃ、居場所なんて簡単になくなるの。みやびみたいに好き勝手わがまま言って、のほほんとしてたら、ハブられるの。っていうか月宮さんこそ本当に性格悪いよね。最初から私の気持ち分かってたなら、みやびに誘われたとき断ってくれたらよかったのに」
後半は、月宮さんを睨みつけながら言った。もう、遠慮していい子ぶるのがバカらしくなってきた。こうなったらどうにでもなれ、だ。
「はぁ? なんであたしがあんたに気を遣ってやらなきゃいけないわけ?」
月宮さんも負けじと私を睨んで言い返してくる。
「バカみたい。うそをついて、だれかと一緒にいたって虚しくなるだけじゃん。そんなことまでして一軍にいることに、なんの意味があんの? あんた、一軍にいないと死んじゃうわけ? なにそれウケる」
必死に守ってきたものを笑ってバカにされ、悔しさのあまり私は、歯が砕けそうなほど噛み締める。
「うるさいうるさいっ! あんたになにが分かるの! 私の、なにがっ……!」
私は、震える声で言い返す。
「あんたはいいよ。じぶんに自信があるんでしょ!? でも、私は違う。私は、ひとりにさえならなければなんだっていいっ! いじめられないなら、どんな無茶だってするし、うそだってつく」
私は間違ってない。ぜったい、間違ってなんかない。
「それって、もはや友だちじゃなくない?」
頭にカッと血が昇るのが分かった。
「そうだよ? そのとおりだよ。でも青春ってそういうものでしょ? なんなのあんた、いちいちつっかかってきて! どうせ、いじめられたこともないくせに……」
握った手がぷるぷると震える。その震えは、果たして怒りから来るものなのか、それとも悔しさから来るものなのか。もはやじぶんでも分からない。
「私はべつに、どれだけ性格悪いって思われたとしてもいい。いじめられなければなんだっていいの! 月宮さんはいいよ。ひとりでいても平気なんだろうし、なんなら男子が寄ってくるんだから! でも、私がひとりでいたってだれも助けてくれない。ずーっとひとりのまま。努力しなきゃ、だれも私を仲間になんていれてくれないの!」
小学生のとき、ひとより太っていた私は、それが理由でみんなに無視されていた。
あのときの日常は、たぶん一生忘れない。私をいじめてきた奴らの名前も顔も、忘れたくても、忘れられない。
今でも、思い出すだけで手汗が滲み出してくる。それくらい、トラウマなのだ。あのときのことは。
『おいデブ。こっち来んな、きもい』
『くせーんだよ』
私が声を発するだけで空気が張りつめる、あの感じ。笑い声が響く教室で、私の存在だけが透明になっていく、あの感じ。
ペアになる授業ではいつも必ず取り残され、ひとりで掃除させられ、目が合ったら逸らされる。私は空気。いないのが当たり前。そんな雰囲気が漂う教室に、三年間通い続けた。
脳内で流れ出す光景を遮断するように、私はぎゅっと目を瞑った。
違う。今は、違う。
私は痩せた。可愛くなった。ブスじゃない。可愛い。私はいじめられっ子なんかじゃない!
「ふたりと違って私は凡人だから、努力しなきゃいけないの。太らないように食べたいものも我慢して、お洒落にも気を遣って、思ってもいないことを言って笑って。そうやってようやく、私はクラスメイトとして認識されるの」
ふたりは黙って私の話を聞いていた。
困惑したようなみやびの眼差し。私は虚しさのあまり、思わず笑みを漏らした。
「……バカみたいでしょ? んなの、じぶんでも分かってるよ。だけど、それでもいじめられてたあの頃よりはずっと幸せ。私には、ふたりがそうやってバカにしてる日常が、なにより守りたいものなの!」
「亜子……」
みやびが私の名前を呼ぶ。
でも、顔を上げられない。だって私は、みやびにすごく失礼なことを言ってしまった。もう、終わりだ。明日からきっと、一緒に笑い合うことなんてできなくなる。周りには、騒ぎを聞きつけてきたたくさんのギャラリー。なかには、カメラを向けているひともいる。
見るなよ、うざい。勝手に撮るなよ、鬱陶しい。なんて、言ったって無駄か。
……あーぁ。これできっと、噂も広がる。
また、ひとりになるんだ、私は。あの頃のように……。
がっくりと肩が落ちた。もうなにもかもどうでも良くなった。深く息を吐き、私は低い声でふたりに告げる。
「……もういい。私、今日はもうひとりでいるから。あとはふたりで楽しみなよ」
このままいっしょに行動する選択肢は、もうない。私はひとりで歩き出す。
しかし、ひとごみに紛れる直前、月宮さんの声が聞こえた。
「バカみたい」
私はもう、なにも言い返す気にはならなかった。
***
私はパーク内にあるカフェに入った。海賊船をモチーフにしたカフェで、店内は薄暗い。周りにいる客の顔もよく見えないほどだ。
足元危ないし、カバンの中身も見づらいけど、今は助かる。たぶん、私は今ひどい顔をしているから。
スマホを見る。『チップス』を開くと、案の定、私と月宮さんが喧嘩している動画があちこちで出回っていた。
『やば。なにコレ』
『淡島亜子ってこんな性格だったの? 可愛いと思ってたのにショック』
『いや、あの顔はどう考えても作ってるでしょ笑』
『だいぶキレてるなー笑』
どんどんいいねがされて、拡散されている。
引用されて、私の悪口も書き込まれている。
私を悪く言って動画を拡散しているのは、ぜんぶ知ってるアカウントだった。
みんな、中学のときや一年のときに一軍の女子みんなでハブいた子やいじめてきた子たち。
『淡島亜子終わったな』
ほんと。
『隼クン、別れて正解じゃん?』
ほんとにそう。
『てか、淡島亜子ってそもそも友だちから隼くんを奪ったらしいよ』
そうだよ。私は、桃果から隼くんを奪った。
『淡島亜子はクズ』
知ってる。
『淡島亜子死ね』
私は乱暴に頭を搔く。
あぁ、もう。うるさいうるさいうるさい!
黙れブス!
あんたらになにが分かるんだよ!
そうだよ、私はこんな性格だよ。
だからなに。悪い?
私を責めるなら、あんたたちはどうなの?
だれかの悪口言ったことないわけ?
嘘ついて、他人にいい顔したことないわけ?
じぶんを守るために生きて、なにが悪いの。
好き勝手言いやがって……あんたたちだって中身はどうせこんなもんでしょ。ひとに理想抱く前に、じぶんのことを省みてみなさいよ!
……つーか、
「外野は黙ってろ!」
テーブルを叩いて叫んだ瞬間、カフェのなかが静まり返る。周囲の目が一斉に私に向く。
集まった視線に、泣きそうになる。
私は力なく椅子に座り直して、項垂れた。
「……サイアク」
だけど、いちばん最悪なのは、私だ。
為すすべもなく、私は拡散されていく動画を見つめた。
どうせこのあと、月宮さんが私の裏アカの存在を暴露して、私はもっと炎上するんだろう。いや、若しくはもう既に桃果が暴露しているかもしれない。
あーぁ。完全に摘んだ。
これまで積み上げてきたものが、ぜんぶなくなった。
積み上げてきた? なにを?
私はなにを積み上げてきた?
いじめられないように、可愛くなる努力をして、言動も陽キャを意識して、じぶんより下の子を見て笑って。
じぶんだって、少し前まで見下されてきたくせに。でも、そうしなきゃいじめっ子たちのなかに入れなかった。
三ノ輪茜、山口美香、金森真奈。
下品に笑う、あのなかに。
「…………」
私は、なんであのなかに入りたいと思ったんだろう……。
あんなにきらいだったはずなのに。
「……バカみたい」
涙で視界が滲んだ。