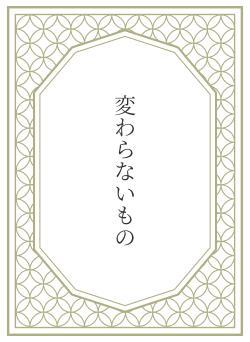自分らしくいることで、自分を地獄に落としてしまうことがある。なぜなら、僕たちには、普通であることを求めているからだ。普通なんてものはないはずなのに、周りに合わせて、それぞれの良さを殺してまで、普通でなければならない。普通になれない者は、地獄を見る環境。世間は多様性を認めようとか言っているけど、人間簡単にそうできる生き物ではない。自分らしくいたってよいはずなのに、自分らしくいることで、生き地獄と化す。とくに、学校はその傾向が強い。僕も、自分らしくいることで、生き地獄を味わった1人だ。
僕の名前は、関 智也(せき ともや)。高校1年生だ。
僕は苦しみにもまれていた。孤独にならないために、自分を捨てなければならなかったから。
僕には他の人とは違うところがある。それは、男の子が好きだということ。いわゆるゲイというものだ。だが、このことを周りは知らない。それは、とある出来事があったからだ。
中学生のころ、夕食を食べ終わり、リビングでテレビを見ていた時、両親のとある会話を耳にした。
「今は男が男に恋をするなんてこともあるんだとよ。」
「あら、やだわね気持ち悪い。智也は違うよね。」
「あいつにしかわからないだろうな。まあ、同性婚とかは認めないでほしいわな。」
俺の周りに味方なんていない。そう思った。男が男を好きになって何が悪い。だけど、そんな思いは、届かないんだろうな。
あれから、ずっと自分の気持ちを隠して生きてきた。だからこそ、息苦しいんだ。
俺には好きな人がいる。それが同じクラスの高身長で、センター分けの少年、名波暁人(ななみ あきと)。だが、その気持ちを伝えることなど、できるはずがなかった。
暁人は、中学時代からの仲だ。だが、あくまで恋人ではなく友達。告白なんてできるはずがなく、今に至る。
5月5日、俺は暁人の誘いで山奥の温泉に来ていた。
「智也。久しぶりの温泉、気持ちいいな!」
「そうだね。暁人。」
暁人とふたりきりの露天風呂は、とても気持ちいいものだ。
ふと、暁人がこう言った。
「智也。」
「なんだい?改まって。」
「実は……」
暁人が改まって話すことは今までなかった。何かあったのか?
「俺は、ゲイだ。」
え?まじで?俺は混乱する。
「そして、俺は智也のことが好きだ。」
え?え!こ、こ、告白!?これもういうしかないやんけ。
「暁人……俺もゲイや。暁人が好きや。」
俺がそう返事すると、暁人は戸惑いの表情を見せる。
「暁人、俺と付き合ってくれないか?」
ダメ押しでお願いをする。
「もちろんさ!智也。」
ありがとう。暁人。
「父さん、母さん。」
僕は言わなければいけないんだ。
「実は……」
言わなければいけないんだ。
「僕は男の子が好きだ。」
それを聞いた両親は、わかりやすくがっかりした様子だった。
「お前なんか、要らない。」
父さんは言う。は?要らないってどういうことだよ。
「お前を産んだのが間違いだったわ。」
母さん……2人とも、そういう人間なんだね。
わかってもらえなかった。それどころか、僕は家を追い出されてしまったのだ。
正直生きる希望はない。消えてしまいたい。そんなときに、たまたま暁人が家の前を通りかかったのだ。
「暁人」
「なんだい、智也」
「僕、死にたい……」
つらい。息苦しい。
死にたいのに死ねない。生きたくないのに、生きてる。そんな俺の言葉を聞いた暁人は、険しい表情を浮かべる。
「智也を必要としている人間がいる限り、智也は死んじゃだめだ。」
「そんなのいな……」
「ここにいるさ!」
僕の言葉を、暁人は遮った。
「だから、今は……生きててくれ……」
ありがとう。暁人。おかげで生きたくなった。
あれから両親は虐待の罪で逮捕され、僕は、ゲイに理解のある祖父母に引き取られた。暁人とは、未だに恋人同士の仲だ。暁人には感謝している。生きる希望を与えてくれたから
僕の名前は、関 智也(せき ともや)。高校1年生だ。
僕は苦しみにもまれていた。孤独にならないために、自分を捨てなければならなかったから。
僕には他の人とは違うところがある。それは、男の子が好きだということ。いわゆるゲイというものだ。だが、このことを周りは知らない。それは、とある出来事があったからだ。
中学生のころ、夕食を食べ終わり、リビングでテレビを見ていた時、両親のとある会話を耳にした。
「今は男が男に恋をするなんてこともあるんだとよ。」
「あら、やだわね気持ち悪い。智也は違うよね。」
「あいつにしかわからないだろうな。まあ、同性婚とかは認めないでほしいわな。」
俺の周りに味方なんていない。そう思った。男が男を好きになって何が悪い。だけど、そんな思いは、届かないんだろうな。
あれから、ずっと自分の気持ちを隠して生きてきた。だからこそ、息苦しいんだ。
俺には好きな人がいる。それが同じクラスの高身長で、センター分けの少年、名波暁人(ななみ あきと)。だが、その気持ちを伝えることなど、できるはずがなかった。
暁人は、中学時代からの仲だ。だが、あくまで恋人ではなく友達。告白なんてできるはずがなく、今に至る。
5月5日、俺は暁人の誘いで山奥の温泉に来ていた。
「智也。久しぶりの温泉、気持ちいいな!」
「そうだね。暁人。」
暁人とふたりきりの露天風呂は、とても気持ちいいものだ。
ふと、暁人がこう言った。
「智也。」
「なんだい?改まって。」
「実は……」
暁人が改まって話すことは今までなかった。何かあったのか?
「俺は、ゲイだ。」
え?まじで?俺は混乱する。
「そして、俺は智也のことが好きだ。」
え?え!こ、こ、告白!?これもういうしかないやんけ。
「暁人……俺もゲイや。暁人が好きや。」
俺がそう返事すると、暁人は戸惑いの表情を見せる。
「暁人、俺と付き合ってくれないか?」
ダメ押しでお願いをする。
「もちろんさ!智也。」
ありがとう。暁人。
「父さん、母さん。」
僕は言わなければいけないんだ。
「実は……」
言わなければいけないんだ。
「僕は男の子が好きだ。」
それを聞いた両親は、わかりやすくがっかりした様子だった。
「お前なんか、要らない。」
父さんは言う。は?要らないってどういうことだよ。
「お前を産んだのが間違いだったわ。」
母さん……2人とも、そういう人間なんだね。
わかってもらえなかった。それどころか、僕は家を追い出されてしまったのだ。
正直生きる希望はない。消えてしまいたい。そんなときに、たまたま暁人が家の前を通りかかったのだ。
「暁人」
「なんだい、智也」
「僕、死にたい……」
つらい。息苦しい。
死にたいのに死ねない。生きたくないのに、生きてる。そんな俺の言葉を聞いた暁人は、険しい表情を浮かべる。
「智也を必要としている人間がいる限り、智也は死んじゃだめだ。」
「そんなのいな……」
「ここにいるさ!」
僕の言葉を、暁人は遮った。
「だから、今は……生きててくれ……」
ありがとう。暁人。おかげで生きたくなった。
あれから両親は虐待の罪で逮捕され、僕は、ゲイに理解のある祖父母に引き取られた。暁人とは、未だに恋人同士の仲だ。暁人には感謝している。生きる希望を与えてくれたから