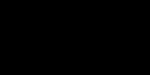オレ、兄ちゃ……兄貴からパソコンもらったんす。三か月くらい前に。新しいの買うからやるよって。オレも自分のほしかったしちょうどいいやってもらって。で、家だとスマホよりパソコンいじってる時間の方が長くなりました。それまでスマホでやってたネット関係を全部パソコンでやるようにしました。フィルターかけられてるけどやっぱ便利なんすよね。画像とか動画とかやっぱでかい画面で見たいし。
え? あーまぁそりゃサッカーのあとだし疲れてるし眠いっすよ。宿題もあるし。でもそれとこれとは別でしょ。お姉さんも仕事だけして生きてるんすか? ですよね。
んで……あー、そうだ。ツイッターもその中のひとつで。あーそういや知ってるんすよね? エスさんからオレに辿り着いたってことは。じゃあエスさん見てたのバレてんのか……恥じぃな。仕方ないけど……
あ、うん、それで、夜はパソコンでツイッターいじるようになって……どんくらい経ったんだっけな。数週間とか? あんま覚えてないっすけど、もう寝ようと思って閉じる時に画面真っ暗になるじゃないっすか。そん時に、なんか見られてる気がしたんす。理由なんてわかんねえっすよ。ただ何となく。けど、マジで何となくだったし勘違いだろって終わって。
んでー……そのあとも普通にパソコン立ち上げるじゃないっすか。で、まぁ色々やってて、つい夢中になって前のめりになってたりすると、こう、ぞわあってしたんすよ。耳が。
ちっちぇえ息が吹きかけられたみたいっつか、よくわかんねぇけど、とにかくぞわあってして。はあ? って振り返ったけど誰もいなくて、気のせいかっつってまた画面に戻ると、しばらく経ってから、また。さすがに気味悪いし意味わかんないしでパソコン閉じようとしたら、今度はハッキリ見えました。あれは目だった。人間の。
そこまで一気に話すと、大翔はジンジャエールをストローで思いきり吸い込んだ。
ずずず、と場に不似合いな音が響く。肩をすくめた大翔は小さく「すんません」と呟いた。
「……ハッキリ見たの?」
訊ねると、彼は頷く。
「見ました。オレ、動体視力はいいんすよ。あれは絶対目だった」
視線は合わない。
グラスを両手で握るようにした大翔は、空になり氷だけになったそこをただ見つめている。
「……何回見たか教えてもらってもいい?」
私の問いに、ようやく目線をあげる。
「数えたことないっす。……つか、目を見たのはそん時だけかも」
「え?」
「あの気味悪い息は何回も味わいました。耳に吹きかけられるみたいな、何か言ってるみたいな、よくわかんないやつ」
「家の外で感じたことは?」
「ありました。授業中がキツかったっす。
──ありました。
過去形だ。
「今はもうないの?」
大翔は俯き、両腕を組んで唸るように考えはじめた。
そして、はい、と顔を上げる。
「ないっす」
「家の中でも?」
「……たまにあるかもってくらいで、ひどかった時に比べたら全然っす」
「自分でその理由に心当たりはある?」
質問を重ねる私に嫌な顔ひとつせず、しかし、大翔はしばらく黙り込んだ。
考えているというよりも、話そうかどうか悩んでいるといったように見える。
ここで急かすような真似をしたら、おそらく絶対に話してくれなくなるだろう。かといって、このまま黙り込まれていては時間ばかりが過ぎてしまう。せっかく浜松まで来たというのに、それでは私が辛い。
考えた末、まだ聞いていなかった質問を先にすることにした。
「心当たりについてはまた後で教えてくれたら嬉しい。先に、聞くの忘れてたことがあったの。いいかな」
「……はい」
「大翔くんは、その不思議な──不気味なと言ってもいいな。その出来事をツイッターに呟いていたんだよね?」
そうでなければ、彼の言うエスさん──紗和が、大翔も同じ経験をしたと知ることが出来ない。
彼女は自分をリストに入れていた彼のアカウントを見に行き、タイムラインを見たと言っていた。
大翔はなぜか少し微妙な表情を浮かべて頷いた。
「……全部が全部、マジなことは呟かなかったけど」
「そうなの?」
「ツイッターっすよ? ガチすぎたら馬鹿にされるかもしれないじゃないっすか。オレ、鍵アカじゃねぇし。ちょっとおふざけ程度っつか、呟いたあとにやべぇって思ったら『さっきの盛ったわ~』つって誤魔化したりしたし」
そういうものなのだろうか。……そうかもしれない。
私の中学時代はここまでSNSが普及していなかった。やや上の世代にミクシィなどはあったが顔見知りとはコミュニティ内にこもり、もう少しクローズな関係性を築けた気がする。
「まぁ、匿名の掲示板には書き込んだりもしたけど」
「え?」
また新しい話が出てきた。
私が聞き取れなかったと思ったらしい大翔が繰り返してくれる。
「掲示板っすよ。ウチの学校の裏サイトから飛べる掲示板があす。あんまでかくないけど、オカルト版とか分かれてて。それこそパソコン使うようになってから知ったんすけど」
「……匿名のネット掲示板ってことね?」
大翔は頷くと、耳の裏をポリポリと掻きながら続けた。
え? あーまぁそりゃサッカーのあとだし疲れてるし眠いっすよ。宿題もあるし。でもそれとこれとは別でしょ。お姉さんも仕事だけして生きてるんすか? ですよね。
んで……あー、そうだ。ツイッターもその中のひとつで。あーそういや知ってるんすよね? エスさんからオレに辿り着いたってことは。じゃあエスさん見てたのバレてんのか……恥じぃな。仕方ないけど……
あ、うん、それで、夜はパソコンでツイッターいじるようになって……どんくらい経ったんだっけな。数週間とか? あんま覚えてないっすけど、もう寝ようと思って閉じる時に画面真っ暗になるじゃないっすか。そん時に、なんか見られてる気がしたんす。理由なんてわかんねえっすよ。ただ何となく。けど、マジで何となくだったし勘違いだろって終わって。
んでー……そのあとも普通にパソコン立ち上げるじゃないっすか。で、まぁ色々やってて、つい夢中になって前のめりになってたりすると、こう、ぞわあってしたんすよ。耳が。
ちっちぇえ息が吹きかけられたみたいっつか、よくわかんねぇけど、とにかくぞわあってして。はあ? って振り返ったけど誰もいなくて、気のせいかっつってまた画面に戻ると、しばらく経ってから、また。さすがに気味悪いし意味わかんないしでパソコン閉じようとしたら、今度はハッキリ見えました。あれは目だった。人間の。
そこまで一気に話すと、大翔はジンジャエールをストローで思いきり吸い込んだ。
ずずず、と場に不似合いな音が響く。肩をすくめた大翔は小さく「すんません」と呟いた。
「……ハッキリ見たの?」
訊ねると、彼は頷く。
「見ました。オレ、動体視力はいいんすよ。あれは絶対目だった」
視線は合わない。
グラスを両手で握るようにした大翔は、空になり氷だけになったそこをただ見つめている。
「……何回見たか教えてもらってもいい?」
私の問いに、ようやく目線をあげる。
「数えたことないっす。……つか、目を見たのはそん時だけかも」
「え?」
「あの気味悪い息は何回も味わいました。耳に吹きかけられるみたいな、何か言ってるみたいな、よくわかんないやつ」
「家の外で感じたことは?」
「ありました。授業中がキツかったっす。
──ありました。
過去形だ。
「今はもうないの?」
大翔は俯き、両腕を組んで唸るように考えはじめた。
そして、はい、と顔を上げる。
「ないっす」
「家の中でも?」
「……たまにあるかもってくらいで、ひどかった時に比べたら全然っす」
「自分でその理由に心当たりはある?」
質問を重ねる私に嫌な顔ひとつせず、しかし、大翔はしばらく黙り込んだ。
考えているというよりも、話そうかどうか悩んでいるといったように見える。
ここで急かすような真似をしたら、おそらく絶対に話してくれなくなるだろう。かといって、このまま黙り込まれていては時間ばかりが過ぎてしまう。せっかく浜松まで来たというのに、それでは私が辛い。
考えた末、まだ聞いていなかった質問を先にすることにした。
「心当たりについてはまた後で教えてくれたら嬉しい。先に、聞くの忘れてたことがあったの。いいかな」
「……はい」
「大翔くんは、その不思議な──不気味なと言ってもいいな。その出来事をツイッターに呟いていたんだよね?」
そうでなければ、彼の言うエスさん──紗和が、大翔も同じ経験をしたと知ることが出来ない。
彼女は自分をリストに入れていた彼のアカウントを見に行き、タイムラインを見たと言っていた。
大翔はなぜか少し微妙な表情を浮かべて頷いた。
「……全部が全部、マジなことは呟かなかったけど」
「そうなの?」
「ツイッターっすよ? ガチすぎたら馬鹿にされるかもしれないじゃないっすか。オレ、鍵アカじゃねぇし。ちょっとおふざけ程度っつか、呟いたあとにやべぇって思ったら『さっきの盛ったわ~』つって誤魔化したりしたし」
そういうものなのだろうか。……そうかもしれない。
私の中学時代はここまでSNSが普及していなかった。やや上の世代にミクシィなどはあったが顔見知りとはコミュニティ内にこもり、もう少しクローズな関係性を築けた気がする。
「まぁ、匿名の掲示板には書き込んだりもしたけど」
「え?」
また新しい話が出てきた。
私が聞き取れなかったと思ったらしい大翔が繰り返してくれる。
「掲示板っすよ。ウチの学校の裏サイトから飛べる掲示板があす。あんまでかくないけど、オカルト版とか分かれてて。それこそパソコン使うようになってから知ったんすけど」
「……匿名のネット掲示板ってことね?」
大翔は頷くと、耳の裏をポリポリと掻きながら続けた。