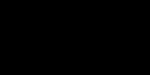**
ドアを開け、三か所あるロックをかける。
流れ作業となったそれらを済ませると、脱いだヒールを揃えずに室内へ入った。
「……ただいま」
ひとり暮らしを始めて数年、クセとなった言葉を紡ぐことすら今は怖い。本当は、怖い。
頭の片隅で、「おかえり」と返ってきてしまうのではという恐怖を拭うことが出来ない。
手を洗うために洗面台に対峙することさえ、怖い。廊下から入る明かりがあるから節約のためと洗面所の電気は点けないのが自分ルールだ。
ケチな性分を曲げることが出来ないままそれを貫いているせいで、光の届かない隅に何かが蠢いているように感じてしまう。
蛇口から水が出る。瞬間。
耳のすぐそばで、ハァと小さなため息が聞こえた。
振り返る。当然誰もいない。いるはずがない。
──『だれかいる』。
紗和の記した文字が頭を過ぎった。
濡れたままの手で空を掴む。いるわけがない。いるはずがない。
うるさいほど鳴っている心臓を落ち着かせようと、服越しで左胸を掴んだ。気のせいだと言い聞かせて洗面台から離れ、リビングへ向かった。
ソファの前にあるローテーブルの上には、ノートパソコンが置いてある。
異変のはじまりはこれだ。
『パソコンを閉じようとした時に気づいたんです」
つい数時間前に別れた紗和の話を思い出す。
映りこんだのは、一瞬母かと思いました。また来たのかと思って。
でも違うんですよ。そもそも母だったら黙って入ってくるはずもない。大きな声で「ただいま」「何してるの」って言いながら玄関を開けるんです。人の家だと思ってないからお邪魔しますじゃなくてただいまなんです。ありえないでしょう? この前も悪びれもせず勝手に……
話がずれましたね。ええ、そう、シャットダウンの時です。
真っ暗になるから自分の顔が映るのは当たり前。でも、私の顔のすぐ後ろに誰かが映ってたんです。最初は気のせいだと思い込んでたけど、勘違いじゃないんです。
初めてそれがいたのは、私の顔の後ろでした。本当にすぐ後ろです。自分の影がブレて見えただけかなとも思って最初は気にしてなかったんです。次にいたのは肩のそば。変わってました。さすがにあれ? と思ったけど、目が疲れてるせいだと思い込んで、気にしないようにしました。その次は、顔の横です。私の隣にいて、一緒にパソコンを覗き込んでいるようでした。それからも気のせいだって思い続けました。無理やりにでもです。でも、無視できないことが起きて……
息遣いです。ハァって、すぐそばで小さなため息が聞こえるようになりました。
さっき、私の感じたのがそれだ。
ラグを敷いた床に座り、ノートパソコンを開く。
こうしている間にも、部屋の隅が気になる。明かりの届かない、暗闇が。
意識をそこから逸らして電源を入れる。青白い光が私の顔を舐めるように照らし、いつもの画面が立ちあがった。ブックマークからいつもの場所へ潜り込む。
あれから逃れた紗和と、私の違いは何か。
わかっているけど、今はまだ、無理だ。
*
カーテンの隙間から入ってくる光に、朝が来たことを知る。
もう何日こんな風に夜を過ごしただろう。
背筋を伸ばして伸びをしてから、ゆっくりと立ちあがる。
一晩中座っていた足腰が悲鳴を上げることにも慣れた。カーテンを開けると痛いくらいの日差しが目を刺す。ベッドで眠っていた頃は気持ちよく感じていた鳥の囀りは、今や苛立ちの原因でしかない。
そのまま身体を引きずるようにして洗面所に向かう。顔を洗う時にあれを感じる。昨夜隅に蠢いていた(ように思った)気配は、朝という時間と窓を開けたことによる清々しい空気のせいか全てなくなっていた。
泡だらけになった顔を水で洗い流す。
その隙間を縫って、肩越しに、いる。
ハァと小さな──いや。昨夜よりも大きくなった気がする、ため息。
荒くはない。本当に小さな、耳をそばだてないと聞き逃してしまうほどの息。
はたと気づく。
そんなに小さなため息なのに、どうしてこんなにも気になるのか。どうしてこんなに耳に入ってくるのか。
物音を立てれば消えてしまうほどのものなのに、歯磨きをしていても、顔を洗っていても、すぐそばから聞こえてくる。
どうして。
──その時、部屋に着信音が響いた。
急いでリビングに向かい、ローテーブルに置いてあったスマホを見る。登録していない番号だった。
羅列された数字に覚えがない。間違い電話か迷惑電話か。登録外の番号からの電話は基本受け取りたくない私は、しばらく見つめたままでいた。
それでも切れる気配がない。諦めて電話に出た。
「……はい」
『朝早くに失礼します。芳野さんの携帯ですか』
「はい」
機械越しで印象が少し変わるが、昨日聞いたばかりの女性の声だった。
「……紗和さんですか?」
『ええ、そうです』
何を今さら、という声が聞こえたような気がして、私は理由を話す。
「ご自分の携帯ではないんですね。出るのが遅れてすみません、どなたかわからなかったので」
『え? ……あ、ごめんなさい。これプライベートじゃなくて会社用だった』
「いえ、大丈夫なんですけど……何かありましたか」
『あったっていうか、思い出したんですけど』
「なんでしょう」
小さく息を吸い込む気配がする。これはあれじゃなく、紗和のものだ。
『あれの気配を感じたことがあるって言ってた子がいたんです』
「えっ」
『すみません、昨日は自分の話をすることに夢中になっちゃって……芳野さんにお会いするまでは教えなきゃって思ってたんですけど』
紗和の背後から忙しない空気が伝わる。時計を見ると、九時を過ぎていた。
会社用の携帯だと言っていたし、すでに出社しているのかもしれない。
「思い出してくださっただけで充分です」
『今もまだ続いてるかは聞いてないんですけど、それでもいいですか?』
「ええ。充分です」
言葉を重ねて、協力を頼む。
ほかにも経験者がいた。
渦中から逃れた人の話も参考にはなるが、今の紗和のようにしょせん他人事になってしまうだろう。憐憫と同情の目を向けられることになる。
もしもその人が現在進行形ならば願ってもない。
ひとりを追うわけではないとわかれば、どうにかしようがあるかもしれない。
共通点がハッキリすれば、どこか現実的ではない今の状況を解決しようと本腰を入れることができるかもしれない。
「それで、どんな子ですか」
『まだ中学生の男の子です。アカウント名をお送りします』