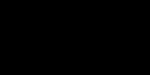架空のツイッターアカウントを作り、ウソばかりの幸せツイートをするようになった。
私が隆介としたいこと。行きたい場所。希望を詰め込んだアカウントだった。
重くて黒いものが浄化していくようだった。
現実はこんなに満たされないのに、この私は恋人に愛されて幸せな毎日を送っている。
そんなある日、タイムラインに回ってきたツイートがあった。
不平不満ばかり呟いているのにフォロワー数の多い不思議なアカウントだった。
鍵リストに入れて、時間がある時にのぞいていた。
ある日を境に恋人のセックスが面倒だという愚痴になり、気の毒な人もいるもんだなと面白半分で見ていた。それが、一度だけ『櫻木』という名の入ったツイートがあがった。直後に消されていたからミスだったんだろう。まさかと思った。
アカウント名はエス。
櫻木隆介の元恋人の名前は多々野紗和。紗和。S。
櫻木なんて名字は特別珍しくはない。
鈴木や佐藤に比べたら少ないかもしれないが、あの時の私は思い込んだ。これはもしかして、紗和の愚痴アカウントではないかと。
それからは気が気ではなかった。
時間の隙を見てはツイッターを監視して、呟きを見た。確信を持った。
デートに行った場所。付き合った期間。点と点を結んでいけば答えは出る。
確信を強めていくうちに、思い知ったことがあった。
彼女が悪戯にツイートしていた隆介の癖を私はどれも知らない。彼はきっと、愛する人にしかああいうことをしない。どんなに変態的であろうと、本当の恋人にしか求めない。見せない。私には絶対に見せてくれない。もう我慢できなかった。直接顔を見て話がしたくなった。何をしたかったのかはわからない。でも、我慢ができなかった。
Sとの接触は賭けだった。
万が一にでも紗和が私を知っていたら。
まさか破局の原因を作った相手だとは思わないだろうが、出版社にいた頃の写真を見たことがあったら。
それでも偶然を装える自信はあった。でも万が一。感情がぐちゃまぜになりながらSと接触を図り、それとなく悩みを打ち明けた。
最近変なため息が聞こえるんですよね。疲れているんでしょうか、なんて世間話の一環で。
人間は単純なもので、相手に「あなたにだけ」と打ち明けられると親密さが増す。
真面目で責任感が強く、情の深いタイプには覿面に効く。
自分は信用されているという意識と、信用してくれている相手を信頼しようという無意識がうまく作用すればこちらのものだ。隆介にも何度も使った手だった。結局、紗和と隆介は似てるのだろう。
そして何度かメッセージのやり取りをくり返すうちに、S──紗和も同じ経験があると打ち明けてくれた。
会うチャンスだ。賭けがどうなるかはもうどうでもよかった。
私なんかよりよっぽどいい女だと思っていた紗和が、私と同じあれに悩まされたことがある。それだけで自分の価値まで上がったような気がした。
だけど、初めて私と対峙した紗和が何の反応を示さなかったことで、隆介がいかに私の存在を彼女に知らせていなかったかを思い知った。
しかも、破局と原因となった女について、後輩で、「しいな」という名だと馬鹿正直に教えられていても、紗和は調べようともしなかった。
執拗に紗和の事を調べた私とは、雲泥の差だ。
たとえその後、発散のために架空のアカウントを作り上げたといっても、浮気相手の女性については何も書いていない。直接会っても理解した。彼女はただ自分を裏切った隆介を責めていただけ。
私──自分から隆介を奪った女のことなんて眼中になかった。
私は結局、どこまでいっても名ばかりの恋人だ。
「なら最初からずっと冷たくすればよかったじゃない。今だって、怪我したのかなんて心配しなくてよかったんだよ」
あふれてくる。黒い淀となっていた何かが、熱い喉の奥を這ってあふれてしまう。
電話の向こうにいるユキナに聞こえているかもしれない。すでに通話は切れているかもしれない。わからない。身体が揺れる。頭が痛い。泣きたいのに、涙は出ない。
あれにつきまとわれる原因は、漠然とインターネットではないかと思っていた。
それが紗和と大翔と会って話を聞いているうち、私と彼女たちは少し違うのではないかと思いはじめている。
匿名のアカウントや匿名の掲示板。ここまでは変わらない。
ただ。二人は悪意を吐き出していた。隆介のこと。母親のこと。悪意をコントロールできなくなった紗和は、あれが一番近づいた時はおそらく無我夢中で書き込んでいたはずだ。大翔も同じ。人様には言えない悪路的な感情を吐いていた。あの年頃は精神的にも幼い。他人への嫉妬と劣等感をうまくコントロールできないことも多いだろう。だから、悪意が蠢く場所に巣食って待ち構えていたあれに囚われたのではないかと思った。
だけど私は違う。幸せなことしか発していなかった。
なのに捕まった。それも、紗和より先に。
「おかしいと思わない?」
唇が引き攣れてうまく動かない。隆介は目を瞠り、後ずさる。
何が、と言いかけて口を噤むのがわかった。彼はいつもそうだ。肝心なことは何も言ってくれない。だからいつも私は一人で考えてから回って、喉の奥の熱いものに蓋をして、仕事に夢中になるフリをして、
──そうだ。いつだってフリばかり。