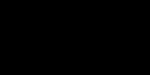「……何これ」
隆介の指についた血を見つめ、私は掠れた声で呟いた。
「だから怪我したんじゃなくて?」
同じ質問をくり返す隆介の手首を引き寄せて、その匂いを嗅いだ。
鉄くさい。間違いなく血だ。でも、私は怪我なんてしていない。
自分で右耳を触って、目の前に持ってくる。今度は何もない。隆介の指を見る。やっぱり血がついている。隆介も血だと認識している。どういうこと?
「私にはつかなかった」
うまく声が出ないままだけど、隆介には伝わったようだ。
私は彼に手を見せる。隆介の視線が私の手に移り、自分の指に戻った。
眉を顰めて「なんだこれ」と呟く。くん、と鼻先で私と同じように匂いを嗅ぎ、納得したように頷いてからぺろりと舐めた。
「……血だ。間違いなく」
気味が悪い。口にはしなかったが、隆介から伝わってきた。私も同じ気持ちだ。気味が悪い。
もう一度私も右耳を手で拭ってみる。やっぱり何もつかなかった。髪を右耳にかけて、改めて隆介へ向ける。
「ついてる?」
何が、とは言わなかった。ただ首を横に振る。
黙ったまま隆介はスマートフォンを撮りだした。そのままで、と動きだけで制され、言われるがまま動かないでいる。
シャッター音がしたあとに彼は画面を確認した。凝視したままさらに眉を顰める。
何、何があったの? 私は隆介の腕を引っ張った。彼はまた首を横に振る。
そんな態度を取られて気にならないわけがない。無理やりスマホを奪い、画面を見て──固まった。
変なものが写りこんでいるのではない。その方がまだマシだったかもしれない。何故なら理由が説明できる現象が起きていることだってあり得るからだ。でも、違った。
横を向いた私が写っている。
そのほぼ中心に写っている耳が、ひしゃげたように歪んでいる。
ブレたとかそんな表現では済まされない。だって、他の部分──目や髪は何も異常なく写っているのだ。
耳だけ。耳だけが、何かが上から押し付けているかのように歪んでひしゃげていた。
気味が悪い。なのに、見ていると妙に引き寄せられてしまう。歪んだ自分の耳に何かが被さっていそうな気がする。それを知りたい。気味が悪いのにずっと見ていたい。
うまく説明できない感情に支配され、食い入るようにそれを見つめた。
「おい」
大きな手が肩を掴む。隆介が訝しげに私を見る。
「そんなもん見ない方がいい」
どうして? だってきっとここには、何かが。何かってなんだろう。そうだ。あれだ。耳元に吐かれる息。あれがきっとここにいる。だから私の耳が歪んで見えるんだ。正体がわかればもうわけのわからない現象に悩まされることはない。そう思えばこれは解決の糸口かもしれない。妙な高揚感が私をかき立てた。
「おいってば」
スマホを握る私の手を隆介が剥がそうとしてきた。思いきり振りほどく。隆介が驚いて、もう一度私に寄り添う。
やめて。邪魔しないで。いつも会いたい時には来てくれないくせに、私の望みなんて何ひとつ叶えてくれないくせに、こんな時に邪魔をしないで。
さっきまであれだけ助けてほしいと願った手を振りほどくなんて、何をしてるの?
頭の片隅から声がする。歪んだ笑みを浮かべた私が、私を見下ろしている。
わかってる。今私がしなきゃいけないのは、怖かったと隆介に甘えることだ。今こそそのタイミングだとわかっているのに、身体が言うことを聞かない。
確かめたかった。おかしな現象に見舞われ始めた頃に紗和に辿り着いた時から。
紗和と会った時から。まさかと疑いを抱いたあれの正体を確かめたかった。
「おい。いい加減にしないと──」
隆介の手に力がこもる。痛い。だからなんで、こんな時ばっかり。
「いい加減にするのはそっちでしょ!」
喘ぐように叫んで、思いきり隆介を突き飛ばした。
床に転がる彼を横目に荒げた息を整えながら立ちあがると、ゆらゆらとチェストへ向かう。
「おまえ……」
呻く隆介の声がする。そうだよ。見たよ。見たくもない写真を見せられた。あなたはまだ彼女のことが忘れられないんだ。ユキナも言っていた。隆介は頭の回転が速い。私の気持ちに気づかないはずがない。不安で潰されそうな今の私を、わからないなんて言わせない。
チェストに辿り着く。初めて見た、私の知らない隆介が収まる写真立て。
隣で微笑んでいるのは──
写真立てを掴み、床に向かって投げつけようとしたところで隆介に止められた。
手首を掴まれ、暴れる私を抑えつけてくる。どれだけやめろとくり返されたってやめたくない。こんなものがある限り、私の心に平穏なんて訪れない。元々そんなものなかったけど。
はたと気づいて動きを止める。写真立ては手にしたまま、床にへたりこんだ。
隆介は私を警戒しながらも、手首を抑えつける力を少し緩めてくれたのがわかった。
そうだ。そんなものなかった。そもそもは私がいけなかった。
スマートフォンが鳴る。電話だ。ゆらりと鞄へ向いて、のろのろと腕を伸ばす。まるで異質なモノを見るかのような視線を感じた。わかっている。隆介だ。彼にとって私はまさに異質で、理解不能で、厄介な恋人なのだろう。
発信元を見ると、『ユキナ』の文字があった。
隆介が未だ訝し気に私を見つめている。彼の手を確認してみる。
さっきまでべっとりとついていた血はなくなっていた。二人そろって幻覚を見たのだろうか。匂いまで嗅いで?
隆介なんて、舐めていた。そんなことありえない。あれは現実だった。あれは……考えがまとまりそうでまとまらない。
着信音は鳴りやまない。私は通話をタップした。
『芳野さん? ごめんねこんな時間に。今大丈夫です?』
ユキナの言葉に隆介を見た。
大丈夫かと問われたら、大丈夫じゃない。隆介の部屋でもわけのわからない現象に襲われ、直後に彼が帰宅して、私の耳に血がついていて、彼もそれを見て、舐めて、写真が──ああ、なんだっけ。そう。あれ。あれは──
『芳野さん? マジで大丈夫なの?』
「……わかんない」
答える唇が歪に笑う。
大翔は逃げることが出来た。本人は本当に終わったのかわからないといった風だったけど、大翔はもう逃げ切っている。くり返されるブックマークはただの名残だ。あれはいつだって影から見ている。いつでもこちらへ戻っておいでというように。
紗和は過去として話せるほどには、被害はないようだった。ひっかかる場面はいくつかあるけど、私に憐憫の目を向けていた。憐憫の目。憐憫、の……
「……やっぱりそうなの?」
ゆっくりと、隆介を見る。
電話の向こうでユキナが何か言っている。だけどもう聞こえない。スマートフォンが私の手から落ちて、鈍い音がした。ケースが頑丈なのか、割れる音はしない。代わりにユキナの声がする。でももう、聞こえない。頭が痛い。割れそうだ。
隆介と目が合う。大好きな人。焦がれて焦がれて、欲しくて欲しくて、やっと手に入れた人の瞳が──恐怖に歪む。
なにが、と言いかけているのは理解する。でもきっと、隆介だってわかっている。そうでなきゃこんな仕打ちはできないはずだ。
彼が手に持った写真立てに目を遣る。
私が隆介と同じ会社に入社する前に撮られたもの。
今より若いスーツを着た隆介。遠慮がちに並ぶ女性は、細く長い髪を肩まで伸ばし、その下には意志の強そうな切れ長の瞳があって、パンツスーツがよく似合っていて、私なんかよりよっぽど大人な考えの、それなのに恋人に浮気されて振られた──紗和だ。
あの人から私は、隆介を奪った。
隆介の指についた血を見つめ、私は掠れた声で呟いた。
「だから怪我したんじゃなくて?」
同じ質問をくり返す隆介の手首を引き寄せて、その匂いを嗅いだ。
鉄くさい。間違いなく血だ。でも、私は怪我なんてしていない。
自分で右耳を触って、目の前に持ってくる。今度は何もない。隆介の指を見る。やっぱり血がついている。隆介も血だと認識している。どういうこと?
「私にはつかなかった」
うまく声が出ないままだけど、隆介には伝わったようだ。
私は彼に手を見せる。隆介の視線が私の手に移り、自分の指に戻った。
眉を顰めて「なんだこれ」と呟く。くん、と鼻先で私と同じように匂いを嗅ぎ、納得したように頷いてからぺろりと舐めた。
「……血だ。間違いなく」
気味が悪い。口にはしなかったが、隆介から伝わってきた。私も同じ気持ちだ。気味が悪い。
もう一度私も右耳を手で拭ってみる。やっぱり何もつかなかった。髪を右耳にかけて、改めて隆介へ向ける。
「ついてる?」
何が、とは言わなかった。ただ首を横に振る。
黙ったまま隆介はスマートフォンを撮りだした。そのままで、と動きだけで制され、言われるがまま動かないでいる。
シャッター音がしたあとに彼は画面を確認した。凝視したままさらに眉を顰める。
何、何があったの? 私は隆介の腕を引っ張った。彼はまた首を横に振る。
そんな態度を取られて気にならないわけがない。無理やりスマホを奪い、画面を見て──固まった。
変なものが写りこんでいるのではない。その方がまだマシだったかもしれない。何故なら理由が説明できる現象が起きていることだってあり得るからだ。でも、違った。
横を向いた私が写っている。
そのほぼ中心に写っている耳が、ひしゃげたように歪んでいる。
ブレたとかそんな表現では済まされない。だって、他の部分──目や髪は何も異常なく写っているのだ。
耳だけ。耳だけが、何かが上から押し付けているかのように歪んでひしゃげていた。
気味が悪い。なのに、見ていると妙に引き寄せられてしまう。歪んだ自分の耳に何かが被さっていそうな気がする。それを知りたい。気味が悪いのにずっと見ていたい。
うまく説明できない感情に支配され、食い入るようにそれを見つめた。
「おい」
大きな手が肩を掴む。隆介が訝しげに私を見る。
「そんなもん見ない方がいい」
どうして? だってきっとここには、何かが。何かってなんだろう。そうだ。あれだ。耳元に吐かれる息。あれがきっとここにいる。だから私の耳が歪んで見えるんだ。正体がわかればもうわけのわからない現象に悩まされることはない。そう思えばこれは解決の糸口かもしれない。妙な高揚感が私をかき立てた。
「おいってば」
スマホを握る私の手を隆介が剥がそうとしてきた。思いきり振りほどく。隆介が驚いて、もう一度私に寄り添う。
やめて。邪魔しないで。いつも会いたい時には来てくれないくせに、私の望みなんて何ひとつ叶えてくれないくせに、こんな時に邪魔をしないで。
さっきまであれだけ助けてほしいと願った手を振りほどくなんて、何をしてるの?
頭の片隅から声がする。歪んだ笑みを浮かべた私が、私を見下ろしている。
わかってる。今私がしなきゃいけないのは、怖かったと隆介に甘えることだ。今こそそのタイミングだとわかっているのに、身体が言うことを聞かない。
確かめたかった。おかしな現象に見舞われ始めた頃に紗和に辿り着いた時から。
紗和と会った時から。まさかと疑いを抱いたあれの正体を確かめたかった。
「おい。いい加減にしないと──」
隆介の手に力がこもる。痛い。だからなんで、こんな時ばっかり。
「いい加減にするのはそっちでしょ!」
喘ぐように叫んで、思いきり隆介を突き飛ばした。
床に転がる彼を横目に荒げた息を整えながら立ちあがると、ゆらゆらとチェストへ向かう。
「おまえ……」
呻く隆介の声がする。そうだよ。見たよ。見たくもない写真を見せられた。あなたはまだ彼女のことが忘れられないんだ。ユキナも言っていた。隆介は頭の回転が速い。私の気持ちに気づかないはずがない。不安で潰されそうな今の私を、わからないなんて言わせない。
チェストに辿り着く。初めて見た、私の知らない隆介が収まる写真立て。
隣で微笑んでいるのは──
写真立てを掴み、床に向かって投げつけようとしたところで隆介に止められた。
手首を掴まれ、暴れる私を抑えつけてくる。どれだけやめろとくり返されたってやめたくない。こんなものがある限り、私の心に平穏なんて訪れない。元々そんなものなかったけど。
はたと気づいて動きを止める。写真立ては手にしたまま、床にへたりこんだ。
隆介は私を警戒しながらも、手首を抑えつける力を少し緩めてくれたのがわかった。
そうだ。そんなものなかった。そもそもは私がいけなかった。
スマートフォンが鳴る。電話だ。ゆらりと鞄へ向いて、のろのろと腕を伸ばす。まるで異質なモノを見るかのような視線を感じた。わかっている。隆介だ。彼にとって私はまさに異質で、理解不能で、厄介な恋人なのだろう。
発信元を見ると、『ユキナ』の文字があった。
隆介が未だ訝し気に私を見つめている。彼の手を確認してみる。
さっきまでべっとりとついていた血はなくなっていた。二人そろって幻覚を見たのだろうか。匂いまで嗅いで?
隆介なんて、舐めていた。そんなことありえない。あれは現実だった。あれは……考えがまとまりそうでまとまらない。
着信音は鳴りやまない。私は通話をタップした。
『芳野さん? ごめんねこんな時間に。今大丈夫です?』
ユキナの言葉に隆介を見た。
大丈夫かと問われたら、大丈夫じゃない。隆介の部屋でもわけのわからない現象に襲われ、直後に彼が帰宅して、私の耳に血がついていて、彼もそれを見て、舐めて、写真が──ああ、なんだっけ。そう。あれ。あれは──
『芳野さん? マジで大丈夫なの?』
「……わかんない」
答える唇が歪に笑う。
大翔は逃げることが出来た。本人は本当に終わったのかわからないといった風だったけど、大翔はもう逃げ切っている。くり返されるブックマークはただの名残だ。あれはいつだって影から見ている。いつでもこちらへ戻っておいでというように。
紗和は過去として話せるほどには、被害はないようだった。ひっかかる場面はいくつかあるけど、私に憐憫の目を向けていた。憐憫の目。憐憫、の……
「……やっぱりそうなの?」
ゆっくりと、隆介を見る。
電話の向こうでユキナが何か言っている。だけどもう聞こえない。スマートフォンが私の手から落ちて、鈍い音がした。ケースが頑丈なのか、割れる音はしない。代わりにユキナの声がする。でももう、聞こえない。頭が痛い。割れそうだ。
隆介と目が合う。大好きな人。焦がれて焦がれて、欲しくて欲しくて、やっと手に入れた人の瞳が──恐怖に歪む。
なにが、と言いかけているのは理解する。でもきっと、隆介だってわかっている。そうでなきゃこんな仕打ちはできないはずだ。
彼が手に持った写真立てに目を遣る。
私が隆介と同じ会社に入社する前に撮られたもの。
今より若いスーツを着た隆介。遠慮がちに並ぶ女性は、細く長い髪を肩まで伸ばし、その下には意志の強そうな切れ長の瞳があって、パンツスーツがよく似合っていて、私なんかよりよっぽど大人な考えの、それなのに恋人に浮気されて振られた──紗和だ。
あの人から私は、隆介を奪った。