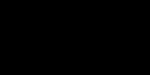「ただ別れただけなら、私もあんなことしませんでした」
遠くを見るような目をして紗和は続ける。
「やっぱり浮気が嫌だったんだと思います」
最後まで紗和に正直でいることが誠実だと思い込んだ櫻木の、馬鹿な告白。それがすべてだったと笑った彼女に、私はどこかうすら寒いものを感じた。
「ツイッターにアカウントを作ったんです」
それまでSNSになんて興味なかったのに。
紗和は頬杖をつくと、よどみなく話し始めた。
フェイスブックはやってたんです。流行り出した頃に登録しただけで書くことないし続かなくて放置してるけど、同窓会には便利なんで。
とにかくツイッターには興味なくて。こう言ったら失礼かもしれませんけど、匿名性が高いから使ってる人のレベルが低いと思ってたんです。実際低いし。時々本名のままだったり学校名出してる学生とか子供の顔載せてる親とかいるけど、馬鹿だなと思いません? ネットリテラシーっていうけど要は警戒心なさすぎですよね。
で、まあ、作ったんですよ。アカウント名ですか? 櫻木の新しい彼女の頭文字にしました。聞きたくもないのに教えてくれたんで。よくある名前だし片仮名にしたし、問題はないでしょう。
そこでほぼ毎日櫻木の話を呟きまくってました。六年も付き合ってたんだからネタは尽きないですよ。名前は出さないで、ノロケと愚痴の絶妙なバランスっていうんですか。会社や学校は伏せてるし、ちょっと盛ったりもしたし、確定されるのは避けたかったのでそこはうまくやってました。
セックスの話まで全部ぶっちゃけてたんですよ。ああいう話って好きな人多いんですかね? フォロワーがすごい増えたんです。何十万って人が櫻木の恥ずかしいセックスのクセまで知ってると思ったら笑えてきて、どんどん呟きました。櫻木にはバレてませんよ。あの人もツイッターするような人間を見下してるんで。
空になった紅茶のカップを見遣り、紗和はウェイトレスを呼ぶ。おかわりを注文すると、改めて私に対峙した。
ダークブラウンのショートカットがさらさらと揺れている。会社のホームページに載っていた紗和は肩下まで伸びた綺麗な黒髪をひとつに結い、凛とした印象を強く与えていた。
「……ご両親は健在ですか?」
突然話の方向性が変わったように感じ、面食らう。
それでも頷くと、紗和は下手な愛想笑いを浮かべた。営業としては致命的なほどに歪んでいる。
「ツイッターで呟きはじめた頃にね、母親にバレたんですよ。櫻木と別れたことが」
下手な愛想笑いと思ったのは気のせいではない。口元は笑っているのに目が笑っていない。
初対面の人間に対して「初めて見る」という表現は適切ではないとわかっているが、それでも紗和のこんな表情はおそらく滅多に見るものではないと想像できた。
先程のウェイトレスから紅茶を受け取る。喉を潤した紗和は、また饒舌に話し出した。
二十八にもなって、いちいち彼氏と別れたとか報告する方がおかしいと思いません?
ちなみにあなたは──あ、二十五歳。彼氏は? あぁ、いるんですね。親御さんは何か口出ししてきます? ですよね。それが普通ですよ。たまに顔合わせたときにうるさいなあって、そのくらいでいいんですよ。
……うちは異常なんです。私の事を自分の作品とか所有物くらいに思ってる。
家の恥でしかないから過去の話は省きますけど、とにかく別れたことがバレてから毎日電話がかかってきたり、アポなしに家に訊ねて来るようになりました。櫻木に謝ってヨリ戻せって言うんですよ。意味が分からないでしょう。むしろ謝られるのは私なのに。
管理人さんに親だからって身分証明して合い鍵もらって勝手に入ってた時にはぞっとしましたね。家に帰ったら電気がついてて料理作ってて、悪びれるどころか「おかえり」「遅かったわね」「いつもこんなに遅いの?」「だから櫻木さんも愛想つかすのよ」って。どこのホラーかと思いました。
紗和の語気が強くなっている。
櫻木の話とは違う種類の憎しみ──むしろ、母親に対しての感情の方が櫻木よりもずっと根深いのはよくわかった。
どう考えても紗和の母親は異常だ。母親という立場を利用して、娘とはいえ別の人間相手に踏み込みすぎている。
「だからもう一つ、アカウントを作ったんです」
そう言った紗和の顔色は、紙のように白くなっていた。
喉の奥が鳴る。初めて知った情報だった。
私が紗和に辿り着いた時に得ていたのは、彼氏について赤裸々に話すツイッターアカウントの主が彼女だったということだけだ。
……キィ、と耳障りな音がする。
ドルチェはすでに食べ終えているのに、紗和がそれのあった場所へとフォークを刺したのだ。黒板に爪を立てたような苦手な音に思わず顔を顰めると、あぁ、と初めて気づいたようにフォークを置いた。
「……それで、どうしたんですか」
質問を重ねる。紗和が顔を上げた。
「夢中で打ち込んでました。それこそ異常なくらい」
少しの間をおいて、紗和が鞄からスマートフォンを取り出した。
「もう手をつけてませんけど、アカウントは消してないんです」
言いながら画面を見せてくれる。綺麗に伸ばした爪の先に、可愛らしい猫のアイコンがあった。
「読んでみてください」
スマートフォンを受け取ったはいいものの、人様のものだという意識から紗和を見上げる。彼女は黙ったまま頷いた。
その顔色は未だ白い。視線を画面に戻し、羅列を追う。
最初の頃はただの愚痴だ。距離が近すぎる母親に対して『鬱陶しい』とわかりやすい文言が続く。勝手に家へ入られていたらしい時には『なんで』『帰ったらいたんだけど』『ありえない』『怖い』と端的に記している。
様子が変わったのは、一か月半が経った頃だ。
『だれかいる』
突然の平仮名。
紗和を見る。私の手元を覗き込むと、納得したように頷いた。
「その頃からです」
──なにが、とは言わなかった。しかし、私にはわかった。
スマートフォンを紗和に手渡すと、彼女は視線を落としたまま口を開く。
「櫻木との赤裸々アカウントと、母の愚痴アカウント。同時進行をはじめて一か月半が経ったころから、何かの気配を感じるようになりました」
あの頃の私はどうかしてたんです、と続ける。
文字通り、狂ったように愚痴や悪口を打ち込み続けていました。
櫻木のことも感情的に責めたて続けて、母への愚痴アカウントでは仕事の愚痴も混ざってました。見ましたよね? ええ、ひどいものです。
休みまで私を頼ってくるお客様に対して『死ね』とか普通に呟いてました。それは営業の仕事じゃないってことまで甘えてくるんですよ。断れない私も悪いのかもしれないけど、それにしてもキツかった。でも、それを当たり前として頑張ってたんです。大変だと思う事はあっても、死ねだなんて思ったことなかった。
でもそんなことばっかり呟いてるんです。気づけば罵詈雑言ですよ。死ね、消えろ、何様のつもりだ。ひどいことばっかり。あれが私の本音だったのかな。どうなんでしょう。自分でもよくわかりません。
呪いのように吐き続けました。正直あの時のことはほとんど覚えてないです。スマホを開いてツイッター開いて、悪口書いてる。何も考えずに毎日……毎時間かな。最終的には一時間に何回も同じようなことばかり呟いてました。
ふ、と息が漏れた。紗和だ。
「──そんなある日、誰かがいるって思って」
その表情を凝視する。彼女は気遣うように私を見た。
「スマホだとわからなかった。パソコンを閉じようとした時に気づいたんです」
あなたもでしょう?
言葉にはしなかったけど、紗和は確かにそう言った。
遠くを見るような目をして紗和は続ける。
「やっぱり浮気が嫌だったんだと思います」
最後まで紗和に正直でいることが誠実だと思い込んだ櫻木の、馬鹿な告白。それがすべてだったと笑った彼女に、私はどこかうすら寒いものを感じた。
「ツイッターにアカウントを作ったんです」
それまでSNSになんて興味なかったのに。
紗和は頬杖をつくと、よどみなく話し始めた。
フェイスブックはやってたんです。流行り出した頃に登録しただけで書くことないし続かなくて放置してるけど、同窓会には便利なんで。
とにかくツイッターには興味なくて。こう言ったら失礼かもしれませんけど、匿名性が高いから使ってる人のレベルが低いと思ってたんです。実際低いし。時々本名のままだったり学校名出してる学生とか子供の顔載せてる親とかいるけど、馬鹿だなと思いません? ネットリテラシーっていうけど要は警戒心なさすぎですよね。
で、まあ、作ったんですよ。アカウント名ですか? 櫻木の新しい彼女の頭文字にしました。聞きたくもないのに教えてくれたんで。よくある名前だし片仮名にしたし、問題はないでしょう。
そこでほぼ毎日櫻木の話を呟きまくってました。六年も付き合ってたんだからネタは尽きないですよ。名前は出さないで、ノロケと愚痴の絶妙なバランスっていうんですか。会社や学校は伏せてるし、ちょっと盛ったりもしたし、確定されるのは避けたかったのでそこはうまくやってました。
セックスの話まで全部ぶっちゃけてたんですよ。ああいう話って好きな人多いんですかね? フォロワーがすごい増えたんです。何十万って人が櫻木の恥ずかしいセックスのクセまで知ってると思ったら笑えてきて、どんどん呟きました。櫻木にはバレてませんよ。あの人もツイッターするような人間を見下してるんで。
空になった紅茶のカップを見遣り、紗和はウェイトレスを呼ぶ。おかわりを注文すると、改めて私に対峙した。
ダークブラウンのショートカットがさらさらと揺れている。会社のホームページに載っていた紗和は肩下まで伸びた綺麗な黒髪をひとつに結い、凛とした印象を強く与えていた。
「……ご両親は健在ですか?」
突然話の方向性が変わったように感じ、面食らう。
それでも頷くと、紗和は下手な愛想笑いを浮かべた。営業としては致命的なほどに歪んでいる。
「ツイッターで呟きはじめた頃にね、母親にバレたんですよ。櫻木と別れたことが」
下手な愛想笑いと思ったのは気のせいではない。口元は笑っているのに目が笑っていない。
初対面の人間に対して「初めて見る」という表現は適切ではないとわかっているが、それでも紗和のこんな表情はおそらく滅多に見るものではないと想像できた。
先程のウェイトレスから紅茶を受け取る。喉を潤した紗和は、また饒舌に話し出した。
二十八にもなって、いちいち彼氏と別れたとか報告する方がおかしいと思いません?
ちなみにあなたは──あ、二十五歳。彼氏は? あぁ、いるんですね。親御さんは何か口出ししてきます? ですよね。それが普通ですよ。たまに顔合わせたときにうるさいなあって、そのくらいでいいんですよ。
……うちは異常なんです。私の事を自分の作品とか所有物くらいに思ってる。
家の恥でしかないから過去の話は省きますけど、とにかく別れたことがバレてから毎日電話がかかってきたり、アポなしに家に訊ねて来るようになりました。櫻木に謝ってヨリ戻せって言うんですよ。意味が分からないでしょう。むしろ謝られるのは私なのに。
管理人さんに親だからって身分証明して合い鍵もらって勝手に入ってた時にはぞっとしましたね。家に帰ったら電気がついてて料理作ってて、悪びれるどころか「おかえり」「遅かったわね」「いつもこんなに遅いの?」「だから櫻木さんも愛想つかすのよ」って。どこのホラーかと思いました。
紗和の語気が強くなっている。
櫻木の話とは違う種類の憎しみ──むしろ、母親に対しての感情の方が櫻木よりもずっと根深いのはよくわかった。
どう考えても紗和の母親は異常だ。母親という立場を利用して、娘とはいえ別の人間相手に踏み込みすぎている。
「だからもう一つ、アカウントを作ったんです」
そう言った紗和の顔色は、紙のように白くなっていた。
喉の奥が鳴る。初めて知った情報だった。
私が紗和に辿り着いた時に得ていたのは、彼氏について赤裸々に話すツイッターアカウントの主が彼女だったということだけだ。
……キィ、と耳障りな音がする。
ドルチェはすでに食べ終えているのに、紗和がそれのあった場所へとフォークを刺したのだ。黒板に爪を立てたような苦手な音に思わず顔を顰めると、あぁ、と初めて気づいたようにフォークを置いた。
「……それで、どうしたんですか」
質問を重ねる。紗和が顔を上げた。
「夢中で打ち込んでました。それこそ異常なくらい」
少しの間をおいて、紗和が鞄からスマートフォンを取り出した。
「もう手をつけてませんけど、アカウントは消してないんです」
言いながら画面を見せてくれる。綺麗に伸ばした爪の先に、可愛らしい猫のアイコンがあった。
「読んでみてください」
スマートフォンを受け取ったはいいものの、人様のものだという意識から紗和を見上げる。彼女は黙ったまま頷いた。
その顔色は未だ白い。視線を画面に戻し、羅列を追う。
最初の頃はただの愚痴だ。距離が近すぎる母親に対して『鬱陶しい』とわかりやすい文言が続く。勝手に家へ入られていたらしい時には『なんで』『帰ったらいたんだけど』『ありえない』『怖い』と端的に記している。
様子が変わったのは、一か月半が経った頃だ。
『だれかいる』
突然の平仮名。
紗和を見る。私の手元を覗き込むと、納得したように頷いた。
「その頃からです」
──なにが、とは言わなかった。しかし、私にはわかった。
スマートフォンを紗和に手渡すと、彼女は視線を落としたまま口を開く。
「櫻木との赤裸々アカウントと、母の愚痴アカウント。同時進行をはじめて一か月半が経ったころから、何かの気配を感じるようになりました」
あの頃の私はどうかしてたんです、と続ける。
文字通り、狂ったように愚痴や悪口を打ち込み続けていました。
櫻木のことも感情的に責めたて続けて、母への愚痴アカウントでは仕事の愚痴も混ざってました。見ましたよね? ええ、ひどいものです。
休みまで私を頼ってくるお客様に対して『死ね』とか普通に呟いてました。それは営業の仕事じゃないってことまで甘えてくるんですよ。断れない私も悪いのかもしれないけど、それにしてもキツかった。でも、それを当たり前として頑張ってたんです。大変だと思う事はあっても、死ねだなんて思ったことなかった。
でもそんなことばっかり呟いてるんです。気づけば罵詈雑言ですよ。死ね、消えろ、何様のつもりだ。ひどいことばっかり。あれが私の本音だったのかな。どうなんでしょう。自分でもよくわかりません。
呪いのように吐き続けました。正直あの時のことはほとんど覚えてないです。スマホを開いてツイッター開いて、悪口書いてる。何も考えずに毎日……毎時間かな。最終的には一時間に何回も同じようなことばかり呟いてました。
ふ、と息が漏れた。紗和だ。
「──そんなある日、誰かがいるって思って」
その表情を凝視する。彼女は気遣うように私を見た。
「スマホだとわからなかった。パソコンを閉じようとした時に気づいたんです」
あなたもでしょう?
言葉にはしなかったけど、紗和は確かにそう言った。