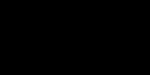ぬるりとした空気が一帯に広がった。神経が耳に集中する。生ぬるい。気持ち悪い。
いつもそうだ。ハァ、と吹きかけられるようでいて、舌まで這わせてきそうな気色悪さを覚える。生理的に受け付けないのだ。
手も脚も床に張り付いたように動けない私の耳元で、ハァ、とまたもや聞こえてくる。
いつか遭った痴漢もこんな風に荒げた息を押し付けてきたが、それとは全然違う。
ため息。うんざりしたような、疲れたような。いや、違う。少し震えている。恐怖? 違う。それは私に湧き上がっている感情のはずだ。でも、やはり震えた唇の存在を感じてしまう気がした。身体を持たないあれの、唇。そんなことがあるはずない。ではこのため息は一体どこから発している? こんなに近くに在るのに、かたちはない。
振り返ることはとても出来なかった。
小さく、ハァ、と続ける息は、たとえば変質者であれば肉体を持つ人間のはずだ。でも、リビングには誰もいない。そんなことは私が一番わかっている。足跡も気配もしなかった。在ったのは、影だけ。
──ハァア。
ため息が大きくなる。汗が頬を伝う。一歩も動けない。
暗闇に瞳が慣れてきて、リビングにある家具の輪郭がぼんやりと浮かび上がってくる。
どうやら私はチェストを背にして、浴室の方向へ──玄関へ向かおうとしている。
斜め奥にはソファもある。でも、動けない。少し前に沸いたことを告げてきた風呂は、主を待っているはずだ。温かいあそこへ行きたい。でも行けない。全身が冷え切っている。温まりたい。でも、逃げたい。なのに動けない。
休まることなく──しかも全く意味のない方向へと思考は動いているのに、自分のものであるはずの手足は相変わらず動かない。
ハァ、ハァア、と息は続いている。
膝をついている床が、手のひらから伝わる床の温度が、ゆっくりと、確実に冷たくなっていく。寒い。耳元の息と同じように、私もハァ、と震える息を吐きだすことになる。寒すぎる。いくら雨に濡れたからといって、こんなに冷え込むなんておかしい。よく見ると、吐き出されたそれが白いもやのように反応する。今、この部屋は一体どうなっているのだろう。
ヴンヴンンン、ン、
ひと際大きく音が跳ねた。電子音。まるでアピールするかのように部屋中に響きはじめる。
頭がおかしくなりそうだ。ヴヴヴ、ハァアアアア。ふたつの存在は呼応するかのように続いている。寒くて寒くてどうしようもない私と、正体不明の音だけが隆介の部屋にある。
──ピ、ピピピッ
玄関の方向から解錠の音がした。隆介だ。隆介が帰ってきた。
それを認めた瞬間、照明がすべて点いた。
照明だけじゃない。テレビもコンポも同時に電源が入り、バラエティー番組の賑やかな笑い声と、隆介の好きな映画のサントラが一気に流れ始めた。
「おい、何やってるんだ?」
リビングに入ってきた隆介は怪訝な顔で訊ねる。
「……あ、……」
喉の奥がはりついて、声を出すことが出来ない。
隆介から見れば帰宅したら部屋中の電気が点いている上、リビングの端で私が四つん這いになり固まっている状態だ。
彼の疑問はもっともだった。
でも、私は声を発することも、身体を動かすことも未だできなかった。
「何やってんだって。ほんとに」
足音をたてながら隆介はテレビとコンポを消していく。
首のうしろをガリガリと掻きながら部屋中を歩き回り、浴室を確認すると、「沸いてる」と微かに眉を顰めた。
お風呂も借りると連絡はしたはずなのに。
それに、私の心配はないのだろうか。
何をやっているのかではなく、何があったんだと心配してくれてもいい場面じゃないのか。
……だめだ、また不満ばっかり。
そういう所が駄目なんだと自戒して、私は意識的に息を吸った。
さっきまで繰り返されていた耳元のため息も、どこからきているのかわからない電子音もすべてが消えている。
「いつまでそうしてるんだ?」
しゃがみ込んだ隆介と目が合った。
仕方ないやつだな、と表情が語っている。ポン、と頭を撫でられた。
鬱陶しいのなら突き放せばいいのに、中途半端に優しくするから私もまだ諦められない。追ってしまう。黒い感情に蓋もできないまま、要望ばかり心のうちに溜まっていく。
隆介に手伝われながら、普通に座る体勢に戻れた。
それでも冷や汗は止まらない。
耳にはあれがずっと吹きかけられている気がするし、呼応した電子音も耳の奥で止みそうになかった。
「とりあえず風呂入ったら。雨に相当ふられたんだろ。そんな寒がって」
私を立ちあがらせようと手を伸ばした隆介の顔が、ふと傾いた。
なに?
声が出なくても私の表情でわかったようだ。隆介は「いや……」と反対側にもう一度首を傾げ、私の耳に手を伸ばす。
ずっとずっとあれが吹きかけられていた右耳だ。
「怪我でもしたのか」
そして、指で軽く触れた隆介が、うわ、と小さな声をあげて、今度は明らかに顔を顰める。
痛まないかと訊ねられたが、私は首を振った。怪我はしていないはずだ。
ただただ、あれを感じていただけ。
「……これ」
さしだされた隆介の指に、塗りつけられたような真っ赤な血がついていた。
いつもそうだ。ハァ、と吹きかけられるようでいて、舌まで這わせてきそうな気色悪さを覚える。生理的に受け付けないのだ。
手も脚も床に張り付いたように動けない私の耳元で、ハァ、とまたもや聞こえてくる。
いつか遭った痴漢もこんな風に荒げた息を押し付けてきたが、それとは全然違う。
ため息。うんざりしたような、疲れたような。いや、違う。少し震えている。恐怖? 違う。それは私に湧き上がっている感情のはずだ。でも、やはり震えた唇の存在を感じてしまう気がした。身体を持たないあれの、唇。そんなことがあるはずない。ではこのため息は一体どこから発している? こんなに近くに在るのに、かたちはない。
振り返ることはとても出来なかった。
小さく、ハァ、と続ける息は、たとえば変質者であれば肉体を持つ人間のはずだ。でも、リビングには誰もいない。そんなことは私が一番わかっている。足跡も気配もしなかった。在ったのは、影だけ。
──ハァア。
ため息が大きくなる。汗が頬を伝う。一歩も動けない。
暗闇に瞳が慣れてきて、リビングにある家具の輪郭がぼんやりと浮かび上がってくる。
どうやら私はチェストを背にして、浴室の方向へ──玄関へ向かおうとしている。
斜め奥にはソファもある。でも、動けない。少し前に沸いたことを告げてきた風呂は、主を待っているはずだ。温かいあそこへ行きたい。でも行けない。全身が冷え切っている。温まりたい。でも、逃げたい。なのに動けない。
休まることなく──しかも全く意味のない方向へと思考は動いているのに、自分のものであるはずの手足は相変わらず動かない。
ハァ、ハァア、と息は続いている。
膝をついている床が、手のひらから伝わる床の温度が、ゆっくりと、確実に冷たくなっていく。寒い。耳元の息と同じように、私もハァ、と震える息を吐きだすことになる。寒すぎる。いくら雨に濡れたからといって、こんなに冷え込むなんておかしい。よく見ると、吐き出されたそれが白いもやのように反応する。今、この部屋は一体どうなっているのだろう。
ヴンヴンンン、ン、
ひと際大きく音が跳ねた。電子音。まるでアピールするかのように部屋中に響きはじめる。
頭がおかしくなりそうだ。ヴヴヴ、ハァアアアア。ふたつの存在は呼応するかのように続いている。寒くて寒くてどうしようもない私と、正体不明の音だけが隆介の部屋にある。
──ピ、ピピピッ
玄関の方向から解錠の音がした。隆介だ。隆介が帰ってきた。
それを認めた瞬間、照明がすべて点いた。
照明だけじゃない。テレビもコンポも同時に電源が入り、バラエティー番組の賑やかな笑い声と、隆介の好きな映画のサントラが一気に流れ始めた。
「おい、何やってるんだ?」
リビングに入ってきた隆介は怪訝な顔で訊ねる。
「……あ、……」
喉の奥がはりついて、声を出すことが出来ない。
隆介から見れば帰宅したら部屋中の電気が点いている上、リビングの端で私が四つん這いになり固まっている状態だ。
彼の疑問はもっともだった。
でも、私は声を発することも、身体を動かすことも未だできなかった。
「何やってんだって。ほんとに」
足音をたてながら隆介はテレビとコンポを消していく。
首のうしろをガリガリと掻きながら部屋中を歩き回り、浴室を確認すると、「沸いてる」と微かに眉を顰めた。
お風呂も借りると連絡はしたはずなのに。
それに、私の心配はないのだろうか。
何をやっているのかではなく、何があったんだと心配してくれてもいい場面じゃないのか。
……だめだ、また不満ばっかり。
そういう所が駄目なんだと自戒して、私は意識的に息を吸った。
さっきまで繰り返されていた耳元のため息も、どこからきているのかわからない電子音もすべてが消えている。
「いつまでそうしてるんだ?」
しゃがみ込んだ隆介と目が合った。
仕方ないやつだな、と表情が語っている。ポン、と頭を撫でられた。
鬱陶しいのなら突き放せばいいのに、中途半端に優しくするから私もまだ諦められない。追ってしまう。黒い感情に蓋もできないまま、要望ばかり心のうちに溜まっていく。
隆介に手伝われながら、普通に座る体勢に戻れた。
それでも冷や汗は止まらない。
耳にはあれがずっと吹きかけられている気がするし、呼応した電子音も耳の奥で止みそうになかった。
「とりあえず風呂入ったら。雨に相当ふられたんだろ。そんな寒がって」
私を立ちあがらせようと手を伸ばした隆介の顔が、ふと傾いた。
なに?
声が出なくても私の表情でわかったようだ。隆介は「いや……」と反対側にもう一度首を傾げ、私の耳に手を伸ばす。
ずっとずっとあれが吹きかけられていた右耳だ。
「怪我でもしたのか」
そして、指で軽く触れた隆介が、うわ、と小さな声をあげて、今度は明らかに顔を顰める。
痛まないかと訊ねられたが、私は首を振った。怪我はしていないはずだ。
ただただ、あれを感じていただけ。
「……これ」
さしだされた隆介の指に、塗りつけられたような真っ赤な血がついていた。