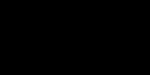**
ユキナとの打ち合わせが終わり、地下鉄ホームでぼんやりと電車を待つ。
何だかどっと疲れてしまった。ポケットに入っているスマートフォンが数秒震えて止まる。反応する気力がない。
無理もないだろう。浜松までの往復ドライブからわけのわからない現象に襲われて倒れ、そのまま打ち合わせだった。
本音を言えば家に帰って早く寝たい。でも、帰りたくない。ノートパソコンに触りたくない。
だから、今から向かうのは、近所のネットカフェだ。昔から色々詰まった時に通っていた馴染みのところ。
どこよりも落ち着く場所だったはずの我が家が怖いなんて、この先どうしたらいいんだろう。
引っ越したら落ち着くとも思えない。あれは場所ではなく人を追うものだ。
見知らぬ男性のスーツの背を見ながら、どうしてこうなってしまったんだろうと瞼を閉じる。
電車を待つ時、先頭に立たなくなった。立てなくなった。
元より新幹線ホームの隙間が苦手の私にとっては似たようなものだけど、それでも毎日使わなくてはいけないという義務感からか、見て見ぬふりをして、常に前を向くように気にしないようにと意識して、頑張っていた。
でも、今はダメだ。どうしても視線が足元を向いてしまう。
底から何かが這い上がってくるのではないか。ぬるりとした何かが足に絡みついて、引きずり込まれるのではないか。
ヘッドフォンで音楽も聞けなくなった。
周囲の雑音をかき消してくれるから大好きだったはずが、怖くなった。
あれは何よりもそばで聞こえる。
なら、もしも、ヘッドフォンをしているのに聞こえてしまったら。
電車がすべりこんでくる瞬間、耳元であの息が響いたら。
どんなに大きな音がしても、何よりも響くあの息が。
電車の轟音も、聞いていたはずの音楽もすべて消して聞こえてしまったら、動揺のあまり飛び出してしまう恐怖があった。
アナウンスが聞こえる。少し遠くから電車の光が見える。並ぶ乗客たちは皆手元のスマートフォンに夢中で、そんなこと気に留める様子もない。前に並ぶスーツの男性も同じ。
もしもここで私がそっと背中を押したところで、目撃する人はいるのだろうか。
ふとそんな考えが過ぎって首を振る。今、私は何を。
両手で耳を塞ぎ、すべりこんでくる電車を迎えた。風で髪が煽られて視界に揺れる。隆介が長い方が好きと言ったから伸ばした髪。
背後から押されるようにして車内に入る。ドア付近に立ち、周囲の乗客たちと同じようにスマートフォンを取り出した。
さっき何らかの連絡が入ったはずだと確認すると、ユキナからのラインだった。
『あんまりひどいようなら、ちゃんと病院行ってくださいよ』
末尾には、可愛く描かれた猫がこちらに向かって指をさすスタンプ。
ユキナは私より年下だ。学生の頃から画力がインターネットで話題となり、あっという間にイラストを生業とした。
本人曰く「こもって絵ばっか描いてたんで」ということだが、元々の感性もないと今のような売れっ子にはなっていないだろう。
『ありがとうございます。引き続きお願いしますね』
お礼を打ち込んで、スマホをポケットに突っ込む。
年下だが、私よりよっぽど大人な女性だ。
軽いノリで茶化してはいるが、人を見る目はかなり鋭く、何事においても達観している節がある。
それは本人が望んだものではない。
会ってまもない頃、隆介が開いてくれた懇親会という名の飲み会で、「本当に大人ですよね。どうしたらユキナさんみたいになれますか」と褒めたつもりの私に、『周りの顔色を窺って生きてきた賜物ですよ』と、あっけらかんと笑っていた。
若くて努力を忘れない才能のある、美しく強い女の子。
はじめの頃こそ、ユキナが言っていた通り隆介との仲を疑ったことがあった。
まだ私が隆介と付き合う前だ。一緒に仕事をするようになったからこそ、彼女の魅力を充分に理解した上の嫉妬だった。
隆介がユキナを狙っているのではないか。
そして彼女も、それをまんざらでもなくあしらっているのではないか。
すべてが勘違いだとわかったのは、ユキナの恋愛対象が女性だと本人が教えてくれたからだ。
恥ずかしかった。そんな目でしか仕事仲間を見られなかった恋愛脳の自分も、時折ユキナが「あたしは普通じゃないから」と寂しそうに笑っていた理由を察することが出来なかった自分も。
そして、そんな悲しい言葉で自身を否定するユキナが、どれだけ抑え込まれて傷ついて生きてきたのかを想像して、どうしようもなくなった。
またスマートフォンが震える。取り出して、確認する。
『大きなお世話とはわかってるけど、苦しいのは手放すのもアリだよ』
フッ、と息が漏れた。
具体的なことは何ひとつ書かれていないけど、何のことかは一目瞭然だ。隆介のことだろう。
私もきっと、友達に私のような恋愛相談を受けたら「やめるのもいいんじゃない」と言うかもしれない。
仕事のスケジュールにまで支障を来すのは、確かに異常だ。頭の隅ではわかっている。これはよくない、と。
それでも止められないから、恋なのだろう。そう思うしかない。そうでも思わないと、私のしていることはすべて間違っていることになる。
そんなの耐えられない。無理だ。今さら変えられない。
『この人きっと、どんどん深みにハマりそうって』
ユキナの予想は当たった。沼のように足をとられる深みにハマって、浮上できる気がしない。
『具体的な理由はわかんないけど。何かすごく印象的なことがあった気がする』
私は一体、ユキナの前で何をしたのだろう。
また話を聞いてみないとと思ったところで、最寄り駅への到着を知らせるアナウンスが聞こえた。