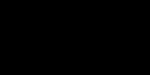*
隆介が笑っている。
細くて長い髪をゆったりと撫でながら、満ち足りたように笑っている。
あんな優しい表情を、私はしばらく見ていない。
忙しく飛び回る彼のあとをついて必死だった頃は、何度か目にしたことがあった。
ああ、と納得する。これは夢だ。あの頃の、夢だ。
夢を夢だと自覚する夢は、私はこれまでに幾度も経験があった。
初めて見たのは中学生の頃。あまり話したことのないクラスメイトの男子に淡い恋心を抱いた時の事だ。本当に、ただただ見つめるだけの恋だった。
特別教室へ移動するまでの距離を、偶然を装って近くで歩く。野外活動で一緒の班になろうと声をかけるなんてことが出来るはずもなく、それでも近くにいて、話しかけられるのをひたすらに待っていた。
今でも鮮明に覚えている。ある日、彼が笑顔で私の肩を叩く。私は驚き、頬を染めて振り返る。話してみたかったんだよねと屈託なく彼が笑う。その瞬間、これは夢だと自覚した。
それなのに、私も──たった一言が夢の中でさえ言えなくて、それ以上何もできなくて、目を覚まして肩を落とした。
夢でさえ、私は声を発することさえ出来なかった。
それから幾度も夢を見た。夢だと自覚している夢を。
恋をしている時が一番多かったのは、きっと願望が夢として具現化したのだろう。
あとは受験や就職など大切な試験前。すべての夢の中で夢だと自覚しているにも関わらず、私は好きに動けないのだ。
今もそう。
隆介に焦がれていた頃の夢を見ているとわかっているというのに、たくさんの資料を胸の前に抱えたまま、私はこの場から動けない。ただ隆介が優しく笑っているのを見ているだけ。資料なんてぶちまけて、駆けて行って、「この人はもう私のものだから」と宣言したって何の問題もない。だって、夢なのだから。
──やめて。さわらないで。
喉の奥が焼けつくように熱い。あの頃言えなかったことを、今は何だって言える。
だって、夢なのだから。
それなのに、言えない。動けない。どろどろとした黒いものが私の心を塗りつぶしていく。
どうして夢の中でまで過去の幻影に縛られないといけないんだろう。今はもう、隆介は私のものなのに。そのはずなのに。何ひとつ満たされていない証拠のように、私は嫉妬で喘いだ。
ハァ。
耳元に大きなため息。こんなところまで追いかけてきた。一体なんなの。邪魔しないで。恐怖よりも怒りが湧き出る。
さっきまであんなに怖かったのに──さっきまで?
サアッと血の気が引いた。私は今夢を見ている。現実の私は?
目を覚まさなくては──ともがいた右手を視界に捉え、詰めていた息が自然と漏れた。
天井だ。自分の部屋の、天井。
意識がハッキリするにつれ、左側の後頭部が痛んだ。どうやら倒れたらしい。そして、ぶつけたらしい。
ゆっくりと身体を起こし、状況を把握する。カーテン越しに眩しい光が差し込み、朝が来ているらしいことを知る。左肩にも微かな痛みが走った。
「……何時」
発した声が情けないほどに掠れているが、どうでもいい。
今日はユキナとの打ち合わせがある。打撲らしい原因で痛む左半身を引きずりながら、中身が散らばっている鞄を引き寄せた。
私の部屋には時計がない。普段は腕時計とスマートフォンで間に合っている。
その腕時計も昨日はドライブ途中で外して鞄に仕舞ってしまった。
手探りでスマートフォンを掴み、タップしようとした瞬間、着信音が響いた。
発信元は、ユキナだった。
「はい」
『芳野さん? 今どこですか』
「え」
『十時半ですよ。珍しいね、芳野さんが何もなしで遅れるの』
「え……あ……もうそんな時間」
『え? もしかしてまだ家? 声掠れてる』
「……申し訳ありません」
『いーよいーよ。いつも十五分前には来てる芳野さんだもん、心配しかしてなかったし。もしかして忙しかったんですか?』
「いや、ちょっと……部屋で倒れてたみたいで。なんか、気づいたら」
『はあ!? 何それ大丈夫?』
大丈夫です、三十分後には迎えますとくり返した私に、ユキナは無理はしないでと言ってくれた。
当然だ。私だって担当作家が家で倒れたと聞いたら打ち合わせより病院に行ってくださいと言うだろう。
それでも大丈夫だと繰り返し、通話を切った。
私は大丈夫だ。倒れた原因を自覚している。体調不良じゃない。今も一切視線を向けないように努めている。パソコンデスクにあるノートパソコン。あれがどうなっているのか、とてもじゃないが確かめる勇気がなかった。
パソコンデスクに背を向けて視線を逸らし続け、とりあえず着替える。
洗面台に立つと、昨日落とせなかったメイクの上からメイク直しを吹きかけて整えた。
部屋の隅に蠢く気配は今は感じられない。それとも、昨夜の恐怖が他の小さな異変を鈍らせているのかもしれない。
次にリップも直そうとして、やめた。かわりにマスクをつける。身体の心配をしてくれたユキナのことだ、マスクのまま会っても何も言わないだろう。
すべての支度を十分以内に終わらせ、洗面室を出ようとして──しまったと思った。
リビングから洗面室へ向かうには、リビングを背にすればいい。だから気にしていなかった。
玄関へ向かうにはリビングを通らなければいけない。
当然、さっきとは逆の方向にすべてが向かうことになる。身体も、視線も。
即座に背けたが、それでも視界の端に捉えた。
昨夜私が設定した覚えのない壁紙を見せつけてきたノートパソコンは、何事もなかったかのように、静かに閉じていた。
隆介が笑っている。
細くて長い髪をゆったりと撫でながら、満ち足りたように笑っている。
あんな優しい表情を、私はしばらく見ていない。
忙しく飛び回る彼のあとをついて必死だった頃は、何度か目にしたことがあった。
ああ、と納得する。これは夢だ。あの頃の、夢だ。
夢を夢だと自覚する夢は、私はこれまでに幾度も経験があった。
初めて見たのは中学生の頃。あまり話したことのないクラスメイトの男子に淡い恋心を抱いた時の事だ。本当に、ただただ見つめるだけの恋だった。
特別教室へ移動するまでの距離を、偶然を装って近くで歩く。野外活動で一緒の班になろうと声をかけるなんてことが出来るはずもなく、それでも近くにいて、話しかけられるのをひたすらに待っていた。
今でも鮮明に覚えている。ある日、彼が笑顔で私の肩を叩く。私は驚き、頬を染めて振り返る。話してみたかったんだよねと屈託なく彼が笑う。その瞬間、これは夢だと自覚した。
それなのに、私も──たった一言が夢の中でさえ言えなくて、それ以上何もできなくて、目を覚まして肩を落とした。
夢でさえ、私は声を発することさえ出来なかった。
それから幾度も夢を見た。夢だと自覚している夢を。
恋をしている時が一番多かったのは、きっと願望が夢として具現化したのだろう。
あとは受験や就職など大切な試験前。すべての夢の中で夢だと自覚しているにも関わらず、私は好きに動けないのだ。
今もそう。
隆介に焦がれていた頃の夢を見ているとわかっているというのに、たくさんの資料を胸の前に抱えたまま、私はこの場から動けない。ただ隆介が優しく笑っているのを見ているだけ。資料なんてぶちまけて、駆けて行って、「この人はもう私のものだから」と宣言したって何の問題もない。だって、夢なのだから。
──やめて。さわらないで。
喉の奥が焼けつくように熱い。あの頃言えなかったことを、今は何だって言える。
だって、夢なのだから。
それなのに、言えない。動けない。どろどろとした黒いものが私の心を塗りつぶしていく。
どうして夢の中でまで過去の幻影に縛られないといけないんだろう。今はもう、隆介は私のものなのに。そのはずなのに。何ひとつ満たされていない証拠のように、私は嫉妬で喘いだ。
ハァ。
耳元に大きなため息。こんなところまで追いかけてきた。一体なんなの。邪魔しないで。恐怖よりも怒りが湧き出る。
さっきまであんなに怖かったのに──さっきまで?
サアッと血の気が引いた。私は今夢を見ている。現実の私は?
目を覚まさなくては──ともがいた右手を視界に捉え、詰めていた息が自然と漏れた。
天井だ。自分の部屋の、天井。
意識がハッキリするにつれ、左側の後頭部が痛んだ。どうやら倒れたらしい。そして、ぶつけたらしい。
ゆっくりと身体を起こし、状況を把握する。カーテン越しに眩しい光が差し込み、朝が来ているらしいことを知る。左肩にも微かな痛みが走った。
「……何時」
発した声が情けないほどに掠れているが、どうでもいい。
今日はユキナとの打ち合わせがある。打撲らしい原因で痛む左半身を引きずりながら、中身が散らばっている鞄を引き寄せた。
私の部屋には時計がない。普段は腕時計とスマートフォンで間に合っている。
その腕時計も昨日はドライブ途中で外して鞄に仕舞ってしまった。
手探りでスマートフォンを掴み、タップしようとした瞬間、着信音が響いた。
発信元は、ユキナだった。
「はい」
『芳野さん? 今どこですか』
「え」
『十時半ですよ。珍しいね、芳野さんが何もなしで遅れるの』
「え……あ……もうそんな時間」
『え? もしかしてまだ家? 声掠れてる』
「……申し訳ありません」
『いーよいーよ。いつも十五分前には来てる芳野さんだもん、心配しかしてなかったし。もしかして忙しかったんですか?』
「いや、ちょっと……部屋で倒れてたみたいで。なんか、気づいたら」
『はあ!? 何それ大丈夫?』
大丈夫です、三十分後には迎えますとくり返した私に、ユキナは無理はしないでと言ってくれた。
当然だ。私だって担当作家が家で倒れたと聞いたら打ち合わせより病院に行ってくださいと言うだろう。
それでも大丈夫だと繰り返し、通話を切った。
私は大丈夫だ。倒れた原因を自覚している。体調不良じゃない。今も一切視線を向けないように努めている。パソコンデスクにあるノートパソコン。あれがどうなっているのか、とてもじゃないが確かめる勇気がなかった。
パソコンデスクに背を向けて視線を逸らし続け、とりあえず着替える。
洗面台に立つと、昨日落とせなかったメイクの上からメイク直しを吹きかけて整えた。
部屋の隅に蠢く気配は今は感じられない。それとも、昨夜の恐怖が他の小さな異変を鈍らせているのかもしれない。
次にリップも直そうとして、やめた。かわりにマスクをつける。身体の心配をしてくれたユキナのことだ、マスクのまま会っても何も言わないだろう。
すべての支度を十分以内に終わらせ、洗面室を出ようとして──しまったと思った。
リビングから洗面室へ向かうには、リビングを背にすればいい。だから気にしていなかった。
玄関へ向かうにはリビングを通らなければいけない。
当然、さっきとは逆の方向にすべてが向かうことになる。身体も、視線も。
即座に背けたが、それでも視界の端に捉えた。
昨夜私が設定した覚えのない壁紙を見せつけてきたノートパソコンは、何事もなかったかのように、静かに閉じていた。