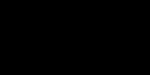家を出る前に閉じてきたはずだ。
少し潔癖なところがあるので、テレビのリモコンを置く場所さえもきちんと決めないと気持ちが悪い。
ノートパソコンの置き場も当然決まっていて、リビングの隅に置いたパソコンデスクの上が定位置だ。
そのはずなのに、開いている。
リビング手前で立ち尽くした私の視線はノートパソコンに集中した。目を逸らしたい。なのに、逸らせない。貼りついてしまったかのように、動かない。
私はこの次に起こることを知っている。
『リビングにあるデスクトップが立ちあがったんです』
脳裏に紗和の声が蘇った。
それと同時に、視線の先のノートパソコンの画面が白く光る。
『触るとか触ってないとかの話じゃないですよ』
また、紗和の声が、する。
でも違う。紗和の時とは違う。だって、彼女は電気が点かなかったと言っていた。
私の部屋は煌々とした灯りに照らされている。怖いはずがない。
明るい部屋で、閉じておいたはずのノートパソコンが開いていて、勝手に起動したくらいなんだというのだ。違う。
紗和の時とは、絶対に違う。誤作動かもしれない。
息を殺して、そっと足を動かした──動いた。ちゃんと動いた。
紗和は動けなくなったと言っていた。やっぱり違う。
前へ、パソコンデスクへ近づこうとする私の意志とは真逆に、足が動いた。
後ずさっている。どうして。わからない。確かめてやろうと思っているはずなのに、全身が拒否している。あれに近づいてはいけない。本能と言ってもいい。さっきまで聞こえていたはずの、外からの車の走行音が全く聞こえなくなった。耳までおかしくなったのだろうか。ドクドクという、自分の心臓の音しか聞こえない。うるさくて、他の音が何も聞こえない。
離れよう。このまま外へ出て玄関の鍵をかけ、隆介のマンションに行くのもいいかもしれない。快く迎えてはくれないだろうが、この部屋でひと晩過ごすよりずっとマシだ。早く家を出よう。
頭ではそう考えているのに、三歩後ずさったら動けなくなってしまった。
立ちあがったノートパソコンの画面に現れた壁紙。元は自分で撮った海外の風景写真を設定している。それが、勝手に、変わっていく。画面中央から渦が巻かれていく。吸い込まれるように壁紙が消えていく。
『目だけはデスクトップの画面から離れてくれない。見なきゃいいのに、視線すら自分の意志で動けなくなりました』
紗和の声がやんでくれない。
額から伝った汗が、顎から滴った。こんなに寒いのに汗をかいている。
今は特に空調を必要としない、過ごしやすい時期のはずだ。それなのに、寒い。背筋から凍っていくような寒さを感じている。でも、汗が止まらない。次に何が起きるのか、私は知っている。
『そして、設定した覚えのない壁紙が現れたんです』
風景写真が消え、真っ黒な画面が現れた。室内が反射され、ソファやテレビが映っている。
なんだやっぱり誤作動とか壊れたとかじゃないの、と、頭の隅で微かな希望が囁いた。
しかし、すぐに絶望に変わる。映りこんだソファやテレビが、私のものじゃない。──いや、私のものなのだろう。でも、違う。が、画面の中のソファはボロボロに破れ、テレビにヒビが入っている。あれは、私のものであって、私のものではない。
──ハァ。
大きな息が耳元に当たる。振り返ることができない。首も動かない。私の意識はすべて、ノートパソコンへ向かっている。まるでそれ以外許されていないかのように。
ブイイン、と濁った音がした。
ようやく瞬きをして──そして、見た。
大翔が言っていた。
『あれは目だった。人間の』
紗和が言っていた。
『最初は猫の目かと思ったけど、絶対違う。あれは人間の目です。イラストじゃない。本物の眼球に見えました』
その瞳が、ぎょろりと動いた。瞼のない眼球は暗闇に浮いているように自由に動き、瞼がないはずなのに目を細めたように見えた。
ひっ、と喉の奥で音がする。それが自分のものだと思った瞬間、私は意識を手放した。
少し潔癖なところがあるので、テレビのリモコンを置く場所さえもきちんと決めないと気持ちが悪い。
ノートパソコンの置き場も当然決まっていて、リビングの隅に置いたパソコンデスクの上が定位置だ。
そのはずなのに、開いている。
リビング手前で立ち尽くした私の視線はノートパソコンに集中した。目を逸らしたい。なのに、逸らせない。貼りついてしまったかのように、動かない。
私はこの次に起こることを知っている。
『リビングにあるデスクトップが立ちあがったんです』
脳裏に紗和の声が蘇った。
それと同時に、視線の先のノートパソコンの画面が白く光る。
『触るとか触ってないとかの話じゃないですよ』
また、紗和の声が、する。
でも違う。紗和の時とは違う。だって、彼女は電気が点かなかったと言っていた。
私の部屋は煌々とした灯りに照らされている。怖いはずがない。
明るい部屋で、閉じておいたはずのノートパソコンが開いていて、勝手に起動したくらいなんだというのだ。違う。
紗和の時とは、絶対に違う。誤作動かもしれない。
息を殺して、そっと足を動かした──動いた。ちゃんと動いた。
紗和は動けなくなったと言っていた。やっぱり違う。
前へ、パソコンデスクへ近づこうとする私の意志とは真逆に、足が動いた。
後ずさっている。どうして。わからない。確かめてやろうと思っているはずなのに、全身が拒否している。あれに近づいてはいけない。本能と言ってもいい。さっきまで聞こえていたはずの、外からの車の走行音が全く聞こえなくなった。耳までおかしくなったのだろうか。ドクドクという、自分の心臓の音しか聞こえない。うるさくて、他の音が何も聞こえない。
離れよう。このまま外へ出て玄関の鍵をかけ、隆介のマンションに行くのもいいかもしれない。快く迎えてはくれないだろうが、この部屋でひと晩過ごすよりずっとマシだ。早く家を出よう。
頭ではそう考えているのに、三歩後ずさったら動けなくなってしまった。
立ちあがったノートパソコンの画面に現れた壁紙。元は自分で撮った海外の風景写真を設定している。それが、勝手に、変わっていく。画面中央から渦が巻かれていく。吸い込まれるように壁紙が消えていく。
『目だけはデスクトップの画面から離れてくれない。見なきゃいいのに、視線すら自分の意志で動けなくなりました』
紗和の声がやんでくれない。
額から伝った汗が、顎から滴った。こんなに寒いのに汗をかいている。
今は特に空調を必要としない、過ごしやすい時期のはずだ。それなのに、寒い。背筋から凍っていくような寒さを感じている。でも、汗が止まらない。次に何が起きるのか、私は知っている。
『そして、設定した覚えのない壁紙が現れたんです』
風景写真が消え、真っ黒な画面が現れた。室内が反射され、ソファやテレビが映っている。
なんだやっぱり誤作動とか壊れたとかじゃないの、と、頭の隅で微かな希望が囁いた。
しかし、すぐに絶望に変わる。映りこんだソファやテレビが、私のものじゃない。──いや、私のものなのだろう。でも、違う。が、画面の中のソファはボロボロに破れ、テレビにヒビが入っている。あれは、私のものであって、私のものではない。
──ハァ。
大きな息が耳元に当たる。振り返ることができない。首も動かない。私の意識はすべて、ノートパソコンへ向かっている。まるでそれ以外許されていないかのように。
ブイイン、と濁った音がした。
ようやく瞬きをして──そして、見た。
大翔が言っていた。
『あれは目だった。人間の』
紗和が言っていた。
『最初は猫の目かと思ったけど、絶対違う。あれは人間の目です。イラストじゃない。本物の眼球に見えました』
その瞳が、ぎょろりと動いた。瞼のない眼球は暗闇に浮いているように自由に動き、瞼がないはずなのに目を細めたように見えた。
ひっ、と喉の奥で音がする。それが自分のものだと思った瞬間、私は意識を手放した。