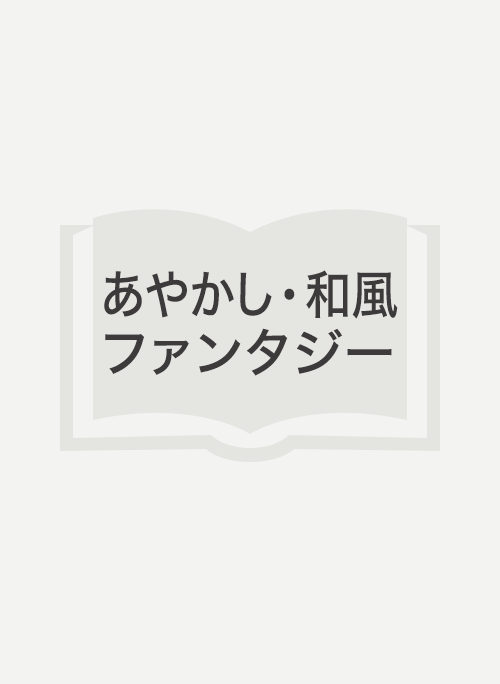この作家の他の作品
表紙を見る
「夢を渡って君に逢いに来た」
不遇な扱いを受けていた那美の目の前に現れたのは白龍の綺世。
ずっと夢見ていた相手が現れて嬉しいはずなのに心に思うのは戸惑いで……。
わたしは綺世さまに相応しくない──。
高貴なる白龍である彼の隣に立つ自信がなく、差し出された手をとれない那美。
「私は那美が良いのだ。他の誰でもなく」
優しい眼差しと言葉が凍てついた心を溶かしていく。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
落ちこぼれ狐の幸せな嫁入り
を読み込んでいます