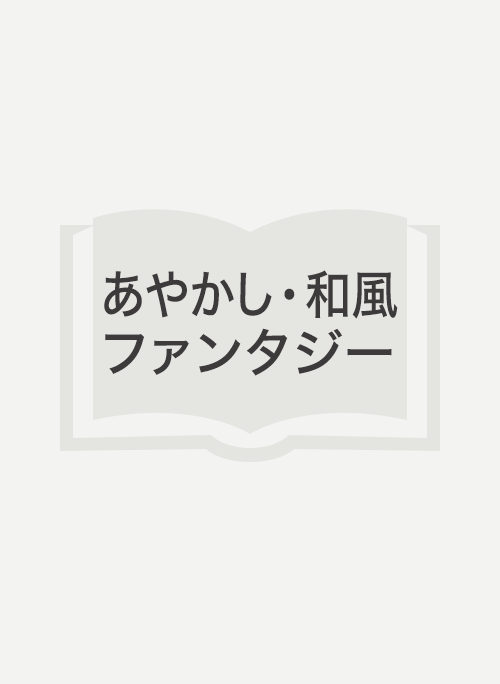「ありのままの君が素敵だと私は思うよ」
水園小夜はきっとこの言葉を一生、忘れることはない。
こんなにも優しくされたのはいつぶりだろう。
丁寧に記憶を辿っても思い出すことはない。
鮮明に残っているのは、憎ましそうに見つめる家族の視線と降りかかる罵倒だけ。
「お前がそんなふうになったのは、俺たちのせいではない。恨むなら自分を恨め」
脳内でこだまするのは、父の冷たく鋭い声色。
今さら言われずとも、何度も嘆き、恨んで、諦めた。
一族の落ちこぼれだと、恥だと、どれだけ蔑まれようとも、この運命は変えられないと。
これから訪れるどんな不条理にも従いながら、閉ざされた世界で生き続けていく、そう覚悟していたのに。
「君となら良い夫婦になれると思うんだ」
黒く染まった心を照らすような彼の花笑み、それが一欠片の希望に見えて、小夜は泣きたくなった。
「いつまで、そんな姿でいるつもりだ。早く人間へ変化せんか、この愚図が」
「……申し訳ありません。お父様」
額に青筋を立てながら睨みつけている男の視線の先には、一匹の狐が板張りの廊下に伏していた。
許可なく、顔を上げてしまえば、父の怒りを買ってしまうと知っている狐──水園小夜は微動だにせずに次の言葉を待っていた。
そう、彼女の本当の正体は空狐。
文明開化が目覚ましい、この時代。
より良い國づくりに尽力しているのは人間だけではない。
人間には有さない特別な霊力で古来から陰から國を支えているのは狐である。
全国各地に数多いた狐はいつしか帝都に移り住み、町を築き上げた。
和洋入り混じる華やかな帝都から離れた山手に集うのは由緒正しい狐たちの名家。
中でも、ひと際目を引くのは荘厳な門構えの、広大な木造平屋の屋敷。
そこに小夜の住まう場所、水園家だ。
狐たちには天帝より位が与えられている。
下から野狐、気狐、空狐、そして天狐。
他の追随を許さないほどの圧倒的な力を宿す天狐は生を受けた瞬間から最高位に君臨してきた。
天狐以外の狐も普通の人間から見れば神秘的な雰囲気を纏っているが、彼らはそれをはるかに上回る優美さを放っている。
現在、父親に蔑まれている小夜も二番目に位の高い空狐の一族。
本来ならば血の繋がった家族からこんな扱いを受けることはない。
「まさか、外でもこの姿になっていないだろうな?」
「そ、れは」
「人前で変化を解いてはならないと何度言えば分かる!この恥さらしめ!」
「ぐっ、うぅ……」
首根っこを乱暴に掴まれ、強引に上を向かされる。
暴力を受けるのは今日が初めてではなく、小夜にとって日常茶飯事だ。
(どうして、わたしだけ変化が出来ないの)
彼女は空狐の一族に生まれながらも、ろくに人間へ化けることが出来ない、いわゆる落ちこぼれである。
この国に住む狐は学校を卒業したあと、当主やその秘書、側近など特別な職務に就く者以外、町を出て働くのがしきたり。
人間に紛れながら暮らし、己に秘める霊力を行使してこの国を安寧へと導く、それが天帝より課せられた命令でもある。
狐は人間に化けられてこそ一人前。
位が高ければ高いほど、霊力も高く、才能の開花も早い。
天狐ならば、ほとんどの者が赤子の頃には可能らしい。
空狐でも物心がつく歳には大体が技を取得するのだが、小夜だけは違った。
驚いたり恐怖心を感じたりすると、変化が解けて狐へと戻ってしまうのだ。
徐々に首に伝わる強い力に耐えられなくなって、懇願するように父親を見た。
「も、申し訳ありま、せん。も……」
「ふん。謝罪など聞き飽きたわ。謝って上達すれば、どれだけ良いことか」
そこで、ようやく首から手が離れる。
ぼとりと音を立てながら、その場に倒れ込む。
ごほ、ごほと吐きそうなほどむせ、目から一筋の涙がこぼれる。
(……何か役に立ちたいと思っても、結局は駄目になる。わたしは空っぽね)
小夜よりも年下の子は皆、すでに力に目覚めているというのに十六歳にもなって、この調子ではもう希望など皆無だ。
それでもこんな自分でも存在価値を見出したいと、休日は仕事を見つけて働くが、ほとんど今のような結果になる。
「まったく、これから大事な客が来るというのに、手間をかけさせよって」
呼吸が落ち着いても、憤怒を露わにしている父親の顔を見るに見られない。
まるで殺されるのではないかと錯覚するほどの表情が呪いのように脳裏に焼きつくからだ。
今日は朝から水園家へ来客の予定があった為、忙しくしている使用人たちの代わりに花瓶の水を取り替えようとしたのだが、誤って手を滑らせて廊下に落としたのだ。
無惨にも美しく絵付けされた花瓶が割れ、辺りは水浸しになっている。
破片で出血はしていないが、こうなるのであれば怪我をしてでも身体を張って受け止めれば良かったと後悔する。
いつまで寝てる、起き上がらんかと罵声を浴びて、ようやくふらつきながら立つ。
ぽたり、ぽたりと雫が滴り落ち、雪色の毛並みが水を吸って重たい。
憂いを帯びた表情が水面に写るが、ギシギシと板張りの廊下を歩く音でハッと視線を上げる。
奥から現れた二人は散らばる破片、水に濡れた狐、腕を組んでそれを睨みつける父の光景を見て、すぐに状況を理解したようだった。
細く長い指を口の前に持ってきては、笑いを堪えるように声を押し殺している。
「ねぇ、小夜。自分が見向きもされないからってどれだけ私たち家族に構って欲しいの?」
「本当に。貴方が私の娘だなんて信じられない。水園家に生まれてくる子は一華だけで十分だったわ」
空虚に満ちた目に映るのは、二つ歳が離れた姉の一華、そして母の華織。
姉は妹とは見目が正反対で実年齢より、ずっと大人びていて名前の通りに華やかなで存在感を放つ。
背中まで伸びた長い髪は真っ直ぐで艶やか、肌は透明感のある肌で、小さな唇はほんのりとほどよい紅色。
(ああ、確か昨晩に新しくできたパーラーの話題に興じていたわね)
これから母とその場所へ行くのだろう、女学院用ではない、白椿の柄に瑠璃色の振袖を纏っている。
母もそこまで派手ではないが、何とも上品で落ち着いた小花柄の単衣を纏っていて、美しい彼女にたいそう似合っている。
小夜はそんな高価な振袖など持っていない。
人間の姿のときは使用人から譲り受けたお仕着せ服。
愛嬌もあり、器量良しの姉にのみ父から贈られたのだ。
まあ、羨ましいなどといった感情はとうの昔に忘れたが。
「一華は女学院で優秀な成績を修めているというのに、お前はいつまでも阿呆だ。水園家の唯一の汚点め」
(それは、わたしが一番よく分かっている)
家でも女学院でも姉と比べられ、陰で過ごしてきた小夜に今さら説教なんて、意味がない。
最初はまともに変化できない自分をここまで育て、学ばせてくれたことには感謝していた。
けれどそれは、別に小夜を大切に思って、というわけではない。
娘を女学院にも行かせない男だと世間から思われたくなかっただけだ。
だがもう比較されるのは慣れている。
今さら、この程度で口ごたえをする気も起きない。
しかし、黙り込む姿が逆に三人を苛立たせたようだった。
「貴方、本当に目障りなのよ!才能も無い、仕事もろくにできないなんて生きる価値などないわ!」
「お前は本来ならば即刻、捨てられるはずなのだぞ」
「周囲の目もあるから、最大限生かせてあげているだけ。感謝しなさい」
「は、い」
たった二文字を発するのが限界だった。
三人の目を見ないで返事をしてしまえば、再び怒りを買うのは知っている。
ただ、心が疲弊していた彼女は、叩かれても暴言を浴びても、どれでも良かったのだ。
「お前──」
小夜の態度を見て、予想通りに父が怒鳴ろうとした瞬間に「あ!」と、それを一華が遮る。
「お母さま、もうそろそろ屋敷を出た方が良いのでは?開店時間に間に合わなくなっちゃう。食べたい物、数量が限られているんですって。売り切れたら大変よ」
「あら、もうそんな時間?いけない、こんな娘に時間を割いている暇はないわね」
「私がよく叱っておくから、二人は行ってきなさい」
「はい、お父さま」
一華と母は小夜と打って変わって物欲がかなり凄い。
一華が話していた「食べたい物」というのは、おそらく雑誌に掲載していた品だろう。
帝都のモガたちの流行をいち早く取り入れるのが、どうやら、欠かせないらしい。
とにかく目立ち、その上、何をしても優秀。
それもあって、一華は女学院のマドンナだ。
大輪の牡丹が咲いたように笑みを浮かべ、返事をすると、二人は軽い足取りで玄関へと向かって行った。
何やら楽しげに会話をしている彼女たちの後ろ姿は皆が憧れるような理想の親子の光景だ。
小夜だって正真正銘、母、華織から生まれた娘だ。
あんな風に横に並んで買い物へ行く権利もある。
(……駄目よ、水園小夜。もう夢を見ない、何も望まないと決めたじゃない。思いを巡らせるだけ虚しいもの)
遠くに玄関で草履に履き替えて、明るい外へと出て行く二人。
光に満ちた外と暗く閉ざされた屋敷。
まるで初めから住む世界が違うよう。
ぴしゃりと戸が閉められて、辺りに静寂に包まれる。
二人に向けられていた父の穏やかな視線が鋭いものに変わり、小夜へと移された。
「私の知人の娘は天狐の一族の息子に見初められて、来年に結婚するんだぞ。お前のような落ちこぼれなど存在するだけで恥ずかしくてかなわんわ。少しは見習ったらどうだ」
「はい」
「空狐の娘が人間に殺されたとなれば、我が水園家の名に泥を塗ることになる。まあ、これ以上無様な姿を世間に見せるのであれば、私とて考えがある。この意味が分かるな?」
「……っ」
脅迫にも感じ取れる問いかけに、ひゅっと息を吸い込んだ。
分かっている、誰からも愛されていないことなど。
けれど、想像していたよりもずっと自分の命を軽く見られていたのだと改めて思い知らされる。
(仮に女学院を卒業出来たとしても、この町の外で暮らしていける自信はないわ。嘘をつきながら毎日を過ごすだなんて、わたしなんかに務まるはずがない)
狐が化けて人間たちに紛れながら生きているのは当然、秘匿である。
小夜らが通う女学院があるように、町を離れる者は、しっかりと訓練を受ける義務がある。
(もし、人間に正体がばれてしまったら)
殺される。
帝都で暮らす狐は年に一度、町に帰り、成果などを報告する義務がある。
それに反すれば、罰が下るとあって、ほとんどが義務の果たしているのだ。
そう、ほとんどということは全員ではない。
身分を偽ったまま人間と恋に落ちて駆け落ちする者、自らに背負った重責から逃れようと仕事を放棄し、帝都からいなくなった者……。
毎年、少なからず、そういった事案が確認される。
たとえ逃亡したとしても、狐の妖力があれば居場所など特定出来るので無駄だというのに己の欲望にはどうやら勝てないらしい。
違反者は、直ちに捕らえられ、罰として幽閉される。
それだけ、狐の妖力がこの國にとって欠けてはならない大切なものなのだ。
しかし、探し出せる力があったとしても稀に居場所を突き止められないこともある。
すなわち、その者の死を示す。
人間の姿のまま事件や事故に巻き込まれる場合、誤って狐の姿を見られ、殺される場合など多種多様だ。
優秀な狐でも、怖ろしく悲しい結末を迎える。
それなのに、狐の中で一番といっていいほどの落ちこぼれが仕事を全う出来るはずがない。
「お前が死ぬか否かは卒業試験にかかっている。卒業も出来ない娘など、この家にいらんわ。それが嫌なら完璧な変化を習得するんだな」
(きっとお父さまなら、わたしを殺して、あたかも自害したかのように見せることも可能。……ああ、でもいっそそれも良いかもしれない。生きていても幸せな未来など待っていないもの)
俯いたまま、輝きを失った目でぼんやりと濡れた廊下の木目を見つめる。
身体を濡らし、一方的に怒られても、水園家には誰も小夜を助ける者はいない。
家族だけでなく、屋敷で働く使用人もそうだ。
幼い頃は両親に理不尽に暴言を吐かれ、使用人たちに泣きついたこともあった。
全員ではなくても一人だけでも味方になってほしかったのだ。
しかし、使用人たちは小夜に優しくすれば両親の怒りを買い、解雇になることを怖れたため、無視をし始めた。
最初は物音や怒号に一度はこちらの様子伺うように見ていた使用人たちも今は何事もなかったように仕事を再開していた。
もう何年も、つらさや悲しさを他人に伝えたことはない。
すべての感情は、外に流れることなく、心に溜まっていく。
きっと他の家の娘は、友人と恋愛の話に花を咲かせて、休日にはパーラーや観劇に行き、夜には温かい布団で眠りにつく。
世間にとっては普通なことでも、小夜には夢のよう。
「旦那さま。間もなく、お客様がいらっしゃるお時間でございます」
白髪を綺麗に結った使用人頭が廊下の奥から姿を現し、報告をしたところでハッと我に返る。
色々なことが重なって、すっかり忘れてしまっていた。
今日はこのあと、父の大事な客人が訪問する予定があるのだ。
玄関に近い廊下は小夜が手を滑らせて割ってしまった花瓶の破片がまだ散らばっている。
それに加え、水で廊下を濡らしているので早く片付けをしないと予定時刻になってしまう。
小夜はまだ狐の姿のままである。
この姿では時間までに片付けを済ますなど、限りなく不可能だ。
しかし、この状況を招いてしまった責任がある。
早く人間の姿に化けて、散乱した破片を集めないとと思えば思うほど焦りが募る。
身体に妖力を集中させることを意識しながら、慌てて口を開く。
「あっ。ではわたし、ここの片付けを──」
「余計な手出しはするな!鈍いお前にやらせたら、間に合わん。片付けは使用人たちに任せる。お前は客人が来ている間は部屋から一歩も出るな」
「……はい」
ここで下がらなければ、また苛つかせるのは目に見えている。
素直に従った方が良いとすぐに察して大人しく待つ。
頷く小夜を見て、父はまだ何か言いたそうにしたいたが、フンッと鼻を鳴らして背を向けた。
傍に控えていた使用人頭にちらりと視線をやり、ここはお前たちに任せた、と言い残すと廊下の奥へ消えて行った。
「かしこまりました」
「あの。わたしのせいで、ごめんな──」
「貴方たち!手が空いている者は今すぐこちらへ!」
小夜の謝罪の声も使用人頭の屋敷中に響き渡るような呼びかけの声に掻き消される。
すると数名の使用人が箒や雑巾などを手にして足早にこちらへ来ると、片付けを始める。
まるで、小夜がいないかのように辺りを動くので、これ以上邪魔をせず、迷惑をかけないよう、そっとその場を離れるのだった。
自室へ戻ってきた小夜は前足で襖を開けて中へと入る。
ここは水園家の屋敷の、奥まった場所にある。
文机と箪笥、籠しか置いてない殺風景さは、他人から見れば令嬢の部屋とは思えないだろう。
小夜は部屋の隅に置いてある籠から一枚の手ぬぐいを取り出す。
人の手のように綺麗には拭けないが、このままでは風邪をひいてしまう。
(体調を崩して女学院を休んだら、またお父さまたちに叱られる)
ある程度拭いたところで、文机の前に敷いてある座布団の上に座る。
(実技は苦手だけれど、筆記は頑張らないと。だけど、この姿だと勉強も出来ないわ)
今はただの文机でも身体より大きく見えて、教科書さえも見られない。
仮に届いたとしても、この手では雑記帳も開けず、筆記用具も握れない。
(わたしは本当に情けないわ)
今は父は客人をもてなしていて、姉と母は買い物中。
静かに勉強が出来る良い機会なのに、自分の不甲斐なさで時間を無駄にしていると自覚してしまう。
小夜は町の一角に門を構える五年制高等女学校──鈴風女学院に通っている。
狐のみが通えることができ、周辺には、妖力が込められている特別な結界が張られており、人間にはその目で確認することは不可能だ。
まだ昼前だが、連日の寝不足のせいで、ドッと疲労感と眠気が小夜を襲う。
(いけない、休んでいる暇はないわ。早く人間の姿に変化しないと。皆の用事が終わって尚このままだったら、次は何をされるか──)
変化が苦手な分、筆記は頑張っているのだが、知識だけでは一人前になれない。
小夜は妖力が少ないうえ、臆病だ。
人間の姿のままで順調に過ごせていても、苦手な虫や雷が原因で変化が解けてしまう。
しまいには、自分自身の影が幽霊に見えてしまい、驚いたはずみに狐に戻ったことも。
このままではいけないとわかっている。
空狐の一族の長の家である水園家に生まれたからには娘としての役目を果たしたい。
女学院を卒業した者は、帝都に赴くという選択肢の他に、狐の一族の当主や側近の花嫁になれる場合もある。
過去に抱いた「いつかは華やかな帝都で働いてみたい」「花嫁となって幸せな家庭を築きたい」といった夢は叶わなくても良いし、見てもいない。
ふと、鳥のさえずりが聞こえ、外へ視線を向ける。
空には青空が広がり、白い雲がゆったりと流れている。
小夜の心情とは正反対のような輝きを放った光景。
(今頃、お姉さまたちはお買い物を楽しんでいるかしら)
小夜は女学院へ登校する以外は、自由な外出は認められていない。
ほとんど、水園家という鳥籠に囚われているような状態だ。
(将来、この家を継ぐのはお兄さま。お姉さまは花嫁になる。そうしたら、わたしの居場所が完全に無くなってしまうわ)
小夜と一華には歳の離れた兄がいる。
現在は、洋行していて仕事をしながら様々な勉強をしているらしい。
伝統を重んじつつ、革新を取り入れ、この町をさらに発展させるのが狙いのようだ。
数年前から洋行している兄は、多忙を極めているため、年に一度、帰国出来るかどうか否かというぐらいだ。
兄も他の家族と同様に小夜を嫌っている。
先ほどの三人のように、直接虐めるのではなく、完全に無視をするのだ。
まるで、小夜が存在しないかのように。
妖力に恵まれなかった妹を受け入れなかったのだ。
逆に、優秀で愛嬌をたっぷり振りまく一華のことは溺愛している。
愛するあまり将来、彼女が帝都で働くことに頑固として反対している。
まあ、一華も嫁ぐことを望んでいるので問題はないのだが、兄は相手を慎重に選びたいようだ。
妹を一生かけて守り抜き、幸せにすると誓える者ではなければ、絶対認めないと言うほど。
前回、兄が帰国した際に屋敷で小夜を除いた四人が、広間でたいそう賑やかに話をしているのを耳にした。
一華は過保護で溺愛してくる兄に少し困ったような素振りを見せていたが、それくらい大切に思ってくれているのだと嬉しそうにもしていた。
実際、彼女は女学生の身でありながら、いくつか縁談の話は届いていた。
しかし、時期当主である兄から慎重に選ぶよう頼まれている父は、定めた基準を越えなければ、すべて断っていた。
女学院のマドンナでもある一華に、その魅力に惹きつけられるように男性は近づいてくるが、ある一族のみ、姿を現したことはなかった。
狐たちの最高位に君臨する、気高き一族──。
(天狐さま。あの御方はまだお姉さまに縁談を申し込んでいない)
天狐の一族の当主、七条時雨。
二十五歳という若さで当主の座に就いた彼は、絶世の美男。
狐たちは全員が眉目秀麗だが、時雨は群を抜いており、代々受け継いだ神にも等しい妖力をその身体に宿している。
限られた人間しか会うことは出来ず、情報も噂で聞くのがほとんど。
「今にも消えてしまいそうな儚い雰囲気を纏った御方」だとか「背筋が震えるほどの冷酷無慈悲な御方」などと耳にするので、本当に実在するのかと疑ってしまう。
落ちこぼれである小夜は当然、会ったことはない。
(今までも、そしてこれからもお会いすることなんてないけれど。もし七条さまとお姉さまが結婚するとなっても、わたしはきっと屋敷で留守番ね)
結婚式を欠席する理由なんて、父たちならいくらでも作ってしまう。
家柄も妖力も問題がなく、魅力溢れる彼と女学院一のマドンナである姉なら、きっと誰もが羨む夫婦になれる。
実際、姉の一華も七条家からの縁談を待って、他の男からの誘いを断っている様子。
そこで、「縁談」という言葉に、小夜はふと同級生たちの会話を思い出す。
(でも、名家の令嬢が七条家から縁談を申し込まれても即日、破談になっているみたい)
一見、引く手あまたのように見える時雨でも、何故かなかなか順調に婚約者が決まらないらしい。
欠点すら見当たらないような完璧な淑女でも、時雨の方から断っているという噂が女学院内で持ちきりだ。
つい先日も、一人の令嬢との縁談が破談になったそうなので、時期に水園家に話が持ちかけられるだろう。
もちろん、一華宛てに。
(破談になるのはとても不思議だけれど、きっと七条さまにも理由やお考えがあるのよね)
一切関係のない小夜がいくら考え、悩んでも意味はない。
天地がひっくり返ったとしても、落ちこぼれ宛てに縁談なんてこないのだから。
俯いていた視線を上げ、身体中に僅かな妖力を巡らせる。
いつまでも、こんな姿のわけにはいかない。
姉と母が帰ってくれば、仕事を押しつけられる可能性もある。
二人はいつも「貴方はどんなに頑張っても、どうせ落ちこぼれのままなのだから、勉強なんてしても無駄よ」などと言って、掃除や洗濯をさせる。
使用人もいるのだが、小夜にやらせるために、わざと仕事を残しているのだ。
貴重な一人の時間をこれ以上失いたくはない。
(人間の姿になって──)
強く祈りながら、爪の先まで妖力を行き届かせる。
身体を小刻みに震わせて、一筋の汗が流れたとき、ぽんっという軽い音が鳴る。
ふわりとした煙が小夜を包んで、数秒でゆっくりと消えていく。
「出来た、かしら……?」
おそるおそる目を開けると近くに置いてある姿見へと視線を向ける。
「……はぁ」
姿見に写った自分を見て、心底残念がるため息が漏れた。
長い雪色の髪に白い肌、細い指はどう見ても人間だが、落ち込む原因は二つある。
「耳と尻尾が残ったままだわ……」
頭にはぴくりと動く耳とお尻からはふわりと揺れる尻尾。
つまり、変化には失敗したということだ。
この状況を誰にも見られていないのが不幸中の幸いである。
父たちに見られれば、こっぴどく叱られ、女学院の試験でこの姿ならば即、落第だ。
複雑な感情になりながら、人差し指と中指で耳を二回目ほど触る。
(耳と尻尾が残っているのが気になるけれど、勉強が出来ないわけではないから)
もう一度、変化に挑戦しようかと思ったが、妖力も少なく、身体も弱い小夜にとって、かなり気力も体力も消耗するので、断念する。
生まれつき病弱な上、食事もろくに与えられていないので、変化の練習に励んでも長時間は保たないのが現状だ。
首許や手首が痩せ細っているのを見て、これ以上周囲に怪しまれないように、調理場にある残り物を集めて食べている。
一日に一食でも食べられれば良い方。
何も口に出来ない日が圧倒的に多いのだ。
もし、まともに食べられていれば、他の娘と大差ない身体になっただろう。
(少しでも口にしないとお父さまに怒られるから)
以前、帝都で働く父の友人が町に帰り、小夜を見かけた際、明らかに細すぎる彼女を心配して連絡をしてきたのだ。
もちろん、父は「食事を与えていない」とは絶対に言わない。
(筆記試験がどれだけ良い成績でもお父さまは認めてくださらない。でも今、わたしに出来ることを頑張らないと。区切りがついたら、また変化の練習をしなくちゃ)
外は晴天に恵まれているというのに、日があまり当たらない部屋のせいで、室内は薄暗い。
沈みそうな気持ちを振り払いながら、小夜は教科書と雑記帳を開くのだった。
大小、様々な大きさの穴が空いた障子から差し込む光を薄らと感じて、ゆっくりと瞼を開ける。
中綿が減った布団は、軽く、そして薄い。
掛けても掛けなくても同じようなものだ。
本来ならば、起床には、かなり早い時刻。
眠気と倦怠感を感じながらも、奮い立たせて上体を起こす。
(早く起きないとお母さまに怒られるわ)
水園家は使用人が朝食を準備してくれるが、母の命令で小夜も調理場に立たなくてはいけない。
しかも、使用人たちが来る前に、ある程度、仕込みなど調理の準備をしなくてはならないので、まだ空は若干暗い。
その決まりを破ってしまえば、罰が与えられるので、時間に遅れるわけにはいかないのだ。
夜遅くまで、変化の練習をしていたので、すこぶる体調が悪く、足元がおぼつかない。
小夜のように名家生まれで妖力が少ないのは稀有だ。
(どうにかして妖力を高める方法を見つけないと)
女学院の図書室で様々な本を見ては試しているが、上手くいかない。
妖力が高い者でも、さらなる力を求めて、あらゆる手段を選んでいるらしい。
(一番、有効的なのは妖力が高い狐の血を分け与えてもらうことらしいけれど、わたしは無理ね)
空狐の一族の長である水園家は定期的に会合に参加しているので、天狐たちとも繋がりはある。
もし、一華がもっと妖力が欲しいとねだれば、父は天狐へ願いを乞うかもしれない。
(お父さまたちがわたしに血を分けてくれるはずがないし、何か別の方法を探らないと)
何度目か分からないため息をついて、押し入れへ布団をしまうと、箪笥から着替えを取り出す。
お仕着せ服で作業をした方が汚れる心配がないのだが、今のうちに着替えておかないと登校に間に合わなくなってしまう。
片付けもやりなさいと母から言いつけられているので仕方ない。
わざと遅刻寸前にさせるように仕組んでいることを小夜は知っていた。
そうならないよう、てきぱきと手を動かし、身支度を始める。
家の裏の流しで顔を洗い、薄く化粧を施す。
菖蒲柄の単衣に学校指定な行燈袴を身に纏う。
そして髪をまとめ、控えめな飾りが付いた留め具を付ければ完成だ。
教科書と雑記帳、筆記用具を鞄に入れて文机に置くと割烹着を持って台所へ向かった。
(良かった、何とか間に合いそう)
学院から少し離れた場所で自動車を降り、小夜は歩き出す。
周囲には、小夜と同じく歩いて登校したり、自転車を走らせたりする女学生が多くいた。
その光景を見て、自分は遅刻をしていないのだと理解して胸を撫で下ろす。
遅刻や欠席などしてしまえば、さらに評価が下がってしまう。
たださえ、同級生や教師からも、良くは思われていないのだから。
すると、小夜の後ろから横を小走りで追い越していく生徒がいた。
前方に歩いていた一人の浅緑色の単衣を纏った女学生の元へ一直線に駆けていく。
「ごきげんよう、瑠璃子さん」
「あら、ごきげんよう。梢さん」
あのふたりは確か隣の学級の生徒だ。
時折、休み時間に小夜の学級へ来ては友人と会話に興じているのを見たことがある。
梢さんと呼ばれた生徒が足を止めた瑠璃子の隣へ並ぶと早速仲睦まじそうに話し始める。
「ねえ、瑠璃子さん。その単衣は新しく買ったの? 初めて見るわ。とても素敵ね」
確かに浅緑色の単衣は爽やかで可愛らしく、近くを歩いている女学生たちも気になるのか、ちらりと視線を向けている。
「ありがとう。定期試験で良い成績を修めたら買ってもらう、それがお父さまとの約束だったから」
「羨ましいわ。わたしも今度、お願いしてみようかしら」
きらきらと輝く眼差しに見つめられ、瑠璃子は照れたように頬をほんのりと染めた。
そして二人は、ふふっと何やら楽しそうに会話をしながら、後方を足取り重く歩く小夜を置いて先へ行った。
(今までで、お父さまから貰った物といえば、この単衣だけ)
ふと視線を横に動かすと、近くの建物の硝子に自分の姿が映った。
この単衣は父からの贈り物。
落ちこぼれでも、身なりだけは水園家の名前に恥じないようにと、昔から贔屓にしている呉服屋に仕立ててもらったのだ。
今も覚えている、父が珍しく自分の書斎に呼び出した日のことを。
「お前に、上等な単衣を贈るなんて金の無駄だ」と言って顔をしかめながら、しぶしぶといった様子で箱に入った単衣を小夜に渡したのだ。
まだ女学院に入学する前の遠き記憶。
その時はすでに、家族から落ちこぼれ扱いを受けていたが、それでも小夜は純粋に嬉しかった。
蔑まれても見向きもされなくても、少しでも自分のことを考えてくれたのだと。
正直、兄姉や母は小夜の物よりもさらに最上級な着物などを貰っている。
安くてもいい、もう何も買ってもらわなくてもいい、そう思うほど幼いながらに舞い上がっていたのかもしれない。
小走りで自室に戻り、箱を開けて目に飛び込んできた菖蒲柄の単衣。
可愛らしく、気品溢れる美しさに魅了され、何度も鏡で確認をした。
これから先、もっと酷い仕打ちをされることも知らずに。
(結局、入学しても緊張したり怖い思いをすると変化が頻繁に解けて皆から笑われたわ)
落ちこぼれ扱いは家だけでなく、女学院でも。
妖力も少ない上、暗い性格はマドンナの姉とよく比較されている。
周囲から浴びる冷ややかな視線と口元を抑えながら嘲笑う同級生。
授業中はまだ良い。
皆の意識は教師や黒板に向いているから。
休み時間など、小夜にとって憩いの時間ではない。
お弁当が準備出来た日は屋上の隅で食べている。
元々、賑やかな場所は苦手なので、ひとりの方が気が楽なのも事実だ。
落ちこぼれから脱却出来ると思って志し高く門をくぐった鈴風女学院も今となっては苦痛である。
(今日は実技の授業もあるし、憂鬱だわ。遅くまで練習したけれど、あまり上手く出来なかったし)
ぼんやりと見つめていた鏡から踵を返し、女学院まで歩を進めていく。
「小夜ちゃん、おはよう」
背後から快活な声で名前を呼ばれて、足を止めて振り返る。
そこには、路肩に停車した自動車から降りてきた、ひとりの女学生、緒方凛がいた。
肩まで伸びた琥珀色の髪と珊瑚色の単衣姿は華やかで人々の注目を集める。
そんな彼女は片手を挙げて、何度も振りながらこちらへ小走りでやって来る。
落ちこぼれに自ら声をかける者などいないので、彼女の通る声に気づいて、登校していた女学生たちが、ぎょっとした瞳で凛を見ている。
「緒方さん……。おはようございます」
「もう。同学年なんだから、そんなにかしこまらないでって言っているじゃない」
眉を八の字にして苦笑する凛に小夜は出来る限り口角を上げようと励んだ。
彼女は隣の学級の生徒で、入学式の日に校舎内で迷子になっていた小夜を助けてくれたのだ。
周囲と馴染めず、何かとひとりでいるのを気にかけてくれている心優しい生徒。
「ですが、父から礼儀作法は忘れないよう、きつく言われていますので……」
「小夜ちゃんは本当に真面目ね」
違う。
凛との間に線を引いている一番の理由は、関係のない彼女を傷つけないようにするため。
ただでさえ、挨拶をして軽く会話をするだけでも、「落ちこぼれの友人」と凛も悪く言われるのだ。
一線を引くのは心苦しいが、これ以上彼女への風評被害も避けたい。
「もしかして、話しかけるのって迷惑?」
「い、いえ……!迷惑なんかじゃないです。いつも緒方さんに優しくしていただけで嬉しいです」
「それなら良かった。私が話しかけると、肩をびくって震わせるから怖がらせてるのかなって」
「違います。ただ、少し驚いただけで」
「あら、そうなの?もっと早く気がつけば良かった。ごめんなさい」
凛は口元に片手を添えて申し訳なさそうに眉を八の字にさせた。
普段から明るい彼女の謝罪に小夜は慌てて首を横に振った。
「そんな、謝らないでください。わたしが臆病すぎるんです」
「でも、よく私、声が大きいって言われるの。今度から気をつけるわ」
「緒方さんは、何も悪くないです。無理に治さなくてもいいと、わたしは思います」
凛の眩しい太陽のような笑顔と声は彼女の宝物。
それが人を傷つけているわけではないのに、無くしたり、変えたりするのは間違いだ。
その想いを込めて、訴えかけるように、真っ直ぐに見つめた。
小夜の真剣な眼差しに凛は僅かに目を見開いたあと、細めて微笑んだ。
「小夜ちゃん……。ありがとう、実はずっと悩んでいたことだったの。背中を押してもらったようで気持ちが晴れたわ」
「わたしなんかがお力になれるなんて、嬉しいです」
今出来る精一杯の笑顔をはりつけて、言葉を返す。
(……ああ。わたしにもっと妖力があれば、落ちこぼれではなければ、緒方さんともっと仲良くなれたのに)
いつも顔に血の気がなく、周りと話を合わせることさえできずに、ただ勉学にのみ打ち込んでいる小夜など、凛と大違いだ。
何かと気にかけてくれる同級生。
何度か友人になりたいと言ってくれたこともあったが、今日まで曖昧にしたまま。
友人になったとしても、自由な外出は禁止されているので、休日はパーラーも観劇も一緒に行けない。
休み時間でさえ、自分なんかと関われば凛にも悪影響になってしまう。
誘ってくれて、ありがたくはあったけれど、それも小夜には無理な相談だった。
(本当に申し訳ないわ)
ばつの悪い思いを抱え、小夜は荷物が入った鞄を持つ手に、力を加えた。
誰にも水園家での内情を知られないように、隠し通すのも心が痛む。
そんな暗い影を落とした表情を凛は見逃さなかった。
「ねえ、小夜ちゃん。何か悩みがあるんじゃない?私で良ければ話、聞くわよ」
「えっ、あの……」
どきりと心臓が鳴った。
図星をつかれ、慌てて視線を逸らす。
これでは、悩みがあると言っているようなものだ。
しかし、流石に「家で家族から虐げられている」などと言えるはずがない。
その秘密を他人に明かしてしまえば、必ず相手も巻き込んでしまう。
一度、静かに深呼吸をすると、くるりと凛へと向き直る。
「ご心配ありがとうございます。でも、わたしは大丈夫です」
「そんな風には見え──」
「何かあったときは、すぐに緒方さんに相談させてください」
普段の小夜なら、他人の話を遮るような真似はしない。
しかしこれ以上、追及されては本当に口を滑らせてしまうような気がした。
安心させるように、しっかりと笑みを浮かべる。
(ごめんなさい、緒方さん)
自分が落ちこぼれでいる限り、いや、たとえ最底辺から脱却しても、この秘密を明かすことはないだろう。
寄り添ってくれるひとがすぐ近くにいるというのに、壁をつくる。
こんなに悲しく、つらいことはない。
これで、嫌われてしまうかもしれない。
それでも、凛や緒方家にまで迷惑をかけるわけにはいかなかった。
凛は気狐の一族、緒方家の娘。
位で見ると空狐より下に値する。
小夜はどちらが上で下かなんて考えないが、両親や兄姉は違う。
水園家は何百年も前から権勢を振るう。
立場をわきまえない者は、容赦なく制裁を下してきたのを、小夜は知っている。
優しい凛のことだ。
小夜が虐げられていると知れば、彼女の性格から考えて、屋敷に乗り込んできても、何ら可笑しくない。
もし、それが現実となれば、凛は女学院に通えなくなり、緒方家は終わりだ。
(駄目、絶対に駄目。そんなことになれば、わたしは後悔する)
立ち止まり、黙り込む小夜に凛は一度、目を伏せて、そして微笑んだ。
「分かったわ。私、待ってる」
切れ長の瞳を細めて、笑いかけている表情は、たいそう美しく、眩しかった。
(わたしが落ちこぼれでなければ)
他者の目を気にせずに堂々とおしゃべり出来たらどれだけ良いだろう。
一緒に買い物だってしてみたい。
だが家族はそれを決して許さない。
小夜は重たい気持ちを抱えながら、今出来る精一杯の笑みをつくった。
「ありがとうございます」
「いいのよ。もし、小夜ちゃんに何かあったら、わたしは笑って過ごせないと思うの」
何故か、同級生というより、妹に見えるのよねと言いながら再び歩き出す。
凛には三人の兄がいる。
男子が多い環境で育ったからか、お嬢さま学校の鈴風女学院では珍しい、砕けた口調だ。
校風を損なうから直すようにと教師や上級生から注意を受けているのを見たことがある。
小夜はまったく嫌悪感を抱かない。
出逢った当初は、多少驚いたけれど、不思議とすぐに馴染んだ。
耳に届く、凛の声と、近くの木に止まる小鳥たちのさえずり、そして穏やかな風の音。
(家のことは忘れて、ずっと聞いていたくなるわ)
小夜は凛の他愛のない話を聞きながら、鈴風女学院の正門を通る。
聞き手に徹しながらでも忘れない。
周辺には数多くの生徒が校舎を目指しているので、凛に迷惑がかからないよう、距離をあけることを。
女学院の敷地は広大で、規則的に敷かれている石畳、その両側にある色彩豊かな花壇などがあり、そして一番に存在感を放つのは、噴水。
昼休みには、噴水近くの長椅子に座ってお弁当を食べる生徒も多い。
以前、凛にもその場所で一緒にお弁当を、と誘われたが、丁寧に断った。
色とりどりの鮮やかな花の乙女たちが、かしましくおしゃべりに興じている空間に、耐えられる自信はないから。
「あら、誰かと思えば落ちこぼれ狐さんがいるわ」
昇降口までの長い道を歩いていると、背後から和やかな雰囲気を壊すような声が聞こえ、思わず足を止めた。
すでに、その声の主に気がついている小夜は、ひゅっと息を吸い込むと、ゆっくりと振り返る。
マガレイトに結われている艶のある黒髪にぷるりとした紅色の唇、唐紅色の単衣と学校指定の行燈袴を身に纏っている少女を見た瞬間、小夜に緊張が走った。
「……寺石さま」
名前を呼ばれた娘──寺石舞子は、まるで獲物を狙うかのような鋭いまなざしを小夜に向ける。
彼女は小夜と同じ、空狐の一族の娘。
寺石家は水園家に次いで、権勢を振るっている家であり、舞子はその家の長女。
姉の一華と比べても見劣りしないほどの美貌を兼ね備えており、成績も優秀。
空狐の筆頭の家に生まれながらも、妖力をほとんど有さない小夜を昔から馬鹿にしているのだ。
普通ならば、位が上であるはずの小夜を虐めているとなれば、舞子は周囲から咎められるはず。
だが、よく一華が「あんな落ちこぼれが妹だなんて恥ずかしくてたまりませんわ」とか「皆さんも、あの子に対しては立場などわきまえなくて結構ですよ」などと言うので、堂々と行われている。
それが、実の家族に対する言葉なのか、一令嬢として恥ずべきことではないかと誰も問わない。
それだけ、水園家は敵に回したくない怖ろしい家なのだ。
「よく、女学院に通い続けることが出来ますね。私だったら、惨めになって、堂々と登校なんて無理ですわ」
「本当に一華さまと同じ血が流れているのかと疑ってしまいますね」
舞子の両隣には彼女と一華を敬愛する生徒ふたり。
品定めでもするかのように、馬鹿にするかのように、小夜を見ている。
近くを歩く生徒たちも、ちらりとこちらの様子を伺っていて、今すぐに逃げたくなった。
でも、彼女たちが言っていることは正論で反論も逃げ出す勇気もない。
矢継ぎ早に発せられる凶器の言葉が胸を深々と抉る。
「あの、ごめんなさ──」
小夜は何も悪いことなどしていない。
謝る必要も、陰で生きる必要もないけれど、そうしなければと頭が勝手に命令するのだ。
今もこうして、攻められているのは、自分が未熟だから。
謝罪することで、この瞬間だけでも許されるかもしれない。
しかし、頭を下げた瞬間、目の前に誰かが立ったのが分かった。
「貴方たちこそ、弱い者虐めをして、いつまでも幼稚じゃない。そんな性格、早く直した方が良いわよ」
庇うように立ち、彼女たちに向かい合う凛に小夜は、ぱっと顔を上げる。
(……緒方さんを巻き込むことだけは避けたかったのに)
味方がいるという嬉しさの反面、彼女が傷つかないか、迷惑をかけないかと冷や汗が出た。
相手は空狐、凛は気狐。
舞子からしてみれば、位が下の凛が自分に逆らってくるなんて、腸が煮えくりかえるだろう。
凛と小夜は学級が違うので、いつも守れるわけではない。
しかし、こうして舞子たちと会うと、必ずといっていいほど、喧嘩を始めるのだ。
しかし、力強くはっきりとした口調に対して、臆することなく負けじと舞子も言い返す。
その表情は、背筋が凍るほど、品が良く優美だ。
「あら、私は事実を申したまで。緒方さんは、もう少し令嬢らしく振る舞ったらいかが?」
「舞子さま。それはきっと無理ですわ」
「ええ。気狐には、これが精一杯ですから」
「それも、そうね」
「……何ですって?」
彼女たちの間にバチバチと音が鳴るような火花が散っている。
「あの方たち大丈夫かしら?」
「先生を呼んできます?」
こそこそと話す声に気づき、視線を向けると、事情をよく知らない下級生が不安げにこちらを見ていた。
(先生たちが来てしまったら、まずいわ)
女学院から家に連絡がきてしまえば、父は憤慨する。
声を荒げて叱って、そして殴られる。
凛だって、手は出されないだろうけれど、きっと、こっぴどく怒られるはずだ。
凛と舞子が喧嘩して、舞子が両親に言いつければ寺石家から緒方家へ、抗議の知らせがゆく。
小夜もそれを心配して、問いかけても彼女は首を横に振るだけだった。
〈私は大丈夫よ。困っている友人を守ることがいけない、なんてあったら、たまらないわ〉
自身の名前のように凜々しく、そして正義感に満ちる表情が脳裏に浮かぶ。
凛も一華や舞子に劣らず、成績優秀だ。
無事に卒業出来れば、帝都で辣腕を振るって働くことも、嫁いで幸せな花嫁にもなれる。
数年後には輝かしい未来が待っている。
そこに傷などつけたくはない。
これ以上、騒ぎが大きくなる前に止めなければと、小夜は慌てて凛の腕を掴んだ。
「緒方さん、わたしは大丈夫ですから……!」
「駄目よ、小夜ちゃん。今日こそはぎゃふんと言わせないと」
その瞳には炎のように熱い闘志が宿っていて、相変わらず、舞子を睨みつけたままだ。
「ふふっ。冗談はよしてくださいな。貴方なんか到底、私たちに及びませんし」
「なんかってなによ!」
刺のある口調にさらに苛立ちが募ったのか、声を張り上げる。
遠目からだが、こちらの様子を伺う人数も増えてきた。
焦りが募り、腕を掴む力を少しだけ強めた。
もちろん痛みは感じないように。
「お願い、お願いします」
「……っ!」
か細く、震える声に凛は、はっと我に返って、斜め後ろにいる小夜へと視線を向けた。
それと同時に周囲の人数に気づいたようだ。
「ご、ごめんなさい!私、ついカッとなっちゃって……」
申し訳なさそうに謝る凛に小夜は何度も首を横に振った。
「いえ……!わたしのために怒ってくれた。それだけで十分嬉しかったですから」
その言葉とは裏腹にいつもより笑みが弱々しい。
そして若干、呼吸も乱れている。
「小夜ちゃん、もしかして具合悪い?」
舞子に向けられていた怒りの眼差しは、すっかり消えて、いつも通りの穏やかさに戻っている。
「わたしは──」
大丈夫、そう言おうとした矢先、ぽんっという軽い音と共に身体を煙が包んだ。
その場にいる誰もが、理解した。
変化の術が解けて、元の狐へと姿が戻ったのだと。
案の定、煙が霧散すると、小夜は人間から狐になっていた。
「ふ、ふふっ!」
「あはは!」
「本当に愉快だわ……!」
舞子たちは雪色の狐を見るやいなや、可笑しそうに笑い始めた。
登校中の生徒も、くすくすと笑う者、引いている者、反応は様々で、小夜に重くのしかかる。
授業前で、術が解けるのは、かなりまずいことだった。
妖力がそこそこある普通の者ならば、ある程度は自由に操れるので問題はないが、小夜の場合は違う。
再度、人間に化けることに時間をかなり要するため、下校後ならまだしも、朝に起こってしまえば授業にも影響してしまうのだ。
特に今日は一限目から筆記の授業なので、早く人間の姿にならなければ、受けられないし、教師にもたしなめられる。
荷物が入った鞄も地面に落ちていて、この手では持つことすらままならない。
羞恥心と悔しさと悲しさが心に一気に押し寄せる。
もうこのまま消えてしまえたら、どれだけ良いか。
泣いてしまいたくなる。
(いや、わたしに泣く資格なんてない)
どれだけ虐げられても笑われても、こんな身体に生まれてきてしまった運命を受け入れるしかないのだ。
目を固く閉じて俯いていると、ふわりと浮遊感を感じた。
一瞬、何が起きたのかと驚いて目を開くと、凛が真剣な面持ちで身体を抱き上げてくれていた。
地面に落ちていた鞄も持っていてくれている。
「もうこんな人たちと関わることはないわ。行きましょ、小夜ちゃん」
「……あ」
それだけ言うと凛は足早に校舎へ歩き出す。
まだ後ろでは、「逃げたわ」「私たちに怖じ気づいたのよ」と何やら話し声が聞こえたが、勝ち気な凛も無視をしていた。
昇降口に着いて、そっと降ろしてくれた彼女に小夜は丁寧に頭を下げる。
「あの、緒方さん。連れてきてくれてありがとうございます」
「いいのよ。元はといえば、私があの人たちの挑発にのってしまったのもあるし。荷物、教室まで運ぶわね」
「そこまでしていただくわけには……」
「いいわよ、これくらい。私たちの教室、隣なんだから一緒に行きましょうよ」
にっこりと笑い、下足から上履きの草履に履き替えると歩き出した。
きっと彼女なりに、強引になったくらいの方が控えめな小夜には良いのだと思ったのかもしれない。
そんなことを考えているうちに凛はどんどん先を行く。
教科書などが入った重い鞄を小夜の分に加え、自身の物も持っているのだ。
本人が大丈夫といっても、こちらが気にしてしまう。
普段から家で甘えることを許されていないので余計に申し訳なくなる。
おろおろと立ち尽くしていると、少しずつ昇降口に生徒がやって来る。
「ま、待ってください……!」
小夜は慌てて階段を上がり始める彼女を追いかけた──。
「時雨さま。少々よろしいでしょうか」
「うん。どうぞ」
ひとりの男が襖の外から声をかけ、中にいた相手からの返事を確認すると、ゆっくりと開けた。
「……また婚約者候補についての書類を持ってきたのかい?」
時雨と呼ばれた男──七条時雨は部屋に入ってきた従者、六木律と彼が手にしている書類の束を交互に見つめ、訝しげに目を細めた。
「また、とは何です。せっかく用意した縁談を次々と破棄にしているのは、紛れもなく時雨さま、貴方ですよ?」
律は淡々と答えながら、不服そうな表情の時雨に書類を手渡す。
それを受け取ると、仕方なさそうに目を通し、適当にめくっていく。
きちんと火熨斗の当てられた三つ揃いのスーツに身を包んでいる律は時雨からふたり分ほどの距離をとって座った。
一通り見終え、嘆息をする。
そして文机にバサリと書類の束を置くと、頬杖をついた。
「僕はしばらく結婚などしないと言っているだろう」
「時雨さま、ご自身が現在おいくつかお解りになられていますか?」
「馬鹿にしないで。僕は二十五歳だよ」
「先代が二十五歳の頃にはすでに奥さまは身籠もっておられましたよ」
「父上と母上は仲の良い幼なじみだったんだ。事が進むのが早くて当然だよ」
「ですが、そろそろ時雨さまも結婚をして子を成しませんと。のんびりし過ぎはいけません。七条家の当主として自覚を──」
「はい、はい。分かったよ。婚約者候補に会えば良いんだろう?」
「投げやりになっていませんか?」
「なってない」
即答すると再度、書類の束を手にする。
律は時雨が縁談の話に耳を傾けてくれそうな雰囲気に安堵する。
「次はどこの一族の令嬢?」
やや気怠げだが、完全に関心をもたないよりはマシだ。
今は彼の態度については目を瞑る。
「五頁に載っています、空狐の一族の水園一華嬢はいかがでしょうか」
「水園家、ねぇ」
「天狐の令嬢たちに問題はなかったのですが、すべて時雨さまが断ってしまったので、空狐から選出しました」
「あの娘たちの欠点が分からないなんて律はまだまだだね」
「え?事前にこちらで調査しましたが、申し分ない令嬢ばかりだったはず……」
「そうだね、表面は」
「表面、ですか?」
ああ、と言うと目を伏せながら余裕のある笑みを浮かべた。
「美しく輝く表面だけ見ても駄目だよ。そのさらに奥まで見ないと」
「……肝に銘じておきます」
きっと時雨の言葉の真意を理解したわけではない。
しかし、生真面目な性格の彼らしい返事に、これ以上、諭すのはやめた。
何気なく、六頁目をめくると再び、水園という苗字が目に入ってきた。
婚約者候補関連の書類で同じ苗字が続いていることは過去になかったので、見間違いかと五頁と比べてみる。
「あれ、六頁目に載っている娘って水園一華の妹?」
「はい、妹です。……ですが時雨さま。彼女だけは遠慮なされた方がよろしいかと」
「どうしてだい?」
律は時雨の問いかけに視線を逸らして逡巡した後、言葉を選ぶようにして答えた。
「水園小夜は生まれつき、妖力をほとんど有しておりません。すぐに術が解けてしまう、落ちこぼれであると有名です。一応、形式として書類を準備しましたが……。そのような娘と時雨さまがつり合うわけがございません」
「やけに断定的だね。能力がすべてではないと思うけれど」
「私の親戚が彼女と同じ鈴風女学院に通っていますが、あろうことか毎日のように狐の姿に戻っていると聞きました。時雨さまもご存知でしょう。我々、狐は人間に化けられてこそ一人前。空狐でありながら、その様では花嫁として認められません」
律は昔から真面目で、あまり融通の利く性格ではないが、ここまで意見するのは珍しい。
嘘やいい加減を良しとしない彼が言っているのだ、確かな情報なのだろう。
時雨は黙りながら、じっと小夜について書かれている書類を見つめる。
そこには、他の令嬢と比べると圧倒的に情報が少ない。
名前、年齢、住所、在籍している学校名、そして妖力が僅かであるということのみ。
特筆すべき点がないことに何故か興味を惹かれた。
(この娘に会ったら何が変わるだろうか)
先ほど「結婚はしばらくしない」と言ったが、本心は違う。
七条家に足を運ぶ令嬢は皆、偽りの仮面を被っている。
部屋に来た律を見て、きっと、また破棄になる縁談をよこしてきたのだと嫌気が差したのだ。
時雨はずっと待ち望んでいた。
容姿も財力も地位も目的ではない、心か自分を愛して安らぎとなってくれる花嫁を。
「では、次の縁談の相手は水園一華嬢でよろしいですか?」
まるで決定事項のように同意を求める律に首を横に振った。
「いや、妹の方だ」
「え?」
「水園家の次女──水園小夜を呼んでくれ」
「時雨さま、御冗談はやめてください」
「冗談なんかじゃない。僕は本気だよ」
時雨の態度はどこまでも真摯で、その瞳から偽りは感じられなかった。
あらゆる決定権を握っている彼の判断が過去に間違っていたことはない。
それでも、無能に近い娘を天狐の妻にさせるなど、あってはならないと本能が律に告げていた。
「悪いことは言いません。彼女だけは、やめてください」
普段から柔らかいとは言い難い律の口調は、このときはさらに頑として、ひどく堅かった。
「やめないよ。もちろん、会ってみて違うと思えば縁談は白紙に戻す。見合いくらい良いだろう?」
「ですが、もしも──」
時雨が彼女を正式な婚約者に選んでしまったら。
その不安が過り、律はすぐには頷くことは出来ない。
天狐の当主の一言が、判断が、この國の未来を左右するといっても過言ではない。
「心配はありがたく受け取っておく。それでも、どうか私の願いも聞いてはくれないだろうか」
「……やはり賛成出来ません。大切な主だから、私もここまで言うのです。考え直してくださいませ」
「私もこの七条家に生まれたときから、この國を安寧へと導く責務を背負っている。それは何があろうとも死を迎えるまで貫き通す。その人生を共に歩む大切な花嫁は自分で決めたい」
「それなら、尚更。落ちこぼれと縁談する時間など無駄です。結婚相手にふさわしい好条件は一華嬢の方です。彼女と会ってください」
「そこまで言うなら君が結婚したらいい」
「そういう話ではなくて──」
「律、私も君に怒りたくはないんだよ」
「……っ」
時雨は普段、しっかりとしつつも、どこかのんびりとしている一面があって、めったに怒らない。
しかし、一瞬だけいつもの穏やかで温かさに満ちた瞳の色が、鬼気迫るような赤色へと変わった。
「これが一回目だ。これでも抑えているつもりだったのだけれど……。いやはや私もまだまだ未熟だ」
はっ、はっと笑うが、その声も乾いている。
目もどこか憂いを帯びていて、その様子に律は口を噤んだ。
先ほどまで白熱していた言い合いも一気に萎み、部屋はしんと静まり返る。
少しの沈黙の後、先に口を開いたのは律だった。
「……かしこまりました。水園小夜との縁談を進めます」
仕方ないとでもいうような口調だが、それを気にしないほど嬉しかったのか、時雨の表情に笑みが戻る。
「ありがとう。よろしく頼んだよ」
「はい」
「ああ、それと」
失礼致しますと言い、お辞儀をして、部屋を出て行こうとする律を時雨は引き止める。
「念のため、今日一日は私の部屋には誰も近づけさせないで」
「しかし、お食事などは……」
「一日くらい大丈夫。天狐はやわじゃないって同じ一族の律も十分知っているだろう。それに三回目を迎えたら、もっと大変だから」
「承知しました。ですが決してご無理はなさらないでください」
「うん。分かったよ」
律はもう一度、丁寧に腰を曲げると今度こそ部屋を出て行った。
襖がぱたりと閉まると、時雨はふっと息を吐き出す。
そして、手にしている書類に印字されている、次の婚約者候補の名前を見つめた。
(水園小夜……一体どんな娘だろう。私の秘密を知ったら逃げ出すだろうか。それとも……)
心に募るのは好奇心と微かな恐怖心。
まだ見ぬ娘に思いを馳せながら、そっと目を閉じるのだった。
◆
女学院での騒ぎから数日後。
小春日和の休日、朝食を済ませた小夜は、中庭の掃き掃除をしていた。
(今日は残り物があって良かったわ。昨夜は何も食べられなかったから)
めったに食事が残ることはないが、先日、新しく料理人に雇われたひとりが誤って作りすぎたらしい。
ひとり分もなかったが、白米とほうれん草の胡麻和えを口にすることが出来た。
起床してから、抜けない疲労と空腹で、ふらついていたので、多少でも力になる。
そのまま部屋で休めば、さらに体力も回復したはずだが、家族はそれを良しとしない。
居間で使用済みの食器を片づけていると、母から中庭の掃除を命じられたのだ。
朝から働くことは日常茶飯事なので、別に嫌だとか逃げたいとか思わない。
仮に反抗心が生まれても、もちろん拒否権などないので、命じられたことを粛々とこなすだけだ。
季節は春といっても、雲一つない青空から降り注ぐ陽射しは容赦なく小夜の体力を奪っていく。
額に浮かんだ汗をお仕着せ服の袖で拭いながら、顔を上げて澄み渡る空を憎らしげに見つめる。
ふと、ひらりと数枚の桜の花びらが舞って、地面に落ちた。
爽やかな風のせいで、見頃の満開の桜の木から一枚、また一枚と花びらが離れていく。
掃除しきれていない箇所はそれらが重なっていて、ふわりと山になっている。
(いけない。手を動かさないと)
今日は買い物好きな母も姉も珍しく屋敷にいるのだ。
ぼうっとしていたら叱られるし、中庭の掃除が済んでも、きっとまた他の仕事を与えるはずである。
隅から掃いて、花びらや諸々の落葉を中心に集めていく。
「小夜さま」
集めたものを風で吹き飛ばされないうちに、ちり取りで回収しようとした矢先、声がかかる。
顔を上げて視線を向けると声の主は使用人頭の秋江だった。
彼女は中庭に面した廊下に凛とした佇まいで立っている。
一切、ほつれのないお仕着せ服にきっちりとまとめた白髪の髪、感情が読めないような目。
小夜は昔から秋江が苦手だ。
虐げられているわけではないけれど、母や姉とはまた違った怖さを感じるから。
冷たく厳しい眼差しはいつまで経っても慣れることなく、自然と背筋が伸びる。
「は、はい。何でしょう」
震え、上擦る声で、小夜はやっとそれだけ呟く。
秋江は一切、表情を変えずに、薄い唇を開いた。
「旦那さまがお呼びです。今すぐ居間へ来るようにと」
「お父さまが……?」
もしかして、先日の騒ぎが教師の耳に届いて、女学院から連絡が来たのだろうか。
父がこうして使用人を通じて呼び出すことは稀にあった。
そんなときは決まって叱られているので、今回もおそらく同じはずである。
様々な憶測が過り、恐怖と緊張で胸がどきりと鳴った。
「奥さまと一華さまもお待ちです。急いでください」
「え……」
何故、ふたりもいるのだろう。
叱られるのであれば、本人だけで十分なはずだ。
偶然、近くにいたり、通りがかったりすれば嘲笑われることはあっても、わざわざ待ち構えていることは一度もない。
考えを巡らせて理由を探るが、納得する答えまで辿り着かない。
「小夜さま」
青白い顔で立ち尽くす小夜に秋江は苛立ちを募らせたように、声を張って屋敷の中へ来るように促す。
「あ、はい……!今行きます」
我に返った小夜は、手にしていた箒を外壁に立て掛け、ちり取りをその場に置くと、下足を脱いで廊下へと上がる。
こちらを待たずに、先を行く秋江を急いで追う。
小夜は彼女に続いて板張りの廊下を足早に歩く。
居間の前に着くと、秋江は他の使用人に呼ばれ、何も言わずに去って行った。
返事は期待していなかったが、ありがとうございます、とだけ去りゆく背中に伝える。
聞こえるように、はっきりと言ったが、当然のごとく、無視をされる。
秋江も父に命じられて、仕方なく小夜を呼びに来たのだろうと大体は予想がつく。
無視をされることなど、日常茶飯事なので特につらくはない。
慣れてしまっているのが異常なのだけれど。
秋江が廊下の角を曲がって姿が消えたのを確認すると、襖へと向き直る。
「お父さま、小夜です」
「入れ」
「……失礼いたします」
襖を開けると両親、姉の鋭い視線が一斉に突き刺さる。
「ひとをこれだけ待たせておいて、貴方はいつから、そんなに偉くなったの?」
「せっかくの休日なんだから。早くそのとろい性格を直しなさいよ」
「申し訳ありません」
一瞬でも呼び出しの理由など考えず、すぐさま駆けつければ、彼らを待たせなかった?
いや、秋江からの言伝を聞いて、走って向かったとしても、おそらく今のような態度だろう。
「小夜、そこに座れ」
「はい」
父は座卓の前ではなく、襖のすぐ近く、隅に座るよう、視線だけで指示した。
そこは、普段、使用人が座る位置。
元々、座布団も小夜の分を抜いた、三枚しか置いていなかったので、ある程度は予想していた。
私たちとお前は違うんだ。
家族の輪から外されている、娘として認められていない、そんな疎外感をひしひしと感じながらも従順な返事をする。
小夜が座ると、一華が痺れを切らしたように口を開いた。
「お父さま、大事な話ってなんですの?」
(大事な話?わたしのことを叱るんじゃないの?)
てっきり、叱責されるのだと思っていた小夜は、呆気にとられる。
とはいえ、まだ油断は出来ないが。
でも確かに、わざわざ姉や母を呼んでまで小夜に時間を割かないだろう。
(……お父さま?)
小夜はふと違和感を覚える。
普段から威厳を放つ父が、一華の問いかけにすぐには答えず、困惑したように眉を下げ、顎に片手を添えているのだ。
こんな姿を見せるのは珍しい、いや初めてかもしれない。
普段は三人の笑い声で賑やかな居間も、沈黙と不穏な空気が流れている。
「貴方?」
呼びかける母の声もどこか不安げである。
そこでようやく、逡巡するように目を閉じていた父は、開くと一華と母を見つめながら話し始めた。
「……ああ。実は七条家からうちに縁談の申し入れがあった」
「まあ!わたくしに縁談が?夢みたい!」
「おめでとう、一華!娘が天狐さまの花嫁になるなんて、わたくし鼻が高いわ」
覚悟はしていた。
七条家から一華宛に話が舞い込むのは時間の問題だと。
けれど、これほど急とは思わず、心臓がずきりと鳴った。
元々、この家に居場所などなかったけれど、一華が嫁いだとしたら。
小夜を妹として認識していない兄が当主の座を引き継いだら。
この状況になってわかる。
水園家の名前のおかげでいかに自分が守られてきたか。
(わたしは、どうしたらいいの)
目の前が真っ暗で到底、先のことを考える余裕すらない。
膝の上に置いている手のひらをぎゅっと固く握る。
視線の先には、幸せと喜びを噛みしめているひとたちがいるというのに、部屋の隅で小さくなっている自分は惨めにも思えた。
祝福しようにも、彼女らはきっと望んではいないだろうし、おめでとう、とたった一言を言う勇気すらない。
父からの報告に、一華は頬を赤く染め、満面の笑みを浮かべながら、母と抱き合っている。
時雨との縁談を喜ばないはずがない。
きっと、いや絶対に一華は本当の自分を隠して、立派な淑女を演じるだろう。
時雨は舞台役者も真っ青な美男子だという噂を耳にする。
すべてがうまくいけば、手に入る。
美貌を兼ね備えた麗しい旦那さまも、狐たちの頂点に立つ地位も余るほどの財の山も。
それをみすみす逃すわけがない。
そう思っていた。
次の言葉を聞くまでは。
「一華ではない」
父の一言に冷めやらぬ興奮に包まれていた居間は一気に凪いだ。
一華と母は甲高い話し声を徐々に萎める。
「貴方。今、何とおっしゃいました?」
母が上座へ座る父へとおそるおそるといった様子で視線を向ける。
もしかしたら聞き間違いかもしれない、そう願っているようにも見えた。
ただ、どう見ても先ほどから父の表情は苦虫をかみつぶしたように見えて、一華を祝っているようには思えない。
「時雨さまの縁談の相手は──小夜、お前だ」
「……え」
唖然としたままの驚愕したふたりの双眸が小夜へと向けられる。
どういうことなのか、いったい何が起きているのか。
これだけの情報では理解に苦しむ。
「お父さま、何かの間違いでは……!?」
「なぜ一華ではなく、小夜なのです!」
座卓に両手をついて身を乗り出しながら、声を荒げるふたり。
「私も七条家に長女の一華の間違いではないかと何度も尋ねた。しかし七条さまが小夜を望んでいると……」
(望んでいる? わたしを?)
誰かに必要とされるような価値などない。
落ちこぼれだということは、天下の七条家も周知のはず。
彼らの貴重な時間を割いてまで、縁談を行う意味は何なのだろう。
小夜は驚きと困惑で何度も目を瞬かせた。
「どうして会ったこともない娘を七条さまは求めるの!?」
唇をわななかせ、一華は必死の形相で小夜を睨んでくる。
結婚相手に好条件である男性との縁談をすべて断り、一途に待ち続けていた彼女の想いを一瞬で砕けさせてしまった。
「私にもそこまでの理由はわからん。ただ、落ちこぼれ宛とはいえ、七条家からの縁談を断るわけにはいかん」
「でも……!」
「安心しなさい、一華。七条さまもこいつと会えば一目でわかる。花嫁にふさわしくないと」
父は低く、渋い声で激怒する一華を宥めつつ、一方で動揺する小夜を一瞥した。
それに、はっと微かに息を吐き出すと、何かを考えこむようにして、目を閉じる。
数秒後、開いた目からは、怒りや嫉妬といった感情は読み取れない。
冷静さを取り戻したのがわかった。
「……そ、そうよね。落ちこぼれなんか選ばれるはずがないもの」
ゆっくりと深呼吸をすると、完全に落ち着きを取り戻して、座り直る。
母はそんな彼女の肩に手を置くと、優しく励ますように声をかけた。
「きっと、その次は一華よ。大丈夫、すぐに貴方宛に話がくるわ」
「ええ、お母さま」
「小夜」
「縁談は二日後だ。必ず赴くこと、いいな?まあ、お前には拒否権など、最初から無いのだから聞くまででもないが」
「は、はい」
「破談前提とはいえ、七条さまとお会いするのだ。水園家の顔に泥を塗るような真似は絶対にするなよ」
顔に泥を塗るような真似──つまり、術が解けること。
父が念を押すのも無理はない。
何せ、ここ最近は毎日のように人間の姿から、狐へと戻ってしまっているから。
ただ破談になるだけならまだ良い。
もし、時雨の前でへまをすれば、水園家の評判もガタ落ちだ。
天狐の前で狐になるなんて前代未聞。
それだけは何とかして避けなければ。
「お前は器量もないのだし、相手が七条家でなければ、こちら側から断っていた。見合いだけでもできることに感謝しろ。いいか、くれぐれも無礼な振る舞いはするなよ」
「かしこまりました」
畳の上に両手をつき、頭を下げる。
きっと、数分だけだ。
孤高の天狐である縁談の相手と会う想像をするだけで酷く震えるけれど挨拶だけ、済ませればすべてが終わる。
そう呑気に考えることが今の小夜の限界だった。
破談になったそれから先のことはわからない。
幸せな未来が訪れることはないと確定して、ただ愕然とするしかできなかった。
「話は以上だ。お前は仕事に戻れ」
「はい」
あまり頭が働かない中、返事をして立ち上がると、居間から出た。
早く掃除を再開しなければならないのに、足に鉛を付けたかのような感覚に陥り、前へと進めない。
(まさか、わたしに縁談がくるなんて)
あの水園家の令嬢ということで一華には、以前からいくつもの縁談が舞い込んでいた。
しかし、落ちこぼれで名前を知られていた小夜に、結婚の話などきたこともない。
人生で初めての縁談が七条時雨である。
彼の役職は知っているが、どのような性格の男までは、ほとんど知らない。
数多くの縁談を破談にしているというぐらいしか。
(そんなに冷酷無慈悲な方なのかしら。お父さまは七条さまに会ってもわたしには何も話してくれないから、わからないわ)
小夜の父で、空狐の一族の長である水園家の当主、高志郎。
彼は定期的に開かれている狐たちの会合に参加している。
そこには、もちろん天狐の一族の長、七条時雨も参加していて、父とは面識があった。
いつも父が会合から帰宅すると、一華は、時雨の話を聞きたいと強請る。
一華に甘い父は仕方ないと言いながら、彼女と母には様子を話していた。
家族との団欒にさえ、加わることを許されていない小夜は、和やかな光景を横目に仕事をするのが常である。
(噂程度くらいしか知らないけど、類い稀なる美貌の持ち主なのよね)
舞台役者も真っ青の美貌ということもあって、一華と同様、時雨との縁談を望んでいる令嬢も多いと聞く。
そこで、ふと女学院、令嬢という単語で、ある不安が押し寄せる。
見合いの前に懸念すべき点が一つあった。
(寺石さまたちは、どう思われるのかしら)
頭に思い浮かんだのは、日頃から小夜を嘲笑う同級生らの顔。
たださえ、色恋沙汰は瞬く間に女学院内に広がるというのに、落ちこぼれだと馬鹿にしていた娘が七条家の当主と縁談すると知ったら、どのような反応をするのだろう。
一華だって、両親の宥めがあってようやく落ち着いたというのに、最低でも同じくらいは嫉妬するはず。
縁談まではあと二日。
今日は女学院側の都合で休校だったが、明日からは通常授業だ。
宥める者が不在での登校は考えるだけでも恐ろしい。
(でも、わたしもどうにもできないの)
これは、父のいや、七条家からの申し出だ。
小夜の気持ちなど関係ない。
ただ頷いて、命令に従うだけ。
時雨を想う令嬢たちを差し置いて、こんな考えのまま七条家へ赴くのは心苦しい。
どれだけ、嫌味を言われようとも、嫌がらせを受けようとも、判断を覆すことはない。
(覚悟して数日は過ごさないと。破談になれば多少は平気になるはずよ)
手のひらをぎゅっと握り、廊下の角を曲がろうとしたとき、母の高い話し声が聞こえた。
「ねえ、一華。頂き物の和菓子があるの。帝都にある老舗の朝霧屋の塩大福よ」
「あの朝霧屋……!?女学院で、どの和菓子も美味しいって話題になっていたから、一度食べてみたいと思っていたの!」
「では、使用人に茶を用意させよう」
父が居間から出てくる気配を感じて、慌てて廊下の角に隠れる。
隠れる必要などないのに、身体が勝手に動いてしまう。
「おい。三人分の茶を用意しろ」
「かしこまりました。すぐにお持ちいたします」
どうやら、居間を出てすぐの場所に使用人が歩いていたようで、声をかけると、父は再び妻と娘の元へ戻っていく。
(どうして、わたしは)
父から逃れ、胸を撫で下ろす自分に違和感を感じる。
家族から見放され、こちらからも距離をとっている娘が本当に水園家の名を名乗って良いのだろうか。
そう疑念を抱いても、何も変えられないし変わらない。
立ち止まって考えていると、カタカタと窓に風が吹きつける音で我に返る。
(いけない。早く掃除の続きをしないと)
風が強くなっては寄せ集めた落葉も舞って、綺麗にした中庭が台無しだ。
小夜は頭の中の靄を無理矢理、消すように両手で頬を軽く叩いた。
中庭へ歩き出す足は相変わらず重かった。
けれど仕事を放棄するわけにはいかないと、小夜は懸命に動かしたのだった。
「ここで降ります。ありがとうございます」
小夜は、いつもより正門から遠く離れた場所で運転手に声をかけ、自動車から降りた。
春の午前中らしい、ひやりと爽やかな風が吹くが、気持ちよさを感じる余裕は生まれなかった。
代わりに眠気に襲われて、片目を二回ほど擦る。
(結局、縁談のことが気になって、あまり眠れなかったわ)
七条家からの縁談の知らせを聞いてから一晩が経過した。
日中だけでなく、日が暮れ、布団に入っても、疑問や動揺、恐怖心が消えることなく、脳内にこびりついていた。
覚悟は決めているつもりだが、どうやら完璧には拭えていないらしい。
不安も的中して、登校する女学生たちの刺すような視線が痛い。
どこからか情報が漏れ、約一日で噂が広まったのだろう。
自転車を漕いで傍を通り過ぎる者、送迎の自動車から降りる者、全員と言っていいほどの人がこちらを見ている。
(……ごめんなさい。わたしなんか七条さまにお目にかかる資格なんてないのはわかっているの)
本人でさえ、状況をろくに理解できず、困惑しているのだ。
たとえそれを口にしても自慢にしか聞こえないだろう。
普段よりもぐっと目線を下げて、足早に校舎を目指す。
(あと少しの辛抱よ、水園小夜)
休み時間は注目されるだろうけど、授業が始まってしまえば、多少は皆の意識も逸らされるはず。
白紙になる明日まで、嫉妬と妬みから耐える、それだけだ。
最終的には鞄を抱え、小走りで昇降口まで向かう。
息を切らしながら何とかして到着した小夜は下足から中履きの草履に履き替える。
体力がない自分に嫌気が差しながら、廊下を歩き始めたとき、階段近くから、ある人物が姿を現した。
「ごきげんよう、水園さん」
「……寺石さま」
同級生の寺石舞子がまるで小夜を待ち構えていたように、立っている。
いつもと変わらないつんと済ました顔と堂々とした立ち居振る舞いなのに、それが何故か怖ろしく感じた。
今朝はほぼ毎日、彼女の両隣に控え、慕っているふたりの生徒はどうやら不在のようだ。
怯えて、立ち尽くす小夜を、舞子はキッと鋭いまなざしで射抜いてくる。
「貴方宛てに七条家から縁談の申し出があったそうですね」
「は、はい……」
小夜が一番驚いたのは、姉の一華のように憤怒の感情を表に出していないことだ。
予想外の展開に立ち尽くすことしかできないでいる。
こくりと頷くと、舞子は小さく鼻を鳴らした。
「さぞかし嬉しいでしょう。何といってもお相手は天狐の当主さまですから」
「あ、の。わたしも縁談の話は昨日、聞いたばかりで。嬉しいというより、戸惑っている気持ちの方が──」
「何よ、それ」
「……っ」
突如として語気を強めた舞子に小夜はびくりと肩を振るわせた。
まずい。
きっと『嬉しいというより戸惑っている』という言葉が彼女の逆鱗に触れたのだ。
正直に気持ちを明かしてしまった自分がとてつもなく阿呆に思える。
曖昧のまま、流せばよかったと後悔するが、すでに遅い。
けれど。
誤魔化されるような相手でも、自分自身に特別な話術がないのは承知している。
人形のような美しい顔立ちが、くしゃりと悔しそうに歪められた。
「天狐さまとの縁談なんて、とても幸運なことなのよ!それも七条家からなんて、名家の娘でも一生に一度あるかどうかなんだから!それが貴方はなに? 嬉しいより戸惑い? どれだけわがままなのよ!」
(違う、違うの)
心の中で精いっぱいの否定をしても、当然彼女に届くことはない。
舞子は小夜が家族から公にできないほど、虐げられていることを知らない。
多少は蔑まれていると勘づいてはいるだろうが。
だからといって、間違って口にしてしまえば大問題になるだろう。
はたまた、小夜の言うことなど誰も信じず、聞く耳をもたないか、どちらかだ。
ただ命令通りに従い、息をするだけ。
想像を絶する苦しい生活。
理解してほしいとまでは言わない。
自分は、孤独に抱え続けなければいけない運命を背負っているのだから。
何の反論も意思表示もしない小夜にさらに苛立ちが増したように唇を噛んだ。
「だんまりだなんて、余計にたちが悪いわ。……まあ、でも夢を見られるのも今のうちね。貴方が七条さまに見初められるはずなんてないもの」
にやりと口角を上げて、目を細める姿は余裕を感じさせる。
そのとき、コツコツと靴音が廊下に反響して聞こえた。
誰かが降りてくるのだろう。
階段から足音が聞こえ、舞子はそちらを一瞥すると、視線をまた戻した。
「貴方の縁談が終われば、次は一華さまやわたくしの番なんだから」
そう言い残すと、舞子はその場を離れていった。
「水園さんが七条さまと縁談?何かの間違いでは?」
「いいえ。わたくしも先ほど聞きましたわ。明日、お見合いのようです」
声を潜めて会話する声が聞こえ、視線を向けると数名の生徒がこちらを影から見ていた。
野次馬が現れるのも、あんなに大きな声量を出せば当然だろう。
その視線たちから逃れるように、教室へ向かう。
(何を言われても動じないって決めたじゃない。明日のために少しでも、わたしにできることをしないと)
仮にも小夜は水園家の令嬢。
父の言いつけ通り、縁談が破棄になろうが、立ち居振る舞いは完璧でいなくてはならない。
尻込みする気持ちを鼓舞して、目線を僅かに上げたのだった。
◆
翌日、ついに見合いの日を迎えた。
外はあいにくの天気で曇天が広がっている。
風はやや強く、木々を揺らしていた。
『わたくしに感謝しなさい』
昨夜、そう言いながら箱に入った振袖を一華に手渡されたのを思い出す。
小夜は女学院に着ていく単衣と学校指定の行燈袴、そしてお下がりのお仕着せ服しか持っていない。
その為、見合いに着ていく振袖を一華に借りたのだ。
父に頼まれて最初は嫌がっていたが、新作の化粧品を買ってもらうという約束で、しぶしぶ許可した。
借りたのは、白の牡丹がよく映える朱色の振袖。
新品にも見えるこの振袖はどうやら、捨てる予定だったらしい。
数回着ただけなのに、次々に買ってもらうものばかり選んでいたら箪笥の奥に眠っていたようだ。
しかし、身に纏う本人が首許も手首を痩せ細っていて、華やかな着物は似合っていない。
血色のない顔色を隠すために、厚めにおしろいと紅を塗ったが、陰鬱さは消えなかった。
(どんなに美しい振袖や髪飾りで着飾っても、まったく駄目ね。まだ普段の格好の方がしっくりくるわ)
貧相な自分にはそれなりの格好が一番よく似合う。
当然、その姿で見合いに行けるわけがないので、脱ぎたい気持ちを抑えてしばらくの我慢だ。
父と自動車に乗り、七条家へ向かう。
基本的に見合いは狐の町にある料亭などで行うことが多いのだが、指定されたのは時雨が住む七条家だった。
時雨は当主であるがゆえ、かなりの多忙らしい。
それに加えて、天狐という存在は天啓を受けることが可能のため、あまり屋敷から離れられないようだ。
(天狐さまの力については知っていたけど、まさか七条家へ行くなんて)
父から見合いの場所を聞かされたのは、ついさっき。
確認せずに、きっと料亭で時雨と会うのだろうと思っていた小夜も小夜だが、まさかの場所に瞠目した。
運転手に行き先を伝えている父に慌てて尋ねると「それくらい考えればわかるだろう」と怒られてしまった。
どうせ破談になるから良いかと思ったのか、それともただ面倒だから伝えなかったのか。
緊張するのは変わらないが、前もって教えてくれればよいのに、と心の中で拗ねたのは秘密。
窓から後方へ流れていく景色を虚しく眺める。
七条家の屋敷は狐の町の最奥地にある。
空狐の一族が住む場所からみると、そこまで遠いわけではない。
自動車なら、あっという間に到着する距離である。
(あれが天狐の一族が住んでいる域……)
遠く先に数々の広大な屋敷を捉えた。
建物だけではない。
近づくにつれて空狐とは違う凄まじい妖力を感じる。
まだ、天狐の住居域に入ったわけではないのに、すでにこの位置でも感じ取れる。
額にじわりと汗が浮かぶ。
(お父さまは平気みたい)
ちらりと隣に座る父を見ると、特に顔色を変えることなく、厳しい目つきで前を見据えていた。
おそらく、定期的に会合で時雨と会っているから慣れているのだろう。
父の送迎を担当している運転手も表情こそ覗えないものの、特に異変は感じられなかった。
この時点で震え上がりそうなほどなのに、七条家に到着したら、どうなってしまうのだろう。
緊張から逃れるように、視線を窓から腿の上に移す。
置いてある両手が小刻みに揺れている。
(挨拶をするだけだもの。きっと大丈夫よ)
何度も言い聞かせて出来る限りの不安を取り除く。
そして自動車が天狐たちが住まう区域に入ると、より一層、妖力が肌にびりびりと伝わる。
小夜は妖力が少ない分、他者の影響を受けやすい体質。
七条家に到着するまで、余計なことは考えずに、目を瞑りながらただ呼吸だけをしていた。
「到着しました」
運転手の声に目をゆっくりと開け、自動車から降りる。
(ここが七条家……)
視界では捉えきれないほど広大な純和風の屋敷。
もちろん、立派だろうとは予想していたが、まさかここまでとは。
今見ただけでも水園家の倍以上はある。
青々しい松と石で縁取られた池など美しく整えられた庭園も目を引く。
「おい、神聖な場でみっともない顔をするな」
圧倒され、開いた口が塞がらなかった小夜を父がぎろりと睨む。
指摘されて、ようやくだらしない顔をしていたのだと気がついて我に返った。
「も、申し訳ありません」
「ったく、これだから欠陥品は。七条さまの前でそんな顔をしたらただではおかないからな」
「はい」
小夜は静かに返事をして歩き出す。
今日を迎えるまで、何度も『くれぐれも当日にへまをするなよ』と言い聞かされてきた。
緊張、不安、恐怖……。
普段ならば狐の姿に戻ってしまうような、すべての感情を抑え込み、前を見据える。
「水園さま、お待ちしておりました」
使用人のひとりなのだろう。
玄関の前に着物を身に纏った品の良い老女が立っていて、小夜たちを出迎えた。
「こちらこそ本日はよろしくお願いいたします」
「よ、よろしくお願いいたします」
先ほどの態度とは打って変わって、にこやかで明るい顔と口調になる父。
小夜も慌てて父に続いて挨拶をする。
「それではご案内いたしますね」
玄関で草履を脱ぎ、使用人の案内のもと、客間まで歩いていく。
七条家に仕えているということは彼女も天狐なのだろう。
一挙一動、無駄な動きはなく、上品で惚れ惚れしてしまう。
しかも、貧相な娘を見ても怪訝な顔をすることなく、柔らかな笑みを浮かべている。
廊下ですれ違う他の使用人たちも小夜たちに深々と頭を下げていた。
もちろん、水園家で雇われているひとたちも礼儀は正しいが、彼女らはそのひと段階、上だ。
(もし、この方たちがわたしの屋敷にいたら、少しは違ったのかしら……。なんて考えても意味はないのだけれど)
水園家の使用人頭、秋江の厳しい顔つきを思い出して、つい比較してしまう。
「こちらでございます。当主さまがいらっしゃるまで少々、お待ちくださいませ」
ありもしない想像をしているうちに、客間に到着し室内へと通される。
藺草の匂いが香る庭園に面した畳敷きの一間。
使用人が去り、ふたりが座布団に座ると父の上っ面が剥がれ落ちた。
「お前は挨拶だけをしろ。余計なことは一切喋るなよ」
「はい」
命令には自らの意思に関係なく、首を縦に振る。
それが、小夜の常である。
「まあ、どうせ、この縁談は破棄になる。こちらが口を開く前に見合いは開きになるだろう。お前のような落ちこぼれ──忌み子が選ばれるわけがない。お前は幸せになれない運命なのだから。これから先、死ぬまで地獄を味わい続けるのだ」
「……っ」
『幸せになれない運命』『地獄を味わい続ける』
わかりきっていたはずなのに改めて言葉にされると恐怖のあまり小さく声を漏らした。
父が当主の座を兄に譲れば、完全に居場所はなくなる。
小夜の存在を認識していない兄は、使用人としても彼女を雇わないだろう。
屋敷内はすべて当主の意思がすべて。
兄が小夜を無視すれば、両親も一華もきっと倣う。
そうすれば、小夜は行く当てをなくして途方を彷徨うはず。
運命に抗うことすら叶わない自分が情けなくて、視界が涙で歪んだ。
神さまはどこまでも不平等だと恨みそうになる。
(わたしだって、わたしだって……。本当はお姉さまのように愛された子になりたかった)
一筋の涙が頬を伝ったとき、ぽんっという軽い音が客間に響いた。
「貴様……!」
あろうことか、小夜は溢れ出る負の感情のせいで術が解け、狐の姿へと戻ってしまった。
父は血相を変えて、すぐさま彼女の首根っこを掴む。
「何をしているんだ!早く人間になれ!」
「……っ」
体内に巡る僅かな妖力に意識を集中させて、術を行使しようとするが、何度やっても狐のまま。
(どうして出来ないの? どうしていつもわたしは家族の役にすら立てないの?)
不甲斐ない自分に腹が立って、哀れな自分に悲しくなる。
それでも自らの背負いし役目は果たしたいという思いがある。
自負と言うにはおこがましいが、途中で務めを投げ出したくなかった。
(──斬りすてられる最後までは水園家の娘でいたい)
いつしか、身体に込めていた力を緩め、そして項垂れた。
しばらく経っても化けられない娘に痺れを切らせたのか、父は舌打ちをした。
「もういい。七条さまがいらっしゃる前に帰るぞ」
小夜の首から手を離さず、立ち上がる父を咄嗟に制止しようと口を開く。
「ま、待ってください」
「私に指図するのか? 良いご身分だな。屋敷に帰って躾直してやる」
ここで止めなければ、七条家の使用人に適当に言い訳をして帰ってしまう。
痛みと苦しみに耐えながら、父の鬼のような形相の顔を見上げた。
「お父さま……。わたしは見合いが終わったら、どうなっても構いません。ですが、せめて破棄になるその瞬間までここにいさせてくれませんか」
「たださえ、落ちこぼれのお前のせいで我が家は恥をかいているというのに、さらに汚名を背負わすのか」
「そんなこと生まれてから一度も思ったことはありません……!」
「小賢しい!黙れ、耳障りだ!」
必死の訴えも虚しく、父は歩みを止めなかった。
そして客間の襖を開けると廊下に出た。
(もう本当に終わりなの……?)
涙が次から次へと溢れ、一粒が廊下に零れ落ちたとき。
「何をしている」
突如、低く艶のある声が耳に届く。
おもむろに顔を上げると、廊下に神秘的な雰囲気を纏った美丈夫が立っていた。
胸の位置辺りまで伸びている長髪を組紐で結っていたため、一瞬、女性だと勘違いしてしまいそうになる。
絹のような白の髪に陶器のような肌、涼しげな目元に薄い唇。
雅、優美。
その褒め称える言葉が似合う、気品に満ち溢れる男性にくぎ付けになる。
こんなにも他者を魅了するひとに逢ったことはない。
きっとこれから先も。
(この御方がもしかして──)
「し、七条さま……」
そう、彼が小夜の見合い相手である七条家当主、時雨だった。
彼の隣には、先ほど小夜たちを客間に案内してくれた使用人が立っていた。
ふたりとも厳しいまなざしを父に向けている。
父は怯えたように声を震わせて一歩、後ずさりをした。
生まれて初めて見る威厳を失った父に驚いて小夜の涙は無意識に止まった。
「水園殿、彼女は貴方の娘だろう? なぜ、そのような手荒な真似をしている」
「い、いや。これは……」
父はぐったりとしている小夜を一瞥すると、掴んでいた手を首根っこから離した。
「……っ!」
急に離されるとは思っておらず、廊下に打ちつけられる衝撃に備える準備すら出来ていなかった。
ぎゅっと目を固く瞑る。
「……え」
しかし、感じたのは痛みではなくふわりとした感触。
おそるおそる目を開けると、そこは廊下の板張りではなく、正絹の着物だった。
「大丈夫かい?」
そして、ちらりと上を見るとすぐ近くに時雨の端正な顔があった。
心配そうに梔子色の瞳が小夜の顔を覗き込んでいる。
「も、申し訳ありません!」
時雨に助けられたのだと理解し、慌てて飛び退こうとしたが、身体に力が入らず、動けなかった。
(どうして動けないの)
いつまでも天狐の当主である彼の腕の中にいるのは、無礼だとわかっているのに、なぜか足がふらついてしまう。
愚図ついている娘に父は慌てたように腕を伸ばした。
「お、お前!いつまでそこにいる──」
また乱暴に抱えられると覚悟したが、父との距離が急に離れた。
(七条さま……?)
時雨は一歩下がり、腕の中にいる小夜を父から遠ざけた。
まるで、この娘は渡さないとでも言うように。
時雨の予想外の行動に父だけでなく、小夜も唖然とする。
「どうして彼女の体調が芳しくないというのに気づかない」
「そ、それは……。娘は朝から見合いで緊張しておりまして」
「では緊張だけで、こんな痩せ細った身体になるのか? これは明らかに普段の食生活に問題があるようにしか見受けられないが」
「昔から食が細いのです。身体も弱く、最近は余計に食べなくてわたくし共も困っております。なあ、小夜?」
一華や母に向けるものとはまったく違う。
軽く腰を曲げ、貼り付けたような笑みを浮かべる父はぞっとするほど、恐ろしい。
『はい、と言え』
きっと父はそう言っていると、すぐにわかる。
身体が弱いのは嘘ではないけれど、極度に悪化したのは小学校の卒業直後。
一般的には物心がつく頃には術が自由に行使出来る。
小学校に通っている間は父も、もしかしたらと待っていてくれていた。
しかし、それが一向に出来ない娘に絶望して、食事もろくに与えないような今のぞんざいな扱いになったのだ。
確かに彼の実の娘であるはずなのに、それを否定したくなってしまった。
目の奥が笑っておらず、同意を求めるような尋ね方を目の前にして。
それでも、家族の命令には従わなくてはならない。
本能が小夜に訴えかける。
つまっているように塞がる喉、小刻みに震える唇、それらに抗って、父の問いかけに答えようとした。
「は──」
「それは君の本心ではないはずだよ」
『はい』何百回、何千回も言ってきたその二文字を告げる前に時雨の声が頭上から降りそそぐ。
もっと愛されて、誰からも縛られることなく自由に生きたいという蓋をしてきた想いを見破られて心臓がどきりと鳴った。
そっと顔を上げると、時雨は真剣なまなざしでこちらを見ていた。
不思議と怖さはなくて、その宝石のような目から目が離せなくなった。
ずっと、見られるとまるで心の中をすべて余すことなく見透かされそうになる。
それでも視線を逸らすという選択肢は小夜になかった。
「君から感じる妖力は極端に少ない。そのせいで望まない扱いを受けていたのだろう。先ほどのように」
「……いいのです。あれくらい何でもありません」
「そ、そうです。あれは躾の一環で──」
「君に聞いてない。黙ってて」
「……っ」
自分の思い通りに強がった娘に良しと思ったのか、間に割って入ってくる父。
しかし、そんな彼に時雨は即座に鋭いまなざしと言葉で黙らせた。
『黙っていて』
ある意味これは命令だ。
天狐の命令に逆らえば、どうなるかぐらい愚かな父にだってわかる。
普段は威張っているのが嘘かのように、静かになった。
口を噤んだのを確認すると、時雨は再び小夜へと視線を向けた。
「妖力がないからといって蔑んでいいという理由にはならない。それに客間での君たちの会話が聞こえたけど、本当はこのまま帰りたくなかったのだろう?」
まさかあの酷い会話が聞かれていたかと思うと羞恥心でどうにかなってしまいそうになる。
しかし、あんなに声を荒げていては、聞きたくなくても耳に入る。
(どうして、七条さまはわたしなんかに寄り添ってくれるの)
初めてだ、こんなにも身を案じてくれるのは。
その優しさに甘えても良いのだろうか、弱音を吐いても良いのだろうか。
ここで首を横に振ってしまえば、またいつも通りの生活に戻ってしまいそうに思えて、小夜は間を開けてこくりと頷いた。
「はい。七条さまが縁談を破棄される、そのときまで、ここにいさせてほしかったのです」
時雨が多くの婚約者候補との縁談を白紙に戻しているのは有名な話。
水園家の令嬢として、この屋敷で見合いをする。
結果がどうあれ、その役目だけは最後まで務めたかった。
しかし小夜の言葉に時雨は以外な反応を見せた。
長い睫毛に縁取られた煌めく目を見開いて、数回瞬かせている。
「え、破棄? 私が縁談を?」
「え?」
なぜ彼が不思議そうな表情をしているのか、すぐには理解出来ず、とぼけたような声の返しをしてしまった。
再度、問いかける。
「七条さまはこの縁談を破棄なさるのですよね?」
「ううん、しないよ」
「えっ!?」
いつもの掻き消されそうな声をしている小夜から考えられないような大きな声量。
驚くのも無理はない。
挨拶を済ませたら帰るものだとばかり思っていたから。
「えっと、それはつまり──」
「君に僕の婚約者になってほしいということだよ」
「……」
あまりの展開の早さに思考が停止する。
この世で一番の高貴な存在と言っても過言ではない天狐の当主が、落ちこぼれ狐を見初めているのだ。
にっこりと笑いながら否定をした時雨の答えに、まるで時が止まってしまったかのような空気が辺りを包む。
しばらくの沈黙のあと、それを破ったのは父だった。
「またまた七条さまは御冗談がお上手で」
眉を八の字に下げ、ははっと笑いながら時雨を見やる姿は彼のご機嫌を伺っているようにも見えた。
(お、お父さま)
もう忘れてしまったのか。
黙れと命令を受けたばかりだというのに。
時雨は一度、はあ、と呆れたように息を吐くと小夜に向けていた笑みとは一変、冷酷非情な面持ちで父を見た。
「声を出して良いと、僕がいつ許可した?」
「ひっ……」
怯えた父は、大きな獲物の標的になったかのように弱々しい。
気を抜けば、腰を抜かして座り込んでしまいそうだ。
時雨の元から低い声がさらに低くなり、父を硬直させるのは簡単だった。
一番近くで彼の表情を見ていた小夜は一瞬、違和感を覚える。
(今、目の色が赤くなったような気がしたのだけれど……。気のせいかしら)
見間違いでなければ、時雨が父に怒りを現した瞬間、彼の梔子色の目が、血のように赤く変化した。
どこか、体調でも悪いのかと一抹の不安を感じたが、改めて見ても特に問題はなさそうだ。
しかし、相手は天帝に最も近い存在。
天狐である彼に秘められた力があってもおかしくない。
ただ、落ちこぼれの自分が踏み込んでも良い領域なのか躊躇してしまう。
胸騒ぎがして、じっと下から様子を伺った。
「どうかしたかい?」
小夜の視線に気がついて、時雨は目を細め、とびきり甘く優しげな笑みを浮かべた。
これまで家族と女学院の教師以外の異性とほとんど会話をしたことがない小夜にとって、それはとても刺激的だった。
頬が熱を帯びて、胸が高鳴る。
「えっ……。あの、その。ど、どうしてわたしなんかを婚約者に選ばれたのでしょうか?他に良い条件の女性は大勢いらっしゃるはずです」
今は照れている場合ではないのだと思い出し、必死に言葉を紡ぐ。
正直、わざわざ落ちこぼれを選ぶ理由がわからない。
きっと、いや絶対に彼につり合うのは姉の一華や同級生の舞子だ。
隠しきれない貧相な身体と陰鬱漂う顔のどこに惹かれるところがあったのだろう。
そもそも家柄で選ぶようならば、天狐の娘と政略結婚をするだろうし、空狐の水園家が七条家に多くの利益をもたらすとは考えにくい。
時雨は小夜のたどたどしい問いかけに一つも嫌な顔をせず、最後まで話を聞くと口を開いた。
「確かに過去に見合いに来た女性たちは皆、家柄も教養も申し分なかった。従者にも言われたよ、君との縁談は辞めておけと」
「それでは──」
「でも」
時雨はそこで初めて小夜の話を遮ると、ふわりと彼女の身体を高く持ち上げた。
見上げる位置から急に目線が等しくなり、どくんと心臓が鳴った。
「君は他の令嬢と違った。水園殿との会話を聞いてすぐにわかったよ。一所懸命で純粋な娘なんだって。七条家の地位や財力目当てではなく、きっと私のことを心から愛してくれる。そう思ったんだ」
よほど小夜と出逢えて嬉しいのか、シミ一つない白い肌にほんのりと赤みが差した。
喜ぶその姿は、まるでずっと待ち望んでいた贈り物を手にした子どものよう。
彼の婚約者に、妻になるには華やか見目でも、由緒正しい家柄でもなかった。
必要だったのは、清らかな心。
どうやらそれが判断材料だったらしい。
「小夜。私の婚約者になってくれる? 近い将来は花嫁として君を七条家に迎え入れたい」
(……どうして。わたしだって本当は望んでいたじゃない)
誰かに求められ、愛されることを。
「もしかして嫌、かな?」
俯いて黙り込む小夜を見て、時雨からにこやかな笑みが消える。
眉を下げ、おそるおそる問いかける様子から、動揺していることが覗える。
堂々とした一面から変わって、今の彼はどこか憂いを帯びている。
小夜はすぐに首を横に振って、抱えている胸の内をすべて伝えようと意を決した。
「嫌、なんかじゃないです。でもわたしを婚約者にしても何も七条家や時雨さまのお力になれません。ただの役立たずで邪魔な存在になります」
時雨の正式な婚約者となれば、厳しい花嫁修業が始まる。
普段から家族に無理難題を強いられているので、それにはある程度慣れている。
しかし、無事に結婚を迎えられるかどうかはわからない。
当主である時雨の決定は絶対だ。
それでも、器量がない小夜に与えられる課題を簡単にこなせる自信はなかった。
優しくしてくれた彼の足枷にはなりたくない。
こんな自分の身を案じてくれた、それだけで十分だ。
その思い出さえあれば、きっとつらいことが待ち受けていようとも、生きる力になってくれる。
(だから、わたしはここにいては駄目)
小夜は丁寧に頭を下げて、時雨の腕の中から出ようと身をよじった。
(え……?)
廊下へ降りようとしたが、まったく身体が動かない。
体調が悪いわけではない。
明らかに動ける程度には回復している。
しかし、離れるのを彼は許さなかった。
「僕は君が笑顔で隣にいてくれたら、それだけでいい。真面目な君は、きっと婚約者の務めを果たせるかどうか考えてくれているのだろう?」
「ど、どうしてそれを?」
読心術の力でもあるのだろうか。
図星を言い当てられて、どきりと心臓が鳴った。
彼の目は美しさを兼ね備えていると共に、ひとの心をすべて見透かしてしまうような雰囲気がある。
驚かせられたり、考えを言い当てられたり。
これでは心臓がいくらあっても足りない。
当の本人は、目を丸くしている小夜を微笑ましそうにくすりと笑った。
「やっぱり。僕はね、他者の本質を見抜ける力がある。異能と呼べるほどまでではないけれど、一種の特技かな。まあ、その体質を利用して次々に婚約者候補たちとの見合いを破棄にするから従者を困らせていたのだけれど」
ははっと困ったように笑う時雨はどこかお茶目で幼くも見えた。
噂だけで勝手に怖い男だと思っていたが、父に接する以外は穏やかな一面が垣間見られた。
「……小夜」
自然と聞き入ってしまいそうな不思議な魅力のある声が耳朶を撫でる。
時雨は自らのしなやかでありながら、逞しい腕の中にいる小さな狐に向けて、すっと目を細めた。
「君の想像している通り、僕の婚約者になれば、必然的に花嫁修業に取り組むことになる。天狐の一族に嫁ぐとなれば、なおのこと厳しいものに、ね」
「はい」
視線を逸らすことは許されないような、いや、小夜自身が逸らしたくなかった。
静かに返事をすると、時雨は続けた。
「泣きたくなるような、つらいと感じる日もあるだろう。僕の母上もそうだったと聞くから。──でも」
一旦、言葉を区切ると時雨は小夜の前足をそっと握った。
こわれものに触るような、繊細な手つきに鼓動が早鐘を打つ。
「必ず僕が君を支える。つらいことも悲しいことも気にならないくらい、笑顔に、幸せにさせる」
「……!」
涙で視界がくしゃりと歪む。
世界で一番、不幸だと思っていたのが、一気にひっくり返ったような気がする。
こんなにも誰かに必要とされて、明るい未来を約束されるなんて、世界で一番の幸せ者だ。
「本当に、わたしで良いのですか……?」
最後に一度だけ、震える声で尋ねた。
ぽろぽろと溢れ出す涙を時雨は人差し指でそっと拭いながら、花笑みを浮かべた。
「ああ。君となら良い夫婦になれると思うんだ」
向けてくれる笑顔も、かけてくれる言葉も、陽だまりのようで小夜の氷の心を溶かすには十分すぎるほどだった。
目の前に現れた希望の欠片を手放したくなくて、小夜はしっかりと頷き、嗚咽を必死に抑えると時雨を見つめた。
「──わたしも、良い妻でありたいと思います。七条さま、よろしくお願いいたします」
小夜の導き出した答えに、安堵したように微笑むと雪色の毛並みをゆっくりと一撫でした。
「ありがとう、小夜。こちらこそよろしくね」
改めて挨拶を交わして、和やかな空気が流れる。
「おめでとうございます、時雨さま。そして小夜さま」
そこで、今までふたりの様子を見守っていた、使用人が声をかける。
両手を胸の前で組み、興奮したように頬を染める姿は心の底から祝福しているようだった。
水園家の使用人に温かな対応をされたことがないので一瞬、戸惑ったがすぐに礼の意味を込めて頭を下げる。
「あ、ありがとうございます」
「色々と玲子さんにも迷惑をかけたね」
申し訳なさそうに眉を下げた時雨に対し、玲子と呼ばれた女性は首を横に振った。
「いいえ。一度もそのように感じたことはありませんわ。時雨さまが運命のお相手に出逢えた、それだけで、わたくしは自分のことのように喜ばしいですから」
「そう言ってもらえてよかった。第二の母でもある玲子さんに反対されたら、どうしようって不安だったから。これから小夜を七条家へ迎える準備で忙しくさせると思うけれど、よろしく頼んだよ」
「お任せくださいませ。改めまして小夜さま、わたくし使用人頭を勤めております、玲子と申します」
「水園小夜です……!よろしくお願いいたします」
「勝手に話を進めないでいただきたい」
深々と一礼したとき、今まで蚊帳の外だった父が、不快感が入り混じったような冷え切った声で和やかな会話を遮った。
その鋭いまなざしは小夜だけでなく、時雨にも向けられていた。
それには当然、当の本人も気がついていているようだったが、怯むことなく堂々とした佇まいで構えている。
「七条家の当主であろう方が、まさかそのような落ちこぼれを選ぶとは。天狐の一族が与える課題など、こいつに成せるはずがございません」
「お父さま、わたしは」
父は小夜の心配をしているのではない。
このまま、小夜が時雨の婚約者になれば、縁談の順番待ちをしていた女性は諦めなければならない。
それは姉の一華も同級生の舞子も。
もしかしたら一華に関しては、破棄を言い渡されてすぐに帰宅する予定のふたりが遅いと愚痴をこぼしているのかもしれない。
彼女が結果を知れば、不満をあらわすどころではない。
劣っていると見下してきた妹が七条家の女主人となり、自分より身分が高くなることに怒り狂うだろう。
それを父は阻止しようと思って、愛嬌があって優秀な一華を七条家へ嫁がせたがっている。
落ちこぼれを嫁がせるなんて、どういうつもりなのだと他の狐たちの世間体も気にしているのだと、焦りを見ればわかる。
結局、大切にしているのは彼女なのだ。
「お前は黙ってろ!これは当主同士の話だ!」
小夜は決意を示そうとしたが、彼はそれを拒絶した。
ここが神聖な場所だと自分が言ったのに、声を荒げて、ぴしゃりと言い放つ父は醜く見えてしまった。
血の繋がった親子なのに、そう思ってしまった自分が少し嫌になる。
荒ぶる父とは反対に時雨は静かに耳を傾けていた。
「万が一でも小夜が七条さまの妻になれば、この國の狐たちの未来は危ういでしょうな。どうでしょう、正式に婚約者関係を結ぶ前に長女の一華とお会いしてみませんか。貴女さまの隣に並ぶ者に相応しいと私が保証します」
額に汗をかき、愛想笑いを浮かべている父はまるで取引相手に商談を持ちかけているようだった。
言い方には刺があるが、確かにこの話に関しては小夜が入る隙はない。
時雨が小夜を婚約者にするという判断を覆せば、話は別だが、あの真剣な想いはそんな軽いものではないと伝わった。
ただ行く末を見守ることしかできない。
「……うん。今の提案を聞いて僕の考えが変わったよ。僕自身が甘かった」
「え?」
彼へ抱く信頼の気持ちが揺れ動きそうになる。
まさか。
考えが変わったということは、つまり──。
「で、では一華と見合いをしていただけるのですか!?」
目を丸くさせながら顔を綻ばせる父に、さらに不安が募る。
もしかしたら、と考えてしまって咄嗟に耳を塞ごうと前足を頭へ伸ばした。
時雨はふうっと軽く息を吐き出す。
「水園高志郎。今後一切、小夜と僕の前に姿を見せるな。これは当主命令だ」
「なっ……!それはどういうことですか!」
もう父は相手が天狐だからといって遠慮はしていない。
何がなんでも、己の望みを叶えようと必死だ。
憤慨している父とは反対に、小夜は胸を撫で下ろした。
(わ、わたしの早とちりだったのね)
てっきり、今の話はなかったことにして一華と見合いをするのかと思ってしまった。
耳へと伸ばしかけていた前足をゆっくりと降ろして、ふたりのやり取りを傍観する。
「そのままの意味だよ。接触もそして会合への参加も禁止する。洋行している息子にでも当主の座を譲るか、代理の者に任せればいい。欲望を満たすことしか考えていない君は愚かで滑稽だよ」
薄々、時雨は父をはじめとした水園家の人間が小夜を虐めてきたのだろうと勘づいている。
仮にここで、事実を隠し通しても、七条家の力で調査をすれば、すべて明らかになるだろう。
これまで、彼女にしてきたことは許せないけれど、当主を引退して、もうこちらに関わらなければ、許容するらしい。
普通ならば、没落という判断でもおかしくないのだが、優しく繊細な小夜に免じて寛大な決断を下したのだ。
反論できる余地はない。
論破されて、父は悔しそうに唇を噛んだ。
「いくら七条さまでも、血縁関係のある親子を引き裂くなんて非情ではありませんか? 娘の気持ちを聞かずに、何と勝手な。お前もそう思うだろう? 小夜」
まただ。
父は都合が悪くなると、小夜までも道連れにしようと、彼女に同意を求める。
でも、奴隷のようだった生活が、たった今、新しいものへと変わろうとしている。
言いなりだった弱い自分自身も。
(わたしは、もう貴方たちの操り人形じゃない)
腕から上半身を乗り出し、父と向き合う形になり小夜は決意に満ちたまなざしで見据えた。
それが普段から高飛車な態度をとっている彼にとって気に食わなかったようで、表情をぐしゃりと歪めた。
「な、なんだその目は!それが親に対する態度か!」
きっと、ここに時雨がいなければ絶対にぶたれていた。
でも今は違う。
彼の体温が小夜に確実に勇気を与えてくれていた。
人さし指をこちらに向ける父に臆することなく、静かに続ける。
吐き出したいほど不満はあるけれど、感情的になったら、それこそ彼らと同じだ。
「お父さま、わたしは感謝しています。たとえ世間体があったとしても女学院にまで通わせてくださって。水園家の力でわたしは守られていました」
「……何が言いたい」
「上手に術が行使できなくても、ずっと家族の役に立ちたいと、役目を果たしたいと思っていました。それを忘れた日は一度たりともありません。──でも」
どれだけ頑張ろうとも、誰も認めてはくれなかった。
いつか努力が報われる日がくると信じていた。
薄幸に生まれた自分は忌み嫌われて当然だと何度も言い聞かせて。
しかし、それは間違っていたのだと長い年月をかけて今日、知った。
まだ完全に時雨と愛と信頼感で結ばれたわけではない。
婚約者になったとしても、花嫁にはなれない可能性だってある。
婚約関係を破棄されるかもしれない。
捨てられて居場所をなくすかもしれない。
水園家を出たといって、必ず幸せになれる保証はない。
でも信じてみたかったのだ。
優しい時雨の言葉を。
「わたしの居場所は水園家ではないのだとわかりました。もし、こんなわたしでも必要になさってくださる方がいるのだとしたら、その御方の傍にいたいです」
自然と熱量が前足に力を入れていたのだろう。
その気持ちに答えるように、時雨が抱きしめる腕の力を強めてくれた。
(今度はわたしの番。頑張ろう、救ってくれた七条さまの恩返しができるように)
時雨からの接触禁止命令が言い渡されたので、しばらく、いや残りの人生ずっと父と会うことはないかもしれない。
こんな状況なのに、寂しさを微塵も感じないのはきっと異常だろう。
清々する、とまではいかないけれど、彼らと一緒に暮らしていても地獄のままだ。
両親や姉の一華は小夜をいいように使い、いざとなれば命も奪うに違いない。
「わたしは、これから先の未来を水園家ではなく、七条さまに捧げます」
高志郎は何を戯れ言をとでも言うかのように呆れながら肩を竦める。
「どうせお前なんかすぐに見放される。水園家の血が流れている娘が捨てられたとなれば醜聞になるな」
嘲笑する高志郎は、表向きの表情を作るのをあきらめていて、別人のようだった。
家族が変わってしまったのは、すべて異端である小夜のせい。
小夜が一華と同じくらい妖力があって、普通の娘として生きられていたら、暴力で現実を教えることなんてしなかった。
「小夜。今ここで先ほどの発言を撤回すれば許してやる。そして今後、お前に手は出さないと七条さまの前で誓おう」
一華や華織にも、よく言っといてやると一言付け足す高志郎は、口角を上げてこれでどうだと言わんばかりの満足げだ。
自分たちが小夜にしてきた行いが、どれだけ酷かったか。
彼の発言が嘘かまことかわからないが微塵も反省していないことは確かである。
仮に本当だとしても、水園家へ戻る選択肢などもうない。
もうあの、喉が痞えて痛くて息苦しい空間には少しもいたくない。
心と身体が拒絶している。
時雨の言葉に改めて、醜悪な環境に身を置いていたか気づいたからだろう。
「いいえ。撤回もしないし屋敷にも戻りません。仰ったではありませんか。以前お父さまたちは、お前を生まなければ良かったと。わたしはわたしの人生を歩んでいきます」
「そのようなことを言ったか? ふん、覚えていないな。それにお前をここまで育てたというのに恩を仇で返すつもりか。何と生意気な」
やはり娘はお返しくださいと、腕の中にいる小夜を無理矢理奪おうと手を伸ばされる。
これだけ時雨に叱られているのに、どこまでも懲りず、反省しない男だろう。
守ってくれるひとがいるとはいえ、手を出される瞬間はこわい。
小夜が怯んだ瞬間、時雨は先ほどのように引くのではなく、逆に前へと出た。
「いいかげんにしないか」
時雨は左手で小夜の身体を抱きかかえたまま、右手で高志郎の肩を掴み、壁へと叩き付けた。
「……っ」
低く、鈍い音と共に高志郎の顔が歪められた。
見目は白鳥のように繊細で麗しいのに、力強さから男らしさを感じる。
きっと打撲はしているだろうけど、小夜はそれ以上に数えきれないほどのつらい経験している。
さすがの高志郎も叩き付けられた瞬間は痛さを堪えるように左手で肩を抑えていた。
しかし、すぐに顔を上げるとにやりとほくそ笑んだ。
「……おやおや。七条家の当主ともあろう御方が暴力とは」
「これは正当防衛だよ。あくまで推測だけれど、君は彼女に対して、この比じゃないくらい非道なことをしてきたんじゃない?」
時雨はこの険悪な雰囲気に似合わない、花が咲いたような笑みを浮かべている。
相変わらずの余裕さを感じて、頼もしい。
しかし、高志郎は未だ挑発的な目つきを向けている。
「時雨さま!」
終わりが見えない争いに困惑し始めたとき、ひとりの男性が小走りで廊下の奥からやって来た。
どうやら状況を見かねた玲子がいつの間にか場を離れて、他の屋敷の者を呼んできたようだ。
艶やかな黒髪に、三つ揃いのスーツ姿の男は廊下に広がる光景にぎょっと瞠目させた。
そのような反応をするのも無理はない。
時雨は水園家の当主を壁へ追いつめていて、腕には一匹の狐がいるのだから。
スーツ姿の男に気がつくと、ぱっと顔を明るくさせた。
「ちょうど良かった。律、このひとをつまみ出して」
「はっ!?……この方は水園家の当主ですよね。見合いは、もうよろしいのですか」
「うん。彼女を正式な婚約者にすることに決めたから。ちなみに彼に接触禁止命令を言い渡したから、今後は監視も警備体制も強化しておいてくれる?」
時雨は律と呼ばれた男に紹介するように小夜を見せる。
目があった瞬間、律は顔面蒼白になり、唇を震わせた。
「はっ!? 時雨さま、見合いをするだけだと仰ったではありませんか!」
「そのつもりだったんだけどね、気が変わった」
「ちょっ、ちょっと待ってください。色々と状況が把握できません」
「すまないね。あとできちんと説明するから」
「とりあえず、落ち着きたい。彼女もだいぶ疲れているだろうし。……僕も二回目に達しそうなんだ」
「……!か、かしこまりました。それでは水園さま、こちらへ」
律は背を向き、ちらりと高志郎を見て玄関へ促す。
しかし、まだ見合いの結果に納得いっていないようで、不満をあらわにしている。
「私はまだ──」
「こちらへ。私共も手荒な真似はしたくないのですが、歯向かうようでしたら、容赦はしません」
「……くそっ」
鋭いまなざしに為す術をなくしたのか、悔しそうに拳を太ももへと叩いて、歩み出した。
小夜と時雨の隣を通り過ぎるとき、一度足を止める。
「この恨みは忘れない。覚えておけ、小夜」
憎しみに満ちた表情は、すぐに脳裏へとはりついた。
この選んだ道は間違っていなかったと信じたい。
でも、やはり恐怖というものは綺麗に拭いきれなくて、簡単に心を脅かす。
「水園さま」
律と玲子に催促され、再び足を動かすと高志郎は廊下の奥へと消えていった。
先ほどの喧騒が嘘のように、辺りが静まり返り、胸を撫で下ろした。
それは時雨も同じようで、ふうっと軽く息を吐き出した。
こんな事態を招いてしまったのは、自分のせいだ。
かなりの迷惑をかけてしまったと小夜は罪悪感に耐えきれなかった。
腕の中で深々と頭を下げる。
「七条さま、父が無礼な態度をとってしまい、まことに申し訳ありません。それもすべて、わたしのせいです。何と詫びたら良いか……」
苦しくて、痛くて、胸が張り裂けそうだった。
もっと高志郎の逆鱗に触れずに済む方法があったかもしれない。
優しい時雨まで不快な思いをさせて、とても彼を見られそうになかった。
じっと動かずにいると、ふわりと頭が撫でられる感触がした。
その手つきは柔くて、そして温かい。
まるで大丈夫だと慰めてくれているようだった。
「君が謝ることなんて何もないよ。僕の方こそ見苦しいところを見せてしまったね。怖い思いをさせただろう」
思いもしなかった時雨の謝罪に、顔を上げて首を横に振った。
「いえ!そんなことないです。わたしなんかを守ってくださって、とても嬉しかったです」
「自分のことを蔑まない方がいいよ。君は純粋で優しい、素敵な女性なんだから」
梔子色の目を細めて、こちらに向ける花笑みに心臓がどく、どく、と強くなっているのがわかる。
「あ、ありがとうございます……」
そこに偽りなどなかった。
こんなにまっすぐに褒められたのは初めてで、頬に熱が帯びる。
照れて恥ずかしさを隠すように俯く、小夜を時雨は微笑ましそうに見ていた。
「さて、ご説明していただけますか。時雨さま」
木製の低いテーブルを挟んだ向かいに、律が静かな双眸でこちらを見ている。
高志郎が七条家の屋敷から出て行ったあと、彼に呼ばれ、ふたりは客間に通された。
どうやら、この男は六木律というらしい。
天狐の一族、六木家の長男で時雨の従者を勤めているという情報は、客間に入ってすぐに時雨に教えてもらった。
彼の反応を見る限り、律はすぐに小夜を受け入れてくれた玲子と違って、彼女を正式な婚約者に選出したことに納得していないようだった。
「……と、その前に水園小夜。そこから降りなさい」
今、小夜は座布団の上ではなく、なぜか時雨のももの上に座っている。
テーブルの前に並んだ二つの座布団のうちの一つに座ろうとしたところ、時雨にひょいっと身体を持ち上げられ、ももの上に座らせられた。
驚いてすぐに、そこから降りようとしたが、ここにいてほしいなと頼まれてしまい、現在に至る。
「は、はい」
おそらく、律は小夜に好感は抱いていない。
それどころか、隠せていない嫌悪感が、肌にひしひしと感じる。
再び、降りようと試みるが、優しく手で制された。
「これくらい、いいでしょ。それより、僕たちに話があるのだろう?」
のんびりと微笑みながら諭す時雨に、律は半ば呆れたようにため息を吐き出したあと、口を開いた。
「時雨さま、本当にその娘を婚約者にするおつもりですか」
「ああ。お互いの意思もきちんと確認したよ。ゆくゆくは僕の妻になってもらうつもりだ」
ある程度、想定はしていたのだろう。
やはり、と小さく呟くと頭を悩ませるように、額を右手で抑えた。
「どうかもう一度、再考してくださいませ」
「どうして?」
「縁談の話があった時点で、申したでしょう。言わなければご理解いただけませんか」
「実際に会ってみて気持ちが変わった。律には小夜の良さがわからないの?」
「ええ。まったく」
ぴしゃりと言い切られる。
躊躇なく己の意見を述べている姿は、何となく高志郎と似ているが、またどこか違うし、時雨も慣れているのか、まったく気にしていないようだった。
(従者というより、仲の良い友人のよう)
日頃から暴言を浴びせられている小夜にとっては、これくらい別に何とも思わない。
話を聞いていれば、大体わかる。
小夜と見合いをしたい時雨を律は何とか阻止をしたかったのだろう。
しかし、相手は七条家当主。
当主の意見は絶対だ。
それは、どこの一族も同じで、律も六木家の血を引くとはいえ、止められるほどの権力はない。
「君も、時雨さまの婚約者になるということの重大さに気がついているのか」
ぎろりと睨まれ、背筋がぴんと伸びる。
玲子のように落ちこぼれである小夜を認めてくれる方が珍しい。
普通ならば律のような意見が、当然である。
時雨の婚約者になると決めたからには、ひとりでも多く、七条家の人間に認めてもらい、受け入れてほしい。
こくりとうなづいて、負けじと律を見つめる。
「はい。七条さまの隣に並んでも恥じないように、これから精進します。どんな厳しい花嫁修業にも逃げ出したりしません。六木さま。どうか、お願いいたします」
「僕からも。頼む、律」
願いを乞う小夜に倣って、時雨も頭を下げる。
影が落ちて、寄り添ってくれる、その優しさに救われる。
「し、時雨さま!顔をお上げください!貴方さまが頭を下げる必要などないのですよ」
ぎょっと目を見開く律。
ひゅっと息を吸い込んだあと、慌てたように止めに入るが、時雨はそのままだった。
「いや。婚約者になってほしいとお願いしたのは僕だ。それに、大切な従者である律に反対されたままは嫌だから」
「時雨さま……」
ただの従者ならば、ここまで説得させないだろう。
彼らには彼らの過去があって、小夜には到底入り込めない絆がある。
そんな大事なひとに祝福されてこそ、一歩前へと進めるのかもしれない。
律を納得させなければ、おそらく他の七条家に仕える者も首を縦に振らないだろう。
三人とも黙り込んで、客間は静寂に包まれている。
僅かな逡巡ののち、先に口を開いたのは律だった。
「時雨さま、水園小夜。顔を上げてください」
時雨が落としていた影が消えて、視界が僅かに明るくなる。
顔を上げたのだとわかって、小夜もそれに続いた。
相変わらず律は気難しい表情をしていたが、若干、寄せられていた眉間の皺が減ったような気がする。
「わかりました。彼女を婚約者として七条家で暮らすことを許可します」
「本当かい? ありがとう、律」
「ありがとうございます……!」
良かったね、とふたりは顔を見合わせる。
きっと小夜だけでは、絶対に無理だった。
律が誠心誠意、仕えている時雨の願いだからこそ。
「ただし」
喜びを分かち合っているふたりの空気にすかさず、冷厳さを帯びた声が届く。
「こちらが与える課題に弱音を吐いたり、達成できたりしなかった場合は即座にこの屋敷から追い出します。それが条件です」
「少し厳しすぎない? 小夜は天狐じゃない、空狐だ。母上だって苦労したのに、それじゃあ、まるで無理難題をこの時点で押しつけているようなものだよ」
「だからこそです。彼女がたとえ落ちこぼれでなかったとしても私どもとは位が違います。ほとんどの天狐の一族が異論を申し立てするでしょう」
(六木さまの仰るとおりね)
基本的に狐たちの結婚は同じ種族同士。
天狐は天狐と。
空狐は空狐と。
そして今回のように、政略結婚の場合が多い。
中には稀に、恋愛結婚をする者もいる。
同じ種族ならば、特に問題はないのだが、位が違うと苦労することが多いようだ。
どちらかが空狐で、どちらかが気狐だと必ずと言っていいほど反対される。
恋愛や結婚に目がない女性が集う女学院でも、自然とそういった話が耳に届く。
妖力が高い者たちから生まれた子供は代々、家を繁栄させてきた。
違う種族だと、どうしても弱まってしまう。
反対する者たちはそれを懸念しているのだ。
圧力に負けて、別れを選ぶ者。
駆け落ちしてでも、愛を選ぶ者。
比べれば前者が圧倒的に多いのが現実だ。
小夜と時雨は恋愛結婚ではないものの、似たようなもの。
過去に天狐の一族に天狐以外の女性が嫁いだ、なんて話は聞いたことがない。
前代未聞である。
(婚約者として、妻として、この場所に居続けるには、大丈夫だってことを皆さまに証明しないといけないわ)
一番は必要だと言ってくれた時雨の気持ちに応えられるように。
地獄の中で蹲っていた小夜に、手を差し伸べてくれた優しさを無駄にはしたくない。
「構いません。わたし、頑張ります」
はっきりとお腹から声を出して決意を伝える。
律はこちらの真意を探るかのように、無言でこちらを見ていた。
「小夜、本当に大丈夫? 体調があまり優れていないのだろう」
おそらく彼は小夜の皮膚に微かに浮き出ている骨の感触に気がついた。
名家の令嬢でありながらも痩せ細った身体は、まともに食事を与えられていないのだと、頭の良い時雨は想像がついているようだ。
心配そうに顔を覗き込む時雨を安心させるように微笑む。
「はい。堂々と七条さまのお隣に立てるようになりたいのです」
「……わかった。僕もできることは協力するから。何でも言ってね」
「ありがとうございます」
頼れる存在がいることは心強く、安堵からか笑みがこぼれた。
しかし、気合いでどうにかなるほど、甘くはない。
ここまで話を進めるだけでも多大な迷惑をかけているのに、順調に事は進まないだろう。
頑張ると強がっているものの、内心は不安もかなりの割合で占めていた。
「まあ、まずは人間の姿になるところからですけどね」
「は、はい」
小夜は見合いが始まる直前に変化の術が解けてから、一度も人間の姿になれていない。
遅いときは、できるようになるまで一日かかるので、日常茶飯事だったが、天狐の彼らからしたら大問題だ。
「実の父にあんなことをされたんだ。恐怖で術が解けてもおかしくないよ。今日だけは多目に見てあげて」
「……はぁ。今日だけですよ。明日の朝には術を行使できるまで回復してくださいね」
「はい」
厳しい彼のことだ。
朝を迎えて、この姿だったら追い出すに違いない。
何とかしなければと焦りが募る。
時雨は何も喋らなかった。
けれど、静かに背中を撫でてくれていて、それがとても心地良かった。
「では、わたしは書類などの準備を進めていきます。書いていただくのは明日に。その状態では筆を持つことさえ、ままならないでしょうから」
律は小夜の前足を一瞥しながら、立ち上がる。
彼は優しさとか思いやりで言ったわけではないだろうが、それが純粋に嬉しく感じた。
「お気遣いありがとうございます」
礼を言うと、ふんと小さく鼻を鳴らして襖へと歩き出す。
そこで、何か思い出したかのようにそうだ、と言って引き止めたのは時雨だった。
「ねえ、律。玲子さんを呼んできてくれないかい? 小夜の身の回りの世話を頼みたいんだ。男の僕だと色々と限界があるから」
「そんな、お世話だなんて。わたしはひとりでも平気ですよ?」
「いいの、いいの。甘えられるときに、存分に身を委ねたらいい。その方が物事が上手くいったりするんだ」
朗らかに笑う時雨には説得力がある。
新たな環境で生活が始まるのだ。
ひとりで抱えて失敗し、誰かに迷惑をかけるよりは、力を借りた方が玲子だってありがたいだろう。
「……では、お願いします」
「うん。そういうわけだから、律もよろしくね」
「かしこまりました。──時雨さまも今日はごゆっくりお休みください。可能ならば誰も近づけず、おひとりで」
(え? 今、近づけるなって……。どういう意味かしら)
まるで念を押すような言い方に疑問を抱く。
一瞬、小夜自身と遅くまで一緒にいるなと言っているのかと思ったが、何やら違うようだ。
使用人でさえも、今夜は関わるなとも聞こえる。
首を傾げる小夜をよそに、時雨はうなづいた。
「わかったよ」
返答を聞くと失礼いたします、と丁寧にお辞儀をして客間から出て行った。
当然のごとく、お辞儀の相手は時雨のみ。
しかし、小夜はそんなことなど微塵も気にならなかった。
それよりも、先ほどの律の発言だ。
そして、高志郎と揉めていたときの、時雨の目の色と、彼の『もうすぐ二回目』の言葉。
小夜の中では起こった出来事と噛み合っていなくて、靄が心を埋め尽くす。
(もしかして、七条さまはどこか体調がよろしくないのかしら。それに六木さまは気がついていらっしゃる?)
目が血のように赤く染まったことも関係しているのだろうか。
もしそうだとしたら、なるべく早く部屋で休んでもらった方がいい。
天狐の頂点に君臨する時雨に一大事が発生すれば、外に影響を及ぼす。
余計なお世話かもしれないが、聞かずにはいられなかった。
「あの、七条さま。体調が優れないのではありませんか?」
「え? 僕はいたって元気だけれど」
きょとんとして、目を丸くさせている表情からして、とても嘘をついているようには見えない。
血色も良いし、風邪をひいているわけではなさそうだ。
あまり深い探りは入れてはいけないとわかっていながらも抑えることはできなかった。
「でも、わたしの見間違いでなければ、先ほどから様子が……。目の色だって変わったように見えました。ご無理はなさらない方がよろしいのではないですか」
「……!」
小夜の『目の色が変わった』の一言に、時雨は涼やかな顔から明らかに動揺したように、肩を揺らす。
瞠目したあと、気まずそうに視線を逸らした。
何か聞いてはいけないようなまずい質問をしてしまっただろうか。
余計な一言で傷つけてしまっただろうか。
あの時雨が視線を逸らすなんて、ずっとやらなかった。
胸がざわつき、後悔が押し寄せる。
(今日が初対面なのに、無神経だったわよね、わたし)
花嫁修業の試練が始まる前に、時雨を悲しませては元も子もない。
婚約者として失格だ。
「あ、あの。わたし、無礼でしたよね。申し訳ありません」
婚約者だからといって、知られたくないことも、深く捜索されるのも嫌うひとだっているはずだ。
頭を下げると、慌てたような声が降ってくる。
「ち、違う!違うから!君は謝るようなことは何も言っていないよ。ただ、見られていたんだって驚いただけ」
「見られていた……? 目の色が、ですか」
「ああ。──話そうかな。飾らずにありのままの姿でいてくれた君には」
時雨は小さく笑っていた。
でもそれが、喜びや嬉しさから生まれたものではない。
悲しさやつらさから成り立ったものだとわかって胸が切なく締めつけられる。
時雨は長い睫毛を伏せたあと、ぱっと輝くような笑みを浮かべていた。
たった今の、憂いは完全に消えている。
「でも、その前に夕食と風呂だ。小夜、お腹は減っていないかい?」
「い、いえ。食欲はあまり……」
突然の変わりように、驚いて声がうわずる。
目をぱちくりと瞬かせている小夜に時雨はくすりと笑った。
「そうか。でも何か口にしないと駄目だよ。汁物くらいなら大丈夫かな」
「はい。大丈夫だと思います」
「わかった。玲子さんがこちらに来たら伝えよう。──小夜」
さらりと垂れる髪がやけに色っぽく、かしこまった声色にどきりと胸が鳴る。
何か大きくて衝撃的な出来事が起こる、そんな予感がした。
「すべて済ませたら、話すよ。君が不思議に感じていること全部。僕の秘密を、ね」
(秘密……?)
内緒話をしているかのような仕草の彼はどこかミステリアスだ。
夕食も風呂も済ませてからだと、秘密を明かされるのは、だいぶ先だ。
天狐の、時雨の知られざる秘密とは一体何なのだろう。
早く知りたいというはやる気持ちと、もし悲しい内容だったらと複雑な感情になる。
でも、どんな秘密だとしても受け入れなければいけない。
いや、受け入れたいと思う。
それは相手が他の誰でもなく時雨だから。
どちらともなく、静かに見つめ合ってそのときを待った。
◆
「お待たせしました。遅くなってしまい、申し訳ありません。七条さま」
「大丈夫だよ。ゆっくり温まれたかい?」
「はい。玲子さんに手伝っていただいたおかげです。この姿でひとりだったら、大変でした」
「それは良かった。これからも困ったことがあれば、玲子にも頼るといい。彼女は君のことを、とても気に入っているようだから」
小夜のお世話係に就任したのは、天狐の一族、五月家の女主人、五月玲子だ。
五月家も大昔から代々、七条家に仕える家。
玲子は多忙をきわめていた七条家の先代当主──時雨の両親の代わりに彼の面倒を見ていたらしい。
時雨からすれば、ふたり目の母親的存在だ。
その手腕から周囲にも一目置かれていて、若くして使用人頭に就いた。
この屋敷にやって来て、突然暮らすことになった落ちこぼれの小夜に対しても嫌な顔などせず、むしろ快く迎えてくれた。
そんな彼女が狐姿の小夜を風呂に入れてくれたのだ。
身体を洗うとなると、そもそも前足では手拭いさえも掴めないので、どうしたものかと頭を悩ませたが、玲子が手伝うと申し出てくれた。
そのおかげで無事に洗い終え、たらいに溜めてくれたお湯で浸かれることもできたことに、ただ感謝しかない。
湯浴みを終えたあとも、西洋手拭いで丁寧に拭いてくれたので、まさにいたせり尽くせりの状態だった。
「ここへどうぞ。夜風が涼しくて気持ちが良いよ」
ふわりとした毛並みで、歩いてくる小夜を隣へと招く。
縁側に座る時雨の髪が通り抜ける風で、さらりと広がって、美しい。
空には無数の星が散らばっていて、一段と明るい光を放つ月が浮かんでいる。
まるで、月の都からやって来た天女のよう。
「失礼いたします。……本当、夜風が心地良いです」
火照った身体をひやりとした風が柔く撫でる。
少しの間、目を瞑り、この静かなときに身を任せる。
そして、目を開けると隣に座り、夜空を見上げる時雨へと視線を向けた。
「七条さま、本当にありがとうございます。たくさん尽くしていただいて。それに、こんなに立派なお部屋まで……」
ちらりと後方を見ると障子が僅かに開いた畳敷きの和室がある。
庭師が剪定している松の木や鯉が棲む池がある中庭。
そこに面しているのが、与えられた小夜の部屋である。
水園家とはまるで違う、広く整えられた部屋。
室内には、たくさんの着物が入りそうな箪笥、異国情緒漂う洋燈に綺麗に木目が入った文机。
押し入れの中には、綿がしっかり詰まった布団や分厚い敷き布団が入っている。
障子には穴など一つもなく、完璧に風を防いでくれる。
もちろん、これは急に用意したわけではない。
時雨の婚約者がいつ住み始めても良いように、あらかじめ準備していたようだ。
愛されていた姉の一華でさえも、こんなに上等な部屋ではなかった。
さすがは七条家の財力といったところか。
「喜んでもらえて安心した。必要なものがあれば遠慮なく言ってね」
「はい、ありがとうございます」
部屋に案内された時点で一通り見たけれど、必要な物はすべて揃っていた。
日用品に加え、美しく細工が施された箱には化粧品やその道具がぎっしりと詰められていた。
水園家でも女学院には見目を整えて行けと言われ、最低限の安い物は貰っていた。
しかし、ここにあるのはすべて一級品。
人気で中々手に入らないと噂の物から、手が届かないような高価な物まで多種多様だ。
流行りが載った雑誌まで取り揃えられており、例えるならば女性が憧れる部屋。
昨日まで殺風景だった部屋が翌日には、充実した部屋に変わるだなんて夢にも思わなかった。
(きっと、欲しい物なんて思いつかないだろうけれど。本当にわたしにはもったいない素敵な部屋ね)
時雨に倣って夜空を見上げる。
(綺麗……)
目の前に広がる光景にくぎ付けになる。
降りそそぐ月光も、きらきらと宝石のように輝く星も、何故だか特別なものに見えて心が弾んだ。
今までは空を見る余裕なんてなかった、ずっと下ばかり見ていたから。
吹き続けていた風がやんだとき、時雨はおそるおそるといった様子で口を開いた。
「小夜、さっき話した僕の秘密のことなんだけど」
ずっと気になっていた本題を切り出されて、どきりと心臓がなる。
孤高の天狐である時雨の隠された秘密。
数字と赤い目は何を意味しているのか。
夕食も風呂の時間も気になって、そわそわしていた。
「……はい」
覚悟を決めてしっかりとうなづく。
「どんな秘密でも君は受け入れてくれる? 僕から離れていかない?」
不安そうに尋ねる時雨は子どものように幼くも見えて、このひとの傍にいなければと本能が訴えかけてくるように感じた。
「七条さまのお側にいると約束します」
その言葉に安堵したのか、ほっと小さな息を漏らした。
そして、柔らかなまなざしから、真剣なまなざしへと変わると、小夜を射抜く。
よそ見などせずに、ただただ、目の前の婚約者だけを。
「ありがとう。──僕は実は」
一呼吸置くと、意を決したように話し始めた。
「三回、怒ると誰も手がつけられないくらい凶暴になるんだ」
「凶暴、ですか?」
それだけでは、要領の悪い小夜にはとても理解できず、首を傾げる。
時雨はそんな彼女を見かねてああ、と言うと続ける。
「天狐は狐たちの中で一番、妖力が高いのは知っているだろう?」
「はい。天帝に最も近い、愛し子だからだと女学院で習いました」
「そう。他の天狐たちを従える七条家はなおさら巨大だった。そして僕は父のように制御が上手くなかった」
時雨は右手のひらを、じっと見つめる。
どこか、遠くを見つめるようなまなざしに胸が苦しくなった。
勝手に時雨は七条家の当主なのだから、非の打ち所がない完璧な人物なのだと思っていた。
しかし本当は、過酷な運命を背負っている。
「そして怒るような状況が三回続くと、妖力が暴走して凶暴になってしまうんだ。目が完全に赤くなって狐の姿になると三回目を迎えた証拠。……他人を襲う、なんてこともある」
「だから六木さまにも二回目と仰ったり、目も一瞬だけ赤くなったのですね」
あのとき、もし律の到着が遅れれば、凶暴化していたに違いない。
高志郎だって、この秘密は知らない。
だから、あそこまで煽るような真似をしたのだ。
「怒らないように気をつけていても、生きていれば当然、感情に支配されるときもある。だから、そういうときはひとりで過ごすんだ。無関係のひとを傷つけたくないからね」
(だから六木さまはひとりで過ごすよう、念を押したのね)
律は時雨をこわがったからではない。
罪のないひとを襲って、我に返ったときに悲しませないようにするためだ。
七条家の屋敷には大勢の使用人たちが働いているのに、広い部屋で孤独に過ごすのは何て寂しいのだろう。
呪いに苦しんでいるようで、そんな姿を想像するだけで、悲しくなる。
妖力が少なく、悩む小夜と多いがゆえに悩む時雨。
どこか重なり合って、もう彼を遠い存在だと思えなくなった。
他人事ではない。
自分自身を見ているようだった。
気がつけば、視界が歪み、涙の雫が一筋、頬を伝っていた。
泣き出した小夜に目を見開いて、すぐに頬へと手を伸ばす。
細く長い人差し指が落ちかけた雫を拾う。
「そんな顔をさせるつもりじゃなかった。ごめんね」
今の感情を上手く整理できなくて、ただ首を横に振ることしかできない。
嗚咽しながら泣く小夜を時雨はそっと抱きしめた。
耳がちょうど彼の胸に当たっているせいで、心臓の音が聞こえる。
音の間隔が短くて、飄々としている時雨も緊張しているのが伝わった。
もしかしたら、自分のせいかもと考えてしまうのは勝手すぎるだろうか。
この状況に小夜の方が動揺を隠せなかった。
「あ、の。七条さま……」
急に密着した身体と分厚い胸板に男らしさを感じて、ぱっと飛び退く。
しかし、頭の後ろに手を回されて再び、ふたりはくっついた。
「君が良ければ、もう少しこのままで」
「でも、お着物も濡らしてしまいますし……」
恥ずかしさを誤魔化すように、慌てて理由を考える。
時雨が身に纏っているのは、正絹の着物。
かなりの上等な品だと、情報に疎い小夜でもわかる。
そんな小夜に気がついたように、くすりと時雨は笑みをこぼした。
「いいよ、そんなこと。僕のために泣いてくれる君が愛おしくて、こうしていたいんだ」
穏やかで慈愛に満ちた声が耳朶を撫でる。
(それを貴方が望んでいるのなら)
胸に温かい感情が広がる。
これが愛、そして幸せなのだろうか。
戸惑うけれど小夜も離れがたくなって、それ以上何も言わずに身を委ねて、涙を流した。
◆
どれくらいの時間が経過したのだろう。
永遠にも感じた愛おしい時間。
ふたりはしばらくの間、月明かりの下で抱き合っていた。
小夜の嗚咽と涙が止まって、自然と身体が離れた。
月光に冴える絹のような髪がはらりと小夜の頬に当たった。
少しだけ擽ったくて、身をよじる。
僅かな明かりが儚げな雰囲気をもつ時雨の魅力を倍増させている。
(とてもそんな風には見えないのに)
彼の怒りに三回触れれば、凶暴化し、襲いかかってくる。
それが時雨の隠された秘密。
おそらく、限られた者しか知らないのだろう。
時雨が狐の民から敬愛されているからといって、真実が広まれば騒ぎになる。
もしも、凶暴化した彼が狐の町だけでなく、人間が住む帝都にまで足を踏み入れれば、騒ぎどころではない。
我を忘れるのが一番、懸念すべき点で、話から察するに信頼を置ける律でさえも止められない。
でも、誰よりもそれを恐れているのは紛れもなく時雨本人である。
「僕が怖い?」
彼の特徴的な美しい笑みが消えて、悲しげにまつげを伏せられる。
前髪が顔に影をつくり、より一層、沈痛な面持ちにうかがえた。
(少し驚きはしたけれど)
孤独といつ起こるかわかりえない恐怖に耐え続けている時雨の心情が痛いほど、よくわかる。
それは、小夜も似たような体験をしてきたから。
彼をひとりにはしたくない。
律も玲子も傍にはいるけれど、きっと時雨はそれ以上の存在を求めている。
容姿や財力、権力でもなく秘密を受け入れてくれて、そして心から愛してくれる花嫁を。
きっと、そんな女性になれたら、どれだけの幸せを彼に与えられて救えるだろう。
小夜は時雨の問いかけに首を横振った。
「いいえ、怖いだなんて思いません。大切な秘密を教えてくださりありがとうございます」
秘密も知っても逃げ出したり怯えたりせずに凛と佇む姿に時雨は僅かに目を見開いたあと、すっと細めた。
陶器のような白い肌に赤みがかかる。
「小夜……。ありがとう。本当にありがとう」
嫌われるかと思った、と呟いて胸を撫で下ろす姿を見て、かなり彼が不安で押し潰されそうだったのだと垣間見る。
そして腕を伸ばし、この夜のように静かに微笑む小夜の頬を細く長い指が撫でる。
まるで宝物を見つけ、喜びを噛みしめるようだった。
異性にこうして愛をもって触れられることが初めてなので、全身に流れる血が沸き立つように熱くなるが不思議と嫌ではなかった。
(わたしを救ってくれたように、今度は七条さまを助けたい。そのために、どんな花嫁修業も乗り越えていかないと)
天狐である時雨の母も花嫁修業には苦労したのだ。
落ちこぼれの小夜には苦労の言葉だけで済むか未知数だ。
それでも。
胸を張って時雨の隣に立てるように、時雨の支えになれるように、時雨と同じ未来を見られるように……。
望みが、かけがえのない夢が、溢れ出してくる。
決意がより強固なものへと変わっていく。
「本当なら、この時間はひとりで過ごさなくてはいけないのだけれど、もう少しだけ一緒にいたい。いいかな?」
小夜は僕を怒らせることはしないだろうからね、と言って提案をしてきた時雨にすぐにこくりとうなづく。
律には申し訳ないけれど、言いつけを破るなんて生まれてはじめてで、どうしてか胸が弾んでしまう。
水園家では絶対に考えられなかったことだ。
「はい。もちろんです」
「何か悪いことをしている気分だ。律に見つかったら怒られるな」
「ふふっ。そのときはわたしも謝りますね」
まるで、いたずらを企む子どものようだ。
思わず顔を見合わせて、吹き出すふたりを月は照らし続けていた。
◆
それから、ふたりは夜の時間を埋め尽くすほど、たくさん話した。
「小夜は好きな食べ物はある?」
「最近は食べられていないですけれど、甘いものが好きなんです。今、気になっているのは帝都にある老舗のお店の塩大福です。美味しいって女学院でも話題で」
「へえ、そうなんだ。僕も甘いものには目がないのだけれど、それは知らなかったな。今度、用意させよう」
「えっ、よろしいのですか」
「ああ。そこまで人気なら僕も一度、食べてみたいし。特別なお茶と一緒に食べたら、きっと、とても美味しいよ」
「わあ、楽しみです」
「七条さまは普段、どのようなお仕事をされているのですか?」
「基本的には他の一族と同じような仕事だけれど、大きく違うのは月に一度の天啓の儀、かな」
「天啓の儀、ですか」
「うん。小夜も知っている通り、僕たち天狐は天帝に最も近い存在。天帝からのお言葉を受け取れる力がある。天狐の代表である僕が儀式を執り行っているんだ」
「そうなんですね。その儀式って天狐である御方しか見られないのでしょうか」
「基本的にはそうだけど、僕の婚約者なら大丈夫だよ。将来、結婚して夫婦になれば必然的に小夜も関わるようになるし。今から見ておけば勉強にもなる」
「ありがとうございます。しっかりお勉強させていただきますね」
「僕の舞を君に見られると思うと少し照れるな」
「舞も披露されるのですか」
「代々、七条家に伝わる羽衣を身に纏って舞うんだ。儀式をする何日も前に練習をして、一族皆に披露するのが習わしなんだよ」
「羽衣を纏って……。きっと、とてもお綺麗なんでしょうね」
「そんなことないよ。でも、観覧席に君がいると思うと一段と気合いが入るな。頑張らないと」
「あの、お手伝いすることがあれば、わたし、何でもやります」
「ありがとう。そのときはよろしくね」
「小夜は好きな花はある?」
「そうですね……。わたしはスイセンが好きです」
「スイセンか。それはどうして?」
「わたしの家──水園家の花壇にスイセンが咲いてて。厳しい冬の寒さに耐えて美しく咲き誇る様に何だか勇気をもらえる気がするんです」
「素敵な理由だね。君にぴったりの花だ」
「そう、でしょうか」
「うん。つらくても一生懸命に生きてて、そして可憐で美しい」
「そ、そんなこと……。し、七条さまは何か好きなお花はありますか」
「顔を赤らめて可愛いね。僕はそうだな、秋生まれだから自然とその季節に咲く花に目がいく。例えばコスモスとか」
「コスモス、綺麗なお花ですよね。わたしも好きです。秋になると女学院の花壇にも咲きますよ」
「君も気に入っているのなら、今度、ふたりで花壇を作らないか」
「ふたりの花壇……」
「そう。普段は庭の管理は屋敷専任の庭師に任せているのだけれど、ふたりの好きな花を種から育ててみたらいいんじゃないかと思って。まだ庭にも十分、作れるほど余裕があるし」
「素敵です……!是非、やりたいです」
「それじゃあ、ふたりの都合がついたら庭師に道具を借りてやってみようか。きっと楽しくて大切な思い出になるよ」
「はい。作るのが待ち遠しいです」
時間を忘れて、ひたすらに語り合う。
つらい出来事が全部嘘だったのではないかと疑ってしまうほど、充実した時が流れる。
時雨と話していると、自分はちゃんと地に足をつけて生きているのだと実感させてくれる。
ずっとこの穏やかで幸せが続きますようにと願わずにはいられなかった。
◆
(許さない、許さない、許さない。──絶対に許さない)
小夜の姉、一華は屋敷の板張りの廊下を大股で歩く。
ギシギシと床が鳴る音と気品さなど微塵も感じさせない足音に、使用人たちも何事かと廊下の角から様子をうかがっている。
「落ち着きなさい、一華」
「怒る気持ちはよくわかるけれど、もう一度ゆっくり話し合いましょう」
「落ち着いてなどいられませんわ!どうして、なんで、よりによって小夜が……!」
足を止めて振り向くと、怒り狂う自分を止めようとしている両親の姿。
高志郎から聞いた見合いの結果──小夜が時雨の婚約者になったと聞いてからというものの、一華はずっとこの調子である。
見合いそのものがなくなれば、すぐに帰宅するだろうと思っていたのに、水園家が所有する自動車が屋敷に戻ってきたのは、遅い時刻。
そして、そこには小夜の姿はなかった。
「お父さまもお父さまよ!どうして小夜を強引にでも連れて帰ってこなかったの!? 七条家にあんな落ちこぼれを置いてくるなんて信じられないわ!」
本当は一華だって知っている。
水園家が歯向かっても、七条家当主が決めたことを覆すことなど不可能なことは。
それでも受け入れたくなかった。
欠陥品だと蔑んでいた妹が、時雨に見初められただなんて。
悔しさをぶつけるように、父の胸元を何度も叩く。
上等な着物の襟元がぐしゃりと乱れるが、そんなことを気にするほど一華には余裕などない。
「一華……。本当にすまない。私もできることはやったんだ。それでも力が及ばなかった」
「ねえ、貴方。どうにもならないの?一応、あの娘も戸籍上はわたくしたちの家族。連れ戻せる可能性だって残っているんじゃないかしら」
高志郎の肩に右手が置かれる。
しかし、問いかける妻──華織の問いかけに首を振った。
「いや、無理だ。私も出来ることはすべて尽くした。しかしこれ以上、こちらが七条さまの反感を買えば、ただでは済まない。没落する可能性だってある」
「そんな……」
もう何も手段は残されていない、その事実が悔しさを倍増させる。
力なくうなだれる母に、やるせなさで自身の振袖を両手で握りしめる一華、そして黙り込む高志郎。
父にいくら諭されようとも、一華の中では諦めがつかなかった。
見目も名前の通り華やかで、他者を魅了するような愛嬌のある性格。
器量だって妹と比べれば秀でているし、何事もそつなくこなせるほどの要領も兼ね備えている。
それなのに、選ばれないなんて絶対におかしい。
(まだ、まだよ。きっと何かあるはず。小夜を婚約者の座から引きずりおろす方法が)
もう両親に頼んだって無駄だろう。
だから、もう自分で何とかするしかない。
「私は部屋に戻る。もう遅い時間だ、ふたりも休みなさい」
「あ、貴方……!ちょっと待って」
自室へ戻る高志郎を華織は小走りで追いかける。
一華は父の話など耳に届いていない。
ただ、その場に立ったまま、考えを巡らせていた。
(何か、あの子の弱みは……。あ、そういえば)
頭に浮かんだのは、女学院での小夜の姿。
そして、よくその隣にいるのは──。
ひとりの女学生の顔と名前を思い出し、次々と作戦が脳内で組み立てられていく。
臆病で優しい小夜だからこそ、この方法が上手くいく気がした。
(ふふっ。いいことを思いついたわ)
ぷるりとした唇の端をにやりと持ち上げてほくそ笑む。
そして、先ほどとはうって変わって、足取り軽く自室へ歩き出す。
まるで気分が良いような、幸運に感じることがあったかのような雰囲気。
ふん、ふん、と鼻歌を歌う一華はどこか恐ろしかった──。
◆
「良かった……。人間の姿になれたわ」
ぺたりと顔を手で触って感触を確かめる。
ふわりとした毛並みではない、ちゃんと柔らかい弾力のある肌だ。
姿見に映る自分自身を見て、はぁっと安堵の吐息を漏らした。
(もし、朝になっても狐のままだったら六木さまに叱られて、ここから追い出されていたかもしれないもの)
『必ず、人間の姿になっていること』
これが律との約束だ。
変化に失敗したら、どうしようかと不安だったが無事に身体も精神もだいぶ回復したようだ。
これもすべて時雨のおかげである。
(感謝してもしきれないわ。あとでお礼を言わないと)
小夜は早速、教えてもらった水場で顔を洗い終えると、再び部屋に戻り、箪笥から用意してもらっていた着物を一着取り出す。
淡い緑色の振袖は赤と白の牡丹がよく映えて、気品さを感じられる。
それを身に纏い終えると、文机の上に置かれた箱の蓋を開ける。
所狭しと詰められた化粧品と道具を簡単に見繕って取り出した。
今日は登校日なので、昨日よりは薄く化粧を施す。
おしろいと頬紅を塗って、紅を塗って完成だ。
雪色の髪は後ろに一つに結ってガバレットで止める。
「これでよし……」
姿見の前に立ち、身だしなみを確認をすると、障子を開けて、台所を目指す。
(七条さまに、ゆっくり寝てていいと言われたけれど、目が覚めてしまったわ。それに、ここでお世話になるのに何もしないわけにはいかないもの)
小夜は花嫁修業以外にも、できることは何でも手伝うつもりだ。
それは律や七条家で働く使用人たちに評価されたいわけではない。
たださえ、落ちこぼれである自分を屋敷に置いてくれているのだ。
中には律のように時雨の命令で仕方なく、と不快に思っている者もいるだろう。
何か役に立って恩返しがしたい、それで朝食作りの手伝いをしようと思い立ったのだ。
昨夜、玲子に屋敷の案内をしてもらったので、台所の場所はわかる。
(あの御方は……)
もうすぐ、台所に到着するところで、廊下の奥から歩いてくる人物が見えた。
朝日に照らされて輝く絹のように長い髪の持ち主はただひとり。
今日は組紐で結っていないようで、また昨日とは違った印象を受ける。
時雨は足を止めると目を丸くさせて数回、瞬かせた。
「あれ、もしかして小夜?」
「七条さま……!おはようございます」
ぱたぱたと軽い足音を立てながら時雨に駆け寄り、挨拶をする。
彼は人間姿の小夜をまじまじと見つめて、嬉しそうに微笑んだ。
「おはよう。そうか、変化が上手くいったんだね」
「はい。七条さまのおかげです。ありがとうございます」
「ううん。僕は何もしていないよ。全部、小夜の力だ。よく頑張ったね」
「……っ」
よしよしと褒めながら頭を撫でられて、思考が止まりそうになる。
昨日だって撫でられているのに、それとはまったく違うように感じる。
狐の姿だったからだろうか。
目線もより近くに感じて、吸い込まれそうになる。
「この姿では、はじめましてだね。改めてよろしく、小夜」
「こ、こちらこそよろしくお願いいたします」
涼しすぎず、適度に柔い朝日をふたりが包む。
新たな生活が始まるにふさわしいような気候だ。
「ああ、それと」
微笑みあっていると、時雨が口を開いた。
「僕のことは七条さまではなく、時雨と呼んでくれないか」
「えっ、でも……」
時雨と出逢ってから一日も経過していないし、それに彼は天狐だ。
こうして会話を交わすだけでも奇跡に近いのに、名前呼びなど畏れ多すぎる。
真意に気づいているのか、いないのか時雨は戸惑っている小夜にずいっと近づく。
昨日から思っていたのだが、彼はだいぶ距離が近い。
「僕たちは婚約しているんだ。僕が君のことを名前で呼んでいるのに片方が名字呼びなんておかしいだろう? 嫌かな」
「嫌というわけでは……。ただ少しだけ恥ずかしくて。殿方のことをそのようにお呼びしたことはありませんから」
「無理強いはしないよ。ただ、お互いに名前で呼んだ方がより距離が近づける気がして」
「そ、そうですよね。では……し、しぐ」
口をぱくぱくさせながら、必死に喋ろうとする姿はまるで小動物のようだ。
呼ぶ決意を固めた小夜を時雨は目をきらきらと輝かせて見ている。
「……や、やっぱり言えません!」
「えっ!?」
顔を真っ赤にさせて、視線を逸らした小夜を時雨は呆然と見つめる。
がくっと肩を落とす様を見て、よほど期待を膨らませていたのがわかる。
「ま、まあ、急かしすぎても駄目だよね。ゆっくり育めばいい。うん、そうだ」
自分に言い聞かせている姿に小夜は罪悪感が募る。
本当は小夜だって、『時雨さま』と呼びたい。
けれど、それよりも恥ずかしさが上回ってしまう。
元々、人見知りなので、名前を呼べるようになるには時間がかかりそうだ。
「申し訳ありません。あの、名前はまだ難しいですが、旦那さまとお呼びするのはどうでしょうか」
「ほ、本当……!?うん、もちろんだよ」
時雨の表情にぱっと明るさが戻る。
嬉しさのあまりに小夜の手をぎゅっと握った。
旦那さま、と呼ぶだけでも彼女にとって大きな一歩だ。
伝わる体温に鼓動が早鐘を打つ。
大きな音がばれてしまわないかとひやひやしてしまう。
にっこりと笑い、喜びを噛みしめる時雨をそっと見つめる。
(喜んでもらえて良かった)
「そういえば、小夜はこんな朝早くからどうしたの?」
「朝食作りをお手伝いしようと思って」
「まだ身体だって本調子ではないだろう? 無理はしないでいいよ」
「ですが、何もしないわけには……」
「小夜のそういう真面目なところ好きだよ。だけど今日は登校日だ。過労で倒れたりしたら大変だ。今日くらい家事は休みなさい」
「旦那さま……。では、お言葉に甘えてそうさせていただきます」
「うん。そうだ、朝食の準備が整うまで屋敷の周りを散歩しに行かないか? 近くに綺麗な花畑もあるだ」
「はい。是非行きたいです」
それじゃあ、行こうかと手を差し出され、小夜はそっと掴むのだった。
◆
「それでは、婚約者さま。下校時刻にはお迎えにあがりますので」
「はい。ありがとうございます」
小夜は七条家が所有する自動車から降りて、ドアを締める前に運転手に向けて礼をする。
運転手も軽く会釈をするとドアを締めて、運転席に戻り、自動車を発進させた。
それをしばらくの間、見送ると昇降口に向けて歩き出す。
「ねえ、聞きました? あの子、七条さまの婚約者になったんですって」
「ええっ!? だって落ちこぼれで有名じゃない。一華さまの間違いでは?」
「間違いないわ。 確かな情報筋ですもの」
自動車から降りたとたん、何人もの女学生の陰口が耳に届く。
やはり予想していた通り、話は広まっていた。
別に何も隠すようなやましいことはないので堂々としていてよいのだが、どうも突き刺すような視線は耐えがたい。
足早に昇降口に向かっていると、少し先に同級生の寺石舞子の姿を捉えた。
(あ……。どうしよう、きっとまた言われるわ)
どく、と心臓が嫌な音を立てて思わず足を止めた。
悪く言われるに違いない。
見合いが決まったというだけで、あんなに激怒していたのに、話が進んで正式に婚約者になったのだから。
今は普段から連れている取り巻きはおらず、舞子ひとりだ。
彼女もこちらに気がついて視線がぶつかる。
怖さのあまり、視線を逸らすが、いつまで経っても舞子がこちらへやって来る気配を感じない。
おそるおそる目を開くと、舞子はただ睨みつけるだけで、昇降口の中へと行ってしまった。
悪口や嫌味を言われると覚悟していたのに、何も起きず、逆に呆然としてしまう。
(え?)
睨みつけられるだけで済むなんて久しぶりだ。
立ち尽くす間にも、続々と他の女学生たちが通り過ぎていく。
(い、いけない。今は気にしないようにしなくちゃ)
始業に遅れれば、内申点が下がってしまう。
時雨の婚約者たるもの、それだけは避けなくては。
小夜は余計な考えを頭から振り払って、小走りで昇降口へと向かうのだった。
鐘が鳴り、教室内にいる女学生たちは荷物をまとめ始める。
普段ならば、家に帰るのが憂鬱だったが、今日は違う。
まあ、屋敷に帰れば律から与えられる厳しい花嫁修業もあるので気は抜けないが。
登下校は時雨が手配をしてくれた送迎の自動車がある。
もう正門近くに到着しているはずなので、急いで帰る支度をする。
机の中から教科書や雑記帳を取り出していると、カサリと軽い音がした。
「これは……?」
不思議に思って、それを手に取ると一枚の紙切れが入っていた。
『小夜ちゃん。放課後に校舎裏まで来て。凛』
送り主は隣の学級の生徒、緒方凛だった。
凛には普段から親切にしてもらっているが、手紙を送られるのははじめてだ。
今日一日、お互いに移動教室が多くて一度も会っていない。
そのせいだろうか。
首を傾げるが、ここで考えているより指定されている校舎裏に向かった方が早い。
座っていた椅子から立ち上がると、鞄を持って教室をあとにした。
(校舎裏ってここよね?)
校舎裏に行くことは特に禁止されているわけではない。
影のせいでやけに暗く、雑草が生えていて物寂しい雰囲気が漂う。
裏門とごみ捨て場があるくらいなので生徒や教師もいない。
二日ほど前の雨のせいで地面はまだ乾いておらず、泥濘んでいる箇所も多い。
それを避けて、日が当たるところに立つ。
(まだ、緒方さんは来ていないのね)
辺りを見渡すが、呼び出した張本人の姿はない。
凛の教室の前を通ってここまで来たが、室内には人の気配はなかった。
自分が早く到着しただけだろうか、そう思いながら凛を待つ。
日が当たる場所に立っているとはいえ、校舎裏はより風が冷たく感じる。
両手を擦り合わせていると、後方から足音が聞こえた。
凛が来たのだと、そうわかって彼女の名前を呼びながら振り向く。
「緒方さ──」
しかし、その相手は凛ではなく、一華だった。
どうして彼女がここにいるのか、そう考え始める前に一華は手にしていたハンケチを小夜の顔へと伸ばす。
「ぐっ……」
ハンケチが顔に押し当てられると、薬品特有のツンとするような香りがした。
嫌な予感がして抵抗しようとするが、後ろから誰かに羽交い締めにされる。
その間に香りも、どんどん吸い込んでしまい、強烈な眠気に襲われて視界が霞み始める。
(一体、これは……)
だんだんと遠のき、小夜の意識はそこで途切れた。
「……っ」
ゆっくりと意識が覚醒して目を開くと、そこは先ほどいた校舎裏ではなく、見知らぬ場所だった。
埃を被っている椅子や割れた鏡、棚から垂れ下がる布の切れ端などからして物置小屋であることはわかった。
しかし、鈴風女学院の物置小屋はここまで古びていない。
身体も打ってしまっているようで、所々に痛みを感じる。
そして視線がやけに低く見えて違和感を覚える。
もしかして、と手を見るとそれは人間のものではなく、狐の前足だった。
(……術が解けているわ)
気絶している間に狐の姿へと戻ってしまったようだ。
不安が押し寄せて辺りを見渡すと、小屋の天井近くに小窓があるだけで、ほとんど光が差し込んでおらず薄暗い。
とりあえず外へ出て状況を確認しようと扉へと向かおうとしたとき、ドアノブが回されて誰かが入ってきた。
「あら、小夜。もう起きてしまったの? もっとゆっくり寝てて良かったのに。ねえ、舞子さん」
「お、お姉さま……」
くすりと笑みを浮かべ、頬に手を添えながら入ってきたのは姉の一華だった。
そして彼女の斜め後ろには舞子が立っていた。
「はい、一華さま。薬の量が少なかったでしょうか。申し訳ありません」
「いいのよ。ここまでは想定内。小夜をここまで連れてくるのが目的でしたから」
「お姉さま、ここは一体どこですか? それにどうしてこんなことを……」
意識を失う前の記憶がよみがえる。
おそらく一華が薬品を含ませたハンケチで小夜に襲いかかり、気絶させたのだ。
舞子が傍にいるということは、背中から羽交い締めをしたのは彼女。
困惑する小夜を一華と舞子は愉快そうに見下した。
「ここは寺石家が所有する敷地内にある小屋。それにしても、まんまと騙されるなんてね。優しい貴方ならきっと来てくれると思っていたわ」
「それじゃあ、あの手紙は……」
「ええ。わたくしたちが用意したものよ」
あれは一華たちが仕組んだ罠。
疑わずにやって来た小夜を待ち構えていたのだろう。
「お姉さまたちは何が目的なのですか」
「わたくしたちの目的はただ一つ。小夜、七条さまの婚約者の座を譲りなさい」
「え……」
一華はゆっくりと近づき、狐姿の小夜を無造作に掴んだ。
「きゃっ……!」
「貴方さえいなければ、わたしに縁談の話がくるはずだったのよ」
七条家からの縁談を待っていたのは一華だけではない。
扉付近に立つ舞子だって同じ。
舞子は小夜の視線に気がつくと淡々とした声色で答えた。
「一華さまはわたくしの憧れなの。だから幸せになってくだされば、それでいいの。何だって協力するわ」
「まあ、嬉しい。素敵な下級生ができて、わたくしは幸せ者ね。婚約者になったあかつきには、うんとご褒美をあげるわ」
一華は舞子にとびきり優美な笑みを向けると、次に空中でもがく小夜を睨みつけた。
どれだけ身体をひねり、動かしても首根っこを掴む手は解けない。
「この手を離してほしい? いいわよ、貴方が七条さまの婚約者を辞めればね」
「い、嫌です……!」
「あら、生意気な口を聞くのね。いいのかしら。断れば傷つくのは貴方だけじゃない。大切な友人の緒方凛も危険な目にあうのよ」
「そんな、緒方さんは関係ありません」
「そんなのどうだっていいの。七条さまの婚約者になれるのならどんな手も使う。──さあ、早く決めなさい」
自分だけならいい。
でもきっと断ればふたりは凛にも危害を加える。
それに、やっと手に入れた幸せを失いたくなかった。
悲しい秘密を抱える時雨のために花嫁修業も頑張りたい。
時雨とふたりで甘味を食べて、好きな花を育てたい。
叶えたい望みが、脳裏をよぎる。
小夜は息を吸い込むと、まっすぐに一華を見つめた。
「絶対に譲りません……!わたしは旦那さまと約束したんです。一緒に幸せになろうって!」
無我夢中で大声で叫ぶと、一華と舞子は僅かに瞠目した。
舞っている埃のせいで、咳をこんでいると、急に手を離されて落下する。
床には木材も置かれていて、背中にその角が当たり、痛みを感じた。
「……うぁ」
苦しんでいると、一華は背を向ける。
「そう。なら貴方にもう頼まないわ。ずっとここでいたらいいのよ」
ちゃらんと金属の音がして、見上げると彼女の左手には鍵があった。
施錠をして閉じ込めるつもりなのだと理解して、追いかけようとするが身体中に痛みが走り、動けない。
「行きましょう、舞子さん」
「もう、よろしいのですか」
「ええ。放っておけば、その内弱るわ。衰弱すれば花嫁なんてなれないもの」
ふんと鼻を鳴らして出て行こうとしたとき、地鳴りが聞こえた。
ガタガタと小屋が揺れて、棚から物が落ち始める。
「な、なんなの? 地震?」
「一華さま、とりあえず外に──」
舞子が先導して扉を開くと、そこには巨大な狐の姿があった。
血のように赤く染まった目。
鋭い歯は剥き出しにしていて、こちらを威嚇していた。
その存在感から狐というより、狼にも見える。
「ひっ……」
ふたりはあまりの恐怖に腰を抜かして座り込んでしまった。
ガルガルと喉を鳴らして、ゆっくりと近づいてくる。
まるで獲物を食らう直前のようだ。
(あれは……)
見覚えのある赤い目と、肌に感じる強い霊力。
小夜は重い足を必死に動かして、立ち上がると、狐の方へと向かう。
狐は呆然とするふたりにすぐにでも飛びかかる勢いだ。
鋭い爪が生える前足を地面から蹴り出した瞬間、小夜はそこに飛びついた。
「やめてください!──旦那さま!」
訴える声に狐の動きはぴたりと止まる。
巻き起こる風で吹き飛ばされそうになるが、必死にしがみついた。
やがて風が収まり、前足は静かに地面へと降ろされる。
「離せ、小夜」
(やっぱり旦那さまだったのね)
一華たちを襲おうとした狐は、凶暴化した時雨だった。
話では我を忘れてしまうと聞いていたが、小夜の声が届いて、僅かだが意識が奇跡的に戻ったようだ。
「離しません!」
「小夜を連れ去り、傷つけたのはあいつらなんだろう。同じ苦しみを与えてやる」
「ここでお姉さまたちに手を出せば、旦那さまも同罪です!わたしは大丈夫ですから、どうか、どうかやめてください」
「大切な婚約者を失う寸前だったんだ。罰を与えなければ僕の気が済まない」
「罰ならばきっと他にも選択肢はあります!わたしはこれからも優しい旦那さまが隣にいてくださるだけで幸せです。だから、お願い……」
「……っ」
時雨は泣きじゃくる小夜に気がつくと、ゆっくりと目を閉じた。
すうっと煙が巨大な身体を包み込む。
しばらくして、そこから現れたのは人間の姿の時雨だった。
「旦那さま……!」
時雨は怪我を負っている小夜を見つけて、ひゅっと息を吸い込んだあと、そっと抱きしめた。
「小夜、本当にごめん。……ありがとう」
涙ぐむ時雨を慰めるように、頬をそっと寄せる。
「時雨さま!水園小夜!」
少し離れた場所に自動車が止まり、中から律が出てきてこちらに駆け寄ってくる。
座り込む一華と舞子、そして物置小屋の破損。
律は見渡して状況を確認すると、傷だらけの小夜に視線を向けた。
「……もしかして君が時雨さまを止めたのか?」
息を切らしながら尋ねる彼に小夜は首を横に振った。
「いえ、わたしはただ想いを旦那さまに伝えただけです」
「……? それは一体どういうことだ」
眉間に皺を寄せて、詳細を尋ねる律に困っていると、時雨がこほんと咳払いをした。
「律、あとできちんと説明するから。ひとまず小夜の治療をしないと」
「え、ええ。それもそうですね。……彼女たちはいかがなさいますか」
時雨の腕の中からふたりの様子をうかがう。
どうやら凶暴化した狐の正体が時雨だと信じられないようで、唇をわなわなと震わせていた。
「警備隊を呼んで連行してもらう。彼女たちは小夜を誘拐して怪我を負わせた。立派な犯罪だよ」
「かしこまりました。手配いたします」
「僕は小夜と一緒に屋敷に戻る。ここは任せてもいい?」
「はい」
時雨はありがとう、と伝えると背を向けて歩き出す。
(良かった……。本当に良かった)
小夜は未だ身体に残る薬品の効能と疲労感のせいで、再び眠りについた。
◆
ゆっくりと目を開けると、見覚えのある木目の天井が視界に入る。
温かく包み込む布団は昨晩、小夜が使用したものだ。
(戻ってきたのね、七条家の屋敷に)
「小夜、具合はどう?」
視線だけを左側へ移すと、時雨が心配そうにこちらを覗き込んでいた。
「旦那さま……。はい、大丈夫です。ご心配をおかけして何と詫びたら良いか」
「君は何も悪くない。だから気にすることなんてないよ」
眠っている間に無意識で人間の姿になったようだ。
ゆっくり起き上がろうとすると、そっと背中に手を添えて支えてくれた。
「起きて大丈夫?」
「はい。あの、旦那さま。どうしてわたしが連れ去られたことをご存知だったのですか?」
人気のないあの場所で誘拐されるのを目撃した者はいなかったはず。
それなのに、どうして凶暴化して居場所を突き詰めたのか。
時雨は繃帯が巻かれた小夜の手にそっと触れながら口を開いた。
「運転手が小夜が来ないことを不審に思って周囲を捜索したんだ。そしたら、彼女たちに連れ去られるところを目撃したらしい。それで急いで連絡をくれたんだ」
「そうだったのですね……」
運転手がいなければ小夜は今頃、どうなっていたかわからない。
体調が回復したら礼をしなければ。
ふと、影が落ちたかと思えば小夜は時雨に抱き寄せられた。
「小夜が連れ去られたと知って、順番を通り越して怒りで凶暴化してしまった。君が呼びかけてくれなければ間違いなく彼女たちを傷つけていた。そうしたら僕は今、ここにいない」
小夜の肩に触れている彼の手は震えていて、心情を察すると胸が切なく締めつけられた。
そんなつらい顔は見たくない。
いつだって望むのは、花が咲き誇るような笑顔だ。
小夜は彼の代わりに、笑った。
「旦那さまがわたしを救ってくれたように、わたしもお支えしたいとずっと思っていました。またこうして一緒にいられるだけで幸せなんです。だから、そんな顔しないでください」
「……ありがとう。必ず君をもっと幸せに笑顔にすると誓うよ。だから傍にいてくれる?」
「はい、もちろんです。わたしも旦那さまをお慕いしていますから」
時雨は小夜の答えに嬉しそうにして笑みを浮かべた。
「好きだよ。僕の愛しの婚約者──」
大切なひとと共にいられる奇跡を噛みしめながら小夜は、目を閉じたのだった。