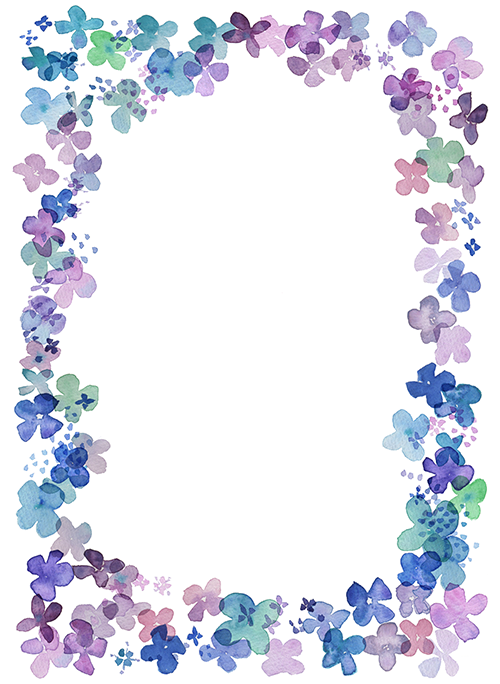泥のように眠った私が次目を開けると星影が東の空にあった。まずい、流石に寝すぎた。丸一日を睡眠で潰してしまった後悔で寝起きから気分が落ち込む。ふと隣を見ると、私より先に起きていた君が小箱と燭台を持っていた。私が寝ている間に街を探索したのか横には水と食料も置いてあった。申し訳ないと思いながらも、喉の渇きに耐えかねて水を一口頂戴する。君は特に何も咎めず、むしろおにぎりも差し出してきた。至れり尽くせりすぎてちょっと怖い。おにぎりを口に含むと、塩気の奥にほんのり甘みがあって噛めば噛むほど鮭の旨味が口いっぱいに広がる。あまりの美味しさに感動していると、おにぎりの包装を片付けようとする君の手元で小箱が軽い音を鳴らす。箱の側面は材質が違うようで、私は巫女が夜になると灯してくれた燐寸を思い出した。
「燐寸ですか?」
「本当はチャッカマンとかあったら良かったんだけどな、売り切れだったから仕方なくマッチを買った」
「何に使うんですか?」
ちゃっかまんが何かは分からなかったけどそれは後回しだ。燐寸は明かりを灯すのに使うのだろうか、でもここ二日夜は明かりなしで生活してきたし今更という感じではある。君は何やらやりたいことがあるようで、私を立たせると付いてきてと一言。またあの洞窟に帰るのかと思ったら少し違った。君は分かれ道でもう歩きなれた右の道へ進もうとする私の腕を掴んで暗い岐路を選ぶ。私は訳の分からないまま取り合えず付いていくと、唐突に蛍光色の光がゆらゆらと目の前を過ぎ去る。
「ひえぇ」
間抜けな声を出して腰を抜かす私に君は怪訝そうな視線を送る。
「ただの蛍だろ」
「妖怪ですか?私そういう類は初めてで……」
心臓の鼓動が煩い。都会に住んでいれば妖怪は普通に出くわすものなんだな、田舎の小さな馬房のような家に住んでいて一度も出会ったことのない謎の飛行物体に私は柄にもなく怯え散らかしている。反射的に目を瞑ってその場で蹲ると、近くの地面が軽く振動した。成人男性に似合わない小さなジャンプだった。
「おっ、意外と熱くないんだな」
「ななな何する気ですか」
「何って折角なら見せてやろうと思って。初めてなんだろ、その反応」
「い、いいですいいです。遠慮させていただきます!」
未知の生物は誰だって怖い、特に光るというなら。声にならない悲鳴をあげながら情けない格好で後ずさりする私に、にやりと含みのある笑みを浮かべた彼は迫ってくる。こんな状況でも無駄に顔がいいので、さながら浪漫小説のワンシーンのようだ。絵になっていて腹が立つ。
ついに距離が三十センチほどになって堪忍した私が両手をあげる。君は両手の間に蠢いていたそれを解き放つ。
星が舞い降りてきたようだった。
不思議と先ほどの恐怖心は薄れて私は、憑りつかれたようにたった一つの光に見入ってしまう。
祭りの提灯とも町の灯りとも違う、誰かを呼ぶような切実で儚い光はゆったりと舞いながら空へと昇って行った。
「ほら、何も怖くない」
「襲われませんか」
「うん」
「……本当ですか?」
私が訝しむ気持ちと冗談を半分ずつ滲ませながら問うと、君は耐えきれなかったように吹き出した。私はこの反応を知っている、私があまりにも世間知らずの田舎者すぎて呆れているのだ。不満だけれども、そういう顔をするということはまるで水の中を揺蕩うように空を泳ぐこの光は無害ということを暗示している。私はほっと胸を撫でおろして、それでも許していないことを伝えるためにじとっと睨んでおく。
「今、馬鹿にしましたね。田舎者だって」
君は視線を逸らした後「いや真の田舎者の方が蛍を知っているというか。別に馬鹿にしてるわけではなくて……」と何やらごにょごにょと言い訳を羅列するが何一つ私の心を動かす言葉はなかった。最終的には彼が折れて謝ってきたのでひとまずは許すとしよう。
「さ、こんなところで腰抜かしてる場合じゃないよ。蛍がいるってことは目的地はもうすぐだから」
「誰のせいで腰を抜かしたと……」
「誰のお陰で食料を調達できたと?」
確かにそれはそうだ、私は言い返したい気持ちをぐっと堪えてまた歩き始める。蛍というのは一匹だけではなかった、奥に進む度に一匹また一匹とその光は増え続け開けた場所に出た時には数百匹いや少なく見積もっても千はいる。若緑の光は所狭しと重なり合い、ぶつかり合い、光ったり、消えたり、昇ったり、止まったりを繰り返しながら浮遊する。幻想的な空間だった。あまりに浮世離れした世界に私は言葉を失う。ふと見た隣の君の指先に留まった蛍が、薄い皮膚を透かしている。赤く染まった皮膚は心なしか心臓の鼓動に合わせて震えているように見えて、思わぬところでこの世のものとは思えない男の生を感じた。
「綺麗ですね」
「ご機嫌は治りましたか、お嬢様」
伺うように、それでいて普通なら茶目っ気を含みながら言うところを不愛想に言うのが君らしい。
「うん」
珍しく私が素直に認めると、君は一瞬ひるんだように眉をあげた。私は表情を崩す。
「上機嫌だよ、連れてきてくれてありがとう」
「……」
興奮のあまりつい砕けた言い方になってしまった。黙りこくる君に首を傾げながら暗闇の先へと進む。そこには大きな岩と静かに流れる浅い川があった。滑らないように慎重に歩くと小石が沢山敷き詰められた比較的平坦な場所で立ち止まる。君はその場でしゃがむとポケットにしまっていた蝋と燐寸を取り出した。ちちっという音と共に火が生まれるのは毎回慣れることなく魔法みたいだと思ってしまう。ぽっと闇に蛍とはまた違う光が灯った。風で揺れる火がようやく安定すると、端正な顔はこちらに向けられた。
「さて問題です、俺たちは今から何をするでしょうか」
「火遊びは辞めてくださいね。昔、神社に来た子供がふざけて神木に火をつけたことで大変な目に遭ってましたので」
「……大変な目とは」
「それ聞きます?」
「いや、いい。それに火遊びはしない」
彼は何を想像したのか身震いをして全力で否定をする。実際、祟られることはなかったにしろ守銭奴な神主から相当な額を請求されたに違いない。私は質問に答えようと再び思考を凝らすが、火遊び以外に思い浮かぶものはなかった。
私が首を振ると、彼は蝋燭の出てきた反対側のポケットからこよりを二本取り出した。私は目を細めながらそれをじっと観察する。どこかで見たような。
「あっ、線香花火ですか」
「正解。祭りで手に入れたやつ、急いでやる必要もないけれど、なるべく思い出が鮮明なうちにやった方がいいかなと思った」
そう言うと君は私に密着してこよりを一本渡してくる。私は顔を顰めて彼を避けた。彼がどうしてと聞いてくるので私は少し恥じらいながら答える。
「湯浴み、してないです」
「ゆあみ……?あぁ、風呂のこと」
こくこくと頷き自分の服の匂いを嗅ぐ。血だらけの着物は流石に着続けられなくて、君がくれたワンピースを着ているが一夜着ただけでも汗はちゃんと染みている。真夏ということもあり蒸れるものは蒸れるので予想通りきつくはないけれど、生乾きの手拭いのような嫌な匂いがして拳三つ分また離れる。彼はくだらないとばかりに鼻で笑った。
「そんなの俺も同じだろ。それにくっついていないと、隙間から風が漏れて炎が消える。嫌かもしれないけど大人しく肩を寄せておけ」
「うう……」
隙間風で今にも消えそうな蝋燭の灯を見せられてしまえば距離を詰める他なかった。私は仕方なく肩を青年の腕に預ける。ばれないように君の匂いも嗅いでみたが、生ぬるい真夏なのが嘘のように春の花畑の匂いがした。ほのかに柑橘の匂いもするので香水なのかもしれない。しかし、俳優とは体臭にまで完璧を求められるのか。何だか知れば知るほど生きづらそうな世界だなと感じる。何気ないことで改めて当たり前に隣にいる場違いすぎる顔面の持ち主は、茶の間では知らない人もいないくらい有名な人間なんだよなと思い出させられた。
これは乙女としてのプライドが傷つく。口を尖らしながら見上げるとへそを曲げた私を気にすることなく、色のない方の先端を炙るんだと教えてくれた。
「持ち手は端っこな」
「そんなの言われなくても分かりますよ……」
「いいや、箱入り娘はいつ何をしでかすか分からないからな」
「透くんは過保護な保護者ですか?」
「引火したら困るのは誰だと思ってる?」
それは私と透くんですが……。言いくるめられたのが悔しくてぶすくれた顔のまま揺れる炎に視線を戻す。隣の手の動きに合わせて私も和紙の先端を燃え盛るものに近づけた。
「「せーのっ」」
同時に白い紙を炎の中に入れる。焦げる匂いと共にぱちぱちと軽い音が鳴り始めた。周りには沢山の光が飛び交う。仄暗い世界の中で君の横顔が淡く照らしだされる。最初のような完璧スマイルよりも、今みたいにほんのり汗ばんだ頬を緩ませているくらいがいいのにと常々思う。しかし需要と供給という言葉があるように、彼は需要があるから王子様の仮面を外せない。世間と私の美意識はかけ離れているようだ。そしてこの場合私が悪食となる。
「阿保な顔してぼうっとしてると見逃すよ」
ハッとして手元を見ると火花が散り始めていた。蛍のお尻よりも鮮やかな色が小さな打ち上げ花火のように花開いては落ちていく。火花があまりにも美しく儚くて思わず反対の手で零れ落ちた光を掴もうとしたら、君に止められた。火傷したら危ないかららしい。私は大人しく二つの光を見つめる。比べると君の花の方が大きく咲いていて羨ましかった。
「知ってるか、線香花火は人の一生を表すんだ」
突然、独り言のような声量で語り出す君。私は虫の声と火花の音にかき消されてしまわないように耳を澄ます。
「蕾は人生のスタートライン、牡丹はよく人生の分岐点と言われるやつだ。迷いながらも間違えながらも自分の道を探して進んでいく、松葉は山場を乗り越えた人生の最盛期、そして散り菊は静かに散りゆく最期」
「牡丹って私と同じですね」
散りゆく花を見ながら私は顔を綻ばせた。今は丁度牡丹くらいだろう。ボタンと牡丹、偶然だとしても親近感が湧いてしまう。
遠くを見つめた。反対側の山にあるはずの小さな襤褸小屋を思い浮かべながら呟く。
「私の人生も今きっと牡丹です。迷いながら間違えながら自分の道を探しています。一番苦しくて、一番鮮やかな時間を過ごしています」
君の言葉では人生の最盛期は松葉らしいが、私にとってはそうではないと思う。苦しいのも迷いも全部含めた今が生きてきた中で最も眩しかった。これ以上の幸せをうまく想像できない私にとって、人生の盛りはこの瞬間なのだ。
ボタンの由来は、ただの釦だ。君の袖で取れかかっていた金ボタンから名前をつけられた。
それでも、
「私はボタンという名を冠することができて幸せです」
私は喜色満面に溢れた。意味が違ったとしても同じ響きなのは嬉しい。喜ぶことができるのは、名前があるからだった。
「透くん、私に名前をくれてありがとうございます」
目の前の二つの目が見開かれる。数秒の間、全ての表情が固まったそれは緩やかに赤く染まっていった。口元がむず痒そうに動いている。そんな反応をされるとは思わず、私の方も照れてしまった。頬を掻きながら視線を君から花火へと外す。
「へへ、改めて言うと照れ臭いですね」
「俺の方こそありがとう」
「えっ……」
唐突な感謝の言葉に動揺する。油の切れたロボットみたいな動きで首を傾げた。
「私、何かしましたっけ」
「……自覚無いのかよ」
「はい、透くんに感謝することは沢山あっても感謝されることはないような」
「勿体ない。折角有名俳優に感謝されたなら、弱みを握ったことに喜べばいいのに」
私は言葉通り阿呆のように口を大きく開けて君の言葉を理解しようとした。あのことかと思い当たることが一つあった。先日の公園での出来事か。しかしあんなこと弱みという弱みでもないだろう、あれをカウントするのであったら私はもう何度君の前で襤褸を出しているのやら。
それに弱みを握ったことを喜ぶってどうして喜ぶのだろう。別に感謝されるようなことをしていたとしてもそれは君の弱みになるのか。それを世間は弱みとして利用するのか。理解する努力は一応してみたが、どう考えたって君の言葉を消化できない。
「自分が有名俳優だという自覚はあるんですね」
「そこじゃねえよ。ただ俺の情けない姿を散々見てきたお前が今業界にこの情報を売ったら俺の今まで築き上げてきたキャラは崩れる。お前は特ダネを提供した人間として報酬がもらえるだろう」
「いやいや、関係ないですよ」
今度は彼がきょとんとする番だった。私は最早笑ってしまう。何を言っているのかと思えば、予想を超えるしょうもないことだった。
「だって私の目の前にいるのは俳優の相島透じゃなくて、ただのぶっきらぼうで愛想の欠片もない、けれど誰よりも真っすぐな、面倒くさくて人間味のある相島透ですもの」
君と出会った頃を思い起こした。あれほど精巧に表情筋を操れる者はきっと世界でも片手に収まるほどしかいないだろう。綻びを見つけるまでは、よもや完璧御仁の正体がこんな人間だと思いもしなかった。
「私は今、一般人の相島透の情けない姿も珍しく感謝する姿も知っていますが、俳優の相島透さんの情けない姿は一度も見ていません。少なくとも取材のときの君はきらきらと輝いていて王子様を演じきっているように見受けられました」
しかしそれはあくまでも君が努力して作り上げた分厚く巧緻を極めた仮面であって、本来の君ではない。
話によると人は弱みを握るとその襤褸を広め、他者を落とし自らの地位を上げるらしい。
でもそんな汚い人間も知っているだろう、どれだけ自分の地位をあげたところで人は完璧にはなれない。完璧を追い求めようと藻掻くことはできても、その頂にたどり着くことは誰一人として叶わないのだ。
結局自分も同じような運命を辿るのであれば、私は君の強いところも脆いところも大切にしまっておきたい。
「人なら一つや二つ、弱みがあって当たり前です。弱みがあるから、支え合えるんです、愛おしいんです」
何より君の地位を落とそうだなんて思えなかった。こんな不器用な生き方で、息継ぎもままならないまま必死に藻掻いている人をどうしたら見捨てることができるというのか。全く想像力が豊かにもほどがあるだろう。
君は俳優の仮面を取り外した自分のことを世に広めればいいと私に言っている。
けれど私にとって、俳優の相島透とここにいる相島透は別人だった。同じ人物として扱うには、あまりにも惜しい。前髪越しに君の瞳を盗み見る。下睫毛が戸惑いを体現するように震える。一挙手一投足なんて言葉では足りない。寝ぐせではねたままの髪先が風に揺れるのも、次々と変わっていく口角も、綺麗だなと思った。
私にとって俳優の相島透と相島透は同じ人物ではないからマスメディアに情報を流すことはない、もしかしたらそれは建前なのかもしれない。
胸に手を添えた。心臓が歪な音を立てながら鼓動を刻む。
私はこんなにも綺麗な君を、世間に知られたくない。
液晶越しで、彼の顔だけしか興味ない人が、君のぜんぶを理解しないでほしい。
私だけでいい。君の醜い姿も、弱い姿も、本当は誰よりもあたたかい姿も、私だけが分かっていればそれでいいのに。
目と鼻の先にある端正な顔とは釣り合わない、醜い欲望が自分の中で沸々と湧き上がるのが確かに感じ取れる。
口に出したいけれど、口にしてしまえば最後、私たちの関係は破綻するだろう。
だから、誤魔化すように笑った。冗談めいた声で、嘘を吐いた。
「ね、だから私は俳優の相島透さんについて知ってる情報はほとんどないんですよ。売る情報がないので私は貧乏人のまま相島透の隣にいます。残念、報酬ってどのくらい貰えたんでしょうねぇ。家何件くらい建てれますか?」
目の前の菊が散ってしまった。最後に一つ、弾けたあと、火の玉はぽとりと足元に零れる。
見つめるものがなくなって視線を横に向けると、君も私を見つめていた。その瞳は珍獣でも見つけたような驚きに満ちている。先ほどの感謝はどうした、そんな目を向けないでほしい。
「私、何か変なこと言いましたかね?」
「……いや、何と言うか」
言葉の続きはくぐもった声で聴きとれない。何よりこの沈黙が気まずかった。臭いことを言ったなと思ったら笑い飛ばすなり、感動したなら目尻を濡らすなりしてほしい。何でもいいから表情変化が欲しい。それだと言うのに、君は驚いた顔をしてから顔を逸らして無言を貫く。こちらとしても次に何と言えばいいのか、判断がつかなかった。聞こえないくらいに小さくため息をついて仕方なく空を見上げた。小さい頃から変わらない、田舎の空。夜の光たちの中で、ひと際大きく存在感を放つあれが月なのだと幼い頃湯浴み場に行くときに教えてもらった。日によっては奇妙な形をしていたり、妙に楕円がかってたりするが、今日は欠けることなく真っ白な光を最大限に注いでいる。
ふふと笑って、空を指さす。ほんの冗談のつもりだった。
「今日の月は綺麗ですね」
びくっと肩を震わせる透くんとようやく視線が交わる。君は先ほどと変わらず、私をこの世のものかと疑う目で見つめてくる。
「お前、意味分かって言ってるの?」
「さぁ、何のことでしょう。まあ、夏目漱石の本なんて数冊しか読んだことはありませんけどね」
「あんまり冗談言ってると本気にするぞ」
突然、澄んだ瞳に獣が宿る。今度は私が驚く番だった。そんな顔できるんだ、果たしてこれは『俳優相島透』なのか『相島透』なのか。見極めようとするが、彼は考える暇すら与えてはくれない。じりじりと距離を詰める綺麗な顔に耐えきれなくなって、掌を支えに背中を仰け反る。全身で警報が鳴っていた、これは危ない。私は引きつりそうな顔に辛うじて、へらりと笑いを張り付けた。
「本気って、貴方が本気を出したらひとたまりもないでしょう」
「嗚呼、本気は本気だ」
「……透くんもどうせ私と同じ箱入り息子ですからね、大したことはできないでしょう。それに大人気俳優様となれば引く手数多でしょうからこんな3日も湯浴みをしていない女、」
何かが唇に触れた。否、その何かとはもう分かり切っていた。だって、瞬きする前にいた君が目の前から消え、代わりに柔らかそうな黒い髪が私の視界を覆ったからだ。頭上から花束みたいな甘い香りが降り注ぎ、長い睫毛は伏せられたまま頬を掠める。たった一瞬、触れたものは名残惜しそうに離れる。近すぎて合わなかったピントがようやく合った。ほんのり朱に染まった耳たぶと、気まずそうに逸らされた視線が明らかにいつもとは違う雰囲気を醸し出す。
「何、してるんですか」
「それ聞きます?」
私が言った言葉が特大ブーメランとしてそっくりそのまま返ってくる。言い返そうとしても、今の私にはただ瞬きをして状況を飲み込もうとすることしかできない。今何が起こった、分かっても解らなかった。頭の中では5w1hが渦巻く。
いつ、どこでは今、ここで。ここまではいいだろう。
では、誰が何をどうした。
相島透が、唇を、寄せてきた。
いやいやいやいや何で?どうしてそうなる。思わずセルフ突っ込みが炸裂する。
上がった息を落ち着かせようと、深呼吸をしてみる。その度に君を纏う花の匂いがもれなく肺を満たして落ち着こうにも落ち着けやしない。もしかしてと思い、両手を顔に添えると私も笑えないくらい顔が熱かった。
君は口を尖らせながら、目線は地面に向けたまま喋る。
「だから言っただろ、本気にするぞって。今更後悔したって遅いからな」
「……はしてません」
「は?」
「後悔はしてません、でも怒ってはいます」
睨め付ける私は本気で心配をしていた。暗がりで遠くまでは見えないけれど、取り合えず人気はなさそうだ。それにしてもこんな大胆な行動をされると困るのは君なのだ。
「君は人気俳優なんでしょう、自覚があるなら行動にも気を配ってくださいよ。そんなことをして誰かに見つかれば」
「俳優の俺と今の俺は別だって言ったやつは何処の誰だよ」
「んぐっ、それとこれとは違います!」
嗚呼、取り返しのつかないことをしてるなぁ。馬鹿な若者だ、本当に。冷静になりきれない心よりも、今は一周回って状況を他人事として捉えている頭を使うことにする。
私は両手で顔を覆いながら、演者のようにわざとらしく噓泣きをした。
「それに私の初接吻を……簡単に奪って……。貴方にとってはもう何十人目かもしれませんが、私にとっては初めてなのですよ!風の噂で初キスはレモンの味と聞きましたが、それを味わう余裕もなく終わってしまいました」
「味わうって、お前なぁ」
「ちなみに噂は本当なのかだけ教えてください」
「……普通に歯磨き粉の味だった」
「引っ掛かりましたね、透くん私以外の女とキスしたことあるんですねぇ」
「なっ……面倒くさいな、お前」
「ふふ、突然された仕返しです。これくらいしないと気が済みません」
よかった、普通に会話できている。先ほどの甘い空気は一連の流れで消え去って私は胸のつかえがとれた。肩の力を抜くと、小さくなった蝋燭の火に息を吹きかけて消す。
「さぁ、行きましょう。もう夜も遅いので明日のために寝床を探さなければ」
立ち上がって、きょろきょろと辺りを見回す。まるで先ほどの出来事はなかったように。夢だったのかと錯覚させるほど、自然に。
なるべく普通を装わなければならない。私は君の口から発せられる言葉を恐れた。
しかし、ここで素直に動かないのがこの男なのだ。その場を離れようとする私の裾が何かに引っかかる。足元を見ると、血の巡りのよい手が私を引き留めていた。
「なぁ」
君の声が硬い。嫌な予感がする。それでも私は平然を装い「何ですか?」と面倒くさそうなトーンで尋ねた。
どこまでも甘かった空気、私は次に告げられる言葉を悟っていた。それを拒むように冷たくあしらう。ほとんど答えのようなものだった。
俯いていた頭が持ち上げられ、表情が露わになる。
相島透は苦しそうに、でもそれを誤魔化すように笑った。
「お前は、俺のことが嫌いか?」
怯えたような聞き方だった。緊張で気づかなかったが地面を思い切り掴んでいたらしい。爪の間に小石や泥が詰まって痛みを伴う。ふっと指先まで入った力が一瞬にして抜ける。「好きだ」とは言われなかったことに安堵する私はきっと悪い女だ。
接吻をされておいて、その行為をないものとされたら誰でも傷つくだろう。でも私は甘えるつもりでいた、無いものとしても君は優しいから許してくれるかと思った。
相島透は優しい男だが、弱みを売るのは許せても、接吻を忘れられるのは許せないらしい。
こういうところが、ずるくて少し憎い。
私は諦めて引き上げていた表情筋を脱力させた。瞼すら重くて瞳は閉じたまま、彼の表情は見えない状態で呟く。
夏の虫の声でかき消されてしまえばいい、こんな願い。
蝉にも脳はあるが、惜しくも空気を読むという行為はできないらしい。深く息を吸い、口を開いた瞬間、虫の大合唱が煩い夜にひと時の静寂が訪れた。
「もし私が死んだら」
「何故死ぬことになる、俺の質問にこた」
「私のことは忘れてください」
それが私なりの答えだった。私が絞り出すことのできる唯一の言葉だった。
人間いつ死ぬか分からない。死ぬことになってても今こうして生きているように、当たり前に生きる明日がないことも時にはある。腹にある爆弾に触れようとした手の神経が伝達不能になったように力なく地面に落ちる。君はまだ知らない、私の中で渦巻くこの爆弾の存在を。
そんな君に向けた私の告白だった。
君の苦しみに触れて、あたたかさに触れて、殺していた欲望がただ君の幸せだけを願って、願って、願い続けた私なりのラブレターだった。
君と手を繋ぎ同じ歩幅で同じ方向を向いて歩む未来ではなく、君が走り出せるようにそっと背を押すだけの存在になることを選んだ。
私が明日死ぬとしたら、君の人生から私を消してほしかった。
私のことは忘れて、また元の光へ続く道に、成功に繋がるレールの上を歩いて欲しい。
きっと私が存在する人生は茨の道だ。
ただの茨の道なら君の元の人生とそう変わらない。しかし、こちらにはたどり着く先に光がある確証はない。むしろ傷ついて立ち上がれないほどの深く病んだところで、明るい未来があったら奇跡だろう。現実は甘くも簡単でもない、真っ暗な世界が広がっているかもれない、茨の道は一生続いて目的地にたどり着くことすらできないかもしれない。
祭りの日に言った言葉が全てだった。
「私がいる限り貴方は苦しいですよ」、何度言ったところで君はそれを否定して苦しい選択でも一緒に歩もうとしてくれる。
だから君を突き放しきれない。
嫌いだと言ってしまえば簡単なのに、我が儘な小娘はそれが怖い。
相島透の存在はもう既に少女の世界の真ん中にあるからだ。
全くどうしてくれるのだ。どうしてたった数日の間に私の心に潜り込んで、私の叫びを開放してしまったのだ。
私はもう透くんのことが。
「それは……」
君の何か言いかけた口が真一門に結ばれる。私の目はこれ以上何も語れることはないと物語っていた。
私はふわりと触れれば消えてしまう、そんな曖昧な笑みを浮かべた。
「私のことは透くんの夢の中に出てきたことにでもしておいてください」
「……善処するよ」
善処という言葉に容易く折れることはないという気概を感じる。今はその言葉の意味を理解できなくてもいい、いずれ嫌というほど理解する君を想像すると少し気の毒に思える。私は反射的に先ほどは触れることのできなかった自分の腹を撫でた。子宮の代わりに埋め込まれたそれは触れる度に腹膜を刺激し意識が飛びそうなほどの激痛が襲う。唇が嚙み切れて血の味が口に広がる。爆弾がもうすぐ雄叫びを上げる。それに怯えながら生きるのは少々疲れた。全部忘れてしまいたいと思うが、私にはまだやることがあるので簡単に死ねない。
君は私の手を取り、腰を持ち上げた。私も釣られて立ち上がると蝋燭はそのままに私たちは森の奥へと入っていく。
月明かりに照らされた横顔は複雑な顔をしていた。
「また明日しましょう、花火」
つい約束を取り付けてしまう。君は私の言葉に頭二つ分高い位置から見下ろすだけだった。
こんな日々が続けばいいのに。
花火の炎が瞬きの間に幾つ散ったのか、それを忘れて喉までせり上がった言葉は声にはならなかった。声にしようとしても魚の小骨のようにつっかえて、君の耳に届くことはない。
牡丹は永遠には続かない。炎が変わらず燃え続けることはない。
再び始まった蝉の声は水の膜が張っているように遠く、四本の足が砂利をかき分けて芝を踏む音だけが聞える。
私は細く息を吐き、繋がれていない方の細い手首を取る。告白を拒んでおいて、自分から接触するのは我が儘の他ない。しかし、透くんは優しいから自ら振りほどくことはなかった。
曖昧な関係は面倒だ。白黒はっきりつけばいいと思う。君もそれは同じだろう、だからあんなことを聞いてきた。
でも、この感情を言語化する術を私は知らない。
言語化できたとしても、その言葉はきっと君に伝えるべきではない。
故に霧のような返答しかできないのだ。
実態があるようで掴もうとすればするほど分からなくなる、そんな関係から逃れることはできないのだ。
雨風が急に来てもしのげそうな木陰を見つけると、私は堪らずその場に横たわった。考えすぎたのだろうか、どっと疲れが押し寄せてきてもう重力には抗えなさそうだ。
横向きになって低くなった視界では君の顔は見えず、少し泥で汚れたズボンの裾だけが見えた。あちらはすぐには横にならず、座り込んだだけらしい。
会話もなく、聞こえるのは騒がしい蝉と僅かな鈴虫の声だけ。瞼を閉じて、脳を休ませることに集中しよう。
そう思っていたはずなのに、無意識のうちに私は君の名前を呼んでいた。
「……ねぇ、透くん」
「ん、なんだ」
「私は貴方に相応しい人間でも、貴方が触れたいと思えるような人間でもないですよ」
何故だか、目尻から涙が一筋零れた。いけない、いけない。これは子供のようではないか。駄目だとわかっているのに、面倒な女だと自覚しているのに、肋骨のもっと奥が痛くて、溢れた感情を抑えることはできなかった。全身の体液全部に「すきだ」という気持ちが溶け混んで細胞に浸み込んでいく。目を逸らし続けていた三文字はもう飽和状態だった。これは目を逸らすどころではない、逸らそうとしても網膜を支配しているのだ。逸らしようがないではないか。差し伸べられた手のひらに、控えめに頬を摺り寄せる。少し冷たい指先が心地よかった。
「いいよそれでも」
硝子の破片みたいに透き通った声が降り注ぐ。とめどなく流れる涙を隠すように小さく蹲る私、君はくくっと喉を鳴らすと頭をそっと撫でる。滑稽だと思ったか、幼子のように我が儘を言って泣きじゃくる私を。
しかし実際私という人間は、素直になれないし、言いたいこともろくに言えないし、突き放しておいて自らは手放したくないと思ってしまう貪欲な人間だ。
自分自身でも至極面倒な女だと思う。
自分の気持ちにはもう気づいていた。君のことを見る目が変な人から頼れる人、そして一緒にいると心が安らぐ人へと変化していることも解っていた。
でもこれ以上近づけば、私はきっと死にきれない。恋をすれば、腹の爆弾が止まるなんて奇跡は起こらない。私がもうすぐ死ぬことはこの世に生を受けた瞬間から決まっている。
君は今日、私に接吻をした。
でもそれ以上は何も手を出さなかった。
きっとあの表情に込められた思いを察したのだろう。不本意で拒んでいると知っているから、「好きだ」とも「付き合おう」とも言わずただ黙って頭を撫でる。
「……ごめんね」
優しさが、痛い。
真にあたたかい人間は時々凶器となる。見返りを求めない愛が、与えられる人間の心の弱いところに沁みて、罪悪感を駆り立てる。君が綺麗な人間であると分かれば分かるほど、自分の汚さが嫌というほど分からされる。
からからに乾いた喉でようやく絞り出せたのはたった四文字だった。
力を入れていた手を解いて仰向けになった。滲む視界を占める君の顔は逆光でよく見えない。
「謝る言葉はいいから、どうかそのままの君でいて。俺はそれだけで満足だ」
青年の小さな声に、私は再び目元を腕で覆う。今夜は私が弱さを曝け出す番だった。仕方がないと割り切った途端、赤子のように涙が止まらなかった。それこそ最初は声を抑えていたが、次第に君ならいいかという思いが強くなっていって最終的には小さい子みたいに声を上げる。月が西に傾きはじめた頃、私は泣き疲れて意識を手放した。
君は私の寝息が聞こえるまで、撫でる手を辞めはしなかった。
「燐寸ですか?」
「本当はチャッカマンとかあったら良かったんだけどな、売り切れだったから仕方なくマッチを買った」
「何に使うんですか?」
ちゃっかまんが何かは分からなかったけどそれは後回しだ。燐寸は明かりを灯すのに使うのだろうか、でもここ二日夜は明かりなしで生活してきたし今更という感じではある。君は何やらやりたいことがあるようで、私を立たせると付いてきてと一言。またあの洞窟に帰るのかと思ったら少し違った。君は分かれ道でもう歩きなれた右の道へ進もうとする私の腕を掴んで暗い岐路を選ぶ。私は訳の分からないまま取り合えず付いていくと、唐突に蛍光色の光がゆらゆらと目の前を過ぎ去る。
「ひえぇ」
間抜けな声を出して腰を抜かす私に君は怪訝そうな視線を送る。
「ただの蛍だろ」
「妖怪ですか?私そういう類は初めてで……」
心臓の鼓動が煩い。都会に住んでいれば妖怪は普通に出くわすものなんだな、田舎の小さな馬房のような家に住んでいて一度も出会ったことのない謎の飛行物体に私は柄にもなく怯え散らかしている。反射的に目を瞑ってその場で蹲ると、近くの地面が軽く振動した。成人男性に似合わない小さなジャンプだった。
「おっ、意外と熱くないんだな」
「ななな何する気ですか」
「何って折角なら見せてやろうと思って。初めてなんだろ、その反応」
「い、いいですいいです。遠慮させていただきます!」
未知の生物は誰だって怖い、特に光るというなら。声にならない悲鳴をあげながら情けない格好で後ずさりする私に、にやりと含みのある笑みを浮かべた彼は迫ってくる。こんな状況でも無駄に顔がいいので、さながら浪漫小説のワンシーンのようだ。絵になっていて腹が立つ。
ついに距離が三十センチほどになって堪忍した私が両手をあげる。君は両手の間に蠢いていたそれを解き放つ。
星が舞い降りてきたようだった。
不思議と先ほどの恐怖心は薄れて私は、憑りつかれたようにたった一つの光に見入ってしまう。
祭りの提灯とも町の灯りとも違う、誰かを呼ぶような切実で儚い光はゆったりと舞いながら空へと昇って行った。
「ほら、何も怖くない」
「襲われませんか」
「うん」
「……本当ですか?」
私が訝しむ気持ちと冗談を半分ずつ滲ませながら問うと、君は耐えきれなかったように吹き出した。私はこの反応を知っている、私があまりにも世間知らずの田舎者すぎて呆れているのだ。不満だけれども、そういう顔をするということはまるで水の中を揺蕩うように空を泳ぐこの光は無害ということを暗示している。私はほっと胸を撫でおろして、それでも許していないことを伝えるためにじとっと睨んでおく。
「今、馬鹿にしましたね。田舎者だって」
君は視線を逸らした後「いや真の田舎者の方が蛍を知っているというか。別に馬鹿にしてるわけではなくて……」と何やらごにょごにょと言い訳を羅列するが何一つ私の心を動かす言葉はなかった。最終的には彼が折れて謝ってきたのでひとまずは許すとしよう。
「さ、こんなところで腰抜かしてる場合じゃないよ。蛍がいるってことは目的地はもうすぐだから」
「誰のせいで腰を抜かしたと……」
「誰のお陰で食料を調達できたと?」
確かにそれはそうだ、私は言い返したい気持ちをぐっと堪えてまた歩き始める。蛍というのは一匹だけではなかった、奥に進む度に一匹また一匹とその光は増え続け開けた場所に出た時には数百匹いや少なく見積もっても千はいる。若緑の光は所狭しと重なり合い、ぶつかり合い、光ったり、消えたり、昇ったり、止まったりを繰り返しながら浮遊する。幻想的な空間だった。あまりに浮世離れした世界に私は言葉を失う。ふと見た隣の君の指先に留まった蛍が、薄い皮膚を透かしている。赤く染まった皮膚は心なしか心臓の鼓動に合わせて震えているように見えて、思わぬところでこの世のものとは思えない男の生を感じた。
「綺麗ですね」
「ご機嫌は治りましたか、お嬢様」
伺うように、それでいて普通なら茶目っ気を含みながら言うところを不愛想に言うのが君らしい。
「うん」
珍しく私が素直に認めると、君は一瞬ひるんだように眉をあげた。私は表情を崩す。
「上機嫌だよ、連れてきてくれてありがとう」
「……」
興奮のあまりつい砕けた言い方になってしまった。黙りこくる君に首を傾げながら暗闇の先へと進む。そこには大きな岩と静かに流れる浅い川があった。滑らないように慎重に歩くと小石が沢山敷き詰められた比較的平坦な場所で立ち止まる。君はその場でしゃがむとポケットにしまっていた蝋と燐寸を取り出した。ちちっという音と共に火が生まれるのは毎回慣れることなく魔法みたいだと思ってしまう。ぽっと闇に蛍とはまた違う光が灯った。風で揺れる火がようやく安定すると、端正な顔はこちらに向けられた。
「さて問題です、俺たちは今から何をするでしょうか」
「火遊びは辞めてくださいね。昔、神社に来た子供がふざけて神木に火をつけたことで大変な目に遭ってましたので」
「……大変な目とは」
「それ聞きます?」
「いや、いい。それに火遊びはしない」
彼は何を想像したのか身震いをして全力で否定をする。実際、祟られることはなかったにしろ守銭奴な神主から相当な額を請求されたに違いない。私は質問に答えようと再び思考を凝らすが、火遊び以外に思い浮かぶものはなかった。
私が首を振ると、彼は蝋燭の出てきた反対側のポケットからこよりを二本取り出した。私は目を細めながらそれをじっと観察する。どこかで見たような。
「あっ、線香花火ですか」
「正解。祭りで手に入れたやつ、急いでやる必要もないけれど、なるべく思い出が鮮明なうちにやった方がいいかなと思った」
そう言うと君は私に密着してこよりを一本渡してくる。私は顔を顰めて彼を避けた。彼がどうしてと聞いてくるので私は少し恥じらいながら答える。
「湯浴み、してないです」
「ゆあみ……?あぁ、風呂のこと」
こくこくと頷き自分の服の匂いを嗅ぐ。血だらけの着物は流石に着続けられなくて、君がくれたワンピースを着ているが一夜着ただけでも汗はちゃんと染みている。真夏ということもあり蒸れるものは蒸れるので予想通りきつくはないけれど、生乾きの手拭いのような嫌な匂いがして拳三つ分また離れる。彼はくだらないとばかりに鼻で笑った。
「そんなの俺も同じだろ。それにくっついていないと、隙間から風が漏れて炎が消える。嫌かもしれないけど大人しく肩を寄せておけ」
「うう……」
隙間風で今にも消えそうな蝋燭の灯を見せられてしまえば距離を詰める他なかった。私は仕方なく肩を青年の腕に預ける。ばれないように君の匂いも嗅いでみたが、生ぬるい真夏なのが嘘のように春の花畑の匂いがした。ほのかに柑橘の匂いもするので香水なのかもしれない。しかし、俳優とは体臭にまで完璧を求められるのか。何だか知れば知るほど生きづらそうな世界だなと感じる。何気ないことで改めて当たり前に隣にいる場違いすぎる顔面の持ち主は、茶の間では知らない人もいないくらい有名な人間なんだよなと思い出させられた。
これは乙女としてのプライドが傷つく。口を尖らしながら見上げるとへそを曲げた私を気にすることなく、色のない方の先端を炙るんだと教えてくれた。
「持ち手は端っこな」
「そんなの言われなくても分かりますよ……」
「いいや、箱入り娘はいつ何をしでかすか分からないからな」
「透くんは過保護な保護者ですか?」
「引火したら困るのは誰だと思ってる?」
それは私と透くんですが……。言いくるめられたのが悔しくてぶすくれた顔のまま揺れる炎に視線を戻す。隣の手の動きに合わせて私も和紙の先端を燃え盛るものに近づけた。
「「せーのっ」」
同時に白い紙を炎の中に入れる。焦げる匂いと共にぱちぱちと軽い音が鳴り始めた。周りには沢山の光が飛び交う。仄暗い世界の中で君の横顔が淡く照らしだされる。最初のような完璧スマイルよりも、今みたいにほんのり汗ばんだ頬を緩ませているくらいがいいのにと常々思う。しかし需要と供給という言葉があるように、彼は需要があるから王子様の仮面を外せない。世間と私の美意識はかけ離れているようだ。そしてこの場合私が悪食となる。
「阿保な顔してぼうっとしてると見逃すよ」
ハッとして手元を見ると火花が散り始めていた。蛍のお尻よりも鮮やかな色が小さな打ち上げ花火のように花開いては落ちていく。火花があまりにも美しく儚くて思わず反対の手で零れ落ちた光を掴もうとしたら、君に止められた。火傷したら危ないかららしい。私は大人しく二つの光を見つめる。比べると君の花の方が大きく咲いていて羨ましかった。
「知ってるか、線香花火は人の一生を表すんだ」
突然、独り言のような声量で語り出す君。私は虫の声と火花の音にかき消されてしまわないように耳を澄ます。
「蕾は人生のスタートライン、牡丹はよく人生の分岐点と言われるやつだ。迷いながらも間違えながらも自分の道を探して進んでいく、松葉は山場を乗り越えた人生の最盛期、そして散り菊は静かに散りゆく最期」
「牡丹って私と同じですね」
散りゆく花を見ながら私は顔を綻ばせた。今は丁度牡丹くらいだろう。ボタンと牡丹、偶然だとしても親近感が湧いてしまう。
遠くを見つめた。反対側の山にあるはずの小さな襤褸小屋を思い浮かべながら呟く。
「私の人生も今きっと牡丹です。迷いながら間違えながら自分の道を探しています。一番苦しくて、一番鮮やかな時間を過ごしています」
君の言葉では人生の最盛期は松葉らしいが、私にとってはそうではないと思う。苦しいのも迷いも全部含めた今が生きてきた中で最も眩しかった。これ以上の幸せをうまく想像できない私にとって、人生の盛りはこの瞬間なのだ。
ボタンの由来は、ただの釦だ。君の袖で取れかかっていた金ボタンから名前をつけられた。
それでも、
「私はボタンという名を冠することができて幸せです」
私は喜色満面に溢れた。意味が違ったとしても同じ響きなのは嬉しい。喜ぶことができるのは、名前があるからだった。
「透くん、私に名前をくれてありがとうございます」
目の前の二つの目が見開かれる。数秒の間、全ての表情が固まったそれは緩やかに赤く染まっていった。口元がむず痒そうに動いている。そんな反応をされるとは思わず、私の方も照れてしまった。頬を掻きながら視線を君から花火へと外す。
「へへ、改めて言うと照れ臭いですね」
「俺の方こそありがとう」
「えっ……」
唐突な感謝の言葉に動揺する。油の切れたロボットみたいな動きで首を傾げた。
「私、何かしましたっけ」
「……自覚無いのかよ」
「はい、透くんに感謝することは沢山あっても感謝されることはないような」
「勿体ない。折角有名俳優に感謝されたなら、弱みを握ったことに喜べばいいのに」
私は言葉通り阿呆のように口を大きく開けて君の言葉を理解しようとした。あのことかと思い当たることが一つあった。先日の公園での出来事か。しかしあんなこと弱みという弱みでもないだろう、あれをカウントするのであったら私はもう何度君の前で襤褸を出しているのやら。
それに弱みを握ったことを喜ぶってどうして喜ぶのだろう。別に感謝されるようなことをしていたとしてもそれは君の弱みになるのか。それを世間は弱みとして利用するのか。理解する努力は一応してみたが、どう考えたって君の言葉を消化できない。
「自分が有名俳優だという自覚はあるんですね」
「そこじゃねえよ。ただ俺の情けない姿を散々見てきたお前が今業界にこの情報を売ったら俺の今まで築き上げてきたキャラは崩れる。お前は特ダネを提供した人間として報酬がもらえるだろう」
「いやいや、関係ないですよ」
今度は彼がきょとんとする番だった。私は最早笑ってしまう。何を言っているのかと思えば、予想を超えるしょうもないことだった。
「だって私の目の前にいるのは俳優の相島透じゃなくて、ただのぶっきらぼうで愛想の欠片もない、けれど誰よりも真っすぐな、面倒くさくて人間味のある相島透ですもの」
君と出会った頃を思い起こした。あれほど精巧に表情筋を操れる者はきっと世界でも片手に収まるほどしかいないだろう。綻びを見つけるまでは、よもや完璧御仁の正体がこんな人間だと思いもしなかった。
「私は今、一般人の相島透の情けない姿も珍しく感謝する姿も知っていますが、俳優の相島透さんの情けない姿は一度も見ていません。少なくとも取材のときの君はきらきらと輝いていて王子様を演じきっているように見受けられました」
しかしそれはあくまでも君が努力して作り上げた分厚く巧緻を極めた仮面であって、本来の君ではない。
話によると人は弱みを握るとその襤褸を広め、他者を落とし自らの地位を上げるらしい。
でもそんな汚い人間も知っているだろう、どれだけ自分の地位をあげたところで人は完璧にはなれない。完璧を追い求めようと藻掻くことはできても、その頂にたどり着くことは誰一人として叶わないのだ。
結局自分も同じような運命を辿るのであれば、私は君の強いところも脆いところも大切にしまっておきたい。
「人なら一つや二つ、弱みがあって当たり前です。弱みがあるから、支え合えるんです、愛おしいんです」
何より君の地位を落とそうだなんて思えなかった。こんな不器用な生き方で、息継ぎもままならないまま必死に藻掻いている人をどうしたら見捨てることができるというのか。全く想像力が豊かにもほどがあるだろう。
君は俳優の仮面を取り外した自分のことを世に広めればいいと私に言っている。
けれど私にとって、俳優の相島透とここにいる相島透は別人だった。同じ人物として扱うには、あまりにも惜しい。前髪越しに君の瞳を盗み見る。下睫毛が戸惑いを体現するように震える。一挙手一投足なんて言葉では足りない。寝ぐせではねたままの髪先が風に揺れるのも、次々と変わっていく口角も、綺麗だなと思った。
私にとって俳優の相島透と相島透は同じ人物ではないからマスメディアに情報を流すことはない、もしかしたらそれは建前なのかもしれない。
胸に手を添えた。心臓が歪な音を立てながら鼓動を刻む。
私はこんなにも綺麗な君を、世間に知られたくない。
液晶越しで、彼の顔だけしか興味ない人が、君のぜんぶを理解しないでほしい。
私だけでいい。君の醜い姿も、弱い姿も、本当は誰よりもあたたかい姿も、私だけが分かっていればそれでいいのに。
目と鼻の先にある端正な顔とは釣り合わない、醜い欲望が自分の中で沸々と湧き上がるのが確かに感じ取れる。
口に出したいけれど、口にしてしまえば最後、私たちの関係は破綻するだろう。
だから、誤魔化すように笑った。冗談めいた声で、嘘を吐いた。
「ね、だから私は俳優の相島透さんについて知ってる情報はほとんどないんですよ。売る情報がないので私は貧乏人のまま相島透の隣にいます。残念、報酬ってどのくらい貰えたんでしょうねぇ。家何件くらい建てれますか?」
目の前の菊が散ってしまった。最後に一つ、弾けたあと、火の玉はぽとりと足元に零れる。
見つめるものがなくなって視線を横に向けると、君も私を見つめていた。その瞳は珍獣でも見つけたような驚きに満ちている。先ほどの感謝はどうした、そんな目を向けないでほしい。
「私、何か変なこと言いましたかね?」
「……いや、何と言うか」
言葉の続きはくぐもった声で聴きとれない。何よりこの沈黙が気まずかった。臭いことを言ったなと思ったら笑い飛ばすなり、感動したなら目尻を濡らすなりしてほしい。何でもいいから表情変化が欲しい。それだと言うのに、君は驚いた顔をしてから顔を逸らして無言を貫く。こちらとしても次に何と言えばいいのか、判断がつかなかった。聞こえないくらいに小さくため息をついて仕方なく空を見上げた。小さい頃から変わらない、田舎の空。夜の光たちの中で、ひと際大きく存在感を放つあれが月なのだと幼い頃湯浴み場に行くときに教えてもらった。日によっては奇妙な形をしていたり、妙に楕円がかってたりするが、今日は欠けることなく真っ白な光を最大限に注いでいる。
ふふと笑って、空を指さす。ほんの冗談のつもりだった。
「今日の月は綺麗ですね」
びくっと肩を震わせる透くんとようやく視線が交わる。君は先ほどと変わらず、私をこの世のものかと疑う目で見つめてくる。
「お前、意味分かって言ってるの?」
「さぁ、何のことでしょう。まあ、夏目漱石の本なんて数冊しか読んだことはありませんけどね」
「あんまり冗談言ってると本気にするぞ」
突然、澄んだ瞳に獣が宿る。今度は私が驚く番だった。そんな顔できるんだ、果たしてこれは『俳優相島透』なのか『相島透』なのか。見極めようとするが、彼は考える暇すら与えてはくれない。じりじりと距離を詰める綺麗な顔に耐えきれなくなって、掌を支えに背中を仰け反る。全身で警報が鳴っていた、これは危ない。私は引きつりそうな顔に辛うじて、へらりと笑いを張り付けた。
「本気って、貴方が本気を出したらひとたまりもないでしょう」
「嗚呼、本気は本気だ」
「……透くんもどうせ私と同じ箱入り息子ですからね、大したことはできないでしょう。それに大人気俳優様となれば引く手数多でしょうからこんな3日も湯浴みをしていない女、」
何かが唇に触れた。否、その何かとはもう分かり切っていた。だって、瞬きする前にいた君が目の前から消え、代わりに柔らかそうな黒い髪が私の視界を覆ったからだ。頭上から花束みたいな甘い香りが降り注ぎ、長い睫毛は伏せられたまま頬を掠める。たった一瞬、触れたものは名残惜しそうに離れる。近すぎて合わなかったピントがようやく合った。ほんのり朱に染まった耳たぶと、気まずそうに逸らされた視線が明らかにいつもとは違う雰囲気を醸し出す。
「何、してるんですか」
「それ聞きます?」
私が言った言葉が特大ブーメランとしてそっくりそのまま返ってくる。言い返そうとしても、今の私にはただ瞬きをして状況を飲み込もうとすることしかできない。今何が起こった、分かっても解らなかった。頭の中では5w1hが渦巻く。
いつ、どこでは今、ここで。ここまではいいだろう。
では、誰が何をどうした。
相島透が、唇を、寄せてきた。
いやいやいやいや何で?どうしてそうなる。思わずセルフ突っ込みが炸裂する。
上がった息を落ち着かせようと、深呼吸をしてみる。その度に君を纏う花の匂いがもれなく肺を満たして落ち着こうにも落ち着けやしない。もしかしてと思い、両手を顔に添えると私も笑えないくらい顔が熱かった。
君は口を尖らせながら、目線は地面に向けたまま喋る。
「だから言っただろ、本気にするぞって。今更後悔したって遅いからな」
「……はしてません」
「は?」
「後悔はしてません、でも怒ってはいます」
睨め付ける私は本気で心配をしていた。暗がりで遠くまでは見えないけれど、取り合えず人気はなさそうだ。それにしてもこんな大胆な行動をされると困るのは君なのだ。
「君は人気俳優なんでしょう、自覚があるなら行動にも気を配ってくださいよ。そんなことをして誰かに見つかれば」
「俳優の俺と今の俺は別だって言ったやつは何処の誰だよ」
「んぐっ、それとこれとは違います!」
嗚呼、取り返しのつかないことをしてるなぁ。馬鹿な若者だ、本当に。冷静になりきれない心よりも、今は一周回って状況を他人事として捉えている頭を使うことにする。
私は両手で顔を覆いながら、演者のようにわざとらしく噓泣きをした。
「それに私の初接吻を……簡単に奪って……。貴方にとってはもう何十人目かもしれませんが、私にとっては初めてなのですよ!風の噂で初キスはレモンの味と聞きましたが、それを味わう余裕もなく終わってしまいました」
「味わうって、お前なぁ」
「ちなみに噂は本当なのかだけ教えてください」
「……普通に歯磨き粉の味だった」
「引っ掛かりましたね、透くん私以外の女とキスしたことあるんですねぇ」
「なっ……面倒くさいな、お前」
「ふふ、突然された仕返しです。これくらいしないと気が済みません」
よかった、普通に会話できている。先ほどの甘い空気は一連の流れで消え去って私は胸のつかえがとれた。肩の力を抜くと、小さくなった蝋燭の火に息を吹きかけて消す。
「さぁ、行きましょう。もう夜も遅いので明日のために寝床を探さなければ」
立ち上がって、きょろきょろと辺りを見回す。まるで先ほどの出来事はなかったように。夢だったのかと錯覚させるほど、自然に。
なるべく普通を装わなければならない。私は君の口から発せられる言葉を恐れた。
しかし、ここで素直に動かないのがこの男なのだ。その場を離れようとする私の裾が何かに引っかかる。足元を見ると、血の巡りのよい手が私を引き留めていた。
「なぁ」
君の声が硬い。嫌な予感がする。それでも私は平然を装い「何ですか?」と面倒くさそうなトーンで尋ねた。
どこまでも甘かった空気、私は次に告げられる言葉を悟っていた。それを拒むように冷たくあしらう。ほとんど答えのようなものだった。
俯いていた頭が持ち上げられ、表情が露わになる。
相島透は苦しそうに、でもそれを誤魔化すように笑った。
「お前は、俺のことが嫌いか?」
怯えたような聞き方だった。緊張で気づかなかったが地面を思い切り掴んでいたらしい。爪の間に小石や泥が詰まって痛みを伴う。ふっと指先まで入った力が一瞬にして抜ける。「好きだ」とは言われなかったことに安堵する私はきっと悪い女だ。
接吻をされておいて、その行為をないものとされたら誰でも傷つくだろう。でも私は甘えるつもりでいた、無いものとしても君は優しいから許してくれるかと思った。
相島透は優しい男だが、弱みを売るのは許せても、接吻を忘れられるのは許せないらしい。
こういうところが、ずるくて少し憎い。
私は諦めて引き上げていた表情筋を脱力させた。瞼すら重くて瞳は閉じたまま、彼の表情は見えない状態で呟く。
夏の虫の声でかき消されてしまえばいい、こんな願い。
蝉にも脳はあるが、惜しくも空気を読むという行為はできないらしい。深く息を吸い、口を開いた瞬間、虫の大合唱が煩い夜にひと時の静寂が訪れた。
「もし私が死んだら」
「何故死ぬことになる、俺の質問にこた」
「私のことは忘れてください」
それが私なりの答えだった。私が絞り出すことのできる唯一の言葉だった。
人間いつ死ぬか分からない。死ぬことになってても今こうして生きているように、当たり前に生きる明日がないことも時にはある。腹にある爆弾に触れようとした手の神経が伝達不能になったように力なく地面に落ちる。君はまだ知らない、私の中で渦巻くこの爆弾の存在を。
そんな君に向けた私の告白だった。
君の苦しみに触れて、あたたかさに触れて、殺していた欲望がただ君の幸せだけを願って、願って、願い続けた私なりのラブレターだった。
君と手を繋ぎ同じ歩幅で同じ方向を向いて歩む未来ではなく、君が走り出せるようにそっと背を押すだけの存在になることを選んだ。
私が明日死ぬとしたら、君の人生から私を消してほしかった。
私のことは忘れて、また元の光へ続く道に、成功に繋がるレールの上を歩いて欲しい。
きっと私が存在する人生は茨の道だ。
ただの茨の道なら君の元の人生とそう変わらない。しかし、こちらにはたどり着く先に光がある確証はない。むしろ傷ついて立ち上がれないほどの深く病んだところで、明るい未来があったら奇跡だろう。現実は甘くも簡単でもない、真っ暗な世界が広がっているかもれない、茨の道は一生続いて目的地にたどり着くことすらできないかもしれない。
祭りの日に言った言葉が全てだった。
「私がいる限り貴方は苦しいですよ」、何度言ったところで君はそれを否定して苦しい選択でも一緒に歩もうとしてくれる。
だから君を突き放しきれない。
嫌いだと言ってしまえば簡単なのに、我が儘な小娘はそれが怖い。
相島透の存在はもう既に少女の世界の真ん中にあるからだ。
全くどうしてくれるのだ。どうしてたった数日の間に私の心に潜り込んで、私の叫びを開放してしまったのだ。
私はもう透くんのことが。
「それは……」
君の何か言いかけた口が真一門に結ばれる。私の目はこれ以上何も語れることはないと物語っていた。
私はふわりと触れれば消えてしまう、そんな曖昧な笑みを浮かべた。
「私のことは透くんの夢の中に出てきたことにでもしておいてください」
「……善処するよ」
善処という言葉に容易く折れることはないという気概を感じる。今はその言葉の意味を理解できなくてもいい、いずれ嫌というほど理解する君を想像すると少し気の毒に思える。私は反射的に先ほどは触れることのできなかった自分の腹を撫でた。子宮の代わりに埋め込まれたそれは触れる度に腹膜を刺激し意識が飛びそうなほどの激痛が襲う。唇が嚙み切れて血の味が口に広がる。爆弾がもうすぐ雄叫びを上げる。それに怯えながら生きるのは少々疲れた。全部忘れてしまいたいと思うが、私にはまだやることがあるので簡単に死ねない。
君は私の手を取り、腰を持ち上げた。私も釣られて立ち上がると蝋燭はそのままに私たちは森の奥へと入っていく。
月明かりに照らされた横顔は複雑な顔をしていた。
「また明日しましょう、花火」
つい約束を取り付けてしまう。君は私の言葉に頭二つ分高い位置から見下ろすだけだった。
こんな日々が続けばいいのに。
花火の炎が瞬きの間に幾つ散ったのか、それを忘れて喉までせり上がった言葉は声にはならなかった。声にしようとしても魚の小骨のようにつっかえて、君の耳に届くことはない。
牡丹は永遠には続かない。炎が変わらず燃え続けることはない。
再び始まった蝉の声は水の膜が張っているように遠く、四本の足が砂利をかき分けて芝を踏む音だけが聞える。
私は細く息を吐き、繋がれていない方の細い手首を取る。告白を拒んでおいて、自分から接触するのは我が儘の他ない。しかし、透くんは優しいから自ら振りほどくことはなかった。
曖昧な関係は面倒だ。白黒はっきりつけばいいと思う。君もそれは同じだろう、だからあんなことを聞いてきた。
でも、この感情を言語化する術を私は知らない。
言語化できたとしても、その言葉はきっと君に伝えるべきではない。
故に霧のような返答しかできないのだ。
実態があるようで掴もうとすればするほど分からなくなる、そんな関係から逃れることはできないのだ。
雨風が急に来てもしのげそうな木陰を見つけると、私は堪らずその場に横たわった。考えすぎたのだろうか、どっと疲れが押し寄せてきてもう重力には抗えなさそうだ。
横向きになって低くなった視界では君の顔は見えず、少し泥で汚れたズボンの裾だけが見えた。あちらはすぐには横にならず、座り込んだだけらしい。
会話もなく、聞こえるのは騒がしい蝉と僅かな鈴虫の声だけ。瞼を閉じて、脳を休ませることに集中しよう。
そう思っていたはずなのに、無意識のうちに私は君の名前を呼んでいた。
「……ねぇ、透くん」
「ん、なんだ」
「私は貴方に相応しい人間でも、貴方が触れたいと思えるような人間でもないですよ」
何故だか、目尻から涙が一筋零れた。いけない、いけない。これは子供のようではないか。駄目だとわかっているのに、面倒な女だと自覚しているのに、肋骨のもっと奥が痛くて、溢れた感情を抑えることはできなかった。全身の体液全部に「すきだ」という気持ちが溶け混んで細胞に浸み込んでいく。目を逸らし続けていた三文字はもう飽和状態だった。これは目を逸らすどころではない、逸らそうとしても網膜を支配しているのだ。逸らしようがないではないか。差し伸べられた手のひらに、控えめに頬を摺り寄せる。少し冷たい指先が心地よかった。
「いいよそれでも」
硝子の破片みたいに透き通った声が降り注ぐ。とめどなく流れる涙を隠すように小さく蹲る私、君はくくっと喉を鳴らすと頭をそっと撫でる。滑稽だと思ったか、幼子のように我が儘を言って泣きじゃくる私を。
しかし実際私という人間は、素直になれないし、言いたいこともろくに言えないし、突き放しておいて自らは手放したくないと思ってしまう貪欲な人間だ。
自分自身でも至極面倒な女だと思う。
自分の気持ちにはもう気づいていた。君のことを見る目が変な人から頼れる人、そして一緒にいると心が安らぐ人へと変化していることも解っていた。
でもこれ以上近づけば、私はきっと死にきれない。恋をすれば、腹の爆弾が止まるなんて奇跡は起こらない。私がもうすぐ死ぬことはこの世に生を受けた瞬間から決まっている。
君は今日、私に接吻をした。
でもそれ以上は何も手を出さなかった。
きっとあの表情に込められた思いを察したのだろう。不本意で拒んでいると知っているから、「好きだ」とも「付き合おう」とも言わずただ黙って頭を撫でる。
「……ごめんね」
優しさが、痛い。
真にあたたかい人間は時々凶器となる。見返りを求めない愛が、与えられる人間の心の弱いところに沁みて、罪悪感を駆り立てる。君が綺麗な人間であると分かれば分かるほど、自分の汚さが嫌というほど分からされる。
からからに乾いた喉でようやく絞り出せたのはたった四文字だった。
力を入れていた手を解いて仰向けになった。滲む視界を占める君の顔は逆光でよく見えない。
「謝る言葉はいいから、どうかそのままの君でいて。俺はそれだけで満足だ」
青年の小さな声に、私は再び目元を腕で覆う。今夜は私が弱さを曝け出す番だった。仕方がないと割り切った途端、赤子のように涙が止まらなかった。それこそ最初は声を抑えていたが、次第に君ならいいかという思いが強くなっていって最終的には小さい子みたいに声を上げる。月が西に傾きはじめた頃、私は泣き疲れて意識を手放した。
君は私の寝息が聞こえるまで、撫でる手を辞めはしなかった。