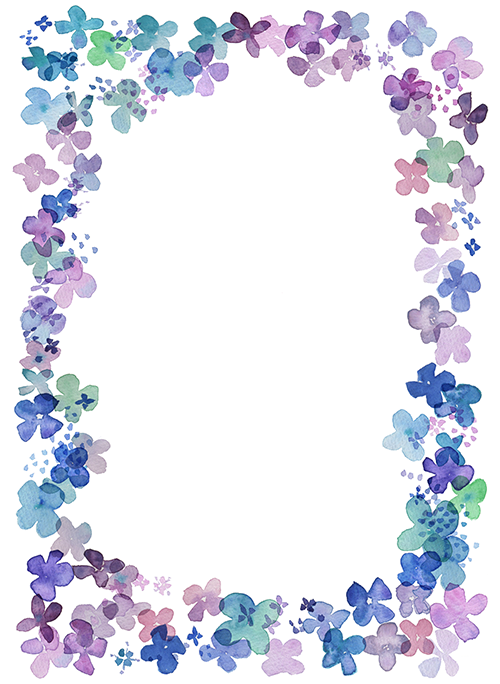約束の時間になっても相島透は戻ってこなかった。私はつい地面の土をいじいじしながら時間を潰す。君の方から時間を指定しておいてもう六時の鐘が鳴ってから一時間を過ぎている。流石に遅すぎるので、私の心では不安と怒りが葛藤していた。
「変なことに巻き込まれてないといいんですけど……。それ以外の理由で遅刻したなら要相談案件ですよ」
ふと顔を上げると、向かい側の山にはもう明かりが灯っていた。いつもの色と違う提灯を透かしたその色は、まるで山全部が燃え盛っているように赤一色に染まっている。少し手前の時計台の長針はゆっくりと時を進めていた。暮相の空には一番星が滲んでいて、薄い衣を透かしたような雲は段々と藍色の空に溶けていく。蝉の音に被せるように微かに笛と和太鼓の音が鳴っているのが分かった。嗚呼、今年もこの時期が来たんだ。17年間代り映えのしなかった風景から一転、今の私はどこまでも行ける自由の身であることが未だに信じられなかった。鳥籠からしか見てこなかった世界はこんなにも広かったんだ。今まで網膜に映っていた狭い世界はどこまでも広がっていた。空も海も山も人もそれこそ星のような大きさで、どこまでもどこまでも果てしない世界として繋がっていた。私は幻想的な風景に怒りも忘れて心を奪われていると、鼻腔に鈴蘭の淡い香りが充満した。
「遅くなった、すまない」
少し掠れた声の持ち主は振り返らずとも分かった。土のついた手を軽くはたくと、私はほっと肩に入れていた力を抜いた。そのままゆっくりと振り返る。さぁこれだけ遅刻したのだ。何という言い訳が出てくるのか見ものだ。
「心配するので約束は守ってくださいね……ってどうしたんですか?その浴衣」
「浴衣だけじゃない、簪もある」
「そうじゃなくて……なんで、」
言及するつもりだったのに、聞く前に驚かされてしまった。君の片手には高そうな生地があった。麻製の通気性のよさそうな布には一面、朝顔の花が咲いている。反対の手にはピンクゴールドを基調としたシンプルな簪も持ち合わせていた。アクセントとして硝子でできた朝顔が添えられていて、言葉にするのも躊躇われるほど美しい。
私が目の前の光景に言葉を失っていると、君は想像と違うリアクションに若干困り眉で頬を掻きながら釈明する。
「いつも眺めてた景色にいた同世代の子はこんな格好じゃなかった?俺の価値観がおじさんだったらすまん」
私がどうしてこんなにも驚いているのか、君の見当外れな推測に思わず頬が緩む。まさか君が遅れてきた理由は私の浴衣を探すためだったのか。小さな町に浴衣をレンタルできる場所なんてそうそうない。きっと隣町まで出たに違いない、一体どれだけの体力と労力を要したのだろう。君の顔面はまるで証拠だというように白いマスクが大半を覆っていた。下瞼ぎりぎりまで持ち上げられたそれは君の煌びやかなオーラを幾分か和らげる。
百歩譲って自分に利益のある人や、有名女優のためとかならまだ分からなくもない。こんな存在するだけで邪魔なちんちくりんのために身を削るなんて君は馬鹿だ。
私は複雑な顔で君を見上げるしかなかった。君は私の表情に一瞬傷ついたような顔をしてみせる。
「そんな顔しないでください。これでも喜んでいます」
私は微笑みをたたえながら、首を横に振ってみせる。
遅刻されたのにこんなの、許すしかできないだろう。私は君の左手に手を重ねて自分の髪に添える。一つに結われていた頭に朝顔の花が三輪咲いた。君は驚いたように瞳孔を大きくして、それから緩やかに目を細めた。俳優の相島透のときには見ることのできなかった新しい仕草に、私はときめきよりも興味深いなと思ってしまう。こんな顔今まで見たこともないし、心理学の本にも書いていなかった。一体これはどういう感情なんだろう。私がじっと彼の瞳の奥を覗こうと奮闘していると、不意に簪に触れた指先が耳たぶをなぞる。冷え性の手が触れた皮膚が不思議とどんどん熱を帯びていく。
「からかうのは辞めてください」
本当は嬉しくて可愛らしくお礼を言ってみてもいいなと思ったが、今更態度を変えてすり寄るのは何だか違う気がしてつい素っ気なくしてしまう。私が眉間に皺を寄せながら訴えかけると、君ははっと我に返ったような表情をしてそのまま高速で手を引っ込めた。挙動不審な動きに私の皺はどんどん深くなっていく。君はもう落ち着きを取り戻した顔で、右手に抱えていた浴衣と帯を押し付けてきた。よく見れば浴衣だけではなく、白く通気性のいいワンピースもあった。私は所々破けた自分の服に目をやる。普段使い用にと考えてくれたのだろう。
「着てみて。サイズが合ってたらそのまま出発しよう」
「はい」
私は半ば強制的に持たされたそれを抱えると、森の深くまで歩いていく。しかし、変な感じだ。表情と言い、耳に触れる手つきと言い、調子が狂う。一体君は何を考えているのだろう。
「私ってこんなに心読むの下手だったっけ」
数日客を取らないだけで、読心術というのはこんなにも鈍るものなのか。それとも、君の表情には私がまだ出会ったことのない感情が込められているのか。私はどうしたものかと唸りながら、誰の目の届かないところまで歩いていくのだった。
ずっと神社にいたはずなのに、踏み入れた瞬間異世界のように感じてしまうのはどうしてだろう。規則正しく並べられた石畳は綺麗に清掃されていて、暗がりに赤く怪しい光が映えていた。賑やかな祭囃子と、子供のはしゃぐ声が絶えず聞こえて気分を高揚させる。
遠くから見ていた世界が現実となった興奮から紅潮していく頬に手を当てた。君にばれないうちに熱を冷まさなきゃ、またからかわれると思った。
すれ違う人は誰もが幸せそうだった。恋人同士が多いような気がする。そんな空間に君みたいな美形と、ガリガリちんちくりんの私が並んで歩いている姿を想像して思わず背中が粟立つ。不釣り合いすぎて恐ろしいくらいだ。あと、浴衣の件の衝撃で薄れていたがちゃっかり君も甚平を身にまとっていた。ちなみに色はお揃いとかでもなんでもなく、白に多彩な色の花々の柄が描かれている私に対して、落ち着いた紺色は派手さはないが統一感があった。
私は何だか落ち着かずちらちらと定期的に隣の男に視線を送ってしまう。どうして彼が私と一緒にいてくれているのか未だに分からない。私は何も考えずに歩いている男と少し距離を取った。
「なんで離れる」
ですよねと思った。私は言い訳をごにょごにょと重ねる。
「いやぁ、透くんの顔が主な原因と言いますか。視線がこう一点集中するといたたまれないと言いますか……あの、怪訝そうな顔辞めてもらっていいですか?」
「怒っていない、ただ理解できないだけだ。ボタンが言っていることは俺の顔のせいでお前が肩身の狭い思いをしている、だから距離を取りたい。そういうことか?」
「そうです!!日本語お上手ですねー」
「じゃあ離れる必要ないな。距離を詰めろ、そう離れられると通行人の邪魔になる」
正論だった。そう言いくるめられてしまえば言い返す言葉が見つからない。
「……はい」
私は肩を落としてなるべく気配を消した。彼に熱い視線を送る女性たちに、誤解なんだと観念した顔をすることと、どうか刺されませんようにと祈ることしかできなかった。私が顔を上げると、君の身長が思ったよりも高いことに気づいた。180は優に超えていそうだ。浴衣の袖を引っ張って、気づいてもらおうとする。見下ろしてきた君に私はじとっと睨みをきかせた。君は面倒くさそうにため息を吐くだけでまた視線を前に戻す。諦めろということだった。
それから目に入る屋台全てを見て回った。金魚すくい、鮫釣り、りんご飴、綿菓子。君は自由奔放に神社を駆け回る私に嫌がることなく着いてきてくれた。彼氏でもないのにどれも文句の一つも言わず付き合ってくれる男、そうそういないだろう。ちらちらと隣の男に視線を送ってくる女性に「お目が高い。優良物件ですよー」なんて紹介してやりたかったが、君の立場的に辞めておいた。
「透くん、あれ射的ですよね!」
射的の文字を見つけて興奮が一段階ギアを上げる。屋台の食べ物も、出店でしか出会えないイベントも、全部楽しみにしていたが、私の一番の目的はこれだった。射的、銃を使って景品を落とす単純な遊びである。しかし、小屋の中では中々見ることのないメカニックなものは私の好奇心を擽る。レバーを引いた後に小気味いい音を鳴らすのも、微かに火薬の煙がたつのも格好いいとずっと思っていた。私が先ほどとは打って変わった光を含んだ瞳で上目遣いをすると、君は表情を変えずに尋ねてくる。
「やりたいのか?」
「はい!やってるところを見たいです」
君の体が拍子抜けしたかのように傾く。何か変なことを言っただろうか、不思議に思う私に彼は呆れたようにマスク越しの表情筋を脱力させる。
「お前がやりたいんじゃないのかよ」
「透くんが銃を構えた姿が様になるかなと思いまして」
「何、ボタンも俺のファンなの?」
目をぱちくりさせながら聞いてくる彼に私は全力でかぶりを振る。ファンだなんて断じてなかった。
「そんな滅相もない!きっと私みたいな人間が捧げられたから、神様は恩恵としてこのような美しい顔を造形されたのだと思うと少し感動したまでです」
「なんかリアクションしずらいな」
「喜んでくださいよ!その顔で生れ落ちることができて嬉しくないんですか?」
そう口にしておきながら、私は勿体ないと思っていた。小さい頃から業界で働いてきたなら、あの初期透の爽やかな水あめみたいに甘い微笑みに懐柔されてきた人間が数多いるのだろう。しかし、そうやって生きてきたからこそ実際君の心の壁は陰で分厚くなって自分の声すら届かなくなってしまった。周りにいた誰一人として、君の笑顔が完璧すぎて静かに崩壊していったことに気づけなかったのだ。
だから私は君の顔は蛇足とさえ思っている。中身のない、屑な人間なんてこの世にごまんといるだろう。それなのにどうして君が選ばれてしまったのだろう。君がどうしようもない人間だったらきっと何も考えなかった。けれど、君は清らかで泥臭い人間だった。思っていた以上に不器用で、思っていた以上に鈍感で、思っていた以上に生きるのが下手な人間だった。
仮に君の顔が興梠だったとしたら、ファンとやらは離れていくんだろう。
でも私はきっと君の顔が興梠だったとしても離れず、いつもと同じように話せる自信がある。それは君の肌に張り付いたパーツとバランスではなく、生き方を尊敬しているからだった。
「いいことばかりじゃないよ、逆に面倒ごとに巻き込まれることが多い。あと偏見に悩まされる」
「……それはそうですよね。失礼しました」
君が真剣に言うので、私も申し訳なさから声量が小さくなる。
「まぁでもボタンみたいな奴には関係ないけどな」
「褒めてるんでしょうかそれ」
「んー、どうだろうね」
訂正しよう、顔だけではなく発言の数々も蛇足であった。つまり私が王道ではなく、B専だと言いたいのだろうか。折角好感度が上がりかけていたのに、上げて落とされた気分になる。私が拗ねているのを他所に、彼は財布から小銭を出していた。
「おっちゃん、二発頼むよ」
射的屋のおっちゃんはだるそうに顔を上げながら二百円を受け取る。割といかついヤクザ顔のおっちゃんは彼と目があった瞬間、その顔に似合わない蕩けた表情で恍惚の息を漏らした。
「……あれ、どっかで見たことのある顔だな。なんかモデルとかやってたりするのか?」
おっちゃんの冗談めいた何気ない一言に心臓が飛び跳ねる。
どきりとしてつい彼の方を向こうとしたが、それは彼の左手によって阻止される。私の頭部は片手一つでがっちりと固定されて微動だにできなかった。君の態度を見る限りここでの正解は何も反応しないことらしい。首筋に冷や汗を流す私に対し、君の態度は涼しいものだった。
「勘違いじゃない?俺は隣町の大学に通ってるただの大学生だよ」
「まぁそりゃそうか、有名人様がこんな街にくるはずないもんな。あいよ、的に当てたらその景品が貰えるからな」
おっちゃんは笑ってスルーしてくれた。私の拍動は徐々に落ち着きを取り戻す。それにしてもマスクをしても尚オーラが消せないのか、最早行き過ぎた美形は恐ろしいものだと他人事としてしか捉えられない世界線だった。
墨色蒼然となった世界に、ぽつりと君の横顔だけが浮き出て見える。作画が違う挿絵のようだと思った。蜃気楼が見えなくなったと言っても、夏盛りの夜さりは蒸し暑い。しかし額から一筋流れる雫もまた様になるので、私は何も言えず黙ってその横顔を観察する。
「ボタンはどれが欲しいの?」
突然私に話が振られた。押さえつけられていた手がようやく離れ、君を見上げると片手に銃を持ったまま袖を捲る色男がいた。ああこういうのを見たことがある。毎年祭りの際一度は見る光景と近似していた。大体恋人同士が射的をしたとき男が「何がほしい?」と甘い声で聞くと、女は決まって一番大きな景品を指さすのだ。彼氏側は奮闘するものの、中央にある大きなぬいぐるみが倒されることはなく、おっちゃんにまんまと搾取される。そういう意味ではこのおっちゃんもある意味策士だ。毎年、大きな景品を狙う恋人たちからたんまり儲けているのだろう。
「あれがいいです!!」
私が指さしたものは全く可愛げのない白いつつみだった。風で飛んで行ってしまいそうなほど儚い和紙に包まれたそれは、墨汁の「花火」の文字が滲んでいた。
君は鳩が豆鉄砲を食ってもそんな顔しないだろうという具合で私をまじまじと見てくる。
「あれって……花火?いいの、熊のデカいぬいぐるみとかあるけど。女子ってそういう方が好きじゃないの?」
「花火一回してみたかったんですよ。いつも打ち上げられるものを遠くからしか見てこなかったので」
「ふぅん、まぁへましないように努力する」
君は変に意気込むこともなく手にある鉄の塊を構えた。照準を合わせるために片目を閉じる彼は顔のほとんどのパーツが見えなくなってしまっているというのに、やけにキラキラしている。私は困ったように笑う、もうこの姿だけで結末が大体分かってしまうじゃないか。
「へましないように努力する」
一見気障な台詞に聞こえるが、期待を裏切ることができないのが相島透の恐ろしいとこだった。
パンっと躊躇いもなく小気味いい音が弾ける。
軽い音を立てて、純白の包みは地面に落ちた。
「やっぱり」
「おいおい、前世はカウボーイか何かか?!まぁ当たったものは当たったからな、おめでとうさん」
カウボーイと揶揄された青年は的に当てたというのに喜びを見せない。そんな姿に店主は若干引きながら、景品を押し付ける。私の方を振り向いた君は完全にスナイパーの目をしていた。役者スイッチというものは変なところで入るらしい。おっちゃんの言葉に引っ張られてか、心なしか彼の背景に荒野とサラブレッドが見えたような気がした。
「どうするあと一発あるけど」
彼にとって大切なのは手に入れた景品より、弾を打ち切ることらしい。表情は変わっていないのに予想以上に楽しんでいるちぐはぐ具合に耐えられなかった。真っすぐなその姿が子供っぽくみえて私は失笑してしまう。
「一発で当てろなんて言ってませんよ、私」
「じゃあボタンがやればいい。ほら構えて、そうレバーに手を掛けて。まだ引くんじゃねぇぞ。ボタンが銃を持ってるってだけでひやひやするのに暴発されたら困るからな」
流石に信用されてなさすぎではないか。彼は私を台の前に立たせると自分は後ろに回って、覆いかぶさるような形になる。銃に二人の手が添えられた。君の薄い胸板が肩に密着して、知りたいとも思っていない心拍数が伝わってくる。私は皺ばむ顔を斜め上の彫刻品から逸らしながら呟く。
「ひぃ……息が首に当たります。気持ち悪い」
「気持ち悪いって言ったか今?」
「い、言ってません……それよりこれを押せばいいんですか」
狙いを定めたつもりだったが、気を散らす要因が多すぎて正直言うと身が入ってなかったこともある。
私が何気なく指を引こうとしたその先には、いかつい眼光を光らせたスキンヘッドがあった。
「下手くそか!」
危うくおっちゃんの脳天をぶち抜きかけた私に拳骨が落とされた。君はもう半分呆れたような表情をしている。私は状況に理解が追い付かず呆けた顔をしていたが、有り得ない状況にじわじわと笑いが込み上げてきた。当の本人が笑いを堪えているというのに、隣の男は本気で心配したような顔で私の顔を覗いてくる。
「いくらコントロールが下手だとして、どうして銃口がそっち向くんだよ。殺意高すぎだろ」
「……すみません……ぶっ」
突っ込みがあまりに的確過ぎて、我慢が出来なかった。耐えきれず吹き出してしまう。自分でも意味がわからない状況だと思う。だって普通、隣にいる人の顔が良すぎるあまり理性を飛ばして危うく人を殺しそうになることあるか。あって堪るか。でも実際起こりかけたのだ、これこそ本当の美の暴力だろう。君は子供が初めて包丁を使う時の保護者の目をしている。それが余計に面白かった。笑いが一向に収まることのない私は「ごめん」と言っておきながら、腹を抱えて崩れ落ちる。
「おいおい、しっかりしろ。どうしたんだよ本当に。気が狂ったのか?」
咳き込む私に、背中がぽんぽんと一定のリズムで叩かれる。
幸せとはこういうもののことを指すのだろうか。
気兼ねなく神社を歩いて、嫌な顔せずに隣を歩いてくれる人がいて、しょうもないことで笑って。
その全てが当たり前だと笑える人が羨ましい。
息も絶え絶えになりながら、それでも笑うことを辞めれない。くだらないことで涙が出るほど笑らう経験なんて、したことがなかった。顔が熱くて胸が苦しいほどにいっぱいだった。
あぁ。
「死にたくないなぁ……」
腹に手を当てながら今度は地獄耳の君に聞こえない声量で呟く。火薬は幸せによって中和されることなく腹に留まり続けている。素直に幸せに身を委ねられれば良かったのに。心が満たされる度に脳裏を掠めるのは、数を減らしていく時限爆弾の秒数だった。
死ぬ前に幸せを見つけてやろうと飛び出したのに、いざ幸せを知れば知るほど知りたくなかったと後悔に襲われる。
馬鹿みたいな話だ。掴んだ幸せを離したくないと思ってしまう。失いたくないと思う思い出が増えてしまう。
『私は失うことが怖いと感じるほどの地位も思い出も積み重ねてきたこともないので』
君に告げた言葉が嘘に塗り替わっていく。幸せと反比例するように別の感情が湧き出る。
頭を振って、笑う膝に力を込めて、立ち上がった。もう一度銃を手に取ると今度はきちんと狙いを定める。狙いは特に考えもせずに選んだ一番大きな熊のぬいぐるみだった。彼がつむじの上で頷くのが分かって、私も真っすぐ前だけを見る。
レバーに掛けた人差し指を思い切り曲げようとした。
その時だった。
「あっ!」
周りの人が避けるほどの声量の持ち主は、何故か私たちを指さす。指の持ち主は全く顔も知らない若い女だった。規則正しく刻まれていた拍動が無くなって私は思わず君の方を見る。白い肌には一筋の汗が流れていた。おっちゃんに声を掛けられたときとは比にならない焦りが浮かぶ彼に、私の指先は一瞬で氷河と化す。
「アレ、神に捧げる少女じゃない?」
「えっ、脱走したって言ってた?」
「気持ち悪い、何でこんなところにいるの」
「てか隣にいる人誰?なんか横顔イケメンじゃない?」
「ほんとだ!!しかもちょっと相島透に似てるー!」
「え、そういえば相島透って今行方不明で活動休止してるんじゃないの?」
「まさか、この女と駆け落ちするために?!はぁ、普通にありえない。冷めるわ」
観衆の声は黄色いものから漆黒へ鮮やかにグラデーションする。たった一人の何気ない言葉がその場にいる大勢の目に悪意の種を宿した。
その結果、瞬きする間に数えきれないほどの矛先が私たちの方を向いていた。
君の腰がくるりと人通りの少ないへ翻る。銃に添えられていた手は私の指先へスライドして掴んだ後、鉄の塊を手放した。君は私を連れて逃げるつもりだと瞬時に判断する。
駄目だ、私は足手まといだ。直感が叫んだ。
私は傾く体にブレーキを掛ける。軽い体ではあるが、踏ん張ればそれなりの抵抗はできる。振り返る君は今にも噛みついてきそうな顔をしていた。
「行くぞ、ボタ」
「透くん、私」
「いいから!!」
そんな喋り方すれば喉が千切れてしまうだろう。宝石にまた一つ傷がついた。私のせいだった。君の声に衝撃を受けてささやかな抵抗は失敗に終わった。透くんは私の手を強引に引くと、人の波を潜り抜ける。彼のボロボロのスニーカーが悲鳴をあげて今にも壊れそうだった。気を抜けば躓いてしまうこの状況で、それでも私が走れているのは自分がどんな酷い言葉に晒されようが迷わずに進む背中が目の前にあったからだ。
嗤う人、物を投げつけてくる人、写真を撮る人。
頬がぶたれたように熱くて繋がれてない方の手で拭うと、豚汁のニンジンが肌に張り付いていた。私は人の目が怖くて、足元だけを見て走る。しかし、皮膚がうっ血して白くなるくらい強い力を込められた腕が視界の端でちらつくと涙が込み上げてきた。君の額からはマスクが剥がれ優美な顔が露わになる。そうなれば流石に周りの人は私の手を引く男が相島透だと確信して、更に騒めきは大きくなる。
あぁ、私なんてことをしてしまったんだ。私の我が儘で透くんを危険な目に合わせて傷つけて、挙句の果てに苦手な群衆の盾なってもらって。やっぱり私は疫病神なのかもしれない、周りにいるだけで誰かの迷惑で誰かの不幸で。傷つけてはいけない人を、傷つけてしまう。
縺れる足を踏ん張って人込みを抜けると、彼だって土地勘がないのに私の姿を誰にも見られないように庇いながら人通りの少ない道を選別してくれた。後はもうひたすら走った。息が苦しくて段々何も考えられなくなってくる、視界に映る石壁と彼岸花がものすごいスピードで後ろへ流れていった。前を向くと肩で息をする透くんがいる。
ごめんなさい、と心の中で呟く。
彼の姿を目にするだけで申し訳なくて、私はそっと目を逸らす。夜風に潤んだ瞳を晒して、早く乾いてくれと願った。
苦しいけれど庇われた私はまだましだった。君が引いてくれる力のお陰で体は勝手に前に進む。君より楽に逃げている自分が情けなかった。
もう神社の提灯の明かりも点になった頃、彼はようやく右手を脱力させた。
「はぁ……っ、はっ」
嗚咽と同時にどさっと重たいものが落ちた音が聞える。驚いて地面の方を見ると、四つん這いになりながら必死に呼吸をしている透くんがいた。
「透くん?!」
背中をさすると、彼は咳き込みながら私の手に自分の手を当てて「やめろ」と静止させる。人に揉まれたせいで、煙草と甘ったるい香水の匂いとアルコールの匂いが纏わりついた。酸素が足りなくて思い切り深呼吸すると、その匂いまで吸い込んでしまって私までむせてしまう。
苦し気に喘ぐ透くんは、涙でぐちゃぐちゃの私の肩を押し出した。
「……逃げろよ、早く」
「何言ってるんですか?!こんな状態の透くんを置いていける訳ないじゃないですか」
「馬鹿だな、ボタンが先に行かなかったら俺がこんな無茶した意味ないだろう。別に死ぬわけじゃないし、後で追いかけるから大丈夫」
「そうやって虚勢張って、倒れているところを無理やり誰かに問いただされたりしたら……」
「黙って早く行け!」
「私は!!」
こんな大声出してもし誰かが来てしまったら元も子もない。彼の努力の水の泡になってしまう。
それでも私は声を荒げる選択をした。
そうしなきゃ、本当の彼には届かないと思ったからだ。彼は私の言葉を本気に捉えていない、掛ける言葉全てを上辺だけのものだと勘違いしている。その背景は、きっと幼いころからお世辞や胡麻をする言葉ばかり掛けられてきて、いつしか本当に心配する言葉が届かなくなってしまったのだろう。
当たり前だ、そんな経験して一体誰が周りの大人を信用したいと思えるのだろう。
彼の周りにはいつも人がいたかもしれないけれど、透くんはずっと孤独と戦ってきた。
極限まで整えられた体裁は自身ですら自分を見失ってしまうほど分厚く、それに加えて騙された周囲の人々も本当の君を知ろうとしなかった。
誰も頼れない、誰も信じられない世界で、たった一人で生きてきた。
だったら今夜、私が貴方の世界で二人目の人間になることを誓おう。
震える喉で息を思い切り吸い込む。普段使わない筋が伸びて、今にも破裂しそうな肺と肋骨が軋む。
私は彼の頬を両手で包み込むと、そのまま引き寄せて額を密着させる。
鼓膜が破れそうなほどの声量で放つ言葉が、虚ろな目をした彼にどうか届きますようにと祈った。
「私は、貴方が苦しむのが一番怖いんです」
酸欠で視界の所々が欠ける。腹筋に力を入れなければ、意識が飛んでしまいそうだった。そんな穴だらけの私の目にも鮮明に映ったのは、彼の揺れる睫毛だった。
大胆なことを言い放っておいて自分が一番驚いていた。気づかないうちに君は静かに私の世界の真ん中にいた。
変な男だと思うだけだったのに、今私はどうしてこんなにも傷つけたくないと願ってしまうのだろう。
どうしてあんなに願い続けていた自由を捨ててまで、君を見捨てたくないと思うのだろう。
答えは一つだ。自分よりも幸せになってほしいと思える人ができたからだ。
君だ。
誰よりも傷ついてほしくなくて、誰よりも背負うものを軽くしてあげたくて、誰よりもこの先に待ち受ける未来が輝くものであってほしい、そんな人。私の頭の中では変な男からこんなにも長い名前に書き換えられていた。
君は与えたものの見返りなんて要らなかった、自分がどれだけ苦しくても幸せを願える人だった。空っぽならそんなことできない、自分のことを蔑む君は俳優という地位も名誉もお金も全部捨ててまで私をここまで連れてきてくれた。
それが例え自分のためであったとしても、事実には変わりない。
そして私はそれが君が失くしていたものの一つだと思った。
人はそれを漢字一文字で表したがる。
ただ敢えて口にする気にはなれない。君が自覚した瞬間、私の願いは破綻するからだ。
私たちにそんな感情、芽生えてはならなかった。
「決めました。私、神社に戻ります」
精一杯の笑顔を浮かべた。もう心は決まっている。私はその場で立ち上がると、千切れた右足のスニーカーの紐をきつく縛る。今ならまだ間に合うだろう。
依然、地べたで脱力したままの君は何か言いかけた言葉を飲み下して、乾いた笑い声をあげる。
「は?何言って、」
「ちゃんと皆に頭下げてごめんなさいってして、白い浴衣に着替えて、腹切ってきますね!せっかく髪飾りも浴衣も全部可愛くしてもらったのに残念です」
「おい、」
「最後に楽しい時間を過ごせて私は幸せでした。人らしい時間は少ししかなかったですけど、悔いのない17年でしたね!何より透くんに出会えましたし!私、実は最初怖かったんですよ、突然貴方が障子を開けたから」
「ふざけたこと言ってんじゃねぇよ、目ぇ覚ませ」
「ふざけてなんか、ないですよ」
指先が小刻みに空気を揺らす。それを抑え込もうと震えている右手で震えている左手を包み込んだ。
私は平気なことを伝えるために笑った。
笑ったはずなのに、口が金縛りにあったように動かなかった。鉛の口角はどんどん下に下がっていって、目から零れ落ちる雫が宝石のように光を孕んで零れた。
「だって、私がいる限り貴方は苦しいですよ」
私が言い放ったとき、見開かれた濁りのない瞳に暗い色が滲んだ。
「歩いているだけで誰かに後ろ指さされて、まともに顔をあげて歩けなくて、皆が私の犠牲を心待ちにしてる。そんな人間と生きていくなんてきっと辛いことだらけです」
普通だったら貴方のような人が豚汁を投げつけられるようなことも、汚い言葉をぶつけられながら逃げることもないのだ。全て、私のせいである。私と関わると碌なことがない、そんなの自分が一番よくわかっていた。
「君は私と出会って、何か一つでもよかったと言えることがありましたか……?」
私は君と出会えてよかったと思えることが沢山ある。けれど、君はどうだろうか。答えは分かり切ったことだった。
私が泣きながらでそれでも笑ったのは、私以上に苦悶の表情を浮かべている人が目と鼻の先にいたからだ。
なんだ、そんな顔できるんだ。よかった、また一つ君が感情を思い出せたことが嬉しい。
でも、そんな顔させたくて私は言った訳ではない。ただ諦めてほしくて、私のことを見捨ててほしかっただけなのだ。
それなのになんで私以上に君が苦しそうな顔をしているのだろう。
「お前は、それでいいのかよ」
掠れた声が余計に私の息を浅くさせる。私の手首を掴もうとした綺麗な手が伸ばされて、私は瞬時に引っ込める。しかし逃がさないとばかりに中指を掴んだ彼は、繋がれた指一本に五本分の力を込める。しかしその力は成人男性の握力とは思えないほど弱弱しかった。強弱を繰り返しながらそれでも離されることのない掌はどちらがともなく震えていた。
「なぁ、生きたくて生きたくて堪らなかったんじゃなかったのかよ。祭り以外にもしたいこと沢山あるんだろ?そんなに簡単に諦められるほどお前の願いは軽いものだったのか……?」
顔があげられない。きっと今顔を合わせればその切実な瞳に全て言いくるめられる。絆されて、生きたいと思ってしまう。許されないことを君だけが許してくれるから、私はそれに甘えてしまう。
頑なに否定せず、俯き続ける私にため息が降り注ぐ。額に焼かれた鉄のような熱がじわっと広がって思わず瞬きを繰り返した。手を伸ばせば簡単に触れられる距離にいる相島透は、目を瞑って私の額に自分のそれを押し付けている。
「村の誰がなんと言おうと、お前はお前の為に生きればいいし、死ねばいい。ただお前に生きてほしいと願っているのは世界でたった一人じゃないことを知ってくれ」
君の言葉は私に対して向けたものであり、自分自身に確認するために呟いたものだった。それは君にとって決して軽い言葉ではないというのは出会って四日の私にも分かる。これほどまでに痛切に言葉を紡げる人が存在するなんて、私は知らなかった。
「……それは同情ですか」
「いいや違う、ただの祈りだ」
そのまま私の体は広い肩にすっぽりと覆われ、ぎゅっと抱き寄せられた。不安や迷いがるつぼのようにどろどろに溶かされて、代わりに君の言う祈りとやらが心に侵入してきた。それは瞬く間に全身に広がって、私の強がる心を解こうとしてくる。
変態だと思った。
芋虫が蛹になってどろどろにされて蝶として体を変えるように、今まさに私は蝶になろうとしていた。
蝶になって、羽を伸ばしたら君と何処までも飛んでいけるだろうか。
誰の手の届かないところまで遠く、高く、昇っていけるだろうか。
「お嬢様……?!」
突然のことに夢見心地だった意識は現実に引き戻される。間違いない、私を探し求める声だった。恐る恐る顔を上げると、汗だくの白い浴衣を着た女が直立したまま信じられないという目で私をじっと睨んでいた。
私が息を吸うのと同時に、彼女の口が開いた。
「巫女さん……っ」
「神主様がお怒りですよ。直ちに戻りましょう、お嬢様」
ずかずかと近づいてきた巫女と目が合う。その瞬間、左頬に火花が散った。何が起こったのか状況が分からず何度も瞬きをしていると今度は髪の毛を思い切り引っ張られる。痛いと叫びたかった、しかし声は出なかった。やはり彼女の顔を見たら私に反抗する資格はないと思った。
「貴方がいなければ、我が神社の損失は計り知れないんですよ。村の住民みんながお嬢様がいなくなったことに対して怒りをぶつけている。その相手は誰だと思いますか?10年前貴方の命をお救いになった神主様なのですよ?」
分かっている。
「恩を仇で返すなんて本当に信じられません」
分かっているよ。
「貴方が17年間生かされた意味を理解してください」
分かっているって。
それでも、生きたいと思ってしまった私は欠損品なのか。
小屋にいるときに同じことを考えたことがある。私の答えは今日で決まった。
ぬるい夜風が肌に張り付く。祭囃子の音も、人々の賑わう声も、耳を澄まさなければ聞こえない。袖に隠してある線香花火の袋と、穴の開いたポイをきゅっと握りしめると、段々と賑やかなあの音が蘇る。
直後、破裂音が鳴り響いた。
祭囃子はもう聞こえない。まとめた髪が濡れて毛先から何かが滴り落ちる。
鉄の匂いが鼻腔を充満させたとき、私は上を向くことができなかった。
「うるさい」
掠れ声の彼が蹲る巫女に向けた言葉はたった四文字だった。巫女は何か言い返そうとしたが、自分の鼻から赤い液体が垂れていることに気づくと声にならない悲鳴をあげる。
私にも生ぬるいものが指先に触れた。生ぬるいといっても夏の空気の生ぬるさではない、もっと人の体温に近いそんな感じだった。丁度花火が打ち上げられる時刻になったらしい。私は暗がりの手元が花火によって明るくなったときに初めてその正体が血液だと知った。
殴って血だらけの手が、私の手に絡みつく。
不快だったけれど不思議と離したくはなかった。
その瞬間、一際大きな花火が打ち上げられた。私は思わず顔をあげると、散っていく風物詩を背景に透くんがいた。
逆光で表情がよく見えない。私が目を細めたとき、細身のシルエットの肩があがった。
一緒に過ごした時間は短いけれどこの仕草の意味を私は知っている。
きっと君は今、笑っているんだろう。
「生きることに意味を見出そうとすることがあったとしても、生かされることに意味を見つける必要なんてねぇよ。人の一生は非売品なんだから、他人が横柄に値踏みできるものじゃないだろ」
息の切れた声で必死に言葉を紡ぐ君。
私は不安定な足元からよそ見して君だけを見つめた。視界を埋め尽くすのは君だけだった。
観察なんてしなくても込められた想いは全部分かる。花火が弾けた光で照らされた一瞬の君を、私は瞬き一つでシャッターを切る。
私の出会った冷酷で感情のない君は、いつの間にか溶けていなくなっていた。感情を殺された青年にはちゃんと心があった。
ちゃんと、そこに、弱弱しいが、確かに。
「世間の目がとか、周りの人が、とかもうどうでもいいんだ。何を言われたっていい、この先進む未来が明けない夜でも、止まない雨でも、藻掻いても浮上できない海の底でも、真っ暗で先の見えない道のりでも一緒にいれば何か一つは変われるって俺は確信している」
花火が遠ざかっていく。私の瞳にはもう、彼岸花も落ちた空き缶も剝がれかけた蛻の殻も何も映らない。
「俺の手を取って一緒に逃げよう、ボタン」
今はただ、貴方が。
私を信じてくれる、君が。
網膜に染みついて、幾ら目を擦っても消えることがない透くんが。
私のちっぽけな世界の真ん中で笑っている。
微かに「待って」という声と、足首を掴む強い力が足元から私を引き留める。
声のする方へ視線を向けると、鼻から血を垂れ流しながらも死んでも離さないとばかりの気迫が私の心を現実に染めようとした。
「許さないから」
紅色の袴が恨めしそうに縋りつく。彼女はきっと私を逃したら神主にこっぴどく叱られるのだろう。
神主は私を取り逃がしたことで村の人たちから罵詈雑言を浴びせられて肩身の狭い思いをするかもしれない。
私がされたような仕打ちを、代わりに育ててくれた巫女が身代わりとなって苦しむのかもしれない。
新しい少女が『神に捧げる少女』となって17年後殺されるのかもしれない。
「はい」
それでも私は笑った。今まで彼女に17年間見せてきた貼り付けの笑みではなく、心からの笑顔で。それは皮肉でも何でもない、解放からの綻びだった。
「許さないでください。気が済むまで、私のことを一生憎み続けてください」
許しなんていらなかった。誰かから許されようと恨まれようと、その感情はどれも私を止めることはできなかったのだ。だとするならばそれはきっと私にとって必要のないものなのだろう。
ただ、彼だけは必要だった。
誰かの言葉より、感情より、私の世界に彼がいることが大切だった。
彼だけは手放したくなかった。
そう思えたことが、生きてきて一番幸せだと感じた。
「育ててくれて、偽りでも大切にしてくれてありがとうございました。……けれど、誰かの言いなりで、自我を殺していた私は今日でおしまいです。誰が何と言おうと、私は神に捧げる少女じゃない」
肩をすくめると私は紫色になった足首に絡みついた手を解く。もう、その華奢な手には力が込められていなかった。諦めたような虚ろな目玉二つが私を見上げる。私は頷くと、背後でずっと見守ってくれていた大切な人の手をとった。
「私はボタンです」
そこからの記憶はあまりなかった。石垣から生えてきた雑草の生い茂る細い道を抜けて、雨蛙の声が微かに聞こえるあぜ道を走って、人気のない丘を登って、たどり着いた先は寂れた公園だった。公園というのは透くんが教えてくれた。小説で何度も出てきた「公園」を目の当たりにして私は柄にもなく高揚した。もう何十年も使われていないのかカラフルであっただろう塗装は全て赤茶色の錆で染められている。切れた息がお互いに穏やかになったのは30分経ってからだった。透くんが目を閉じていると、体温の低そうな雰囲気も相まって死んでいるんじゃないかと錯覚してしまう。だから繋がれた掌はそのまま力を込めて、二人で仰向けで寝転がった。そうすれば目を瞑っていても、蝉の音がうるさくても、とくとくと指先で脈が打つから生きていると分かる。素早い拍動は酸素を取り込む度に緩やかに数を減らしていく。私は安心感で意識を手放してしまいそうだった。芝生の青臭い香りと、満点の星空、隣には顔のいい男。求婚に励む蝉がいなければ完璧だったななんて考えながら、全身に回ったアドレナリンが落ち着くのを待つ。
暫く経って彼が起き上がったので私も立ち上がると、公園とは神社とは全然違う雰囲気の場所だと初めて気づいた。鉄でできたよく分からないものが沢山あったので「これはなに?」と透くんに聞いたら「滑り台」とだけ返ってきた。
「すべりだいってあの滑り台ですか?!私初めて見ました!こんな形なんですね」
「滑り台でそんなオーバーリアクションする奴、いるかよ」
「はい!素晴らしい形状ですね。下にいくほど放物線は緩やかになっていて子供が遊んでも怪我がなさそうです。一度滑ってもいいでしょうか」
私が早口でまくしたてると君は耐えきれないとばかりに真一文字で結んでいた口角をぐにゃりと緩ませた。声を上げて笑う彼に私は驚いて、軽く君の頬を叩いてしまう。
「大丈夫ですか、透くん。壊れてしまいましたか?」
「いや、ボタンの反応が五歳児そのまますぎて……ちょっと……ふっ」
もう君は堪えようとはしなかった。笑いすぎてもう喘いでいるではないか、私は不服を申し立てるように頬を膨らませる。
「透くんにも五歳児時代があるのですから、そんなに笑わないでくださいよ!私だけって訳じゃないでしょう?誰でも最初はおんなじ反応だと思いますよ?!」
「そうだよな……っぶっ、やめろその大真面目な顔」
やめろと言われればやりたくなるのが人間の性だ。私は見せつけるように先ほどより大きく頬を膨らませる。私は君のように特別顔が整っているわけではないからそれはそれは形容し難いほど酷い顔だったのだと思う。君は大袈裟に膝から崩れ落ちて「もうやめてくれ」と呻いている。馬鹿みたいなやり取りだが、それが胸が詰まるほど幸せだと言ったら笑われるだろうか。まぁ伝える気はないが。
「それと、」
笑いすぎて目尻に滲んだ涙を拭った君が付け足す。
「俺、滑り台滑ったことないよ」
私が彼の瞳を覗き込む。ひんやりした革細工のようなこげ茶色のそれは私のそれをじっと見つめたあと、ゆるりと逸らしてしまった。脱力させていた腕が唐突に私の手首を引く。転ばないように淡い懐中電灯の光一つを頼りに鉄の柵にたどり着くとゆっくりと腰掛けた。
この空気で呑気に滑り台に走っていくのは間違いなのは流石の私にも分かる。衝動をぐっと堪えて、一旦話を聞こうと横顔を盗み見る。君は懐かし気に公園を見回してから、また滑り台に視線を戻した。
「俺は小学生の頃からこの業界で働かせてもらってるからさ、まともに遊べなかったんだ。近所の公園に寄ろうとしても周りの大人とか母さんが『もし怪我でもして顔に傷がついたらどうするの?』とか『誰かを一度でも突き飛ばしたりしたら君の芸能人生は終わるよ』とか言うんだよ。だから公園で無邪気に何の気兼ねもなく遊んでふざけて笑っている同級生が羨ましかった」
無条件に私は小さい子は当たり前のように公園で遊ぶものだと思っていた。私の読んできた本に出てくる公園とはそういう場所だったからだ。友達と遊ぶための集合場所、親と喧嘩して行きつく場所、自分が親となったときに今度は懐かしさに胸をいっぱいにしながら自分の子と遊ぶ場所。それが公園というものだと思っていた。
それに条件何て必要なくて、誰でもいつでも行くことのできる場所。それが公園というものだと思っていた。
けれど、君にはその権利がなかったらしい。
誰からも許されずに、周りの期待や重圧を背負わされ、娯楽なんかなくても、無理やり口角を上げてきたというのか。ちらりと横目で表情を確認しようとするが、私は驚愕してしまう。
てっきり辛そうな顔をしていると勘違いしていたが、君の表情は想像とはかけ離れていた。
何故か君は穏やかな顔のまま、ただ淡々と言葉を零す。
「でも、ボタンはそれも知らないんだよな」
私はその言葉に何も言い返せなかった。憐れまれて悲しい気持ちよりも、君には関係ない話だよねと守られた事実が寂しかった。確かに私は世間知らずの少女だ。彼より社会経験もなければ、人に揉まれて苦しんだ経験もない。
それでも、君より私の方が苦しい人生だったとは思わなかった。
私は私なりに、貴方は貴方なりに必死に生きてきたことを短い期間で伝えてきたはずなのに、どうしてこう私ばかり君に守られてしまうのだろう。
自分では気づけない痛みを私は貴方に気づいてほしかった。大丈夫って言葉じゃなくて『痛いよ』って言葉が私はほしい。
「知ってるからこと、しんどいこともあると思います。私はまだ知らないだけ良かったのかもしれません」
微笑みながら言う私に君は顔を歪ませた。何か言おうと深く吸われた君の息は、困り眉に変わって言葉にはならなかった。
今日だけで新しい君を沢山見ることができた。私はその百面相が面白くてつい失笑してしまう。
「ふふ、透くんが変な顔してるの初めて見ました。少し可愛い……」
「なっ、あ」
怪訝そうな顔でこちらから一歩引いた君は、諦めたように頭をぐしゃぐしゃと揉みしだいた。
「この状況でなんでそんなに綺麗な言葉を言えるんだよ、ボタンは」
「透くんが頑張っているからです」
私が迷いもなく言いきると、君は目に塵が入ったのか何度も瞬きを繰り返した。驚いて私が君の瞼に触れると、君の手が私の手を掴む。君はばつが悪そうに手を繋いだままそっぽを向いた。『目に塵が入ったなら早く水で流した方が……』と言っても聞く耳を持たずに、反抗するように握る力を強める。流石男性なので力は強い、それでも私が振りほどけば簡単に離れてしまうほどの臆病な力の込め方だった。怪我したときくらい素直に言うことを聞けばいいのに。
私はため息を吐くと諦めて大きな背に自分の体重を委ねて座る。
「知っていますか、世の中って一生懸命生きている人ほど損をするんですよ」
これは世間知らずの私が学んだ唯一のことだった。英語も読めなければ、簡単な計算しかできない。やることのない日々を小屋の中で過ごしていれば人の表情と言動に機微になるのは難しいことではなかった。外界からの情報は本でしか知らない私にとって情報とは人そのものだった。神捧げる少女として曲がりにも様々な人間と対話をしてきたつもりだ。
一生懸命な人間は決まって澄んだ目に傷が沢山ついていた。何処か世界に対して諦めがあって、常に何かに怯え疲弊していた。
金に、酒に、薬に、中毒になり溺れた人間は無駄な自信に満ちて、傷一つない瞳をぎらつかせていた。
美しいのがどちらかなんて、誰が見ても分かるだろう。それでも美しさと幸せは違うということは幼いなりに理解していた。
「怠けていても、結局は誰かがやってくれる。それを待ちながら生きるのが一番楽で効率的です。そしてそういう人たちは決まって、努力している人たちに言います。『努力は意味ない』と」
私も最初、心理学を極めようとしたとき巫女に止められたことがある。ポーカーで行き詰ったとき、心理学の本が欲しいとお願いをしたら鼻で嗤われて軽くあしらわれたことがある。
きっとすぐ死ぬ身で勉強なんて無駄な行為だと思ったのだろう。
ただ受動的に流れるままに生きていればきっと私の人生は楽なものだった。着替えも食事も手伝ってくれる人がいる、何不自由ない暮らしをして静かに17の夏に神に捧げられる名目で散っていた。
しかし、私は僅かでもいいからこの世界に爪痕を残したかった。
私にとって爪痕を残す方法は一つしかなかった、それが努力し続けることだった。
私のもとを訪れた金持ちのボンボンにも散々なことを言われた。
「ポーカーを頑張ったところで何か意味があるの?ただ食って寝るだけでアンタには生きる価値があるんだからそれでいいじゃん。わざわざ何かする必要ないよね」
それでも私は読みすぎて角の欠けた心理学の本を手放すことなはなかった。効率的に生きることこそ、生きる価値がないように思えたからだ。
私の考えが間違っているのかと疑う時もあった。
でも、君の存在が私は間違っていなかったと証明してくれた。
「君は諦めずに、今あるものも手放さずに、実直に生きている。透くんの生き方は泥臭いけれど綺麗です。私が出会ってきた誰よりも、綺麗です。それを頑張っていると言わずに何と言うんですか」
君の凄いところは欲張りなところだった。手の届かないかもしれない目標に向かって飛ぶとき、背負うものは軽い方がいい。それでも君は沢山の人の想いや応援を全て背負って挑んでいた。それがどれだけ茨の道か、私には分からない。それでも君が俳優の話をするときに時々息が詰まるような表情をしているのを知っている。
背骨越しに君の浅い息遣いが聞えた。どうしよう、なんて声を掛けよう。感情を露わにしない彼の心が揺れている、その事実に動揺してしまって更に焦りが募る。でも、君が今一番必要な言葉を贈ってあげたかった。自分があの時、否定されたときに、欲しかった言葉を言ってあげられたら少しは救えるだろうか。
繋がれた弱弱しい手を振りほどく。君は拒否されたことが恥ずかしかったのか、さっと引っ込めようとするが私は逃さない。ぎりぎりで掴んだ手をもう離れないように強く、強く握りしめた。
「透くん、辛いときは辛いって言っていいんですよ」
当たり前を許されていない私たちだからこそ、二人のときにその当たり前を求めてしまうのだろう。君はその言葉を聞いた瞬間、堰を切ったように目から涙を流す。私がそっとその肩を引き寄せると、いつもの透くんでは想像できないほど苦しそうな声で泣いた。
「俺、きょう、だめかも」
「だめでもいいですよ」
「ん……」
「どれだけ情けなくても、駄目駄目でも、私は貴方が泣き止むまでずっと傍にいます。離れないと約束します」
膝で震える手を必死に抑えようとしている君が愛おしくて、思わず繋がれていない反対の手にも自分の手を重ねた。
その姿はつい一時間前に牙を剝いていた強気の態度の青年とはあまりにもかけ離れている。しかし、それで幻滅するようなことは断じてない。
私も弱いところがあって、君にも弱いところがある。
それでいいじゃないか。私たちは弱いけれど、受け止められないほど脆くはないのだから。
「手、冷たいですよ。夏なのに」
指先から伝わるひんやりとした感覚に驚いた。まるで血が通ってないかのような温度だった。
「うるさい」
「大丈夫です。冷たいなら温めればいいだけなので」
優しく握りこむと君は繋がれた二つを自分の頬に寄せた。涙が二人の手の僅かな隙間に入り込む。しゃっくりの合間の小さな声は、声変わりの終わった青年が少年に戻ったように上ずっていた。
「……ありがとう」
小さな感謝の言葉は私の鼓膜を揺らした後、真っ暗な空に吸い込まれていった。
小高い山にひっそりと佇む古びた公園は、この町で一番空に近い場所だった。
その日、宇宙に一番近いのは間違いなく私たちだった。
私は多分、君が宇宙に行くと言うなら宇宙まで行こうと思う。貴方は私にたくさんの新しいものを教えてくれる。私はその全部を目に、皮膚に、脳に、焼き付けてぜんぶ覚えておきたい。
「変なことに巻き込まれてないといいんですけど……。それ以外の理由で遅刻したなら要相談案件ですよ」
ふと顔を上げると、向かい側の山にはもう明かりが灯っていた。いつもの色と違う提灯を透かしたその色は、まるで山全部が燃え盛っているように赤一色に染まっている。少し手前の時計台の長針はゆっくりと時を進めていた。暮相の空には一番星が滲んでいて、薄い衣を透かしたような雲は段々と藍色の空に溶けていく。蝉の音に被せるように微かに笛と和太鼓の音が鳴っているのが分かった。嗚呼、今年もこの時期が来たんだ。17年間代り映えのしなかった風景から一転、今の私はどこまでも行ける自由の身であることが未だに信じられなかった。鳥籠からしか見てこなかった世界はこんなにも広かったんだ。今まで網膜に映っていた狭い世界はどこまでも広がっていた。空も海も山も人もそれこそ星のような大きさで、どこまでもどこまでも果てしない世界として繋がっていた。私は幻想的な風景に怒りも忘れて心を奪われていると、鼻腔に鈴蘭の淡い香りが充満した。
「遅くなった、すまない」
少し掠れた声の持ち主は振り返らずとも分かった。土のついた手を軽くはたくと、私はほっと肩に入れていた力を抜いた。そのままゆっくりと振り返る。さぁこれだけ遅刻したのだ。何という言い訳が出てくるのか見ものだ。
「心配するので約束は守ってくださいね……ってどうしたんですか?その浴衣」
「浴衣だけじゃない、簪もある」
「そうじゃなくて……なんで、」
言及するつもりだったのに、聞く前に驚かされてしまった。君の片手には高そうな生地があった。麻製の通気性のよさそうな布には一面、朝顔の花が咲いている。反対の手にはピンクゴールドを基調としたシンプルな簪も持ち合わせていた。アクセントとして硝子でできた朝顔が添えられていて、言葉にするのも躊躇われるほど美しい。
私が目の前の光景に言葉を失っていると、君は想像と違うリアクションに若干困り眉で頬を掻きながら釈明する。
「いつも眺めてた景色にいた同世代の子はこんな格好じゃなかった?俺の価値観がおじさんだったらすまん」
私がどうしてこんなにも驚いているのか、君の見当外れな推測に思わず頬が緩む。まさか君が遅れてきた理由は私の浴衣を探すためだったのか。小さな町に浴衣をレンタルできる場所なんてそうそうない。きっと隣町まで出たに違いない、一体どれだけの体力と労力を要したのだろう。君の顔面はまるで証拠だというように白いマスクが大半を覆っていた。下瞼ぎりぎりまで持ち上げられたそれは君の煌びやかなオーラを幾分か和らげる。
百歩譲って自分に利益のある人や、有名女優のためとかならまだ分からなくもない。こんな存在するだけで邪魔なちんちくりんのために身を削るなんて君は馬鹿だ。
私は複雑な顔で君を見上げるしかなかった。君は私の表情に一瞬傷ついたような顔をしてみせる。
「そんな顔しないでください。これでも喜んでいます」
私は微笑みをたたえながら、首を横に振ってみせる。
遅刻されたのにこんなの、許すしかできないだろう。私は君の左手に手を重ねて自分の髪に添える。一つに結われていた頭に朝顔の花が三輪咲いた。君は驚いたように瞳孔を大きくして、それから緩やかに目を細めた。俳優の相島透のときには見ることのできなかった新しい仕草に、私はときめきよりも興味深いなと思ってしまう。こんな顔今まで見たこともないし、心理学の本にも書いていなかった。一体これはどういう感情なんだろう。私がじっと彼の瞳の奥を覗こうと奮闘していると、不意に簪に触れた指先が耳たぶをなぞる。冷え性の手が触れた皮膚が不思議とどんどん熱を帯びていく。
「からかうのは辞めてください」
本当は嬉しくて可愛らしくお礼を言ってみてもいいなと思ったが、今更態度を変えてすり寄るのは何だか違う気がしてつい素っ気なくしてしまう。私が眉間に皺を寄せながら訴えかけると、君ははっと我に返ったような表情をしてそのまま高速で手を引っ込めた。挙動不審な動きに私の皺はどんどん深くなっていく。君はもう落ち着きを取り戻した顔で、右手に抱えていた浴衣と帯を押し付けてきた。よく見れば浴衣だけではなく、白く通気性のいいワンピースもあった。私は所々破けた自分の服に目をやる。普段使い用にと考えてくれたのだろう。
「着てみて。サイズが合ってたらそのまま出発しよう」
「はい」
私は半ば強制的に持たされたそれを抱えると、森の深くまで歩いていく。しかし、変な感じだ。表情と言い、耳に触れる手つきと言い、調子が狂う。一体君は何を考えているのだろう。
「私ってこんなに心読むの下手だったっけ」
数日客を取らないだけで、読心術というのはこんなにも鈍るものなのか。それとも、君の表情には私がまだ出会ったことのない感情が込められているのか。私はどうしたものかと唸りながら、誰の目の届かないところまで歩いていくのだった。
ずっと神社にいたはずなのに、踏み入れた瞬間異世界のように感じてしまうのはどうしてだろう。規則正しく並べられた石畳は綺麗に清掃されていて、暗がりに赤く怪しい光が映えていた。賑やかな祭囃子と、子供のはしゃぐ声が絶えず聞こえて気分を高揚させる。
遠くから見ていた世界が現実となった興奮から紅潮していく頬に手を当てた。君にばれないうちに熱を冷まさなきゃ、またからかわれると思った。
すれ違う人は誰もが幸せそうだった。恋人同士が多いような気がする。そんな空間に君みたいな美形と、ガリガリちんちくりんの私が並んで歩いている姿を想像して思わず背中が粟立つ。不釣り合いすぎて恐ろしいくらいだ。あと、浴衣の件の衝撃で薄れていたがちゃっかり君も甚平を身にまとっていた。ちなみに色はお揃いとかでもなんでもなく、白に多彩な色の花々の柄が描かれている私に対して、落ち着いた紺色は派手さはないが統一感があった。
私は何だか落ち着かずちらちらと定期的に隣の男に視線を送ってしまう。どうして彼が私と一緒にいてくれているのか未だに分からない。私は何も考えずに歩いている男と少し距離を取った。
「なんで離れる」
ですよねと思った。私は言い訳をごにょごにょと重ねる。
「いやぁ、透くんの顔が主な原因と言いますか。視線がこう一点集中するといたたまれないと言いますか……あの、怪訝そうな顔辞めてもらっていいですか?」
「怒っていない、ただ理解できないだけだ。ボタンが言っていることは俺の顔のせいでお前が肩身の狭い思いをしている、だから距離を取りたい。そういうことか?」
「そうです!!日本語お上手ですねー」
「じゃあ離れる必要ないな。距離を詰めろ、そう離れられると通行人の邪魔になる」
正論だった。そう言いくるめられてしまえば言い返す言葉が見つからない。
「……はい」
私は肩を落としてなるべく気配を消した。彼に熱い視線を送る女性たちに、誤解なんだと観念した顔をすることと、どうか刺されませんようにと祈ることしかできなかった。私が顔を上げると、君の身長が思ったよりも高いことに気づいた。180は優に超えていそうだ。浴衣の袖を引っ張って、気づいてもらおうとする。見下ろしてきた君に私はじとっと睨みをきかせた。君は面倒くさそうにため息を吐くだけでまた視線を前に戻す。諦めろということだった。
それから目に入る屋台全てを見て回った。金魚すくい、鮫釣り、りんご飴、綿菓子。君は自由奔放に神社を駆け回る私に嫌がることなく着いてきてくれた。彼氏でもないのにどれも文句の一つも言わず付き合ってくれる男、そうそういないだろう。ちらちらと隣の男に視線を送ってくる女性に「お目が高い。優良物件ですよー」なんて紹介してやりたかったが、君の立場的に辞めておいた。
「透くん、あれ射的ですよね!」
射的の文字を見つけて興奮が一段階ギアを上げる。屋台の食べ物も、出店でしか出会えないイベントも、全部楽しみにしていたが、私の一番の目的はこれだった。射的、銃を使って景品を落とす単純な遊びである。しかし、小屋の中では中々見ることのないメカニックなものは私の好奇心を擽る。レバーを引いた後に小気味いい音を鳴らすのも、微かに火薬の煙がたつのも格好いいとずっと思っていた。私が先ほどとは打って変わった光を含んだ瞳で上目遣いをすると、君は表情を変えずに尋ねてくる。
「やりたいのか?」
「はい!やってるところを見たいです」
君の体が拍子抜けしたかのように傾く。何か変なことを言っただろうか、不思議に思う私に彼は呆れたようにマスク越しの表情筋を脱力させる。
「お前がやりたいんじゃないのかよ」
「透くんが銃を構えた姿が様になるかなと思いまして」
「何、ボタンも俺のファンなの?」
目をぱちくりさせながら聞いてくる彼に私は全力でかぶりを振る。ファンだなんて断じてなかった。
「そんな滅相もない!きっと私みたいな人間が捧げられたから、神様は恩恵としてこのような美しい顔を造形されたのだと思うと少し感動したまでです」
「なんかリアクションしずらいな」
「喜んでくださいよ!その顔で生れ落ちることができて嬉しくないんですか?」
そう口にしておきながら、私は勿体ないと思っていた。小さい頃から業界で働いてきたなら、あの初期透の爽やかな水あめみたいに甘い微笑みに懐柔されてきた人間が数多いるのだろう。しかし、そうやって生きてきたからこそ実際君の心の壁は陰で分厚くなって自分の声すら届かなくなってしまった。周りにいた誰一人として、君の笑顔が完璧すぎて静かに崩壊していったことに気づけなかったのだ。
だから私は君の顔は蛇足とさえ思っている。中身のない、屑な人間なんてこの世にごまんといるだろう。それなのにどうして君が選ばれてしまったのだろう。君がどうしようもない人間だったらきっと何も考えなかった。けれど、君は清らかで泥臭い人間だった。思っていた以上に不器用で、思っていた以上に鈍感で、思っていた以上に生きるのが下手な人間だった。
仮に君の顔が興梠だったとしたら、ファンとやらは離れていくんだろう。
でも私はきっと君の顔が興梠だったとしても離れず、いつもと同じように話せる自信がある。それは君の肌に張り付いたパーツとバランスではなく、生き方を尊敬しているからだった。
「いいことばかりじゃないよ、逆に面倒ごとに巻き込まれることが多い。あと偏見に悩まされる」
「……それはそうですよね。失礼しました」
君が真剣に言うので、私も申し訳なさから声量が小さくなる。
「まぁでもボタンみたいな奴には関係ないけどな」
「褒めてるんでしょうかそれ」
「んー、どうだろうね」
訂正しよう、顔だけではなく発言の数々も蛇足であった。つまり私が王道ではなく、B専だと言いたいのだろうか。折角好感度が上がりかけていたのに、上げて落とされた気分になる。私が拗ねているのを他所に、彼は財布から小銭を出していた。
「おっちゃん、二発頼むよ」
射的屋のおっちゃんはだるそうに顔を上げながら二百円を受け取る。割といかついヤクザ顔のおっちゃんは彼と目があった瞬間、その顔に似合わない蕩けた表情で恍惚の息を漏らした。
「……あれ、どっかで見たことのある顔だな。なんかモデルとかやってたりするのか?」
おっちゃんの冗談めいた何気ない一言に心臓が飛び跳ねる。
どきりとしてつい彼の方を向こうとしたが、それは彼の左手によって阻止される。私の頭部は片手一つでがっちりと固定されて微動だにできなかった。君の態度を見る限りここでの正解は何も反応しないことらしい。首筋に冷や汗を流す私に対し、君の態度は涼しいものだった。
「勘違いじゃない?俺は隣町の大学に通ってるただの大学生だよ」
「まぁそりゃそうか、有名人様がこんな街にくるはずないもんな。あいよ、的に当てたらその景品が貰えるからな」
おっちゃんは笑ってスルーしてくれた。私の拍動は徐々に落ち着きを取り戻す。それにしてもマスクをしても尚オーラが消せないのか、最早行き過ぎた美形は恐ろしいものだと他人事としてしか捉えられない世界線だった。
墨色蒼然となった世界に、ぽつりと君の横顔だけが浮き出て見える。作画が違う挿絵のようだと思った。蜃気楼が見えなくなったと言っても、夏盛りの夜さりは蒸し暑い。しかし額から一筋流れる雫もまた様になるので、私は何も言えず黙ってその横顔を観察する。
「ボタンはどれが欲しいの?」
突然私に話が振られた。押さえつけられていた手がようやく離れ、君を見上げると片手に銃を持ったまま袖を捲る色男がいた。ああこういうのを見たことがある。毎年祭りの際一度は見る光景と近似していた。大体恋人同士が射的をしたとき男が「何がほしい?」と甘い声で聞くと、女は決まって一番大きな景品を指さすのだ。彼氏側は奮闘するものの、中央にある大きなぬいぐるみが倒されることはなく、おっちゃんにまんまと搾取される。そういう意味ではこのおっちゃんもある意味策士だ。毎年、大きな景品を狙う恋人たちからたんまり儲けているのだろう。
「あれがいいです!!」
私が指さしたものは全く可愛げのない白いつつみだった。風で飛んで行ってしまいそうなほど儚い和紙に包まれたそれは、墨汁の「花火」の文字が滲んでいた。
君は鳩が豆鉄砲を食ってもそんな顔しないだろうという具合で私をまじまじと見てくる。
「あれって……花火?いいの、熊のデカいぬいぐるみとかあるけど。女子ってそういう方が好きじゃないの?」
「花火一回してみたかったんですよ。いつも打ち上げられるものを遠くからしか見てこなかったので」
「ふぅん、まぁへましないように努力する」
君は変に意気込むこともなく手にある鉄の塊を構えた。照準を合わせるために片目を閉じる彼は顔のほとんどのパーツが見えなくなってしまっているというのに、やけにキラキラしている。私は困ったように笑う、もうこの姿だけで結末が大体分かってしまうじゃないか。
「へましないように努力する」
一見気障な台詞に聞こえるが、期待を裏切ることができないのが相島透の恐ろしいとこだった。
パンっと躊躇いもなく小気味いい音が弾ける。
軽い音を立てて、純白の包みは地面に落ちた。
「やっぱり」
「おいおい、前世はカウボーイか何かか?!まぁ当たったものは当たったからな、おめでとうさん」
カウボーイと揶揄された青年は的に当てたというのに喜びを見せない。そんな姿に店主は若干引きながら、景品を押し付ける。私の方を振り向いた君は完全にスナイパーの目をしていた。役者スイッチというものは変なところで入るらしい。おっちゃんの言葉に引っ張られてか、心なしか彼の背景に荒野とサラブレッドが見えたような気がした。
「どうするあと一発あるけど」
彼にとって大切なのは手に入れた景品より、弾を打ち切ることらしい。表情は変わっていないのに予想以上に楽しんでいるちぐはぐ具合に耐えられなかった。真っすぐなその姿が子供っぽくみえて私は失笑してしまう。
「一発で当てろなんて言ってませんよ、私」
「じゃあボタンがやればいい。ほら構えて、そうレバーに手を掛けて。まだ引くんじゃねぇぞ。ボタンが銃を持ってるってだけでひやひやするのに暴発されたら困るからな」
流石に信用されてなさすぎではないか。彼は私を台の前に立たせると自分は後ろに回って、覆いかぶさるような形になる。銃に二人の手が添えられた。君の薄い胸板が肩に密着して、知りたいとも思っていない心拍数が伝わってくる。私は皺ばむ顔を斜め上の彫刻品から逸らしながら呟く。
「ひぃ……息が首に当たります。気持ち悪い」
「気持ち悪いって言ったか今?」
「い、言ってません……それよりこれを押せばいいんですか」
狙いを定めたつもりだったが、気を散らす要因が多すぎて正直言うと身が入ってなかったこともある。
私が何気なく指を引こうとしたその先には、いかつい眼光を光らせたスキンヘッドがあった。
「下手くそか!」
危うくおっちゃんの脳天をぶち抜きかけた私に拳骨が落とされた。君はもう半分呆れたような表情をしている。私は状況に理解が追い付かず呆けた顔をしていたが、有り得ない状況にじわじわと笑いが込み上げてきた。当の本人が笑いを堪えているというのに、隣の男は本気で心配したような顔で私の顔を覗いてくる。
「いくらコントロールが下手だとして、どうして銃口がそっち向くんだよ。殺意高すぎだろ」
「……すみません……ぶっ」
突っ込みがあまりに的確過ぎて、我慢が出来なかった。耐えきれず吹き出してしまう。自分でも意味がわからない状況だと思う。だって普通、隣にいる人の顔が良すぎるあまり理性を飛ばして危うく人を殺しそうになることあるか。あって堪るか。でも実際起こりかけたのだ、これこそ本当の美の暴力だろう。君は子供が初めて包丁を使う時の保護者の目をしている。それが余計に面白かった。笑いが一向に収まることのない私は「ごめん」と言っておきながら、腹を抱えて崩れ落ちる。
「おいおい、しっかりしろ。どうしたんだよ本当に。気が狂ったのか?」
咳き込む私に、背中がぽんぽんと一定のリズムで叩かれる。
幸せとはこういうもののことを指すのだろうか。
気兼ねなく神社を歩いて、嫌な顔せずに隣を歩いてくれる人がいて、しょうもないことで笑って。
その全てが当たり前だと笑える人が羨ましい。
息も絶え絶えになりながら、それでも笑うことを辞めれない。くだらないことで涙が出るほど笑らう経験なんて、したことがなかった。顔が熱くて胸が苦しいほどにいっぱいだった。
あぁ。
「死にたくないなぁ……」
腹に手を当てながら今度は地獄耳の君に聞こえない声量で呟く。火薬は幸せによって中和されることなく腹に留まり続けている。素直に幸せに身を委ねられれば良かったのに。心が満たされる度に脳裏を掠めるのは、数を減らしていく時限爆弾の秒数だった。
死ぬ前に幸せを見つけてやろうと飛び出したのに、いざ幸せを知れば知るほど知りたくなかったと後悔に襲われる。
馬鹿みたいな話だ。掴んだ幸せを離したくないと思ってしまう。失いたくないと思う思い出が増えてしまう。
『私は失うことが怖いと感じるほどの地位も思い出も積み重ねてきたこともないので』
君に告げた言葉が嘘に塗り替わっていく。幸せと反比例するように別の感情が湧き出る。
頭を振って、笑う膝に力を込めて、立ち上がった。もう一度銃を手に取ると今度はきちんと狙いを定める。狙いは特に考えもせずに選んだ一番大きな熊のぬいぐるみだった。彼がつむじの上で頷くのが分かって、私も真っすぐ前だけを見る。
レバーに掛けた人差し指を思い切り曲げようとした。
その時だった。
「あっ!」
周りの人が避けるほどの声量の持ち主は、何故か私たちを指さす。指の持ち主は全く顔も知らない若い女だった。規則正しく刻まれていた拍動が無くなって私は思わず君の方を見る。白い肌には一筋の汗が流れていた。おっちゃんに声を掛けられたときとは比にならない焦りが浮かぶ彼に、私の指先は一瞬で氷河と化す。
「アレ、神に捧げる少女じゃない?」
「えっ、脱走したって言ってた?」
「気持ち悪い、何でこんなところにいるの」
「てか隣にいる人誰?なんか横顔イケメンじゃない?」
「ほんとだ!!しかもちょっと相島透に似てるー!」
「え、そういえば相島透って今行方不明で活動休止してるんじゃないの?」
「まさか、この女と駆け落ちするために?!はぁ、普通にありえない。冷めるわ」
観衆の声は黄色いものから漆黒へ鮮やかにグラデーションする。たった一人の何気ない言葉がその場にいる大勢の目に悪意の種を宿した。
その結果、瞬きする間に数えきれないほどの矛先が私たちの方を向いていた。
君の腰がくるりと人通りの少ないへ翻る。銃に添えられていた手は私の指先へスライドして掴んだ後、鉄の塊を手放した。君は私を連れて逃げるつもりだと瞬時に判断する。
駄目だ、私は足手まといだ。直感が叫んだ。
私は傾く体にブレーキを掛ける。軽い体ではあるが、踏ん張ればそれなりの抵抗はできる。振り返る君は今にも噛みついてきそうな顔をしていた。
「行くぞ、ボタ」
「透くん、私」
「いいから!!」
そんな喋り方すれば喉が千切れてしまうだろう。宝石にまた一つ傷がついた。私のせいだった。君の声に衝撃を受けてささやかな抵抗は失敗に終わった。透くんは私の手を強引に引くと、人の波を潜り抜ける。彼のボロボロのスニーカーが悲鳴をあげて今にも壊れそうだった。気を抜けば躓いてしまうこの状況で、それでも私が走れているのは自分がどんな酷い言葉に晒されようが迷わずに進む背中が目の前にあったからだ。
嗤う人、物を投げつけてくる人、写真を撮る人。
頬がぶたれたように熱くて繋がれてない方の手で拭うと、豚汁のニンジンが肌に張り付いていた。私は人の目が怖くて、足元だけを見て走る。しかし、皮膚がうっ血して白くなるくらい強い力を込められた腕が視界の端でちらつくと涙が込み上げてきた。君の額からはマスクが剥がれ優美な顔が露わになる。そうなれば流石に周りの人は私の手を引く男が相島透だと確信して、更に騒めきは大きくなる。
あぁ、私なんてことをしてしまったんだ。私の我が儘で透くんを危険な目に合わせて傷つけて、挙句の果てに苦手な群衆の盾なってもらって。やっぱり私は疫病神なのかもしれない、周りにいるだけで誰かの迷惑で誰かの不幸で。傷つけてはいけない人を、傷つけてしまう。
縺れる足を踏ん張って人込みを抜けると、彼だって土地勘がないのに私の姿を誰にも見られないように庇いながら人通りの少ない道を選別してくれた。後はもうひたすら走った。息が苦しくて段々何も考えられなくなってくる、視界に映る石壁と彼岸花がものすごいスピードで後ろへ流れていった。前を向くと肩で息をする透くんがいる。
ごめんなさい、と心の中で呟く。
彼の姿を目にするだけで申し訳なくて、私はそっと目を逸らす。夜風に潤んだ瞳を晒して、早く乾いてくれと願った。
苦しいけれど庇われた私はまだましだった。君が引いてくれる力のお陰で体は勝手に前に進む。君より楽に逃げている自分が情けなかった。
もう神社の提灯の明かりも点になった頃、彼はようやく右手を脱力させた。
「はぁ……っ、はっ」
嗚咽と同時にどさっと重たいものが落ちた音が聞える。驚いて地面の方を見ると、四つん這いになりながら必死に呼吸をしている透くんがいた。
「透くん?!」
背中をさすると、彼は咳き込みながら私の手に自分の手を当てて「やめろ」と静止させる。人に揉まれたせいで、煙草と甘ったるい香水の匂いとアルコールの匂いが纏わりついた。酸素が足りなくて思い切り深呼吸すると、その匂いまで吸い込んでしまって私までむせてしまう。
苦し気に喘ぐ透くんは、涙でぐちゃぐちゃの私の肩を押し出した。
「……逃げろよ、早く」
「何言ってるんですか?!こんな状態の透くんを置いていける訳ないじゃないですか」
「馬鹿だな、ボタンが先に行かなかったら俺がこんな無茶した意味ないだろう。別に死ぬわけじゃないし、後で追いかけるから大丈夫」
「そうやって虚勢張って、倒れているところを無理やり誰かに問いただされたりしたら……」
「黙って早く行け!」
「私は!!」
こんな大声出してもし誰かが来てしまったら元も子もない。彼の努力の水の泡になってしまう。
それでも私は声を荒げる選択をした。
そうしなきゃ、本当の彼には届かないと思ったからだ。彼は私の言葉を本気に捉えていない、掛ける言葉全てを上辺だけのものだと勘違いしている。その背景は、きっと幼いころからお世辞や胡麻をする言葉ばかり掛けられてきて、いつしか本当に心配する言葉が届かなくなってしまったのだろう。
当たり前だ、そんな経験して一体誰が周りの大人を信用したいと思えるのだろう。
彼の周りにはいつも人がいたかもしれないけれど、透くんはずっと孤独と戦ってきた。
極限まで整えられた体裁は自身ですら自分を見失ってしまうほど分厚く、それに加えて騙された周囲の人々も本当の君を知ろうとしなかった。
誰も頼れない、誰も信じられない世界で、たった一人で生きてきた。
だったら今夜、私が貴方の世界で二人目の人間になることを誓おう。
震える喉で息を思い切り吸い込む。普段使わない筋が伸びて、今にも破裂しそうな肺と肋骨が軋む。
私は彼の頬を両手で包み込むと、そのまま引き寄せて額を密着させる。
鼓膜が破れそうなほどの声量で放つ言葉が、虚ろな目をした彼にどうか届きますようにと祈った。
「私は、貴方が苦しむのが一番怖いんです」
酸欠で視界の所々が欠ける。腹筋に力を入れなければ、意識が飛んでしまいそうだった。そんな穴だらけの私の目にも鮮明に映ったのは、彼の揺れる睫毛だった。
大胆なことを言い放っておいて自分が一番驚いていた。気づかないうちに君は静かに私の世界の真ん中にいた。
変な男だと思うだけだったのに、今私はどうしてこんなにも傷つけたくないと願ってしまうのだろう。
どうしてあんなに願い続けていた自由を捨ててまで、君を見捨てたくないと思うのだろう。
答えは一つだ。自分よりも幸せになってほしいと思える人ができたからだ。
君だ。
誰よりも傷ついてほしくなくて、誰よりも背負うものを軽くしてあげたくて、誰よりもこの先に待ち受ける未来が輝くものであってほしい、そんな人。私の頭の中では変な男からこんなにも長い名前に書き換えられていた。
君は与えたものの見返りなんて要らなかった、自分がどれだけ苦しくても幸せを願える人だった。空っぽならそんなことできない、自分のことを蔑む君は俳優という地位も名誉もお金も全部捨ててまで私をここまで連れてきてくれた。
それが例え自分のためであったとしても、事実には変わりない。
そして私はそれが君が失くしていたものの一つだと思った。
人はそれを漢字一文字で表したがる。
ただ敢えて口にする気にはなれない。君が自覚した瞬間、私の願いは破綻するからだ。
私たちにそんな感情、芽生えてはならなかった。
「決めました。私、神社に戻ります」
精一杯の笑顔を浮かべた。もう心は決まっている。私はその場で立ち上がると、千切れた右足のスニーカーの紐をきつく縛る。今ならまだ間に合うだろう。
依然、地べたで脱力したままの君は何か言いかけた言葉を飲み下して、乾いた笑い声をあげる。
「は?何言って、」
「ちゃんと皆に頭下げてごめんなさいってして、白い浴衣に着替えて、腹切ってきますね!せっかく髪飾りも浴衣も全部可愛くしてもらったのに残念です」
「おい、」
「最後に楽しい時間を過ごせて私は幸せでした。人らしい時間は少ししかなかったですけど、悔いのない17年でしたね!何より透くんに出会えましたし!私、実は最初怖かったんですよ、突然貴方が障子を開けたから」
「ふざけたこと言ってんじゃねぇよ、目ぇ覚ませ」
「ふざけてなんか、ないですよ」
指先が小刻みに空気を揺らす。それを抑え込もうと震えている右手で震えている左手を包み込んだ。
私は平気なことを伝えるために笑った。
笑ったはずなのに、口が金縛りにあったように動かなかった。鉛の口角はどんどん下に下がっていって、目から零れ落ちる雫が宝石のように光を孕んで零れた。
「だって、私がいる限り貴方は苦しいですよ」
私が言い放ったとき、見開かれた濁りのない瞳に暗い色が滲んだ。
「歩いているだけで誰かに後ろ指さされて、まともに顔をあげて歩けなくて、皆が私の犠牲を心待ちにしてる。そんな人間と生きていくなんてきっと辛いことだらけです」
普通だったら貴方のような人が豚汁を投げつけられるようなことも、汚い言葉をぶつけられながら逃げることもないのだ。全て、私のせいである。私と関わると碌なことがない、そんなの自分が一番よくわかっていた。
「君は私と出会って、何か一つでもよかったと言えることがありましたか……?」
私は君と出会えてよかったと思えることが沢山ある。けれど、君はどうだろうか。答えは分かり切ったことだった。
私が泣きながらでそれでも笑ったのは、私以上に苦悶の表情を浮かべている人が目と鼻の先にいたからだ。
なんだ、そんな顔できるんだ。よかった、また一つ君が感情を思い出せたことが嬉しい。
でも、そんな顔させたくて私は言った訳ではない。ただ諦めてほしくて、私のことを見捨ててほしかっただけなのだ。
それなのになんで私以上に君が苦しそうな顔をしているのだろう。
「お前は、それでいいのかよ」
掠れた声が余計に私の息を浅くさせる。私の手首を掴もうとした綺麗な手が伸ばされて、私は瞬時に引っ込める。しかし逃がさないとばかりに中指を掴んだ彼は、繋がれた指一本に五本分の力を込める。しかしその力は成人男性の握力とは思えないほど弱弱しかった。強弱を繰り返しながらそれでも離されることのない掌はどちらがともなく震えていた。
「なぁ、生きたくて生きたくて堪らなかったんじゃなかったのかよ。祭り以外にもしたいこと沢山あるんだろ?そんなに簡単に諦められるほどお前の願いは軽いものだったのか……?」
顔があげられない。きっと今顔を合わせればその切実な瞳に全て言いくるめられる。絆されて、生きたいと思ってしまう。許されないことを君だけが許してくれるから、私はそれに甘えてしまう。
頑なに否定せず、俯き続ける私にため息が降り注ぐ。額に焼かれた鉄のような熱がじわっと広がって思わず瞬きを繰り返した。手を伸ばせば簡単に触れられる距離にいる相島透は、目を瞑って私の額に自分のそれを押し付けている。
「村の誰がなんと言おうと、お前はお前の為に生きればいいし、死ねばいい。ただお前に生きてほしいと願っているのは世界でたった一人じゃないことを知ってくれ」
君の言葉は私に対して向けたものであり、自分自身に確認するために呟いたものだった。それは君にとって決して軽い言葉ではないというのは出会って四日の私にも分かる。これほどまでに痛切に言葉を紡げる人が存在するなんて、私は知らなかった。
「……それは同情ですか」
「いいや違う、ただの祈りだ」
そのまま私の体は広い肩にすっぽりと覆われ、ぎゅっと抱き寄せられた。不安や迷いがるつぼのようにどろどろに溶かされて、代わりに君の言う祈りとやらが心に侵入してきた。それは瞬く間に全身に広がって、私の強がる心を解こうとしてくる。
変態だと思った。
芋虫が蛹になってどろどろにされて蝶として体を変えるように、今まさに私は蝶になろうとしていた。
蝶になって、羽を伸ばしたら君と何処までも飛んでいけるだろうか。
誰の手の届かないところまで遠く、高く、昇っていけるだろうか。
「お嬢様……?!」
突然のことに夢見心地だった意識は現実に引き戻される。間違いない、私を探し求める声だった。恐る恐る顔を上げると、汗だくの白い浴衣を着た女が直立したまま信じられないという目で私をじっと睨んでいた。
私が息を吸うのと同時に、彼女の口が開いた。
「巫女さん……っ」
「神主様がお怒りですよ。直ちに戻りましょう、お嬢様」
ずかずかと近づいてきた巫女と目が合う。その瞬間、左頬に火花が散った。何が起こったのか状況が分からず何度も瞬きをしていると今度は髪の毛を思い切り引っ張られる。痛いと叫びたかった、しかし声は出なかった。やはり彼女の顔を見たら私に反抗する資格はないと思った。
「貴方がいなければ、我が神社の損失は計り知れないんですよ。村の住民みんながお嬢様がいなくなったことに対して怒りをぶつけている。その相手は誰だと思いますか?10年前貴方の命をお救いになった神主様なのですよ?」
分かっている。
「恩を仇で返すなんて本当に信じられません」
分かっているよ。
「貴方が17年間生かされた意味を理解してください」
分かっているって。
それでも、生きたいと思ってしまった私は欠損品なのか。
小屋にいるときに同じことを考えたことがある。私の答えは今日で決まった。
ぬるい夜風が肌に張り付く。祭囃子の音も、人々の賑わう声も、耳を澄まさなければ聞こえない。袖に隠してある線香花火の袋と、穴の開いたポイをきゅっと握りしめると、段々と賑やかなあの音が蘇る。
直後、破裂音が鳴り響いた。
祭囃子はもう聞こえない。まとめた髪が濡れて毛先から何かが滴り落ちる。
鉄の匂いが鼻腔を充満させたとき、私は上を向くことができなかった。
「うるさい」
掠れ声の彼が蹲る巫女に向けた言葉はたった四文字だった。巫女は何か言い返そうとしたが、自分の鼻から赤い液体が垂れていることに気づくと声にならない悲鳴をあげる。
私にも生ぬるいものが指先に触れた。生ぬるいといっても夏の空気の生ぬるさではない、もっと人の体温に近いそんな感じだった。丁度花火が打ち上げられる時刻になったらしい。私は暗がりの手元が花火によって明るくなったときに初めてその正体が血液だと知った。
殴って血だらけの手が、私の手に絡みつく。
不快だったけれど不思議と離したくはなかった。
その瞬間、一際大きな花火が打ち上げられた。私は思わず顔をあげると、散っていく風物詩を背景に透くんがいた。
逆光で表情がよく見えない。私が目を細めたとき、細身のシルエットの肩があがった。
一緒に過ごした時間は短いけれどこの仕草の意味を私は知っている。
きっと君は今、笑っているんだろう。
「生きることに意味を見出そうとすることがあったとしても、生かされることに意味を見つける必要なんてねぇよ。人の一生は非売品なんだから、他人が横柄に値踏みできるものじゃないだろ」
息の切れた声で必死に言葉を紡ぐ君。
私は不安定な足元からよそ見して君だけを見つめた。視界を埋め尽くすのは君だけだった。
観察なんてしなくても込められた想いは全部分かる。花火が弾けた光で照らされた一瞬の君を、私は瞬き一つでシャッターを切る。
私の出会った冷酷で感情のない君は、いつの間にか溶けていなくなっていた。感情を殺された青年にはちゃんと心があった。
ちゃんと、そこに、弱弱しいが、確かに。
「世間の目がとか、周りの人が、とかもうどうでもいいんだ。何を言われたっていい、この先進む未来が明けない夜でも、止まない雨でも、藻掻いても浮上できない海の底でも、真っ暗で先の見えない道のりでも一緒にいれば何か一つは変われるって俺は確信している」
花火が遠ざかっていく。私の瞳にはもう、彼岸花も落ちた空き缶も剝がれかけた蛻の殻も何も映らない。
「俺の手を取って一緒に逃げよう、ボタン」
今はただ、貴方が。
私を信じてくれる、君が。
網膜に染みついて、幾ら目を擦っても消えることがない透くんが。
私のちっぽけな世界の真ん中で笑っている。
微かに「待って」という声と、足首を掴む強い力が足元から私を引き留める。
声のする方へ視線を向けると、鼻から血を垂れ流しながらも死んでも離さないとばかりの気迫が私の心を現実に染めようとした。
「許さないから」
紅色の袴が恨めしそうに縋りつく。彼女はきっと私を逃したら神主にこっぴどく叱られるのだろう。
神主は私を取り逃がしたことで村の人たちから罵詈雑言を浴びせられて肩身の狭い思いをするかもしれない。
私がされたような仕打ちを、代わりに育ててくれた巫女が身代わりとなって苦しむのかもしれない。
新しい少女が『神に捧げる少女』となって17年後殺されるのかもしれない。
「はい」
それでも私は笑った。今まで彼女に17年間見せてきた貼り付けの笑みではなく、心からの笑顔で。それは皮肉でも何でもない、解放からの綻びだった。
「許さないでください。気が済むまで、私のことを一生憎み続けてください」
許しなんていらなかった。誰かから許されようと恨まれようと、その感情はどれも私を止めることはできなかったのだ。だとするならばそれはきっと私にとって必要のないものなのだろう。
ただ、彼だけは必要だった。
誰かの言葉より、感情より、私の世界に彼がいることが大切だった。
彼だけは手放したくなかった。
そう思えたことが、生きてきて一番幸せだと感じた。
「育ててくれて、偽りでも大切にしてくれてありがとうございました。……けれど、誰かの言いなりで、自我を殺していた私は今日でおしまいです。誰が何と言おうと、私は神に捧げる少女じゃない」
肩をすくめると私は紫色になった足首に絡みついた手を解く。もう、その華奢な手には力が込められていなかった。諦めたような虚ろな目玉二つが私を見上げる。私は頷くと、背後でずっと見守ってくれていた大切な人の手をとった。
「私はボタンです」
そこからの記憶はあまりなかった。石垣から生えてきた雑草の生い茂る細い道を抜けて、雨蛙の声が微かに聞こえるあぜ道を走って、人気のない丘を登って、たどり着いた先は寂れた公園だった。公園というのは透くんが教えてくれた。小説で何度も出てきた「公園」を目の当たりにして私は柄にもなく高揚した。もう何十年も使われていないのかカラフルであっただろう塗装は全て赤茶色の錆で染められている。切れた息がお互いに穏やかになったのは30分経ってからだった。透くんが目を閉じていると、体温の低そうな雰囲気も相まって死んでいるんじゃないかと錯覚してしまう。だから繋がれた掌はそのまま力を込めて、二人で仰向けで寝転がった。そうすれば目を瞑っていても、蝉の音がうるさくても、とくとくと指先で脈が打つから生きていると分かる。素早い拍動は酸素を取り込む度に緩やかに数を減らしていく。私は安心感で意識を手放してしまいそうだった。芝生の青臭い香りと、満点の星空、隣には顔のいい男。求婚に励む蝉がいなければ完璧だったななんて考えながら、全身に回ったアドレナリンが落ち着くのを待つ。
暫く経って彼が起き上がったので私も立ち上がると、公園とは神社とは全然違う雰囲気の場所だと初めて気づいた。鉄でできたよく分からないものが沢山あったので「これはなに?」と透くんに聞いたら「滑り台」とだけ返ってきた。
「すべりだいってあの滑り台ですか?!私初めて見ました!こんな形なんですね」
「滑り台でそんなオーバーリアクションする奴、いるかよ」
「はい!素晴らしい形状ですね。下にいくほど放物線は緩やかになっていて子供が遊んでも怪我がなさそうです。一度滑ってもいいでしょうか」
私が早口でまくしたてると君は耐えきれないとばかりに真一文字で結んでいた口角をぐにゃりと緩ませた。声を上げて笑う彼に私は驚いて、軽く君の頬を叩いてしまう。
「大丈夫ですか、透くん。壊れてしまいましたか?」
「いや、ボタンの反応が五歳児そのまますぎて……ちょっと……ふっ」
もう君は堪えようとはしなかった。笑いすぎてもう喘いでいるではないか、私は不服を申し立てるように頬を膨らませる。
「透くんにも五歳児時代があるのですから、そんなに笑わないでくださいよ!私だけって訳じゃないでしょう?誰でも最初はおんなじ反応だと思いますよ?!」
「そうだよな……っぶっ、やめろその大真面目な顔」
やめろと言われればやりたくなるのが人間の性だ。私は見せつけるように先ほどより大きく頬を膨らませる。私は君のように特別顔が整っているわけではないからそれはそれは形容し難いほど酷い顔だったのだと思う。君は大袈裟に膝から崩れ落ちて「もうやめてくれ」と呻いている。馬鹿みたいなやり取りだが、それが胸が詰まるほど幸せだと言ったら笑われるだろうか。まぁ伝える気はないが。
「それと、」
笑いすぎて目尻に滲んだ涙を拭った君が付け足す。
「俺、滑り台滑ったことないよ」
私が彼の瞳を覗き込む。ひんやりした革細工のようなこげ茶色のそれは私のそれをじっと見つめたあと、ゆるりと逸らしてしまった。脱力させていた腕が唐突に私の手首を引く。転ばないように淡い懐中電灯の光一つを頼りに鉄の柵にたどり着くとゆっくりと腰掛けた。
この空気で呑気に滑り台に走っていくのは間違いなのは流石の私にも分かる。衝動をぐっと堪えて、一旦話を聞こうと横顔を盗み見る。君は懐かし気に公園を見回してから、また滑り台に視線を戻した。
「俺は小学生の頃からこの業界で働かせてもらってるからさ、まともに遊べなかったんだ。近所の公園に寄ろうとしても周りの大人とか母さんが『もし怪我でもして顔に傷がついたらどうするの?』とか『誰かを一度でも突き飛ばしたりしたら君の芸能人生は終わるよ』とか言うんだよ。だから公園で無邪気に何の気兼ねもなく遊んでふざけて笑っている同級生が羨ましかった」
無条件に私は小さい子は当たり前のように公園で遊ぶものだと思っていた。私の読んできた本に出てくる公園とはそういう場所だったからだ。友達と遊ぶための集合場所、親と喧嘩して行きつく場所、自分が親となったときに今度は懐かしさに胸をいっぱいにしながら自分の子と遊ぶ場所。それが公園というものだと思っていた。
それに条件何て必要なくて、誰でもいつでも行くことのできる場所。それが公園というものだと思っていた。
けれど、君にはその権利がなかったらしい。
誰からも許されずに、周りの期待や重圧を背負わされ、娯楽なんかなくても、無理やり口角を上げてきたというのか。ちらりと横目で表情を確認しようとするが、私は驚愕してしまう。
てっきり辛そうな顔をしていると勘違いしていたが、君の表情は想像とはかけ離れていた。
何故か君は穏やかな顔のまま、ただ淡々と言葉を零す。
「でも、ボタンはそれも知らないんだよな」
私はその言葉に何も言い返せなかった。憐れまれて悲しい気持ちよりも、君には関係ない話だよねと守られた事実が寂しかった。確かに私は世間知らずの少女だ。彼より社会経験もなければ、人に揉まれて苦しんだ経験もない。
それでも、君より私の方が苦しい人生だったとは思わなかった。
私は私なりに、貴方は貴方なりに必死に生きてきたことを短い期間で伝えてきたはずなのに、どうしてこう私ばかり君に守られてしまうのだろう。
自分では気づけない痛みを私は貴方に気づいてほしかった。大丈夫って言葉じゃなくて『痛いよ』って言葉が私はほしい。
「知ってるからこと、しんどいこともあると思います。私はまだ知らないだけ良かったのかもしれません」
微笑みながら言う私に君は顔を歪ませた。何か言おうと深く吸われた君の息は、困り眉に変わって言葉にはならなかった。
今日だけで新しい君を沢山見ることができた。私はその百面相が面白くてつい失笑してしまう。
「ふふ、透くんが変な顔してるの初めて見ました。少し可愛い……」
「なっ、あ」
怪訝そうな顔でこちらから一歩引いた君は、諦めたように頭をぐしゃぐしゃと揉みしだいた。
「この状況でなんでそんなに綺麗な言葉を言えるんだよ、ボタンは」
「透くんが頑張っているからです」
私が迷いもなく言いきると、君は目に塵が入ったのか何度も瞬きを繰り返した。驚いて私が君の瞼に触れると、君の手が私の手を掴む。君はばつが悪そうに手を繋いだままそっぽを向いた。『目に塵が入ったなら早く水で流した方が……』と言っても聞く耳を持たずに、反抗するように握る力を強める。流石男性なので力は強い、それでも私が振りほどけば簡単に離れてしまうほどの臆病な力の込め方だった。怪我したときくらい素直に言うことを聞けばいいのに。
私はため息を吐くと諦めて大きな背に自分の体重を委ねて座る。
「知っていますか、世の中って一生懸命生きている人ほど損をするんですよ」
これは世間知らずの私が学んだ唯一のことだった。英語も読めなければ、簡単な計算しかできない。やることのない日々を小屋の中で過ごしていれば人の表情と言動に機微になるのは難しいことではなかった。外界からの情報は本でしか知らない私にとって情報とは人そのものだった。神捧げる少女として曲がりにも様々な人間と対話をしてきたつもりだ。
一生懸命な人間は決まって澄んだ目に傷が沢山ついていた。何処か世界に対して諦めがあって、常に何かに怯え疲弊していた。
金に、酒に、薬に、中毒になり溺れた人間は無駄な自信に満ちて、傷一つない瞳をぎらつかせていた。
美しいのがどちらかなんて、誰が見ても分かるだろう。それでも美しさと幸せは違うということは幼いなりに理解していた。
「怠けていても、結局は誰かがやってくれる。それを待ちながら生きるのが一番楽で効率的です。そしてそういう人たちは決まって、努力している人たちに言います。『努力は意味ない』と」
私も最初、心理学を極めようとしたとき巫女に止められたことがある。ポーカーで行き詰ったとき、心理学の本が欲しいとお願いをしたら鼻で嗤われて軽くあしらわれたことがある。
きっとすぐ死ぬ身で勉強なんて無駄な行為だと思ったのだろう。
ただ受動的に流れるままに生きていればきっと私の人生は楽なものだった。着替えも食事も手伝ってくれる人がいる、何不自由ない暮らしをして静かに17の夏に神に捧げられる名目で散っていた。
しかし、私は僅かでもいいからこの世界に爪痕を残したかった。
私にとって爪痕を残す方法は一つしかなかった、それが努力し続けることだった。
私のもとを訪れた金持ちのボンボンにも散々なことを言われた。
「ポーカーを頑張ったところで何か意味があるの?ただ食って寝るだけでアンタには生きる価値があるんだからそれでいいじゃん。わざわざ何かする必要ないよね」
それでも私は読みすぎて角の欠けた心理学の本を手放すことなはなかった。効率的に生きることこそ、生きる価値がないように思えたからだ。
私の考えが間違っているのかと疑う時もあった。
でも、君の存在が私は間違っていなかったと証明してくれた。
「君は諦めずに、今あるものも手放さずに、実直に生きている。透くんの生き方は泥臭いけれど綺麗です。私が出会ってきた誰よりも、綺麗です。それを頑張っていると言わずに何と言うんですか」
君の凄いところは欲張りなところだった。手の届かないかもしれない目標に向かって飛ぶとき、背負うものは軽い方がいい。それでも君は沢山の人の想いや応援を全て背負って挑んでいた。それがどれだけ茨の道か、私には分からない。それでも君が俳優の話をするときに時々息が詰まるような表情をしているのを知っている。
背骨越しに君の浅い息遣いが聞えた。どうしよう、なんて声を掛けよう。感情を露わにしない彼の心が揺れている、その事実に動揺してしまって更に焦りが募る。でも、君が今一番必要な言葉を贈ってあげたかった。自分があの時、否定されたときに、欲しかった言葉を言ってあげられたら少しは救えるだろうか。
繋がれた弱弱しい手を振りほどく。君は拒否されたことが恥ずかしかったのか、さっと引っ込めようとするが私は逃さない。ぎりぎりで掴んだ手をもう離れないように強く、強く握りしめた。
「透くん、辛いときは辛いって言っていいんですよ」
当たり前を許されていない私たちだからこそ、二人のときにその当たり前を求めてしまうのだろう。君はその言葉を聞いた瞬間、堰を切ったように目から涙を流す。私がそっとその肩を引き寄せると、いつもの透くんでは想像できないほど苦しそうな声で泣いた。
「俺、きょう、だめかも」
「だめでもいいですよ」
「ん……」
「どれだけ情けなくても、駄目駄目でも、私は貴方が泣き止むまでずっと傍にいます。離れないと約束します」
膝で震える手を必死に抑えようとしている君が愛おしくて、思わず繋がれていない反対の手にも自分の手を重ねた。
その姿はつい一時間前に牙を剝いていた強気の態度の青年とはあまりにもかけ離れている。しかし、それで幻滅するようなことは断じてない。
私も弱いところがあって、君にも弱いところがある。
それでいいじゃないか。私たちは弱いけれど、受け止められないほど脆くはないのだから。
「手、冷たいですよ。夏なのに」
指先から伝わるひんやりとした感覚に驚いた。まるで血が通ってないかのような温度だった。
「うるさい」
「大丈夫です。冷たいなら温めればいいだけなので」
優しく握りこむと君は繋がれた二つを自分の頬に寄せた。涙が二人の手の僅かな隙間に入り込む。しゃっくりの合間の小さな声は、声変わりの終わった青年が少年に戻ったように上ずっていた。
「……ありがとう」
小さな感謝の言葉は私の鼓膜を揺らした後、真っ暗な空に吸い込まれていった。
小高い山にひっそりと佇む古びた公園は、この町で一番空に近い場所だった。
その日、宇宙に一番近いのは間違いなく私たちだった。
私は多分、君が宇宙に行くと言うなら宇宙まで行こうと思う。貴方は私にたくさんの新しいものを教えてくれる。私はその全部を目に、皮膚に、脳に、焼き付けてぜんぶ覚えておきたい。