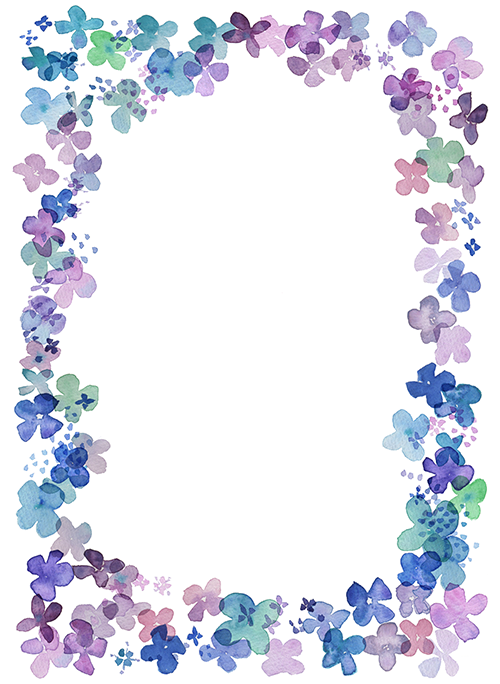「っは……」
目覚めは最悪だった、いや最悪なんて生ぬるいものではない。俺は唐突な嘔気に耐えられなくなって森の中に逃げる。隣に少女がいないことが分かると、我慢の限界だった胃が痙攣して胃酸が逆流してくる。口の中に苦いものが広がった。何度も何度もえずいてとうとう食道が口から飛び出そうになったときに、疲れ果てて横向きに倒れた。
乱れた呼吸を整えながら、目を瞑る。あれは夢だ、母親がこんな辺境にいるはずない。しかし、心拍数は落ち着くどころか、鼓動を早める。俺は珍しく混乱していた、こんな情けない姿君に見られなくてよかった。
「そういえば、ボタンは……」
静寂に包まれる朝の森では寝息も筒抜けだった。洞窟に戻ると規則正しい呼吸音と、寝返りをするのが聞えてきてほっと胸を撫でおろす。気持ちよさそうな寝顔を覗き込み、あがった心拍数を落ち着かせようと深呼吸をした。
丁度その時、彼女の薄い瞼がぴくぴくと痙攣して、躊躇うようにゆっくりと開かれた。
「はよ」
ボタンは眠たそうに目を擦ると、挨拶をした俺の顔をまじまじと見てくる。まだ胃液がついているのかもしれない、一応顔はちゃんと洗ったはずなのに。俺が慌てて口元を拭うと、微睡んでいた彼女の瞳にようやく生気が宿った。驚いたように上体を起こすと、そのまま背骨を仰け反らせて後ろに下がる。目を瞬かせる彼女の不審な動きに俺は自然と目を半眼にして様子を伺った。
「お、おはようございます」
「何、その反応」
「……寝起きで何故そんなに美しい顔をしてるんですか?流石に私も人間を辞めたくなるんですけれど」
「新手の嫌味か」
拭った袖は汚れていないので本当にただそれだけの理由で驚いているらしい。彼女が俺の顔に興味がないことは最初から分かっている。今まで出会ってきた女性は大抵顔ばかりじろじろと見て、大して話も聞かずににこにこ相槌を打っているような奴ばかりだったが君は違った。俺のパーツじゃなくて目を、声じゃなくて話を聞いてくれる。もしかしてそういう趣味か女色なのかと疑ってるが敢えて聞くことはない。そこまで首を突っ込んで知りたいとは思ってないからだ。
夜のうちに雨が降ったのか、洞窟の入り口は濃霧が白く立ちこめている。健気に咲く朝顔の葉では朝露が滑っていた。
土臭い雨上がりの香りが好きだ。
そして隣には自分を性的な目で見てくることのない女。
こんなにも心地の良い朝を迎えたのはいつぶりだろう。
「ため口辞めたの?」
「ため……?」
「砕けた話し方、辞めたの」
「あ、いや、あれは……」
昨日必死になるあまり、丁寧な言葉を忘れた君はもうそこにはいなかった。本心を晒しだすようになったとは言え、理性をまだ砕ききってはいない。依然丁寧な言葉遣いは使い続けるようで、俺は歯痒い表情を向けた。
「まぁいいや」
今はまだいい、いつかそれすらも取っ払って楽になれたらよかった。自分に丁寧な言葉を使ってほしいわけじゃなくて、君が楽に話せればそれでいいのだ。まだ敬語のほうが楽なら無理に砕けずとも敬語を使ってほしい。
「今日何したいの、ボタンは」
話題を変える俺にほっとしたような顔をする。これでも心配していたので少し傷ついた。顔に出ることは無くとも、俺だって色々考えることはあるのだ。感情が薄くなったとしても、濡れた捨て犬を見捨てられぬように多少の情は湧く。君はその枠に当てはまっている。
目の前の少女は考えを巡らせるように斜め右を見つめた後、唇を結んだまま何が言い出そうとする。躊躇うくらいならいっそ言ってから後悔すればいいのに。しかし君の考えはそうではないらしい。熟考に熟考を重ねた彼女の決断は口を開くことだった。
「……祭りに行きたいです」
「は?」
せっかくあそこから逃げてきたのに、もう一度飛び込むなんて阿呆なのか。
喉を通り過ぎて上咽頭までのぼって出掛かった言葉を飲み下す。
でもこれは言ってしまっても良かったかもしれない。なんて無茶な願いを託してくるのだろう。
俺の顔が歪むのを確認しても尚、意志の強い瞳は揺れることなく真っ直ぐと俺を射抜く。
「自分の発言が愚かなのは承知の上で頼んでいます。ですが一度でいいから行ってみたかったんです。ずっと遠くから眺めるだけだったので」
ボタンが零すその一言は俺に二の句を継がせない最適解だった。そんなこと言われてしまえば、駄目だとは言えないだろう。やりたいことをやるために、生きることを決めたのだから。
俺は少女の願いを叶えてあげたいと思った。
ヒーローとは言わずとも救世主になりたい。
二十四の男にしては子供じみた願いだろうか。
でも彼女の背景を知ってしまえばその幸せを願わずにはいられなかった。
貼り付けの笑みではなく心から笑う君を見てみたい。
こんな欲を七つも年下の娘に抱くなんて気色悪いだろう。
それこそ俺を取り巻く人や応援してくれる人がその事実を知れば興醒めしてもう二度と陽の目を浴びれないかもしれない。
何も持ち合わせてない少女に自分が何故振り回されるのか自分でも分からなかった。
しかしただの庇護欲ではないことは確かだった。
その感情に名前をつけてしまうのは勿体ないと思った。汚い自分の中で唯一誰かの幸せを願える綺麗な部分を全部理解してしまうのは嫌だし、そんなに軽々しく名がつくものでないと悟っている。
だから大切に取っておくのだ。気づかないように、あまり見つめすぎないように。
「分かった。ただ俺は準備があるからまた18時、ここに集合しよう」
躊躇うことなく承諾する俺に頼んできた本人は酷く驚いていた。そうやって隠そうとしているが内心喜んでいるのはばればれだった。口角が何かを堪えるようにぴくぴくと震えているのを俺は見逃さない。
「準備って?」
「仕事とか色々」
これは嘘だった。今更マネージャーに何か言ったところで見逃してくれるはずもなく、連行されてしまう。ここで下手な手を取ると君の人生にまで影響が及ぶだろう。
俺は別の用事で君と離れる必要があった。
祭りと言えば「アレ」だろう。
俺は君に背を向けると、街の端に見つけたトンネルを目指した。あそこからだったらもしかしたら隣町まで繰り出せるかもしれない。
足元は山間部ということもあり不安定だったが、俺の足取りは不思議と軽かった。
誰かの為、という思いが俺を少しずつ変えていっている。
足元ばかりだった視界が真っすぐとトンネルの先を見据える。それから意味もなく空を見上げた。
雨上がりの空に似合わない明るい惑星は惜しみなく世界に光を降り注ぐ。俺はその光の雫を余すことなくぜんぶ飲み干したいと思った。
目覚めは最悪だった、いや最悪なんて生ぬるいものではない。俺は唐突な嘔気に耐えられなくなって森の中に逃げる。隣に少女がいないことが分かると、我慢の限界だった胃が痙攣して胃酸が逆流してくる。口の中に苦いものが広がった。何度も何度もえずいてとうとう食道が口から飛び出そうになったときに、疲れ果てて横向きに倒れた。
乱れた呼吸を整えながら、目を瞑る。あれは夢だ、母親がこんな辺境にいるはずない。しかし、心拍数は落ち着くどころか、鼓動を早める。俺は珍しく混乱していた、こんな情けない姿君に見られなくてよかった。
「そういえば、ボタンは……」
静寂に包まれる朝の森では寝息も筒抜けだった。洞窟に戻ると規則正しい呼吸音と、寝返りをするのが聞えてきてほっと胸を撫でおろす。気持ちよさそうな寝顔を覗き込み、あがった心拍数を落ち着かせようと深呼吸をした。
丁度その時、彼女の薄い瞼がぴくぴくと痙攣して、躊躇うようにゆっくりと開かれた。
「はよ」
ボタンは眠たそうに目を擦ると、挨拶をした俺の顔をまじまじと見てくる。まだ胃液がついているのかもしれない、一応顔はちゃんと洗ったはずなのに。俺が慌てて口元を拭うと、微睡んでいた彼女の瞳にようやく生気が宿った。驚いたように上体を起こすと、そのまま背骨を仰け反らせて後ろに下がる。目を瞬かせる彼女の不審な動きに俺は自然と目を半眼にして様子を伺った。
「お、おはようございます」
「何、その反応」
「……寝起きで何故そんなに美しい顔をしてるんですか?流石に私も人間を辞めたくなるんですけれど」
「新手の嫌味か」
拭った袖は汚れていないので本当にただそれだけの理由で驚いているらしい。彼女が俺の顔に興味がないことは最初から分かっている。今まで出会ってきた女性は大抵顔ばかりじろじろと見て、大して話も聞かずににこにこ相槌を打っているような奴ばかりだったが君は違った。俺のパーツじゃなくて目を、声じゃなくて話を聞いてくれる。もしかしてそういう趣味か女色なのかと疑ってるが敢えて聞くことはない。そこまで首を突っ込んで知りたいとは思ってないからだ。
夜のうちに雨が降ったのか、洞窟の入り口は濃霧が白く立ちこめている。健気に咲く朝顔の葉では朝露が滑っていた。
土臭い雨上がりの香りが好きだ。
そして隣には自分を性的な目で見てくることのない女。
こんなにも心地の良い朝を迎えたのはいつぶりだろう。
「ため口辞めたの?」
「ため……?」
「砕けた話し方、辞めたの」
「あ、いや、あれは……」
昨日必死になるあまり、丁寧な言葉を忘れた君はもうそこにはいなかった。本心を晒しだすようになったとは言え、理性をまだ砕ききってはいない。依然丁寧な言葉遣いは使い続けるようで、俺は歯痒い表情を向けた。
「まぁいいや」
今はまだいい、いつかそれすらも取っ払って楽になれたらよかった。自分に丁寧な言葉を使ってほしいわけじゃなくて、君が楽に話せればそれでいいのだ。まだ敬語のほうが楽なら無理に砕けずとも敬語を使ってほしい。
「今日何したいの、ボタンは」
話題を変える俺にほっとしたような顔をする。これでも心配していたので少し傷ついた。顔に出ることは無くとも、俺だって色々考えることはあるのだ。感情が薄くなったとしても、濡れた捨て犬を見捨てられぬように多少の情は湧く。君はその枠に当てはまっている。
目の前の少女は考えを巡らせるように斜め右を見つめた後、唇を結んだまま何が言い出そうとする。躊躇うくらいならいっそ言ってから後悔すればいいのに。しかし君の考えはそうではないらしい。熟考に熟考を重ねた彼女の決断は口を開くことだった。
「……祭りに行きたいです」
「は?」
せっかくあそこから逃げてきたのに、もう一度飛び込むなんて阿呆なのか。
喉を通り過ぎて上咽頭までのぼって出掛かった言葉を飲み下す。
でもこれは言ってしまっても良かったかもしれない。なんて無茶な願いを託してくるのだろう。
俺の顔が歪むのを確認しても尚、意志の強い瞳は揺れることなく真っ直ぐと俺を射抜く。
「自分の発言が愚かなのは承知の上で頼んでいます。ですが一度でいいから行ってみたかったんです。ずっと遠くから眺めるだけだったので」
ボタンが零すその一言は俺に二の句を継がせない最適解だった。そんなこと言われてしまえば、駄目だとは言えないだろう。やりたいことをやるために、生きることを決めたのだから。
俺は少女の願いを叶えてあげたいと思った。
ヒーローとは言わずとも救世主になりたい。
二十四の男にしては子供じみた願いだろうか。
でも彼女の背景を知ってしまえばその幸せを願わずにはいられなかった。
貼り付けの笑みではなく心から笑う君を見てみたい。
こんな欲を七つも年下の娘に抱くなんて気色悪いだろう。
それこそ俺を取り巻く人や応援してくれる人がその事実を知れば興醒めしてもう二度と陽の目を浴びれないかもしれない。
何も持ち合わせてない少女に自分が何故振り回されるのか自分でも分からなかった。
しかしただの庇護欲ではないことは確かだった。
その感情に名前をつけてしまうのは勿体ないと思った。汚い自分の中で唯一誰かの幸せを願える綺麗な部分を全部理解してしまうのは嫌だし、そんなに軽々しく名がつくものでないと悟っている。
だから大切に取っておくのだ。気づかないように、あまり見つめすぎないように。
「分かった。ただ俺は準備があるからまた18時、ここに集合しよう」
躊躇うことなく承諾する俺に頼んできた本人は酷く驚いていた。そうやって隠そうとしているが内心喜んでいるのはばればれだった。口角が何かを堪えるようにぴくぴくと震えているのを俺は見逃さない。
「準備って?」
「仕事とか色々」
これは嘘だった。今更マネージャーに何か言ったところで見逃してくれるはずもなく、連行されてしまう。ここで下手な手を取ると君の人生にまで影響が及ぶだろう。
俺は別の用事で君と離れる必要があった。
祭りと言えば「アレ」だろう。
俺は君に背を向けると、街の端に見つけたトンネルを目指した。あそこからだったらもしかしたら隣町まで繰り出せるかもしれない。
足元は山間部ということもあり不安定だったが、俺の足取りは不思議と軽かった。
誰かの為、という思いが俺を少しずつ変えていっている。
足元ばかりだった視界が真っすぐとトンネルの先を見据える。それから意味もなく空を見上げた。
雨上がりの空に似合わない明るい惑星は惜しみなく世界に光を降り注ぐ。俺はその光の雫を余すことなくぜんぶ飲み干したいと思った。