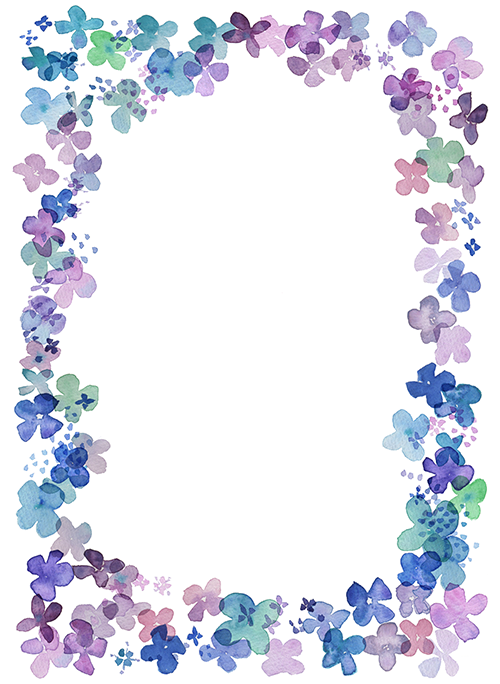「透」
誰かが俺の名前を呼んでいる。視界は膜が張られたようにぼやけてよく見えない。俺は目を凝らしながら耳を澄ませた。
「私はね、透のことが世界で一番大切なのよ」
陶器のようになめらかで毛穴一つない白い肌
透けてしまいそうなほど透き通った瞳
形のよい鼻、薄い桃色の唇
目の前の女は呟きながら俺の顔をまるで骨董品に触れるように撫でまわす。思わずぞわっと鳥肌が立って一歩後ずさった。目の前の表情筋が一瞬引きつったあと、俺の手首を握る。骨が軋むほど強く。
「死んでもいいくらいに大切なの」
女は赤い唇を舐めて湿らす。糸を引く口には歯紅がついていた。艶めかしい手つきで俺の首を撫でると、頸動脈に触れた。女と視線が絡み合う、その目は一度獲物を決めたときの蛇のように獰猛で、俺は逸らしたくても逸らせなかった。
「私は透を裏切らないわ、だから透も私のことを裏切らないって約束してくれる?」
感情のない声だった。
今、この瞬間にこの女を殺せればとれだけ幸せだろうか。
幼い自分はこうやって殺されていったのに、何故この女は今ものうのうと生きているのだろう。
それでも心のどこかでは憎み切れなかった。
人の心はパンみたいなものだ。目に見えなくとも黴が生えればそれは瞬く間に端から端まで侵食される。
健全だった俺の心はこの女の毒牙にかかって壊れてしまった。
許してはいけないと思っても結局は許してしまう。許した瞬間に自我は一つ消えてゆき、黴は広がっていく。彼女がいなければ俺は大人になれなかった、俳優として今人生を歩めていなかった。俯瞰的に見れば俺の人生において彼女は必要不可欠だったのだと思ってしまう。
チャップリンはこう言う、「人生は近くから見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」と。
そうだ、この人は悪くない。人生を瞰視できない自分自身が悪いのだ
俺はゆっくりと瞬きをした。目の前が急に鮮明になって、ぼやけていた女の顔が浮かび上がる。見慣れた顔だと思ったら、そりゃそうか。
そこにいたのは紛れもない俺の母親だった。
「透、欲張っちゃ駄目よ。もし欲張って今まで積み上げたものが全部なくなったら、お母さん透と一緒に死ぬからね」
首筋に長い爪が食い込む。痛いけれど、涙は出なかった。喉が引きつって息も上手くできない。過呼吸になる俺の眼差しと彼女の視線はもう交わらない。母親は傷をつけるどころか肉まで削いで、俺に一生消えない傷跡を付けた。たらたらと流れ続ける血を拭った。人差し指から薬指まで朱に染まったのを見て俺は口角を上げる。
母さんが好きなのは俺ではないことはもう分かっていた。この女は『私の息子であり、大人気俳優の相島透』に愛を注いでいるのだ。
俺はもう相島透ではない、これから一生をかけて『俳優の相島透』として生きよう。
笑えるだろう、でも俺は道化師を演じるよ。
殺された幼い自分が唯一遺して逝ったのは「愛されたい」という欲望だけだったから。
血しぶきの飛んだ手を取ると、汚れた皮膚を舐めとる。
目を閉じると瞼の裏には自分の後ろ姿があった。まるでそれは陽炎のように揺らめいて、やがて輪郭が曖昧になって二つに分裂する。俺の中に新しい「僕」が生まれた。「僕」は唇についた血液を舌に絡ませると満足そうな笑みを浮かべた。
「僕は、母さんだけを信じるよ」
「透くんさぁ、何を思ってこの演技してるの」
大事な役だった。初めて主演の座を頂いた映画の一番大事な場面だった。
よくある余命ものの恋愛映画で、予算が沢山あるわけではない。それでも主演ということに母親は喜んでいた。
カットが掛かった時に監督が俺に向かってこう言った。貧乏ゆすり、吸殻の数、俺の演技に不満があることは明らかだ。おかしいな、いつも通りできたはずなのに。
青白い顔がむくりと手元で起き上がる。主人公が好きな女の子が死んでしまうシーンだったので、腕の中で横たわっていた女優の顔はいつもと違い儚げだ。彼女は撮影が止まったことで困ったような顔をしている。
「すみません。以後は悲しい、苦しい、を伝えられるように表情管理も気を付けます」
申し訳なさを前面に出し、もう一度華奢な少女の肩を抱くと監督は鼻で嗤う。燻るものはあったが、俺はぐっと堪えていつもの穏やかな笑みを浮かべた。
大丈夫だ、いつも通り母さんが教えてくれたテンプレートをそのままなぞればいい。俺は再び当たり障りのないことを答えると、監督は何故か顔を顰める。
「まるでロボットみたいな回答だな。もっと、こう、君の想いはないの?」
「想い……?」
俺が言ったことは間違いなのだろうか。いや、そんなはずはない。母さんが間違えたことを俺に教えるなんてことはない。取り合えずこれ以上歪が生まれぬように、人懐っこくこてんと首を傾げておく。腕に熱を感じて視線を下に向けると、女優が量産的な顔を赤く染めていたのできっと大丈夫だろう。
しかし、俺の考えを否定するように監督は舌打ちをして頭を抱えた。
「透くんは、好きな人が目の前で亡くなったらどうする」
「本当に息をしていないか確認します」
「それで?」
「……葬儀場に連絡する?」
俺が答えた途端監督だけでなく周りのアシスタントの人全員が腫物を見る目で俺を見つめた。その視線全部が俺を脱獄犯のように照らす。俺が世界から否定された瞬間だった。そんな中、俺は一人この状況を理解できずにいた。人が死んで他に何をするんだ、花でも添えるのか、抱きしめるのか。そんなことしたって死んだらもうおしまいじゃないか、死んだ人間は生き返らない、願っても叶わないことにどうやって足掻くって言うんだ。
「これは医者でもないし、俳優でもない、相島透だったらどうするって聞いてるんだ」
「はい」
「それを説明した上でもう一度聞くよ、もし好きな人が死んだらどうする」
俺には恋焦がれる気持ちも、分からない。模範解答を見つけようと頭の中から必死に言葉を探すが、今の俺が何かを言ってもそれは蛇足にしかならない気がした。俺は芸能界に入ってから初めて素直な気持ちを伝える。
「分かりません」
頭を振り俯く俺の前を何かが横切った。床が大半を占める視界の端では監督が絶対零度の瞳でため息を吐いている。他のスタッフが立ち去ろうとする彼の腕を掴んだ、マネージャーでもある母さんは俺の頬を思い切り叩いた後監督の前で土下座をする。嗚呼、俺ついにやらかしてしまったのか。頭が真っ白で他には思い浮かばなかった。涙も出ないし、悔しさもない。どうしようと考えを巡らせるが、こんな事態想定していなかったので母さんから対処法も聞いていないし、この場における最適解が分からない。分からないから俺以外がこの状況はまずいと必死に今自分ができる最善の行動をとる中、俺は一人硬直していた。
引き留めるスタッフを振り切り、号泣しながら頭を地面に擦り付ける母さんにすら脇目も振らずに監督はドアノブに手を掛ける。
早くこんな夜過ぎてしまえばいいと思った。
それが俺の中の何かが完全に崩壊した瞬間だった。
繋ぎとめていた蜘蛛の糸がぷつんと無常に切れる音がした。
それでも過ぎてほしいと願ったところで時計の針は勝手に加速しない。俺が居たたまれなさに拳を握りしめたところで、この後に起こる最悪の事態を想像したって、夜は簡単には明けない。
明けてほしいと願う夜はいつだって明けずに、俺を覆い隠すのだ。
最後に監督が手を振った。俺はその仕草がギロチンの歯を落とす合図だと思って目を逸らすことはできずに、ただ現実とは思えないまま見つめていた。
「透くん。そんな人間、どこにも必要とされないよ」
誰かが俺の名前を呼んでいる。視界は膜が張られたようにぼやけてよく見えない。俺は目を凝らしながら耳を澄ませた。
「私はね、透のことが世界で一番大切なのよ」
陶器のようになめらかで毛穴一つない白い肌
透けてしまいそうなほど透き通った瞳
形のよい鼻、薄い桃色の唇
目の前の女は呟きながら俺の顔をまるで骨董品に触れるように撫でまわす。思わずぞわっと鳥肌が立って一歩後ずさった。目の前の表情筋が一瞬引きつったあと、俺の手首を握る。骨が軋むほど強く。
「死んでもいいくらいに大切なの」
女は赤い唇を舐めて湿らす。糸を引く口には歯紅がついていた。艶めかしい手つきで俺の首を撫でると、頸動脈に触れた。女と視線が絡み合う、その目は一度獲物を決めたときの蛇のように獰猛で、俺は逸らしたくても逸らせなかった。
「私は透を裏切らないわ、だから透も私のことを裏切らないって約束してくれる?」
感情のない声だった。
今、この瞬間にこの女を殺せればとれだけ幸せだろうか。
幼い自分はこうやって殺されていったのに、何故この女は今ものうのうと生きているのだろう。
それでも心のどこかでは憎み切れなかった。
人の心はパンみたいなものだ。目に見えなくとも黴が生えればそれは瞬く間に端から端まで侵食される。
健全だった俺の心はこの女の毒牙にかかって壊れてしまった。
許してはいけないと思っても結局は許してしまう。許した瞬間に自我は一つ消えてゆき、黴は広がっていく。彼女がいなければ俺は大人になれなかった、俳優として今人生を歩めていなかった。俯瞰的に見れば俺の人生において彼女は必要不可欠だったのだと思ってしまう。
チャップリンはこう言う、「人生は近くから見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」と。
そうだ、この人は悪くない。人生を瞰視できない自分自身が悪いのだ
俺はゆっくりと瞬きをした。目の前が急に鮮明になって、ぼやけていた女の顔が浮かび上がる。見慣れた顔だと思ったら、そりゃそうか。
そこにいたのは紛れもない俺の母親だった。
「透、欲張っちゃ駄目よ。もし欲張って今まで積み上げたものが全部なくなったら、お母さん透と一緒に死ぬからね」
首筋に長い爪が食い込む。痛いけれど、涙は出なかった。喉が引きつって息も上手くできない。過呼吸になる俺の眼差しと彼女の視線はもう交わらない。母親は傷をつけるどころか肉まで削いで、俺に一生消えない傷跡を付けた。たらたらと流れ続ける血を拭った。人差し指から薬指まで朱に染まったのを見て俺は口角を上げる。
母さんが好きなのは俺ではないことはもう分かっていた。この女は『私の息子であり、大人気俳優の相島透』に愛を注いでいるのだ。
俺はもう相島透ではない、これから一生をかけて『俳優の相島透』として生きよう。
笑えるだろう、でも俺は道化師を演じるよ。
殺された幼い自分が唯一遺して逝ったのは「愛されたい」という欲望だけだったから。
血しぶきの飛んだ手を取ると、汚れた皮膚を舐めとる。
目を閉じると瞼の裏には自分の後ろ姿があった。まるでそれは陽炎のように揺らめいて、やがて輪郭が曖昧になって二つに分裂する。俺の中に新しい「僕」が生まれた。「僕」は唇についた血液を舌に絡ませると満足そうな笑みを浮かべた。
「僕は、母さんだけを信じるよ」
「透くんさぁ、何を思ってこの演技してるの」
大事な役だった。初めて主演の座を頂いた映画の一番大事な場面だった。
よくある余命ものの恋愛映画で、予算が沢山あるわけではない。それでも主演ということに母親は喜んでいた。
カットが掛かった時に監督が俺に向かってこう言った。貧乏ゆすり、吸殻の数、俺の演技に不満があることは明らかだ。おかしいな、いつも通りできたはずなのに。
青白い顔がむくりと手元で起き上がる。主人公が好きな女の子が死んでしまうシーンだったので、腕の中で横たわっていた女優の顔はいつもと違い儚げだ。彼女は撮影が止まったことで困ったような顔をしている。
「すみません。以後は悲しい、苦しい、を伝えられるように表情管理も気を付けます」
申し訳なさを前面に出し、もう一度華奢な少女の肩を抱くと監督は鼻で嗤う。燻るものはあったが、俺はぐっと堪えていつもの穏やかな笑みを浮かべた。
大丈夫だ、いつも通り母さんが教えてくれたテンプレートをそのままなぞればいい。俺は再び当たり障りのないことを答えると、監督は何故か顔を顰める。
「まるでロボットみたいな回答だな。もっと、こう、君の想いはないの?」
「想い……?」
俺が言ったことは間違いなのだろうか。いや、そんなはずはない。母さんが間違えたことを俺に教えるなんてことはない。取り合えずこれ以上歪が生まれぬように、人懐っこくこてんと首を傾げておく。腕に熱を感じて視線を下に向けると、女優が量産的な顔を赤く染めていたのできっと大丈夫だろう。
しかし、俺の考えを否定するように監督は舌打ちをして頭を抱えた。
「透くんは、好きな人が目の前で亡くなったらどうする」
「本当に息をしていないか確認します」
「それで?」
「……葬儀場に連絡する?」
俺が答えた途端監督だけでなく周りのアシスタントの人全員が腫物を見る目で俺を見つめた。その視線全部が俺を脱獄犯のように照らす。俺が世界から否定された瞬間だった。そんな中、俺は一人この状況を理解できずにいた。人が死んで他に何をするんだ、花でも添えるのか、抱きしめるのか。そんなことしたって死んだらもうおしまいじゃないか、死んだ人間は生き返らない、願っても叶わないことにどうやって足掻くって言うんだ。
「これは医者でもないし、俳優でもない、相島透だったらどうするって聞いてるんだ」
「はい」
「それを説明した上でもう一度聞くよ、もし好きな人が死んだらどうする」
俺には恋焦がれる気持ちも、分からない。模範解答を見つけようと頭の中から必死に言葉を探すが、今の俺が何かを言ってもそれは蛇足にしかならない気がした。俺は芸能界に入ってから初めて素直な気持ちを伝える。
「分かりません」
頭を振り俯く俺の前を何かが横切った。床が大半を占める視界の端では監督が絶対零度の瞳でため息を吐いている。他のスタッフが立ち去ろうとする彼の腕を掴んだ、マネージャーでもある母さんは俺の頬を思い切り叩いた後監督の前で土下座をする。嗚呼、俺ついにやらかしてしまったのか。頭が真っ白で他には思い浮かばなかった。涙も出ないし、悔しさもない。どうしようと考えを巡らせるが、こんな事態想定していなかったので母さんから対処法も聞いていないし、この場における最適解が分からない。分からないから俺以外がこの状況はまずいと必死に今自分ができる最善の行動をとる中、俺は一人硬直していた。
引き留めるスタッフを振り切り、号泣しながら頭を地面に擦り付ける母さんにすら脇目も振らずに監督はドアノブに手を掛ける。
早くこんな夜過ぎてしまえばいいと思った。
それが俺の中の何かが完全に崩壊した瞬間だった。
繋ぎとめていた蜘蛛の糸がぷつんと無常に切れる音がした。
それでも過ぎてほしいと願ったところで時計の針は勝手に加速しない。俺が居たたまれなさに拳を握りしめたところで、この後に起こる最悪の事態を想像したって、夜は簡単には明けない。
明けてほしいと願う夜はいつだって明けずに、俺を覆い隠すのだ。
最後に監督が手を振った。俺はその仕草がギロチンの歯を落とす合図だと思って目を逸らすことはできずに、ただ現実とは思えないまま見つめていた。
「透くん。そんな人間、どこにも必要とされないよ」