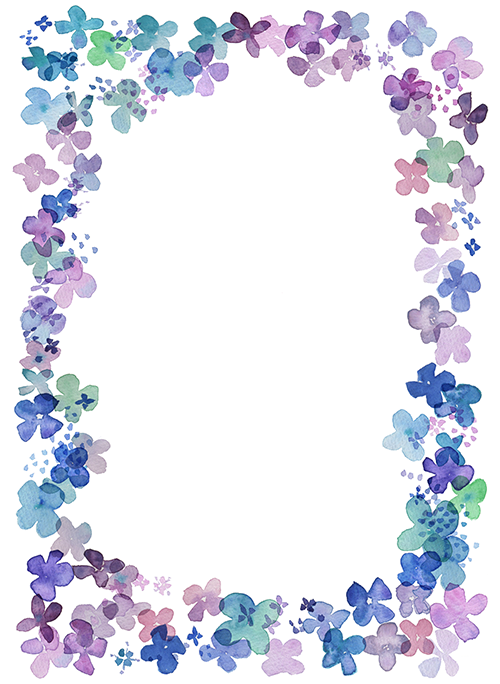息苦しいな。私はどうにかできないものかと腰にきつく巻き付けられた帯に手を当てる。ただでさえ内臓でないものが一つ、腹の中を支配しているのだ。これ以上きつくされれば流石に呼吸が辛かった。しかし、煌びやかなそれは思いのほかしっかりと取り付けられており簡単には緩められない。
それにしてもここまで着飾る意味はあるのだろうか。
朝から湯あみをさせられ、髪を複雑に結われて、上等な絹を何枚も重ねられた。十二単ほどではないが布の厚みの代わりにネックレス、ピアス、簪などの装飾品がこれでもかというほど盛られている。おかげで私は最期の晩餐もろくに味わえなかっのだ。食の恨みは一生というが、私から鰻丼を取り上げた罪は近海の海溝よりも深い。一口しか口につけなかった鰻丼とすまし汁を回収していった巫女には私の死後、毎回鰻丼に致死量の山椒が振りかけられる呪いをかけておこうと決意した。
ため息を吐きながらほの暗い部屋の唯一の光源である外に流し目を送る。いつものもの寂しい石畳とは打って変わって沢山の屋台が並び、境内には赤い提灯がぶら下げられている。どこからか笛と小堤の音が聞こえてきて真夏の訪れを実感する。今年もこの季節がやってきた。今日は私が生まれてから17回目の奉納祭だった。
「お嬢様、お支度は整いましたか」
しばしの間、ぼうっと外を眺めていると、巫女がドア越しに尋ねてくる。慌てて姿勢を正した私が返事をすると、数センチ開いた扉から手が伸びてきて盃が床に置かれた。
「覚悟が決まったからこれを飲んでください」
「これは何ですか」
聞いてから自分のしたことが無粋だと気が付いた。彼女もそれを示唆するように無言を貫く。
「亥の刻までに飲まなければ辛い目に遭います故、それまでには必ずお飲みください」
それでは、と静かに告げると人の気配はなくなった。私は口を真一文字に結びながら取り残された盃を見つめる。紫の液体は提灯の明かりを反射して怪しげに光っている。恐らくこれは葡萄酒だろう。液体に鼻を近づけ、香りを嗅ぐときつい蒸留酒と甘ったるい葡萄の匂いがした。きっとこの中には睡眠薬と遅効性の毒が入っているのだろう。まず睡眠薬で眠って、意識のないまま神に捧げられ私の体は解体される。万が一致死量を超えた睡眠薬で死ねなくとも、毒が全身に回れば確実に心臓は止まる。実に便利な飲み物だ。
「巫女が言ってた辛い目っていうのは、多分意識のあるまま殺されるってことだろうなぁ」
貼り付けにされたまま体をばらばらにされる想像をした。うん、それだけは避けたいな。私は盃に手を伸ばすと、人差し指だけ浸す。赤紫の液体のついた指をぺろりと舐めた。この程度では多分死ねない。舌に山椒を食んだときのような痛みが走ったが、私の意識はまだ保たれたままだった。
視線はゆっくりと傾き、いつの間にか私は布団も敷いていない床に仰向けに転がる。
祭り囃子の音が近づいたり遠ざかったりしてよく聞こえなかった。子供がはしゃぐ声も、段々と膜が張られたようにぼやけていく。年に一度だけ風に乗って流れてくるこの匂い、好きだったなぁ。質素な食事しか口にしてこなかった私にとってこの中濃ソースの香はたこ焼きか、お好み焼きか、たませんか想像を掻き立てるには十分だった。
「りんご飴、綿あめ、金魚すくい……」
屋台ののれんを眺めては口に出す。食べたこともない、体験したこともないそれに想いを馳せながら死ぬのもまた一興だろうか。
目を細めて遠くを見つめる。十にも満たない兄弟が仲良く手を繋ぎながら歩いていた。彼らは金魚すくいの店の前で足を止めると、二人で緑の虫眼鏡みたいなのを使ってすばしっこく泳ぐものを捕まえようとする。兄の方は3つ捕まえて袋を手に下げたが、妹の方は一匹も得られなかったようで空っぽの両手をじっと見つめた後その場で泣き出してしまう。
「あちゃー……」
あれは中々機嫌を取るのが難しい。これから彼らはどうするのか気になってしまった私は引き続きその様子を眺める。
兄は慌てて少女の涙を拭ってから、ぎゅっと小さな体を包み込んだ。そして手に下げた袋を妹に持たせてやる。妹はまだ止まらない涙を忘れて嬉しそうに笑ってそのきらきらした瞳で袋の中をずっと観察していた。
私は思わず綻ぶ。この子たちの幸せを守るために、死ねるならいいか。この世には酒に溺れて死にゆくものや、職場でいじめを受けて身を投げるものもいると聞く。それに比べればまだ私は綺麗に散れる方か。
「さぁ、そろそろ飲まなきゃ」
体を起こして盃を取りに行く。正座をして、襟を整えた。無駄な足掻きかもしれないが、散り際くらい綺麗でいたいのは女としての意地だった。
痛いだろうか、苦しいだろうか。そんなことも感じる間もないまま意識を失うのだろうか。
目を閉じて食器の淵に唇をつける。瞼を固く閉じると、覚悟が今だ定まらない震える手を緩やかに傾ける。
その時だった。
「今日はいつもと服が違うんだな」
どこからか声がする。小さくしていた背中をぴんと伸ばして振り返ると見慣れた顔がそこにはあった。
どうしてここにいるんだろう、昨日でおしまいのはずではなかったのか。
「透くん?」
濡れた唇を舐めながら君の名前を呼ぶ。あまりの衝撃に手の力は抜けて、漆塗りの高級食器は酒を盛大にぶちまけながら砕け散った。
高そうな布は瞬く間に紫色に染まった。嗚呼これは染み抜きしても取れなさそうだ、なんてこの期に及んで冷静な頭はきっと情報過多でショートしていたのだと思う。
「何してたんだ、今日の主人公さん」
神に捧げる少女のことを知ってる癖にこの男はいつもと変わらない不愛想なトーンだった。目の前に数時間後には死ぬ人がいても彼はこんな感じらしい。実に冷淡というか、淡白というか、そういう言葉が似あう人だ。
「たった今死ぬところだったのですが……」
痺れる唇でそう答えると、彼はぎょっとしたように目を見開く。
「それは邪魔した」
彼は珍しく申し訳なさそうな顔をする。私は気にしていないと顔を横に振った。
「それにしてもここで自死なんだな。もっと神殿とかでやると思ってたけど」
「私もびっくりしました」
私は彼から割れた盃に視線を戻した。どうしよう、このままでは生きたまま殺されるのかな。しかし、液体の大半はすでに畳と衣装に染み込んでしまった。絞れば多少はあるかもしれないが、何年前の衣装か分からないものに一度染み込んだものを口にするのは気が引けた。それでも背に腹は代えられないかと仕方なく盃の一番大きな欠片に着物を絞っていると、君のラムネのびいとろみたいに澄んだ声が鼓膜を揺らした。
「最期になんか言っておきたいことはないの?」
「えっ……」
「ほらここにいるのは俺だけだし、吐き出したいことあればここで言っちゃえば?後悔したまま逝くのは嫌だろ」
そう言われると何か遺言を残すのも悪くない。手を止めてうーんと唸ってみるが、特に考えは思いつかなかった。それも自分が空っぽだからだろうか、何も考えずに何も疑わずに生きてきたからこんなにも死に対して思うものがないのかもしれない。
困ってしまって眉を顰めて彼の顔を見ると、一つ案が思い浮かんだ。私はゆるりと口角を上げた。
「では、名前を呼んでください」
君は驚いた顔をしていた。私が言った言葉の意味が分からないようで鸚鵡のように同じ言葉をなぞる。
そんなに難しいことだろうか。彼がいつもやってる『どらま』とやらに比べた簡単だと思うのだが。私はもう一度ゆっくりと区切りながら言う。
「私の名前を、呼んでください」
「……それでいいのか」
「はい」
「……無欲なやつめ」
呆れただろうか、死に際でもこんなことしか願えない少女だと。でも、私だって最期くらい名前を呼ばれてみたかったのだ。世の親が子供に贈る一番最初の贈り物を、私だって受け取ってみたかったのだ。君は私に名前を付けた割に自ら進んでそれを口にしようとはしない。一度くらい呼んでくれてもいいのにと毎回少し落ち込んでいたのは墓場まで持っていこう。
彼と視線が絡まる。ソースの匂いに混ざって、五月の新緑のような匂いがした。君が私の頬を指でなぞっていたのだ。窓から君が手を伸ばして私に触れたのは、それが初めてだった。
「ボタン」
名前を呼んだ瞬間に震えた瞳。その瞬間君がふっと表情を崩した。私はそれに違和感を覚えた。出会った時の笑顔はもっと口角が上がっていて、上がった口角は毎回同じ角度で揃っていて、完璧すぎるほどに完璧であった。今の君の笑い方は不器用で、口角は上がりきることなく照れを隠すためにはにかまれている。涼しげな目じりは何故か悲しみを滲ませていた。
「……どうした?」
「へ……」
彼は首を傾げながら親指で頬骨の辺りを擦ってくる。私は君がふざけているのかと思ってその手を静止させようとしたが、どうやら冗談ではないらしい。悲しげだった目じりは、まるで痛々しくて見ていられないとばかりに歪んだ。
私はそっと彼の右手に自分の手を重ねる。そこには雨漏りのように透明な雫が零れ続けていた。
「なん……っで」
反射的にごしごしと涙を拭った。おかしいな、なんで泣いてるんだろう。特に悲しいとも苦しいとも感じていないのに。平気だと笑う顔とは不釣り合いなくらいに涙は止まることを知らなかった。彼は右手は添えたまま、茫然と目の前を見つめていた。見苦しい姿を見せてしまって申し訳ない。
しかし、「失礼しました」という言葉の代わりに口から零れたのは自分でも全く想像できないものだった。
「なんで私には当たり前がないのかなぁ」
呟いた自分も、呟かれた君も、動揺したように肩を震わす。体をじんわりと侵食するのは冷たい感情だった。駄目だと理性がブレーキを掛けようとする。これはもう小さい頃に殺したものだろう、神に捧げる少女の覚悟を持ったときにもう二度と思い出さないように何度もナイフで刺して殺した感情だろう。
「駄目……」
ぎゅっと閉じた目に力を籠める。鼻を啜って頭を振りながら、必死に元の自分に戻ろうとした。今の私は少しおかしくなっている。早く何でもないですって笑わなきゃ。荒くなる息を止めて表情筋に力を入れると、意志とは反対に口はへの字に曲がっていく。
「言って」
優しい声だった。あたたかくて、ずっと聞いていたいくらい柔らかくて優しい声だった。ゆっくり固く閉じていた目を開くとぼやける世界で、声の主が蕩けそうなくらい優しい表情をしていた。私は人間の、こんな顔を見たことはない。
私の心の声はなんだ。
私が言いたかったことはなんだ。
私の体の奥でずっと燻っていた感情はなんだ。
空っぽなはずの君が私の固まっていたものをいとも簡単に解して、解放する。
鳥籠の鍵を探してあげるのではなく、籠ごと溶かしてくれる。
私はその感覚が不思議で堪らなかった。
「本当だったら、普通の親に育てられて、普通に小学校行って、普通に友達ができて、普通に誰かを好きになって、普通の17歳の誕生日を迎えてるはずだったんです。大切な人に囲まれて、『おめでとう』『生まれてきてくれてありがとう』って祝ってもらって、『こちらこそ生んでくれてありがとう』って笑顔で返したかったんです」
ぽつりぽつりとそれこそあばら屋の雨漏りのように、私は気づけば言葉を君にぶつけていた。
卑しい少女の、くだらない幼少期の話、彼にとっては時間の無駄だろう。
しかし私の考えを否定するように彼は黙って聞いていた。相槌もなければ、何かいうこともないけれど、君が聞いてくれていることがうれしかった。
「私の親は私を育てきれずに、物心つく前に私を神社の前に捨てました。その年の夏は本当に暑くて、神社の隣で育てているスイカが全滅してしまうほどだったみたいです。少しでも発見が遅れていたら死んでいただろうと、だから私たちに感謝しなさいと、毎年おめでとうの代わりに言われてきました」
私の誕生日はおめでたい日ではなく、呪いの始まりだった。
「私はそれから誕生日の日は決まって死にたくなりました」
睫毛を伏せた後、笑いが込み上げてきた。自分自身と親に対しての嘲笑だった。
「この神社に私を捨てるなんてそんなの一択じゃないですか、要らないから捨てよう。でもどうせなら神に捧げる子にして、村の安泰の糧になればいいかって魂胆が丸見えじゃないですか、自分の親ながら笑ってしまいますよね。私は物と同じなんですよ、要らなければ捨てる。物は感情を持たないから誰かの為になるなら喜んで寄贈する」
あまりに滑稽な親子だ。神社に捨てた母親も、捨て子という運命を受け入れて自分を殺してまで『神に捧げる少女』を振舞ってきた娘も。
「もし、私が捨てられたのが神社じゃなければ私は死んでいました」
目の前の俳優は何とも言えない顔をしていた。きっと「それは災難だったね」と微笑みながら慰めることもできたし、「どうせ死ぬんだからぐちぐち考えるな」と冷たい表情で切り捨てることも、この場において役者である彼にしてみれば容易いものだっただろう。
しかし、君は何も言わなかった。
予想以上に話に聞き入っているらしい、表情管理を忘れたようにただ私の口から紡がれる言葉を静かに待っていた。
「でも、もし私が捨てられたのがここでなければ。……私は17年間も生きることに苦しまなかった。苦しみを知る前に死ぬことができた」
そうか、私はずっと苦しかったのか。
固まっていた心の欠片がほぐれていく。とっくに忘れてしまったと思っていた感情は、見て見ぬふりをしていただけでずっと心では渦巻いていたようだ。
でも、と心の中で理性が首を振る。
それに気づいたから何だというのだ、気づいたところで痛む心は数時間後にはもうこの世にないのに。
私は諦めのついた顔で微笑んだ。
「けれど、今日まで生きてしまったから。生きたいと思ってしまったから。今日くらいは自分一人の為に生きるのではなく、この村の私以外の幸せと安泰のために死ぬべきだと思いました」
刹那、右頬に痛みが走る。苦痛に顔を顰める私は彼に厳しい視線を送る。
「何するんですか、痛いですよ」
傷つけた本人からの謝罪はない。代わりに聞こえてきたのは、低く掠れた声だった。
「……死ぬべきって何だよ」
俯いていた顔が持ち上げられた。いつも落ち着いている瞳は暗く、怒りを宿している。再び君は私の知らない顔をした。この男が放つ圧に私はただただ圧倒されて、驚いて目を点にするしかできない。
「じゃあお前、村人全員から生きろって言われたら生きるのか?その後に手のひら返しで全員から死ねって言われたらハイハイ分かりましたって簡単に死ねるのか?」
「それは、」
「お前の死生観よく分かんねぇよ。コロコロコロコロ他人の意見で生きることに苦しんで、死ぬことに苦しんで。それで自分の生きる意味見失うとか馬鹿みたい」
「私は、ただ全うに生を終わらせたかっただけで」
嘘だ、私には見失うほどの自分すらもない。考えることに疲れてしまった私はどうすることもできないまま、朦朧とした視線を向ける。
「綺麗に生きること、それは立派だと思う」
君は言葉を区切る。意志の強い瞳は揺れることなく、私のハリボテの心を食い殺そうとした。その想いの強さは育ちすぎた理性の芽をいとも簡単に間引きする。
「でも綺麗に生きることが正しいとは限んないだろ。綺麗な花を咲かせるためにわざわざお前が死んでその土の肥料になる必要あるか?いずれまた肥料が足りなくなったらボタンみたいに殺される少女が出るかもしれないんだぞ」
私は口を噤む。言い返す言葉が見当たらなかった。私がここで逃げなかったところで死後、また同じように何代も犠牲になっていく少女たちがいる。何も行動を起こさないまま運命を受け入れる私はそんな未来を見殺しにしようとしている。しかし私一人の力でこの儀式が簡単になくなるほど、世間は甘くない。
冷たい声はお囃子の騒がしさの比にならないほど静かだ。しかし、それ以上に澄んでいて、騒がしい音にかき消されることなく生ぬるい夏の夜から頭一つ飛びぬけるように浮いていた。言葉一つ一つがまるで私の脳に直接語りかけるように注がれる。
「世界は結局その繰り返しだ。誰かが骨となって灰となって肥料になるから美しい花が咲く。花は犠牲の連鎖も知らずに綺麗に咲き続けるんだ。おいしいところだけ吸い取って、からからになるまで幸せを奪って。表面上の美しさを切り取ればそれはそれは見事なものかもしれない、でも搾取される側は悔しいだろ、腹立たしいだろ、やりきれないだろ」
言った自分が一番苦しそうな顔をしないでほしい。しかし私には小さな彼が助けを求めているように見えた。きっと君も幼いころから周りの大人に振り回されて虚仮にされてきたのだろう。でなければ、そんな言葉も、そんな表情も、齢20近い青年からは出てくるはずがないのだ。
暫くの静寂の後、喉を震わせたのは私だった。
「透くん、わたし……わたしはっ……」
口が麻痺してまごつく。心臓の鼓動が早まり、頸動脈から脈打つ振動が伝わる。早まる臓器のある場所に手を添えると衣装を揉みしだいた。感情に鈍くなっていたはずの君には苦しい、腹立たしい、やりきれないという感情があるらしい。それじゃあ私の心で燻るこの感情は一体なんという名前なんだろう。
言葉にすれば何かわかるだろうか。
「最期くらい、誰かに生きてほしいって願われたい」
震える声が君に届く声量をもっていたのかは分からない。けれど、不思議とどんなに小さな声でも君が私の願いを聞き逃すことはない自信があった。
「我儘かもしれないけれど、もう一つお願いしてもいい?」
「そのつもりでここに来た」
にやりと表情を変えた透くんには恐らく私が次何を言うかなんてお見通しなのだろう。なら初めから遺言を唆すようなことをしなければよかったのに。私にはまだ君が今何を考えているのか分からない。もしかしたら一か八かだったのかもしれない、君には私は生きても死んでもどちらでもよかったのかもしれない。
本当の相島透を知れば世間は言うだろう、なんて薄情な男なんだと。
けれど、世界でたった一人私が生を選ぶことに賭けてくれたのは紛れもないこの男だった。
私は頬に伸ばされていた手を両手で包む。興奮からか私の手は熱く、白くて綺麗な手はその熱でじんわりとあたためられていった。合図もないのにどちらがともなく力が込められた掌は、私が言葉を発する前に外に引かれる。
「私をここから連れ出して!」
体勢の崩れた私を広い肩が受け止める。見上げると、淡い月の逆光を受けながら君が表情を崩していた。いつものような不愛想な顔かと構えていたのでつい驚いてしまう。しかし、嫋やかなそれは貼り付けのものではないようだ。
「おいで、ボタン」
あまりの美しさに一瞬目が眩んだがたまにはこんな君も悪くない。
知りたかった感情の名前はきっとこれから先、君が教えてくれるだろう。
「行くぞ」
「はい!」
よろめきながら慣れない山道を進む。靴なんかはなくて裸足のままなので、足の裏に石が刺さって血が流れた。着飾るもの全てが邪魔で歩いていく中で、装飾品は捨てていく。気づけば下着とその上に着ていた薄い衣一枚になっていた。成人男性の進むスピードは予想以上に速い。手を繋がれていてもまるで犬の散歩だった。勿論引きずられているのは私だ。
「透くん少し早いです」
「仕方ない、我慢しろ」
「あのそうじゃなくて、」
上手く回らない舌をどうにか動かす。飲んだのは一口だけにしろ、毒は毒のようだ。神経が徐々に蝕まれていく感覚がする。右手の痛覚はとっくにない。足が重くて、回転数が君と合わなかった。言いにくいがこれは仕方がない。できるだけ申し訳なさそうに告げる。
「毒を摂取したせいで体がうまく動かないんですけど」
えへへと誤魔化すと、君は血相を変えて踵を返した。
「馬鹿か、そういうことは早く言え」
いや何度も言おうとしたんですけど、という言葉の前に私の前で跪かれる広い背中。別におぶらなくても、歩くスピードを緩めるだけでよかったのに。しかし、私は言った手前断ることができず、素直に身を委ねることにした。君は私を気遣ってなるべく揺らさないように歩いた。でも私の手を引いて歩くより幾分早い。
私は彼の顔が正面を向いていることを確認して、顔を歪ませた。滲む脂汗を拭う。
正直腹の中にある爆弾を舐めていた。毒もそうだが、500グラム近い鉄の塊は想像以上に体に負担を掛ける。幸い内臓が傷つかないような特殊な加工をしているみたいだが、それでも走ることは想定していないため鈍痛が走る。
ただ小屋を出ただけでは起動しない時限爆弾にそっと手を当てた。
私に残された時間はあと72時間だ。時限爆弾は三日間は作動しないことになっている。神主はなんで72時間なんて中途半端な猶予を与えたのだろう。どうせ殺すならひと思いに殺してしまったほうがいいのに。閉じ込めておけばいいのに。
三日は全力で捜索するという宣戦布告なのだろうか、三日あれば確実に私を捕らえて贄にできる自信があるのだろうか。
ならばこちらも対抗するしかない。
あちらが三日で私を殺そうとするなら、私は三日で幸せを見つけてやる。
暫く山を彷徨っていると、洞穴のような薄暗い場所を見つけた。彼と私の意見は一致してここなら安全だと穴の突き当りまで進むと、ようやく体を下ろしてもらえた。
「どうしたその傷」
開口一番に君はそう言った。人差し指が指すのは私の頬だった。私は小首を傾げながら右頬に触れると、指先に血が付着した。きっと逃げる際、枝か何かが引っ掻いたのだろう。
「大丈夫ですよ、このくらいの傷。それより透くんの方は大丈夫なんですか」
「ああ、結構やばいな。明日のスケジュールも二十二時まで埋まってたのに。マネージャーに申し訳ないな。ボタンもちょっと……と言わず結構責任取ってほしいくらいだ」
微塵も気を遣わずに言ってのける君。普通そういうのって大丈夫だよっていうところじゃないのか。しかし、お互い疲れてしまって何も言う気になれない。石壁に持たれかかると、疲れがどっと押し寄せてきた。よく見れば頬だけじゃなくて、腕も足も全身傷だらけだった。着物も所々破けてしまっている。
「捨て犬みたいだな」
全身を気にする私に君はぼそりと呟いた。私は素早い動きで君と距離を取ると、服の襟に鼻を押し付ける。
「えっ……そんなに臭いますか私」
「そうじゃなくて」
何か言おうとした口が突然動きを辞める。面倒だったのか、その後は言及することなく黙ってこちらに来た。獣臭がするわけではなさそうだ。
私はきゅーんと鳴き真似をするわけもなく、そのまま丸くなって寝た。君は寝れないのか、私の隣で小さくなった入り口を見つめた。その瞳は僅かに見える町を捉えていた。君も色々考えることがあるだろう。大体どうするのだ、こんな少女を誘拐して。仕事に大なり小なり支障をきたすんじゃないか。それでも君の澄んだ瞳は憂いを帯びることなく遠くを見つめるものだから、私も難しいことを考えるのはもう辞めようと思った。
触れた肌は驚くほどに温かい。敷布団も毛布も何もなかった。寝苦しい夜に欠かせない扇風機もここにはない。それでも空気は小屋にいたときの何倍も美味しい。
微睡み意識を手放す瞬間、何かが私の頬に触れた。かさぶたになった傷を撫でるその手は優しかった。
それにしてもここまで着飾る意味はあるのだろうか。
朝から湯あみをさせられ、髪を複雑に結われて、上等な絹を何枚も重ねられた。十二単ほどではないが布の厚みの代わりにネックレス、ピアス、簪などの装飾品がこれでもかというほど盛られている。おかげで私は最期の晩餐もろくに味わえなかっのだ。食の恨みは一生というが、私から鰻丼を取り上げた罪は近海の海溝よりも深い。一口しか口につけなかった鰻丼とすまし汁を回収していった巫女には私の死後、毎回鰻丼に致死量の山椒が振りかけられる呪いをかけておこうと決意した。
ため息を吐きながらほの暗い部屋の唯一の光源である外に流し目を送る。いつものもの寂しい石畳とは打って変わって沢山の屋台が並び、境内には赤い提灯がぶら下げられている。どこからか笛と小堤の音が聞こえてきて真夏の訪れを実感する。今年もこの季節がやってきた。今日は私が生まれてから17回目の奉納祭だった。
「お嬢様、お支度は整いましたか」
しばしの間、ぼうっと外を眺めていると、巫女がドア越しに尋ねてくる。慌てて姿勢を正した私が返事をすると、数センチ開いた扉から手が伸びてきて盃が床に置かれた。
「覚悟が決まったからこれを飲んでください」
「これは何ですか」
聞いてから自分のしたことが無粋だと気が付いた。彼女もそれを示唆するように無言を貫く。
「亥の刻までに飲まなければ辛い目に遭います故、それまでには必ずお飲みください」
それでは、と静かに告げると人の気配はなくなった。私は口を真一文字に結びながら取り残された盃を見つめる。紫の液体は提灯の明かりを反射して怪しげに光っている。恐らくこれは葡萄酒だろう。液体に鼻を近づけ、香りを嗅ぐときつい蒸留酒と甘ったるい葡萄の匂いがした。きっとこの中には睡眠薬と遅効性の毒が入っているのだろう。まず睡眠薬で眠って、意識のないまま神に捧げられ私の体は解体される。万が一致死量を超えた睡眠薬で死ねなくとも、毒が全身に回れば確実に心臓は止まる。実に便利な飲み物だ。
「巫女が言ってた辛い目っていうのは、多分意識のあるまま殺されるってことだろうなぁ」
貼り付けにされたまま体をばらばらにされる想像をした。うん、それだけは避けたいな。私は盃に手を伸ばすと、人差し指だけ浸す。赤紫の液体のついた指をぺろりと舐めた。この程度では多分死ねない。舌に山椒を食んだときのような痛みが走ったが、私の意識はまだ保たれたままだった。
視線はゆっくりと傾き、いつの間にか私は布団も敷いていない床に仰向けに転がる。
祭り囃子の音が近づいたり遠ざかったりしてよく聞こえなかった。子供がはしゃぐ声も、段々と膜が張られたようにぼやけていく。年に一度だけ風に乗って流れてくるこの匂い、好きだったなぁ。質素な食事しか口にしてこなかった私にとってこの中濃ソースの香はたこ焼きか、お好み焼きか、たませんか想像を掻き立てるには十分だった。
「りんご飴、綿あめ、金魚すくい……」
屋台ののれんを眺めては口に出す。食べたこともない、体験したこともないそれに想いを馳せながら死ぬのもまた一興だろうか。
目を細めて遠くを見つめる。十にも満たない兄弟が仲良く手を繋ぎながら歩いていた。彼らは金魚すくいの店の前で足を止めると、二人で緑の虫眼鏡みたいなのを使ってすばしっこく泳ぐものを捕まえようとする。兄の方は3つ捕まえて袋を手に下げたが、妹の方は一匹も得られなかったようで空っぽの両手をじっと見つめた後その場で泣き出してしまう。
「あちゃー……」
あれは中々機嫌を取るのが難しい。これから彼らはどうするのか気になってしまった私は引き続きその様子を眺める。
兄は慌てて少女の涙を拭ってから、ぎゅっと小さな体を包み込んだ。そして手に下げた袋を妹に持たせてやる。妹はまだ止まらない涙を忘れて嬉しそうに笑ってそのきらきらした瞳で袋の中をずっと観察していた。
私は思わず綻ぶ。この子たちの幸せを守るために、死ねるならいいか。この世には酒に溺れて死にゆくものや、職場でいじめを受けて身を投げるものもいると聞く。それに比べればまだ私は綺麗に散れる方か。
「さぁ、そろそろ飲まなきゃ」
体を起こして盃を取りに行く。正座をして、襟を整えた。無駄な足掻きかもしれないが、散り際くらい綺麗でいたいのは女としての意地だった。
痛いだろうか、苦しいだろうか。そんなことも感じる間もないまま意識を失うのだろうか。
目を閉じて食器の淵に唇をつける。瞼を固く閉じると、覚悟が今だ定まらない震える手を緩やかに傾ける。
その時だった。
「今日はいつもと服が違うんだな」
どこからか声がする。小さくしていた背中をぴんと伸ばして振り返ると見慣れた顔がそこにはあった。
どうしてここにいるんだろう、昨日でおしまいのはずではなかったのか。
「透くん?」
濡れた唇を舐めながら君の名前を呼ぶ。あまりの衝撃に手の力は抜けて、漆塗りの高級食器は酒を盛大にぶちまけながら砕け散った。
高そうな布は瞬く間に紫色に染まった。嗚呼これは染み抜きしても取れなさそうだ、なんてこの期に及んで冷静な頭はきっと情報過多でショートしていたのだと思う。
「何してたんだ、今日の主人公さん」
神に捧げる少女のことを知ってる癖にこの男はいつもと変わらない不愛想なトーンだった。目の前に数時間後には死ぬ人がいても彼はこんな感じらしい。実に冷淡というか、淡白というか、そういう言葉が似あう人だ。
「たった今死ぬところだったのですが……」
痺れる唇でそう答えると、彼はぎょっとしたように目を見開く。
「それは邪魔した」
彼は珍しく申し訳なさそうな顔をする。私は気にしていないと顔を横に振った。
「それにしてもここで自死なんだな。もっと神殿とかでやると思ってたけど」
「私もびっくりしました」
私は彼から割れた盃に視線を戻した。どうしよう、このままでは生きたまま殺されるのかな。しかし、液体の大半はすでに畳と衣装に染み込んでしまった。絞れば多少はあるかもしれないが、何年前の衣装か分からないものに一度染み込んだものを口にするのは気が引けた。それでも背に腹は代えられないかと仕方なく盃の一番大きな欠片に着物を絞っていると、君のラムネのびいとろみたいに澄んだ声が鼓膜を揺らした。
「最期になんか言っておきたいことはないの?」
「えっ……」
「ほらここにいるのは俺だけだし、吐き出したいことあればここで言っちゃえば?後悔したまま逝くのは嫌だろ」
そう言われると何か遺言を残すのも悪くない。手を止めてうーんと唸ってみるが、特に考えは思いつかなかった。それも自分が空っぽだからだろうか、何も考えずに何も疑わずに生きてきたからこんなにも死に対して思うものがないのかもしれない。
困ってしまって眉を顰めて彼の顔を見ると、一つ案が思い浮かんだ。私はゆるりと口角を上げた。
「では、名前を呼んでください」
君は驚いた顔をしていた。私が言った言葉の意味が分からないようで鸚鵡のように同じ言葉をなぞる。
そんなに難しいことだろうか。彼がいつもやってる『どらま』とやらに比べた簡単だと思うのだが。私はもう一度ゆっくりと区切りながら言う。
「私の名前を、呼んでください」
「……それでいいのか」
「はい」
「……無欲なやつめ」
呆れただろうか、死に際でもこんなことしか願えない少女だと。でも、私だって最期くらい名前を呼ばれてみたかったのだ。世の親が子供に贈る一番最初の贈り物を、私だって受け取ってみたかったのだ。君は私に名前を付けた割に自ら進んでそれを口にしようとはしない。一度くらい呼んでくれてもいいのにと毎回少し落ち込んでいたのは墓場まで持っていこう。
彼と視線が絡まる。ソースの匂いに混ざって、五月の新緑のような匂いがした。君が私の頬を指でなぞっていたのだ。窓から君が手を伸ばして私に触れたのは、それが初めてだった。
「ボタン」
名前を呼んだ瞬間に震えた瞳。その瞬間君がふっと表情を崩した。私はそれに違和感を覚えた。出会った時の笑顔はもっと口角が上がっていて、上がった口角は毎回同じ角度で揃っていて、完璧すぎるほどに完璧であった。今の君の笑い方は不器用で、口角は上がりきることなく照れを隠すためにはにかまれている。涼しげな目じりは何故か悲しみを滲ませていた。
「……どうした?」
「へ……」
彼は首を傾げながら親指で頬骨の辺りを擦ってくる。私は君がふざけているのかと思ってその手を静止させようとしたが、どうやら冗談ではないらしい。悲しげだった目じりは、まるで痛々しくて見ていられないとばかりに歪んだ。
私はそっと彼の右手に自分の手を重ねる。そこには雨漏りのように透明な雫が零れ続けていた。
「なん……っで」
反射的にごしごしと涙を拭った。おかしいな、なんで泣いてるんだろう。特に悲しいとも苦しいとも感じていないのに。平気だと笑う顔とは不釣り合いなくらいに涙は止まることを知らなかった。彼は右手は添えたまま、茫然と目の前を見つめていた。見苦しい姿を見せてしまって申し訳ない。
しかし、「失礼しました」という言葉の代わりに口から零れたのは自分でも全く想像できないものだった。
「なんで私には当たり前がないのかなぁ」
呟いた自分も、呟かれた君も、動揺したように肩を震わす。体をじんわりと侵食するのは冷たい感情だった。駄目だと理性がブレーキを掛けようとする。これはもう小さい頃に殺したものだろう、神に捧げる少女の覚悟を持ったときにもう二度と思い出さないように何度もナイフで刺して殺した感情だろう。
「駄目……」
ぎゅっと閉じた目に力を籠める。鼻を啜って頭を振りながら、必死に元の自分に戻ろうとした。今の私は少しおかしくなっている。早く何でもないですって笑わなきゃ。荒くなる息を止めて表情筋に力を入れると、意志とは反対に口はへの字に曲がっていく。
「言って」
優しい声だった。あたたかくて、ずっと聞いていたいくらい柔らかくて優しい声だった。ゆっくり固く閉じていた目を開くとぼやける世界で、声の主が蕩けそうなくらい優しい表情をしていた。私は人間の、こんな顔を見たことはない。
私の心の声はなんだ。
私が言いたかったことはなんだ。
私の体の奥でずっと燻っていた感情はなんだ。
空っぽなはずの君が私の固まっていたものをいとも簡単に解して、解放する。
鳥籠の鍵を探してあげるのではなく、籠ごと溶かしてくれる。
私はその感覚が不思議で堪らなかった。
「本当だったら、普通の親に育てられて、普通に小学校行って、普通に友達ができて、普通に誰かを好きになって、普通の17歳の誕生日を迎えてるはずだったんです。大切な人に囲まれて、『おめでとう』『生まれてきてくれてありがとう』って祝ってもらって、『こちらこそ生んでくれてありがとう』って笑顔で返したかったんです」
ぽつりぽつりとそれこそあばら屋の雨漏りのように、私は気づけば言葉を君にぶつけていた。
卑しい少女の、くだらない幼少期の話、彼にとっては時間の無駄だろう。
しかし私の考えを否定するように彼は黙って聞いていた。相槌もなければ、何かいうこともないけれど、君が聞いてくれていることがうれしかった。
「私の親は私を育てきれずに、物心つく前に私を神社の前に捨てました。その年の夏は本当に暑くて、神社の隣で育てているスイカが全滅してしまうほどだったみたいです。少しでも発見が遅れていたら死んでいただろうと、だから私たちに感謝しなさいと、毎年おめでとうの代わりに言われてきました」
私の誕生日はおめでたい日ではなく、呪いの始まりだった。
「私はそれから誕生日の日は決まって死にたくなりました」
睫毛を伏せた後、笑いが込み上げてきた。自分自身と親に対しての嘲笑だった。
「この神社に私を捨てるなんてそんなの一択じゃないですか、要らないから捨てよう。でもどうせなら神に捧げる子にして、村の安泰の糧になればいいかって魂胆が丸見えじゃないですか、自分の親ながら笑ってしまいますよね。私は物と同じなんですよ、要らなければ捨てる。物は感情を持たないから誰かの為になるなら喜んで寄贈する」
あまりに滑稽な親子だ。神社に捨てた母親も、捨て子という運命を受け入れて自分を殺してまで『神に捧げる少女』を振舞ってきた娘も。
「もし、私が捨てられたのが神社じゃなければ私は死んでいました」
目の前の俳優は何とも言えない顔をしていた。きっと「それは災難だったね」と微笑みながら慰めることもできたし、「どうせ死ぬんだからぐちぐち考えるな」と冷たい表情で切り捨てることも、この場において役者である彼にしてみれば容易いものだっただろう。
しかし、君は何も言わなかった。
予想以上に話に聞き入っているらしい、表情管理を忘れたようにただ私の口から紡がれる言葉を静かに待っていた。
「でも、もし私が捨てられたのがここでなければ。……私は17年間も生きることに苦しまなかった。苦しみを知る前に死ぬことができた」
そうか、私はずっと苦しかったのか。
固まっていた心の欠片がほぐれていく。とっくに忘れてしまったと思っていた感情は、見て見ぬふりをしていただけでずっと心では渦巻いていたようだ。
でも、と心の中で理性が首を振る。
それに気づいたから何だというのだ、気づいたところで痛む心は数時間後にはもうこの世にないのに。
私は諦めのついた顔で微笑んだ。
「けれど、今日まで生きてしまったから。生きたいと思ってしまったから。今日くらいは自分一人の為に生きるのではなく、この村の私以外の幸せと安泰のために死ぬべきだと思いました」
刹那、右頬に痛みが走る。苦痛に顔を顰める私は彼に厳しい視線を送る。
「何するんですか、痛いですよ」
傷つけた本人からの謝罪はない。代わりに聞こえてきたのは、低く掠れた声だった。
「……死ぬべきって何だよ」
俯いていた顔が持ち上げられた。いつも落ち着いている瞳は暗く、怒りを宿している。再び君は私の知らない顔をした。この男が放つ圧に私はただただ圧倒されて、驚いて目を点にするしかできない。
「じゃあお前、村人全員から生きろって言われたら生きるのか?その後に手のひら返しで全員から死ねって言われたらハイハイ分かりましたって簡単に死ねるのか?」
「それは、」
「お前の死生観よく分かんねぇよ。コロコロコロコロ他人の意見で生きることに苦しんで、死ぬことに苦しんで。それで自分の生きる意味見失うとか馬鹿みたい」
「私は、ただ全うに生を終わらせたかっただけで」
嘘だ、私には見失うほどの自分すらもない。考えることに疲れてしまった私はどうすることもできないまま、朦朧とした視線を向ける。
「綺麗に生きること、それは立派だと思う」
君は言葉を区切る。意志の強い瞳は揺れることなく、私のハリボテの心を食い殺そうとした。その想いの強さは育ちすぎた理性の芽をいとも簡単に間引きする。
「でも綺麗に生きることが正しいとは限んないだろ。綺麗な花を咲かせるためにわざわざお前が死んでその土の肥料になる必要あるか?いずれまた肥料が足りなくなったらボタンみたいに殺される少女が出るかもしれないんだぞ」
私は口を噤む。言い返す言葉が見当たらなかった。私がここで逃げなかったところで死後、また同じように何代も犠牲になっていく少女たちがいる。何も行動を起こさないまま運命を受け入れる私はそんな未来を見殺しにしようとしている。しかし私一人の力でこの儀式が簡単になくなるほど、世間は甘くない。
冷たい声はお囃子の騒がしさの比にならないほど静かだ。しかし、それ以上に澄んでいて、騒がしい音にかき消されることなく生ぬるい夏の夜から頭一つ飛びぬけるように浮いていた。言葉一つ一つがまるで私の脳に直接語りかけるように注がれる。
「世界は結局その繰り返しだ。誰かが骨となって灰となって肥料になるから美しい花が咲く。花は犠牲の連鎖も知らずに綺麗に咲き続けるんだ。おいしいところだけ吸い取って、からからになるまで幸せを奪って。表面上の美しさを切り取ればそれはそれは見事なものかもしれない、でも搾取される側は悔しいだろ、腹立たしいだろ、やりきれないだろ」
言った自分が一番苦しそうな顔をしないでほしい。しかし私には小さな彼が助けを求めているように見えた。きっと君も幼いころから周りの大人に振り回されて虚仮にされてきたのだろう。でなければ、そんな言葉も、そんな表情も、齢20近い青年からは出てくるはずがないのだ。
暫くの静寂の後、喉を震わせたのは私だった。
「透くん、わたし……わたしはっ……」
口が麻痺してまごつく。心臓の鼓動が早まり、頸動脈から脈打つ振動が伝わる。早まる臓器のある場所に手を添えると衣装を揉みしだいた。感情に鈍くなっていたはずの君には苦しい、腹立たしい、やりきれないという感情があるらしい。それじゃあ私の心で燻るこの感情は一体なんという名前なんだろう。
言葉にすれば何かわかるだろうか。
「最期くらい、誰かに生きてほしいって願われたい」
震える声が君に届く声量をもっていたのかは分からない。けれど、不思議とどんなに小さな声でも君が私の願いを聞き逃すことはない自信があった。
「我儘かもしれないけれど、もう一つお願いしてもいい?」
「そのつもりでここに来た」
にやりと表情を変えた透くんには恐らく私が次何を言うかなんてお見通しなのだろう。なら初めから遺言を唆すようなことをしなければよかったのに。私にはまだ君が今何を考えているのか分からない。もしかしたら一か八かだったのかもしれない、君には私は生きても死んでもどちらでもよかったのかもしれない。
本当の相島透を知れば世間は言うだろう、なんて薄情な男なんだと。
けれど、世界でたった一人私が生を選ぶことに賭けてくれたのは紛れもないこの男だった。
私は頬に伸ばされていた手を両手で包む。興奮からか私の手は熱く、白くて綺麗な手はその熱でじんわりとあたためられていった。合図もないのにどちらがともなく力が込められた掌は、私が言葉を発する前に外に引かれる。
「私をここから連れ出して!」
体勢の崩れた私を広い肩が受け止める。見上げると、淡い月の逆光を受けながら君が表情を崩していた。いつものような不愛想な顔かと構えていたのでつい驚いてしまう。しかし、嫋やかなそれは貼り付けのものではないようだ。
「おいで、ボタン」
あまりの美しさに一瞬目が眩んだがたまにはこんな君も悪くない。
知りたかった感情の名前はきっとこれから先、君が教えてくれるだろう。
「行くぞ」
「はい!」
よろめきながら慣れない山道を進む。靴なんかはなくて裸足のままなので、足の裏に石が刺さって血が流れた。着飾るもの全てが邪魔で歩いていく中で、装飾品は捨てていく。気づけば下着とその上に着ていた薄い衣一枚になっていた。成人男性の進むスピードは予想以上に速い。手を繋がれていてもまるで犬の散歩だった。勿論引きずられているのは私だ。
「透くん少し早いです」
「仕方ない、我慢しろ」
「あのそうじゃなくて、」
上手く回らない舌をどうにか動かす。飲んだのは一口だけにしろ、毒は毒のようだ。神経が徐々に蝕まれていく感覚がする。右手の痛覚はとっくにない。足が重くて、回転数が君と合わなかった。言いにくいがこれは仕方がない。できるだけ申し訳なさそうに告げる。
「毒を摂取したせいで体がうまく動かないんですけど」
えへへと誤魔化すと、君は血相を変えて踵を返した。
「馬鹿か、そういうことは早く言え」
いや何度も言おうとしたんですけど、という言葉の前に私の前で跪かれる広い背中。別におぶらなくても、歩くスピードを緩めるだけでよかったのに。しかし、私は言った手前断ることができず、素直に身を委ねることにした。君は私を気遣ってなるべく揺らさないように歩いた。でも私の手を引いて歩くより幾分早い。
私は彼の顔が正面を向いていることを確認して、顔を歪ませた。滲む脂汗を拭う。
正直腹の中にある爆弾を舐めていた。毒もそうだが、500グラム近い鉄の塊は想像以上に体に負担を掛ける。幸い内臓が傷つかないような特殊な加工をしているみたいだが、それでも走ることは想定していないため鈍痛が走る。
ただ小屋を出ただけでは起動しない時限爆弾にそっと手を当てた。
私に残された時間はあと72時間だ。時限爆弾は三日間は作動しないことになっている。神主はなんで72時間なんて中途半端な猶予を与えたのだろう。どうせ殺すならひと思いに殺してしまったほうがいいのに。閉じ込めておけばいいのに。
三日は全力で捜索するという宣戦布告なのだろうか、三日あれば確実に私を捕らえて贄にできる自信があるのだろうか。
ならばこちらも対抗するしかない。
あちらが三日で私を殺そうとするなら、私は三日で幸せを見つけてやる。
暫く山を彷徨っていると、洞穴のような薄暗い場所を見つけた。彼と私の意見は一致してここなら安全だと穴の突き当りまで進むと、ようやく体を下ろしてもらえた。
「どうしたその傷」
開口一番に君はそう言った。人差し指が指すのは私の頬だった。私は小首を傾げながら右頬に触れると、指先に血が付着した。きっと逃げる際、枝か何かが引っ掻いたのだろう。
「大丈夫ですよ、このくらいの傷。それより透くんの方は大丈夫なんですか」
「ああ、結構やばいな。明日のスケジュールも二十二時まで埋まってたのに。マネージャーに申し訳ないな。ボタンもちょっと……と言わず結構責任取ってほしいくらいだ」
微塵も気を遣わずに言ってのける君。普通そういうのって大丈夫だよっていうところじゃないのか。しかし、お互い疲れてしまって何も言う気になれない。石壁に持たれかかると、疲れがどっと押し寄せてきた。よく見れば頬だけじゃなくて、腕も足も全身傷だらけだった。着物も所々破けてしまっている。
「捨て犬みたいだな」
全身を気にする私に君はぼそりと呟いた。私は素早い動きで君と距離を取ると、服の襟に鼻を押し付ける。
「えっ……そんなに臭いますか私」
「そうじゃなくて」
何か言おうとした口が突然動きを辞める。面倒だったのか、その後は言及することなく黙ってこちらに来た。獣臭がするわけではなさそうだ。
私はきゅーんと鳴き真似をするわけもなく、そのまま丸くなって寝た。君は寝れないのか、私の隣で小さくなった入り口を見つめた。その瞳は僅かに見える町を捉えていた。君も色々考えることがあるだろう。大体どうするのだ、こんな少女を誘拐して。仕事に大なり小なり支障をきたすんじゃないか。それでも君の澄んだ瞳は憂いを帯びることなく遠くを見つめるものだから、私も難しいことを考えるのはもう辞めようと思った。
触れた肌は驚くほどに温かい。敷布団も毛布も何もなかった。寝苦しい夜に欠かせない扇風機もここにはない。それでも空気は小屋にいたときの何倍も美味しい。
微睡み意識を手放す瞬間、何かが私の頬に触れた。かさぶたになった傷を撫でるその手は優しかった。