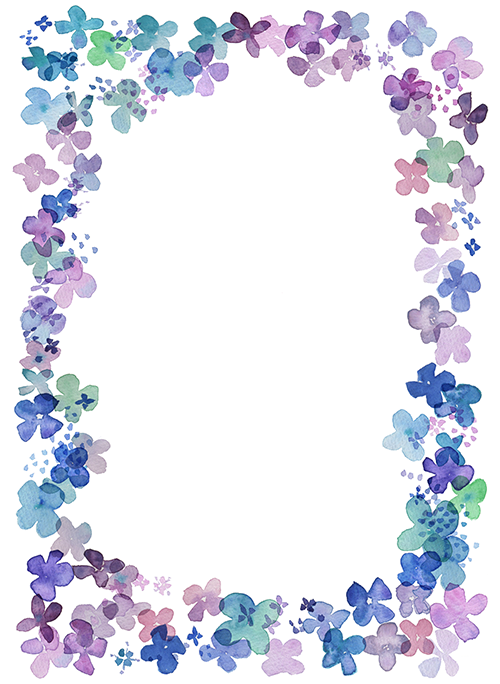「はぁ、本当に来るんですかね」
真っ白な和紙を見てため息を吐いた。もうすぐ夜が更けようとしている時刻、私は奉納祭の書類に追われていた。もう何十枚目かも分からない書類に墨を滲ませていく。幾ら文字を書いたって、頭の中は昨日の男のことばかりだった。軽薄そうな笑みを果たして信じてもいいのか、期待に胸を膨らませる感情が体を充満させる。しかし、期待しすぎていざ来なかったときの落胆を想像すると手放しでわくわくは出来なかった。
相島透はまだ来ない。
その間に私の手首は限界を迎えていた。文字を書きすぎて腱鞘炎になってしまったようだ。痙攣する右手を抑え込む。今日はもう寝てしまおうか。どうせあんなの言葉の綾だったのだ、私は単なるお遊びに過ぎない。芸能人さんの戯れの相手に過ぎなかったのだ。
ただ、知りたかっただけなのに。
どうして、あんな表情をしていたのか。
君はどうして自分を偽って生きているのか。
ぼうっと考えを巡らせていると、いつの間にか和紙の上には黒い染みが出来ていた。いけない、書き損じたそれを丸めてちり箱に投げ捨てる。
その時、夏嵐が障子の木枠を激しく揺らした。
「よぉ」
私はその声で一瞬誰だか気づくことができなかった。顔を見て、ああ約束をしていた人だとようやく分かった。約束通り訪れたことに喜びを感じながら、私は違和感を抱く。それにしても昨日の媚びるような態度はどうしたのか、一変して年相応の男のように振る舞う彼を見て私は目を丸くした。いや、彼の年齢は知らないが一般的な男性と比較して随分不愛想である。没落貴族という言葉がぴったりだと思った。
昨日と同じような気楽な服を着こなしている彼は、今日も障子を開け放つ。それから今度は座布団を持ってきたらしく枯葉の上に自前の座布団を敷いてそこに腰掛けた。居心地を良くしてどうする。
そんな専横な態度をされると自分だけきっちりしているのが馬鹿らしくなって、私も正座で折りたたんでいた足を崩した。
「なんか昨日より態度悪くないですか?」
「お前も昨日より随分本音を言うようになったな」
「おま……お前って……初めて言われましたよ」
「お前はお前だろ。だって俺名前知らないし」
「だって私名前ないですもん」
君の顎が外れそうになる。驚愕の表情で瞳孔が開かれたまま一点を見つめ続けるものだから死人のように見えた。一応目の前で手を振って意識を確認するが、うざかったのか振り払われる。
「名前、ないのか」
「はい」
「だって、年は17だろ?17年間どうやって過ごしてきたんだよ」
「お嬢様とかお姫様とか神に捧げる少女って呼ばれてきました」
「親の苗字とかは?」
「私は孤児ですので、物心つく頃にはここにいました」
平然と言う私に君は理解が追い付かないとばかりに瞬きを繰り返す。私はどんな顔をしていいのか分からなくて苦笑いを浮かべた。こういうとき普通は躊躇ったり、悲しそうな顔をしたりするのだろうか。けれど親がいないのも、名前がないのも、当たり前として生きてきた私にとっては逆に名前があることや親がいることの方が不思議に思えてしまう。名前がなくともお嬢様と呼べば私だと分かるし、身の回りのことは愛情がなくとも巫女が全てやってくれた。不自由はない。なのに皆、私が一言その言葉を告げると腫物を見るかのような視線を向けてくる。
その度に私はどうやって反応していいのか分からなくなるのだ。
私は可哀そうな子なのか。私の存在は変なのか。
認めてしまえば、何かが崩壊する。そんな予感がして、ただ曖昧な顔しかできないままでいる。
「あ、袖のとこ、取れかかってますよ」
ふと君の袖で蓑虫のように揺れる何かをみつけた。金色に揺れるそれを手に取ると、立派な細工が施された釦だった。流石芸能人ということもあり、服の装飾一つにしても高価である。君は現実に引き戻されたように袖口と私の方に視線を向ける。話題を転換させるのにも丁度よかった。私は部屋の奥から刺繍用の針と糸を取りに行こうと立ち上がると、君が俯かせてた顔を上げた。
「じゃあボタンで」
「へ?」
「名前、お前の。ボタンに決めた」
君は私の額に人差し指を突き立てると、「ボタン」と何度も口ずさんで少し顔を綻ばせた。自然に表情筋が上がる様に、私は初めて彼の本当の笑顔を知れた気がする。控えめだが、繕った笑い以外の笑い方もできるんだと彼の数少ない人らしい部分に少し安堵した。
私も真似して声でなぞる。何度も言っていくうちに、二人の声が重なった。微かに不協和音を避けた声で紡がれる3文字の名前は、ゆっくりと私の細胞全てに落とし込められる。
適当すぎやしないだろうか。しかしこの瞬間に17年間何もなかった私という存在に名前がついた。しかも出会って二日の男の釦が取れかかっていたという理由で。
ボタン
実に適当で、安直な名前である。しかし、私如きに名前をつけられるのならその程度でいいような気がした。
私はこの状況が何だかおかしくて、耐えきれず小さく噴き出した後、誤魔化すように咳ばらいを一回。射貫くような眼光をひんやりした瞳に向けてやる。
「勝手に決めるんですね」
「ああ、不便だからな。あと名前くらいはあってもいいだろ」
「一応お礼を言っておきます」
「一応ってなんだ、一応って」
つんけんした態度を取っているが、名前を付けられたことは悪くない。しかし正直に感謝の言葉を述べられないのは、会話の主導権を全て相手に握られていたからだ。子供じみた理由だが、そこは数多の客を手玉に取ってきた神に捧げる少女としての矜持が許さなかった。そんな私を察してか彼は不躾な態度に対して何も言及してこない。大人な対応に仕掛けた私はますます居心地が悪くなって、黙りこくる。
ここまでくると私の態度も随分砕けたものになっていた。染みついた言葉遣いは丁寧なままだが、自分だけ笑顔を取り繕うのも疲れるので表情筋を弛緩させた。
不意に神社の方から重たいものがぶつかる音がして目の前の男から視線を外す。斜め下の石畳には村の男たちが集まって、木製の骨組みが組み立てられていた。明日の祭りに備えて屋台を夜のうちに設置するようだ。今週の天気は概ね晴れらしく、提灯が雨天に気兼ねなく装飾されている。赤い和紙は淡い光に透かされていて、怪しく境内を染めていた。
私は特に表情も変えずに呟く。
「祭りの準備が進んでますねぇ」
「呑気だな、生贄のくせに」
「こういうのってもっと怯えた方がいいんですかね」
「そうじゃなくて」
君は私の問いを否定すると、神社の方に向けられていた顔を再びこちらに戻す。その顔には「昨日俺のことを分からないって言ったけど、お前も大概だぞ」という感情が滲んでいた。
「怖くないの?」
「透くんが私の質問に一つ答えてくれたら、私も一つ答えます」
「……お前、思っていた以上に強欲なんだな」
「失礼な、したたかと言ってください」
私が臍を曲げて顔を背けると、彼は面倒そうにため息を吐く。
「んで、質問って言うのは?」
「透くんはどうしてあのようなキャラを作っているのですか」
彼は思い出したように眉を上げた。それが目的でここにいるのではないか、と思った。けれど、忘れているなら君の目的はもしかしたら別なのかもしれないなと考えて口には出さなかった。
「あぁ、そういえば昨日教えるって言ったね」
「忘れないでくださいよ、その答えを知るまでは私も死に切れませんから」
目の前の男はふっと温度のない瞳を更に絶対零度まで下げる。怒りが込められているわけでも、憎しみが込められているわけでもない。それなのに冷たいと思わせるのは、透き通るそれが放つ光が一切ないからだろう。君の目から急に人らしい温度がなくなると無機物のように見えた。それこそ、びいどろだった。澄んでいて美しいのに、あたたかみはない。それが二つ埋め込まれた顔は美しさと同時に危うさを持ち合わせていた。
これ以上何かが欠けてしまえば、その場で消えてしまいそうな儚い危うさだった。
「空っぽだからだよ」
すり硝子の声が耳をなぞって私は鳥肌が立った。無意識のうちに細く白い首に手を伸ばし、手の甲を押し付ける。私の肌よりほんのりあたたかい皮膚は血管の震えをそのまま伝える。人離れした美しい声は触れた首筋の振動が無ければ、精巧に作られた傀儡だと疑ってしまいそうだなと思った。
「俺は感情の起伏が著しく薄い」
「どうして、」
「周りの環境が特殊だったからだと俺は思ってる。俺は幼い頃からこういう職業をしてたからさ、お前ほどではないけど普通の人生とはかけ離れた世界で生きてきた。その過程で、まぁ何と言うか色々あった訳」
虚ろという言葉をそのまま擬人化した人間に一歩を踏み入れるのは流石の私でも恐怖があった。それでも喉のすぐそこまでせり上がってきてしまうのが、強い好奇心の悪いところだ。後先考えずに口にするのは軽率であるし、何より寿命を縮める。それでもいいから知りたいと思ってしまうのが私だった。ゆっくりと足音を立てないように、気配を殺すように、獲物に近づく猫みたいに、私は慎重に言葉を紡ぐ。
「その、『まぁ何と言うか色々』が知りたいと言ったら、怒りますか?」
「さっきも言ったように俺は怒るも何も、全部どうでもいいと思ってる。でもお前には聞かせたくない」
「……それは何故」
「壊れちゃうから」
私と同じだと思った。君の壊れるが何かは分からない。どの程度なのかも知らない。もしかしたら同じだと比喩するには大袈裟すぎるかもしれないし、同じだと言うには私が身の程を弁えた方がいいほどの大事なのかもしれない。けれど私が私自身の運命を疑った瞬間に世界が壊れるのと同じように、そこが一つ君の踏み越えてはならない境界線のような気がする。欲張って知ろうと踏み込めば最後、君の瞳の真っ暗な部分の深淵から抜け出せなくなる。壊れると言うのは、僅かに残った理性や感情が全てなくなってしまうということを指しているのかもしれない。
君は全身の筋肉の緊張を解いて仰向けに寝転ぶ。そんなところで寝たら汚いはずなのに、妙に自然に溶け込むそれに私は悪寒がした。
「空虚な人間はいらないんだよ。感情のない、ロボットみたいな奴に価値なんてない。感情があるのが人が唯一ロボットより優れていると言える部分なのにそれが欠損してるってばれたら、俺は途端に存在価値がなくなる」
「そうやって怯えて生きるならいっそのこと、俳優なんて辞めてしまえばいいのに」
「……そんな簡単に辞めれたら、俺はもうとっくに表舞台からは消えてるよ」
それはそうか。酷なことを言ってしまったかもしれないと思い、謝罪の言葉を述べておく。君は気にしていないというように軽く頭を振った。
「では二つ目です。どうして再び私のところに来てくれたのですか」
「おい、質問一つにつき一個って」
「後で二つ答えますから」
私が無理やり言いくるめると、君は遅い瞬きをする。すると、真っ暗だった瞳に一つだけ光が宿った。仰向けになったことと、雲隠れしていた月が気まぐれで顔を出したことで、夜の空で場違いなほど輝くそれが映りこんでいるらしい。惑星が溶け込んだ瞳が私の姿を捉えると、一つ吐息を零してまた瞼を閉じた。
「……俺の仮面を見破った人間はお前だけだったから」
また、君が一つ私の知らない表情をする。
君の話を聞く度に私は増々君のことが分からなくなっていく。
足跡を辿ったからと言って元の関係に戻れるわけがないなら、先に進むしかない。
しかし、無性に立ち止まりたいと願ってしまうのはどうしてだろうか。
立ち止まれば何も変わらないと分かっているからなのか。
関係ではなく、私自身が変わってしまうと薄々気づいてきているからなのか。
自分でもよく分からなかった。
「今から言うことは打算に打算を重ねた私欲だ。嫌な気持ちにさせるかもしれない」
「別に構わないです」
分からないからと言って知ろうとするのが正しい訳ではない。時には目を逸らす方が物事が円滑に進むことだってある。
この状況は正にそれであった。知りたい、ただその欲望に従って他人の心にずけずけ入りこみ、挙句の果てに自分さえ見失おうとしている。ここで辞めるべきなのだ、こんな男はとっとと付き人に引き取らせるべきなのだ。
何も知らない赤の他人は今の私を見れば嗤うだろう。
とんだ愚か者だ、と。
「年月を重ねる度に、取り繕うものがどんどん分厚くなっていった。塗り重ねる度にそれは剥がれなくなって、いつしか笑顔を絶やさない完璧な俺が、感情の起伏が薄い何も価値のない俺を乗っ取った。時々自分でもよくわからなくなってたんだ、本当の俺って何だろうって。兎に角笑って、打算的に反感を買わないくらいのお世辞と気遣いの言葉ばかり吐く。それで王子様って言ってもらえるなら、誰かから必要とされるならもうそれでいいかって思ってた」
男は一度言葉を句切る。それから喉を鳴らして、私の目を捉える。
「でも、昨日のお前の目は違った」
人ならざぬものの声は僅かな期待を帯びていた。
「穏やかに見えて鋭い視線は、人の本質を見抜こうとしていた。その目で思い出したんだよ、あぁそういえばこんなへらへら笑うのは俺じゃないなって。俺が必死になって作り上げた『相島透』だったなって。だからお前といれば何か取り戻せるかと思ったんだ」
昨日のことがまるでその場で出来事のように鮮明に再生される。あの時は試合に集中するあまり気づかなかったけれど、言われてみれば君を纏う空気が途中から少し変わったような気がした。
「お前が空っぽな俺を見抜いたなら、それを埋められるのもお前だけかもしれないって勝手に期待して、今ここにいる」
君は不思議と満足そうな表情をしていた。もしかしたら君の目的とは私の知りたいと言う欲を満たすためではなく、自分を取り戻せるかもという淡い期待からなのかもしれない。
「これで全部だ。さて次は俺の番だ。まずお前は死ぬのは怖くないのか?」
今度は私が質問を受ける番だった。私は逡巡の考えを巡らせた後、正直に自分が今感じていることを口にすることにした。
「うーん、怖いというよりはそれが私の生まれた意味なのでもう割り切っているという感じですね。怖いという感情は未知のものに対して生まれると思います。地位、金、人脈、家族、苦しんでようやく掴んだそれがたった一瞬で無に帰する経験は生きていてそうそうないでしょう。味わったことがないから人は死に対して怯えて生きるのです。私は失うことが怖いと感じるほどの地位も思い出も積み重ねてきたこともないので」
私が淡々と答えると、君はなるほどと納得したような顔をした。反対側の山から厳かな鐘の音が聞こえる。もう子の刻だった。明日のために少しでも体を休めておきたい私はここらが潮時だと障子に手を掛ける。
「今日はこれにて失礼します。明日は朝から色々とやることが多いので」
閉めようとした瞬間、木枠を掴んでた手に何かが重ねられた。冷えた指先が閉めようとする私を阻止する。どうしたものかと顔を上げると、君は珍しく動揺したように目を見開いていた。
「どうしたんですか、そんな顔して。もしかして私の晴れ舞台に来てくれたりするんですか?」
「いや、待て。まだ質問をもう一つする権利が俺にはある」
嗚呼覚えていたのか、しつこい男だ。門外不出だった神に捧げる少女の情報が、数多の記者が喉から手が出るほど欲しいそれが、得られたなら、多少妥協してくれたっていいのに。しかし、端から君の目的は私の情報ではないことを思い出して私は肩を落とした。
私はぶっきらぼうに「何ですか」と尋ねた。
澄んだ瞳と視線が絡み合う。私の心を全部見透かしていそうな真っ暗な闇に眼を逸らしてしまいたかった。ばれたくない、自分の醜さを知られたくはない。でも目を逸らしたところで結局は全部君は分かっている、そんな予感がした。だから私は諦めて、ただじっと目と鼻の先にある珠玉の瞳を見つめる。
「お前は生きたいとは思わないのか」
私は瞬きも忘れて彼と見つめ合う。君の両腕はだらりと脱力しているのにどうしてか首を絞められているような錯覚に陥る。喉に詰まる空気と食道から落ちていかない唾液に私の視界は一瞬、真っ白になった。
何秒意識を飛ばしていたのだろう。私の視界が再び鮮明になったときには、傾きかけていた体は重力とは反対の方向に引っ張られていた。
「っぶな……貧血か?」
「え、あ、ありがとうございます」
もやしみたいな腕に見えて中身は筋繊維が詰まっているらしい。私の体を腕一本で支える力は思いの外強かった。いやだいやだ、この男といると全てが乱されていく。主導権を握られた時点で私は負けなのだ。焦りからこめかみに冷たい汗が流れた。これ以上失態を犯すのはまずい。神に捧げる少女の実態は謎であればあるほど客受けもいい。彼の情報の使い方次第では赤字、ひいては存続の危機に関わってくる。明日死ぬとは言え、この神社の損害賠償でも求められたら私は堪ったものではない。私は早口でまくしたて、強引に会話を終わらせようとする。
「正直に言うと口を滑らせました。本来なら扑克に勝利しても高いくらいの情報を貴方には渡したつもりです」
とっととお帰りくださいと広い背中をぐいぐい押す。君は半ば強制的に立たされると、またすまほとやらの光を付けて足元を照らした。私は最後にとっておきの言葉をあげようと思った。
明日死ぬ私を人生で経験したことないくらい楽しませてくれた男だ、これくらいの褒美はあげてもいいだろう。
私は顔を綻ばせると、縛って殺して奥に仕舞っていた感情の片鱗を君に一つ渡す。
それは神主も知らない、扑克に百回勝ったって手に入らない、神に捧げる少女の心の声だった。
「知っていますか?最初から孤独な人間は、自分で知ろうとしない限り、願い方すら分からないんですよ」
真っ白な和紙を見てため息を吐いた。もうすぐ夜が更けようとしている時刻、私は奉納祭の書類に追われていた。もう何十枚目かも分からない書類に墨を滲ませていく。幾ら文字を書いたって、頭の中は昨日の男のことばかりだった。軽薄そうな笑みを果たして信じてもいいのか、期待に胸を膨らませる感情が体を充満させる。しかし、期待しすぎていざ来なかったときの落胆を想像すると手放しでわくわくは出来なかった。
相島透はまだ来ない。
その間に私の手首は限界を迎えていた。文字を書きすぎて腱鞘炎になってしまったようだ。痙攣する右手を抑え込む。今日はもう寝てしまおうか。どうせあんなの言葉の綾だったのだ、私は単なるお遊びに過ぎない。芸能人さんの戯れの相手に過ぎなかったのだ。
ただ、知りたかっただけなのに。
どうして、あんな表情をしていたのか。
君はどうして自分を偽って生きているのか。
ぼうっと考えを巡らせていると、いつの間にか和紙の上には黒い染みが出来ていた。いけない、書き損じたそれを丸めてちり箱に投げ捨てる。
その時、夏嵐が障子の木枠を激しく揺らした。
「よぉ」
私はその声で一瞬誰だか気づくことができなかった。顔を見て、ああ約束をしていた人だとようやく分かった。約束通り訪れたことに喜びを感じながら、私は違和感を抱く。それにしても昨日の媚びるような態度はどうしたのか、一変して年相応の男のように振る舞う彼を見て私は目を丸くした。いや、彼の年齢は知らないが一般的な男性と比較して随分不愛想である。没落貴族という言葉がぴったりだと思った。
昨日と同じような気楽な服を着こなしている彼は、今日も障子を開け放つ。それから今度は座布団を持ってきたらしく枯葉の上に自前の座布団を敷いてそこに腰掛けた。居心地を良くしてどうする。
そんな専横な態度をされると自分だけきっちりしているのが馬鹿らしくなって、私も正座で折りたたんでいた足を崩した。
「なんか昨日より態度悪くないですか?」
「お前も昨日より随分本音を言うようになったな」
「おま……お前って……初めて言われましたよ」
「お前はお前だろ。だって俺名前知らないし」
「だって私名前ないですもん」
君の顎が外れそうになる。驚愕の表情で瞳孔が開かれたまま一点を見つめ続けるものだから死人のように見えた。一応目の前で手を振って意識を確認するが、うざかったのか振り払われる。
「名前、ないのか」
「はい」
「だって、年は17だろ?17年間どうやって過ごしてきたんだよ」
「お嬢様とかお姫様とか神に捧げる少女って呼ばれてきました」
「親の苗字とかは?」
「私は孤児ですので、物心つく頃にはここにいました」
平然と言う私に君は理解が追い付かないとばかりに瞬きを繰り返す。私はどんな顔をしていいのか分からなくて苦笑いを浮かべた。こういうとき普通は躊躇ったり、悲しそうな顔をしたりするのだろうか。けれど親がいないのも、名前がないのも、当たり前として生きてきた私にとっては逆に名前があることや親がいることの方が不思議に思えてしまう。名前がなくともお嬢様と呼べば私だと分かるし、身の回りのことは愛情がなくとも巫女が全てやってくれた。不自由はない。なのに皆、私が一言その言葉を告げると腫物を見るかのような視線を向けてくる。
その度に私はどうやって反応していいのか分からなくなるのだ。
私は可哀そうな子なのか。私の存在は変なのか。
認めてしまえば、何かが崩壊する。そんな予感がして、ただ曖昧な顔しかできないままでいる。
「あ、袖のとこ、取れかかってますよ」
ふと君の袖で蓑虫のように揺れる何かをみつけた。金色に揺れるそれを手に取ると、立派な細工が施された釦だった。流石芸能人ということもあり、服の装飾一つにしても高価である。君は現実に引き戻されたように袖口と私の方に視線を向ける。話題を転換させるのにも丁度よかった。私は部屋の奥から刺繍用の針と糸を取りに行こうと立ち上がると、君が俯かせてた顔を上げた。
「じゃあボタンで」
「へ?」
「名前、お前の。ボタンに決めた」
君は私の額に人差し指を突き立てると、「ボタン」と何度も口ずさんで少し顔を綻ばせた。自然に表情筋が上がる様に、私は初めて彼の本当の笑顔を知れた気がする。控えめだが、繕った笑い以外の笑い方もできるんだと彼の数少ない人らしい部分に少し安堵した。
私も真似して声でなぞる。何度も言っていくうちに、二人の声が重なった。微かに不協和音を避けた声で紡がれる3文字の名前は、ゆっくりと私の細胞全てに落とし込められる。
適当すぎやしないだろうか。しかしこの瞬間に17年間何もなかった私という存在に名前がついた。しかも出会って二日の男の釦が取れかかっていたという理由で。
ボタン
実に適当で、安直な名前である。しかし、私如きに名前をつけられるのならその程度でいいような気がした。
私はこの状況が何だかおかしくて、耐えきれず小さく噴き出した後、誤魔化すように咳ばらいを一回。射貫くような眼光をひんやりした瞳に向けてやる。
「勝手に決めるんですね」
「ああ、不便だからな。あと名前くらいはあってもいいだろ」
「一応お礼を言っておきます」
「一応ってなんだ、一応って」
つんけんした態度を取っているが、名前を付けられたことは悪くない。しかし正直に感謝の言葉を述べられないのは、会話の主導権を全て相手に握られていたからだ。子供じみた理由だが、そこは数多の客を手玉に取ってきた神に捧げる少女としての矜持が許さなかった。そんな私を察してか彼は不躾な態度に対して何も言及してこない。大人な対応に仕掛けた私はますます居心地が悪くなって、黙りこくる。
ここまでくると私の態度も随分砕けたものになっていた。染みついた言葉遣いは丁寧なままだが、自分だけ笑顔を取り繕うのも疲れるので表情筋を弛緩させた。
不意に神社の方から重たいものがぶつかる音がして目の前の男から視線を外す。斜め下の石畳には村の男たちが集まって、木製の骨組みが組み立てられていた。明日の祭りに備えて屋台を夜のうちに設置するようだ。今週の天気は概ね晴れらしく、提灯が雨天に気兼ねなく装飾されている。赤い和紙は淡い光に透かされていて、怪しく境内を染めていた。
私は特に表情も変えずに呟く。
「祭りの準備が進んでますねぇ」
「呑気だな、生贄のくせに」
「こういうのってもっと怯えた方がいいんですかね」
「そうじゃなくて」
君は私の問いを否定すると、神社の方に向けられていた顔を再びこちらに戻す。その顔には「昨日俺のことを分からないって言ったけど、お前も大概だぞ」という感情が滲んでいた。
「怖くないの?」
「透くんが私の質問に一つ答えてくれたら、私も一つ答えます」
「……お前、思っていた以上に強欲なんだな」
「失礼な、したたかと言ってください」
私が臍を曲げて顔を背けると、彼は面倒そうにため息を吐く。
「んで、質問って言うのは?」
「透くんはどうしてあのようなキャラを作っているのですか」
彼は思い出したように眉を上げた。それが目的でここにいるのではないか、と思った。けれど、忘れているなら君の目的はもしかしたら別なのかもしれないなと考えて口には出さなかった。
「あぁ、そういえば昨日教えるって言ったね」
「忘れないでくださいよ、その答えを知るまでは私も死に切れませんから」
目の前の男はふっと温度のない瞳を更に絶対零度まで下げる。怒りが込められているわけでも、憎しみが込められているわけでもない。それなのに冷たいと思わせるのは、透き通るそれが放つ光が一切ないからだろう。君の目から急に人らしい温度がなくなると無機物のように見えた。それこそ、びいどろだった。澄んでいて美しいのに、あたたかみはない。それが二つ埋め込まれた顔は美しさと同時に危うさを持ち合わせていた。
これ以上何かが欠けてしまえば、その場で消えてしまいそうな儚い危うさだった。
「空っぽだからだよ」
すり硝子の声が耳をなぞって私は鳥肌が立った。無意識のうちに細く白い首に手を伸ばし、手の甲を押し付ける。私の肌よりほんのりあたたかい皮膚は血管の震えをそのまま伝える。人離れした美しい声は触れた首筋の振動が無ければ、精巧に作られた傀儡だと疑ってしまいそうだなと思った。
「俺は感情の起伏が著しく薄い」
「どうして、」
「周りの環境が特殊だったからだと俺は思ってる。俺は幼い頃からこういう職業をしてたからさ、お前ほどではないけど普通の人生とはかけ離れた世界で生きてきた。その過程で、まぁ何と言うか色々あった訳」
虚ろという言葉をそのまま擬人化した人間に一歩を踏み入れるのは流石の私でも恐怖があった。それでも喉のすぐそこまでせり上がってきてしまうのが、強い好奇心の悪いところだ。後先考えずに口にするのは軽率であるし、何より寿命を縮める。それでもいいから知りたいと思ってしまうのが私だった。ゆっくりと足音を立てないように、気配を殺すように、獲物に近づく猫みたいに、私は慎重に言葉を紡ぐ。
「その、『まぁ何と言うか色々』が知りたいと言ったら、怒りますか?」
「さっきも言ったように俺は怒るも何も、全部どうでもいいと思ってる。でもお前には聞かせたくない」
「……それは何故」
「壊れちゃうから」
私と同じだと思った。君の壊れるが何かは分からない。どの程度なのかも知らない。もしかしたら同じだと比喩するには大袈裟すぎるかもしれないし、同じだと言うには私が身の程を弁えた方がいいほどの大事なのかもしれない。けれど私が私自身の運命を疑った瞬間に世界が壊れるのと同じように、そこが一つ君の踏み越えてはならない境界線のような気がする。欲張って知ろうと踏み込めば最後、君の瞳の真っ暗な部分の深淵から抜け出せなくなる。壊れると言うのは、僅かに残った理性や感情が全てなくなってしまうということを指しているのかもしれない。
君は全身の筋肉の緊張を解いて仰向けに寝転ぶ。そんなところで寝たら汚いはずなのに、妙に自然に溶け込むそれに私は悪寒がした。
「空虚な人間はいらないんだよ。感情のない、ロボットみたいな奴に価値なんてない。感情があるのが人が唯一ロボットより優れていると言える部分なのにそれが欠損してるってばれたら、俺は途端に存在価値がなくなる」
「そうやって怯えて生きるならいっそのこと、俳優なんて辞めてしまえばいいのに」
「……そんな簡単に辞めれたら、俺はもうとっくに表舞台からは消えてるよ」
それはそうか。酷なことを言ってしまったかもしれないと思い、謝罪の言葉を述べておく。君は気にしていないというように軽く頭を振った。
「では二つ目です。どうして再び私のところに来てくれたのですか」
「おい、質問一つにつき一個って」
「後で二つ答えますから」
私が無理やり言いくるめると、君は遅い瞬きをする。すると、真っ暗だった瞳に一つだけ光が宿った。仰向けになったことと、雲隠れしていた月が気まぐれで顔を出したことで、夜の空で場違いなほど輝くそれが映りこんでいるらしい。惑星が溶け込んだ瞳が私の姿を捉えると、一つ吐息を零してまた瞼を閉じた。
「……俺の仮面を見破った人間はお前だけだったから」
また、君が一つ私の知らない表情をする。
君の話を聞く度に私は増々君のことが分からなくなっていく。
足跡を辿ったからと言って元の関係に戻れるわけがないなら、先に進むしかない。
しかし、無性に立ち止まりたいと願ってしまうのはどうしてだろうか。
立ち止まれば何も変わらないと分かっているからなのか。
関係ではなく、私自身が変わってしまうと薄々気づいてきているからなのか。
自分でもよく分からなかった。
「今から言うことは打算に打算を重ねた私欲だ。嫌な気持ちにさせるかもしれない」
「別に構わないです」
分からないからと言って知ろうとするのが正しい訳ではない。時には目を逸らす方が物事が円滑に進むことだってある。
この状況は正にそれであった。知りたい、ただその欲望に従って他人の心にずけずけ入りこみ、挙句の果てに自分さえ見失おうとしている。ここで辞めるべきなのだ、こんな男はとっとと付き人に引き取らせるべきなのだ。
何も知らない赤の他人は今の私を見れば嗤うだろう。
とんだ愚か者だ、と。
「年月を重ねる度に、取り繕うものがどんどん分厚くなっていった。塗り重ねる度にそれは剥がれなくなって、いつしか笑顔を絶やさない完璧な俺が、感情の起伏が薄い何も価値のない俺を乗っ取った。時々自分でもよくわからなくなってたんだ、本当の俺って何だろうって。兎に角笑って、打算的に反感を買わないくらいのお世辞と気遣いの言葉ばかり吐く。それで王子様って言ってもらえるなら、誰かから必要とされるならもうそれでいいかって思ってた」
男は一度言葉を句切る。それから喉を鳴らして、私の目を捉える。
「でも、昨日のお前の目は違った」
人ならざぬものの声は僅かな期待を帯びていた。
「穏やかに見えて鋭い視線は、人の本質を見抜こうとしていた。その目で思い出したんだよ、あぁそういえばこんなへらへら笑うのは俺じゃないなって。俺が必死になって作り上げた『相島透』だったなって。だからお前といれば何か取り戻せるかと思ったんだ」
昨日のことがまるでその場で出来事のように鮮明に再生される。あの時は試合に集中するあまり気づかなかったけれど、言われてみれば君を纏う空気が途中から少し変わったような気がした。
「お前が空っぽな俺を見抜いたなら、それを埋められるのもお前だけかもしれないって勝手に期待して、今ここにいる」
君は不思議と満足そうな表情をしていた。もしかしたら君の目的とは私の知りたいと言う欲を満たすためではなく、自分を取り戻せるかもという淡い期待からなのかもしれない。
「これで全部だ。さて次は俺の番だ。まずお前は死ぬのは怖くないのか?」
今度は私が質問を受ける番だった。私は逡巡の考えを巡らせた後、正直に自分が今感じていることを口にすることにした。
「うーん、怖いというよりはそれが私の生まれた意味なのでもう割り切っているという感じですね。怖いという感情は未知のものに対して生まれると思います。地位、金、人脈、家族、苦しんでようやく掴んだそれがたった一瞬で無に帰する経験は生きていてそうそうないでしょう。味わったことがないから人は死に対して怯えて生きるのです。私は失うことが怖いと感じるほどの地位も思い出も積み重ねてきたこともないので」
私が淡々と答えると、君はなるほどと納得したような顔をした。反対側の山から厳かな鐘の音が聞こえる。もう子の刻だった。明日のために少しでも体を休めておきたい私はここらが潮時だと障子に手を掛ける。
「今日はこれにて失礼します。明日は朝から色々とやることが多いので」
閉めようとした瞬間、木枠を掴んでた手に何かが重ねられた。冷えた指先が閉めようとする私を阻止する。どうしたものかと顔を上げると、君は珍しく動揺したように目を見開いていた。
「どうしたんですか、そんな顔して。もしかして私の晴れ舞台に来てくれたりするんですか?」
「いや、待て。まだ質問をもう一つする権利が俺にはある」
嗚呼覚えていたのか、しつこい男だ。門外不出だった神に捧げる少女の情報が、数多の記者が喉から手が出るほど欲しいそれが、得られたなら、多少妥協してくれたっていいのに。しかし、端から君の目的は私の情報ではないことを思い出して私は肩を落とした。
私はぶっきらぼうに「何ですか」と尋ねた。
澄んだ瞳と視線が絡み合う。私の心を全部見透かしていそうな真っ暗な闇に眼を逸らしてしまいたかった。ばれたくない、自分の醜さを知られたくはない。でも目を逸らしたところで結局は全部君は分かっている、そんな予感がした。だから私は諦めて、ただじっと目と鼻の先にある珠玉の瞳を見つめる。
「お前は生きたいとは思わないのか」
私は瞬きも忘れて彼と見つめ合う。君の両腕はだらりと脱力しているのにどうしてか首を絞められているような錯覚に陥る。喉に詰まる空気と食道から落ちていかない唾液に私の視界は一瞬、真っ白になった。
何秒意識を飛ばしていたのだろう。私の視界が再び鮮明になったときには、傾きかけていた体は重力とは反対の方向に引っ張られていた。
「っぶな……貧血か?」
「え、あ、ありがとうございます」
もやしみたいな腕に見えて中身は筋繊維が詰まっているらしい。私の体を腕一本で支える力は思いの外強かった。いやだいやだ、この男といると全てが乱されていく。主導権を握られた時点で私は負けなのだ。焦りからこめかみに冷たい汗が流れた。これ以上失態を犯すのはまずい。神に捧げる少女の実態は謎であればあるほど客受けもいい。彼の情報の使い方次第では赤字、ひいては存続の危機に関わってくる。明日死ぬとは言え、この神社の損害賠償でも求められたら私は堪ったものではない。私は早口でまくしたて、強引に会話を終わらせようとする。
「正直に言うと口を滑らせました。本来なら扑克に勝利しても高いくらいの情報を貴方には渡したつもりです」
とっととお帰りくださいと広い背中をぐいぐい押す。君は半ば強制的に立たされると、またすまほとやらの光を付けて足元を照らした。私は最後にとっておきの言葉をあげようと思った。
明日死ぬ私を人生で経験したことないくらい楽しませてくれた男だ、これくらいの褒美はあげてもいいだろう。
私は顔を綻ばせると、縛って殺して奥に仕舞っていた感情の片鱗を君に一つ渡す。
それは神主も知らない、扑克に百回勝ったって手に入らない、神に捧げる少女の心の声だった。
「知っていますか?最初から孤独な人間は、自分で知ろうとしない限り、願い方すら分からないんですよ」