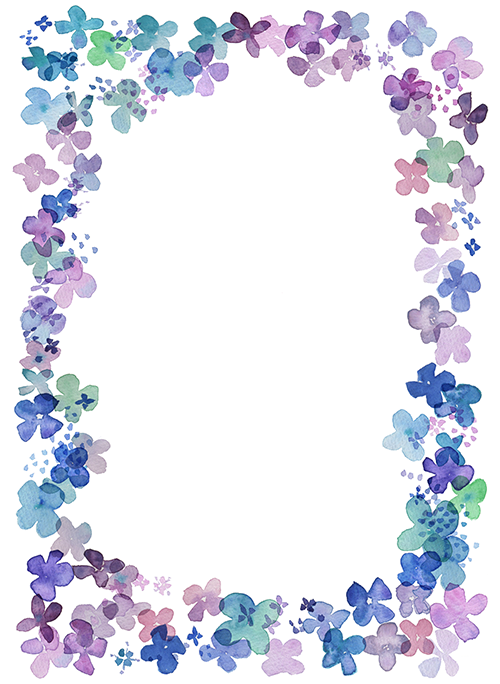ミシミシミシミシミシミシ
けたたましい一定の波が鼓膜を貫き、脳で響く。
「っううぅ」
あまりの不快感に飛び起きると、もう光が外から漏れていた。朝だった。蝉は今日も休むことを忘れて鳴いている。私はむくりと起き上がると、掛け布団を畳み始めた。
昨晩の寝苦しさで今晩は寝れないかも……なんて不安は杞憂だったようだ。気が付けば私は意識を手放していたらしい。窓のない部屋は熱を帯びた空気で満たされていた。ふと背中に手を伸ばすと小さい頃のおもらしを彷彿させるほどぐっしょりと汗で濡れていた。
「気持ちが悪い……」
何もかもが上手くいかない朝で顔が歪む。しかし、朝から風呂に行くことなんてきっと許してはもらえないから我慢して手拭いで首筋を拭った。
「あっ!!!本!!!!」
枕の隣には無造作に積まれた心理学の本がある。完全に忘れていた。睡魔に身を委ねすぎたあまり、そのまま熟睡してしまったようだ。がっくりと肩を落としながら部屋の掃除を始める。流石の私も凄い人が来ると知ってしまったので、多少は身構えてしまう。
敷布団のシーツを剥がし、枕のカバーも剥がす。裸になった敷布団を三つ折りにして部屋の隅に追いやる。普段はやらない床のからぶきをすると、赤紫色の染みが所々についた。昨日の客が零したものがまだ残っていたようだ。
いつものルーティーンが終わると、唯一の扉が叩かれる音と共に一人の人影が見えた。
「おはようございます」
背中を九十度に曲げて、こちらに入ってきたのは顔なじみの巫女だった。私に仕える巫女は二人いる。昨日の巫女は年と感性が近いこともあり、比較的仲は良好だった。観察する限り下心もないので、純粋な気持ちで向き合ってくれていると分かる。
しかし、彼女は違った。明らかに私を毛嫌いして、汚らわしいものとして扱う。態度や言葉では表立つことないが、私にとってはとても分かりやすい。何なら私だけに伝わるよう意識してやっているのではという節まである。
「お嬢様、本日のお加減はいかがでしょうか」
まるで機械のように、淡々と台本を読むように、巫女は問う。私が調子が良かろうが悪かろうが本当はどうでも良いのだろう。ひんやりとした声音に私は本心を覆い隠す完璧な笑みを浮かべる。
「今日も今日とて蒸し暑いですね。風も入ってこないので参ってしまいます。……障子をあけてもよろしいでしょうか」
「えぇ、ただお嬢様はそこに。私が開けます」
目の前に翳される手。立ち上がろうとする私を制してきびきびとした動きで木枠に手を掛ける。
私が障子を開けることを禁じられているのは、万が一ここから逃げ出したら困るからだろう。
『神に捧げる少女』
建前では崇められる綺麗な言葉であるが、実態はそうでもない。
100年に一度、『神に捧げる少女』に選ばれた娘は17歳の夏、奉納祭にて神に捧げられる。神に捧げると言えば聞こえがいいが、事実は腹を切って死ぬことを指す。
そして『神に捧げる少女』は奉納祭までこの小屋から出ることを許されてはいない。かつて、奉納祭前夜に夜逃げを実行しようとした前例があることから祭りの日まで外出することは禁じられることになったらしい。
心拍数が早まる胸をそっと撫でる。ドクドクと妙に生々しい鼓動が掌に伝わった。
私は不安になるとよく胸に手を当てて自分の心臓が動いているかどうかを確認する。
鼓動が確認できると、今度は少し下に手を滑らせる。
そうすると丁度子宮の辺り、硬いものとジグザクに縫われた皮膚が当たるのだ。
私の爆弾。私だけの爆弾。
10年前に埋められた傷跡が、無理やり隠すように残されていた。
この爆弾は私が小屋を出ると爆発するようになっている。
小さい頃はただの脅し文句だと思っていたが、巫女が言うには本当に爆発するようだ。
50キロ近い体が、それは花火のように粉々と、鮮やかに、一瞬で爆ぜる。
震える指を抑え込むために腕を掴んだ。しかし掴んだそれもハイノキの枝のよう細く、力を込めればぐにゃりと曲がってしまいそうだった。いつも客と対峙しているときの自信は何処へやら。自分のことを考えると途端に意気消沈してしまう。顔を洗うための水が張られた桶には情けない顔の自分が反射していた。私はこんな体でも生きながらえているんだ、と思った。
顔を上げると巫女と目が合う。絹に似た髪を一つに括って靡かせる彼女は、世間と私の感性が一致すればきっと美人の部類に入るのだと思う。私はその顔をじっと観察した。
爆弾の詰められた他は空っぽの少女は、どれだけ心が読めようが誰にも生きることを願われていない。誰からも生きてほしいと思われていないのに、世界で私だけが私に生きてほしいと思ってしまうのは薄汚い人間の証拠だ。
「姫様、今日は大人しいですね。いつもは何やら怪しい本を読んでぶつぶつ呟いているのに。それが習慣となればいずれ客の前でも襤褸を出しますよ」
急に声が頭上から降り注いできて、私は肩を震わせた。視線を上げると巫女が不思議そうにのぞき込んでいる。考えこんでいたのが、大人しいと捉えられたみたいだ。
「ふふふ、私はもう十七ですよ。そんな粗相はしませんよ」
襖が開け放たれた長方形の木枠は、窮屈な部屋に光をもたらした。と言っても、広がるのは小屋の前の雑木林だけなのだが。襖という障壁がなくなった途端に今がその時だと言わんばかりに蝉が一斉に鳴きだす。
季節は夏なのだ。
もう、とっくに17歳の夏なのだ。
それなのに、どうして私は17年間もこの狭い6畳半の小屋に一人閉じ込められているのだろう。
「神に捧げる少女だなんて……」
馬鹿馬鹿しい
喉までせり上がった言葉を飲み下す。危ない、私はあくまでも純粋無垢な神に捧げる少女なのだから、自分自身が何故ここにいるのかなんて疑問に思ってはいけない。幸いにも呟きは蝉の求婚にかき消され巫女の耳には届いていないようで、私は生まれて初めて耳障りな蝉を好きになりかけた。
「お嬢様。朝食はどういたしましょう」
巫女が手についた埃を親指と人差し指で擦り合わせながら問いかける。姫様、なんて恭しい呼び方に全くそぐわない態度に思わず笑ってしまいそうになる。結局彼女の目に映る私はその程度のただの小汚い少女なのだ。
「いつもと同じでいいですよ。どうして改めてそんなこと聞くの?」
彼女は微塵も心配していなさそうな声で答える。
「もうすぐ奉納祭なので。主から姫様の好きなものを召し上がればよいと承りました」
なら初めからそう言えばいいじゃないか。飛び出しそうになった言葉をぐっと堪えて「それは嬉しいわ」と綻んでみせる。
互いに仮初のこの空間に吐き気がする。
私は貴方が嫌い、貴方も私が厄介。
それで話が済めばどれほど楽だろう。
それでも私を捨てられないのは、村人の反感を買うのが怖いのか、神に見捨てられるのが怖いのか、神社の収入源が無くなるのは困るからか。
何にせよ、私は傀儡だと思ってくれた構わなかった。私は生かされている、生かされている間は「神に捧げる少女」なのだ。
いい感情しか持つことしか許されていない、純粋な少女なのだ。
むしろこの場での正解は彼女みたいな対応なのかもしれない。変に情が入ると、自分の身まで亡ぼすことになる。私を逃がす手助けなんてしたら連帯責任でここの巫女は全員殺されるだろう。そんな馬鹿なことを彼女たちがするようには思えない。
諦めの表情で「では、だし粥に梅干を添えたものを」と答えようとしたとき、緊迫した空気を切り裂くほどの大きな声量が小屋を貫いた。
「姫さまああああ!」
私を呼ぶのは先ほどの粘っこい声ではなく、鈴を鳴らしたような愛らしい声だった。声の在処を探すようにきょろきょろと首を動かすと、乱れた足音が近づいてくる。まさかと思い若干引きながら窓の方を見つめると、予想通り昨日会った巫女が鬼の顔で迫ってきていた。この急斜面の山を駆け上がってきているのか、なんと恐ろしい女なんだ。
勾配20%を超える激坂を普通の道と同じスピードで走る彼女はさながら猪である。
「何あの子……」
流石の嫌味巫女もドン引きしたようで、無意識に顔を引きつらせていた。
「何かとんでもなく急ぎの用事があるのでしょうか」
「それは私にも聞いてみないと分かりません」
呆れたように巫女が首を左右に揺らすのと同時に、息を切らした巫女が飛び込んでくる。とんでもなく急いで来たのか、袴の裾は粘土だらけで頭頂部には葉っぱが刺さっていた。年上巫女が汚いとばかりに顔を顰めるが、そんなのお構いなしで年下巫女は必死な形相で声を荒げる。
「い、います!!相島透っ」
「へ?」
「だから、もういらっしゃっています!!相島透さんが」
「それは貴方の見間違えではないですよね。いくらなんでも早すぎますよ、約束の時間より3時間も前倒しだなんて」
「見間違えるわけないじゃないですか!だってあんな天女みたいなお方そうそういませんよ。あれ、本当に野郎ですか?」
「野郎なんて汚い言葉使わないでください!仮にでもお嬢様付の巫女なのですよ」
「仮にでもって、姉さんが言えることじゃないでしょ……」
おいおいそれが昨日私に言葉遣いを指摘した人間の言う言葉なのか。このままでは突っ込みの大渋滞が起きてしまう。私は混乱する現場を何とか整理しようとした。
「まぁまぁ喧嘩はよしてください。それと私も確認するけれど本当に相島透さんで間違いないのですね?」
「はい、お嬢様もあってみれば分かります。驚いてひっくり返らないでくださいね」
私はもう朝食をとることが出来ないまま、寝起きで扑克に挑まなければいけないのか。ふらふらと千鳥足で今日の着物を取った。瞼を重く落としたまま直立していると、巫女が帯を締めてくれる。
「待ってください、そんな約束の時間を守らない方、お嬢様と会わせられません」
片手でウエストを容赦なく締め上げながら年上巫女は厳格な態度で言う。危うく胃酸が逆流しそうになったが、そこは乙女の意地で何とか持ちこたえる。
年下巫女は体の左半分を小屋に、右半分を外に出しながら言い訳を述べる。全く、忙しない人だ。
「そうは言っても……ってあ!!駄目ですよぉ、ここまでいらっしゃったんですか、えぇ時間がない?次の予定があるにしろお嬢様優先ではないですか……ってグチグチ口答えするな?はぁ分かりましたよ……」
大丈夫なのか、何か言いくるめられていないか。何だか外が賑やかになってきて私はそわそわとしてしまう。慌てていつもの皮張りの椅子に腰掛けると、背筋を伸ばして客人を待った。ひと悶着あった後、年下巫女に加えて年上巫女も参戦した口論は決着がついたらしい。年下巫女が申し訳なさそうに手で小さく罰を作った。私が展開に追いつく暇もなく、年下巫女は作り笑いで扉を開け放つ。
「それではお待ちかね!相島透さんのとーじょーです!」
心の準備が整わない中、光と共に人影が入ってきた。しかし、外の太陽光が明るすぎて逆光になっている。顔はよく見えないが上背がとても高かった。巫女が余裕をもって入れる扉を、頭を下げてくぐる仕草が見えて私は目を疑った。
「急に来てしまって申し訳ないです」
なんと声もよかった。私は感嘆の声を漏らす。
流石俳優と言うだけある。一人の人間に対して五人もの男や女が仰々しく連なっていた。その中心で腰を折るのは頭一つ飛びぬけたシルエットであった。随分楽な格好をしている、だぼっとした着こなしなのにどうしてこうも体のバランスが良く見えるのだろう。私は間抜けな顔で彼の一挙手一投足に集中した。
「こんにちは、お嬢様」
ようやく光が落ち着いて、彼の顔が鮮明になる。
にこりと上がった口角。一目見た瞬間、世が世であったら国が傾いていただろうと思った。涼し気な切れ長の目元に、薄い唇と、すっと通った主張の少ない鼻梁。男性のわりに透明感のある肌はそのまま後ろの背景を透かしてしまいそうだ。
「ぇ……」
情報量が多すぎる。私の頭は意味のない言葉が口から漏れてしまうほど、故障寸前だった。きっと彼の美しさを文字に書きだせばきりがないだろう。たじろぐ私に悪い笑みを浮かべて距離を詰める男。私は思わず身を縮こませそうになったが、何とか神に捧げる少女としての理性が繋ぎとめる。
「どうしたの?」
試すような表情、きっと彼は私が見とれているのだと勘違いしている。でなければ、たった五文字をそんなに意気揚々と発音できないのだ。
生憎、私は彼の顔面に驚いてはいるが、性的衝動は感じていなかった。
神に捧げる少女は今まであらゆる人間と対峙してきた。その経験から段々と人にそういう感情を抱かなくなってしまったのだ。
少女は人の心理状態を察することができる。その過程で、善人を探そうとふるいに掛けると驚くことに誰も残らない。出会ってきた人間が特殊なだけかもしれないが、私にとっては経験が世界のすべてだった。結果、人に対する期待や恋心の類を忘れてしまった現在の少女が完成したのだった。
「笑いかけないで貰ってもよろしいでしょうか」
私の腰の低い態度に、何を勘違いしたのか目の前の男は更に蕩けるような笑みを浮かべる。
「ふふ、我慢しなくていいんだよ」
「そうじゃなくて……巫女が倒れます」
突如、何やら重いものが倒れる音がして私は苦笑いを張り付けながら振り返る。
案の定、巫女が鼻血を垂れ流しながらぴくぴくと打ち上げられた魚のように痙攣していた。
私の言わんこっちゃないという表情に、君はただ驚く表情を浮かべて立ち尽くしていた。
「仕切り直して本日はよろしくお願い致します。神に捧げる少女です」
「相島透です!今日はよろしくね。君とポーカーできるの楽しみにしてたんだよ!」
「私も同じ気持ちです」
社交辞令を適当に言ってのけると、机の横で慎ましやかに立っている巫女に目配せをする。ちなみに年下巫女は鼻にちり紙を詰めて小屋の裏で待機することになった。年上巫女が「夏炉冬扇だわ」とぼやいていたのは僅かな良心から伝えないことにする。早速巫女が札を混ぜ、振り分ける。私も手元を見たが悪くない数字だった。これは余裕で勝てるだろう。
しかし、正面の男を見ていると拭えない違和感があった。何だろう、別におかしいところはない。いや、現実離れした顔はさておき言動、動作、息遣い、どれも嘘を吐いているようには見えず落ち着いていた。
「落ち着いて……?」
それが一番おかしいのか。私はようやく腑に落ちた。
「どうかしたの?早く次の手を」
「あっ、はい。すみません」
私は慌てて手札を見た。しかし、あまり集中はできない。彼は落ち着きすぎている。普通なら金を掛けていようが掛けていまいが、真剣勝負の賭け事となれば多少の緊張と高揚で汗ばんだり脈が速くなったりする。彼にはその兆候が一切見られなかった。まるで眠っているかのように、穏やかで乱れが一切ない。
それが完璧の域にまで達しようとしているので余計に怖い。
彼の様子を観察していると、私如きに神の使いというのは間違いだと思った。これは後天的に身につけたものだ。彼はどうだろう、私の見解では生まれつきのように見える。仮に後天的に身に着けたものだとすれば一体どれだけの努力と時間を要したのだろう。
彼こそ本当に天の使いかと勘違いしてしまいそうだ。
手元から視線を外して、正面を見る。口角のあがった表情はまだ余裕があるように見えた。
負けられない。私は気持ちを切り替えるために深呼吸をする。遅い瞬きを一度、まるでスイッチが押されたかのように世界が変わる。五感全てが研ぎ澄まされた今、負ける気はしない。
「ふふ、余裕ぶっていられるのも今のうちかもしれませんよ」
「お、よーやく本気出す気になったんだね!」
勝負は一時間半も掛かった。
ほぼ互角の勝負では接戦の末、神に捧げる少女の勝利であった。
しかし、私は結果に釈然としなかった。
神に捧げる少女にとってはお見通しだった、相島透にはまだ余力があったことが。
八百長で勝ってしまったことにどうしても納得がいかない。負けた時でさえ、彼は騙されてしまいそうなほど精巧な演技をしていた。
私は彼が考えていることがさっぱり理解できなかった。
取材班が帰ってから、よく分からない薬を巫女から手渡された。飲み込んだ瞬間、脳みそがとろとろと溶けてしまったのかと錯覚するほどの強い眠気に襲われて少し眠った。
夢の中で、何故か相島透が出てきた。私は彼の真正面に立って彼の顔を見つめる。私は今日彼の笑顔しか見ていないはずなのに、夢の中では洞窟のように暗い瞳が虚ろにこちらを見つめていた。
彼には感情が何もないように見える。
私とおんなじ、空っぽ。
衝動的に手を伸ばすと、目の前にいたのはペインターパンツの男ではなく、今にも落ちてきそうな天井だった。
体がだるくて視線だけを動かすと、締め切った障子の僅かな隙間から月明かりが夏風と共に差し込んでいる。
「あ、もう……夜かぁ」
一人しかいない部屋で、はぁとでかいため息を吐いた。
「どうしたの、ため息なんて吐いちゃって」
突然、薄い壁一枚の向こう側から声がして飛び起きた。巫女か?違う、女の人の声じゃなかった。じゃあ一体誰。今まで物珍しさで小屋の付近に訪れる人はいるが、誰も私を気味悪がって話しかけようとしてこなかった。
思い当たる節もないし、相当な変人が来たか。私は眉を顰めながら壁を叩いた。
「あの、誰かいますか……」
「いませんよー」
「ほら、やっぱりいるじゃないですか!!」
私が反応すると、外から笑いを堪えるような声がした。
「誰か当ててみてよ」
問いかける声音は水あめのように甘い。しかし、声量を抑えているからか時々低く掠れて、忘れかけていた声の持ち主が男性だということを意識させる。どうしよう、このまま彼が喋り続けたら心地よくてまた寝てしまいそうだ。意識が飛ばないように私は今までの記憶から男性の声を引っ張り出す。と言っても人生でこんなに透明感のある声、今日以外に聞いたことはない。
「え……まさか、相島透さん?」
「おお、正解」
相当驚いたのか声が震えていた。
「よく分かったね」
「吃驚するのはこちらですよ。どうしてここに?」
相島透は相当有名で多忙な人物だというのを知った今日、どうして彼がこんな辺鄙な神社の小屋に訪れたのか真意が分からない。大体マスメディアの取材に来る人は、表向きには興味があるように熱心に話を聞きに来るが、私がただの少女だと分かると途端に興味を無くしてどこかに行って二度と帰ってこないではないか。
私はとりあえず声のする方へ移動した。壁を軽く叩くと右から軽い音が返ってくる。私は右に移動してまた壁を叩く。今度はちゃんと正面から音がした。
「ここにいるの?」
確かめるように爪が木の柱を撫でる音がする。相手からは見えないというのに反射的に首を縦に振ると、突然、眩しい光が差して目を細めた。暫くして眩しさにも慣れてきた私は恐る恐る顔を上げる。二重の輪が重なり合う形は、よく巫女が夜の巡回に来る時に障子から見える形とよく似ていた。
「懐中電灯ですか?」
「いや、スマホのライト機能だけど」
光源の正体は和紙に透けた懐中電灯ではないのか。私は聞きなれない単語に首を傾げる。
「恐れながら、すまほって何ですか?新しい懐中電灯の種類ですか?」
「スマホ、知らない?携帯電話。ガラケーとかなら分かる?」
彼が軽々と口にする単語を繰り返そうと試みるが、すぐ口の中でへばりついた。知らない単語の波が押し寄せて私の頭は爆発寸前だ。なんだ、すまほって。『けいたいでんわ』も分からなければ、がら何とかもよく分からない。返事に困って緘黙を続けると、「ねぇ」と外から甘い声がする。
「障子、開けてよー。僕、君と会って話してみたいんだよね」
「何故?」
「昼間見て、めっちゃ可愛かったからー」
「お世辞は結構です」
「って理由が半分と、半分は今度のオカルト映画の勉強のため」
「んぐっ……騙されました」
「ほら、そういうところが可愛いんだよ」
「……お口が達者なことで」
私はそのすらすらと流れる口説き文句に一種の感心を抱きながらも、障子に触れることはできなかった。昔からそうだ、障子まで近づいて開ける寸前まではできるのに、どうしてもその先をしようとすると腕に力が入らなくなる。死にたくないから、朝の言葉を思い出した。別に障子を開けたところでここから逃げなければ爆弾は起動しないのに、私は死の池に飛び込むことは愚か石を投げ入れることすら怖いみたいだ。
そこまで生に縋りついたところで私には何もないのに。
醜い、醜い、醜い
自分のことが嫌いで嫌いで、今すぐ畳の上でのたうち回って絶叫したくなる。爪の奥に血が溜まるまで腕を掻きむしって、こんな自分消してしまいたくなる。
それでも正座の姿勢は崩せなかった。深呼吸をして乱れた精神を統一する。
私は『神に捧げる子』だから、こんなところで襤褸を出すことは許されない。
例え誰であろうと、一回きりの仲であろうと、人前に出るときの私は純粋無垢で清廉潔白な相応しい女を演じなくてはいけない。
私は微笑みを浮かべると、申し訳ない気持ちを前面に出して答える。
「映画の勉強は感心しますし、協力したいと思います。けれど、私は障子を開けることはできません」
「どうして」
「開けてはいけないと言いつけられているからです」
私がきっぱり答えると、彼は数秒の沈黙の後ケラケラと笑いだす。私は何故彼が笑うのか分からず、戸惑いながら「何か変なこと言ってしまいましたか?」と聞く。すると壁の向こうから衣擦れの音が聞こえ、彼が首を振っていることが分かった。
「いやいや、真面目だなぁと思って」
「……馬鹿にしてますか?」
「そんな!むしろ感心してるんだよ。君、反抗期とかなさそうだね」
「反抗なんて、出来ませんよ」
笑ったはずなのに、口角が痙攣して上手く笑えなかった。よかった、顔合わせしなくて。和紙一枚に守られた私の威厳にほっと息を吐く。
彼は何か勘違いしている。私は聖人君子なんかじゃない。反抗したところで、弱くて未熟で未来なんて何も変わりやしないから反抗しないのだ。
腹に手を当てて、風化しかけている傷口を掻きむしった。乱暴にしたせいで中にある硬いものが腹膜を刺激し、激痛が襲う。かはっと少量の胃液と共に私は畳の上に倒れこみ、酸素を貪った。
駄目だ、立ち上がれ。まるで呪いのように脳内で何度も繰り返される言葉に、反射的に足に力が入る。よろけながらも何とか立ち上がると私は腰を90度に曲げた。
彼は知らない。
17年前、神に捧げる少女となった日から私の内臓は爆弾に支配され、静かなる魔物が腹の中を牛耳っているということを。
「……申し訳ないのですが、お帰りいただけますか。先ほども申し上げた通り、私にそこを開ける権利はございませんので」
お帰り頂けますかと言ったのは私なのに、口の中が乾燥している。擦り合わせる手汗が止まらない。私が拒絶すればこれ以上、彼が踏み込んでくることはないのに。落ち着けと言い聞かせていることに対して反比例するように荒くなっていく息に、頭は混乱していた。こめかみに冷や汗が流れる。それを拭いながら、気づく。
私、怖いのか。
だって、彼は、
「じゃあ僕が開ければいいか」
カラカラカラ
夜の静寂に響く木材。
ひっ、と喉の奥から引きつる音がした。
「おっ、開いた」
彼は、変な人だから。
「ビックリしすぎじゃない?あ、これ不法侵入とかで訴えられないよねぇ?」
あ、や、と意味のない言葉が飛び出す。
「じゃじゃーん。本日二度目の相島透です!って言ってもテレビないもんなぁ。興味ないか、僕のこと」
「やっ、なんであああけたんですか!!」
「何でって、君が開けられないっていうから。じゃあ僕が開ければいいかなって」
当然のように答える彼。罪悪感というものはないらしい。彼はにこにこと暗い部屋の中を見回して、しかし家具すらない部屋は数秒で見飽きたようですぐ私に視線を戻し唇を尖らせた。
「なんでこう、乙女の部屋なのに防犯対策ガバガバなのかなぁ。もっと南京錠を付けるなり何なりして欲しくない?」
「いえ、誰も私を気味悪がってここになんて侵入しようとはしないので不要かと」
「勿体ないねぇ、こんなに面白い子なのに」
「……初めて言われました、そんなこと」
「嬉しい?」
無駄にきらきらとした瞳が五センチの距離まで接近してきて私は仰け反る。それこそ猫であれば毛を逆立てて威嚇をしていただろう。今まで不気味だの、詐欺師だの、散々言われてきたが面白いという感想は初めてだった。言われて悪い気はしないが、何だか肯定するのも違う気がする。戸惑いながら私は引きつる頬を無理やり作り笑顔に変える。
「嬉しい……です」
君は私の態度にふぅんと値踏みするような目で見つめてくる。先ほどの潤んだ宝石の瞳は何処へ行ったのやら。ころころと変わる表情に私はついていけない。
「早速だけど質問、いい?」
「あ、はい」
「神に捧げる少女っていつもは何してるの?」
私は少し迷った後、後で巫女に怒られない程度にふんわりと伝える。
「特に何もしておりません。私の仕事は17歳の奉納祭の日に神様に捧げられるのみなので」
「そうなんだね、なんかもっとしているのかと思っていたけど」
「いえいえ、この狭い小屋の中では本を嗜んだり来客をおもてなしする以外の娯楽はないのですよ」
「それは……辛かったね。ごめんね、しんどいことを話させちゃって」
「いえいえ、一度話すと決めたのは私なのでどんな質問でも大丈夫ですよ」
質問は本当にどんなものでも大丈夫だった。17年間神に捧げる少女と言う奇妙な傀儡をさせられてきた私にとって、この手の質問はざらにある。むしろだいぶ甘い方だ。世の中の物好きはもっと際どいことを聞いてくる。それに比べればオーバーリアクションで、単純な質問ばかりの彼は答えやすいほうだろう。
しかし、この人間が大丈夫ではない。
改めて目の前の彼をじっと見つめた。
人当たりのよい笑顔、自然に振り分けられた艶のある髪、毛穴の見えない頬と、切れ長の瞳の奥にある黒曜石のような瞳。
全世界の人間から最も美しいパーツを集めて張り付けたような顔だった。
それだけでも信じられないというのに、顔の良さを自覚したような自信に満ち溢れたオーラで溢れている。鼻につかないのは常に謙虚な言動を心掛けているからだろう。
世間知らずな私にも分かる、この男只者ではない。
「どうしてここの神社では神に捧げる少女が必要なの?」
「それは、村の作物の豊作を願うためです。この土地は海にも近く、山もすぐ傍にあって自然豊かなのが一つの特徴なのですが、如何せん昔から自然災害が多くてですね。こうやって神に捧げる少女を土地神様に100年に一度納めなければならないといけないそうです」
「へぇ、神に捧げる少女になる基準とかは?」
「……親族がいない、もしくは不明な孤児です。あと、未婚の少女なのも条件です」
なるべく落ち着いたトーンで聞きやすいように答える。彼は常時頷きを欠かさず、表情を変えながら真剣に話を聞いてメモを取った。私が話せるのはこのくらいだと一息つくと、つむじに突然ぬくもりが伝わった。驚いて視線を上に向けると、穢れのない白魚のような手が私の頭の伸ばされていた。綺麗な顔がすっと近づいてきてそっと耳打ちをする。
「協力してくれてありがとうね」
全身に鳥肌が立った。顔に出なかっただけまだ頑張った方だと思う、思いたい。ぴくぴくと痙攣しかける表情筋は限界だと文句を言っている。なんだこの男、何がしたいんだ。今まで様々な人と出会ってきた、やたら自分語りをしたがるおばさん、「それだから若い者は……」と主語のでかい愚痴を零す記者、変なカルト集団からやってきた話の通じない男。
どんな人でも全て完璧に対応し捌ききってきた歴戦の戦士ともいえる私にとってみても、彼の存在は『異常』そのものだった。
自己愛の高い人なのかと思えば、ふとした瞬間に滲み出る自己嫌悪の感情。
洗練された顔を最大限に活用していながらも、決して自分自身を認めてほしいという気持ちは見られない。
普通の人間であれば、誰しも欲という概念が存在する。誰かに認められたい、褒められたい、相手より優位に立ちたい。そういう汚らしく、ある意味人間らしい感情が彼は欠損しているように見受けられる。
だから私は錯乱状態に陥っていた。
「相島さん」
「透でいいよ!」
「透さん」
「……」
「透くん?」
「まぁ及第点かな。それでどうしたの?」
まただ。全身からその謎のキラキラを出さないでほしい。
私はふと昨日の晩読んだ小説を思い出した。女が顔のいい男に口説かれ口づけをされ駆け落ちをするという話だったような気がする。小説によると女はこのような状況ではときめきを感じて頬を赤らめるそうだが、私は今対極の状態と言っても過言ではない。
真っ青を通り越して血色感の皆無な頬、紫に染まり震える唇。
とてもじゃないけれど、恋なんて感情生まれそうにない。
「貴方のことは教えてくれないんですか」
私はついそんなことを聞いてしまった。得体の知れない人間過ぎて一周回って興味が湧いてきた。それに私だけべらべらと個人情報を渡しておいて、彼のことを何も知れないなんてずるいだろう。彼はよくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに、片目を閉じた。そう自然にやっているが、普通に気障なウインクである。
「僕の名前は相島透で、年齢は二十歳をちょっと過ぎたところ!」
そのちょっとの部分が大事なんだろ、とは突っ込む勇気がなかった。
「職業は俳優とかタレントとか色々。今日はオカルト映画の特集インタビューでこの村に来たんだ。趣味は音楽鑑賞とか映画鑑賞。特技は演技、かな。ファンの人からはよく王子様って言ってもらうよ、へへ恥ずかしいよね」
「王子様、ですか。はは、いいですね」
寸前で出掛かった「盲信者め」という言葉が飛び出さなくて本当によかった。私は取り合えず笑っておく、勿論目は合わせずに。人の感情は何よりも目に最初に現れると思う。今の私が仮にでも俳優の彼と視線を交わせば、観察力の高さですぐに呆れた感情を見抜かれるだろう。
逸らした顔に白い指が滑る。耳の付け根から顎にかけて頬骨をなぞる手つきは絶妙に気色悪い。私は神に捧げる少女だと心の中で何度も唱えて心の中のざわつきを静める。彼が中途半端な美しさであればそのへらへらと笑う顔面を殴って再起不能にさせていたかもしれない。
「それにしてもどうしたのー?急に僕のこと知りたくなったの?」
わざとらしく首を傾げる彼は認めたくないが様になっていた。私は嫋やかな笑みを絶やさずに、それでも不安から震える指先をぎゅっと抑え込んだ。本当のことを言ってしまえば、何かが壊れる。そんな予感がした。まるで禁足地に初めの一歩を踏み出すかのような恐ろしさと漠然とした不安で背中に冷たい汗が流れる。それでも他に言う言葉が見つからなかった。いや、ここで誤魔化せば良かったのだ。そんなことないと、ただの気まぐれだと、当たり障りのないことを言えばよかった。
そんな後悔は私が本心を告げた後に襲った。
「貴方の心が読めないんです」
刹那、彼の表情が固まる。完璧な笑顔はぼろぼろと乾いた粘土のように剥がれ落ちた。大きく見開かれた瞳の奥の、光のない瞳孔が揺れる。肺が急速に萎んで息ができなかった。殺されると、本能的が警告音を鳴らしても私は微動だにできなかった。
そればかりか、畳みかけるように死にかけの喉は言葉を続ける。
「透くん、本当の君はどんな人なんですか」
私は今どんな顔をしているだろう。うまく笑えているだろうか、否そうではないことは分かっていた。表情筋は全て弛緩して、荒い息遣いだけが、鼓膜を揺らす。サバンナの真ん中のガゼルとライオンだった。次、何か行動を起こせばきっと私の命はない。
先ほどまで穏やかな笑みを浮かべていた彼はもういない。
代わりにいるのは、怪しげに光る瞳を冷ややかに細める男だった。目と鼻の先にある口角がぎこちなく持ち上げられ、三日月形に歪んだ。
「知りたい?」
試すような口ぶりで聞く彼。口を開いた瞬間その場の空気が底冷えした。冷淡な声はトーンからしてみても、先ほどの相島透とは別人なのではと思ってしまう。それでも目の前の人物は二人に分かれることなく、輪郭はしっかりと一人分しかない。
私は密かに好奇心を抱いていた。
彼は確かに変な人だ、私が出会ってきた中で一番腹の底が読めない。
だからこそもっと接近してみたいと思った。今まで懐柔できなかった人間はいない私にとって、未だ懐柔できていない彼のことをもっと知りたい欲が、恐怖に打ち勝とうとしていた。
「……はい」
固唾を呑む。喉が生々しく音を立てた。
無表情の男は脱力していた私の手首を強引に掴んで小指を絡ませてきた。
「じゃあ明日も来てあげる」
けたたましい一定の波が鼓膜を貫き、脳で響く。
「っううぅ」
あまりの不快感に飛び起きると、もう光が外から漏れていた。朝だった。蝉は今日も休むことを忘れて鳴いている。私はむくりと起き上がると、掛け布団を畳み始めた。
昨晩の寝苦しさで今晩は寝れないかも……なんて不安は杞憂だったようだ。気が付けば私は意識を手放していたらしい。窓のない部屋は熱を帯びた空気で満たされていた。ふと背中に手を伸ばすと小さい頃のおもらしを彷彿させるほどぐっしょりと汗で濡れていた。
「気持ちが悪い……」
何もかもが上手くいかない朝で顔が歪む。しかし、朝から風呂に行くことなんてきっと許してはもらえないから我慢して手拭いで首筋を拭った。
「あっ!!!本!!!!」
枕の隣には無造作に積まれた心理学の本がある。完全に忘れていた。睡魔に身を委ねすぎたあまり、そのまま熟睡してしまったようだ。がっくりと肩を落としながら部屋の掃除を始める。流石の私も凄い人が来ると知ってしまったので、多少は身構えてしまう。
敷布団のシーツを剥がし、枕のカバーも剥がす。裸になった敷布団を三つ折りにして部屋の隅に追いやる。普段はやらない床のからぶきをすると、赤紫色の染みが所々についた。昨日の客が零したものがまだ残っていたようだ。
いつものルーティーンが終わると、唯一の扉が叩かれる音と共に一人の人影が見えた。
「おはようございます」
背中を九十度に曲げて、こちらに入ってきたのは顔なじみの巫女だった。私に仕える巫女は二人いる。昨日の巫女は年と感性が近いこともあり、比較的仲は良好だった。観察する限り下心もないので、純粋な気持ちで向き合ってくれていると分かる。
しかし、彼女は違った。明らかに私を毛嫌いして、汚らわしいものとして扱う。態度や言葉では表立つことないが、私にとってはとても分かりやすい。何なら私だけに伝わるよう意識してやっているのではという節まである。
「お嬢様、本日のお加減はいかがでしょうか」
まるで機械のように、淡々と台本を読むように、巫女は問う。私が調子が良かろうが悪かろうが本当はどうでも良いのだろう。ひんやりとした声音に私は本心を覆い隠す完璧な笑みを浮かべる。
「今日も今日とて蒸し暑いですね。風も入ってこないので参ってしまいます。……障子をあけてもよろしいでしょうか」
「えぇ、ただお嬢様はそこに。私が開けます」
目の前に翳される手。立ち上がろうとする私を制してきびきびとした動きで木枠に手を掛ける。
私が障子を開けることを禁じられているのは、万が一ここから逃げ出したら困るからだろう。
『神に捧げる少女』
建前では崇められる綺麗な言葉であるが、実態はそうでもない。
100年に一度、『神に捧げる少女』に選ばれた娘は17歳の夏、奉納祭にて神に捧げられる。神に捧げると言えば聞こえがいいが、事実は腹を切って死ぬことを指す。
そして『神に捧げる少女』は奉納祭までこの小屋から出ることを許されてはいない。かつて、奉納祭前夜に夜逃げを実行しようとした前例があることから祭りの日まで外出することは禁じられることになったらしい。
心拍数が早まる胸をそっと撫でる。ドクドクと妙に生々しい鼓動が掌に伝わった。
私は不安になるとよく胸に手を当てて自分の心臓が動いているかどうかを確認する。
鼓動が確認できると、今度は少し下に手を滑らせる。
そうすると丁度子宮の辺り、硬いものとジグザクに縫われた皮膚が当たるのだ。
私の爆弾。私だけの爆弾。
10年前に埋められた傷跡が、無理やり隠すように残されていた。
この爆弾は私が小屋を出ると爆発するようになっている。
小さい頃はただの脅し文句だと思っていたが、巫女が言うには本当に爆発するようだ。
50キロ近い体が、それは花火のように粉々と、鮮やかに、一瞬で爆ぜる。
震える指を抑え込むために腕を掴んだ。しかし掴んだそれもハイノキの枝のよう細く、力を込めればぐにゃりと曲がってしまいそうだった。いつも客と対峙しているときの自信は何処へやら。自分のことを考えると途端に意気消沈してしまう。顔を洗うための水が張られた桶には情けない顔の自分が反射していた。私はこんな体でも生きながらえているんだ、と思った。
顔を上げると巫女と目が合う。絹に似た髪を一つに括って靡かせる彼女は、世間と私の感性が一致すればきっと美人の部類に入るのだと思う。私はその顔をじっと観察した。
爆弾の詰められた他は空っぽの少女は、どれだけ心が読めようが誰にも生きることを願われていない。誰からも生きてほしいと思われていないのに、世界で私だけが私に生きてほしいと思ってしまうのは薄汚い人間の証拠だ。
「姫様、今日は大人しいですね。いつもは何やら怪しい本を読んでぶつぶつ呟いているのに。それが習慣となればいずれ客の前でも襤褸を出しますよ」
急に声が頭上から降り注いできて、私は肩を震わせた。視線を上げると巫女が不思議そうにのぞき込んでいる。考えこんでいたのが、大人しいと捉えられたみたいだ。
「ふふふ、私はもう十七ですよ。そんな粗相はしませんよ」
襖が開け放たれた長方形の木枠は、窮屈な部屋に光をもたらした。と言っても、広がるのは小屋の前の雑木林だけなのだが。襖という障壁がなくなった途端に今がその時だと言わんばかりに蝉が一斉に鳴きだす。
季節は夏なのだ。
もう、とっくに17歳の夏なのだ。
それなのに、どうして私は17年間もこの狭い6畳半の小屋に一人閉じ込められているのだろう。
「神に捧げる少女だなんて……」
馬鹿馬鹿しい
喉までせり上がった言葉を飲み下す。危ない、私はあくまでも純粋無垢な神に捧げる少女なのだから、自分自身が何故ここにいるのかなんて疑問に思ってはいけない。幸いにも呟きは蝉の求婚にかき消され巫女の耳には届いていないようで、私は生まれて初めて耳障りな蝉を好きになりかけた。
「お嬢様。朝食はどういたしましょう」
巫女が手についた埃を親指と人差し指で擦り合わせながら問いかける。姫様、なんて恭しい呼び方に全くそぐわない態度に思わず笑ってしまいそうになる。結局彼女の目に映る私はその程度のただの小汚い少女なのだ。
「いつもと同じでいいですよ。どうして改めてそんなこと聞くの?」
彼女は微塵も心配していなさそうな声で答える。
「もうすぐ奉納祭なので。主から姫様の好きなものを召し上がればよいと承りました」
なら初めからそう言えばいいじゃないか。飛び出しそうになった言葉をぐっと堪えて「それは嬉しいわ」と綻んでみせる。
互いに仮初のこの空間に吐き気がする。
私は貴方が嫌い、貴方も私が厄介。
それで話が済めばどれほど楽だろう。
それでも私を捨てられないのは、村人の反感を買うのが怖いのか、神に見捨てられるのが怖いのか、神社の収入源が無くなるのは困るからか。
何にせよ、私は傀儡だと思ってくれた構わなかった。私は生かされている、生かされている間は「神に捧げる少女」なのだ。
いい感情しか持つことしか許されていない、純粋な少女なのだ。
むしろこの場での正解は彼女みたいな対応なのかもしれない。変に情が入ると、自分の身まで亡ぼすことになる。私を逃がす手助けなんてしたら連帯責任でここの巫女は全員殺されるだろう。そんな馬鹿なことを彼女たちがするようには思えない。
諦めの表情で「では、だし粥に梅干を添えたものを」と答えようとしたとき、緊迫した空気を切り裂くほどの大きな声量が小屋を貫いた。
「姫さまああああ!」
私を呼ぶのは先ほどの粘っこい声ではなく、鈴を鳴らしたような愛らしい声だった。声の在処を探すようにきょろきょろと首を動かすと、乱れた足音が近づいてくる。まさかと思い若干引きながら窓の方を見つめると、予想通り昨日会った巫女が鬼の顔で迫ってきていた。この急斜面の山を駆け上がってきているのか、なんと恐ろしい女なんだ。
勾配20%を超える激坂を普通の道と同じスピードで走る彼女はさながら猪である。
「何あの子……」
流石の嫌味巫女もドン引きしたようで、無意識に顔を引きつらせていた。
「何かとんでもなく急ぎの用事があるのでしょうか」
「それは私にも聞いてみないと分かりません」
呆れたように巫女が首を左右に揺らすのと同時に、息を切らした巫女が飛び込んでくる。とんでもなく急いで来たのか、袴の裾は粘土だらけで頭頂部には葉っぱが刺さっていた。年上巫女が汚いとばかりに顔を顰めるが、そんなのお構いなしで年下巫女は必死な形相で声を荒げる。
「い、います!!相島透っ」
「へ?」
「だから、もういらっしゃっています!!相島透さんが」
「それは貴方の見間違えではないですよね。いくらなんでも早すぎますよ、約束の時間より3時間も前倒しだなんて」
「見間違えるわけないじゃないですか!だってあんな天女みたいなお方そうそういませんよ。あれ、本当に野郎ですか?」
「野郎なんて汚い言葉使わないでください!仮にでもお嬢様付の巫女なのですよ」
「仮にでもって、姉さんが言えることじゃないでしょ……」
おいおいそれが昨日私に言葉遣いを指摘した人間の言う言葉なのか。このままでは突っ込みの大渋滞が起きてしまう。私は混乱する現場を何とか整理しようとした。
「まぁまぁ喧嘩はよしてください。それと私も確認するけれど本当に相島透さんで間違いないのですね?」
「はい、お嬢様もあってみれば分かります。驚いてひっくり返らないでくださいね」
私はもう朝食をとることが出来ないまま、寝起きで扑克に挑まなければいけないのか。ふらふらと千鳥足で今日の着物を取った。瞼を重く落としたまま直立していると、巫女が帯を締めてくれる。
「待ってください、そんな約束の時間を守らない方、お嬢様と会わせられません」
片手でウエストを容赦なく締め上げながら年上巫女は厳格な態度で言う。危うく胃酸が逆流しそうになったが、そこは乙女の意地で何とか持ちこたえる。
年下巫女は体の左半分を小屋に、右半分を外に出しながら言い訳を述べる。全く、忙しない人だ。
「そうは言っても……ってあ!!駄目ですよぉ、ここまでいらっしゃったんですか、えぇ時間がない?次の予定があるにしろお嬢様優先ではないですか……ってグチグチ口答えするな?はぁ分かりましたよ……」
大丈夫なのか、何か言いくるめられていないか。何だか外が賑やかになってきて私はそわそわとしてしまう。慌てていつもの皮張りの椅子に腰掛けると、背筋を伸ばして客人を待った。ひと悶着あった後、年下巫女に加えて年上巫女も参戦した口論は決着がついたらしい。年下巫女が申し訳なさそうに手で小さく罰を作った。私が展開に追いつく暇もなく、年下巫女は作り笑いで扉を開け放つ。
「それではお待ちかね!相島透さんのとーじょーです!」
心の準備が整わない中、光と共に人影が入ってきた。しかし、外の太陽光が明るすぎて逆光になっている。顔はよく見えないが上背がとても高かった。巫女が余裕をもって入れる扉を、頭を下げてくぐる仕草が見えて私は目を疑った。
「急に来てしまって申し訳ないです」
なんと声もよかった。私は感嘆の声を漏らす。
流石俳優と言うだけある。一人の人間に対して五人もの男や女が仰々しく連なっていた。その中心で腰を折るのは頭一つ飛びぬけたシルエットであった。随分楽な格好をしている、だぼっとした着こなしなのにどうしてこうも体のバランスが良く見えるのだろう。私は間抜けな顔で彼の一挙手一投足に集中した。
「こんにちは、お嬢様」
ようやく光が落ち着いて、彼の顔が鮮明になる。
にこりと上がった口角。一目見た瞬間、世が世であったら国が傾いていただろうと思った。涼し気な切れ長の目元に、薄い唇と、すっと通った主張の少ない鼻梁。男性のわりに透明感のある肌はそのまま後ろの背景を透かしてしまいそうだ。
「ぇ……」
情報量が多すぎる。私の頭は意味のない言葉が口から漏れてしまうほど、故障寸前だった。きっと彼の美しさを文字に書きだせばきりがないだろう。たじろぐ私に悪い笑みを浮かべて距離を詰める男。私は思わず身を縮こませそうになったが、何とか神に捧げる少女としての理性が繋ぎとめる。
「どうしたの?」
試すような表情、きっと彼は私が見とれているのだと勘違いしている。でなければ、たった五文字をそんなに意気揚々と発音できないのだ。
生憎、私は彼の顔面に驚いてはいるが、性的衝動は感じていなかった。
神に捧げる少女は今まであらゆる人間と対峙してきた。その経験から段々と人にそういう感情を抱かなくなってしまったのだ。
少女は人の心理状態を察することができる。その過程で、善人を探そうとふるいに掛けると驚くことに誰も残らない。出会ってきた人間が特殊なだけかもしれないが、私にとっては経験が世界のすべてだった。結果、人に対する期待や恋心の類を忘れてしまった現在の少女が完成したのだった。
「笑いかけないで貰ってもよろしいでしょうか」
私の腰の低い態度に、何を勘違いしたのか目の前の男は更に蕩けるような笑みを浮かべる。
「ふふ、我慢しなくていいんだよ」
「そうじゃなくて……巫女が倒れます」
突如、何やら重いものが倒れる音がして私は苦笑いを張り付けながら振り返る。
案の定、巫女が鼻血を垂れ流しながらぴくぴくと打ち上げられた魚のように痙攣していた。
私の言わんこっちゃないという表情に、君はただ驚く表情を浮かべて立ち尽くしていた。
「仕切り直して本日はよろしくお願い致します。神に捧げる少女です」
「相島透です!今日はよろしくね。君とポーカーできるの楽しみにしてたんだよ!」
「私も同じ気持ちです」
社交辞令を適当に言ってのけると、机の横で慎ましやかに立っている巫女に目配せをする。ちなみに年下巫女は鼻にちり紙を詰めて小屋の裏で待機することになった。年上巫女が「夏炉冬扇だわ」とぼやいていたのは僅かな良心から伝えないことにする。早速巫女が札を混ぜ、振り分ける。私も手元を見たが悪くない数字だった。これは余裕で勝てるだろう。
しかし、正面の男を見ていると拭えない違和感があった。何だろう、別におかしいところはない。いや、現実離れした顔はさておき言動、動作、息遣い、どれも嘘を吐いているようには見えず落ち着いていた。
「落ち着いて……?」
それが一番おかしいのか。私はようやく腑に落ちた。
「どうかしたの?早く次の手を」
「あっ、はい。すみません」
私は慌てて手札を見た。しかし、あまり集中はできない。彼は落ち着きすぎている。普通なら金を掛けていようが掛けていまいが、真剣勝負の賭け事となれば多少の緊張と高揚で汗ばんだり脈が速くなったりする。彼にはその兆候が一切見られなかった。まるで眠っているかのように、穏やかで乱れが一切ない。
それが完璧の域にまで達しようとしているので余計に怖い。
彼の様子を観察していると、私如きに神の使いというのは間違いだと思った。これは後天的に身につけたものだ。彼はどうだろう、私の見解では生まれつきのように見える。仮に後天的に身に着けたものだとすれば一体どれだけの努力と時間を要したのだろう。
彼こそ本当に天の使いかと勘違いしてしまいそうだ。
手元から視線を外して、正面を見る。口角のあがった表情はまだ余裕があるように見えた。
負けられない。私は気持ちを切り替えるために深呼吸をする。遅い瞬きを一度、まるでスイッチが押されたかのように世界が変わる。五感全てが研ぎ澄まされた今、負ける気はしない。
「ふふ、余裕ぶっていられるのも今のうちかもしれませんよ」
「お、よーやく本気出す気になったんだね!」
勝負は一時間半も掛かった。
ほぼ互角の勝負では接戦の末、神に捧げる少女の勝利であった。
しかし、私は結果に釈然としなかった。
神に捧げる少女にとってはお見通しだった、相島透にはまだ余力があったことが。
八百長で勝ってしまったことにどうしても納得がいかない。負けた時でさえ、彼は騙されてしまいそうなほど精巧な演技をしていた。
私は彼が考えていることがさっぱり理解できなかった。
取材班が帰ってから、よく分からない薬を巫女から手渡された。飲み込んだ瞬間、脳みそがとろとろと溶けてしまったのかと錯覚するほどの強い眠気に襲われて少し眠った。
夢の中で、何故か相島透が出てきた。私は彼の真正面に立って彼の顔を見つめる。私は今日彼の笑顔しか見ていないはずなのに、夢の中では洞窟のように暗い瞳が虚ろにこちらを見つめていた。
彼には感情が何もないように見える。
私とおんなじ、空っぽ。
衝動的に手を伸ばすと、目の前にいたのはペインターパンツの男ではなく、今にも落ちてきそうな天井だった。
体がだるくて視線だけを動かすと、締め切った障子の僅かな隙間から月明かりが夏風と共に差し込んでいる。
「あ、もう……夜かぁ」
一人しかいない部屋で、はぁとでかいため息を吐いた。
「どうしたの、ため息なんて吐いちゃって」
突然、薄い壁一枚の向こう側から声がして飛び起きた。巫女か?違う、女の人の声じゃなかった。じゃあ一体誰。今まで物珍しさで小屋の付近に訪れる人はいるが、誰も私を気味悪がって話しかけようとしてこなかった。
思い当たる節もないし、相当な変人が来たか。私は眉を顰めながら壁を叩いた。
「あの、誰かいますか……」
「いませんよー」
「ほら、やっぱりいるじゃないですか!!」
私が反応すると、外から笑いを堪えるような声がした。
「誰か当ててみてよ」
問いかける声音は水あめのように甘い。しかし、声量を抑えているからか時々低く掠れて、忘れかけていた声の持ち主が男性だということを意識させる。どうしよう、このまま彼が喋り続けたら心地よくてまた寝てしまいそうだ。意識が飛ばないように私は今までの記憶から男性の声を引っ張り出す。と言っても人生でこんなに透明感のある声、今日以外に聞いたことはない。
「え……まさか、相島透さん?」
「おお、正解」
相当驚いたのか声が震えていた。
「よく分かったね」
「吃驚するのはこちらですよ。どうしてここに?」
相島透は相当有名で多忙な人物だというのを知った今日、どうして彼がこんな辺鄙な神社の小屋に訪れたのか真意が分からない。大体マスメディアの取材に来る人は、表向きには興味があるように熱心に話を聞きに来るが、私がただの少女だと分かると途端に興味を無くしてどこかに行って二度と帰ってこないではないか。
私はとりあえず声のする方へ移動した。壁を軽く叩くと右から軽い音が返ってくる。私は右に移動してまた壁を叩く。今度はちゃんと正面から音がした。
「ここにいるの?」
確かめるように爪が木の柱を撫でる音がする。相手からは見えないというのに反射的に首を縦に振ると、突然、眩しい光が差して目を細めた。暫くして眩しさにも慣れてきた私は恐る恐る顔を上げる。二重の輪が重なり合う形は、よく巫女が夜の巡回に来る時に障子から見える形とよく似ていた。
「懐中電灯ですか?」
「いや、スマホのライト機能だけど」
光源の正体は和紙に透けた懐中電灯ではないのか。私は聞きなれない単語に首を傾げる。
「恐れながら、すまほって何ですか?新しい懐中電灯の種類ですか?」
「スマホ、知らない?携帯電話。ガラケーとかなら分かる?」
彼が軽々と口にする単語を繰り返そうと試みるが、すぐ口の中でへばりついた。知らない単語の波が押し寄せて私の頭は爆発寸前だ。なんだ、すまほって。『けいたいでんわ』も分からなければ、がら何とかもよく分からない。返事に困って緘黙を続けると、「ねぇ」と外から甘い声がする。
「障子、開けてよー。僕、君と会って話してみたいんだよね」
「何故?」
「昼間見て、めっちゃ可愛かったからー」
「お世辞は結構です」
「って理由が半分と、半分は今度のオカルト映画の勉強のため」
「んぐっ……騙されました」
「ほら、そういうところが可愛いんだよ」
「……お口が達者なことで」
私はそのすらすらと流れる口説き文句に一種の感心を抱きながらも、障子に触れることはできなかった。昔からそうだ、障子まで近づいて開ける寸前まではできるのに、どうしてもその先をしようとすると腕に力が入らなくなる。死にたくないから、朝の言葉を思い出した。別に障子を開けたところでここから逃げなければ爆弾は起動しないのに、私は死の池に飛び込むことは愚か石を投げ入れることすら怖いみたいだ。
そこまで生に縋りついたところで私には何もないのに。
醜い、醜い、醜い
自分のことが嫌いで嫌いで、今すぐ畳の上でのたうち回って絶叫したくなる。爪の奥に血が溜まるまで腕を掻きむしって、こんな自分消してしまいたくなる。
それでも正座の姿勢は崩せなかった。深呼吸をして乱れた精神を統一する。
私は『神に捧げる子』だから、こんなところで襤褸を出すことは許されない。
例え誰であろうと、一回きりの仲であろうと、人前に出るときの私は純粋無垢で清廉潔白な相応しい女を演じなくてはいけない。
私は微笑みを浮かべると、申し訳ない気持ちを前面に出して答える。
「映画の勉強は感心しますし、協力したいと思います。けれど、私は障子を開けることはできません」
「どうして」
「開けてはいけないと言いつけられているからです」
私がきっぱり答えると、彼は数秒の沈黙の後ケラケラと笑いだす。私は何故彼が笑うのか分からず、戸惑いながら「何か変なこと言ってしまいましたか?」と聞く。すると壁の向こうから衣擦れの音が聞こえ、彼が首を振っていることが分かった。
「いやいや、真面目だなぁと思って」
「……馬鹿にしてますか?」
「そんな!むしろ感心してるんだよ。君、反抗期とかなさそうだね」
「反抗なんて、出来ませんよ」
笑ったはずなのに、口角が痙攣して上手く笑えなかった。よかった、顔合わせしなくて。和紙一枚に守られた私の威厳にほっと息を吐く。
彼は何か勘違いしている。私は聖人君子なんかじゃない。反抗したところで、弱くて未熟で未来なんて何も変わりやしないから反抗しないのだ。
腹に手を当てて、風化しかけている傷口を掻きむしった。乱暴にしたせいで中にある硬いものが腹膜を刺激し、激痛が襲う。かはっと少量の胃液と共に私は畳の上に倒れこみ、酸素を貪った。
駄目だ、立ち上がれ。まるで呪いのように脳内で何度も繰り返される言葉に、反射的に足に力が入る。よろけながらも何とか立ち上がると私は腰を90度に曲げた。
彼は知らない。
17年前、神に捧げる少女となった日から私の内臓は爆弾に支配され、静かなる魔物が腹の中を牛耳っているということを。
「……申し訳ないのですが、お帰りいただけますか。先ほども申し上げた通り、私にそこを開ける権利はございませんので」
お帰り頂けますかと言ったのは私なのに、口の中が乾燥している。擦り合わせる手汗が止まらない。私が拒絶すればこれ以上、彼が踏み込んでくることはないのに。落ち着けと言い聞かせていることに対して反比例するように荒くなっていく息に、頭は混乱していた。こめかみに冷や汗が流れる。それを拭いながら、気づく。
私、怖いのか。
だって、彼は、
「じゃあ僕が開ければいいか」
カラカラカラ
夜の静寂に響く木材。
ひっ、と喉の奥から引きつる音がした。
「おっ、開いた」
彼は、変な人だから。
「ビックリしすぎじゃない?あ、これ不法侵入とかで訴えられないよねぇ?」
あ、や、と意味のない言葉が飛び出す。
「じゃじゃーん。本日二度目の相島透です!って言ってもテレビないもんなぁ。興味ないか、僕のこと」
「やっ、なんであああけたんですか!!」
「何でって、君が開けられないっていうから。じゃあ僕が開ければいいかなって」
当然のように答える彼。罪悪感というものはないらしい。彼はにこにこと暗い部屋の中を見回して、しかし家具すらない部屋は数秒で見飽きたようですぐ私に視線を戻し唇を尖らせた。
「なんでこう、乙女の部屋なのに防犯対策ガバガバなのかなぁ。もっと南京錠を付けるなり何なりして欲しくない?」
「いえ、誰も私を気味悪がってここになんて侵入しようとはしないので不要かと」
「勿体ないねぇ、こんなに面白い子なのに」
「……初めて言われました、そんなこと」
「嬉しい?」
無駄にきらきらとした瞳が五センチの距離まで接近してきて私は仰け反る。それこそ猫であれば毛を逆立てて威嚇をしていただろう。今まで不気味だの、詐欺師だの、散々言われてきたが面白いという感想は初めてだった。言われて悪い気はしないが、何だか肯定するのも違う気がする。戸惑いながら私は引きつる頬を無理やり作り笑顔に変える。
「嬉しい……です」
君は私の態度にふぅんと値踏みするような目で見つめてくる。先ほどの潤んだ宝石の瞳は何処へ行ったのやら。ころころと変わる表情に私はついていけない。
「早速だけど質問、いい?」
「あ、はい」
「神に捧げる少女っていつもは何してるの?」
私は少し迷った後、後で巫女に怒られない程度にふんわりと伝える。
「特に何もしておりません。私の仕事は17歳の奉納祭の日に神様に捧げられるのみなので」
「そうなんだね、なんかもっとしているのかと思っていたけど」
「いえいえ、この狭い小屋の中では本を嗜んだり来客をおもてなしする以外の娯楽はないのですよ」
「それは……辛かったね。ごめんね、しんどいことを話させちゃって」
「いえいえ、一度話すと決めたのは私なのでどんな質問でも大丈夫ですよ」
質問は本当にどんなものでも大丈夫だった。17年間神に捧げる少女と言う奇妙な傀儡をさせられてきた私にとって、この手の質問はざらにある。むしろだいぶ甘い方だ。世の中の物好きはもっと際どいことを聞いてくる。それに比べればオーバーリアクションで、単純な質問ばかりの彼は答えやすいほうだろう。
しかし、この人間が大丈夫ではない。
改めて目の前の彼をじっと見つめた。
人当たりのよい笑顔、自然に振り分けられた艶のある髪、毛穴の見えない頬と、切れ長の瞳の奥にある黒曜石のような瞳。
全世界の人間から最も美しいパーツを集めて張り付けたような顔だった。
それだけでも信じられないというのに、顔の良さを自覚したような自信に満ち溢れたオーラで溢れている。鼻につかないのは常に謙虚な言動を心掛けているからだろう。
世間知らずな私にも分かる、この男只者ではない。
「どうしてここの神社では神に捧げる少女が必要なの?」
「それは、村の作物の豊作を願うためです。この土地は海にも近く、山もすぐ傍にあって自然豊かなのが一つの特徴なのですが、如何せん昔から自然災害が多くてですね。こうやって神に捧げる少女を土地神様に100年に一度納めなければならないといけないそうです」
「へぇ、神に捧げる少女になる基準とかは?」
「……親族がいない、もしくは不明な孤児です。あと、未婚の少女なのも条件です」
なるべく落ち着いたトーンで聞きやすいように答える。彼は常時頷きを欠かさず、表情を変えながら真剣に話を聞いてメモを取った。私が話せるのはこのくらいだと一息つくと、つむじに突然ぬくもりが伝わった。驚いて視線を上に向けると、穢れのない白魚のような手が私の頭の伸ばされていた。綺麗な顔がすっと近づいてきてそっと耳打ちをする。
「協力してくれてありがとうね」
全身に鳥肌が立った。顔に出なかっただけまだ頑張った方だと思う、思いたい。ぴくぴくと痙攣しかける表情筋は限界だと文句を言っている。なんだこの男、何がしたいんだ。今まで様々な人と出会ってきた、やたら自分語りをしたがるおばさん、「それだから若い者は……」と主語のでかい愚痴を零す記者、変なカルト集団からやってきた話の通じない男。
どんな人でも全て完璧に対応し捌ききってきた歴戦の戦士ともいえる私にとってみても、彼の存在は『異常』そのものだった。
自己愛の高い人なのかと思えば、ふとした瞬間に滲み出る自己嫌悪の感情。
洗練された顔を最大限に活用していながらも、決して自分自身を認めてほしいという気持ちは見られない。
普通の人間であれば、誰しも欲という概念が存在する。誰かに認められたい、褒められたい、相手より優位に立ちたい。そういう汚らしく、ある意味人間らしい感情が彼は欠損しているように見受けられる。
だから私は錯乱状態に陥っていた。
「相島さん」
「透でいいよ!」
「透さん」
「……」
「透くん?」
「まぁ及第点かな。それでどうしたの?」
まただ。全身からその謎のキラキラを出さないでほしい。
私はふと昨日の晩読んだ小説を思い出した。女が顔のいい男に口説かれ口づけをされ駆け落ちをするという話だったような気がする。小説によると女はこのような状況ではときめきを感じて頬を赤らめるそうだが、私は今対極の状態と言っても過言ではない。
真っ青を通り越して血色感の皆無な頬、紫に染まり震える唇。
とてもじゃないけれど、恋なんて感情生まれそうにない。
「貴方のことは教えてくれないんですか」
私はついそんなことを聞いてしまった。得体の知れない人間過ぎて一周回って興味が湧いてきた。それに私だけべらべらと個人情報を渡しておいて、彼のことを何も知れないなんてずるいだろう。彼はよくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに、片目を閉じた。そう自然にやっているが、普通に気障なウインクである。
「僕の名前は相島透で、年齢は二十歳をちょっと過ぎたところ!」
そのちょっとの部分が大事なんだろ、とは突っ込む勇気がなかった。
「職業は俳優とかタレントとか色々。今日はオカルト映画の特集インタビューでこの村に来たんだ。趣味は音楽鑑賞とか映画鑑賞。特技は演技、かな。ファンの人からはよく王子様って言ってもらうよ、へへ恥ずかしいよね」
「王子様、ですか。はは、いいですね」
寸前で出掛かった「盲信者め」という言葉が飛び出さなくて本当によかった。私は取り合えず笑っておく、勿論目は合わせずに。人の感情は何よりも目に最初に現れると思う。今の私が仮にでも俳優の彼と視線を交わせば、観察力の高さですぐに呆れた感情を見抜かれるだろう。
逸らした顔に白い指が滑る。耳の付け根から顎にかけて頬骨をなぞる手つきは絶妙に気色悪い。私は神に捧げる少女だと心の中で何度も唱えて心の中のざわつきを静める。彼が中途半端な美しさであればそのへらへらと笑う顔面を殴って再起不能にさせていたかもしれない。
「それにしてもどうしたのー?急に僕のこと知りたくなったの?」
わざとらしく首を傾げる彼は認めたくないが様になっていた。私は嫋やかな笑みを絶やさずに、それでも不安から震える指先をぎゅっと抑え込んだ。本当のことを言ってしまえば、何かが壊れる。そんな予感がした。まるで禁足地に初めの一歩を踏み出すかのような恐ろしさと漠然とした不安で背中に冷たい汗が流れる。それでも他に言う言葉が見つからなかった。いや、ここで誤魔化せば良かったのだ。そんなことないと、ただの気まぐれだと、当たり障りのないことを言えばよかった。
そんな後悔は私が本心を告げた後に襲った。
「貴方の心が読めないんです」
刹那、彼の表情が固まる。完璧な笑顔はぼろぼろと乾いた粘土のように剥がれ落ちた。大きく見開かれた瞳の奥の、光のない瞳孔が揺れる。肺が急速に萎んで息ができなかった。殺されると、本能的が警告音を鳴らしても私は微動だにできなかった。
そればかりか、畳みかけるように死にかけの喉は言葉を続ける。
「透くん、本当の君はどんな人なんですか」
私は今どんな顔をしているだろう。うまく笑えているだろうか、否そうではないことは分かっていた。表情筋は全て弛緩して、荒い息遣いだけが、鼓膜を揺らす。サバンナの真ん中のガゼルとライオンだった。次、何か行動を起こせばきっと私の命はない。
先ほどまで穏やかな笑みを浮かべていた彼はもういない。
代わりにいるのは、怪しげに光る瞳を冷ややかに細める男だった。目と鼻の先にある口角がぎこちなく持ち上げられ、三日月形に歪んだ。
「知りたい?」
試すような口ぶりで聞く彼。口を開いた瞬間その場の空気が底冷えした。冷淡な声はトーンからしてみても、先ほどの相島透とは別人なのではと思ってしまう。それでも目の前の人物は二人に分かれることなく、輪郭はしっかりと一人分しかない。
私は密かに好奇心を抱いていた。
彼は確かに変な人だ、私が出会ってきた中で一番腹の底が読めない。
だからこそもっと接近してみたいと思った。今まで懐柔できなかった人間はいない私にとって、未だ懐柔できていない彼のことをもっと知りたい欲が、恐怖に打ち勝とうとしていた。
「……はい」
固唾を呑む。喉が生々しく音を立てた。
無表情の男は脱力していた私の手首を強引に掴んで小指を絡ませてきた。
「じゃあ明日も来てあげる」