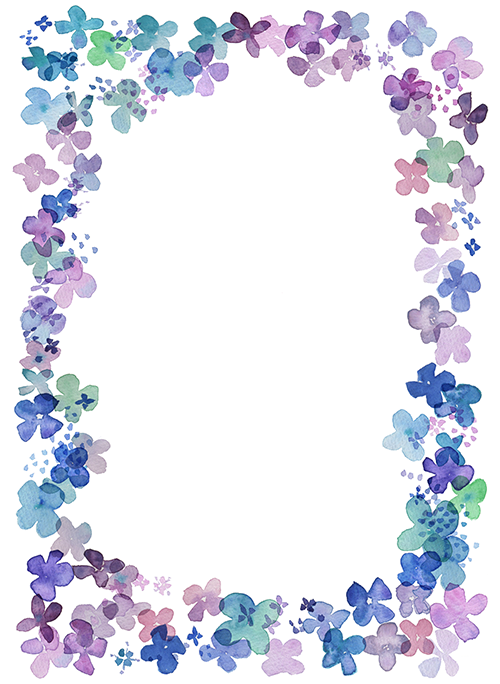海岸線を目指して丘を下ると、そこは偶然にも最期にボタンが爆ぜた場所だった。
「ここって」
横持が何か言いかけたあと、珍しく動揺しながら俺の方を見る。マスメディアに報道されまくったせいで、ここはほぼ聖地化していた。立ち入り禁止線の周りには、弔う気持ちもない癖に律儀に花が添えられている。俺は気にしてないことを伝えるために首を振った。
「いいんだ、俺がここに来たいと思ったのは横持に聞きたいことがあったからだから」
「聞きたいことって?」
「神に捧げる少女についてどう思う?」
氷河期に生きていたライオンの死体はまるで眠っているかのように、それは綺麗な状態で現代で発見されたらしい。
彼はまさに氷河期の生き残りだった。
まるで地球に隕石が落ちた瞬間みたいな顔をして、そのまま固まる。
一度呼吸をすれば肺が凍りつく。
そんな空気だった。
一つでも言葉を間違えれば首が吹き飛ぶ。
そんな空気でもあった。
俺は別にどんなことを言われても良かった。でも彼はそこを気にするらしい。その原因が鬼気迫る俺の表情だったら申し訳ない。
彼は暫くの間、沈黙を貫いた後慎重に言葉を選びながら言う。
「俺では公正な判断ができないよ。だって透の背景を全てではなくとも多少なりには知っているから」
横持らしい誰も傷つけない言葉だった。俺はそれに一種の感心を抱きながら、おどけたように言う。
「お前、案外真面目なんだな」
「案外ってなんだよー、オレはいつでも真面目ちゃんなのに」
「前言撤回、そういえば横持は虚言癖なのを忘れてた」
「おいー、オレは誠実ジェントルマンキャラで売ってるのにー」
なんだ誠実ジェントルマンキャラって。俺が苦虫を踏み潰したような顔で彼を見ると、自信満々にこちらを見てきた。しかし、その顔がふっと真顔に戻ると落ち着いたトーンで話し始めた。
「ただ、お前から話を聞くまでは自分勝手な奴だと思ってた。俺はトロッコ問題とかでも5人助かるんだったら1人の犠牲くらいどうってことないと思っちゃう人間だから、村の言い伝えは馬鹿らしいと思ったけど、でもその子が一人犠牲になるだけで村での争いとか心の健康とかが保たれるならそれでいいんじゃない?って考えてた」
改めて彼はできた人間だと思った。普段は冗談交じりの軽快なトークが持ち味の癖に、時に思慮深い冷静な意見も述べることができる。私情に偏ることなくきちんと俯瞰して物事を捉えているので、俺としても忌憚のないそれが有難かった。
俺が真顔でその言葉を受け止めてしまったあまり、彼は俺が傷ついたと誤解をしたらしい。慌てて両手を振って否定する。
「ごめんな、俺はこう考えるけどお前は違うんだよな」
彼はただ一般論を述べただけだ。それなのに俺への心のケアを欠かさない。そういうところが面倒見がいいというか、女性にもてる要因だと思った。ただ相手は俺なのだ。彼の性的対象が俺だったら話は別だが、横持がストレートなのは知っている。もう何年の付き合いになる、そろそろ気を抜いてくれたっていいのにという言葉は恐らく俺が言えることではないだろう。俺は気を使いすぎる彼に俺は何とも言えない顔で首を振る。
「いや横持は正しいよ。普通なら誰だってそう考える」
何が正しいのか、何が間違えなのかは立場によって大きく変わってくる。
そして大抵の場合、背景も知らぬまま流動的に多数派の意見に流されるというのが正しさというのもだ。
ネットで見たことを、真実だと鵜吞みにして。ついたいいねとコメントに踊らされて。「何が正しいのか」より先に、「誰が愚者か」が推測されていく。生きている間もそうだったが、死後も尚、歪んだ正しさが君の周りには蔓延っていた。
更に君の存在は、村の人たちにとっては「よくもやってくれたな、祭事のときにとっとと死ねばよかったのに」であるし、
神社の関係者にとっては「お前のせいで人生滅茶苦茶だ」の一言に尽きるであろう。
世界は一夜にして君を悪者に仕立て上げようとした。
ただ君にとっては違う。
俺と君にだけは違ったんだ。
俺は憂いを帯びた目をすると、唇をゆっくり湿らせる。中々言葉が出てこなかったのは、綺麗に舗装されたコンクリートの堤防が欠けていたからだ。3年前同じ場所で見た苦しそうな顔の君と、口論になって腕を引っ張り合ったときに出来た痕だった。誰かとあれだけの言い合いをしたのは最初で最後だ。
君は俺が今から言うことを許してくれるかい。
これを言ってしまえばきっと世界は全て敵になるんだ。
心の中で語りかける。記憶の片鱗にいる君は首を縦にも横にも振らない。代わりに笑ってみせた。
そうだ、二人で十分だった。二人いれば例え世界は変わらなくても、幸せになる方法は見つけ出すことができたんだ。
だから俺は破顔した。複雑なことは忘れて、気の向くままに笑ってやった。
「ただ、正しさが一つだけだとは思わないんだ」
あの時、結局何が正しかったのかなんて誰にも分かりやしなかった。
傍から見れば彼女が生贄となってこの村の平穏が保たれたと錯覚するのが正しかったのかもしれない。俺は彼女と初めから接触するべきではなかったのかもしれない。
けれど、あの時
ボタンがあまりにも屈託なく笑ったから。
俺は間違えてないと思えた。
曲がりなりにも見つけた自分なりの正義を俺は、俺たちはこれからも肯定したいと思えたんだ。
いつだって俺の世界の真ん中ではボタンが大の字になって寝転がっている。狭い小屋で、窮屈な姿勢で閉じこもっている少女なんかじゃない。白地に鮮やかな朝顔を咲かせた浴衣で、一生懸命水鏡と睨めっこしながら結った髪の毛を揺らして、頬を染めて、
何度も何度も、俺から貰った名前を宝物のように舌で丁寧に転がす少女が腹をよじりながら笑っているのだ。
海藻の絡みついたテトラポッドを撫でると、体温のようなあたたかさが伝わる。昼間直射日光を浴びた石が、まだ熱を帯びていた。君と肩を寄せ合って手持ち花火をした夜を思い出す。少し生ぬるい夏の空気と、隣にあったぬくもりがボタンとの思い出を彷彿とさせた。
夕陽が山に吸い込まれて手元さえよく見えなくなる中、灰色の石に一つ黒い染みが浮かび上がった。
「まだ、少しだけ、忘れられないかも……」
忘れようとした、もう蓋をして二度と思い出すものかと思った記憶がじわじわと体を侵食する。
あぜ道を歩いていたときに決壊しそうだった感情が溢れ出す。
忘れたくない、忘れられない。忘れるものか。
君との約束を破ってしまうことになる。遂行したかったのに、君の願いならば全て忘れてしまうことも苦でないと思ったのに、ここに来たいと心が叫んだ。
もうその衝動から俺の心は変わっていたのだろう。
なぁ。
俺、君との日々を思い出すことより、君への想いをなかったことにする方が何百倍もしんどいみたいなんだ。
段々、吐き出す息の量が多くなる。吸い込む酸素が足りない。
苦しいけれど、涙が止まらないくらい貴方が好きだった。
君がいない朝を俺は知りたくなかった。ずっとずっと隣で、そうだ、ただ隣にいるだけでよかった。
君の呼吸が肩から聞こえる朝を、迎えたかった。
「俺は……おれは……おれは……っ」
ボタンの未来を守れなかった。
そう言いかけて、息が足りずに体を折りたたんだ。
瞼が痙攣する。歪んだ視界の中、黒い海の奥で俺は光るものを見つけた。虚空に手を伸ばす。震える指先が涙で滲んで二重に見える。
光を掴んだ瞬間、全身を震わせるほど大きな音が轟く。
掴んだはずの光は遥か彼方まで上昇して散った。
花火だった。
俺の両手からは火花が溢れだした。
「あぁ、そっか……ボタン笑ってたなぁ」
二人でボロボロになりながら逃げだした夏祭りの宵、笑いながら走った。背負い続けた責任を捨てて、出会って3日の俺の手を取ってくれた。
劣等感と自己嫌悪でぐちゃぐちゃだった俺の肩を抱きしめてくれた。
何度も泣いた、お互いの心臓を曝け出すように弱い部分も見せあった。
何度も笑った、泣きたくなるくらいにあたたかい感情は存在するんだと思った。
ボタンと過ごしたすべてが、過去に囚われる枷とではなく、いつまでも忘れたくない一瞬の瞬きとして俺の中で未だに残り続けている。
それがまた、君がいた時には知ることができなかったまた別の形の幸せだった。
『今日の月は綺麗ですね』
ふとボタンが笑いながら言った日を思い出した。軽々しく言ったことが許せなくて、接吻してやると君は突然のことに酷く狼狽えながらも耳を真っ赤にしていて。思い出の中の君があまりに愛おしくて思わずはにかむ。
月を見上げた。今日はひと際大きな月だった。少しオレンジ色の混じったそれは暗い海を淡く照らしていた。LEDよりも白熱電球よりも弱く、けれど柔らかい光に俺は思わず感嘆の息を漏らす。
「月明かりってこんなにも綺麗だったんだな」
小さい頃、仕事帰りに見上げた空が重なる。すれ違う酔っ払い、居酒屋の煙でぼやけた月の輪郭、きつい香水の匂いと媚びるような視線、いつからかそれが当たり前だった。
今、目の前に広がるのは涙で滲む可惜夜だった。一生明けなくてもいい、この月の下をただ真っすぐに歩いていたい、そう願えるほど美しい夜だった。
「……俺の知ってる夜はこんなはずじゃなかったのに」
脚に力が入らなくてがくがくと震わせたあと、情けなく崩れ落ちる。また、熱いものが込み上げてくる。泣かないように必死に唇を嚙みしめるが鼻腔に込み上げる熱に耐えられず、俺は大人げなく嗚咽を漏らした。
なんでいつの間にかこんなにも優しい夜になっていたのだろう。
「ボタンが俺に残してくれたものはこんなにも素敵なものなんだな。本当に立派だよ君は……ほんとうに……本当にさぁ」
君が傍にいなくたって愛すことを辞めることはできなかった。
こんなに美しい世界を遺してくれた貴方を忘れてしまうなんて出来なかった。
人間、愛という見えない概念に囚われがちだけど、愛してはじめて分かることが本当は大切にするべきものなんだろうな。
夜更けの海は漆黒ではないのとか、花火の火薬の匂いとか、笑ったときに右だけ下がりがちな目尻とか、澄んだ空気で見上げる月はこんなにも綺麗なこととか。
きっと君を愛さなければ生きているうちに知らなかったことがこれ以上に沢山沢山あって、君を愛した世界では綺麗なものが溢れていた。
君の世界もそうだったらいいなと思う。
愛した世界で、愛された世界で、愛で照らされるものが一つでも多く君の世界に満ち溢れていたら、俺が君の隣にいたことには意味があったのだと思う。
男泣きする俺に狼狽しながらも、背中にそっと手を添えてくれる友のぬくもりに一気に力が抜ける。
「大丈夫だよ、透」
それだけ言って、後は何も言及せずに背中をさすり続ける横持に俺は甘えた。ボタン、人ってこんなにいい奴もいたんだな。こうやって人の弱みに漬け込むこともせずに黙って隣にいてくれる人だっているんだな。
痙攣する横隔膜に涙と鼻水にまみれた汚い掌。みすぼらしくて滑稽で、こんな姿で人気俳優だなんてとてもじゃないけれど言い切れない。溢れる涙をどうにかして抑えようと目を瞑る。けれど、瞼の裏のその先にいたのは貴方だった。
「ボタン……ボタン……ぼた、ん……」
今も、名前を呼べばあの長い睫毛を震わせて、輝く瞳に沢山の色を蓄えて、「どうしたんですか?」と小首を傾げながら近づいてくる君がすぐ傍にいるような気がする。
俺は、あの時から変わりたいとずっと願ってきた。
周りの人を大切にできない俺は醜い存在だって、だからいつか人を大切にできるようになりたいって。
母さんとは縁を切ったよ。もう会わないと約束して、俺はようやく透明な鎖を断ち切ることができた。
でも人間そう簡単には変われなくて、信じれる人なんて片手で治まるくらいで、そんな俺が俳優なんて職業に就いてていいのかなって何度も疑った。
それでも、大切にしたいと思える人は増えたよ。すぐ傍にいる男に視線をやる。優しい目をした男はその一人だった。
君が歩み寄ることを教えてくれたから、俺は今一人じゃないんだよ。俺とボタンだけだった世界にいつの間にか人が増えていくんだ。
これからもどんどん、どんどん増えていって、いつの間にか孤独だった自分を忘れてしまうくらい人のあたたかさを知るんだ。
「ボタン、君を思い出すだけで俺はこんなにもあったかい気持ちになれるんだ。やっぱり必要なんだ、君にはこれからも俺の真ん中にいてもらわなきゃ、困るんだ」
相島透は情けなくて、不甲斐なくて、臆病で、後悔ばかりの男だ。
それでも君を誰よりも想っていることに変わりはなかった。これからも、変わることはないだろう。
「……愛しているよ」
言葉にしきれない気持ちの一つが溢れて、俺は息を吐いたまま暫く呼吸ができなかった。
たんぽぽが揺れ、陸風が背中を撫でる。涙はもう出なかった。俺は再び足に力を込めて立ち上がる。痙攣していた口角を持ち上げると、不思議と震えは治まった。横持に「大丈夫」と一言告げると、彼はほっとしたように肩の力を抜いた。それからまた元通りの会話をする。今日の宿はどうしよう、予約してなかったのかよ。ありふれた会話をして、沢山笑った。1時間ほど潮風に吹かれた後、俺たちは今日の宿に向かうことにした。海に背を向けて、進もうとした足を止める。俺はゆっくりと振り返った。
目を細めながら小さく手を振る。
きっとまた来るから。また来るときには、君との思い出を笑って話せるようになっているから。どうかそれまで待っていてほしい。
「愛してる」
静かな声で語りかけると、いるはずのない少女が嬉しそうに頷いた幻影が見えて、俺はまた破顔した。
「あいしてる」
牡丹の火花が、鮮やかに爆ぜた。
「ここって」
横持が何か言いかけたあと、珍しく動揺しながら俺の方を見る。マスメディアに報道されまくったせいで、ここはほぼ聖地化していた。立ち入り禁止線の周りには、弔う気持ちもない癖に律儀に花が添えられている。俺は気にしてないことを伝えるために首を振った。
「いいんだ、俺がここに来たいと思ったのは横持に聞きたいことがあったからだから」
「聞きたいことって?」
「神に捧げる少女についてどう思う?」
氷河期に生きていたライオンの死体はまるで眠っているかのように、それは綺麗な状態で現代で発見されたらしい。
彼はまさに氷河期の生き残りだった。
まるで地球に隕石が落ちた瞬間みたいな顔をして、そのまま固まる。
一度呼吸をすれば肺が凍りつく。
そんな空気だった。
一つでも言葉を間違えれば首が吹き飛ぶ。
そんな空気でもあった。
俺は別にどんなことを言われても良かった。でも彼はそこを気にするらしい。その原因が鬼気迫る俺の表情だったら申し訳ない。
彼は暫くの間、沈黙を貫いた後慎重に言葉を選びながら言う。
「俺では公正な判断ができないよ。だって透の背景を全てではなくとも多少なりには知っているから」
横持らしい誰も傷つけない言葉だった。俺はそれに一種の感心を抱きながら、おどけたように言う。
「お前、案外真面目なんだな」
「案外ってなんだよー、オレはいつでも真面目ちゃんなのに」
「前言撤回、そういえば横持は虚言癖なのを忘れてた」
「おいー、オレは誠実ジェントルマンキャラで売ってるのにー」
なんだ誠実ジェントルマンキャラって。俺が苦虫を踏み潰したような顔で彼を見ると、自信満々にこちらを見てきた。しかし、その顔がふっと真顔に戻ると落ち着いたトーンで話し始めた。
「ただ、お前から話を聞くまでは自分勝手な奴だと思ってた。俺はトロッコ問題とかでも5人助かるんだったら1人の犠牲くらいどうってことないと思っちゃう人間だから、村の言い伝えは馬鹿らしいと思ったけど、でもその子が一人犠牲になるだけで村での争いとか心の健康とかが保たれるならそれでいいんじゃない?って考えてた」
改めて彼はできた人間だと思った。普段は冗談交じりの軽快なトークが持ち味の癖に、時に思慮深い冷静な意見も述べることができる。私情に偏ることなくきちんと俯瞰して物事を捉えているので、俺としても忌憚のないそれが有難かった。
俺が真顔でその言葉を受け止めてしまったあまり、彼は俺が傷ついたと誤解をしたらしい。慌てて両手を振って否定する。
「ごめんな、俺はこう考えるけどお前は違うんだよな」
彼はただ一般論を述べただけだ。それなのに俺への心のケアを欠かさない。そういうところが面倒見がいいというか、女性にもてる要因だと思った。ただ相手は俺なのだ。彼の性的対象が俺だったら話は別だが、横持がストレートなのは知っている。もう何年の付き合いになる、そろそろ気を抜いてくれたっていいのにという言葉は恐らく俺が言えることではないだろう。俺は気を使いすぎる彼に俺は何とも言えない顔で首を振る。
「いや横持は正しいよ。普通なら誰だってそう考える」
何が正しいのか、何が間違えなのかは立場によって大きく変わってくる。
そして大抵の場合、背景も知らぬまま流動的に多数派の意見に流されるというのが正しさというのもだ。
ネットで見たことを、真実だと鵜吞みにして。ついたいいねとコメントに踊らされて。「何が正しいのか」より先に、「誰が愚者か」が推測されていく。生きている間もそうだったが、死後も尚、歪んだ正しさが君の周りには蔓延っていた。
更に君の存在は、村の人たちにとっては「よくもやってくれたな、祭事のときにとっとと死ねばよかったのに」であるし、
神社の関係者にとっては「お前のせいで人生滅茶苦茶だ」の一言に尽きるであろう。
世界は一夜にして君を悪者に仕立て上げようとした。
ただ君にとっては違う。
俺と君にだけは違ったんだ。
俺は憂いを帯びた目をすると、唇をゆっくり湿らせる。中々言葉が出てこなかったのは、綺麗に舗装されたコンクリートの堤防が欠けていたからだ。3年前同じ場所で見た苦しそうな顔の君と、口論になって腕を引っ張り合ったときに出来た痕だった。誰かとあれだけの言い合いをしたのは最初で最後だ。
君は俺が今から言うことを許してくれるかい。
これを言ってしまえばきっと世界は全て敵になるんだ。
心の中で語りかける。記憶の片鱗にいる君は首を縦にも横にも振らない。代わりに笑ってみせた。
そうだ、二人で十分だった。二人いれば例え世界は変わらなくても、幸せになる方法は見つけ出すことができたんだ。
だから俺は破顔した。複雑なことは忘れて、気の向くままに笑ってやった。
「ただ、正しさが一つだけだとは思わないんだ」
あの時、結局何が正しかったのかなんて誰にも分かりやしなかった。
傍から見れば彼女が生贄となってこの村の平穏が保たれたと錯覚するのが正しかったのかもしれない。俺は彼女と初めから接触するべきではなかったのかもしれない。
けれど、あの時
ボタンがあまりにも屈託なく笑ったから。
俺は間違えてないと思えた。
曲がりなりにも見つけた自分なりの正義を俺は、俺たちはこれからも肯定したいと思えたんだ。
いつだって俺の世界の真ん中ではボタンが大の字になって寝転がっている。狭い小屋で、窮屈な姿勢で閉じこもっている少女なんかじゃない。白地に鮮やかな朝顔を咲かせた浴衣で、一生懸命水鏡と睨めっこしながら結った髪の毛を揺らして、頬を染めて、
何度も何度も、俺から貰った名前を宝物のように舌で丁寧に転がす少女が腹をよじりながら笑っているのだ。
海藻の絡みついたテトラポッドを撫でると、体温のようなあたたかさが伝わる。昼間直射日光を浴びた石が、まだ熱を帯びていた。君と肩を寄せ合って手持ち花火をした夜を思い出す。少し生ぬるい夏の空気と、隣にあったぬくもりがボタンとの思い出を彷彿とさせた。
夕陽が山に吸い込まれて手元さえよく見えなくなる中、灰色の石に一つ黒い染みが浮かび上がった。
「まだ、少しだけ、忘れられないかも……」
忘れようとした、もう蓋をして二度と思い出すものかと思った記憶がじわじわと体を侵食する。
あぜ道を歩いていたときに決壊しそうだった感情が溢れ出す。
忘れたくない、忘れられない。忘れるものか。
君との約束を破ってしまうことになる。遂行したかったのに、君の願いならば全て忘れてしまうことも苦でないと思ったのに、ここに来たいと心が叫んだ。
もうその衝動から俺の心は変わっていたのだろう。
なぁ。
俺、君との日々を思い出すことより、君への想いをなかったことにする方が何百倍もしんどいみたいなんだ。
段々、吐き出す息の量が多くなる。吸い込む酸素が足りない。
苦しいけれど、涙が止まらないくらい貴方が好きだった。
君がいない朝を俺は知りたくなかった。ずっとずっと隣で、そうだ、ただ隣にいるだけでよかった。
君の呼吸が肩から聞こえる朝を、迎えたかった。
「俺は……おれは……おれは……っ」
ボタンの未来を守れなかった。
そう言いかけて、息が足りずに体を折りたたんだ。
瞼が痙攣する。歪んだ視界の中、黒い海の奥で俺は光るものを見つけた。虚空に手を伸ばす。震える指先が涙で滲んで二重に見える。
光を掴んだ瞬間、全身を震わせるほど大きな音が轟く。
掴んだはずの光は遥か彼方まで上昇して散った。
花火だった。
俺の両手からは火花が溢れだした。
「あぁ、そっか……ボタン笑ってたなぁ」
二人でボロボロになりながら逃げだした夏祭りの宵、笑いながら走った。背負い続けた責任を捨てて、出会って3日の俺の手を取ってくれた。
劣等感と自己嫌悪でぐちゃぐちゃだった俺の肩を抱きしめてくれた。
何度も泣いた、お互いの心臓を曝け出すように弱い部分も見せあった。
何度も笑った、泣きたくなるくらいにあたたかい感情は存在するんだと思った。
ボタンと過ごしたすべてが、過去に囚われる枷とではなく、いつまでも忘れたくない一瞬の瞬きとして俺の中で未だに残り続けている。
それがまた、君がいた時には知ることができなかったまた別の形の幸せだった。
『今日の月は綺麗ですね』
ふとボタンが笑いながら言った日を思い出した。軽々しく言ったことが許せなくて、接吻してやると君は突然のことに酷く狼狽えながらも耳を真っ赤にしていて。思い出の中の君があまりに愛おしくて思わずはにかむ。
月を見上げた。今日はひと際大きな月だった。少しオレンジ色の混じったそれは暗い海を淡く照らしていた。LEDよりも白熱電球よりも弱く、けれど柔らかい光に俺は思わず感嘆の息を漏らす。
「月明かりってこんなにも綺麗だったんだな」
小さい頃、仕事帰りに見上げた空が重なる。すれ違う酔っ払い、居酒屋の煙でぼやけた月の輪郭、きつい香水の匂いと媚びるような視線、いつからかそれが当たり前だった。
今、目の前に広がるのは涙で滲む可惜夜だった。一生明けなくてもいい、この月の下をただ真っすぐに歩いていたい、そう願えるほど美しい夜だった。
「……俺の知ってる夜はこんなはずじゃなかったのに」
脚に力が入らなくてがくがくと震わせたあと、情けなく崩れ落ちる。また、熱いものが込み上げてくる。泣かないように必死に唇を嚙みしめるが鼻腔に込み上げる熱に耐えられず、俺は大人げなく嗚咽を漏らした。
なんでいつの間にかこんなにも優しい夜になっていたのだろう。
「ボタンが俺に残してくれたものはこんなにも素敵なものなんだな。本当に立派だよ君は……ほんとうに……本当にさぁ」
君が傍にいなくたって愛すことを辞めることはできなかった。
こんなに美しい世界を遺してくれた貴方を忘れてしまうなんて出来なかった。
人間、愛という見えない概念に囚われがちだけど、愛してはじめて分かることが本当は大切にするべきものなんだろうな。
夜更けの海は漆黒ではないのとか、花火の火薬の匂いとか、笑ったときに右だけ下がりがちな目尻とか、澄んだ空気で見上げる月はこんなにも綺麗なこととか。
きっと君を愛さなければ生きているうちに知らなかったことがこれ以上に沢山沢山あって、君を愛した世界では綺麗なものが溢れていた。
君の世界もそうだったらいいなと思う。
愛した世界で、愛された世界で、愛で照らされるものが一つでも多く君の世界に満ち溢れていたら、俺が君の隣にいたことには意味があったのだと思う。
男泣きする俺に狼狽しながらも、背中にそっと手を添えてくれる友のぬくもりに一気に力が抜ける。
「大丈夫だよ、透」
それだけ言って、後は何も言及せずに背中をさすり続ける横持に俺は甘えた。ボタン、人ってこんなにいい奴もいたんだな。こうやって人の弱みに漬け込むこともせずに黙って隣にいてくれる人だっているんだな。
痙攣する横隔膜に涙と鼻水にまみれた汚い掌。みすぼらしくて滑稽で、こんな姿で人気俳優だなんてとてもじゃないけれど言い切れない。溢れる涙をどうにかして抑えようと目を瞑る。けれど、瞼の裏のその先にいたのは貴方だった。
「ボタン……ボタン……ぼた、ん……」
今も、名前を呼べばあの長い睫毛を震わせて、輝く瞳に沢山の色を蓄えて、「どうしたんですか?」と小首を傾げながら近づいてくる君がすぐ傍にいるような気がする。
俺は、あの時から変わりたいとずっと願ってきた。
周りの人を大切にできない俺は醜い存在だって、だからいつか人を大切にできるようになりたいって。
母さんとは縁を切ったよ。もう会わないと約束して、俺はようやく透明な鎖を断ち切ることができた。
でも人間そう簡単には変われなくて、信じれる人なんて片手で治まるくらいで、そんな俺が俳優なんて職業に就いてていいのかなって何度も疑った。
それでも、大切にしたいと思える人は増えたよ。すぐ傍にいる男に視線をやる。優しい目をした男はその一人だった。
君が歩み寄ることを教えてくれたから、俺は今一人じゃないんだよ。俺とボタンだけだった世界にいつの間にか人が増えていくんだ。
これからもどんどん、どんどん増えていって、いつの間にか孤独だった自分を忘れてしまうくらい人のあたたかさを知るんだ。
「ボタン、君を思い出すだけで俺はこんなにもあったかい気持ちになれるんだ。やっぱり必要なんだ、君にはこれからも俺の真ん中にいてもらわなきゃ、困るんだ」
相島透は情けなくて、不甲斐なくて、臆病で、後悔ばかりの男だ。
それでも君を誰よりも想っていることに変わりはなかった。これからも、変わることはないだろう。
「……愛しているよ」
言葉にしきれない気持ちの一つが溢れて、俺は息を吐いたまま暫く呼吸ができなかった。
たんぽぽが揺れ、陸風が背中を撫でる。涙はもう出なかった。俺は再び足に力を込めて立ち上がる。痙攣していた口角を持ち上げると、不思議と震えは治まった。横持に「大丈夫」と一言告げると、彼はほっとしたように肩の力を抜いた。それからまた元通りの会話をする。今日の宿はどうしよう、予約してなかったのかよ。ありふれた会話をして、沢山笑った。1時間ほど潮風に吹かれた後、俺たちは今日の宿に向かうことにした。海に背を向けて、進もうとした足を止める。俺はゆっくりと振り返った。
目を細めながら小さく手を振る。
きっとまた来るから。また来るときには、君との思い出を笑って話せるようになっているから。どうかそれまで待っていてほしい。
「愛してる」
静かな声で語りかけると、いるはずのない少女が嬉しそうに頷いた幻影が見えて、俺はまた破顔した。
「あいしてる」
牡丹の火花が、鮮やかに爆ぜた。